Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
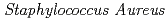
Cui, L.*; 岩本 昭; Lian, J.-Q.*; Neoh, H.*; 丸山 敏毅; 堀川 弥太郎*; 平松 啓一*
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 50(2), p.428 - 438, 2006/02
被引用回数:170 パーセンタイル:97.66(Microbiology)世界中の病院で猛威をふるうMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)に対して、唯一強力な効果を発揮する抗生物質であるバンコマイシンは抗生物質のエースとして知られていたが、1996年に順天堂大学の平松により、このバンコマイシンに耐性を示すMRSAが臨床的に分離され、以来世界各地で追認が続いた。現在はVISAと呼ばれるこの菌の耐性のメカニズム解明のため、反応拡散方程式を拡張した定式化を行い、平松研究室の実験データを用いた計算を行った結果、この菌の特異な耐性機構を以下のように明らかにした。(1)バンコマイシンが細胞壁を拡散する際に、「目詰まり効果」というメカニズムにより、後から来るバンコマイシンの拡散が妨げられる。(2)「目詰まり効果」と、さらに細胞壁の厚さを通常の感受性菌の1.6倍程度にする戦略の相乗効果として、細胞壁の透過に要する時間を本来数分であったものを20 30分にまでに長引かせる。(3)この長引かされた時間を利用して、バンコマイシンが細胞壁透過後に増殖機能を破壊する以前に細胞分裂を行い、増殖継続を可能にする。以上に述べた細菌の耐性メカニズムは今まで全く知られていなかったもので、細菌の耐性メカニズムの知見を広げ、また院内感染の予防などの実用面からの研究にも役立つと考えられる。
30分にまでに長引かせる。(3)この長引かされた時間を利用して、バンコマイシンが細胞壁透過後に増殖機能を破壊する以前に細胞分裂を行い、増殖継続を可能にする。以上に述べた細菌の耐性メカニズムは今まで全く知られていなかったもので、細菌の耐性メカニズムの知見を広げ、また院内感染の予防などの実用面からの研究にも役立つと考えられる。
磯部 博志; 妹尾 宗明
Journal of Nuclear Science and Technology, 32(4), p.372 - 373, 1995/04
被引用回数:0 パーセンタイル:0.41(Nuclear Science & Technology)米国材料学会(MRS)は、放射性廃棄物管理に関する科学的基礎研究についての会議を、秋期年会の一部として開催している。1994年は、10月23日から27日まで、日本原子力学会等5団体の共催により、過去最高の参加者を集めて京都で開催された。この会議では、全体の4割の発表が処分環境下での核種と人工バリアや地質媒体との相互作用についての研究であった。還元環境にある複雑な系である天然の地質媒体を理解、モデル化するための研究が、ナチュラルアナログ研究や地下実験室での研究など多くの手法で試みられていることが印象づけられた。
磯部 博志; 妹尾 宗明
原子力工業, 41(5), p.68 - 72, 1995/00
米国材料学会(MRS)は、Scientific Basis for Nuclear Waste Managementのタイトルで放射性廃棄物管理に関する科学的基礎研究についての会議を開催している。1994年は、10月23日から27日まで、日本原子力学会等5団体の共催により、過去最高の参加者を集めて京都市で開催された。分野別、国別の発表内訳は、研究者の関心の趨勢を反映している。また、基調講演等では現在最新のトピックスが紹介された。本文ではそれらのなかから、スウェーデンにおける地下水流、核種移行機構に関する研究、反応移行及び環境中金属元素化学形のモデル化に関する研究、及びナチュラルアナログ研究について紹介する。
亀井 玄人; 本田 明
PNC TN8600 92-005, 23 Pages, 1992/03
本報告書は1991年11月、仏ストラスブールで開催された、EMRS 1991 Fall Meeting(主催、欧州材料学会)および、同月、米ハワイ州で開催された、Life Prediction of Corrodible Structures(主催、米国腐食学会)において発表された研究のうち、動燃の地層処分研究上とくに重要と考えられるものの概要や所感を記すものである。前者の会議では放射性廃棄物の処理・処分技術全般にわたる材料研究の成果が発表された。亀井はこれらのうち、種々の人工バリア材料と水との相互作用や、核種移行挙動等を重点に情報を集めるとともに、ベントナイトの長期耐久性について発表した。世界的に処分研究は、現象の本質を理解しようとする方向で進められているように感じられた。後者の会議では、構造物の腐食寿命予測に関する研究の成果が報告された。本田はオーバーパック研究に参考となる各種測定技術、加速試験手法および寿命予測手法に関する情報を集めるとともに、炭素鋼オーバーパックの寿命予測について発表した。腐食モニタリング技術では交流インピーダンス法が注目されており、寿命予測手法の主流は、従来の確定論的手法から確率統計的手法へと移り変わりつつあるように感じられた。