Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
 Co
Co Fe
Fe O
O
駒淵 舞*; 漆原 大典*; 浅香 透*; 福田 功一郎*; 大原 高志; 宗像 孝司*; 石川 喜久*
Journal of the Physical Society of Japan, 89(3), p.034601_1 - 034601_5, 2020/03
被引用回数:2 パーセンタイル:17.95(Physics, Multidisciplinary)The crystal structure of an X-type hexaferrite Sr Co
Co Fe
Fe O
O was investigated by the X-ray and neutron diffraction methods for a single crystal. Sr
was investigated by the X-ray and neutron diffraction methods for a single crystal. Sr Co
Co Fe
Fe O
O has the crystal structure described as a space group
has the crystal structure described as a space group  (
( ) and its lattice constants are
) and its lattice constants are  = 5.9165(2)
= 5.9165(2)  ; and
; and  = 84.1395(33)
= 84.1395(33)  ; at 843 K. Co ions are almost localized in the octahedral site (
; at 843 K. Co ions are almost localized in the octahedral site ( ) in the middle of S
) in the middle of S S
S blocks. In addition, the adjacent octahedral and tetrahedral sites to
blocks. In addition, the adjacent octahedral and tetrahedral sites to  site contain the significant number of Co
site contain the significant number of Co .
.
阿部 充志*; Bae, S.*; Beer, G.*; Bunce, G.*; Choi, H.*; Choi, S.*; Chung, M.*; da Silva, W.*; Eidelman, S.*; Finger, M.*; et al.
Progress of Theoretical and Experimental Physics (Internet), 2019(5), p.053C02_1 - 053C02_22, 2019/05
被引用回数:156 パーセンタイル:99.31(Physics, Multidisciplinary)この論文はJ-PARCにおける、ミューオン異常磁気モーメント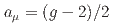 と電気双極子モーメント(EDM)
と電気双極子モーメント(EDM)  を測定する新しいアプローチを紹介する。我々の実験のゴールは、これまでと独立の、1/10の運動量と1/20のストレージリングを用いて、
を測定する新しいアプローチを紹介する。我々の実験のゴールは、これまでと独立の、1/10の運動量と1/20のストレージリングを用いて、 と
と をこれまでにない精密な磁場で測定することである。さらに過去の実験との顕著な違いは、1/1000の横エミッタンスミューオンビーム(サーマルミューオンビーム)を用い、効率的なソレノイドへ縦入射し、ミューオンからの崩壊陽電子をトラッキングし、その小さな運動量ベクトルを求める点である。
をこれまでにない精密な磁場で測定することである。さらに過去の実験との顕著な違いは、1/1000の横エミッタンスミューオンビーム(サーマルミューオンビーム)を用い、効率的なソレノイドへ縦入射し、ミューオンからの崩壊陽電子をトラッキングし、その小さな運動量ベクトルを求める点である。 は統計精度450ppb、系統誤差70ppb、EDMについては
は統計精度450ppb、系統誤差70ppb、EDMについては e
e cmの精度で測定することを目標とする。
cmの精度で測定することを目標とする。
松井 裕哉; 丹野 剛男; 平野 享*; 郷家 光男*; 熊坂 博夫*; 多田 浩幸*; 石井 卓*
JAEA-Research 2010-043, 87 Pages, 2010/12
予察的解析の妥当性評価を目的として、壁面観察結果に基づきクラックテンソルを算定し、地中変位計測と比較して、その妥当性を評価し、立坑内から実施したパイロットボーリング調査や地表からの調査段階で設定したクラックテンソルの比較を行った。(1)2004年度の予察的解析で設定されたクラックテンソルを用いた換気立坑の深度350mの変形解析値は地中変位計測値よりも小さい値を示した。一方、壁面観察結果から設定されたクラックテンソルを用いた換気立坑の深度350mの変形解析の結果、計算された最大値は計測値に近い値を示した。(2)これは、2004年度の評価で十分考慮できていない非常に連続性の高いNE系の割れ目の情報が新たに考慮されたためである。換気立坑より掘削したパイロットボーリング調査結果に基づきクラックテンソルを求めて両者と比較した結果、パイロットボーリング調査で把握された割れ目の方向分布は壁面観察の方向分布と近いこと、求められたクラックテンソルは両者の中間に位置することがわかった。(3)パイロットボーリングデータにおける深度350mと深度500m間の割れ目の統計量の関係より深度500mにおけるクラックテンソルを推定した。推定されたクラックテンソルを用いて深度500mにおける換気立坑と水平展開坑道の変形解析を行った結果、2004年度の結果よりも岩盤のヤング率は低減し、支保工に作用する応力は増加した。
長根 悟; 北原 勝美; 吉川 静次; 宮坂 靖彦*; 福村 信男*; 西沢 市王*
デコミッショニング技報, (42), p.2 - 10, 2010/09
原子力船「むつ」の中央部分に搭載された原子炉室は、1996年から附帯陸上施設の原子炉室保管棟に安全に保管,展示されている。主要な放射性廃棄物である原子炉容器及び炉内構造物等は、将来の合理的な廃止措置計画を考えるうえで特に重要な機器であると位置づけている。本報告では、原子炉容器と炉内構造物を収納容器又は追加遮へいにより廃棄体化し、撤去する一括撤去工法について述べる。原子炉容器の一括廃棄体(最大100トン)は、放射能濃度上限値からピット処分に区分され、また、容器密封処置を含む輸送上の要求に基づきIP-2型容器相当の輸送物に該当する。
北垣 徹; 田坂 應幸; 樋口 英俊; 小泉 健治; 平野 弘康; 鷲谷 忠博; 小林 嗣幸*
Proceedings of 17th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE-17) (CD-ROM), 5 Pages, 2009/06
文部科学省公募研究として、平成18年度から4年計画で実施中の「FBR燃料集合体を対象とした解体・せん断技術開発」において、平成18年度に実施した基本設計に基づき解体システム試験装置を製作した。本報ではこの解体システム試験装置の概略と、模擬燃料集合体を用いた動作試験の概要について報告する。
菊池 康之; 長谷川 明; 田坂 完二; 西村 秀夫; 大竹 巌*; 桂木 学
JAERI-M 6001, 80 Pages, 1975/02
シグマ研究委員会で評価された重要FP28核種の群定数を作成し、その適用性に関して種々の試験を行った。この評価値は中間報告であり、共鳴構造を無視して100eV以上を統計モデルで計算している。しかしランプ化された状態では、これに起因する誤差は十分小さくなる事が確められた。さらにランプ化に伴う諸問題が検討された。30日から300日の燃焼中にFPの cは5%増大する。一方燃焼に伴いFPガスが燃料から放出されると、断面積は約10%低下する。中性子捕獲による
cは5%増大する。一方燃焼に伴いFPガスが燃料から放出されると、断面積は約10%低下する。中性子捕獲による -チェイン間の移行の効果は無視しうる。このJNDCの
-チェイン間の移行の効果は無視しうる。このJNDCの c評価値はCookによる評価値より約25%大きい。FP炉定数の25%の差は、燃焼寿命に10%、実効増倍率に0.6%、Naポイド係数に10%の影響を与える。一方、オランダのPettenにおいて、FP混合物及び同位体のサンプル反応度が測定された。そこでJNDC炉定数を用いてこれを解析した所、かなり良好な一致が見られた。
c評価値はCookによる評価値より約25%大きい。FP炉定数の25%の差は、燃焼寿命に10%、実効増倍率に0.6%、Naポイド係数に10%の影響を与える。一方、オランダのPettenにおいて、FP混合物及び同位体のサンプル反応度が測定された。そこでJNDC炉定数を用いてこれを解析した所、かなり良好な一致が見られた。
菊池 康之; 田坂 完二; 西村 秀夫; 長谷川 明; 桂木 学
JAERI-M 5492, 71 Pages, 1973/12
FPの炉定数に対する強い要望に答えて、 委員会炉定数専門部会では、オーストラリアのCookによる184核種の評価データを用いて、JAERI Fast Set型の炉定数を作成した。これらは、さらにBurn upの状態毎にランプされて、一つの擬核種の炉定数として、このレポートにテーブルで与えられている。また、Cookのデータの共鳴領域の評価法について、検討が行なわれ、いくつかの問題点が指摘された。
委員会炉定数専門部会では、オーストラリアのCookによる184核種の評価データを用いて、JAERI Fast Set型の炉定数を作成した。これらは、さらにBurn upの状態毎にランプされて、一つの擬核種の炉定数として、このレポートにテーブルで与えられている。また、Cookのデータの共鳴領域の評価法について、検討が行なわれ、いくつかの問題点が指摘された。
神原 豊三; 宇野 英郎; 荘田 勝彦; 平田 穣; 庄司 務; 小早川 透; 高柳 弘; 藤村 勤; 森田 守人; 市原 正弘; et al.
JAERI 1045, 11 Pages, 1963/03
この報告書はJRR-2の第1次出力上昇試験後、設計出力10MWの出力上昇までの1つのステップとしての3MW,第2次出力上昇試験について記したものである。試験は昭和36年11月15日から開始され、11月29日に3MWに到達し、3MWでの連続運転を行って12月16日終了した。
JRR-2管理課; 神原 豊三; 荘田 勝彦; 平田 穣; 庄司 務; 小早川 透; 両角 実; 上林 有一郎; 蔀 肇; 小金澤 卓; et al.
JAERI 1027, 57 Pages, 1962/09
1961年3月に行われたJRR-2の第1次出力上昇試験全般にわたって記してある。まず第1章に出力上昇の問題となった第1次燃料について、燃料要素の仕様・検査及び問題点と安全性についての検討をした結果を述べてある。この検討に従い、万一燃料被覆破損が生じた場合、でき得る限り早期に発見し、処置を容易にするために破損燃料検出装置を追加設置した。この破損燃料検出装置の検出の方法,装置の内容について第2章に記してある。最後に第3章に実施した第1次出力上昇試験の経過について述べてある。
神原 豊三; 荘田 勝彦; 平田 穣; 庄司 務; 萩野谷 欣一; 小早川 透; 八巻 治恵; 横田 光雄; 堀木 欧一郎; 柚原 俊一; et al.
JAERI 1023, 120 Pages, 1962/09
JRR-2原子炉は、1956年11月米国AMF社と契約を結び、1958年4月より建設工事に着手した。建設工事期間には、ほかの報告に見られるように、種々の問題があり、据付組立が完了したのは1959年12月末であった。その後引続き、制御系,冷却系の機能試験が行われた。これはそれらの試験の報告である。
JRR-2管理課; 神原 豊三; 荘田 勝彦; 平田 穣; 庄司 務; 萩野谷 欣一; 小早川 透; 八巻 治恵; 横田 光雄; 堀木 欧一郎; et al.
JAERI 1024, 79 Pages, 1962/08
この報告は、JRR-2が臨海になる前に行った重水ヘリウム系の乾燥及び重水注入と、臨海後1960年11月の3000kWへの第2次出力上昇に至るまでに実施した重水の分析とイオン交換樹脂の重水化,ヘリウムの純化及び二次冷却水の処理について、その問題点とこれを解決するためにとった方法及び実施の経験を、5編にまとめたものである。JRR-2は重水減速冷却型であって、重水は入手が容易でなく、その稀釈あるいは消耗は炉の運転上重大な問題となる恐れがあるので、その炉への注入は臨界前に重水ヘリウム系を十分に乾燥した後慎重に行った。臨界後は重水濃度,pH,不純物,放射性核種等運転上重要なものについて測定を行い、また、精製系のイオン交換樹脂は軽水を重水と置換して取り付けた。ヘリウム系は1960年2月出力上昇に先立って空気とヘリウムを置換し、その後は活性炭吸収装置を内蔵する純化装置により純化を行っている。二次冷却水については腐食による障害を監視しながら処理を実施してきた。以上のような作業を行うことにより、水ガス系にはほとんど問題なく、炉は安全に運転することができた。
JRR-2臨界実験グループ; 神原 豊三; 荘田 勝彦; 平田 穣; 庄司 務; 小早川 透; 両角 実; 上林 有一郎; 蔀 肇; 小金澤 卓; et al.
JAERI 1025, 62 Pages, 1962/03
第2号研究用原子炉JRR-2は、20%濃縮ウランのMTR型燃料を用いた重水減速・冷却の熱中性子研究炉である。この炉の最大熱出力は10MW,平均熱中性子束密度は1 10
10 n/cm
n/cm secである。この論文は昭和35年10月1日、臨界に到達し、翌36年1月末まで実施した各種の特性試験についての報告書である。内容はJRR-2の臨界試験,制御棒の校正,重水上部反射体効果,燃料要素の反応度効果,温度係数等の特性試験,熱中性子束分布の測定と出力の校正について述べてある。これらの実験は、JRR-2管理課並びに技術研究室より特別に編成されたJRR-2臨界実験グループによって実施されたものである。
secである。この論文は昭和35年10月1日、臨界に到達し、翌36年1月末まで実施した各種の特性試験についての報告書である。内容はJRR-2の臨界試験,制御棒の校正,重水上部反射体効果,燃料要素の反応度効果,温度係数等の特性試験,熱中性子束分布の測定と出力の校正について述べてある。これらの実験は、JRR-2管理課並びに技術研究室より特別に編成されたJRR-2臨界実験グループによって実施されたものである。
北垣 徹; 樋口 英俊; 小泉 健治; 平野 弘康; 田坂 應幸*; 鷲谷 忠博; 小林 嗣幸*
no journal, ,
原子力機構と日本原子力発電は、FaCTプロジェクトの一環としてFBR燃料集合体を対象とした解体技術の開発を行っている。平成20年度には解体システム試験装置の基本性能評価試験を実施し、一連の解体工程の成立性の見通しを得た。本報ではこれらの成果及び今後の計画について報告する。
島田 隆*; 北垣 徹; 田坂 應幸*; 鷲谷 忠博; 坪田 秀峰*; 光畑 幸史*; 西川 秀紹*; 黒田 一彦*
no journal, ,
高速炉模擬燃料集合体のラッパ管切断(スリットカット)・燃料ピン束切断(クロップカット)の各試験により、解体切断工法としてのレーザー切断技術の適用性を評価した。
北垣 徹; 鷲谷 忠博; 田坂 應幸
no journal, ,
文部科学省公募研究として、平成18年度から4年計画で実施中の「FBR燃料集合体を対象とした解体・せん断技術開発」において、H18年度に実施した基本設計に基づき解体システム試験装置を製作した。本報ではこの解体システム試験装置の概略と、模擬実用燃料集合体を用いた動作試験の概要について報告する。
鷲谷 忠博; 北垣 徹; 樋口 英俊; 小泉 健治; 小林 嗣幸*; 小山 智造; 田坂 應幸*
no journal, ,
機械式切断方式を採用したFBR燃料の解体システム及び短尺せん断技術を採用したせん断システムの要素試験及び工学規模試験の概要を報告する。
中塚 亨; 岡 芳明*; 石渡 祐樹*; 奥村 啓介; 長崎 晋也*; 手塚 健一*; 森 英夫*; 江里 幸一郎; 赤坂 尚昭; 中園 祥央*; et al.
no journal, ,
圧力容器型の超臨界圧水冷却炉は、1989年より東京大学で研究開発が進められてきており、現在、第4世代炉の一つとして、日本,欧州及び他の国で実用化に向けた研究が行われている。東京大学の概念は、熱中性子炉は「スーパー軽水炉」,高速炉は「スーパー高速炉」と呼ばれている。高速炉は、熱中性子炉と同じプラントシステムで実現可能と期待されている。経済的な高速炉体系を開発することを目的として、「スーパー高速炉」の研究プロジェクトが2005年12月から2010年3月まで東京大学を代表機関として進められ、九州大学,原子力機構,東京電力がこのプロジェクトに参加した。このプロジェクトは、(1)スーパー高速炉の概念の構築,(2)伝熱流動実験,(3)材料開発の3つからなる。本論文では、このプロジェクトで得られた成果の概要を紹介する。具体的には、(1)では東京大学による炉心核熱結合解析やシステム解析等の結果、(2)では九州大学による模擬流体を用いた熱流動実験、原子力機構による超臨界圧水を用いた熱流動実験と3次元解析コード開発の結果、また、(3)では東京大学・原子力機構によるクリープ試験,腐食試験等の材料基礎研究の結果について報告する。
黒田 一彦*; 北垣 徹; 樋口 英俊; 田坂 應幸*; 鷲谷 忠博; 遠矢 優一*; 西川 秀紹*; 唐津 史明*
no journal, ,
FBR燃料再処理技術開発の一環として実施した模擬燃料集合体のラッパ管切断(スリットカット)及び燃料ピン束切断(クロップカット)に関する要素試験結果について報告する。
樋口 英俊; 小泉 健治; 平野 弘康; 北垣 徹; 鷲谷 忠博; 小林 嗣幸*; 田坂 應幸*
no journal, ,
平成19年度に製作した燃料ピンの移送システムに昇降機能の改良を加え、燃料ピンの脱落を防止できる信頼性の高い移送システムを開発した。昇降機能を応用して燃料ピン束を整列させて移送する方法、並びに将来的なシステムとして解体装置から直接、せん断マガジンへ装荷する方式の要素試験結果とその可能性について報告する。
北垣 徹; 田坂 應幸; 鷲谷 忠博; 小林 嗣幸
no journal, ,
FaCTプロジェクトの一環として実施中のFBR燃料集合体を対象とした解体技術開発において、機械式解体システム試験装置の製作,一連の解体動作確認を行った。本報ではこれらの成果及び今後の計画について報告する。