Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
志賀 英明*; 滝 淳一*; 鷲山 幸信*; 山本 純平*; 木名瀬 栄; 奥田 光一*; 絹谷 清剛*; 渡邉 直人*; 利波 久雄*; 越田 吉郎*; et al.
PLOS ONE (Internet), 8(2), p.e57671_1 - e57671_8, 2013/02
被引用回数:20 パーセンタイル:68.98(Multidisciplinary Sciences)Current olfactory function tests are useful for the analysis of olfactory thresholds in olfaction-impaired patients. However, a decrease in olfactory thresholds has not been used as an index for olfactory nerve damage in patients. The authors assessed peripheral olfactory nerve viability by performing combined SPECT-CT after nasal administration of Tl-201 to determine whether olfactory nerve was damaged in patients with olfactory impairments in comparison to healthy volunteers. It was found that nasal Tl-201 migration to the olfactory bulb was significantly lower in the patients with head trauma, respiratory infection, and chronic rhinosinusitis than in healthy volunteers.
白石 淳也; 吉田 善章*; 古川 勝*
Astrophysical Journal, 697(1), p.100 - 105, 2009/03
被引用回数:5 パーセンタイル:17.25(Astronomy & Astrophysics)原始星などの中心天体近傍に形成される、ジェット放出を伴う降着円盤は、理想流体モデルの枠組みから見れば特異な構造を持っている。降着流とジェット流は、ケプラー回転している円盤に対する「特異摂動」とみなすことができる。ここで特異摂動とは、何らかの(微分階数に関して)高次な効果をいう。本論文では、原始星円盤の弱電離プラズマ中ではホール効果がそのような構造を形成することを示した。実際、特異摂動によって規定される特徴的なスケールを評価すると、ホール効果が支配的である。
 Sn; Evidence for anisotropic
Sn; Evidence for anisotropic  -wave pairing
-wave pairing門野 良典*; 佐藤 宏樹*; 幸田 章宏*; 永田 貴志*; 古川 はづき*; 鈴木 淳市; 松田 雅昌; 大石 一城; 髭本 亘; 黒岩 壮吾*; et al.
Physical Review B, 74(2), p.024513_1 - 024513_5, 2006/07
被引用回数:10 パーセンタイル:43.29(Materials Science, Multidisciplinary)ミュオンスピン回転法及び中性子小角散乱実験法を用いてNb Snの磁束状態の研究を行った。その結果、中性子小角散乱実験から比較的低磁場(2-3T)で磁束格子が三角格子から四角格子へと変形する様子が観測された。またミュオンスピン回転法から得られた磁場侵入長の磁場依存性は、外部磁場が増加するにつれて磁場侵入長は徐々に大きくなることから、Nb
Snの磁束状態の研究を行った。その結果、中性子小角散乱実験から比較的低磁場(2-3T)で磁束格子が三角格子から四角格子へと変形する様子が観測された。またミュオンスピン回転法から得られた磁場侵入長の磁場依存性は、外部磁場が増加するにつれて磁場侵入長は徐々に大きくなることから、Nb Snは異方的な
Snは異方的な 波超伝導体(もしくはマルチギャップを有する超伝導体)であると結論づけた。
波超伝導体(もしくはマルチギャップを有する超伝導体)であると結論づけた。
 F-labeled water movement in a cowpea plant by positron emitting tracer imaging system (PETIS)
F-labeled water movement in a cowpea plant by positron emitting tracer imaging system (PETIS)古川 純*; 横田 はる美*; 田野井 慶太朗*; 上岡 志ほり*; 松橋 信平; 石岡 典子; 渡辺 智; 内田 博*; 辻 淳憲*; 伊藤 岳人*; et al.
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 249(2), p.495 - 498, 2001/08
被引用回数:16 パーセンタイル:72.43(Chemistry, Analytical)ポジトロン放出核種を利用したイメージング装置であるPETIS(Positron Emitting Tracer Imaging System)を用いてササゲにおけるバナジウム(V )吸収をリアルタイムで測定した。バナジウム-48は、日本原子力研究所高崎研究所のAVFサイクロトロンを用い、Sc箔に50MeVの
)吸収をリアルタイムで測定した。バナジウム-48は、日本原子力研究所高崎研究所のAVFサイクロトロンを用い、Sc箔に50MeVの 粒子を照射することにより製造した。
粒子を照射することにより製造した。 Vを水耕液に添加し、PETISによりリアルタイム計測を行った。また
Vを水耕液に添加し、PETISによりリアルタイム計測を行った。また V水溶液を添加してから3,6,20時間目の植物体を用いてバナジウム分布をラジオグラフィにより測定した。これらにより処理開始後20時間目には植物体全体にバナジウムが分布していることが明らかになった。植物に吸収されたバナジウムが及ぼす影響を見るために、同様にポジトロン放出核種であるフッ素-18で標識した水を用いてPETISによりササゲの水分吸収動態を測定した。計測前に20時時間バナジウムを吸収させると、標識水の吸収が極端に抑えられることが示された。これらの結果は植物体の地上部に移行したバナジウムが標識水の吸収を阻害する主な原因であることを示唆している。
V水溶液を添加してから3,6,20時間目の植物体を用いてバナジウム分布をラジオグラフィにより測定した。これらにより処理開始後20時間目には植物体全体にバナジウムが分布していることが明らかになった。植物に吸収されたバナジウムが及ぼす影響を見るために、同様にポジトロン放出核種であるフッ素-18で標識した水を用いてPETISによりササゲの水分吸収動態を測定した。計測前に20時時間バナジウムを吸収させると、標識水の吸収が極端に抑えられることが示された。これらの結果は植物体の地上部に移行したバナジウムが標識水の吸収を阻害する主な原因であることを示唆している。
 O-labeled and
O-labeled and  F-labeled water uptake in a soybean plant by PETIS (Positron Emitting Tracer Imaging System)
F-labeled water uptake in a soybean plant by PETIS (Positron Emitting Tracer Imaging System)中西 友子*; 横田 はる美*; 田野井 慶太朗*; 池上 奈通子*; 大國 曜子*; 古川 純*; 石岡 典子; 渡辺 智; 長 明彦; 関根 俊明; et al.
Radioisotopes, 50(6), p.265 - 269, 2001/06
ダイズにおける O標識水と
O標識水と F標識水の吸収動態をPETIS(Positron Emitting Tracer Imaging System)法を用いて比較検討した。
F標識水の吸収動態をPETIS(Positron Emitting Tracer Imaging System)法を用いて比較検討した。 O標識水(半減期: 2分)はサイクロトロンを用いて
O標識水(半減期: 2分)はサイクロトロンを用いて N(d,n)
N(d,n) O反応により、また、
O反応により、また、 F標識水(半減期: 110分)は
F標識水(半減期: 110分)は O(
O( ,pn)
,pn) F反応により調製した。標識水の供給は、根を切り落としたダイズの茎の下部から行い、植物中の標識水から放出される
F反応により調製した。標識水の供給は、根を切り落としたダイズの茎の下部から行い、植物中の標識水から放出される 線をBGO検出器(5cm
線をBGO検出器(5cm 15cm)を用いてリアルタイム計測を行った。15秒ごとの計測の積算値からダイズの各茎における20分間の吸水動態を調べたところ、
15cm)を用いてリアルタイム計測を行った。15秒ごとの計測の積算値からダイズの各茎における20分間の吸水動態を調べたところ、 F標識水の方が
F標識水の方が O標識水より早く吸収されることがわかり、
O標識水より早く吸収されることがわかり、 F標識水ではフッ素は
F標識水ではフッ素は F
F イオンとなり、バルクの水とは異なる動態を示すことが示された。吸収された
イオンとなり、バルクの水とは異なる動態を示すことが示された。吸収された O標識水の静止画像を撮ったところ、10分間の吸収後においても初葉よりも上部に
O標識水の静止画像を撮ったところ、10分間の吸収後においても初葉よりも上部に O標識水の分布は見られなかった。
O標識水の分布は見られなかった。
古川 純*; 中西 友子*; 松林 政仁
可視化情報学会誌, 20(suppl.1), p.377 - 380, 2000/07
生きた根の水分吸収動態を中性子ラジオグラフィを用いて可視化した。根の成長と水分の分布はコンピュータトモグラフィを用いて3次元的に解析した。ダイズ幼植物をアルミ製のコンテナで育成し、熱中性子ラジオグラフィにより根圏の水分像を時系列的に得た。画像解析の結果、水分の減少する部位は根の成長とともに上部から下部へと移行していくことがわかった。また根近傍の水分動態の計測から、根の成長に沿った三段階の吸収様式が示された。水分を吸収する二つの相と、その中間の根近傍の水分が一時的に増加する相である。この水分が増加する相と側根の発生が同時期であったことから、根の活動と周囲の水分布の関連性が示唆された。これまで根の周囲の水分動態を微視的に解析した研究例は少なく、中性子ラジオグラフィによる可視化手法は植物の活性解析に非常に重要情報を与えるものと期待される。
中西 友子*; 古川 純*; 松林 政仁
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 424(1), p.136 - 141, 1999/00
被引用回数:16 パーセンタイル:73.49(Instruments & Instrumentation)中性子コンピュータ断層撮影を用いてカーネーションの花内部の水のプロファイルを得た。花の部分を回転台上に固定し、熱中性子ビームを用いて1枚につき4秒間照射で冷却型CCDカメラを用いて撮影した。撮影枚数は1試料につき、半回転180枚(1枚/1度)とした。カーネーションは乾燥前と乾燥後の2つの試料を用意し、CTの再構成計算にはShepp-Loganフィルタを用いるフィルタ逆投影法を使用した。得られた断層画像は、これまでの投影画像では観察が困難であった花の内部における水分の分布を明らかとした。カーネーションの花のCT撮影は初めての試みであり、空間解像度において改善の必要性は認められるものの、花の内部における水の動態を解析できる有望な手法であることが示された。
古川 純*; 中西 友子*; 松林 政仁
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 424(1), p.116 - 121, 1999/00
被引用回数:19 パーセンタイル:77.90(Instruments & Instrumentation)根の吸水活動が土壌中に存在するヴァナジウムにより如何に抑制されるかを報告した。ヴァナジウムを添加した吸水性ポリマーを入れたアルミニウム製容器中で大豆を成長させ、熱中性子ラジオグラフィのフィルム法で撮影した。現像後、フィルム上の画像をスキャナーでコンピュータに読み込み、画像解析により主根及び側根周りの吸水方法について調べた。その結果、根の生育の形態変化に関してヴァナジウム添加による影響は認められなかったものの、根から1mm以内の根に沿った土壌中の水分量が2日目以降変動しなくなり、根の活動低下に影響していることが示された。根の周りの水の動きの微視的研究はこれまであまり行われておらず、本結果は根の吸水モデル構築に有用であると期待できる。
古川 純*; 岩田 佳晃*; 鈴井 伸郎; 石井 里美; 河地 有木; 山崎 治明; 藤巻 秀; 佐藤 忍*
no journal, ,
亜鉛集積機構の解明を目的として、マメ科のモデル植物であり、先行研究から主要実験系統であるMiyakojimaとGifuで亜鉛集積に系統間差があることが知られているミヤコグサ(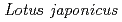 )を用いて亜鉛集積・輸送特性をリアルタイムイメージングの手法により解析するとともに、それを司るQTLの解析を行った。実験には、Miyakojima及びGifuと、それらをかけ合わせ、分子マーカーにより遺伝子型が決定された組換え自殖系統を用いた。生育1か月のMiyakojimaとGifuの非放射性亜鉛の集積濃度を比較すると、根・茎・葉のすべてでGifuが高濃度に亜鉛を蓄積していた。同時期の植物体に
)を用いて亜鉛集積・輸送特性をリアルタイムイメージングの手法により解析するとともに、それを司るQTLの解析を行った。実験には、Miyakojima及びGifuと、それらをかけ合わせ、分子マーカーにより遺伝子型が決定された組換え自殖系統を用いた。生育1か月のMiyakojimaとGifuの非放射性亜鉛の集積濃度を比較すると、根・茎・葉のすべてでGifuが高濃度に亜鉛を蓄積していた。同時期の植物体に Znを吸収させ、ガンマカウンタ, オートラジオグラフィ並びにPETIS法を用いて解析を行ったところ、Gifuの地上部への亜鉛輸送活性がMiyakojimaよりも高いことが示された。また、組換え自殖系統の亜鉛集積を地上部に蓄積された
Znを吸収させ、ガンマカウンタ, オートラジオグラフィ並びにPETIS法を用いて解析を行ったところ、Gifuの地上部への亜鉛輸送活性がMiyakojimaよりも高いことが示された。また、組換え自殖系統の亜鉛集積を地上部に蓄積された Zn量から解析したところ、亜鉛集積にかかわる複数のQTL領域が得られた。それぞれのQTL領域による地上部への亜鉛輸送や集積に対する影響を解析するため、QTL領域の遺伝子型が異なる組換え自殖系統を選抜し、亜鉛の吸収・輸送をオートラジオグラフィ並びにPETIS法を用いて比較したところ、根, 地上部、あるいは根と地上部の両方に高濃度の亜鉛を蓄積している系統が得られた。
Zn量から解析したところ、亜鉛集積にかかわる複数のQTL領域が得られた。それぞれのQTL領域による地上部への亜鉛輸送や集積に対する影響を解析するため、QTL領域の遺伝子型が異なる組換え自殖系統を選抜し、亜鉛の吸収・輸送をオートラジオグラフィ並びにPETIS法を用いて比較したところ、根, 地上部、あるいは根と地上部の両方に高濃度の亜鉛を蓄積している系統が得られた。
三輪 周平; 中島 邦久; Di Lemma, F. G.; 鈴木 知史; 山下 真一郎; 岡根 哲夫; 高井 俊秀; 高田 準太郎; 古川 智弘; 逢坂 正彦
no journal, ,
原子力機構では、核分裂生成物(FP)の放出移行挙動評価手法を高度化するために、炉内各位置における化学挙動を評価してデータベース化し、FP化学モデルの高度化を行うことを目的としたFP化学に関する基礎研究を実施している。本研究では、Cs及びIを対象に、MoやBWR制御材炭化ホウ素(B C)等の影響に着目して、FP及びBの放出速度評価、沈着FP化学形の直接測定技術開発、SSへのCs化学吸着挙動評価、熱力学データベース拡充等を実施している。
C)等の影響に着目して、FP及びBの放出速度評価、沈着FP化学形の直接測定技術開発、SSへのCs化学吸着挙動評価、熱力学データベース拡充等を実施している。
高井 俊秀; 平川 康; 栗原 成計; 斉藤 淳一; 古川 智弘
no journal, ,
高速炉プラントでは、冷却材に沸点が高く熱伝導特性に優れたナトリウム(Na)を用いることで、低圧の構造設計を可能としている。一方でNaは化学的に活性であり、Na漏えいが発生した場合における構造材の腐食や温度上昇に起因する熱機械荷重の発生等を考慮することが必要となる。そこで、過酷事象時における「格納機能の維持」に対する裕度向上を目指し、Na漏えいを起点とした事象進展の遮断・抑制に向けた基盤技術開発を進めている。本報では、この中で取り組んだ燃焼抑制技術及び腐食抑制技術に関する要素試験結果について報告する。
古川 智弘; 高井 俊秀; 平川 康; 栗原 成計; 斉藤 淳一
no journal, ,
高速炉におけるナトリウム漏えい時の影響緩和方策や事象の終息方策に向けて、高速炉の主たるウィークポイントであるナトリウムの化学的特性に着目して立案した高速炉の安全性向上技術に係る研究概要と要素試験結果について報告する。
大森 栄和; 栗原 研一; 松川 誠; 寺門 恒久; 岡野 潤; 古川 弘
no journal, ,
日本原子力研究開発機構の大型核融合実験装置JT-60は、実験運転において約130万kVAもの大電力をパルス的に必要とするため、商用電力系統からすべての電力を受電することができない。このため、フライホイール効果を持つ総容量約110万kVAの電動発電機3台を設置し、JT-60の実験運転に必要なパルス電力を供給している。JT-60の電動発電機は、1985年の供用開始以来20年以上にわたり運転を継続してきた。その間、オーバーホールや細密点検などの保守に加え、幾つかのトラブルも経験してきた。世界最大級のフライホイール付電動発電機やその周辺機器について、20年以上にわたる運転経験を発表する。
古川 純*; 山本 剛史*; 野田 浩希*; 佐藤 忍*; 江夏 昌志; 山田 尚人; 喜多村 茜; 佐藤 隆博; 横山 彰人; 大久保 猛; et al.
no journal, ,
大気Micro-PIXE (particle induced X-ray emission)を用いた植物組織切片の元素分析手法の確立と、微量元素の生理学的機能の解明を目的に研究を進めている。今回は、植物体の構造維持に関与する不溶性の元素(Ca,Si)を残存させることができるパラフィン包埋法とTIARAの大気Micro-PIXE分析システムを用いた分析手法を考案し、通常及び遺伝子改変したイネの葉身の切片試料の分析に応用した。その結果、Caは葉身の内側、特に細胞と細胞の接着部分である中葉と呼ばれる部位に粒状に分布しており、Siは葉の表皮に一様かつ多量に分布するが葉身の内側には少量しか検出されなかった。CaもSiも細胞壁における構造維持が中心的な役割の一つとされており、これを支持する結果と考えられる。遺伝子改変されたイネ葉身の分析では、表皮のSi分布が不均一になり量も減っていたが、葉身の内側に存在する量は増加していた。また、Caの蓄積量が少ないはずの未成熟葉であっても葉身内部にCaの局在が認められた。このように、パラフィン包理法と大気Micro-PIXEによって元素局在の変化を解析することに成功し、遺伝子機能の変化や欠損が起こった際の植物の応答の詳細な解析が可能となった。
島田 勝弘; 寺門 恒久; 大森 栄和; 岡野 潤; 古川 弘; 柴田 一之; 寺門 祐之; 柴田 孝俊; 松川 誠; 栗原 研一
no journal, ,
トカマク国内重点化装置JT-60SAでは、コイルの超伝導化,加熱装置の増力,運転時間の伸長に向け新しい電源システムが必要となる。JT-60SA電源システムは、既存の電源設備を有効に利用し、新規製作する電源と組合せたシステムとする予定である。そのため、標準運転パターンからコイル電源構成の基本仕様を検討し、コイル電源及び加熱装置への新しい給電システムの設計検討を行った。その結果、5つのEFコイル電源は、新規製作するベース電源と既存電源を再利用したブースタ電源で構成し、2つのEFコイル電源は、ベース電源とブースタ電源のほかに、既存電源を再利用したアシスト電源で構成し、CSコイル電源は、ベース電源と遮断器と抵抗による高電圧発生回路で構成する必要があることがわかった。また、加熱装置の増力により、供給電力の一部を商用系統から直接受電する必要があるので、シミュレーションにより、受電点での高調波電流及び電圧降下を評価した。その結果、275kV受電点における電圧変動率約1%,等価妨害電流は5.17Aとなり、受電条件を満たしていないことから、高調波フィルタ及び無効電力補償装置が必要であることがわかった。
高井 俊秀; 高田 準太郎; 中島 邦久; 古川 智弘; 逢坂 正彦
no journal, ,
福島第一原子力発電所(1F)廃止措置において、炉内構造材に付着したCsからの被ばく線量評価及び取出し工法選定のための基礎情報として、Csの付着性状の評価が重要となる。シビアアクシデント時には、高温に熱せされた構造材に含まれるケイ素とCsが化学反応を起こし強固に吸着する「化学吸着」を生じることが想定されているが、既存知見だけでは1F事故条件範囲を網羅するには十分でない。そこで本研究では、より広い温度・雰囲気条件範囲下でCs化学吸着挙動を実験的・熱力学解析的に調査することした。本報告では、化学吸着により生成する化合物と想定される高純度セシウムシリケート試料の合成結果について述べる。
山野 秀将; 高井 俊秀; 古川 智弘; 斉藤 淳一; 菊地 晋; 江村 優軌; 東 英生*; 福山 博之*; 西 剛史*; 太田 弘道*; et al.
no journal, ,
我が国の先進ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷事故評価において制御棒材の炭化ホウ素(B C)とステンレス鋼(SS)の共晶溶融反応及び移動挙動を模擬する必要がある。そのため、新規プロジェクトを立ち上げ、共晶溶融反応実験、共晶溶融物の熱物性評価、共晶溶融反応に関する物理モデル開発に着手した。共晶溶融実験では可視化実験、反応速度実験及び材料分析を行う。物性は液相から固相までの範囲で測定する。これらの反応速度や物性を基に、シビアアクシデント解析コードのための物理モデルを開発する。本発表はプロジェクト全体概要及び平成29年度までの進捗概要について報告する。
C)とステンレス鋼(SS)の共晶溶融反応及び移動挙動を模擬する必要がある。そのため、新規プロジェクトを立ち上げ、共晶溶融反応実験、共晶溶融物の熱物性評価、共晶溶融反応に関する物理モデル開発に着手した。共晶溶融実験では可視化実験、反応速度実験及び材料分析を行う。物性は液相から固相までの範囲で測定する。これらの反応速度や物性を基に、シビアアクシデント解析コードのための物理モデルを開発する。本発表はプロジェクト全体概要及び平成29年度までの進捗概要について報告する。