Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Guo, B.*; Xiong, Y.*; Chen, W.*; Saslow, S. A.*; 香西 直文; 大貫 敏彦*; Dabo, I.*; 笹木 恵子*
Journal of Hazardous Materials, 389, p.121880_1 - 121880_11, 2020/05
被引用回数:55 パーセンタイル:89.33(Engineering, Environmental)To elucidate retention mechanism of cement waste form for radioactive iodine, this paper investigated interaction mechanism between iodine and ettringite, which is a component mineral of cement and has anion exchange ability. We revealed that ettringite has a high capacity for accommodating IO
 via anion substitution for SO
via anion substitution for SO
 . The combined iodine K-edge extended X-ray absorption fine structure spectra and first-principles calculations using density functional theory suggested that IO
. The combined iodine K-edge extended X-ray absorption fine structure spectra and first-principles calculations using density functional theory suggested that IO
 was stabilized in ettringite by hydrogen bonding and electrostatic forces. The bonding charge density analysis of the substituted IO
was stabilized in ettringite by hydrogen bonding and electrostatic forces. The bonding charge density analysis of the substituted IO
 into the ettringite structure revealed the interaction between intercalated IO
into the ettringite structure revealed the interaction between intercalated IO
 with the structural water molecules. These results provided valuable insight into the long-term stabilization of anionic iodine species and their migration in cementitious nuclear waste repository or alkaline environments.
with the structural water molecules. These results provided valuable insight into the long-term stabilization of anionic iodine species and their migration in cementitious nuclear waste repository or alkaline environments.
Yu, Q.*; 大貫 敏彦*; 香西 直文; 坂本 文徳; 田中 万也; 笹木 恵子*
Chemical Geology, 470, p.141 - 151, 2017/10
被引用回数:16 パーセンタイル:51.87(Geochemistry & Geophysics)本研究では、2種類のMn酸化物(トドロカイトとバーネサイト)が持つCs保持能を評価した。トドロカイトには、Csの吸着選択性がバーネサイトよりも高いサイトがあることがわかった。Cs初期濃度10 mol/Lで吸着させた後、吸着したCsを1M NaClとNH
mol/Lで吸着させた後、吸着したCsを1M NaClとNH Clで脱離させたところ、約34%のCsが脱離せずにトドロカイトに残った。この値はバーネサイトに残ったCsの割合よりもずっと多かった。これらの結果は、トドロカイトが土壌中の放射性Csの固定に寄与することを強く示唆する。
Clで脱離させたところ、約34%のCsが脱離せずにトドロカイトに残った。この値はバーネサイトに残ったCsの割合よりもずっと多かった。これらの結果は、トドロカイトが土壌中の放射性Csの固定に寄与することを強く示唆する。
Yu, Q.; 笹木 圭子*
Hydrometallurgy, 150, p.253 - 258, 2014/12
被引用回数:9 パーセンタイル:39.33(Metallurgy & Metallurgical Engineering)Microbial catalysis, a primary pathway for the generation of Mn oxides in most natural environments, provides potential to fabricate new materials. A microtube-type lithium manganese oxide (LMO-MT) was synthesized through a solid-state transformation using Mn-oxidizing fungus, Paraconiothyrium sp. WL-2. Compared with abiotic precursors, the lithium-ion sieve microtube (HMO-MT) showed better performance for Li+ recovery. In order to clarify the formation process of LMO-MTs, in situ high-temperature X-ray diffraction was used to compare with three synthetic references. The effects of calcination temperature on crystal phase, composition, particle size and lattice parameters of the LMO-MTs were systematically discussed. It was found that the poorly crystalline structure of biogenic precursor as well as high content of organic matter facilitated the formation of highly crystalline LMO-MTs at low temperature. The unique structural properties of LMO-MTs, including high crystallinity and small lattice constant, are attributed to the high Li sorption capacity of HMO-MTs.
sorption capacity of HMO-MTs.
 on biogenic birnessite
on biogenic birnessite笹木 圭子*; Yu, Q.; 桃木 大地*; 忰山 卓也*
Applied Clay Science, 101, p.23 - 29, 2014/11
被引用回数:14 パーセンタイル:40.30(Chemistry, Physical)Adsorption of Cs on biogenic birnessite was investigated and compared with (ad)sorption of other heavy metals and also with (ad)sorption on chemically synthesized birnessite. The adsorption density of Cs
on biogenic birnessite was investigated and compared with (ad)sorption of other heavy metals and also with (ad)sorption on chemically synthesized birnessite. The adsorption density of Cs on biogenic birnessite was smaller than that on chemically synthesized birnessite; however, the (ad)sorption densities of Co
on biogenic birnessite was smaller than that on chemically synthesized birnessite; however, the (ad)sorption densities of Co and Ni
and Ni on biogenic birnessite were larger than on chemically synthesized birnessite. These phenomena can be interpreted by considering the distinctive nano-structure of biogenic birnessite, which is not only poorly crystalline and includes organic matter but also according to EXAFS contains a greater proportion of vacant central metal sites than is found in synthetic birnessite. Adsorbed Cs
on biogenic birnessite were larger than on chemically synthesized birnessite. These phenomena can be interpreted by considering the distinctive nano-structure of biogenic birnessite, which is not only poorly crystalline and includes organic matter but also according to EXAFS contains a greater proportion of vacant central metal sites than is found in synthetic birnessite. Adsorbed Cs ions on both birnessites were mainly in the form of outer sphere complexes, which cannot easily occupy vacant central metal sites in biogenic birnessite. Biogenic birnessite has a greater specific surface area and more fine pores than synthetic birnessite, but these factors do not necessarily lead to more adsorption sites for Cs
ions on both birnessites were mainly in the form of outer sphere complexes, which cannot easily occupy vacant central metal sites in biogenic birnessite. Biogenic birnessite has a greater specific surface area and more fine pores than synthetic birnessite, but these factors do not necessarily lead to more adsorption sites for Cs ions.
ions.
 sp. strain NGY-1
sp. strain NGY-1田中 万也*; Yu, Q.; 笹木 圭子*; 大貫 敏彦
Geomicrobiology Journal, 30(10), p.874 - 885, 2013/08
被引用回数:21 パーセンタイル:49.25(Environmental Sciences)生物起源のMn酸化物への2価Coの収着挙動を調べた結果、生物起源Mn酸化物への収着は無機合成Mn酸化物への速度よりも遅かった。2価Coの生物起源及び無機合成Mn酸化物への収着は3価Coへの酸化収着であった。両者の違いの原因は構造の違い及び共存イオンの違いに起因すると考えられる。
Yu, Q.; 笹木 圭子*; 田中 万也*; 大貫 敏彦; 平島 剛*
Geomicrobiology Journal, 30(9), p.829 - 839, 2013/07
被引用回数:38 パーセンタイル:70.99(Environmental Sciences)真菌により生成するMn酸化物の生成過程におけるZnイオンの影響を調べた結果、生成したMn酸化物はバーネサイトであった。バーネサイトの構造をXAFS等により調べたところ、Zn濃度に依存してMn酸化物の積層構造が変化した。ZnのMn酸化物への収着様式により生成するMn酸化物の積層が変化したと考えられる。
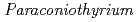 sp. WL-2 strain affecting sorption of Co
sp. WL-2 strain affecting sorption of Co
Yu, Q.*; 笹木 圭子*; 田中 万也*; 大貫 敏彦; 平島 剛*
Chemical Geology, 310-311, p.106 - 113, 2012/06
被引用回数:69 パーセンタイル:84.69(Geochemistry & Geophysics)生物起源のMn酸化物の層間の空の吸着サイトの存在とMn(III)の存在がCo の特異的な吸着に寄与していることを、吸着実験及びXAFSによる構造解析から明らかにした。
の特異的な吸着に寄与していることを、吸着実験及びXAFSによる構造解析から明らかにした。
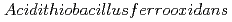
笹木 圭子*; 高次 晃一郎*; 金子 賢治*; 香西 直文; 大貫 敏彦; Tuovinen, O. H.*; 平島 剛*
Hydrometallurgy, 104(3-4), p.424 - 431, 2010/10
被引用回数:23 パーセンタイル:69.13(Metallurgy & Metallurgical Engineering)ヒ素含有鉱物(エナジャイト)の鉄酸化菌による溶解を調べた結果、中間的なヒ素鉱物が形成されることをXRDやXANES測定により明らかにした。
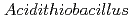
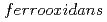
笹木 圭子*; 高次 晃一郎*; 平島 剛*; 香西 直文; 大貫 敏彦; Tuovinen, O. H.*
Advanced Materials Research, 71-73, p.485 - 488, 2009/05
被引用回数:4 パーセンタイル:88.70(Ecology)ヒ素耐性鉄酸化菌を用いてヒ素含有鉱物であるenargiteの溶解を行い、ヒ酸を含む2次鉱物が生成することを明らかにした。
佐々木 明; 周藤 佳子; 横田 恒*
JAERI-Data/Code 2002-003, 54 Pages, 2002/03
Java言語は、インターネット技術の要素として開発され、広く活用されるようになっているが、その基幹にあるオブジェクト指向の概念が、多種多様のオリジナルなデータを扱う大規模計算機シミュレーションとその可視化にも有用なことを示す。すなわちJava言語を活用することによって、れまで市販の可視化ツールを用いないとできなかった可視化表現を行い、しかもそれをユーザーが自分のプログラムの中で意のままにあやつるという、研究の現場で永く望まれていたことが実現する可能性が開かれると考えられる。本報告書では、Java言語を用いた実験,シミュレーション結果の可視化技術について検討し、1次元,2次元データの可視化,解析のためのプログラム開発に応用した例を示す。
森林 健悟; 周藤 佳子*; Zhidkov, A. G.; 佐々木 明; 香川 貴司*
Laser and Particle Beams, 19(4), p.643 - 646, 2001/10
被引用回数:6 パーセンタイル:30.03(Physics, Applied)高強度レーザー照射で生成した多価イオンが固体と衝突すると中空原子になる。この中空原子から発生するX線に関して考察する。原子課程シミュレーションからこの中空原子は超高速(1fs程度)に生成され、X線への変換効率は非常に高い(一つのイオンが固体に衝突したとき約0.03個のX線が発生する。)ことが明らかとなった。このX線発生過程を用いた高密度プラズマのイオン数の温度の診断法及び、X線源の実験系を提案した。数keVのX線領域では従来のX線源はレーザー強度がある程度大きくするとX線量は飽和してしまい、レーザー強度の増加に対して一定あるいは、減少するようになる。一方、中空原子から発生するX線はレーザーのエネルギーとともに増加するので、高強度レーザー開発の発展に伴ってX線量が増加することが予測される。レーザーエネルギーが10Jのとき、X線の個数は3 10
10 個であることが見積もれた。
個であることが見積もれた。
森林 健悟; Zhidkov, A. J.*; 佐々木 明; 周藤 佳子; 鈴木 慎悟*
Atomic Collision Research in Japan, No.27, p.1 - 3, 2001/00
短パルス高強度レーザーを数nmの大きさの巨大クラスターに照射することにより高温高密度電子状態を生成することが予測されている。この電子の衝突電離により内殻励起状態を形成し、X線を発生する。特に、クリプトンやゼノンのような高い電子番号の原子のクラスターの場合は、短波長X線が発生し、短波長X線源やX線レーザー源として注目されている。ここでは高温高密度状態でのゼノンイオンの多価イオン及び、内殻励起状態の生成過程に関して考察する。電子温度を数keV,電子密度を10 ~10
~10 /cm
/cm とする。考慮した原子過程としては電子衝突励起・電離,自動イオン化,輻射遷移である。この条件のもとでニッケル様ゼノンイオンを初期状態とし、電子衝突で電離し、数100fs後の内殻励起状態などのカルシウム様ゼノンイオンのポピュレーションを計算した。ポピュレーションの密度,温度依存性を調べた。ポピュレーションは密度と比例して増加するが、10
とする。考慮した原子過程としては電子衝突励起・電離,自動イオン化,輻射遷移である。この条件のもとでニッケル様ゼノンイオンを初期状態とし、電子衝突で電離し、数100fs後の内殻励起状態などのカルシウム様ゼノンイオンのポピュレーションを計算した。ポピュレーションの密度,温度依存性を調べた。ポピュレーションは密度と比例して増加するが、10 cm
cm のとき約100fsで飽和すること、また、温度とともに増加するが、10keVを超えると温度依存性がなくなることがわかった。内殻(1s,2s,2p,3s,3p)電離過程を含む場合と含まない(3d電子だけが電離する)場合を計算した結果、前者のポピュレーションの方が三桁程度大きくなり、高温高密度電子状態では内殻電離過程が多価イオン生成に重要であることを発見した。
のとき約100fsで飽和すること、また、温度とともに増加するが、10keVを超えると温度依存性がなくなることがわかった。内殻(1s,2s,2p,3s,3p)電離過程を含む場合と含まない(3d電子だけが電離する)場合を計算した結果、前者のポピュレーションの方が三桁程度大きくなり、高温高密度電子状態では内殻電離過程が多価イオン生成に重要であることを発見した。
森林 健悟; Zhidkov, A. G.; 佐々木 明; 周藤 佳子; 鈴木 慎悟*
Proceedings of 2nd International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA 2001), p.1182 - 1185, 2001/00
短パルス高強度レーザーを数nmの大きさの巨大クラスターに照射することにより高温高密度電子状態を生成することが予測されている。この電子の衝突電離により内殻励起状態を形成し、X線を発生する。特に、クリプトンやゼノンのような高い原子番号の原子のクラスターの場合は、短波長X線が発生し、短波長X線源やX線レーザー源として注目されている。ここでは高温高密度状態でのクリプトン,ゼノンイオンの多価イオン及び、内殻励起状態の生成過程,内殻励起状態から発生する短波長X線発生に関して考察する。電子温度を数keV,電子密度を10 ~10
~10 /cm
/cm とする。考慮した原子過程としては電子衝突励起・電離,自動イオン化,輻射遷移である。この条件のもとでニッケル様イオンを初期状態とし、電子衝突で電離し、数100fs後の内殻励起状態などのポピュレーションを計算し、それからのX線発生のスペクトルを求める。ゼノンイオンに対して内殻(1s,2s,2p,3s,3p)電離過程を含む場合と含まない(3d電子だけが電離する)場合を計算した結果、前者のポピュレーションの方が三桁程度大きくなり、高温高密度電子状態では内殻電離過程が多価イオンに重要な役割を演じることがわかった。クリプトンクラスターの場合は、ナトリウム様やネオン様イオンのポピュレーションが大きくなることが観測されているが、基底状態のナトリウム様クリプトンイオン(1s
とする。考慮した原子過程としては電子衝突励起・電離,自動イオン化,輻射遷移である。この条件のもとでニッケル様イオンを初期状態とし、電子衝突で電離し、数100fs後の内殻励起状態などのポピュレーションを計算し、それからのX線発生のスペクトルを求める。ゼノンイオンに対して内殻(1s,2s,2p,3s,3p)電離過程を含む場合と含まない(3d電子だけが電離する)場合を計算した結果、前者のポピュレーションの方が三桁程度大きくなり、高温高密度電子状態では内殻電離過程が多価イオンに重要な役割を演じることがわかった。クリプトンクラスターの場合は、ナトリウム様やネオン様イオンのポピュレーションが大きくなることが観測されているが、基底状態のナトリウム様クリプトンイオン(1s 2s
2s 2p
2p 3s)では内殻2p電子の電離断面積は最外殻3s電子の電離断面積よりも非常に大きく、ネオン様イオンでは2pの内殻励起状態と基底状態の間に反転分布を形成する可能性がある。
3s)では内殻2p電子の電離断面積は最外殻3s電子の電離断面積よりも非常に大きく、ネオン様イオンでは2pの内殻励起状態と基底状態の間に反転分布を形成する可能性がある。
森林 健悟; 佐々木 明; Zhidkov, A. G.; 上島 豊; 周藤 佳子*; 香川 貴司*
Atomic Collision Research in Japan, No.26, p.111 - 113, 2000/00
最近の高強度レーザーの発展に伴い、高輝度X線、高速電子、多価イオンなどの新しい励起源が利用できるようになりつつある。これらが固体や蒸気と相互作用すると内殻励起状態や中空原子を生成し、それからX線が発生する。今回は、このX線発生の原子過程とそれを用いた応用に関して議論する。高輝度X線源の場合は、マグネシウム蒸気を標的として場合の内殻電離型、中空原子型X線レーザーの実験系を提案した。高速電子源の場合は、内殻励起状態と中空原子のポピュレーションとレーザー強度との関係で計算した。多価イオン源の場合は、X線発生の原子過程が超高速(1fs程度)で起こること、及び、X線への変換効率は約0.03で高効率であることを明らかにした。10Jのレーザーを用いたとき発生するX線の個数は約10 個と見積もられた。これはX線源として十分に機能する。
個と見積もられた。これはX線源として十分に機能する。
小林 隆俊*; 横堀 仁*; 佐々木 誠*; 多田 恵子*
PNC TJ206 73-07, 228 Pages, 1973/04
本作業の成果を、高速増殖炉(原型炉)もんじゅの設計に反映する事を目的とし、その模擬実験であるモーツアルト計画の臨界実験解析を行なった。今回は、炉物理的な興味を主とした1領域炉心のMZA実験およびもんじゅのClean‐mock up体系である2領域炉心のMZB実験の解析を行なった。「但し、MZBに関しては、径方向グランケツト部の90 セクターに、(1)天然ウラン酸化物、(2)劣化ウラン配化物、および(3)天然金属ウランの各組成を用いた3つのVersionの解析を行なった。」またさらに、Pu同位体の影響を見る目的で実験が行われた。FCA-VI-1炉心の解析を行なった。解析した項目は、臨界量、中性子バランス、中性子スペクトル、形状因子、輸送補正値、中性反応率比、エッヂ・ワース、中心物質反応度価値、非均質効果、ナトリウムボイド反応度係数および反応率分布である。特に、反応率分布については詳細な解析を行い、実験値との比較検討からC/Eを求めた。
セクターに、(1)天然ウラン酸化物、(2)劣化ウラン配化物、および(3)天然金属ウランの各組成を用いた3つのVersionの解析を行なった。」またさらに、Pu同位体の影響を見る目的で実験が行われた。FCA-VI-1炉心の解析を行なった。解析した項目は、臨界量、中性子バランス、中性子スペクトル、形状因子、輸送補正値、中性反応率比、エッヂ・ワース、中心物質反応度価値、非均質効果、ナトリウムボイド反応度係数および反応率分布である。特に、反応率分布については詳細な解析を行い、実験値との比較検討からC/Eを求めた。