Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
廣瀬 エリ; 横谷 明徳*; 野口 実穂*; Huart, L.*; 鈴木 啓司*
放射線生物研究, 59(2), p.134 - 156, 2024/06
細胞が放射線照射を受けた後、どのようなプロセスをたどって長期期間を経て現れる発がんなどの放射線影響につながるのか、放射線の長期影響をゲノムの構造・機能変化とエネルギー代謝の2つの視点から論じる。放射線によるゲノムへの長期影響の一つとして、ゲノム不安定性が子孫細胞に受け継がれることがわかってきた。X線照射によりX染色体上のHPRT1遺伝子座に欠失を有するヒト細胞のクローン株を樹立し、これらを用いて筆者らが子孫細胞に受け継がれた大規模なDNA欠失を調べたところ、欠失部位の両端にはっきりとした境目がなく、少なくともX染色体上の約130-137 Mbにわたって、DNA欠失部分と残存部分がパッチワーク状に混在していることが分かった。これはX線照射時における細胞核内でのDNAの収納のされ方に依存して、放射線エネルギー付与の空間密度を反映したDSBの分布を示していると考えられる。また、一般に考えられている1Gyあたり約40個/細胞に生じるDSBの頻度を考慮すると、非DSB型クラスターDNA損傷の塩基除去修復によって引き起こされる 二次的なDSBに起因する欠失も生じたと考えられる。さらに、複雑なDNA欠失パターンがゲノム全体の機能に及ぼす影響を、遺伝子発現を指標に調べたところ、遺伝子発現変動は大規模欠失領域の近傍だけでなくDNA欠失が位置するX染色体全域に及んでいた。これは、二次的なDSBに伴うCTCF結合サイトの欠失が要因であることを示唆している。他方、放射線照射後に細胞周期から離脱し細胞周期を不可逆的に停止した細胞(放射線誘発早期老化細胞)の場合、放射線の長期影響がエネルギー代謝に現れる。放射線誘発早期老化細胞は、細胞周期が回転しないため、DNA合成や細胞分裂に必要なエネルギーは不要で、このため、正常細胞と比較してエネルギー代謝活性は、一見、低いと予想されがちである。しかし、ミトコンドリアの膜電位差を通じて代謝活性を調べたところ、放射線誘発早期老化細胞では、代謝活性が上昇する様子が観察され、代謝活性化に伴うATP量の増加も合わせて報告された。ミトコンドリア活性の亢進に伴い生産された活性酸素種が近傍の細胞の損傷を誘発すると考えられることから、放射線誘発早期老化細胞は長期にわたって周囲の正常細胞にも影響を与えることが予想される。本稿ではこのような、長い時間が経っても残り続ける放射線の"爪痕"について論じる。
三上 智; 時吉 正憲*; 佐藤 里奈*; 田中 大輔*; 吉村 和也
日本放射線安全管理学会誌, 23(1), p.10 - 17, 2024/06
複数の除染作業員のリアルタイムの被ばく管理に適用することをねらいとして大成建設とインフォキューブLAFLAが開発したスマートフォン無線接続型線量計について基本特性を把握するため、原子力機構の光子線校正場にて校正及び線量率特性、エネルギー特性、方向特性等の試験を行った。結果は、それぞれの項目で概ね良好な特性を示した。除染作業には有効に利用できるものと評価した。
熊谷 友多
放射線(インターネット), 49(1), p.15 - 17, 2024/03
水の放射線分解による反応はウラン酸化物の表面を酸化し、ウランの溶解を引き起こす。この反応過程の理解は、使用済み燃料の深地層処分場の安全性評価の化学的基礎であり、また過酷事故後の燃料デブリの取り出しと保管に知見を提供する。これまでにも使用済核燃料からの放射性核種の溶出速度を評価するために、いくつかの化学反応速度モデルが開発されてきた。しかし、最近の実験研究で得られた新たな知見から、UO 表面での反応過程は従来の反応モデルよりも相当に複雑であること分かってきている。そのため、ウランの表面酸化と溶解の反応機構を再検討するべく基礎研究が進められている。本稿では、その反応機構に関する最近の研究例を紹介する。
表面での反応過程は従来の反応モデルよりも相当に複雑であること分かってきている。そのため、ウランの表面酸化と溶解の反応機構を再検討するべく基礎研究が進められている。本稿では、その反応機構に関する最近の研究例を紹介する。
藤田 奈津子; 松原 章浩*; 神野 智史; 木村 健二
放射線(インターネット), 48(4), p.137 - 138, 2024/02
東濃地科学センターでは大きさ約2m 2mの超小型AMSを開発中であり、本装置はイオンチャネリングを利用して炭素-14のAMS測定の際に妨害核種となる同質量分子を分別する新しい方法を実証するための装置である。本投稿では開発中の装置に関する紹介と開発状況を報告した。
2mの超小型AMSを開発中であり、本装置はイオンチャネリングを利用して炭素-14のAMS測定の際に妨害核種となる同質量分子を分別する新しい方法を実証するための装置である。本投稿では開発中の装置に関する紹介と開発状況を報告した。
 Srの加速器質量分析
Srの加速器質量分析本多 真紀; Martschini, M.*; Marchhart, O.*; Steier, P.*; Golser, R.*; 坂口 綾*
放射線(インターネット), 48(4), p.130 - 136, 2024/02
ストロンチウム90( Sr、28.9年)は、体内では骨や歯に蓄積して健康障害を引き起こすため、内部被ばく線量評価において重要な核分裂生成物核種である。そのため、環境中の
Sr、28.9年)は、体内では骨や歯に蓄積して健康障害を引き起こすため、内部被ばく線量評価において重要な核分裂生成物核種である。そのため、環境中の Srの分布やその経時変化(生物相における
Srの分布やその経時変化(生物相における Srの濃縮)を知ることが不可欠である。
Srの濃縮)を知ることが不可欠である。 Srの経年変化を調査するためには多くの環境試料を効率的に分析する必要がある。本稿では
Srの経年変化を調査するためには多くの環境試料を効率的に分析する必要がある。本稿では Sr AMSの実用化に向けて、オーストリア共和国ウィーン大学の3MV AMS施設(VERA: Vienna Environmental Research Accelerator)と共に実施した、
Sr AMSの実用化に向けて、オーストリア共和国ウィーン大学の3MV AMS施設(VERA: Vienna Environmental Research Accelerator)と共に実施した、 Sr濃度既知の環境試料の分析成果に関して解説する。本研究では、
Sr濃度既知の環境試料の分析成果に関して解説する。本研究では、 Sr濃度が既知の環境試料(IAEA-447, IAEA-A-12, IAEA-TEL-2015-03 sample 5:各1 dry-g)を分析することでAMS法の妥当性を示した。本研究で開発した化学分離にかかる時間は約2日であり、従来の
Sr濃度が既知の環境試料(IAEA-447, IAEA-A-12, IAEA-TEL-2015-03 sample 5:各1 dry-g)を分析することでAMS法の妥当性を示した。本研究で開発した化学分離にかかる時間は約2日であり、従来の 線検出法よりシンプルな手法である。
線検出法よりシンプルな手法である。 Srの測定は、加速したイオンとレーザーの相互作用を利用した質量分析装置(ILIAMS)と組み合わせたAMSシステムで実施した。AMS法は
Srの測定は、加速したイオンとレーザーの相互作用を利用した質量分析装置(ILIAMS)と組み合わせたAMSシステムで実施した。AMS法は Srの検出限界
Srの検出限界 0.1mBq (
0.1mBq ( 1.3
1.3 10
10 atoms)を達成し、これは一般的な
atoms)を達成し、これは一般的な 線検出の1/30である。この低い検出限界を達成した結果、AMS法はより少ないサンプル量で
線検出の1/30である。この低い検出限界を達成した結果、AMS法はより少ないサンプル量で Srの定量が可能になり、例えば
Srの定量が可能になり、例えば Sr濃度が4 mBq/Lの日本の淡水試料では、5リットルの試料量で分析可能である。
Sr濃度が4 mBq/Lの日本の淡水試料では、5リットルの試料量で分析可能である。
前田 茂貴
放射線科学フロンティア, (5), P. 17, 2024/02
Ac-225は医薬品向け 放出核種として注目されており、今後需要が増えることが見込まれる。創薬分野の研究開発のみならず経済安全保障の観点でも国産化が急務である。「常陽」では、Ac-225製造の技術基盤を確立するため、「常陽」に隣接するPIE施設への照射装置の迅速な払出し技術の確立、Ra-226の中性子照射によるAc-225製造量評価、Ra-226からAc-225を効率的に回収するための分離プロセスを検討している。本発表では、国産化への国内の動き、原子力機構の取り組み、「常陽」での照射、試料移送、化学処理、医療側ニーズへの対応を検討した結果の見通しについて報告する。
放出核種として注目されており、今後需要が増えることが見込まれる。創薬分野の研究開発のみならず経済安全保障の観点でも国産化が急務である。「常陽」では、Ac-225製造の技術基盤を確立するため、「常陽」に隣接するPIE施設への照射装置の迅速な払出し技術の確立、Ra-226の中性子照射によるAc-225製造量評価、Ra-226からAc-225を効率的に回収するための分離プロセスを検討している。本発表では、国産化への国内の動き、原子力機構の取り組み、「常陽」での照射、試料移送、化学処理、医療側ニーズへの対応を検討した結果の見通しについて報告する。
新居 昌至; 前田 茂貴
臨床放射線, 68(10), p.963 - 970, 2023/10
Ac-225は医薬品向け 放出核種として注目されており、今後需要が増えることが見込まれる。創薬分野の研究開発のみならず経済安全保障の観点でも国産化が急務である。「常陽」では、Ac-225製造の技術基盤を確立するため、「常陽」に隣接するPIE施設への照射装置の迅速な払出し技術の確立、Ra-226の中性子照射によるAc-225製造量評価、Ra-226からAc-225を効率的に回収するための分離プロセスを検討している。本発表では、「常陽」での照射からPIE施設への移送、化学処理の経過時間による減衰を考慮しても十分なAc-225製造が可能なことについて報告する。また、原子力委員会のRI製造部会のアクションプランを踏まえた今後の計画を述べる。
放出核種として注目されており、今後需要が増えることが見込まれる。創薬分野の研究開発のみならず経済安全保障の観点でも国産化が急務である。「常陽」では、Ac-225製造の技術基盤を確立するため、「常陽」に隣接するPIE施設への照射装置の迅速な払出し技術の確立、Ra-226の中性子照射によるAc-225製造量評価、Ra-226からAc-225を効率的に回収するための分離プロセスを検討している。本発表では、「常陽」での照射からPIE施設への移送、化学処理の経過時間による減衰を考慮しても十分なAc-225製造が可能なことについて報告する。また、原子力委員会のRI製造部会のアクションプランを踏まえた今後の計画を述べる。
河原 梨花*; 越智 康太郎; 山口 克彦*; 鳥居 建男*
放射線(インターネット), 48(2), p.43 - 48, 2023/04
福島第一原子力発電所事故により、大量の放射性物質が周辺環境に拡散した。現在も帰還困難区域に位置する地域の放射線分布を把握することは重要である。本研究では、コンプトンカメラと光学カメラを組み合わせ、線源位置とその強度の三次元分布図の作成を目指した。帰還困難区域(大熊町)の公園駐車場と民家周辺の2カ所で調査を行った。空間線量率分布を、杖型GPS付きサーベイメータ(日本放射線エンジニアリング株式会社製、ガンマプロッターH)による測定で把握した。ホットスポットに向けて、異なった複数の位置及び角度でコンプトンカメラ(米H3D社製、H420)による測定を行った。ソフトウェア(Application Programming Interface Example)により、コンプトンカメラで得られた放射線の入射情報(入射時間, エネルギー, x, y, z)をリアルタイムで確認した。高線量地域でホットスポットをさまざまな位置や角度から撮影をすることで、放射線源の位置とその空間的広がりを確認することができた。
熊谷 友多
放射線化学(インターネット), (115), p.43 - 49, 2023/04
ウラン酸化物の放射線による酸化と水への溶解反応に関する研究は、使用済核燃料の地層処分を背景として進められてきた。またその知見は、原子炉過酷事故で形成される燃料デブリの化学的な安定性を検討する基礎となっている。本稿ではウラン酸化物の放射線よる化学反応について既往研究についても取り上げ、受賞対象となった研究の背景や意義について紹介する。
岡 壽崇
知ってるつもりの放射線読本, p.215 - 216, 2023/04
ESR線量計測法を用いた野生ニホンザルの外部被ばく線量推定に関連して、ESR線量計測法の歴史や原理、試料前処理法などについて解説した。
五十嵐 悠; 山口 一郎*; 小田 啓二*; 福士 政広*; 阪間 稔*; 飯本 武志*
日本放射線安全管理学会誌, 21(2), p.74 - 76, 2022/11
日本保健物理学会エックス線被ばく事故検討WGでは、2021年に国内で発生したエックス線被ばく事故の背景と経緯、線量評価、健康影響などの情報収集を行い、(1)安全管理上の対策・課題、(2)測定、線量推定に関する課題、(3)社会とのコミュニケーション上の課題等の整理を進めている。本発表では検討WGを代表して、これまでに集約された国内外におけるエックス線被ばく事故事例を紹介し、事故に至る原因の整理とこれにより明らかとなった問題を提起する。
寺阪 祐太; 渡辺 賢一*; 瓜谷 章*
放射線(インターネット), 47(3), p.89 - 96, 2022/10
We developed a novel single-end readout type position-sensitive optical fiber radiation sensor. This sensor measures the radiation intensity distribution along the fiber with light readout only from single end of the optical fiber. To estimate the radiation intensity distribution, we analyzed the wavelength spectrum output at single end of the fiber, which contains information about the transmission distance of light inside the fiber. Based on the unfolding of the wavelength spectrum, the radiation intensity distribution along the fiber could be estimated. The effects of wavelength channel selection and signal-to-noise ratio of the wavelength spectrum on radiation distribution estimation were evaluated. In addition, we performed that our optical fiber sensor could estimate the radiation intensity distribution under the dose rate of 3 Gy/h. The dose rate detection limit was estimated to be 21 mGy/h for the irradiation range of 20 cm.
端 邦樹; 佐藤 智徳
放射線化学(インターネット), (114), p.33 - 38, 2022/10
福島第一原子力発電所(1F)の格納容器内の汚染水中における腐食環境の評価に資することを目的に、放射線環境下での鉄鋼材料の腐食データ及び関連するラジオリシスデータをまとめた腐食データベースを整備した。今回のデータ整理によって、1F汚染水中の不純物が腐食因子である過酸化水素の生成挙動等に与える影響の解析的評価を可能とするとともに、放射線環境下で生成する酸化剤濃度と腐食速度や腐食電位との関係を示すことができるようになった。
熊谷 友多; 日下 良二; 中田 正美; 渡邉 雅之; 秋山 大輔*; 桐島 陽*; 佐藤 修彰*; 佐々木 隆之*
放射線化学(インターネット), (113), p.61 - 64, 2022/04
東京電力福島第一原子力発電所(1F)事故では燃料や被覆管、構造材料等が高温で反応して燃料デブリが形成されたとみられている。1F炉内は注水や地下水の流入で湿潤な環境にあり、放射線による水の分解が継続していると考えられ、これが燃料デブリの化学的な性状に影響する可能性がある。1F燃料デブリの組成や形状については、いまだに十分な情報が得られていないが、炉内や周辺で採取された微粒子の分析結果では、様々な組成が観測されており、事故進展における温度履歴や物質移動の複雑さを反映していると考えられる。1Fサンプルのように複雑組成の混合物については、水の放射線分解が与える影響に関する知見が乏しい。そこで、水の放射線分解の影響として想定すべき燃料デブリの性状変化を明らかにするため、模擬デブリ試料を用いてH O
O 水溶液への浸漬試験を行った。その結果、H
水溶液への浸漬試験を行った。その結果、H O
O の反応により、模擬デブリ試料からウランが溶出し、過酸化ウラニルの形成が進むことが分かった。またUO
の反応により、模擬デブリ試料からウランが溶出し、過酸化ウラニルの形成が進むことが分かった。またUO 相の固溶体形成によるH
相の固溶体形成によるH O
O に対する安定化が観測された。これらの酸化劣化の過程は、ウラン含有相の反応性や安定性に基づいて説明できることを明らかにした。
に対する安定化が観測された。これらの酸化劣化の過程は、ウラン含有相の反応性や安定性に基づいて説明できることを明らかにした。
松谷 悠佑; 甲斐 健師; 小川 達彦; 平田 悠歩; 佐藤 達彦
放射線化学(インターネット), (112), p.15 - 20, 2021/11
Particle and Heavy Ion Transport code System (PHITS)は、放射線挙動を模擬する汎用モンテカルロコードであり、原子力分野のみならず工学,医学,理学などの多様な分野で広く利用されている。PHITSは2010年に公開されて以降、機能拡張や利便性向上のために改良が進められてきた。今日までに、電子線,陽電子線,陽子線,炭素線の4種類の荷電粒子を対象として、液相水中における個々の原子との反応を模擬できる飛跡構造解析モードの開発を進めてきた。本モードの開発により、DNAスケールまで分解した微視的な線量付与の計算が可能となった。加えて、飛跡構造解析モードの高精度化へ向けて、任意物質中において多様な粒子タイプに適用可能な汎用的飛跡構造解析モードの開発も進められている。本稿で解説するPHITS飛跡構造解析モードに関するこれまでの開発経緯と将来展望により、PHITSコードの原子物理学,放射線化学,量子生命科学分野への応用がより一層期待される。
宮崎 康典; 佐野 雄一
放射線化学(インターネット), (112), p.27 - 32, 2021/11
使用済燃料再処理で発生する高レベル放射性廃液からマイナーアクチニド(MA: Am, Cm)を分離回収する抽出クロマトグラフィの技術開発を行っている。圧力損失を低減する大粒径吸着担体に対し、MAと希土類元素を相互分離する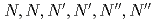 -ヘキサオクチルニトリロトリアセトアミド(HONTA)を含浸した吸着材の安全性を評価した。
-ヘキサオクチルニトリロトリアセトアミド(HONTA)を含浸した吸着材の安全性を評価した。 線照射後の熱的特性や吸着性能の変化、並びに水素ガスの発生量から、MAをランタニド(Ln)から分離可能な線量を1MGyに設定するとともに、分離操作において、現在の想定設備以外で冷却ユニットやオフガスユニット等の予防措置は必要ないことを示した。
線照射後の熱的特性や吸着性能の変化、並びに水素ガスの発生量から、MAをランタニド(Ln)から分離可能な線量を1MGyに設定するとともに、分離操作において、現在の想定設備以外で冷却ユニットやオフガスユニット等の予防措置は必要ないことを示した。
神崎 訓枝
放射線生物研究, 56(3), p.295 - 307, 2021/09
低線量放射線の生体影響は、様々な要因が絡み合い複雑である。生命維持のためのその反応は単純ではない。そこで、動物実験を行って得られた分析結果を自己組織化マップ(Self-organizing maps: SOM)を用いて可視化し、これまでとは違った視点から低線量放射線の生体影響を評価した研究成果を報告する。例えば、低線量放射線の影響は明確なクラスタリングが不可能なデータであったが、SOMでの解析により複数の指標を総合的に評価し、直感的にデータの特徴を把握することが可能となった。本稿では、実例を挙げ、機械学習を用いて放射線生体影響のデータを可視化した成果とその有用性を議論する。
福永 久典*; 松谷 悠佑
放射線生物研究, 56(2), p.208 - 223, 2021/06
ホウ素中性子捕捉療法(Boron Neutron Capture Therapy, BNCT)は、「腫瘍細胞選択的にホウ素薬剤を集積させ、 Bと熱中性子の核反応から生成される短飛程の
Bと熱中性子の核反応から生成される短飛程の 線やLiイオンを利用して、腫瘍細胞に効率的に線量を集中させる」という放射線治療である。最近開発された加速器型中性子線源の登場により、近い将来、BNCTは多くの医療施設で利用可能になることが期待されている。BNCTでは、静脈注射によってホウ素薬剤を腫瘍部に取り込ませた後、比較的長い時間をかけて中性子線照射を行うため、照射中の腫瘍部ホウ素濃度分布が時空間的に不均一に変化することが判っている。したがって、その物理学的な特性と薬理学・生物学的な特性の両方がBNCT治療効果に影響していると予想されるが、このような特性を十分に考慮した予測モデルは現在も開発途上にある。本稿で解説するBNCT治療効果予測モデルの開発に関する歴史的経緯と将来展望は、放射線物理学,薬理学,生物学,医学分野の間をつなぐ学際的な研究アプローチによるシナジー効果を生み、新しいBNCTの時代を切り拓くことが期待される。
線やLiイオンを利用して、腫瘍細胞に効率的に線量を集中させる」という放射線治療である。最近開発された加速器型中性子線源の登場により、近い将来、BNCTは多くの医療施設で利用可能になることが期待されている。BNCTでは、静脈注射によってホウ素薬剤を腫瘍部に取り込ませた後、比較的長い時間をかけて中性子線照射を行うため、照射中の腫瘍部ホウ素濃度分布が時空間的に不均一に変化することが判っている。したがって、その物理学的な特性と薬理学・生物学的な特性の両方がBNCT治療効果に影響していると予想されるが、このような特性を十分に考慮した予測モデルは現在も開発途上にある。本稿で解説するBNCT治療効果予測モデルの開発に関する歴史的経緯と将来展望は、放射線物理学,薬理学,生物学,医学分野の間をつなぐ学際的な研究アプローチによるシナジー効果を生み、新しいBNCTの時代を切り拓くことが期待される。
鳥居 建男*; 眞田 幸尚
放射線, 46(3), p.93 - 101, 2021/05
福島原子力発電所事故から10年が経過し、環境中での放射線状況は様々な計測から変化傾向とその環境要因との関係が明らかになりつつある。放射線計測技術においても事故後、環境測定及び廃炉のために新たな手法が多く提案されている。本稿では、それらの最新動向について概説する。
岡 壽崇; 高橋 温*
放射線化学(インターネット), (110), p.13 - 19, 2020/10
東京電力福島第一原子力発電所によって野生動物が受けた外部被ばくを、電子スピン共鳴(ESR)法を用いてどのように計測するかを解説した。ニホンザルのエナメル質を用いて、炭酸ラジカル強度と吸収線量の関係、いわゆる検量線を作成した。検量線から推定された検出限界は33.5mGyであり、ヒト臼歯を用いた際の検出限界とほぼ同等であった。この検量線を用いて福島県で捕獲された野生ニホンザルの外部被ばく線量を推定したところ、45mGyから300mGyの被ばくをしているサルが見つかった。確立した方法により、ニホンザルだけでなく、アライグマやアカネズミなどの野生動物の外部被ばく線量推定が可能になった。