Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
大西 弘明
no journal, ,
磁場中フラストレート強磁性鎖のスピンネマティック状態において、マグノン対がどのように伝播するのかを、時間依存密度行列繰り込み群を用いて解析した結果を報告する。マグノン対の流れによるスピン伝導・熱伝導のメカニズムを議論する。
 の軟X線磁気円二色性による研究
の軟X線磁気円二色性による研究竹田 幸治; 岡根 哲夫; 斎藤 祐児; 山上 浩志; 山本 悦嗣; 芳賀 芳範
no journal, ,
強磁性超伝導体として注目されているUGe に対して、元素選択的な強磁性秩序過程を調べるためにU N
に対して、元素選択的な強磁性秩序過程を調べるためにU N 吸収端およびGe L
吸収端およびGe L 吸収端での内殻吸収磁気円二色性(XMCD)の実験を行った。温度・磁場の変化に対して、吸収(XAS)スペクトルおよびXMCDスペクトルの形状は変化しなかった。そして、XASスペクトルの形状からUGe
吸収端での内殻吸収磁気円二色性(XMCD)の実験を行った。温度・磁場の変化に対して、吸収(XAS)スペクトルおよびXMCDスペクトルの形状は変化しなかった。そして、XASスペクトルの形状からUGe におけるU 5f電子数はほぼ3であることが分かった。一方、XMCD強度については、強磁性転移温度52K以下で急激に増大する様子が観測された。さらにUサイトとGeサイトでの磁化曲線の温度依存性を詳細に調べてみると、両者で異なる温度依存性を示すことが分かった。このサイトによる磁化過程の違いは、30K近傍にある二つの異なる強磁性相間の転移との関連を示唆する結果であり、元素選択的な研究でしか得られない重要な情報である。
におけるU 5f電子数はほぼ3であることが分かった。一方、XMCD強度については、強磁性転移温度52K以下で急激に増大する様子が観測された。さらにUサイトとGeサイトでの磁化曲線の温度依存性を詳細に調べてみると、両者で異なる温度依存性を示すことが分かった。このサイトによる磁化過程の違いは、30K近傍にある二つの異なる強磁性相間の転移との関連を示唆する結果であり、元素選択的な研究でしか得られない重要な情報である。
 Fe
Fe O
O の高エネルギーマグノン分散とそのシミュレーション
の高エネルギーマグノン分散とそのシミュレーション社本 真一; 伊藤 孝; 大西 弘明; 松浦 直人*; 赤津 光洋*; 中村 充孝; 稲村 泰弘; 樹神 克明; 河村 聖子; 根本 祐一*; et al.
no journal, ,
Y Fe
Fe O
O の高エネルギーのマグノン分散について、その強度分布を含めて簡単なモデルでの計算によるシミュレーションと比較した。
の高エネルギーのマグノン分散について、その強度分布を含めて簡単なモデルでの計算によるシミュレーションと比較した。
 崩壊遅延核分裂確率の系統的計算
崩壊遅延核分裂確率の系統的計算小浦 寛之
no journal, ,
最近改良した 崩壊の大局的理論(H. Koura et al., PRC95, 2017)およびKTUY質量模型の核分裂障壁計算(H. Koura, PTEP2014, 2014)を用いて重・超重核領域の
崩壊の大局的理論(H. Koura et al., PRC95, 2017)およびKTUY質量模型の核分裂障壁計算(H. Koura, PTEP2014, 2014)を用いて重・超重核領域の 崩壊遅延核分裂確率の系統的計算を行う。その結果中性子過剰核の未知核種領域で例えば
崩壊遅延核分裂確率の系統的計算を行う。その結果中性子過剰核の未知核種領域で例えば No付近および
No付近および Ds付近を中心とする領域で
Ds付近を中心とする領域で 崩壊遅延核分裂確率が大きくなる傾向があることがわかった。この領域はr過程の関連でみると、r過程が中性子捕獲から
崩壊遅延核分裂確率が大きくなる傾向があることがわかった。この領域はr過程の関連でみると、r過程が中性子捕獲から 崩壊に転じて
崩壊に転じて 安定核に崩壊を進める過程、いわゆるフリーズアウト時の崩壊経路に当たる。このような傾向は主に核分裂障壁の高さの高低の傾向が主要な要素であるが、これは核分裂の模型計算(FRDM, ETFSIなど)によりその様相は大きく変わることもわかった。本講演では本計算の手法の概要及び結果について報告する。
安定核に崩壊を進める過程、いわゆるフリーズアウト時の崩壊経路に当たる。このような傾向は主に核分裂障壁の高さの高低の傾向が主要な要素であるが、これは核分裂の模型計算(FRDM, ETFSIなど)によりその様相は大きく変わることもわかった。本講演では本計算の手法の概要及び結果について報告する。
 O
O (R:希土類)の平均場近似による基底状態解析
(R:希土類)の平均場近似による基底状態解析吉井 賢資; 野村 拓司*; 池田 直*
no journal, ,
われわれが発見した強誘電体RFe O
O は、330K以下でFe
は、330K以下でFe とFe
とFe が三角格子上で電荷整列することに由来する強誘電性を発現する。また、250K以下で鉄スピンがフェリ磁性を示すマルチフェロイック系でもある。しかし、この系の性質は未だに不明な点が多い。例えば、YFe
が三角格子上で電荷整列することに由来する強誘電性を発現する。また、250K以下で鉄スピンがフェリ磁性を示すマルチフェロイック系でもある。しかし、この系の性質は未だに不明な点が多い。例えば、YFe O
O で示されたように、温度によって電荷秩序状態が変化し、強誘電性を示す三角格子上の3倍周期構造のみならず、7倍周期のような構造が出現する。本研究では、その長周期秩序の微視的な起源を探るべく、RFe
で示されたように、温度によって電荷秩序状態が変化し、強誘電性を示す三角格子上の3倍周期構造のみならず、7倍周期のような構造が出現する。本研究では、その長周期秩序の微視的な起源を探るべく、RFe O
O の基底状態を平均場近似の範囲で解析した。強誘電性を伴う3倍周期の電荷秩序構造の他に、均一な電荷分布状態、2倍周期などの秩序解を調べた。その結果、確かに3倍周期構造が安定になる領域、強誘電的領域が見出される。ただし、実験から主張されるような3倍周期でかつ鉄層間で電荷が不均衡となる基底状態を見出すことはできなかった。すなわち、3倍周期電荷秩序を伴う強誘電性が発現するには、格子歪みなど他の要素が影響している可能性も示唆される。
の基底状態を平均場近似の範囲で解析した。強誘電性を伴う3倍周期の電荷秩序構造の他に、均一な電荷分布状態、2倍周期などの秩序解を調べた。その結果、確かに3倍周期構造が安定になる領域、強誘電的領域が見出される。ただし、実験から主張されるような3倍周期でかつ鉄層間で電荷が不均衡となる基底状態を見出すことはできなかった。すなわち、3倍周期電荷秩序を伴う強誘電性が発現するには、格子歪みなど他の要素が影響している可能性も示唆される。
三浦 昭彦; 宮尾 智章*
no journal, ,
J-PARCリニアックでは、利用運転前に必要なビーム調整に、ビームプロファイルモニタを用いたビーム形状の測定を行っている。しかし、ビーム電流の増加につれて、従来の炭素繊維ワイヤでは、破断等による問題が増えてきた。そこで、高い電気伝導度を持ち、無酸素状態で3000 Cという熱的耐久性もあるカーボンナノチューブ(CNT)に着目した。直径100
Cという熱的耐久性もあるカーボンナノチューブ(CNT)に着目した。直径100 mのCNTワイヤによる3MeVの負水素イオンビームのビームプロファイル測定し、炭素繊維線と同等以上の信号利得があることを確認した。また、ビーム照射後の表面観察の結果、ワイヤに損傷が見られなかったことから、プロファイルモニタ用ワイヤとしてビーム調整に使用できる見込みを得た。
mのCNTワイヤによる3MeVの負水素イオンビームのビームプロファイル測定し、炭素繊維線と同等以上の信号利得があることを確認した。また、ビーム照射後の表面観察の結果、ワイヤに損傷が見られなかったことから、プロファイルモニタ用ワイヤとしてビーム調整に使用できる見込みを得た。
守屋 克洋; 原田 寛之; 三浦 昭彦; 二ツ川 健太*
no journal, ,
大強度線形加速器では、ビーム位相幅(縦方向分布)を測定するためにバンチシェイプモニタ(BSM)を用いる。BSMはビーム通過位置にワイヤを挿入することでビームと同じ時間構造を持つ2次電子を生成し、高周波電場を用いて2次電子の縦方向分布を横方向分布に移すことでビーム位相幅を検出する。しかし、大強度ビームを測定する際、ワイヤがビームの熱負荷に耐え切れず断線する。そこでワイヤの代わりに、ビーム構造を持つ電子を非破壊に生成する残留ガスプロファイルモニタ(IPM)の技術に着目し、BSMとIPMを組み合わせた非破壊型縦方向ビームプロファイルモニタを考案した。
原田 寛之; Saha, P. K.; 田村 文彦; 明午 伸一郎
no journal, ,
大強度陽子加速器J-PARCにおける3GeVシンクロトロン(RCS)は、設計出力1MWの大強度陽子加速器である。このRCSで3GeVまで加速された陽子ビームは、リング内の8台のパルスキッカー電磁石で取り出しラインへ導かれ、物質生命科学実験施設や後段の加速器へ供給されている。しかしながら、この電磁石の電磁回路的なリンギングにより時間的な磁場変調を生じており、取り出しビームが5mm以上大きく変動していた。この変動は、中性子源標的の故障リスクの増大や後段加速器のビーム損失の増大を生じ、大きな課題であった。特別な短パルスビームと各電磁石のタイミングスキャンを行い、取り出しビームの位置変動特性を測定することで、この磁場変調を実測し把握した。それを用いて各電磁石の磁場変調を抑制する最適なタイミングを求め、適用することで装置の改造を行うことなく要求以上の1mm以下のビーム取り出し変動を実現した。さらにタイミングのずれを自動で測定し補正するシステムを導入し、安定化も実現した。本発表では、パルスキッカー電磁石で生じた課題を紹介し、ビームの実測データを用いた原因の特定や解析手法、補正手法とその結果などを報告する。
林 直樹
no journal, ,
安定的な加速器の運転を継続するには、インターロック時のイベントを収集、分析することで、本質的な原因を明らかにし、その対処を行う必要がある。J-PARCリニアックでは、インターロック発報時の電流モニタ、ビームロスモニタの信号を記録し、そのパターンを分類し、個々の対策を検討中である。RCS(Rapid-Cycling Synchrotron)では、新しいBPM回路の導入により、インターロック発報時の電流モニタ、ビーム位置モニタの記録を目指しており、今後の展望について発表する。
吉本 政弘; 岡部 晃大; 原田 寛之; 金正 倫計; 加藤 新一*
no journal, ,
J-PARC 3GeVシンクロトロン加速器(RCS)では1MWの大強度陽子ビームを実現するために、荷電変換ビーム多重入射方式を採用している。従来のセプタム・バンプ電磁石のみを使ったビーム多重入射方式に比べてセプタム境界面でのビーム損失はほとんど起こらないため、原理的には多重入射する回数に制限は存在しない。しかし、詳細な残留線量測定の結果、荷電変換フォイルの周辺に非常に強い残留線量があることが分かった。PHITSシミュレーションの結果は、この強い放射化の原因が荷電変換方式ビーム多重入射時に、入射ビーム及び周回ビームが荷電変換フォイルに衝突することで起こる核反応による2次粒子によって引き起こされていることを強く示唆していた。このことを明らかにするために、フォイルからの2次粒子計測が重要になってくる。しかし、RCSの入射部は様々な機器が配置されている複雑な系になっているため、純粋にフォイルからの2次粒子を実験的に観測することは困難である。そこで、100度ダンプラインに新たにフォイル導入装置を設置し、2次粒子計測に必要な単純な実験系を構築した。ここでは、2次粒子の直接計測と金属薄膜を用いた放射化法による計測の2種類を計画している。まずは金属薄膜による放射化法で2次粒子種及びエネルギー分布の同定に向けた検討についてPHITSコードを用いて行った。この放射化法の有効性に関する評価結果について詳細に報告する。
 K
K Fe
Fe As
As の磁気励起バンドの繰り込み
の磁気励起バンドの繰り込み村井 直樹; 梶本 亮一; 鈴木 雄大*; 中島 正道*; 池田 浩章*; 出田 真一郎*; 田中 清尚*
no journal, ,
鉄系超伝導体の発見以来、その磁性・超伝導を対象とした中性子散乱研究が盛んに行われてきた。今回我々はホールドープ型鉄系超伝導体Ba K
K Fe
Fe As
As の磁気励起の測定をJ-PARCチョッパー分光器「四季」にて行い、ブリルアンゾーン中心から境界までをカバーする磁気励起データを得た。得られた磁気励起の運動量・エネルギー方向の構造は、同一試料のARPES測定から決定されたバンド繰り込み因子を考慮することで、5軌道模型に 対する乱雑位相近似(RPA)により再現される。これらの結果は、電子相関効果としてしばしば現れる電子バンドの繰り込み効果が磁気励起においても現れることを意味する。講演では鉄系超伝導体の電子構造の情報がどのように磁気励起スペクトルに反映されるのかについて議論する。
の磁気励起の測定をJ-PARCチョッパー分光器「四季」にて行い、ブリルアンゾーン中心から境界までをカバーする磁気励起データを得た。得られた磁気励起の運動量・エネルギー方向の構造は、同一試料のARPES測定から決定されたバンド繰り込み因子を考慮することで、5軌道模型に 対する乱雑位相近似(RPA)により再現される。これらの結果は、電子相関効果としてしばしば現れる電子バンドの繰り込み効果が磁気励起においても現れることを意味する。講演では鉄系超伝導体の電子構造の情報がどのように磁気励起スペクトルに反映されるのかについて議論する。
神藤 勝啓
no journal, ,
J-PARCをはじめSNSやCERNなどの大強度陽子加速器施設では、大強度高周波負水素(H )イオン源が用いられている。イオン源プラズマの生成には2MHzの高周波(RF)源を用い、イオン源より数10mAのH
)イオン源が用いられている。イオン源プラズマの生成には2MHzの高周波(RF)源を用い、イオン源より数10mAのH ビームを引き出している。J-PARC大強度高周波H
ビームを引き出している。J-PARC大強度高周波H イオン源では、2MHzのパルスRF源からイオンチャンバー内に設置したアンテナに約25kWのRFを印加することにより、イオン源内に水素プラズマを生成し、大強度H
イオン源では、2MHzのパルスRF源からイオンチャンバー内に設置したアンテナに約25kWのRFを印加することにより、イオン源内に水素プラズマを生成し、大強度H ビームを引き出している。ビーム引き出し孔近傍に生成されるイオンシースの時間応答性は、イオンプラズマ周波数f
ビームを引き出している。ビーム引き出し孔近傍に生成されるイオンシースの時間応答性は、イオンプラズマ周波数f で決まる。大強度水素イオン源のプラズマ密度は10
で決まる。大強度水素イオン源のプラズマ密度は10 m
m 以上とするとf
以上とするとf は70MHz以上であり、プラズマ中のイオンは2MHzのRFに追随して振動する。そのため、ビーム引出領域近傍のイオンシースもRFに追随しプラズマの電位搖動が生じるために、イオン源より引き出したビームは2MHzの搖動を持っている可能性がある。そこで、H
は70MHz以上であり、プラズマ中のイオンは2MHzのRFに追随して振動する。そのため、ビーム引出領域近傍のイオンシースもRFに追随しプラズマの電位搖動が生じるために、イオン源より引き出したビームは2MHzの搖動を持っている可能性がある。そこで、H ビーム信号の周波数特性を測定したところ、H
ビーム信号の周波数特性を測定したところ、H ビームにはプラズマ生成に連動しているRF周波数成分があることが分かった。
ビームにはプラズマ生成に連動しているRF周波数成分があることが分かった。
佐甲 博之; 長谷川 勝一; 佐藤 進; 谷田 聖; 市川 裕大
no journal, ,
J-PARC E42(Hダイバリオン探索実験)/E45(( , 2
, 2 )反応を利用したハドロン分光実験)実験用に新しいスペクトロメータHyperon Spectrometerを開発している。このHyperon Spectrometerは、超電導電磁石Hyperon Magnet, 三次元飛跡検出器HypTPC, 時間検出器TPC Hodoscopeで構成される。ここで、TPC Hodoscopeは高磁場中に設置するため、磁場中でも動作可能なMPPCを用いて、100ps程度の高時間分解能の性能を目指している。我々は150
)反応を利用したハドロン分光実験)実験用に新しいスペクトロメータHyperon Spectrometerを開発している。このHyperon Spectrometerは、超電導電磁石Hyperon Magnet, 三次元飛跡検出器HypTPC, 時間検出器TPC Hodoscopeで構成される。ここで、TPC Hodoscopeは高磁場中に設置するため、磁場中でも動作可能なMPPCを用いて、100ps程度の高時間分解能の性能を目指している。我々は150 70
70 10(T)mm
10(T)mm の小型のシンチレータ(実機は長さ800mmを想定している)を製作し、MPPCを両端に接続し、実験室で宇宙線を用いてテストを行った。高時間分解能を得るため、MPPCを1, 2, 4個と複数設置し、測定を行った。また、接続方法として、直列接続, NIM Mixer, Individual(接続なしでoff-line解析で平均化)を使用したデータを取得した。
の小型のシンチレータ(実機は長さ800mmを想定している)を製作し、MPPCを両端に接続し、実験室で宇宙線を用いてテストを行った。高時間分解能を得るため、MPPCを1, 2, 4個と複数設置し、測定を行った。また、接続方法として、直列接続, NIM Mixer, Individual(接続なしでoff-line解析で平均化)を使用したデータを取得した。
Gubler, P.; Kim, H. J.*; Lee, S. H.*
no journal, ,
有限運動量を持つ核物質中のphiメソンの振る舞いについての最近の研究の進捗状況について報告する。J-PARCのE16実験との関連についても議論する。
 凝縮-ハイペロン物質共存相の状態方程式へのバリオン間普遍3体力の効果
凝縮-ハイペロン物質共存相の状態方程式へのバリオン間普遍3体力の効果武藤 巧*; 丸山 敏毅; 巽 敏隆*; 高塚 龍之*
no journal, ,
中性子星内部のような高密度物質中でのマルチストレンジネス物質の発現形態としてK中間子( )凝縮とハイペロン(
)凝縮とハイペロン( )物質の共存相の存否が中性子星の質量・半径の観測との整合性という視点から追究されてきた。
)物質の共存相の存否が中性子星の質量・半径の観測との整合性という視点から追究されてきた。 凝縮と
凝縮と 混合の共存の結果、状態方程式が著しく軟化し、これまでの理論では重い中性子星の観測結果を説明できなかった。本講演では相対論的平均場によるバリオン(
混合の共存の結果、状態方程式が著しく軟化し、これまでの理論では重い中性子星の観測結果を説明できなかった。本講演では相対論的平均場によるバリオン( )間相互作用と
)間相互作用と -
- ,
,  -
- 間の非線形カイラル相互作用とを結合した枠組みにバリオン間普遍3体力(UTBF)を取り入れ、状態方程式を調べる。具体的なUTBFとしては、玉垣によるstring junction modelに基づくクォーク閉じ込め機構に関した相互作用を
間の非線形カイラル相互作用とを結合した枠組みにバリオン間普遍3体力(UTBF)を取り入れ、状態方程式を調べる。具体的なUTBFとしては、玉垣によるstring junction modelに基づくクォーク閉じ込め機構に関した相互作用を 混在物質に適用したものを用いる。その結果、あるパラメータで中性子星の最大質量が太陽質量の1.58倍にしかならなかったのが、UTBFを加えたることで太陽質量の2.16倍まで増加し、重い中性子星の観測事実と矛盾しない結果が得られることが分かった。
混在物質に適用したものを用いる。その結果、あるパラメータで中性子星の最大質量が太陽質量の1.58倍にしかならなかったのが、UTBFを加えたることで太陽質量の2.16倍まで増加し、重い中性子星の観測事実と矛盾しない結果が得られることが分かった。
 SR測定
SR測定伊藤 孝; 髭本 亘; 鈴木 博之*; 井村 敬一郎*; 佐藤 憲昭*
no journal, ,
SmSは0.1eV程度の小さなエネルギーギャップをもつ黒色の絶縁体であり、0.65GPa程度の圧力を印加することにより黄金色を呈する金属相へと転移することが知られている。これに加え、低温において数々の異常物性が観測されており、これらの発現において励起子が重要な役割を演じている可能性が指摘されている。我々はSmSにおける励起子の電子状態を明らかにするために、ミュオンスピン回転・緩和法による測定を行った。SmSに 粒子を打ち込むと、電子を1つ捕らえて「浅いミュオニウム」と呼ばれる水素原子状の束縛状態を形成する。この浅いミュオニウムと励起子の有効ボーア半径および束縛エネルギーは共通のモデルにより近似的に記述できることから、ミュオニウムの電子状態を調べることにより励起子に関する知見を得ることができると期待される。測定の結果、常圧下におけるミュオニウムの有効ボーア半径は0.33nmであり、加圧によりこの値が増加傾向を示すことが明らかになった。励起子も同様の振る舞いを示すと考えられる。
粒子を打ち込むと、電子を1つ捕らえて「浅いミュオニウム」と呼ばれる水素原子状の束縛状態を形成する。この浅いミュオニウムと励起子の有効ボーア半径および束縛エネルギーは共通のモデルにより近似的に記述できることから、ミュオニウムの電子状態を調べることにより励起子に関する知見を得ることができると期待される。測定の結果、常圧下におけるミュオニウムの有効ボーア半径は0.33nmであり、加圧によりこの値が増加傾向を示すことが明らかになった。励起子も同様の振る舞いを示すと考えられる。
古府 麻衣子
no journal, ,
イオン液体とは、室温付近で液体状態をとる塩の総称であり、現在の液体科学分野で注目されている多機能性液体である。我々はイオン液体の階層構造とそのダイナミクスを明らかにするため、中性子散乱研究を行ってきた。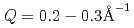 に現れる低
に現れる低 ピークがnmスケールのドメイン構造(ナノ構造)に対応することを示すとともに、中性子スピンエコー法を用いてその緩和挙動を観測することに初めて成功した。さらに、我々は緩和挙動の陽・陰イオン依存性を調べ、イオン液体の運動を支配しているのは極性部分のクーロン力であることを明らかにした。講演では、最近行っている中性子散乱で観測する自己拡散運動の空間スケール依存性についての研究についても紹介する。
ピークがnmスケールのドメイン構造(ナノ構造)に対応することを示すとともに、中性子スピンエコー法を用いてその緩和挙動を観測することに初めて成功した。さらに、我々は緩和挙動の陽・陰イオン依存性を調べ、イオン液体の運動を支配しているのは極性部分のクーロン力であることを明らかにした。講演では、最近行っている中性子散乱で観測する自己拡散運動の空間スケール依存性についての研究についても紹介する。
大谷 将士*; 近藤 恭弘; 北村 遼*; 中沢 雄河*; 須江 祐貴*; Bae, S.*; Choi, S.*; 長谷川 和男; 飯沼 裕美*; 河村 成肇*; et al.
no journal, ,
J-PARCミューオンg-2実験(E34)では世界初のミューオン加速によって低エミッタンスビームを実現し、先行実験で主要な系統誤差であったビーム由来の系統誤差を排除して世界最高精度測定を目指している。我々は今回、J-PARC MLFにおいて世界初のミューオン加速を実現した。本講演では、この加速試験成功を踏まえ、ミューオンリニアック全体と今後の展望について報告する。
北村 遼*; 大谷 将士*; 近藤 恭弘; Bae, S.*; Choi, S.*; 深尾 祥紀*; 二ツ川 健太*; 長谷川 和男; 飯沼 裕美*; 石田 勝彦*; et al.
no journal, ,
J-PARC E34実験ではミューオンg-2/EDMの精密測定に向けて、ミューオン線形加速器の開発を進めている。初段加速器のRFQを用いたミューオンRF加速実証試験を2017年10月にJ-PARC MLFで実施した。運動エネルギー3MeVのミューオンビームは、金属薄膜標的に照射されることで負ミューオニウムイオン(Mu )となって冷却された後、静電加速収束器により5.6keVまで静電加速され、さらにRFQにより88.6keVまでRF加速される。加速Mu
)となって冷却された後、静電加速収束器により5.6keVまで静電加速され、さらにRFQにより88.6keVまでRF加速される。加速Mu ビームは偏向電磁石による運動量選別を経てMCPで検出され、TOF測定により加速Mu
ビームは偏向電磁石による運動量選別を経てMCPで検出され、TOF測定により加速Mu の識別を行った。本講演では最新の実験結果について報告する。
の識別を行った。本講演では最新の実験結果について報告する。
 の中性子散乱による研究
の中性子散乱による研究目時 直人; 山内 宏樹; 松田 雅昌*; Fernandez Baca, J.*; 吉田 雅洋*; 吉澤 英樹*; 萩原 雅人*; 綿貫 竜太*
no journal, ,
NdB の磁気構造と
の磁気構造と 電子状態を報告し、逐次転移のメカニズムを提案する。II相では面内磁気モーメント
電子状態を報告し、逐次転移のメカニズムを提案する。II相では面内磁気モーメント を伴うAll-in All-out構造(
を伴うAll-in All-out構造( 4)と、
4)と、 軸モーメント
軸モーメント の反強磁性ダイマー構造(
の反強磁性ダイマー構造( 10)が共存し、さらに低温のIII・IV相では
10)が共存し、さらに低温のIII・IV相では の長周期変調を伴う。ランダウ理論による解析から
の長周期変調を伴う。ランダウ理論による解析から が
が の高次(
の高次( )の誘起秩序変数として表現され、多極子相互作用が示唆される。NdB
)の誘起秩序変数として表現され、多極子相互作用が示唆される。NdB の
の 電子状態は基底状態(
電子状態は基底状態( =
= 5/2)の3meV上に
5/2)の3meV上に =
= 7/2の第一励起が存在し、これらによる準四重項状態を使って(1)中間相は
7/2の第一励起が存在し、これらによる準四重項状態を使って(1)中間相は の磁気秩序相、(2)低温相は
の磁気秩序相、(2)低温相は と電気四極子
と電気四極子 の結合相、という逐次転移のメカニズムが提案できる。
の結合相、という逐次転移のメカニズムが提案できる。