Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
吉田 純也; 赤石 貴也; 藤田 真奈美; 長谷川 勝一; 橋本 直; 細見 健二; 市川 真也; 市川 裕大; 今井 憲一*; Kim, S.; et al.
JPS Conference Proceedings (Internet), 33, p.011112_1 - 011112_8, 2021/03
J-PARC E07 is the most ambitious and complex emulsion experiment to date investigating double hypernuclei with Hybrid emulsion method. The physics run at the K1.8 beam line in the J-PARC hadron experimental facility have been completed in 2017. The emulsion sheets are presently being analyzed with dedicated optical microscopes. Current statistics are estimated to be more 3 times than that of previous experiments. Quantitative data on the  and
and  interaction are being accumulated successfully via analysis of double
interaction are being accumulated successfully via analysis of double  and
and  hypernuclei. Multiple
hypernuclei. Multiple  hypernucleus candidates suggests several features about
hypernucleus candidates suggests several features about  hypernucleus that the identification efficiency of
hypernucleus that the identification efficiency of  C is significantly higher than other mode, many daughters of
C is significantly higher than other mode, many daughters of  C are identified as He or Be, and multiple bound states of
C are identified as He or Be, and multiple bound states of  exist in the
exist in the  N nucleus. An analysis of X-ray spectroscopy of
N nucleus. An analysis of X-ray spectroscopy of  hyperatoms are ongoing.
hyperatoms are ongoing.
Kim, S. H.*; 市川 裕大; 佐甲 博之; 長谷川 勝一; 早川 修平*; 七村 拓野*; 佐藤 進; 谷田 聖; 吉田 純也; 他11名*
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 940, p.359 - 370, 2019/10
被引用回数:5 パーセンタイル:47.59(Instruments & Instrumentation)We have developed a gas electron multiplier (GEM)-based time projection chamber (TPC) for the H-dibaryon search experiment at J-PARC. High-rate  beam particles enter a TPC gas volume of approximately 0.2 m
beam particles enter a TPC gas volume of approximately 0.2 m , in a direction perpendicular to the electric field. A long-rectangular hollow section is located inside the TPC volume to accommodate a diamond target. We commissioned the TPC using 230 MeV protons with beam rates of up to 1 MHz. The TPC data acquisition system collected 5768 pad signals in full readout mode, with almost 100% efficiency, at a preset trigger rate of 230 Hz. We operated the TPC in an Ar/CH
, in a direction perpendicular to the electric field. A long-rectangular hollow section is located inside the TPC volume to accommodate a diamond target. We commissioned the TPC using 230 MeV protons with beam rates of up to 1 MHz. The TPC data acquisition system collected 5768 pad signals in full readout mode, with almost 100% efficiency, at a preset trigger rate of 230 Hz. We operated the TPC in an Ar/CH gas mixture (90/10) without a magnetic field. The spatial resolutions on the pad plane are measured to be 400-700
gas mixture (90/10) without a magnetic field. The spatial resolutions on the pad plane are measured to be 400-700  m, which correspond to 230-300
m, which correspond to 230-300  m in a magnetic field of 1 T. We confirmed high tracking capability at beam rates of up to 1 MHz.
m in a magnetic field of 1 T. We confirmed high tracking capability at beam rates of up to 1 MHz.
江川 弘行; 足利 沙希子; 長谷川 勝一; 橋本 直; 早川 修平; 細見 健二; 市川 裕大; 今井 憲一; 金原 慎二*; 七村 拓野; et al.
Progress of Theoretical and Experimental Physics (Internet), 2019(2), p.021D02_1 - 021D02_11, 2019/02
被引用回数:25 パーセンタイル:83.09(Physics, Multidisciplinary)A double- hypernucleus,
hypernucleus,  , was observed by the J-PARC E07 collaborationin nuclear emulsions tagged by the
, was observed by the J-PARC E07 collaborationin nuclear emulsions tagged by the  reaction. This event was interpreted as a production and decay of
reaction. This event was interpreted as a production and decay of  ,
, , or
, or  via
via  capture in
capture in  .By assuming the capture in the atomic 3D state, the binding energy of two
.By assuming the capture in the atomic 3D state, the binding energy of two  hyperons
hyperons (
( )of these double-
)of these double- hypernuclei are obtained to be
hypernuclei are obtained to be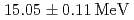 ,
, 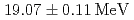 , and
, and 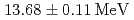 , respectively. Based on the kinematic fitting,
, respectively. Based on the kinematic fitting,  is the most likely explanation for the observed event.
is the most likely explanation for the observed event.
保坂 淳; 肥山 詠美子; Kim, S.-H.*; Kim, H.-C.*; 永廣 秀子*; 野海 博之*; 岡 眞; 白鳥 昂太郎*; 吉田 哲也*; 安井 繁宏*
Nuclear Physics A, 954, p.341 - 351, 2016/10
被引用回数:3 パーセンタイル:26.61(Physics, Nuclear)チャームバリオンの生成反応とその崩壊過程測定に基いて、バリオンの構造や励起モードの特定を行う方法を考察した。生成反応は一段階過程によるバリオン生成に注目し、崩壊はパイオン放出による過程を考えた。J-PARCにおける今後の実験計画においてこれらの過程の測定を目指す。
錦織 良; 小島 有志; 花田 磨砂也; 柏木 美恵子; 渡邊 和弘; 梅田 尚孝; 戸張 博之; 吉田 雅史; 市川 雅浩; 平塚 淳一; et al.
Plasma and Fusion Research (Internet), 11, p.2401014_1 - 2401014_4, 2016/03
ITERやJT-60SAにおける中性粒子入射装置では、多孔多段(MAMuG)加速器による高エネルギー、大電流ビームの安定供給が要求されている。これらの加速器の設計に向けては、真空放電で決まる耐電圧の予測が重大な課題となっており、原子力機構では、MAMuG加速器をの耐電圧を物理理解に基づいて設計するために、真空放電の物理過程の研究を実施している。これまでの研究成果から、この真空放電は電界放出電子による暗電流が起点となっていると考えている。しかし、F-N理論によれば、暗電流は電界増倍係数 によって決まるが、これまで
によって決まるが、これまで は実験的にしか求めることができなかった。そこで、今回、
は実験的にしか求めることができなかった。そこで、今回、 の決定機構を調べるために、MAMuG加速器の大面積電極の電界の異なる3つの領域で独立に暗電流を測定した。その結果、
の決定機構を調べるために、MAMuG加速器の大面積電極の電界の異なる3つの領域で独立に暗電流を測定した。その結果、 は電極のコンディショニングと共に低下するが、絶縁破壊電界Eによって表される実効電界
は電極のコンディショニングと共に低下するが、絶縁破壊電界Eによって表される実効電界 Eが一定で1MV/mmであることが分かった。これは、小型電極から求めた実効電界
Eが一定で1MV/mmであることが分かった。これは、小型電極から求めた実効電界 Eよりも1桁大きい値であり、面積の依存性を示唆していると考えている。この
Eよりも1桁大きい値であり、面積の依存性を示唆していると考えている。この Eの値を利用することにより、絶縁破壊電界時における
Eの値を利用することにより、絶縁破壊電界時における を求めることができ、暗電流の評価と耐電圧の予測を関連付けることができると考えている。
を求めることができ、暗電流の評価と耐電圧の予測を関連付けることができると考えている。
平塚 淳一; 花田 磨砂也; 小島 有志; 梅田 尚孝; 柏木 美恵子; 宮本 賢治*; 吉田 雅史; 錦織 良; 市川 雅浩; 渡邊 和弘; et al.
Review of Scientific Instruments, 87(2), p.02B137_1 - 02B137_3, 2016/02
被引用回数:4 パーセンタイル:21.48(Instruments & Instrumentation)負イオンの引出・加速の物理を理解するために、ITER原型加速器において加速電極上の熱負荷密度分布を初めて測定した。熱負荷密度分布を測定するために、加速電極孔周辺領域をそれぞれが熱絶縁された34個の銅ブロックで構成し、それぞれの銅ブロックに熱電対を接合することで、空間分解能3mm程度の熱負荷密度分布測定に成功した。これはビーム径16mmのビームのテイル成分を測定するのに十分な分解能である。この測定により、加速電極孔周辺において熱負荷密度分布に2箇所のピークを発見した。ビームオプティクスやガス密度分布を変化させる実験により、これら2つのピークは負イオン及び2次電子の衝突であることが明らかになった。これは負イオンや2次電子の軌道を理解するために必要な初めての実験結果である。
小島 有志; 花田 磨砂也; 戸張 博之; 錦織 良; 平塚 淳一; 柏木 美恵子; 梅田 尚孝; 吉田 雅史; 市川 雅浩; 渡邊 和弘; et al.
Review of Scientific Instruments, 87(2), p.02B304_1 - 02B304_5, 2016/02
被引用回数:11 パーセンタイル:48.61(Instruments & Instrumentation)原子力機構では、ITERやJT-60SAで利用する中性粒子入射装置の実現に向けて、大面積多孔多段負イオン加速器を開発中であり、1MVや500kVの直流超高電圧を真空中で安定して保持できる耐電圧性能が要求されている。そこで、真空放電の物理理解に基づく耐電圧設計手法を確立することを目的として、今回、これまでの耐電圧試験結果に基づいて、多段の入れ子構造である加速電極支持構造の形状を、耐電圧や境界条件から最適化する手法を開発した。本手法では、ビーム光学から要求される電圧及びギャップ長から、電極平板部の面積、つまり同軸の入れ子構造となる円筒型電極の半径を決定することにより、耐電圧を満たすための同軸間ギャップ長を求める。これにより一段分の対向する陰極・陽極の電極構造が決まるため、本手法を段数分くり返すことにより、耐電圧を満たした加速電極支持構造を境界条件の中で一意に設計することが可能となる。得られた加速器の耐電圧を予測するために、未解明であった多段による耐電圧の劣化を、5段電極を用いて実験的に調べた結果、5段の耐電圧は1段耐電圧の段数倍よりも25%程度耐電圧が減少し、段数の増加による影響が見られた。この効果を考慮した結果、本手法によるJT-60用負イオン加速器の耐電圧解析が10%以下の誤差の範囲で一致し、ITERやJT-60SAの耐電圧設計の精度を向上することができた。
花田 磨砂也; 小島 有志; 戸張 博之; 錦織 良; 平塚 淳一; 柏木 美恵子; 梅田 尚孝; 吉田 雅史; 市川 雅浩; 渡邊 和弘; et al.
Review of Scientific Instruments, 87(2), p.02B322_1 - 02B322_4, 2016/02
被引用回数:12 パーセンタイル:51.28(Instruments & Instrumentation)本論文は原子力機構(JAEA)で開発中の負イオンビームに関する最新結果を報告するものである。JAEAでは、国際熱核融合実験炉(ITER)およびJT-60SAの実現に向けて、それぞれ1MeV, 40A,3600秒および22A, 500keV, 100秒の重水素負イオンビームの開発を行っている。これらの負イオンビームを開発するために、ITERやJT-60SAの設計と同様、多段静電加速器とセシウム添加型負イオン源を開発している。静電加速器の開発においては、長時間加速をした開発を指向しており、その課題である加速電極の熱負荷を、イオンビームの軌道を制御することにより、許容値以下に低減した。その結果、負イオンの加速時間を、従来の1秒未満から試験装置の電源の限界である60秒まで進展させた。また、セシウム添加型負イオン源の開発においては、大電流負イオンビームの長パルス生成を指向しており、これまでに15A、100秒のビーム生成を達成している。今後、長パルス生成時に顕在化した、イオン源内のアーク放電プラズマの放電破壊(アーキング)の問題を解決し、JT-60SAで要求される22Aを超える電流値で100秒以上の負イオンビーム生成を目指す。
小島 有志; 梅田 尚孝; 花田 磨砂也; 吉田 雅史; 柏木 美恵子; 戸張 博之; 渡邊 和弘; 秋野 昇; 小又 将夫; 藻垣 和彦; et al.
Nuclear Fusion, 55(6), p.063006_1 - 063006_9, 2015/06
被引用回数:41 パーセンタイル:89.45(Physics, Fluids & Plasmas)原子力機構では、JT-60SAやITERで利用する中性粒子入射装置の開発に向けて、大型高エネルギー負イオン源による100秒を超える負イオン生成・加速の実証を目指した研究を進めている。まず、JT-60SA用負イオン源の負イオン生成部のプラズマ閉じ込め用磁石配置を変更することにより、生成されたプラズマの密度分布を一様化することに成功した。これにより、引出領域の83%から一様な負イオンビームを生成し、これまでの最高値17Aを大きく超える32Aの負イオン電流を1秒間引き出すことに成功した。この磁場配位とこれまでに開発した長時間負イオン生成用温度制御型プラズマ電極を適用し、さらに負イオン電流のフィードバック制御手法を用いることにより、15Aの大電流負イオンビームを100秒間維持することに成功した。これは、JT-60SAの定格の68%の電流に相当し、パルス幅は定格を満たしている。また、ITER用高エネルギー加速器の開発に向けては、負イオンビームが加速途中で電極に衝突して生じる熱負荷を低減するだけでなく、負イオンと同時に引き出される電子を熱的に除去することが重要であった。今回、冷却構造を改良することにより従来の5倍の電子熱負荷を許容できると共に、残留磁場で偏向する負イオンビームの軌道制御機構を組み合わせて、新しい引出部を開発した。その結果、700keV、100A/m の負イオンビームを従来の7倍以上長いパルス幅である60秒間維持することに成功した。
の負イオンビームを従来の7倍以上長いパルス幅である60秒間維持することに成功した。
小島 有志; 花田 磨砂也; 吉田 雅史; 梅田 尚孝; 平塚 淳一; 柏木 美恵子; 戸張 博之; 渡邊 和弘; Grisham, L. R.*; NB加熱開発グループ
AIP Conference Proceedings 1655, p.060002_1 - 060002_10, 2015/04
被引用回数:6 パーセンタイル:87.08(Physics, Applied)JT-60SA用負イオン源に向けては、22Aの大電流負イオンを100秒間生成することが大きな課題である。負イオンを長時間効率よく生成するためには、これまでの研究の結果、セシウム原子層が形成されることで負イオン生成が促進されるプラズマ電極の温度を、200 C程度の高温に維持する必要があることが分かっている。そこで、1気圧で高沸点を有するフッ素系冷媒をプラズマ電極内に循環させて温度を制御する手法を開発し、目標の電流密度(120-130A/m
C程度の高温に維持する必要があることが分かっている。そこで、1気圧で高沸点を有するフッ素系冷媒をプラズマ電極内に循環させて温度を制御する手法を開発し、目標の電流密度(120-130A/m )を100秒間維持する原理実証に成功した。その結果を基に、全引出領域において電極温度を制御する実機プラズマ電極を製作し、試験を開始した。初期結果として、原理実証用電極と同様の制御時定数が得られ、プラズマ電極の全引出領域において、温度を一定に制御することに成功した。また、セシウムを導入して負イオン電流量を増大させ、現在までに70%の出力に相当する15Aの大電流負イオンビームを100秒間一定に生成することに成功している。
)を100秒間維持する原理実証に成功した。その結果を基に、全引出領域において電極温度を制御する実機プラズマ電極を製作し、試験を開始した。初期結果として、原理実証用電極と同様の制御時定数が得られ、プラズマ電極の全引出領域において、温度を一定に制御することに成功した。また、セシウムを導入して負イオン電流量を増大させ、現在までに70%の出力に相当する15Aの大電流負イオンビームを100秒間一定に生成することに成功している。
平塚 淳一; 花田 磨砂也; 梅田 尚孝; 小島 有志; 柏木 美恵子; 渡邊 和弘; 戸張 博之; 吉田 雅史
Plasma and Fusion Research (Internet), 10(Sp.2), p.3405045_1 - 3405045_4, 2015/04
国際熱核融合実験炉(ITER)で必要な高電流密度( 200A/m
200A/m )、高エネルギー(
)、高エネルギー( 1MeV)、長パルス時間(1時間)の負イオンビームを生成するために、電極孔位置の変位により偏向角を補正する技術を用いた負イオンと電極との直接衝突の抑制についての研究が注意深く行われてきた。偏向制御電極(SCG)の孔径
1MeV)、長パルス時間(1時間)の負イオンビームを生成するために、電極孔位置の変位により偏向角を補正する技術を用いた負イオンと電極との直接衝突の抑制についての研究が注意深く行われてきた。偏向制御電極(SCG)の孔径 14mmにおいて偏向角の非線形な依存性が現れている。この依存性からSCGの孔径と位置の変位量をそれぞれ16mm、0.7mmと決定し、ITERの原型加速器において試験を実施した。複数の電極孔のそれぞれのビームに対し加速器内の残留磁場による偏向は適切に補正され、電極熱負荷は大きく減少した。これにより加速ビーム電流は10%増加した。
14mmにおいて偏向角の非線形な依存性が現れている。この依存性からSCGの孔径と位置の変位量をそれぞれ16mm、0.7mmと決定し、ITERの原型加速器において試験を実施した。複数の電極孔のそれぞれのビームに対し加速器内の残留磁場による偏向は適切に補正され、電極熱負荷は大きく減少した。これにより加速ビーム電流は10%増加した。
小島 有志; 花田 磨砂也; 吉田 雅史; 戸張 博之; 柏木 美恵子; 梅田 尚孝; 渡邊 和弘; Grisham, L. R.*
Review of Scientific Instruments, 85(2), p.02B312_1 - 02B312_5, 2014/02
被引用回数:12 パーセンタイル:48.2(Instruments & Instrumentation)JT-60SAに向けて、500keV, 22Aの負イオンビームを100秒間生成するためには、大電流負イオンを長時間生成することが大きな課題である。これまでの結果から、Csによる表面生成方式を用いて負イオンを長時間効率よく生成するには、Csの付着したプラズマ電極の温度を200 C程度に維持する必要があることが分かっていた。しかしこれまでのプラズマ電極では慣性冷却方式を採用しており、パルスとともに電極温度が上昇することが問題であった。そこで、沸点の高いフッ素系冷媒を200
C程度に維持する必要があることが分かっていた。しかしこれまでのプラズマ電極では慣性冷却方式を採用しており、パルスとともに電極温度が上昇することが問題であった。そこで、沸点の高いフッ素系冷媒を200 C程度でプラズマ電極内を循環させ、プラズマ電極を高温に保ちながらプラズマからの熱を冷却するシステムを開発した。その結果、7秒程度の短い時定数でプラズマ電極の温度を長時間一定に制御することが可能となり、1/10の引出領域から120A/m
C程度でプラズマ電極内を循環させ、プラズマ電極を高温に保ちながらプラズマからの熱を冷却するシステムを開発した。その結果、7秒程度の短い時定数でプラズマ電極の温度を長時間一定に制御することが可能となり、1/10の引出領域から120A/m の高密度負イオンビームを、JT-60SAの目標である100秒間生成することに成功した。
の高密度負イオンビームを、JT-60SAの目標である100秒間生成することに成功した。
柏木 美恵子; 梅田 尚孝; 戸張 博之; 小島 有志; 吉田 雅史; 谷口 正樹; 大楽 正幸; 前島 哲也; 山中 晴彦; 渡邊 和弘; et al.
Review of Scientific Instruments, 85(2), p.02B320_1 - 02B320_3, 2014/02
被引用回数:29 パーセンタイル:74.94(Instruments & Instrumentation)ITER, JT-60SA及びDEMO用の核融合炉の加熱・電流駆動に必要なNBIに向けて、高パワー・長パルス用負イオン引出し部の電極を今回新たに開発した。まず、長パルスの間、十分除熱できる電極を熱解析で設計した。次に、負イオン加速試験で、新しい電極の負イオン生成と電子抑制能力について実験的に検証した。その結果、負イオン電流は1.3倍増加し、懸念していた電子電流の増加は抑えることができ、さらにビーム発散角も4mradまで十分低減できることを明らかにした。
小島 有志; 花田 磨砂也; 吉田 雅史; 井上 多加志; 渡邊 和弘; 谷口 正樹; 柏木 美恵子; 梅田 尚孝; 戸張 博之; Grisham, L. R.*; et al.
Fusion Engineering and Design, 88(6-8), p.918 - 921, 2013/10
被引用回数:6 パーセンタイル:43.64(Nuclear Science & Technology)JT-60SAに向けて、500keV, 22A負イオンビームを100秒間生成するために、JT-60負イオン源は電極熱負荷を低減するとともに、負イオンを長時間生成する研究開発を行っている。電極の熱負荷に関しては、1.2m 0.6mの面積を有するプラズマの不均一に起因した負イオン電流分布の非一様性による周辺ビームの発散角の増大が問題となっている。そこで、従来小型負イオン源で開発されたテント型磁気フィルターを有する軸対象磁場を、JT-60の大型負イオン源に適用する検討を行った。今回、フィラメントから生成される一次電子の軌道計算から磁場配位の最適化を行い、磁石の入れ替えのみで長手方向の一様性が従来の偏差30%から10%にまで改善できる可能性があることがわかった。また、負イオンを長時間生成するため、負イオン生成量がプラズマ電極の温度に依存することを利用した、高温冷媒による温度制御型プラズマ電極の検討を行った。開発した初期型プラズマ電極では、高温冷媒の物性値から見積もると10秒程度の時定数を持ち、プラズマ電極の最適温度である270
0.6mの面積を有するプラズマの不均一に起因した負イオン電流分布の非一様性による周辺ビームの発散角の増大が問題となっている。そこで、従来小型負イオン源で開発されたテント型磁気フィルターを有する軸対象磁場を、JT-60の大型負イオン源に適用する検討を行った。今回、フィラメントから生成される一次電子の軌道計算から磁場配位の最適化を行い、磁石の入れ替えのみで長手方向の一様性が従来の偏差30%から10%にまで改善できる可能性があることがわかった。また、負イオンを長時間生成するため、負イオン生成量がプラズマ電極の温度に依存することを利用した、高温冷媒による温度制御型プラズマ電極の検討を行った。開発した初期型プラズマ電極では、高温冷媒の物性値から見積もると10秒程度の時定数を持ち、プラズマ電極の最適温度である270 Cに維持できることがわかった。
Cに維持できることがわかった。
 -ray simultaneous imaging by using a Si/CdTe Compton camera
-ray simultaneous imaging by using a Si/CdTe Compton camera鈴木 義行*; 山口 充孝; 小高 裕和*; 島田 博文*; 吉田 由香里*; 鳥飼 幸太*; 佐藤 隆博; 荒川 和夫*; 河地 有木; 渡辺 茂樹; et al.
Radiology, 267(3), p.941 - 947, 2013/06
被引用回数:23 パーセンタイル:64.71(Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging)Capabillity tests of 3D imaging for medical applications were performed by using a new Compton camera.  F,
F,  I and
I and  Ga separately compacted into micro tubes were injected subcutaneously into a Wister rat and imaged after sacrifice of the rat (ex-vivo model). In a separate experiment
Ga separately compacted into micro tubes were injected subcutaneously into a Wister rat and imaged after sacrifice of the rat (ex-vivo model). In a separate experiment  In-chloride and
In-chloride and  I-Methylnorcholestenol were injected into a rat intravenously and
I-Methylnorcholestenol were injected into a rat intravenously and  Cu was injected into the stomach orally just before imaging (more physiological model). The Compton camera demonstrated its 3D multinuclear imaging capability by separating out the three nuclear distributions clearly in ex-vivo model. In the more physiological model, the distributions of
Cu was injected into the stomach orally just before imaging (more physiological model). The Compton camera demonstrated its 3D multinuclear imaging capability by separating out the three nuclear distributions clearly in ex-vivo model. In the more physiological model, the distributions of  I and
I and  Cu were clearly imaged although
Cu were clearly imaged although  In was difficult to visualize due to blurring at low energy region of
In was difficult to visualize due to blurring at low energy region of  -ray. In conclusion, our new Compton camera successfully demonstrated highly resolved multiplanar and multinuclear
-ray. In conclusion, our new Compton camera successfully demonstrated highly resolved multiplanar and multinuclear  -ray simultaneous imaging.
-ray simultaneous imaging.
河地 有木; 渡邉 茂樹; 佐藤 隆博; 荒川 和夫; 武田 伸一郎*; 石川 真之介*; 青野 博之*; 渡辺 伸*; 山口 充孝*; 高橋 忠幸*; et al.
2008 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record (CD-ROM), p.1540 - 1543, 2008/10
The Compton camera is a very promising medical imaging system when we consider multiple radionuclide imaging and its sensitivity, portability and compactness. We have developed a Compton camera by using Si and CdTe semiconductors for medical imaging. The prototype Compton camera head consists of a double-sided Si strip detector (DSSD) module as the scatter detector and four layered 16 CdTe pixel detector modules as the absorber detector. The DSSD has an area of 2.56 2.56 cm, a thickness of 500
2.56 cm, a thickness of 500  m and a strip pitch of 400
m and a strip pitch of 400  m. The CdTe pixel detector has an area of 1.35
m. The CdTe pixel detector has an area of 1.35 1.35 cm, a thickness of 500
1.35 cm, a thickness of 500  m and a pixel size of 1.35 mm
m and a pixel size of 1.35 mm . The high-energy resolution detectors (DSSD:
. The high-energy resolution detectors (DSSD:  E/E
E/E 2.5%, CdTe:
2.5%, CdTe:  E/E
E/E 1%) enable detect the Compton scatter events of the incident
1%) enable detect the Compton scatter events of the incident  -rays, in consequence image radioactive multi-nuclide tracer. We evaluated distributions of sensitivity and spatial resolution, and rat study was performed with three tracers (
-rays, in consequence image radioactive multi-nuclide tracer. We evaluated distributions of sensitivity and spatial resolution, and rat study was performed with three tracers ( In,
In,  I,
I,  Cu) concurrently-administered. As results, lines of point-source data indicated 4 mm spatial resolution in the center of field of view (FOV) in this experimental design, and a characteristic manner of the distributions in the Compton camera FOV was shown. The nuclides in the rat body were distinguished by the
Cu) concurrently-administered. As results, lines of point-source data indicated 4 mm spatial resolution in the center of field of view (FOV) in this experimental design, and a characteristic manner of the distributions in the Compton camera FOV was shown. The nuclides in the rat body were distinguished by the  -ray energies, each tracer imaged separately in vivo, and the difference in distribution among the nuclide was visualized successfully.
-ray energies, each tracer imaged separately in vivo, and the difference in distribution among the nuclide was visualized successfully.
吉川 博; 榊 泰直; 佐甲 博之; 高橋 博樹; Shen, G.; 加藤 裕子; 伊藤 雄一; 池田 浩*; 石山 達也*; 土屋 仁*; et al.
Proceedings of International Conference on Accelerator and Large Experimental Physics Control Systems (ICALEPCS '07) (CD-ROM), p.62 - 64, 2007/10
J-PARCは多目的科学研究のために日本で建設されている大規模陽子加速器施設である。この施設は3つの加速器と3つの実験施設から成り、現在建設中である。リニアックは稼動開始して1年が経過し、3GeVシンクロトロンはこの10月1日に試験運転が開始されたところで、施設全体の完成は来年の夏の予定である。加速器の制御システムは、初期の試運転に必要な性能を実現させた。この制御システムに求められる最も重要な機能は加速器構成機器の放射化を最小限に食い止めることである。この論文では、調整運転の初期の段階において、制御システムの各部分が達成した性能を示す。
田中 伸幸; 吉田 光徳; 奥田 泰之; 佐藤 博之; 久保 真治; 小貫 薫
Proceedings of International Conference on Advanced Nuclear Fuel Cycles and Systems (Global 2007) (CD-ROM), p.833 - 836, 2007/09
熱化学水素製造法ISプロセスの効率化に関する電解電気透析法(EED)を用いたHIx溶液(HI-H O-I
O-I 混合液)濃縮研究の一環として、EEDの最適操作条件検討及びセル構造の最適設計に役立てるため、EEDセル電圧の内訳にかかわる予備的検討を行った。セル電圧検討の基礎データである溶液の電気抵抗,黒鉛電極におけるヨウ素-ヨウ化物イオンの酸化還元反応の過電圧、及び膜にかかわる電圧降下について、プロセス条件に近い組成を有するHIx溶液を用いた場合の値を測定した。また、セル電圧の推算方法を検討し、取得した基礎データをもとに試算した結果、実測値と良好な一致が認められ、用いた方法の妥当性を確認した。
混合液)濃縮研究の一環として、EEDの最適操作条件検討及びセル構造の最適設計に役立てるため、EEDセル電圧の内訳にかかわる予備的検討を行った。セル電圧検討の基礎データである溶液の電気抵抗,黒鉛電極におけるヨウ素-ヨウ化物イオンの酸化還元反応の過電圧、及び膜にかかわる電圧降下について、プロセス条件に近い組成を有するHIx溶液を用いた場合の値を測定した。また、セル電圧の推算方法を検討し、取得した基礎データをもとに試算した結果、実測値と良好な一致が認められ、用いた方法の妥当性を確認した。
近藤 恭弘; 秋川 藤志; 穴見 昌三*; 浅野 博之*; 福井 佑治*; 五十嵐 前衛*; 池上 清*; 池上 雅紀*; 伊藤 崇; 川村 真人*; et al.
Proceedings of 1st Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and 29th Linear Accelerator Meeting in Japan, p.156 - 158, 2004/08
現在KEKにおいて、J-PARCリニアックのDTL1のビームコミッショニングが行われている。ピーク電流30mA,パルス幅20micro-sec,繰り返し12.5HzのビームをDTL1から透過率100%で引出し、設計値通りの19.7MeVに加速されていることを確認した。本発表では、DTL1のビームコミッショニングで現在までに得られている結果を発表する。
井尻 裕二; 澤田 淳; 吉田 英一; 内田 雅大; 石黒 勝彦; 梅木 博之
Proceedings of 4th GEOTRAP Workshop, p.227 - 278, 1999/00
高レベル放射性廃棄物地層処分に係わる第2次取りまとめにおける亀裂ネットワークモデルを用いた天然バリア中の核種移行解析により得られた結果に基づいて今後のサイト特性調査における課題を明らかにするとともに、サイト特性調査と性能評価と処分場の設計の具体的なアプローチについても言及する。