Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
中山 真一; 奥村 雅彦*; 長崎 晋也*; 榎田 洋一*; 梅木 博之*; 高瀬 博康*; 川崎 大介*; 長谷川 秀一*; 古田 一雄*
原子力バックエンド研究(CD-ROM), 23(2), p.131 - 148, 2016/12
平成28年6月25日に東京大学にて、核燃料サイクル・バックエンドに関する研究を支えるためのシンポジウム「核燃料サイクル・バックエンドの科学 -その研究教育の在り方-」が開催された。限られた参加者による限られた時間内のシンポジウムであったが、この分野に身を置いてきた参加者による闊達な意見交換がなされ、今後の議論につながる意見を共有できた。このシンポジウムの内容を報告するとともに、本シンポジウムの企画者のひとりであり、シンポジウム直前に亡くなられたカリフォルニア大学バークレー校の安俊弘(Joonhong Ahn)教授に対する追悼の意を表し、本紙面を借りてその功績を紹介する。
鈴木 義規; 南川 卓也; 尾崎 卓郎; 大貫 敏彦; Francis, A. J.*; 榎田 洋一*; 山本 一良*
Journal of Nuclear Science and Technology, 44(9), p.1227 - 1232, 2007/09
被引用回数:17 パーセンタイル:73.51(Nuclear Science & Technology)シュウ酸,マロン酸,コハク酸,アジピン酸,リンゴ酸又は酒石酸の存在下におけるウラニルイオンの酸化還元反応をサイクリックボルタンメトリーにより調べた。各有機酸水溶液においてUO
 /UO
/UO
 の酸化還元反応及びU(IV)の酸化反応が観測された。UO
の酸化還元反応及びU(IV)の酸化反応が観測された。UO
 の還元ピーク電位は、1:1 UO
の還元ピーク電位は、1:1 UO
 -有機酸錯体の錯形成定数の対数値に比例して減少することがわかった。また、マロン酸又はシュウ酸の存在下におけるUO
-有機酸錯体の錯形成定数の対数値に比例して減少することがわかった。また、マロン酸又はシュウ酸の存在下におけるUO
 /UO
/UO
 の酸化還元電位のpH依存性を調べ、pHによる酸化還元反応の変化を明らかにした。
の酸化還元電位のpH依存性を調べ、pHによる酸化還元反応の変化を明らかにした。
鈴木 義規; 南川 卓也; 吉田 崇弘*; 尾崎 卓郎; 大貫 敏彦; Francis, A. J.; 津島 悟*; 榎田 洋一*; 山本 一良*
Radiochimica Acta, 94(9-11), p.579 - 583, 2006/11
被引用回数:20 パーセンタイル:78.89(Chemistry, Inorganic & Nuclear)クエン酸存在下、pH2-7におけるUO
 の還元挙動をカラム電極電解法を用いて調べた。UO
の還元挙動をカラム電極電解法を用いて調べた。UO
 は、pH2で1段階の還元反応により、pH3-5で2段階の還元反応によりU(IV)まで還元された。UO
は、pH2で1段階の還元反応により、pH3-5で2段階の還元反応によりU(IV)まで還元された。UO
 の還元電位は、pHが2から7に増加するのにしたがって低電位にシフトした。pH6-7では、-0.8V以下の電位でもUO
の還元電位は、pHが2から7に増加するのにしたがって低電位にシフトした。pH6-7では、-0.8V以下の電位でもUO
 は完全に還元されなかった。紫外可視吸収スペクトル分析及び化学種計算から、クエン酸存在下におけるUO
は完全に還元されなかった。紫外可視吸収スペクトル分析及び化学種計算から、クエン酸存在下におけるUO
 の化学種は、pH2-3ではおもにUO
の化学種は、pH2-3ではおもにUO
 , pH3-5でおもに[(UO
, pH3-5でおもに[(UO )
) Cit
Cit ]
] , pH5-7では3量体以上の化学種であった。これらの結果から、UO
, pH5-7では3量体以上の化学種であった。これらの結果から、UO
 は中性pH付近でクエン酸と多量体を形成し、還元されにくくなることがわかった。
は中性pH付近でクエン酸と多量体を形成し、還元されにくくなることがわかった。
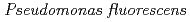 in the presence of citric acid
in the presence of citric acid鈴木 義規; 南川 卓也; 吉田 崇弘*; 尾崎 卓郎; 大貫 敏彦; Francis, A. J.*; 津島 悟*; 榎田 洋一*; 山本 一良*
Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences, 6(1), p.91 - 93, 2005/07
Eu(III)のPseudomonas fluorescensへの吸着に及ぼすクエン酸の影響を調べた。2 MのEu(III)をクエン酸濃度0, 100, 1000
MのEu(III)をクエン酸濃度0, 100, 1000 M, pH3-9で細胞と接触させた。クエン酸を含まない溶液では、pH7以下でほぼ100%のEu(III)が細胞に吸着した。pH7以上ではpHの増加とともにEu(III)の吸着量が減少した。アルカリ性溶液でのEu(III)の吸着量が時間とともに減少していたことから、P. fluorescensがEu(III)と錯体を形成する有機物を分泌している可能性が示唆された。クエン酸が存在する溶液では、クエン酸濃度の増加に伴ってEu(III)の吸着量が減少した。これはEu(III)-クエン酸錯体の形成とEu(III)-細胞表面錯体の形成が競合しているためであると考えられる。クエン酸によるEu(III)の吸着量の減少はアルカリ性溶液で顕著であった。
M, pH3-9で細胞と接触させた。クエン酸を含まない溶液では、pH7以下でほぼ100%のEu(III)が細胞に吸着した。pH7以上ではpHの増加とともにEu(III)の吸着量が減少した。アルカリ性溶液でのEu(III)の吸着量が時間とともに減少していたことから、P. fluorescensがEu(III)と錯体を形成する有機物を分泌している可能性が示唆された。クエン酸が存在する溶液では、クエン酸濃度の増加に伴ってEu(III)の吸着量が減少した。これはEu(III)-クエン酸錯体の形成とEu(III)-細胞表面錯体の形成が競合しているためであると考えられる。クエン酸によるEu(III)の吸着量の減少はアルカリ性溶液で顕著であった。
井口 哲夫*; 渡辺 賢一*; 河原林 順*; 瓜谷 章*; 榎田 洋一*; 渡部 和男
JAERI-Tech 2004-010, 62 Pages, 2004/03
短パルス・高繰り返し率で適切な出力強度の得られる波長可変レーザーを用いて、中性子ドジメトリーへ共鳴アブレーション(RLA)現象を効果的に活用するため、理論モデルにより最適条件、すなわち、高感度性と元素選択性の両立を図ることのできる条件を探索した。その結果、従来の低繰り返しレーザーと比べ、約100倍検出感度を改善できることを実証した。さらに、改良型RLA-質量分析システムにより、14MeVDT中性子照射を行った高純度Al試料中に生成された極微量長半減期核種Al-26を明瞭に検出することに成功し、本分析手法に基づく中性子ドジメトリー手法の実現可能性を示すことができた。
 Complex for Super-DIREX Process
Complex for Super-DIREX Process紙谷 正仁; 三浦 幸子; 野村 和則; 小山 智造; 小雲 信哉*; 森 行秀*; 榎田 洋一*
2nd International Conference ATALANTE 2004, 4 Pages, 2004/00
Super-DIREX再処理法における直接抽出プロセスの成立性を確認するため,照射済MOX燃料を機械的処理に粉体化し、常圧40-80 のTBP錯体でウラン及びプルトニウムを抽出する試験を行った。ウラン及びプルトニウムの抽出及び核分裂生成物との除染について実験データを取得した。
のTBP錯体でウラン及びプルトニウムを抽出する試験を行った。ウラン及びプルトニウムの抽出及び核分裂生成物との除染について実験データを取得した。
榎田 洋一*; 山本 一良*; 小林 登*; 富岡 修*; 宮原 幸子; 駒 義和; 青嶋 厚
JNC TY8400 2002-004, 115 Pages, 2002/05
核燃料再処理や放射性廃棄物の除染への将来における適用を想定し、リン酸トリブチル(TBP)の硝酸錯体を超臨界二酸化炭素に溶解して用いることにより、ランタニド酸化物と他の金属酸化物の混合物からランタニドだけを選択的に、また、二次廃棄物発生量を最小化し、かつ、大きな処理速度で回収することが可能であることを示すことを本研究の目的とした。粉末もしくはバルクのGd2O3等のランタニド酸化物とTBP硝酸錯体をn-ドデカンで希釈した有機流体と反応させ、ランタニド酸化物の溶解抽出速度を明らかにした。また、ランタニド酸化物に金属酸化物または金属単体を混合した試料に対しても同様の実験を行い、ランタニド酸化物の選択的な溶解抽出が可能であるかどうか、また、その反応機構を検討した。さらに、同様の試料を超臨界二酸化炭素中でTBP硝酸錯体と反応させ、超臨界二酸化炭素中でのランタニド酸化物の溶解抽出速度を明らかにするとともに、ランタニド酸化物の選択的な溶解抽出が可能であることを示した。また、TBPの超臨界二酸化炭素に対する溶解度を分子シミュレーションを用いて定量的に評価することが可能であることを確認した。さらに、得られた基礎データを見かけの速度定数を算出するとともに、溶解抽出過程を解析するための化学工学モデルを作成した。本報告書は、核燃料サイクル開発機構の核燃料サイクル公募型研究により実施した業務成果に関するものである。
山本 一良*; 榎田 洋一*; 小林 登*; 高梨 光博*; 青嶋 厚*; 野村 和則; 柴田 淳広
JNC TY8400 2002-003, 81 Pages, 2002/05
経済性の革新的向上と廃棄物発生量の大幅低減を実現するために提案されている先進的核燃料再処理分離プロセスは、晶析法を採用する等により、従来と異なるプロセスパラメタ(重金属負荷度、除染係数、流量率等)で運転されることになるため、実用プロセス条件の選定に先立ち、化学プロセスフローシートに関して十分な変動範囲にわたったさまざまな視点からの基礎検討が必要である。本研究では、先進的核燃料再処理分離プロセスの化学プロセスフローシートに関して、さまざまな変動の及ぼす影響を理論・計算解析により把握し、より経済性の向上と廃棄物発生量の低減を実現するプロセスとして高い完成度を目指すものである。本研究では、まず、化学プロセスフローシートの定常分離特性に関する研究を行い、溶媒抽出分離プロセスでウラン、プルトニウム及びこれらに混入する主要な不純物の定常状態における分離特性(回収率、廃液発生量等)をプロセス計算解析によって明確にした。次に、化学プロセスフローシートの変動後の分離特性に関する研究で、ウラン、プルトニウム及びこれらに混入する主要な不純物の分離特性(回収率等)がプロセスパラメタ(重金属負荷度、流量率等)の変動によってどのように変化するかをプロセス計算解析の観点から明確にした。最後に、分離プロセスシステムの微小変動が分離特性に与える影響に関する研究で、現実の化学分離プロセスで生じる可能性があり、通常の計算機解析では考慮されないような比較的微小な変動が再処理分離プロセスに与える影響の大きさをプロセス計算解析によって明確にした。本報告書は、核燃料サイクル開発機構の先行基礎工学研究協力制度により実施した業務成果に関するものである。
 fluid leaching (SFL) of uranium from solid wastes using HNO
fluid leaching (SFL) of uranium from solid wastes using HNO -TBP complex as a reactant
-TBP complex as a reactant富岡 修*; 目黒 義弘; 磯 修一; 吉田 善行; 榎田 洋一*; 山本 一良*
Proceedings of International Solvent Extraction Conference 2002 (CD-ROM), p.1143 - 1147, 2002/00
ウラン酸化物で汚染した固体廃棄物からウランを除去するための新しい方法を開発した(超臨界CO リーチング(SFL)法と称する)。本法は硝酸-TBP錯体を含む超臨界CO
リーチング(SFL)法と称する)。本法は硝酸-TBP錯体を含む超臨界CO 中へのウラン酸化物の溶解反応を原理とする。UO
中へのウラン酸化物の溶解反応を原理とする。UO 及びU
及びU O
O の粉末がともに60
の粉末がともに60 ,20MPaの条件で超臨界CO
,20MPaの条件で超臨界CO 中に完全に溶解することを明らかにした。固体廃棄物中のウランの除染法としてのSFL法の適用性を、模擬試料(海砂約50gとUO
中に完全に溶解することを明らかにした。固体廃棄物中のウランの除染法としてのSFL法の適用性を、模擬試料(海砂約50gとUO またはU
またはU O
O 約120mgの混合物)を用いて実証した。UO
約120mgの混合物)を用いて実証した。UO 及びU
及びU O
O の除染係数としてそれぞれ100及び10000を得た。
の除染係数としてそれぞれ100及び10000を得た。
 medium containing HNO
medium containing HNO -TBP complex
-TBP complex富岡 修*; 目黒 義弘; 磯 修一; 吉田 善行; 榎田 洋一*; 山本 一良*
Journal of Nuclear Science and Technology, 38(6), p.461 - 462, 2001/06
被引用回数:27 パーセンタイル:85.61(Nuclear Science & Technology)超臨界二酸化炭素(SF-CO )を媒体として用いて、ウラン酸化物を含む固体廃棄物からウランを選択的に溶解して回収する除染方法を開発した。模擬汚染試料として、約100~200mgのUO
)を媒体として用いて、ウラン酸化物を含む固体廃棄物からウランを選択的に溶解して回収する除染方法を開発した。模擬汚染試料として、約100~200mgのUO あるいはU
あるいはU O
O を均一に混合した砂(平均直径~1mm)約50gを用いた。試料をステンレス鋼製の容器(内容積約50ml)に採取し、これに、200気圧に加圧したSF-CO
を均一に混合した砂(平均直径~1mm)約50gを用いた。試料をステンレス鋼製の容器(内容積約50ml)に採取し、これに、200気圧に加圧したSF-CO と硝酸-リン酸トリブチル錯体溶液(HNO
と硝酸-リン酸トリブチル錯体溶液(HNO -TBP錯体,モル比: 4.8:3)との混合流体を50~60
-TBP錯体,モル比: 4.8:3)との混合流体を50~60 で圧入する(流速: 3ml/min CO
で圧入する(流速: 3ml/min CO ,0.3ml/min HNO
,0.3ml/min HNO -TBP)。一定時間放置後、SF-CO
-TBP)。一定時間放置後、SF-CO を流しながら洗浄し、ウランを含むCO
を流しながら洗浄し、ウランを含むCO 流体を回収した。溶解処理した後に試料中に残存するウランは、1mg以下(UO
流体を回収した。溶解処理した後に試料中に残存するウランは、1mg以下(UO )あるいは0.01mg(U
)あるいは0.01mg(U O
O )であり、砂中のウランを100~10000分の1以下に除染できた。
)であり、砂中のウランを100~10000分の1以下に除染できた。
 complex
complex宮原 幸子; 船坂 英之; 榎田 洋一*; 山本 一良*
ATALANTE2000, 0 Pages, 2000/00
超臨界二酸化炭素にTBP-硝酸錯体をエントレーナとして添加した流体により、使用済燃料から直接U,Puの回収を行う超臨界直接法の開発を行っている。臨界直接抽出法の再処理工程への適用性を評価するため、Uと模擬FPを用いた超臨界試験及びMOX燃料の溶解・抽出試験を実施し、超臨界直接抽出法のU酸化物への適応性評価及び技術的課題の摘出を試みた。U及びSr,Zr,Mo,Ru,Pd,Ce,Ndの酸化物を用いた超臨界試験では、Uのみが選択的に抽出されたことから、超臨界直接抽出法による選択的なU抽出の可能性が示唆される。このほか大気圧条件下で実施したMOX燃料の溶解抽出試験の結果について報告する。
榎田 洋一*; 和田 光二; 和田 幸男
PNC TN8410 90-050, 62 Pages, 1990/04
レーザー光を用いた核燃料サイクル技術の特徴として、次のような利点が考えられている。(1)レーザー光の波長選択性、短い波長巾およびパルス化等を利用して、対象物質の選択的励起、分離が可能となる。(2)ネプツニウムやルテニウムなどウラン・プルトニウム製品に同伴する元素の濃度プロファイルを制御できることからウラン・プルトニウムの品質管理を高度化できる。(3)酸化還元に必要な酸化還元試薬の代わりに、レーザーによって誘起される光酸化還元反応を利用するため、廃棄物量を低減できる。また、高レベル放射性廃液から、資源物質を回収する事により、廃棄物として処分される元素量を低減できる。(4)化学薬品の代わりにレーザーエネルギーを利用するので、プロセスが単純になり装置を小型化する事ができ、遠隔操作性のため新たな耐放射性機器や特殊な遠隔保守技術の開発の必要がないことにより高い経済性が得られる。(5)レーザー発生装置を、反応容器から距離的に引き離せるところから優れた遠隔操作性が得られる。これらの多くの優れた特徴を有するレーザー分離技術を群分離技術およびピュレックス法核燃料再処理工程技術等に導入することにより核燃料サイクル技術の一層の高度化を図れると期待される。そのための手始めとして、文献調査および基礎実験を実施した。まず、核燃料再処理工程に反映できるレーザー化学の適用性を探るため、プルトニウムおよびネプツニウムを使用した基礎試験を行った。今回の試験は、プルトニウム精製工程でプルトニウムに同伴してしまうネプツニウムの除去を目的とした、光酸化還元原子価調整を試み、その可能性を確認した。
鈴木 篤之*; 榎田 洋一*; 梅木 博之*
PNC TJ5602 86-002, 93 Pages, 1986/03
放射性廃棄物を花崗岩のような亀裂状媒体に地層処分する場合の安全評価は,従来,各種の移行を亀裂と岩体とに分けて取り扱い,岩体の部分では,核種が均一に拡散するとして解析が行われている。しかし昨年度の研究の一部として実施されたCsの花崗岩への吸着実験から,岩体中の拡散空隙が核種の移行に対して必ずしも均一に寄与していないという結果が得られた。本研究では,花崗岩中の拡散空隙の構造を調べるため,非吸着性核種としてトリチウム,ヨウ素を用いて拡散実験を行った。さらに花崗岩を電解質溶液で飽和させ,その抵抗を測定することにより空隙の構造を調べる実験を併せて行った。 花崗岩は直径20mmの円盤で,厚さ0.7mmから7mmまで変化させそれぞれの厚さに対して,室温で拡散実験と抵抗測定を行った。その結果,得られた実効拡散係数は,花崗岩の厚さが厚くなるに従い10-11M2/sから 10-12M2/sに減少することが確かめられた。また,抵抗測定より得られたフォーメーション・ファクターの値も同様に
10-12M2/sに減少することが確かめられた。また,抵抗測定より得られたフォーメーション・ファクターの値も同様に 10-2から
10-2から 10-3に減少した。
10-3に減少した。
鈴木 篤之*; 梅木 博之*; 榎田 洋一*; 岡本 毅*
PNC TJ160 85-05, 132 Pages, 1985/03
1 ガラス固化体の長期浸出挙動 MCC-1テスト法に準拠した方法を用い、静水系における長期浸出実験( 300日)を行った。実験ではガラス表面積対液量比(SA/V)を0.1cm/SUP-1、0.2cm/SUP-1、1.0cm/SUP-1と変えてその影響を調べ、またバルク試料と粉末試料とを比較した。温度は90度Cである。ガラス成分のうち、Si、Na、Cs、Sr、Uの期浸出挙動について調べたが、その結果一般に浸出量はバルク試料の方が粉末試料より大きい傾向を示した。この原因としては、濃度がまだ充分飽和していないこと、あるいは飽和濃度がSA/Vに依存する可能性があることが上げられる。またSi、Csについては簡単な物質収支モデルによる解析を試み、そのモデルによって実験値をうまく表すことができたが、求められた飽和濃度は他の報告に見られる値に比べて小さくなった。これは、実験方法・ガラス組成が若干異なることによるものと思われる。2 花崗岩の核種収着作用 花崗岩の薄片試量を用いたCsの収着実験を行ない、岩体内の有効拡散空隙を評価した。花崗岩薄片の厚さは0.7
300日)を行った。実験ではガラス表面積対液量比(SA/V)を0.1cm/SUP-1、0.2cm/SUP-1、1.0cm/SUP-1と変えてその影響を調べ、またバルク試料と粉末試料とを比較した。温度は90度Cである。ガラス成分のうち、Si、Na、Cs、Sr、Uの期浸出挙動について調べたが、その結果一般に浸出量はバルク試料の方が粉末試料より大きい傾向を示した。この原因としては、濃度がまだ充分飽和していないこと、あるいは飽和濃度がSA/Vに依存する可能性があることが上げられる。またSi、Csについては簡単な物質収支モデルによる解析を試み、そのモデルによって実験値をうまく表すことができたが、求められた飽和濃度は他の報告に見られる値に比べて小さくなった。これは、実験方法・ガラス組成が若干異なることによるものと思われる。2 花崗岩の核種収着作用 花崗岩の薄片試量を用いたCsの収着実験を行ない、岩体内の有効拡散空隙を評価した。花崗岩薄片の厚さは0.7 7.0mmとし、濃度依存性を調べるために3.84x10/SUP-4
7.0mmとし、濃度依存性を調べるために3.84x10/SUP-4 5x10/SUP3 g/mlの濃度範囲のCsCl溶液を用いた。約1500時間の実験で収着は平衡に達したと見なすことができ、花崗岩単位重量当りの平衡収着量は薄片厚の増加に従って減少した。このことは、花崗岩の有効拡散空隙が岩体内で均一ではないことを示している。そこで有効拡散空隙が表面からの距離に従って減少するモデルを考え、それによって実験値をうまく表すことができた。また平衡収着量の濃度依存性については、実験の範囲でフロインドリッヒの式q=
5x10/SUP3 g/mlの濃度範囲のCsCl溶液を用いた。約1500時間の実験で収着は平衡に達したと見なすことができ、花崗岩単位重量当りの平衡収着量は薄片厚の増加に従って減少した。このことは、花崗岩の有効拡散空隙が岩体内で均一ではないことを示している。そこで有効拡散空隙が表面からの距離に従って減少するモデルを考え、それによって実験値をうまく表すことができた。また平衡収着量の濃度依存性については、実験の範囲でフロインドリッヒの式q= C
C を用いてよく近似でき、パラメタ
を用いてよく近似でき、パラメタ 、
、 の値はそれぞれ2.29、0.75となった。
の値はそれぞれ2.29、0.75となった。
鈴木 義規; 榎田 洋一*; 山本 一良*; 南川 卓也; 尾崎 卓郎; 大貫 敏彦
no journal, ,
9種類の有機酸を対象に嫌気性条件下でのShewanella putrefaciensによるU(VI)の還元挙動への共存有機酸の影響を調べた。培地の溶存ウランの濃度,吸収スペクトル及び培養過程で生成した沈殿物の分析から、共存する有機酸の種類により、U(VI)の還元挙動が異なることが示された。