Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
浪江 将成; 斉藤 淳一; 岡 涼太郎*; Kim, J.-H.*
Vacuum, 234, p.114038_1 - 114038_9, 2025/04
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Materials Science, Multidisciplinary)Wettability of titanium (Ti) and surface-modified (Oxidized or Fluorinated) Ti with liquid sodium (Na) were investigated via experiments and theoretical calculations. From the experimental results, a sliding angle of Na droplet on oxidized Ti was smaller than that on untreated Ti, indicating the worsening of wettability by oxidation. In contrast, the sliding angle of Na droplet on fluoridated Ti was larger than that on untreated Ti, indicating an improvement in wettability by fluorination. Additionally, the cluster models for the interface between Na droplets and treated or untreated Ti were constructed for theoretical calculations of electronic states at the interface, covalent and ionic bonds at the interface were evaluated from the calculation results. The sliding angles obtained in the wettability tests and the strength of covalent bonding at the interface showed no correlation, but good correlation was observed between the sliding angles and ionic bonding at the interface. Thus, the wettability of surface-modified Ti with liquid Na can be theoretically understood based on the atomic interactions at the interface.
浪江 将成; 斉藤 淳一; 池田 明日香; 岡 涼太郎*; Kim, J.-H.*
Surfaces (Internet), 7(3), p.550 - 559, 2024/09
The iron (Fe) specimens selected as the substrate metal for this study were surface-treated using fluorine gas, and their wettability with liquid sodium (Na) was evaluated using the sliding angle. Additionally, the surface morphology and binding state were analyzed, and the applicability of wettability control with liquid sodium by fluorination was discussed using the analysis results. Fluorination formed a fluoride layer comprising FeF and FeF
and FeF bonds on the iron surface. The composition of the fluoride layer varied, depending on the treatment conditions. The surface of the specimen that contains a lot of FeF
bonds on the iron surface. The composition of the fluoride layer varied, depending on the treatment conditions. The surface of the specimen that contains a lot of FeF bonds had a small sliding angle for the liquid sodium droplet and was harder to wet than the untreated specimen. In contrast, the surface of the specimen that contains a lot of FeF
bonds had a small sliding angle for the liquid sodium droplet and was harder to wet than the untreated specimen. In contrast, the surface of the specimen that contains a lot of FeF bonds had a large sliding angle for the liquid sodium droplet and was easier to wet than the untreated specimen. These results indicate that fluorination is an effective surface modification technique that can be applied to control the wettability of iron with liquid sodium.
bonds had a large sliding angle for the liquid sodium droplet and was easier to wet than the untreated specimen. These results indicate that fluorination is an effective surface modification technique that can be applied to control the wettability of iron with liquid sodium.
浪江 将成; 斉藤 淳一
Computational Materials Science, 239, p.112963_1 - 112963_7, 2024/04
被引用回数:1 パーセンタイル:35.94(Materials Science, Multidisciplinary)Atomic interactions at the interface involving iron, iron fluorides (iron (II) fluoride and iron (III) fluoride), and sodium were investigated using first-principles calculations. The wettability with liquid sodium was subsequently examined, focusing on the calculated atomic interactions. From a covalent bonding perspective, iron (II) fluoride exhibited weaker bonds between neighboring atoms in the substrate material than iron (III) fluoride. However, it exhibited relatively strong bonds between the substrate material and sodium atoms. In contrast, iron (III) fluoride had stronger bonds between neighboring atoms in the substrate material, with weaker bonds between the substrate material and sodium atoms. Additionally, in terms of ionic bonding, the contact of the sodium atom with the substrate material increased the charge transfer of the substrate material atom, correlating with the oxidation number of iron. Iron (III) fluoride exhibited the most substantial charge transfer among the substrate materials. The charge transfer from the sodium atom to the atom in contact with it was approximately 2.5 times that of iron. This result underscores the change in electronic states induced by the iron or iron fluoride interface, potentially influencing the wettability between the material surface and liquid sodium.
 Ga K-edge XANES study of Ga-exchanged zeolites at high temperatures under different atmospheres including vacuum, CO, and pressurized H
Ga K-edge XANES study of Ga-exchanged zeolites at high temperatures under different atmospheres including vacuum, CO, and pressurized H
Huang, M.*; 金城 哲弥*; 安村 駿作*; 鳥屋尾 隆*; 松村 大樹; 齋藤 寛之*; 清水 研一*; 並木 則和*; 前野 禅*
Catalysis Science & Technology, 13(23), p.6832 - 6838, 2023/12
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Chemistry, Physical)Ga-exchanged zeolites are promising catalysts for dehydrogenative alkane transformations. Reduced Ga species, such as Ga hydrides and Ga cations, are possible active sites for alkane dehydrogenation based on in situ spectroscopic studies. However, most of the reported studies were conducted at lower temperatures compared with those encountered in actual operating conditions. In this study, the in situ Ga K-edge XANES analysis of Ga-exchanged MFI zeolite was performed under actual operating temperatures and different atmospheres (H
cations, are possible active sites for alkane dehydrogenation based on in situ spectroscopic studies. However, most of the reported studies were conducted at lower temperatures compared with those encountered in actual operating conditions. In this study, the in situ Ga K-edge XANES analysis of Ga-exchanged MFI zeolite was performed under actual operating temperatures and different atmospheres (H , He, CO, vacuum, and C
, He, CO, vacuum, and C H
H ). The absorption edge appeared at similarly lower energy values than that of Ga
). The absorption edge appeared at similarly lower energy values than that of Ga O
O in all atmospheres, whereas the main absorption peak intensity differed depending on the presence or absence of a hydride source in the gas phase. Higher intensities were observed under H
in all atmospheres, whereas the main absorption peak intensity differed depending on the presence or absence of a hydride source in the gas phase. Higher intensities were observed under H and C
and C H
H atmospheres than under CO and vacuum atmospheres.
atmospheres than under CO and vacuum atmospheres.
高木 寛貴*; 高木 里奈*; 見波 将*; 野本 拓也*; 大石 一城*; 鈴木 通人*; 柳 有起*; 平山 元昭*; Khanh, N.*; 軽部 皓介*; et al.
Nature Physics, 19(7), p.961 - 968, 2023/07
被引用回数:50 パーセンタイル:99.07(Physics, Multidisciplinary)In ferromagnets, electric current generally induces a transverse Hall voltage in proportion to the internal magnetization. This effect is frequently used for electrical readout of the spin up and down states. While these properties are usually not expected in antiferromagnets, recent theoretical studies predicted that non-coplanar antiferromagnetic order with finite scalar spin chirality - meaning a solid angle spanned by neighboring spins - can induce a large spontaneous Hall effect even without net magnetization or external magnetic field. This phenomenon, the spontaneous topological Hall effect, can potentially be used for the efficient electrical readout of the antiferromagnetic states, but it has not been experimentally verified due to a lack of appropriate materials hosting such magnetism. Here, we report the discovery of all-in-all-out type non-coplanar antiferromagnetic order in triangular lattice compounds CoTa S
S and CoNb
and CoNb S
S . These compounds are reported to host unconventionally large spontaneous Hall effect despite their vanishingly small net magnetization, and our analysis reveals that it can be explained in terms of the topological Hall effect that originates from the fictitious magnetic field associated with scalar spin chirality. These results indicate that the scalar spin chirality mechanism offers a promising route to the realisation of giant spontaneous Hall response even in compensated antiferromagnets, and highlight intercalated van der Waals magnets as a promising quasi-two-dimensional material platform to enable various nontrivial ways of electrical reading and possible writing of non-coplanar antiferromagnetic domains.
. These compounds are reported to host unconventionally large spontaneous Hall effect despite their vanishingly small net magnetization, and our analysis reveals that it can be explained in terms of the topological Hall effect that originates from the fictitious magnetic field associated with scalar spin chirality. These results indicate that the scalar spin chirality mechanism offers a promising route to the realisation of giant spontaneous Hall response even in compensated antiferromagnets, and highlight intercalated van der Waals magnets as a promising quasi-two-dimensional material platform to enable various nontrivial ways of electrical reading and possible writing of non-coplanar antiferromagnetic domains.
近藤 恭弘; 北村 遼; 不破 康裕; 森下 卓俊; 守屋 克洋; 高柳 智弘; 大谷 将士*; Cicek, E.*; 恵郷 博文*; 深尾 祥紀*; et al.
Proceedings of 31st International Linear Accelerator Conference (LINAC 2022) (Internet), p.636 - 641, 2022/09
J-PARCにおいて、現代の素粒子物理学で最も重要な課題の一つである、ミューオン異常磁気モーメント、電気双極子モーメントを精密測定する実験のためのミューオンリニアック計画が進行中である。J-PARCミューオン施設からのミューオンはいったん室温まで冷却され、212MeVまで加速される。横エミッタンスは1.5 mm mradであり、運動量分散は1%である。高速で規格化した粒子の速度で0.01から0.94におよぶ広い範囲で効率よく加速するため、4種類の加速構造が用いられる。計画は建設段階に移行しつつあり、初段の高周波四重極リニアックによるミューオン再加速はすでに2017年に実証済である。次段の交差櫛形Hモードドリフトチューブリニアックのプロトタイプによる大電力試験が完了し、ディスクアンドワッシャ型結合セルリニアックの第一モジュールの製作が進行中である。さらに円盤装荷型加速管の設計もほぼ終了した。本論文ではこれらミューオンリニアックの最近の進捗について述べる。
mm mradであり、運動量分散は1%である。高速で規格化した粒子の速度で0.01から0.94におよぶ広い範囲で効率よく加速するため、4種類の加速構造が用いられる。計画は建設段階に移行しつつあり、初段の高周波四重極リニアックによるミューオン再加速はすでに2017年に実証済である。次段の交差櫛形Hモードドリフトチューブリニアックのプロトタイプによる大電力試験が完了し、ディスクアンドワッシャ型結合セルリニアックの第一モジュールの製作が進行中である。さらに円盤装荷型加速管の設計もほぼ終了した。本論文ではこれらミューオンリニアックの最近の進捗について述べる。
鷲見 一路*; 飯嶋 徹*; 居波 賢二*; 須江 祐貴*; 四塚 麻衣*; 恵郷 博文*; 大谷 将士*; 齊藤 直人*; 三部 勉*; 吉田 光宏*; et al.
Journal of Physics; Conference Series, p.012038_1 - 012038_6, 2022/07
ミューオンリニアック用円盤装荷型加速構造(DLS)がJ-PARCミューオンg-2/EDM実験のために開発中である。4つの加速勾配20MV/mのDLSにより、ミューオンが40MeVから212MeV(高速の70%から94%)に加速される。加速にしたがい円盤間隔が増加していく2592MHz準定勾配型TM01-2 /3モードDLSを設計し、ミューオン速度と高周波の位相速度の位相スリップが2度以下となることを確認した。さらに、理想的な同期位相を同定し、全エミッタンス1.5
/3モードDLSを設計し、ミューオン速度と高周波の位相速度の位相スリップが2度以下となることを確認した。さらに、理想的な同期位相を同定し、全エミッタンス1.5 mm mrad、運動量分散0.1%(RMS)という要求を満たすことをシミュレーションにより確認した。
mm mrad、運動量分散0.1%(RMS)という要求を満たすことをシミュレーションにより確認した。
須江 祐貴*; 四塚 麻衣*; 二ツ川 健太*; 長谷川 和男; 飯嶋 徹*; 飯沼 裕美*; 居波 賢二*; 石田 勝彦*; 河村 成肇*; 北村 遼; et al.
Physical Review Accelerators and Beams (Internet), 23(2), p.022804_1 - 022804_7, 2020/02
被引用回数:2 パーセンタイル:20.59(Physics, Nuclear)低エネルギー、低インテンシティーミューオンビームのビーム進行方向のバンチ幅を測定するための破壊的モニターを開発した。このバンチ幅モニター(BWM)は、1つずつのミューオンを高い分解能で測定するためにマイクロチャンネルプレートを用いている。それに加え、タイミングウオークを抑制するために、コンスタントフラクションディスクリミネータ回路を用いている。時間分解能は精密パルスレーザーを用いて65psと測定された。この分解能は、J-PARC E34実験で要求される性能を満たしている。我々は、このBWMを用いて、高周波四重極リニアックによって加速された負ミューオニウムイオンのバンチ幅を測定した。バンチ幅54 11nsと測定することに成功した。
11nsと測定することに成功した。
大谷 将士*; 深尾 祥紀*; 二ツ川 健太*; 河村 成肇*; 的場 史朗*; 三部 勉*; 三宅 康博*; 下村 浩一郎*; 山崎 高幸*; 長谷川 和男; et al.
Journal of Physics; Conference Series, 1350, p.012067_1 - 012067_6, 2019/12
被引用回数:3 パーセンタイル:78.48(Physics, Particles & Fields)負ミューオニウムはそのユニークな性質から様々な科学の分野で応用される可能性がある。1980年代に真空中で初めて生成されて以来、仕事関数の低い物質を用いて負ミューオニウム生成効率を高めることが議論されてきた。アルミナセメントの構成物質であるC12A7は良く知られた絶縁体であるが、電子をドープすることで導体として振舞うことが近年発見された。このC12A7エレクトライドは2.9eVという比較的低い仕事関数を持ち、負イオン生成効率を示すと期待されている。本論文では、従来用いていたアルミニウム、C12A7エレクトライド、さらにステンレスターゲット用いた負ミューオニウムイオン生成効率の比較について述べる。測定された生成率は10 /sであり、現状セットアップではエレクトライドにおいても大きな生成率向上は確認されず、表面状態をより注意深く整える必要であることが推定される。また、生成された負ミューオニウムの平均エネルギーに材質依存はなく、0.2
/sであり、現状セットアップではエレクトライドにおいても大きな生成率向上は確認されず、表面状態をより注意深く整える必要であることが推定される。また、生成された負ミューオニウムの平均エネルギーに材質依存はなく、0.2 0.1keVであった。
0.1keVであった。
須江 祐貴*; 飯嶋 徹*; 居波 賢二*; 四塚 麻衣*; 飯沼 裕美*; 中沢 雄河*; 大谷 将士*; 河村 成肇*; 下村 浩一郎*; 二ツ川 健太*; et al.
Proceedings of 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan (インターネット), p.55 - 60, 2019/07
本論文では、RFQによって89keVまで加速されたミューオンのバンチ長測定について述べる。ミューオンの性質の詳細測定のための、4種類の加速構造を持つリニアックがJ-PARCにおいて開発中である。2017年に、RFQを用いたミューオン加速の実証と横方向プロファイル測定が行われた。次の課題は、次段の加速器のアクセプタンスとビーム整合するために必要な縦方向のビームモニタである。このために、マイクロチャンネルプレートを用いた新しい縦方向ビームモニタを開発中である。このモニタは加速周波数324MHzの1%に相当する時間分解能である30から40psを目標にしている。2018年10月に、RFQによって89keVまで加速された負ミューオニウムイオンのバンチ長測定に成功した。測定されたバンチ長は、0.54 0.13nsであった。
0.13nsであった。
四塚 麻衣*; 飯嶋 徹*; 飯沼 裕美*; 居波 賢二*; 大谷 将士*; 河村 成肇*; 北村 遼; 近藤 恭弘; 齊藤 直人; 下村 浩一郎*; et al.
Proceedings of 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan (インターネット), p.814 - 817, 2019/07
ミューオンの異常磁気能率(g-2)は新物理の兆候が期待されている物理量であり、実験値と標準理論の予測値の間には現在3 以上の乖離が確認されている。J-PARC E34実験では独自の手法による精密測定を目指しており、主要な系統誤差を削減するために低エミッタンスビームを使用する。これは、熱エネルギーまで冷却したミューオンを、速度に応じた複数段階の線形加速器を用い212MeVまで再加速することによって生成する。実験の要求から加速中のエミッタンス成長を抑える必要があるため設計値実現には異なる加速器間でのビームマッチングが重要であり、実際のビームプロファイル測定に基づいて行われる必要がある。時間方向の測定に使用するモニターには、加速位相の1%である30
以上の乖離が確認されている。J-PARC E34実験では独自の手法による精密測定を目指しており、主要な系統誤差を削減するために低エミッタンスビームを使用する。これは、熱エネルギーまで冷却したミューオンを、速度に応じた複数段階の線形加速器を用い212MeVまで再加速することによって生成する。実験の要求から加速中のエミッタンス成長を抑える必要があるため設計値実現には異なる加速器間でのビームマッチングが重要であり、実際のビームプロファイル測定に基づいて行われる必要がある。時間方向の測定に使用するモニターには、加速位相の1%である30 40psに相当する精度が要求されている。また、イオン源開発初期のビーム強度が低い段階でも使用可能でなければならないため、ミューオン1つに対して感度を持つ必要がある。この2つの要求を満たすため、高い感度を持つマイクロチャンネルプレートと、波高依存性の削減により高時間分解能の達成が可能であるCFD回路を用いたモニターの開発を行った。また、性能評価のためにテストベンチの構築を行い、ピコ秒パルスレーザーをMCP表面に照射した際に起こる光電効果によって生成した光電子を用い、時間分解能65psの評価値を得た。本発表では、テストベンチによるモニターの性能評価結果を報告する。
40psに相当する精度が要求されている。また、イオン源開発初期のビーム強度が低い段階でも使用可能でなければならないため、ミューオン1つに対して感度を持つ必要がある。この2つの要求を満たすため、高い感度を持つマイクロチャンネルプレートと、波高依存性の削減により高時間分解能の達成が可能であるCFD回路を用いたモニターの開発を行った。また、性能評価のためにテストベンチの構築を行い、ピコ秒パルスレーザーをMCP表面に照射した際に起こる光電効果によって生成した光電子を用い、時間分解能65psの評価値を得た。本発表では、テストベンチによるモニターの性能評価結果を報告する。
須江 祐貴*; 飯嶋 徹*; 居波 賢二*; 四塚 麻衣*; 二ツ川 健太*; 河村 成肇*; 三部 勉*; 三宅 康博*; 大谷 将士*; 長谷川 和男; et al.
Proceedings of 10th International Particle Accelerator Conference (IPAC '19) (Internet), p.37 - 40, 2019/06
この論文では、RFQによって89keVまで加速されたミューオンのバンチ長測定について述べる。ミューオンの性質の詳細測定のための、4種類の加速構造を持つリニアックがJ-PARCにおいて開発中である。2017年に、RFQを用いたミューオン加速の実証と横方向プロファイル測定が行われた。次の課題は、次段の加速器のアクセプタンスとビーム整合するために必要な縦方向のビームモニタである。このために、マイクロチャンネルプレートを用いた新しい縦方向ビームモニタを開発中である。このモニタは加速周波数324MHzの1%に相当する時間分解能である30から40psを目標にしている。2018年10月に、RFQによって89keVまで加速された負ミューオニウムイオンのバンチ長測定に成功した。測定されたバンチ長は、0.54 0.13nsであった。
0.13nsであった。
四塚 麻衣*; 飯嶋 徹*; 居波 賢二*; 須江 祐貴*; 飯沼 裕美*; 中沢 雄河*; 齊藤 直人; 長谷川 和男; 近藤 恭弘; 北村 遼; et al.
Proceedings of 10th International Particle Accelerator Conference (IPAC '19) (Internet), p.2571 - 2574, 2019/06
J-PARC E34実験はミューオンの異常磁気モーメントと電気双極子モーメントの高精度測定を目標にしている。この実験では、室温で生成されたミューオニウムをレーザー共鳴方でイオン化した超低速ミューオンを多段のリニアックで加速したミューオンビームを用いる。実験の要請を満たすには加速中のエミッタンス増大を抑えることが必要である。エミッタンス増大の主要な要因の一つは異なった加速構造間でのビームの不整合であるので、これらを測定するための縦横両方向のビームモニタが重要である。このうち、324MHzの加速構造の縦方向測定を行うモニタは、その加速周期の1%の時間分解能が要求される。さらに、ビーム調整段階でのミューオンビーム強度が非常に低いので、ミューオン1つに対する感度が必要である。これらの要求を実現するために、我々はマイクロチャンネルプレートを用いた縦方向ビームモニタを開発している。テストベンチでの分解能評価では、65psを達成した。さらに、RFQを用いたビーム試験で、縦方向バンチ長を測定することに成功した。さらに精度を高めるための改良も計画中である。本論文ではこの縦方向ビームモニタのテストベンチでの性能評価について述べる。
阿部 充志*; Bae, S.*; Beer, G.*; Bunce, G.*; Choi, H.*; Choi, S.*; Chung, M.*; da Silva, W.*; Eidelman, S.*; Finger, M.*; et al.
Progress of Theoretical and Experimental Physics (Internet), 2019(5), p.053C02_1 - 053C02_22, 2019/05
被引用回数:156 パーセンタイル:99.31(Physics, Multidisciplinary)この論文はJ-PARCにおける、ミューオン異常磁気モーメント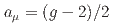 と電気双極子モーメント(EDM)
と電気双極子モーメント(EDM)  を測定する新しいアプローチを紹介する。我々の実験のゴールは、これまでと独立の、1/10の運動量と1/20のストレージリングを用いて、
を測定する新しいアプローチを紹介する。我々の実験のゴールは、これまでと独立の、1/10の運動量と1/20のストレージリングを用いて、 と
と をこれまでにない精密な磁場で測定することである。さらに過去の実験との顕著な違いは、1/1000の横エミッタンスミューオンビーム(サーマルミューオンビーム)を用い、効率的なソレノイドへ縦入射し、ミューオンからの崩壊陽電子をトラッキングし、その小さな運動量ベクトルを求める点である。
をこれまでにない精密な磁場で測定することである。さらに過去の実験との顕著な違いは、1/1000の横エミッタンスミューオンビーム(サーマルミューオンビーム)を用い、効率的なソレノイドへ縦入射し、ミューオンからの崩壊陽電子をトラッキングし、その小さな運動量ベクトルを求める点である。 は統計精度450ppb、系統誤差70ppb、EDMについては
は統計精度450ppb、系統誤差70ppb、EDMについては e
e cmの精度で測定することを目標とする。
cmの精度で測定することを目標とする。
 VFeAsO
VFeAsO studied by X-ray magnetic circular dichroism
studied by X-ray magnetic circular dichroism堀尾 眞史*; 竹田 幸治; 並木 宏允*; 片桐 隆雄*; 若林 勇希*; 坂本 祥哉*; 野中 洋亮*; 芝田 悟朗*; 池田 啓祐*; 斎藤 祐児; et al.
Journal of the Physical Society of Japan, 87(10), p.105001_1 - 105001_2, 2018/10
被引用回数:2 パーセンタイル:19.05(Physics, Multidisciplinary)We have performed X-ray magnetic circular dichroism (XMCD) measurements on the iron-based superconductor Sr VFeAsO
VFeAsO to study the origin of weak ferromagnetism (WFM) reported for this compound. While Fe 3d electrons show a magnetic response similar to the other iron pnictides, signals from V 3d electrons remain finite at zero magnetic field and may be responsible for the WFM.
to study the origin of weak ferromagnetism (WFM) reported for this compound. While Fe 3d electrons show a magnetic response similar to the other iron pnictides, signals from V 3d electrons remain finite at zero magnetic field and may be responsible for the WFM.
坂本 浩幸*; 赤木 洋介*; 山田 一夫*; 舘 幸男; 福田 大祐*; 石松 宏一*; 松田 樹也*; 齋藤 希*; 上村 実也*; 浪平 隆男*; et al.
日本原子力学会和文論文誌, 17(2), p.57 - 66, 2018/05
福島第一原子力発電所の事故によって放射性セシウムによって汚染されたコンクリート瓦礫が発生しており、さらに、将来の原子炉の廃止措置に伴って多量の放射性コンクリート廃棄物が生じることが想定される。床や壁等のフラットな表面の除染には既存技術が有効であるが、コンクリート瓦礫に対する除染技術の適用性については課題がある。本研究では、パルスパワー放電技術の適用性可能性に着目して、汚染コンクリートの骨材とセメントペーストへの分離と、それぞれの放射能測定による基礎的な試験と評価を実施した。試験結果より、汚染コンクリートの骨材とセメントペーストへの分離によって、放射性コンクリートの除染と減容が達成される可能性が示された。
 and their Zr-O surface modified electrodes
and their Zr-O surface modified electrodes阿部 真知子*; 射場 英紀*; 鈴木 耕太*; 南嶋 宏映*; 平山 雅章*; 田村 和久; 水木 純一郎*; 齋藤 智浩*; 幾原 雄一*; 菅野 了次*
Journal of Power Sources, 345, p.108 - 119, 2017/03
被引用回数:12 パーセンタイル:37.37(Chemistry, Physical)Ni, Co, Mn三元系リチウムイオン電池正極材料について、その劣化機構について、電気化学測定、X線・中性子線測定により調べた。実験の結果、Ni, Co, Mn三元系正極は、層状岩塩型構造とスピネル構造で構成されており、充放電を繰り返すと、充放電に関与しないスピネル構造が表面を覆っていくことが分かった。一方で、Zr-Oで表面をコートした材料は劣化しないことが知られており、その原因を調べた結果、層状岩塩型構造が安定に存在し続けていることが分かった。さらに、電極/溶液界面のLi濃度を上昇していることも分かった。
島田 紘行*; 南 寛威*; 奥泉 直人*; 佐久間 一郎*; 鵜飼 正敏*; 藤井 健太郎; 横谷 明徳; 福田 義博*; 斎藤 祐児
Journal of Chemical Physics, 142(17), p.175102_1 - 175102_9, 2015/05
被引用回数:12 パーセンタイル:42.27(Chemistry, Physical)X-ray absorption near edge structure (XANES) was measured at energies around the N K-edge of the pyrimidine-containing nucleotides cytidine 5'-monophosphate (CMP), 2'-deoxythymidine 5'-monophosphate (dTMP), and uridine 5'-monophosphate (UMP) in aqueous solutions and in dried films under various pH conditions. The features of resonant excitations below the N K-edge in the XANES spectra for CMP, dTMP, and UMP changed depending on the pH of the solutions. The spectral change thus observed is systematically explained by the chemical shift of the core-levels of N atoms in the nucleobase moieties caused by structural changes due to protonation or deprotonation at different proton concentrations. This interpretation is supported by the results of theoretical calculations using density functional theory for the corresponding nucleobases in the neutral and protonated or deprotonated forms.
島田 紘行*; 深尾 太志*; 南 寛威*; 鵜飼 正敏*; 藤井 健太郎; 横谷 明徳; 福田 義博*; 斎藤 祐児
Journal of Chemical Physics, 141(5), p.055102_1 - 055102_8, 2014/08
被引用回数:22 パーセンタイル:63.01(Chemistry, Physical)The N K-edge X-ray absorption near edge structure (XANES) spectra of the purine-containing nucleotide, guanosine 5'-monophosphate (GMP), in aqueous solution are measured under various pH conditions. The spectra show characteristic peaks, which originate from resonant excitations of N 1s electrons to 
 orbitals inside the guanine moiety of GMP. The relative intensities of these peaks depend on the pH values of the solution. The pH dependence is explained by the core-level shift of N atoms at specific sites caused by protonation and deprotonation. The experimental spectra are compared with theoretical spectra calculated by using density functional theory for GMP and the other purine-containing nucleotides, adenosine 5'-monophosphate, and adenosine 5'-triphosphate. The N K-edge XANES spectra for all of these nucleotides are classified by the numbers of N atoms with particular chemical bonding characteristics in the purine moiety.
orbitals inside the guanine moiety of GMP. The relative intensities of these peaks depend on the pH values of the solution. The pH dependence is explained by the core-level shift of N atoms at specific sites caused by protonation and deprotonation. The experimental spectra are compared with theoretical spectra calculated by using density functional theory for GMP and the other purine-containing nucleotides, adenosine 5'-monophosphate, and adenosine 5'-triphosphate. The N K-edge XANES spectra for all of these nucleotides are classified by the numbers of N atoms with particular chemical bonding characteristics in the purine moiety.
尾関 秀将; 濱田 一弥; 高橋 良和; 布谷 嘉彦; 河野 勝己; 押切 雅幸; 齊藤 徹; 手島 修*; 松並 正寛*
IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 24(3), p.4800604_1 - 4800604_4, 2014/06
被引用回数:16 パーセンタイル:60.26(Engineering, Electrical & Electronic)JAEA is in charge of procuring Center Solenoid (CS) conductor in ITER project. CS conductor is Cable-In-Conduit type, and conduit is also called jacket. The cross-sectional shape of CS jacket is circle-in-square type, whose outer dimension is 51.3 mm and inner diameter is 35.3 mm. The length of one CS jacket section is 7 m, and the necessary total length of CS conductor is about 43 km. CS coil is expected to suffer high electro-magnetic force, so JAEA developed JK2LB, which is modified stainless steel expected to better characteristics of fatigue and thermal contraction in 4 K than SUS316LN, in cooperate with Kobe Steel, Ltd. The remaining problem was to establish production process of jackets which satisfy dimensional and mechanical requirement in ITER consistently, and also, Non-Destructive Examination (NDE) by ITER-original criteria. To carry out the R&D for above, production of dummy CS jackets were executed and these jackets were fabricated successfully. The results are reported.