Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
片山 芳則; 稲村 泰弘*
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 238(1-4), p.154 - 159, 2005/08
被引用回数:8 パーセンタイル:52.01(Instruments & Instrumentation)多くの物質が結晶状態で異なった構造を持ち、圧力の変化によって一次の構造相転移を起こすことはよく知られている。一方、液体やガラスの状態では、圧力誘起構造変化は単調であると考えられてきた。最近の放射光光源の発達によって、高温高圧条件下における液体やガラスの構造研究を行うことが可能になった。これらの研究は、液体やガラス状態での変化が必ずしも単調でないことを明らかにした。われわれは、液体リンと石英ガラスの最近の結果について報告する。
坂場 成昭; 橘 幸男; 中川 繁昭; 濱本 真平
Transactions of 18th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology (SMiRT-18), p.4499 - 4511, 2005/08
高温ガス炉固有の安全性を定量的に実証するため、HTTRを用いた安全性実証試験が行われている。安全性実証試験による成果は、将来高温ガス炉及び第四世代原子炉システムの候補の一つであるVHTRの経済性の向上につながることが期待されている。安全性実証試験の一つとして実施されている冷却材流量の部分喪失を模擬した循環機停止試験では、温度及び冷却材であるヘリウム中の不純物組成が過渡状態となる。そこで、循環機停止試験における、温度及びヘリウム中の化学組成の実測値をもとに、1次系の主要な機器である、高温二重管,1次加圧水冷却器等の健全性を評価した。温度変化に基づく応力評価及び化学組成変化による炭素析出の評価の結果、原子炉出力100%からの試験における1次系主要機器の健全性が確認された。
 resolution
resolution茶竹 俊行*; 栗原 和男; 田中 伊知朗*; Tsyba, I.*; Bau, R.*; Jenney, F. E. Jr.*; Adams, M. W. W.*; 新村 信雄
Acta Crystallographica Section D, 60(8), p.1364 - 1373, 2004/08
被引用回数:34 パーセンタイル:88.49(Biochemical Research Methods)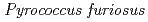 由来ルブレドキシンの高い熱安定性の起源を明らかにするため、その変異型に対する1.6
由来ルブレドキシンの高い熱安定性の起源を明らかにするため、その変異型に対する1.6 分解能中性子結晶構造解析(重水中で結晶育成)を生体高分子用中性子回折装置BIX-3(原研原子炉JRR-3内設置)を用いて行った。
分解能中性子結晶構造解析(重水中で結晶育成)を生体高分子用中性子回折装置BIX-3(原研原子炉JRR-3内設置)を用いて行った。 由来ルブレドキシンは、通常の熱安定性を持つ常温菌由来のルブレドキシンと異なるアミノ酸残基部分を持つ。そこで、その中で重要と考えられる3つの残基を常温菌のものに変えた変異型を発現させ、その水素結合パターンを変異の無い野生型と比較した。その結果、変異を行った残基の一つで水素結合パターンの違いが明らかになった。これをもとに熱安定性の議論を行った。一方で、このタンパク質の水素/重水素置換率の詳細も調べた。その結果、ルブレドキシンの鉄-硫黄中心(酸化還元機能を司る)にかかわる4つのシステイン残基周辺は、最も水素/重水素置換が進んでいないということがわかった。これはこの周囲の構造が安定であることを示唆している。加えて、この高分解能な中性子構造解析により、水和水の秩序性も含めた詳細な水和構造が明らかになった。
由来ルブレドキシンは、通常の熱安定性を持つ常温菌由来のルブレドキシンと異なるアミノ酸残基部分を持つ。そこで、その中で重要と考えられる3つの残基を常温菌のものに変えた変異型を発現させ、その水素結合パターンを変異の無い野生型と比較した。その結果、変異を行った残基の一つで水素結合パターンの違いが明らかになった。これをもとに熱安定性の議論を行った。一方で、このタンパク質の水素/重水素置換率の詳細も調べた。その結果、ルブレドキシンの鉄-硫黄中心(酸化還元機能を司る)にかかわる4つのシステイン残基周辺は、最も水素/重水素置換が進んでいないということがわかった。これはこの周囲の構造が安定であることを示唆している。加えて、この高分解能な中性子構造解析により、水和水の秩序性も含めた詳細な水和構造が明らかになった。
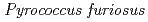 by BIX-3, a single-crystal diffractometer for biomacromolecules
by BIX-3, a single-crystal diffractometer for biomacromolecules栗原 和男; 田中 伊知朗*; 茶竹 俊行*; Adams, M. W. W.*; Jenney, F. E. Jr.*; Moiseeva, N.*; Bau, R.*; 新村 信雄
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(31), p.11215 - 11220, 2004/08
被引用回数:48 パーセンタイル:60.08(Multidisciplinary Sciences)原研原子炉JRR-3設置の生体高分子用中性子回折装置BIX-3を用いて、高い熱安定性を持つ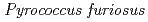 由来ルブレドキシンの中性子結晶構造解析を行った。結晶化はH原子からのバックグラウンドを抑えるため重水中で行った。回折実験は常温で行い、1.5
由来ルブレドキシンの中性子結晶構造解析を行った。結晶化はH原子からのバックグラウンドを抑えるため重水中で行った。回折実験は常温で行い、1.5 分解能でデータ収率81.9%を得た。立体構造モデルの精密化では、306個のH原子と50個のD原子及び37個の水和水を同定した。その結果、モデルの信頼性を示す
分解能でデータ収率81.9%を得た。立体構造モデルの精密化では、306個のH原子と50個のD原子及び37個の水和水を同定した。その結果、モデルの信頼性を示す 因子及び
因子及び
 因子は最終的に各々18.6%, 21.7%となった。この中性子解析により、X線解析では明確でなかったアミノ酸側鎖のO-D結合の方位を明らかにできた。また、主鎖のN-H結合のH原子は多くがD原子に置換されている一方で、その中で5つのH原子は置換されずに保たれていることがわかった。これはその周囲の高い構造安定性を示す。さらに中性子散乱密度図では、このタンパク質の高い熱安定性に寄与していると考えられているND
因子は最終的に各々18.6%, 21.7%となった。この中性子解析により、X線解析では明確でなかったアミノ酸側鎖のO-D結合の方位を明らかにできた。また、主鎖のN-H結合のH原子は多くがD原子に置換されている一方で、その中で5つのH原子は置換されずに保たれていることがわかった。これはその周囲の高い構造安定性を示す。さらに中性子散乱密度図では、このタンパク質の高い熱安定性に寄与していると考えられているND
 末端のその周囲に広がる水素結合ネットワークを詳細に明らかにすることができた。
末端のその周囲に広がる水素結合ネットワークを詳細に明らかにすることができた。
竹田 武司; 橘 幸男; 中川 繁昭
JAERI-Tech 2002-091, 45 Pages, 2002/12
HTTR(高温工学試験研究炉)の中間熱交換器(IHX)は、ヘリウム/ヘリウムの熱交換器であり、高温ガス炉の核熱利用を将来実証するうえで重要な機器である。IHXの熱容量は10MWであり、ヘリカルコイル状の伝熱管を96本有している。IHXの構造設計では、内部構造物のうち、ハステロイXR材である伝熱管,内筒等に対して弾クリープ解析を実施している。HTTRの出力上昇試験の中で、原子炉スクラム時におけるIHX内の冷却材温度変化は設計時の想定より早いことがわかった。そこで、出力上昇試験で得られた冷却材温度データに基づき、想定した高温試験運転で全出力(30MW)からの原子炉スクラム時の冷却材温度変化が、IHXの伝熱管,内筒下部レジューサの構造強度に及ぼす影響について調べた。その結果、寿命期間中(10 h)の累積クリープ主ひずみ,累積クリープ疲れ損傷係数は、「高温ガス炉第1種機器の高温構造設計指針」に定められた制限値を満足していることを確認した。
h)の累積クリープ主ひずみ,累積クリープ疲れ損傷係数は、「高温ガス炉第1種機器の高温構造設計指針」に定められた制限値を満足していることを確認した。
寺崎 英紀*; 加藤 工*; 浦川 啓*; 舟越 賢一*; 佐藤 公則*; 鈴木 昭夫*; 岡田 卓
Geophysical Research Letters, 29(8), p.68_1 - 68_3, 2002/05
高圧下における溶融純鉄の粘性その場測定を、X線影像落球法によりおこなった。約2000Kにおける粘性係数は、2.7-5.0GPaでは15-24mPa sであり、5.0-7.0GPaでは4-9mPa sであった。粘性係数の急激な減少が5GPa付近で観察された、この圧力条件では融点直下における安定固相はデルタ相(bcc)からガンマ相(fcc)に変化する。今回得られた結果は、溶融鉄の構造変化が固相の相転移と近い圧力条件において、狭い圧力幅(1GPa)で起こる可能性を示唆している。
栗原 和男; 田中 伊知朗; Adams, M. W. W.*; Jenney, F. E. Jr.*; Moiseeva, N.*; Bau, R.*; 新村 信雄
Journal of the Physical Society of Japan, Vol.70, Supplement A, p.400 - 402, 2001/05
生体物質中性子回折装置BIX-3(日本原子力研究所JRR-3M 1Gサイト)を用いてルブレドキシン(超好熱菌由来、分子量約6,000、鉄-硫黄タンパク質)の中性子構造解析を現在行っている。このタンパク質は熱安定性が高く、その安定性と立体構造の関係が注目されている。今回用いた結晶の大きさは2.0 2.0
2.0 1.0 mmであった。データはステップスキャン法で測定し、ステップ間隔は
1.0 mmであった。データはステップスキャン法で測定し、ステップ間隔は 軸の周り0.3°とした。露出時間は1フレームにつき約60-77分であり、全体では正味約35日間測定を行った。この回折測定では、d=1.5Å付近まで(コンプリートネスは76.8%)回折点を検出することができた。構造の精密化では301個の水素原子を含めた。現在のところ、分解能=1.5ÅでR因子=24.0%, R-free因子=26.3%である。また40個の重水素原子と29個の水和水を決定している。
軸の周り0.3°とした。露出時間は1フレームにつき約60-77分であり、全体では正味約35日間測定を行った。この回折測定では、d=1.5Å付近まで(コンプリートネスは76.8%)回折点を検出することができた。構造の精密化では301個の水素原子を含めた。現在のところ、分解能=1.5ÅでR因子=24.0%, R-free因子=26.3%である。また40個の重水素原子と29個の水和水を決定している。
羽田 一彦; 西口 磯春; 武藤 康; 辻 宏和
Nucl. Eng. Des., 132, p.1 - 11, 1991/00
被引用回数:25 パーセンタイル:90.43(Nuclear Science & Technology)高温工学試験研究炉(HTTR)においては、第1種機器はヘリウム雰囲気下で通常運転時の最高温度が900 Cを超えることがあり、また、制御棒は原子炉スクラム時に約900
Cを超えることがあり、また、制御棒は原子炉スクラム時に約900 Cまで加熱される。超高温で使用する第1種機器用材料としてはニッケル基耐熱超合金のハステロイXRを開発し、また、制御棒用材料としては耐照射性を考慮し鉄基耐熱超合金のアロイ800Hを選定した。上記超合金のHTTRにおける使用条件は、LMFBRに適用する高温構造設計方針の適用範囲を超えているため、新たに高温構造設計方針を開発することが是非とも必要である。また、超高温ではクリープが非常に顕著に生ずるため、構造解析法としてクリープ解析法が必要になる。本論文は、上記超合金の選定・開発並びに高温構造設計方針及びクリープ解析法の開発成果を述べたものである。
Cまで加熱される。超高温で使用する第1種機器用材料としてはニッケル基耐熱超合金のハステロイXRを開発し、また、制御棒用材料としては耐照射性を考慮し鉄基耐熱超合金のアロイ800Hを選定した。上記超合金のHTTRにおける使用条件は、LMFBRに適用する高温構造設計方針の適用範囲を超えているため、新たに高温構造設計方針を開発することが是非とも必要である。また、超高温ではクリープが非常に顕著に生ずるため、構造解析法としてクリープ解析法が必要になる。本論文は、上記超合金の選定・開発並びに高温構造設計方針及びクリープ解析法の開発成果を述べたものである。
橘 幸男
no journal, ,
日本原子力研究開発機構は、これまで実施してきた研究開発成果に基づき、国内実証炉開発を開始した。本講演では、高温ガス炉プロジェクトの概要、HTTR高温機器の材料及び使用条件、特に、中間熱交換器及びハステロイXRの開発を中心として発表するとともに、高温ガス炉第1種機器の高温構造設計指針を紹介する。さらに、今後の課題について述べる。