Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
中村 一男*; 松藤 伸治*; 友田 誠志*; Wang, F.*; 御手洗 修*; 栗原 研一; 川俣 陽一; 末岡 通治; 佐藤 浩之助*; 図子 秀樹*; et al.
no journal, ,
JT-60で開発したプラズマ最外殻磁気面の同定法であるコーシー条件面(CCS)法は、穴の開いた特異性のある真空場の厳密解を基本とし、電磁気センサー信号を用いて精度よくプラズマの断面形状を同定できる。このCCS法を九州大学で計画されている球状トカマク装置(ST)のプラズマ平衡実時間制御へ適用し高精度に再構築することを確認した。これまではCCS法における観測方程式に最小自乗法を用いてきたが、ここでは、係数マトリクスを特異値分解し特異値の大きな成分から順に一般逆行列を求めた。また、真空容器に流れる渦電流の寄与がある場合の最小自乗法,特異値分解法を含む一般逆行列の特徴も比較した。本発表は、一連の検討結果報告である。
春日井 敦; 梶原 健; 高橋 幸司; 小田 靖久; 小林 則幸; 坂本 慶司
no journal, ,
原子力機構では、ITER用170GHzジャイロトロンの開発において、出力1MW,パルス幅500秒,エネルギー変換効率50%の開発目標値を上回る1MW-800秒-55%の性能を達成した。本成果によりジャイロトロンの開発ミッションを世界に先駆けて達成した。これは発振を維持しつつ共振器磁場強度を変化させる積極的なパラメータ制御を行う先進運転方法によって、高効率が期待できる難発振領域に安定に移行できたことによるものである。この先進運転方法を応用し、0.8MWの出力で2000秒間の動作や、数秒間で0.8MW出力を立ち上げる手法を確立した。さらにITER用ジャイロトロン調達に向けた、5kHzの出力変調化や、一層の出力向上へ向けた発振モードの高次化などのITER用ジャイロトロンの高性能化の検討と実験を行っている。
森山 伸一; 小林 貴之; 横倉 賢治; 下野 貢; 長谷川 浩一; 澤畠 正之; 寺門 正之; 五十嵐 浩一; 和田 健次; 藤井 常幸
no journal, ,
JT-60U電子サイクロトロン加熱装置のジャイロトロンにおいて、1秒以上のパルス幅では世界初となる1.5MWの高パワー発振に成功している。1-1.5MW出力時のジャイロトロン各部の温度分布測定を行って、運転可能領域を評価するための試験を実施した。キャビティ温度の飽和時間は出力1MW以上の場合、1秒以下であった。1.5MW 1秒間出力時の温度上昇は120 C(到達温度140
C(到達温度140 C)と冷却水(3-5atm)の沸点を下回っており、さらにパルス幅を伸ばしても、キャビティ温度に関しては問題ないと考えられる。一方、コレクタ温度分布測定では、1.44MW, 1秒間において最高温度が100
C)と冷却水(3-5atm)の沸点を下回っており、さらにパルス幅を伸ばしても、キャビティ温度に関しては問題ないと考えられる。一方、コレクタ温度分布測定では、1.44MW, 1秒間において最高温度が100 Cを大きく上回らないと推測できるデータが得られた。コレクタ周方向の温度の偏差は25%以下であった。また、1-1.5MWの範囲でコレクタ温度と出力RFパワーの相関は小さかった。これは、定格の1MWを超えてもなお、大出力になるほど効率が高くなる(
Cを大きく上回らないと推測できるデータが得られた。コレクタ周方向の温度の偏差は25%以下であった。また、1-1.5MWの範囲でコレクタ温度と出力RFパワーの相関は小さかった。これは、定格の1MWを超えてもなお、大出力になるほど効率が高くなる( 45%)傾向に起因すると考えられる。長パルス技術の開発においてはアノード、ヒーター制御を用いて0.5MW, 30秒をプラズマに入射し、伝送系の健全性を評価した。
45%)傾向に起因すると考えられる。長パルス技術の開発においてはアノード、ヒーター制御を用いて0.5MW, 30秒をプラズマに入射し、伝送系の健全性を評価した。
小林 貴之; 森山 伸一; 横倉 賢治; 長谷川 浩一; 鈴木 貞明; 平内 慎一; 佐藤 文明; 鈴木 高志; 和田 健次; 藤井 常幸
no journal, ,
電子サイクロトロン加熱(ECH)装置の高出力・長パルス化に対応するため、信頼性の高い冷却・駆動・排気機構を持つ伝送・結合系の開発が重要である。現在、直線駆動のみによりミリ波のポロイダル入射角度( )を制御し、冷却・駆動機構の信頼性を高めた結合系の検討を進めている。電子サイクロトロン波による電流駆動と電子加熱を効率的に行うには、目的に応じてトロイダル入射角(
)を制御し、冷却・駆動機構の信頼性を高めた結合系の検討を進めている。電子サイクロトロン波による電流駆動と電子加熱を効率的に行うには、目的に応じてトロイダル入射角( )を制御することが求められるため、本方式で可能な
)を制御することが求められるため、本方式で可能な の範囲についてミリ波伝送の観点から検討した。本方式の特徴として、
の範囲についてミリ波伝送の観点から検討した。本方式の特徴として、 に応じて直線可動鏡での反射位置がポートの奥行き方向へ変化するため、ポートサイズ制限と曲面鏡曲率により、
に応じて直線可動鏡での反射位置がポートの奥行き方向へ変化するため、ポートサイズ制限と曲面鏡曲率により、 が小さい場合は
が小さい場合は の範囲に制限を受ける。JT-60U ECHポートを仮定したポート内でのミリ波伝送計算によりポート出口でのRF強度分布を調べた結果、
の範囲に制限を受ける。JT-60U ECHポートを仮定したポート内でのミリ波伝送計算によりポート出口でのRF強度分布を調べた結果、 =0
=0 の中心入射の場合においても0
の中心入射の場合においても0


 20
20 が可能であることがわかった。これにより、トカマク実験に有効な範囲でトロイダル入射角度を振ることが、本アンテナ方式で可能であることをミリ波伝送の観点から示した。
が可能であることがわかった。これにより、トカマク実験に有効な範囲でトロイダル入射角度を振ることが、本アンテナ方式で可能であることをミリ波伝送の観点から示した。
梶原 健; 高橋 幸司; 小林 則幸; 小田 靖久; 春日井 敦; 坂本 慶司
no journal, ,
原子力機構においては、調達予定のITER電子サイクロトロン加熱/電流駆動用水平ポートランチャーの開発を行っており、20MWの電子サイクロトロン波のトロイダル入射角を20度から40度まで掃引可能なランチャーを設計している。ランチャーには十分な中性子遮蔽性を有し、ランチャー内で発生する不要電磁波が最小になるよう設計することが求められ、これらを満たすためには中性子を遮断する隔壁の狭い隙間を通して電磁波をプラズマ中に入射する必要がある。狭い空間に、電磁波ビームの束を集めるため、電磁波を集光するミラーが必要であり、その集光ミラーの形状の最適化等を行った。この最適化設計をもとにランチャーモックアップの製作を行った。モックアップは実機と同じサイズで8本の電磁波ビームラインを有しておりそのうち一本は実際に高パワー(1MW)連続の電磁波の伝送試験ができるように、コルゲート導波管、及び、冷却構造が採用されている。今後ジャイロトロンを用いたランチャーモックアップの高パワー試験を行う予定である。
神藤 勝啓; Vermare, C.*; 杉本 昌義; Garin, P.*; 前原 直; Mosnier, A.*
no journal, ,
During 6 years of IFMIF/EVEDA project, design, construction, operation and dismantle of a prototype accelerator as an engineering validation activity and an accelerator engineering design activity for IFMIF including the interfaces with the Li loop target system and the material irradiation test facilities will be performed. The prototype accelerator consists of a 100 keV injector equipped with an ECR ion source, a radio-frequency quadrupole (RFQ) linac accelerating the beam up to 5 MeV, the first section of the drift tube linac (DTL) accelerating the beam up to 9 MeV, a beam diagnostic system, RF high power sources and subsystems. Most of the accelerator components are provided by European institutions (CEA/Saclay, CIEMAT, INFN, etc.), while the RF couplers for the RFQ linac, the supervision of the accelerator control system and the accelerator prototype building constructed at Rokkasho BA site for the beam tests are provided by JAEA. The R&D activities and the future schedule of the prototype accelerator of the IFMIF/EVEDA project will be presented.
安堂 正己; 谷川 博康; 若井 栄一
no journal, ,
低放射化フェライト鋼F82H鋼は、核融合炉の第一壁構造材料として開発が進められており、照射特性評価については米国HFIR炉を用い、重照射データの取得が進行中である。一方、これまでに取得されたデータの信頼性を高めるために、イオン照射実験から得られる硬化挙動・ミクロ組織変化評価からの硬化予測によるデータ補間の努力が一層必要となってくると考えられる。本研究では、これまでにF82H鋼を中心として実施した、イオン照射材からの照射硬化挙動、中性子照射材による引張試験・ビッカース硬さ試験の結果より、高照射量での硬化挙動についての予測を行った。その結果、10dpaまでの中性子照射材から得られたF82H鋼のビッカース硬さ(VH)及び微小引張試験の結果から、降伏応力(
 )は以下の近似式で求められる。
)は以下の近似式で求められる。
 =3.2
=3.2 3.4
3.4 VH
VH (0.1)
(0.1) 、ただしnは加工硬化指数。この結果と、未照射材から得た微小硬さとビッカース硬さからの相関近似式によって得られた降伏応力の見積り結果とは比較的よく一致する傾向にあった。これらの結果と、ミクロ組織から降伏応力変化量を見積もった場合についても報告する予定である。
、ただしnは加工硬化指数。この結果と、未照射材から得た微小硬さとビッカース硬さからの相関近似式によって得られた降伏応力の見積り結果とは比較的よく一致する傾向にあった。これらの結果と、ミクロ組織から降伏応力変化量を見積もった場合についても報告する予定である。
久保 隆司; 奥村 義和; 大平 茂; 前原 直; 榊 泰直; 大西 世紀; 米本 和浩; 小島 敏行; Garin, P.*; 杉本 昌義; et al.
no journal, ,
IFMIF/EVEDAのうち加速器系の工学実証試験を行う加速器試験建家は、青森県六ヶ所村に開設されるBAサイト内に建設される。実施設計及び建設工事に先立ち、日欧協議により合意した基本設計に基づく調達取決めを日欧の実施機関間で結んでいる。実施設計は平成19年度に行い、平成20年度から建設工事を開始する。加速器試験建家は、東西約58m,南北約37m,延床面積約2,020m の規模である。建家内の配置は、南北の中央に加速器室があり、その北側に高周波源及び電源関係を、南側に給排気設備及び冷却水設備を配置している。制御室を含むユーティリティ関係は建家の北西側にまとめている。遮蔽設計は、日欧の専門家による評価に基づいて行っている。IFMIF/EVEDAで試験する加速器は、重陽子を125mA, 10MeV程度まで加速する計画であり、発生する放射線遮蔽のために、加速器室は厚さ1.5mの普通コンクリートの遮蔽体で覆われている。また、中性子のストリーミング防止のために、高周波導波管は地下ピットを、給排気ダクトは加速器室上部に設けた迷路を経由して加速器室内に引き込まれる。冷却水配管は壁貫通としている。
の規模である。建家内の配置は、南北の中央に加速器室があり、その北側に高周波源及び電源関係を、南側に給排気設備及び冷却水設備を配置している。制御室を含むユーティリティ関係は建家の北西側にまとめている。遮蔽設計は、日欧の専門家による評価に基づいて行っている。IFMIF/EVEDAで試験する加速器は、重陽子を125mA, 10MeV程度まで加速する計画であり、発生する放射線遮蔽のために、加速器室は厚さ1.5mの普通コンクリートの遮蔽体で覆われている。また、中性子のストリーミング防止のために、高周波導波管は地下ピットを、給排気ダクトは加速器室上部に設けた迷路を経由して加速器室内に引き込まれる。冷却水配管は壁貫通としている。
沓掛 忠三; 田中 滋; 阿部 雄一; 川辺 勝*; 鈴木 卓美; 山田 正行; 山西 敏彦; 今野 力
no journal, ,
原子力機構トリチウムプロセス研究棟で、核融合中性子工学用中性子源(FNS)の小型トリチウムターゲットの自主製作に成功した。トリチウムターゲットは銅基盤にチタンを蒸着し、そのチタンにトリチウムを吸蔵させたもので、製作上の課題は、チタン活性化表面の良好な状態の確保,トリチウム吸蔵条件の確立及び取扱い上安全な装置の開発にあった。トリチウムを吸蔵させるチタン金属は酸素に対して活性で、すぐに酸化膜ができてしまい、トリチウムを十分に吸蔵しない。そこで、アルゴン放電洗浄でチタン表面の酸化皮膜を除去し、チタン表面を活性化させてからトリチウム吸蔵工程を行った。製作したターゲットのトリチウム吸蔵量は約400GBqで、FNS加速器の重陽子ビーム照射によるDT中性子の発生量は約1.7 10
10 n/秒/mAで中性子発生率の減衰も少なく、極めて良好な中性子発生特性であることを確認した。
n/秒/mAで中性子発生率の減衰も少なく、極めて良好な中性子発生特性であることを確認した。
佐藤 和義; 大森 順次; 近藤 貴; 波多江 仰紀; 梶田 信*; 石川 正男; 草間 義紀; 閨谷 譲; 海老沢 克之*
no journal, ,
ITERの計測装置は、中性子遮蔽構造を兼ね備えたポートプラグと呼ばれる構造体に組み込まれる。上部ポートプラグは長さ約6m、重量約20tの片持ち構造であるため、構造健全性を評価することは必須である。このため、ディスラプション時における電磁力解析結果をもとに三次元モデルを用いて変位及び応力を評価した。ポートプラグ先端に荷重を与え静解析により変位量を求めたところ、最大変位約9mmが得られた。これはポートとの隙間20mmに対して製作・組立誤差を考慮すると設計裕度は5 6mmとなるが、動的拡大係数(DAF)は含まれていない。遮蔽ブランケットのDAFが1.5であることを考慮すると変位をさらに抑制する必要がある。このため、ブランケット遮蔽モジュール先端にスリットを3本設け電磁力の低減を図ったところ、変位量は約5mmと低減できることがわかった。一方応力はマニフォールドと側板接続部、フランジ付け根部で高い応力が発生し、最大値は230MPaである。同部位は、接続形状の変更や補強構造を設けることにより、発生応力を相当低減することが可能である。以上の結果から、ポートプラグは応力上の問題はなく、変位抑制対策を取ることで健全性を確保できる見通しを得た。
6mmとなるが、動的拡大係数(DAF)は含まれていない。遮蔽ブランケットのDAFが1.5であることを考慮すると変位をさらに抑制する必要がある。このため、ブランケット遮蔽モジュール先端にスリットを3本設け電磁力の低減を図ったところ、変位量は約5mmと低減できることがわかった。一方応力はマニフォールドと側板接続部、フランジ付け根部で高い応力が発生し、最大値は230MPaである。同部位は、接続形状の変更や補強構造を設けることにより、発生応力を相当低減することが可能である。以上の結果から、ポートプラグは応力上の問題はなく、変位抑制対策を取ることで健全性を確保できる見通しを得た。
山西 敏彦; 林 巧; 河村 繕範; 中村 博文; 岩井 保則; 小林 和容; 磯部 兼嗣; 山田 正行
no journal, ,
BA活動において、日本とEUの学術的に強い共通理解により、核融合原型炉に向けたトリチウム工学に関する課題として、トリチウム計量管理(マイクロGC,連続水モニター,カロリーメータ等),材料(先進増殖材・増倍材、先進構造材料)とトリチウムの相互作用,トリチウム耐久性(高分子材料の耐放射線性)に関する基礎的研究が行われる。またそのために、青森県六ヶ所に、トリチウム及びその他放射性物質の取り扱いが可能な多目的RI施設を整備する(トリチウム取り扱い量:3.7TBq/日,トリチウム貯蔵量:7.4TBq,その他
 核種の取り扱い)。上記トリチウム研究課題の概要と研究スケジュール,現在設計が進められている多目的RI施設の状況を紹介する。
核種の取り扱い)。上記トリチウム研究課題の概要と研究スケジュール,現在設計が進められている多目的RI施設の状況を紹介する。
岡野 文範; 三代 康彦; 西山 友和; 佐藤 洋司; 佐々木 昇*; 及川 晃; 酒井 俊也; 佐藤 正泰
no journal, ,
原子力機構では、JT-60U(臨界プラズマ試験装置)を超伝導トカマクに改造するJT-60SA計画によりJT-60U装置を解体する。JT-60Uの機器及び構造物は、重水素反応により発生する中性子により放射化しているとともに、滞留トリチウムにより真空容器内面とそれに通ずる真空機器の内面が汚染している。このため、解体作業は、放射線安全を考慮して行う必要がある。特に、本体室の複数の箇所で、空気汚染を伴う放射化物を溶断するため、汚染及び被曝の低減は、放射線防護上重要である。そのため、「空気汚染を伴う作業」と「伴わない作業」を区分する(作業区分)とともに、本体室を「空気汚染を伴う切断等の作業エリア」と「空気汚染を伴わない作業エリア」に区分(エリア区分)する。空気汚染を伴う切断等の作業は広範囲に設定した作業エリアにて可能な限り同時期に行うことを基本とし、グリーンハウス等を用い、負圧維持の下で養生を行う。解体手順は、はじめに計測装置・加熱装置(NBI, RF)や本体周辺設備(冷却系,ガス循環系等)を撤去し、本体周辺にグリーンハウス等のスペースを確保してから本体装置の解体を行う。本体装置は、上部にある構造物から解体し、トロイダル磁場コイル(TFC),ポロイダル磁場コイル(PFC),真空容器(VV)の順に解体する。これらのTFC, PFC及びVVの解体では、装置の構造が複雑かつ狭隘であるため、ダイヤモンドワイヤソー等の特殊な技術を用いて切断作業を行う。
相羽 信行; 徳田 伸二; 大山 直幸; 小関 隆久; 古川 勝*
no journal, ,
ITER等の大型トカマク装置において、高閉じこめ運転モードでの高い周辺閉じこめ性能の維持としばしば発生するType-Iエッジローカライズモード(ELM)の安定化・小振幅化は重要な課題である。このType-I ELMの安定化・小振幅化に対してプラズマ回転が重要な役割を持つことがJT-60Uにおいて観測されているが、その物理機構については十分な理解が得られておらず、理論・数値解析による解析が求められている。本研究ではType-I ELMの原因である周辺局在MHDモードの安定性に対するプラズマのトロイダル回転の影響を数値解析し、実験的に観測されているELM現象とプラズマ回転との相関についての理解を深めることを目的としている。そのために、線形初期値問題安定性解析コードMINERVAを開発し、同コードを用いて周辺MHD安定性に対するトロイダル回転の影響を定量的に評価した。その結果、プラズマ回転により周辺MHDモードが安定化され、Type-I ELMに相当するMHDモードが不安定化しにくくなることを確認した。
末岡 通治; 戸塚 俊之; 関 暁之; 川俣 陽一; 栗原 研一
no journal, ,
遠隔地から実験運転に参加する研究者にとって、プラズマ映像をライヴで観察できることは不可欠である。高解像度のプラズマ映像(2映像+1音声)を映像情報としてWEB回線でライヴ配信することを目指し、通信環境との整合のとれた方式の市場の動向を注視しているところである。今回、JT-60のプラズマ映像の中に含まれるプラズマ断面映像はCGであることから、JAVA言語を用いた実時間映像配信を提案する。リフレクティブメモリを介して受信した「プラズマ最外殻磁気面座標(数値)データ」をプログラムを用いてWEB回線でライヴ配信する。利用者は、専用JAVAアプリケーションにて受信し、パソコン上で転送劣化のないプラズマ断面CGを観察することができる。この結果を踏まえ、遠隔実験に向けた実時間映像データ配信技術の現状と展望について報告する。
白石 淳也; 徳田 伸二; 相羽 信行
no journal, ,
高性能定常プラズマの研究において、MHD摂動と外部系(安定化板等)とが相互作用する現象[特に抵抗性壁モード(RWM: Resistive Wall Mode)]の解析が重要な課題となっている。本研究では、理想MHD安定性解析コードMARG2Dを拡張し、RWM解析コード(RWMaC: RWM analysis Code)を開発することを目的とする。プラズマの慣性が無視できる場合、RWMの安定性はエネルギー汎関数を用いて解析することができる。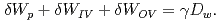
 はプラズマのポテンシャルエネルギー、
はプラズマのポテンシャルエネルギー、 は内部(外部)真空における磁気エネルギー、
は内部(外部)真空における磁気エネルギー、 はRWMの成長率/減衰率、
はRWMの成長率/減衰率、 は抵抗壁において散逸されるエネルギーである。
は抵抗壁において散逸されるエネルギーである。 はMARG2Dにより計算することができる。本研究では
はMARG2Dにより計算することができる。本研究では 及び
及び を計算するモジュールを開発し、MARG2Dに組み込んでRWMaCを開発した。不安定なRWMによって抵抗性壁上に誘起される渦電流パターンがNMA(Normal Mode Approach)コードの結果と一致することを確かめた。RWMaCにより、プラズマ内部のモード構造解析が可能となる。
を計算するモジュールを開発し、MARG2Dに組み込んでRWMaCを開発した。不安定なRWMによって抵抗性壁上に誘起される渦電流パターンがNMA(Normal Mode Approach)コードの結果と一致することを確かめた。RWMaCにより、プラズマ内部のモード構造解析が可能となる。
今野 力; 佐藤 聡; 落合 謙太郎; 高倉 耕祐; 大西 世紀; 飯田 浩正; 和田 政行*
no journal, ,
2004年に公開された核データライブラリーFENDL-2.1は、当時公開されていた核データライブラリーENDF/B-VI.8, JENDL-3.2, JENDL-3.3, JENDL Fusion File, JEFF-3.0, Brond-2.0の中から核種ごとに最も良いものを選び出した核データライブラリーで、ITERを含め核融合炉の核設計に使われ良い結果を与えている。近年、核データライブラリーJEFF-3.1及びENDF/B-VII.0が新たに公開され、より精度の高い核解析を目指し、FENDLの次期バージョンのための核データライブラリーのセレクションが行われる可能性がある。そこで、原子力機構FNSでこれまでに実施してきたDT中性子を用いた核融合中性子工学積分実験(単純組成・単純形状実験,飛行時間法実験)をFENDL-2.1及び他の最新の核データライブラリーを用いて解析し、最新の核データライブラリーの精度検証を行った。本講演会では、鉄,ベリリウム,酸化リチウム、等の典型的な結果について報告する。
岩前 敦; 小川 宏明; 杉江 達夫; 草間 義紀; 河西 敏*; 勝沼 淳*; 武山 芸英*
no journal, ,
ITER計画において日本が調達予定のダイバータ不純物モニターの設計検討と試作光学系の性能評価について報告する。ダイバータプラズマからの紫外及び可視領域の発光は、不純物モニターの先端部光学系を介し、観測窓を通り集光光学系により結像され光ファイバーを通じて分光器に導入される。プラズマ近傍に位置する先端部光学系では、 線,中性子,高エネルギー粒子の照射を受けるため放射線耐性の金属ミラー(Mo, Al)を用い、これらミラーは核発熱除熱用の冷却路つき保持機構に取り付けられる。金属ミラー,集光光学系カセグレン望遠鏡,マイクロレンズアレイ(MLA),光ファイバー分配器を試作した。ITERの実機規模に光学系を配置し、結像特性,空間分解能,感度等を調べた。MLAにより磁力線方向に観測視野を広げ、検出光量を増加したことにより、集光効率はファイバー単体に比べて最大3.3倍となった。衝突輻射モデルを用いてダイバータプラズマの不純物発光線強度を評価した。計算により得られた炭素イオンの発光線C IV(581nm)の視線積分発光強度は、強度の高い一部の視線においては計測可能と推定される。
線,中性子,高エネルギー粒子の照射を受けるため放射線耐性の金属ミラー(Mo, Al)を用い、これらミラーは核発熱除熱用の冷却路つき保持機構に取り付けられる。金属ミラー,集光光学系カセグレン望遠鏡,マイクロレンズアレイ(MLA),光ファイバー分配器を試作した。ITERの実機規模に光学系を配置し、結像特性,空間分解能,感度等を調べた。MLAにより磁力線方向に観測視野を広げ、検出光量を増加したことにより、集光効率はファイバー単体に比べて最大3.3倍となった。衝突輻射モデルを用いてダイバータプラズマの不純物発光線強度を評価した。計算により得られた炭素イオンの発光線C IV(581nm)の視線積分発光強度は、強度の高い一部の視線においては計測可能と推定される。
荻原 寛之; 榎枝 幹男; 谷川 博康; 秋場 真人; 廣瀬 貴規
no journal, ,
ITER-テストブランケットモジュール(TBM)では、冷却材流路を内蔵する低放射化鋼製壁をベリリウム(Be)アーマで被覆した第一壁を採用する予定である。本報では、原子力機構において実施した熱間等方圧加圧法(HIP)による実機大TBM第一壁の製作実証試験及びBeアーマと低放射化鋼の接合試験結果について報告する。第一壁は、冷間及び熱間圧延により製作したF82H製矩形管及び板を曲げ加工後TIG溶接により組立てた後にHIP接合で一体化する製作方法を採用した。HIP熱履歴の最適化及び組立隙間の極小化等の対策により、第一壁構造体の寸法変化は、後工程での矯正が可能な範囲に抑制された。構造物に対する検査の結果、鋼の結晶粒は接合界面を跨いで形成されており、空隙等の接合欠陥がないことを確認した。また、BeとF82Hの異材接合試験では、接合界面にクロムを拡散障壁として用い、接合温度を最適化することで、接合強度低下の要因となるBeの鋼への拡散を抑制することに成功した。これらの成果により、工業的に施工可能な工程での第一壁の製作に見通しが得られた。
大西 世紀; 前原 直; 飯田 浩正; 山内 通則*; 榊 泰直; 佐藤 聡; 落合 謙太郎; 今野 力
no journal, ,
IFMIF/EVEDAで加速器の工学実証試験を行う9MeV, 125mA重陽子ビーム加速器では、加速器コンポーネント、ビームダンプでのビームロスにより多量の中性子が発生する。この中性子を遮へいするためのコンクリート壁厚さ、追加遮へい体の構造・厚さを決めるために詳細な遮へい評価を行った。計算コードにはMCNP5を、断面積ライブラリはFENDL-2.1を用いた。線源としては9MeV, 125mAの重陽子ビームがビームダンプ表面に一様に照射され、全ビームが停止すると仮定した場合の中性子源を用いた。また、現在の設計案に加えてビームダンプ開口径を 20cmから
20cmから 10cmに縮小した場合と、ビームダンプ遮へい水タンクを50cm延長した場合の評価も行った。計算の結果、加速器室側壁ビームダンプ最近接点での線量は0.6
10cmに縮小した場合と、ビームダンプ遮へい水タンクを50cm延長した場合の評価も行った。計算の結果、加速器室側壁ビームダンプ最近接点での線量は0.6 Sv/hとなり、常時立ち入り可の管理区域上限値(25
Sv/hとなり、常時立ち入り可の管理区域上限値(25 Sv/h)以下になっていることを確認した。また、ビームダンプ径縮小と水タンク延長により、それぞれ57%, 87%の線量低下が見られた。これらの結果より、加速器室の壁は厚さ150cmのコンクリートで十分であるということがわかった。
Sv/h)以下になっていることを確認した。また、ビームダンプ径縮小と水タンク延長により、それぞれ57%, 87%の線量低下が見られた。これらの結果より、加速器室の壁は厚さ150cmのコンクリートで十分であるということがわかった。
藤田 隆明; 神谷 健作; 小島 有志; 井口 春和*; 大山 直幸; 鈴木 隆博; 鎌田 裕
no journal, ,
JT-60Uでは、プラズマ周辺部の密度分布,電流分布の高空間分解能計測を目的として、リチウムビーム偏光計測装置の開発を進めている。プラズマ上方から入射したビームの発光を磁気面に沿う斜め下方向から観測することで高い空間分解能(約1cm)を得る。エタロン(透過幅 0.1nm)を用いてビーム発光のゼーマン分離の
0.1nm)を用いてビーム発光のゼーマン分離の 成分を抽出し、その円偏光成分と直線偏光成分の強度比から磁場のピッチ角を測定し電流分布を求める。口径50mmの電子ビーム加熱型イオン源を用いたビーム入射装置を開発し、テストスタンドにて、イオン源から6.5mの点(JT-60U設置時の測定点に相当)でエネルギー10keV,等価電流3mA,発散角0.2度の中性ビームを得て、偏光計測に必要な高輝度・低発散ビームを実現した。JT-60Uに移設後、ビーム発光強度分布から密度分布を計測するとともに、ビーム発光の波長スペクトルを観測してエタロンの波長を調整し、偏光計測を開始した。本研究は科学研究費補助金基盤研究(S)17106013の支援を得て実施している。
成分を抽出し、その円偏光成分と直線偏光成分の強度比から磁場のピッチ角を測定し電流分布を求める。口径50mmの電子ビーム加熱型イオン源を用いたビーム入射装置を開発し、テストスタンドにて、イオン源から6.5mの点(JT-60U設置時の測定点に相当)でエネルギー10keV,等価電流3mA,発散角0.2度の中性ビームを得て、偏光計測に必要な高輝度・低発散ビームを実現した。JT-60Uに移設後、ビーム発光強度分布から密度分布を計測するとともに、ビーム発光の波長スペクトルを観測してエタロンの波長を調整し、偏光計測を開始した。本研究は科学研究費補助金基盤研究(S)17106013の支援を得て実施している。