Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Catumba, G.*; 平口 敦基; Hou, W.-S.*; Jansen, K.*; Kao, Y.-J.*; David Lin, C.-J.*; Ramos, A.*; Sarkar, M.*
Physical Review Research (Internet), 6(4), p.043172_1 - 043172_12, 2024/11
様々な表現の物質場と結合するゲージ理論は、物理学の様々な分野で重要な役割を果たしている。最近、銅酸化物超伝導体の最適ドーピング近傍の興味深い擬ギャップ相のいくつかの側面が、発現したSU(2)ゲージ対称性によって説明できるかもしれないことが提案された。ホールドーピングによる転移付近では、4つの随伴スカラー場と結合した(2+1)次元SU(2)ゲージ理論を構築することができ、異なる破れた対称性を持つ様々な相が存在する豊かな相図を与える。我々は、ハイブリッドモンテカルロ法を用いて、ユークリッド格子上でこのモデルの相図を研究した。その結果、これまでの平均場の研究で予言されていたように、対称性が破れた複数の相が存在することがわかった。4点相互作用によって、摂動論の範囲ではこの理論のSU(2)ゲージ対称性はU(1)か に分解される。さらに、我々はこの理論における閉じ込め-非閉じ込め転移を評価し、我々が研究した格子体積の範囲では、どちらの破れた相も非閉じ込め相であることを見いだした。しかしながら、ポリヤコフループの振る舞いには2つの相で顕著な違いがあることがわかった。
に分解される。さらに、我々はこの理論における閉じ込め-非閉じ込め転移を評価し、我々が研究した格子体積の範囲では、どちらの破れた相も非閉じ込め相であることを見いだした。しかしながら、ポリヤコフループの振る舞いには2つの相で顕著な違いがあることがわかった。
 gauge fields
gauge fieldsCatumba, G.*; 平口 敦基; W.-S. Hou, G.*; Jansen, K.*; Kao, Y.-J.*; David Lin, C.-J.*; Ramos, A.*; Sarkar, M.*
Proceedings of Science (Internet), 453, p.87_1 - 87_9, 2024/11
本研究では、 ゲージ場と相互作用する一般的な2ヒッグスダブレット模型を格子ゲージ理論で議論する。秩序変数の代わりとしてゲージ不変の大域的観測量を計算することにより、この模型の相図を調べた。それぞれの相において、裸の結合定数の組み合わせや対称性の破れのパターンを変えて理論のスカラー粒子およびベクトルボソン粒子の質量の評価を行なった。またスケール設定と走るゲージ結合定数の決定は、ウィルソンフロウの計算によって行なった。
ゲージ場と相互作用する一般的な2ヒッグスダブレット模型を格子ゲージ理論で議論する。秩序変数の代わりとしてゲージ不変の大域的観測量を計算することにより、この模型の相図を調べた。それぞれの相において、裸の結合定数の組み合わせや対称性の破れのパターンを変えて理論のスカラー粒子およびベクトルボソン粒子の質量の評価を行なった。またスケール設定と走るゲージ結合定数の決定は、ウィルソンフロウの計算によって行なった。
Catumba, G.*; 平口 敦基; W.-S. Hou, G.*; Jansen, K.*; Kao, Y.-J.*; David Lin, C.-J.*; Ramos, A.*; Sarkar, M.*
Proceedings of Science (Internet), 453, p.362_1 - 362_7, 2024/11
本研究では、最近Sachdevらによって最適ドーピング付近の銅酸化物超伝導体の物理を説明するために提案された、随伴表現の4つのヒッグス場を持つ3次元SU(2)ゲージ理論を議論する。この理論の閉じ込め相は通常のフェルミ液体相に対応し、ヒッグス相は銅酸化物の擬ギャップ相に対応しており、我々はハイブリッドモンテカルロ法を用いて理論の相図を調査した。我々は、先行研究の平均場での計算に定性的に従う様々な相の存在を発見し、銅酸化物におけるそれらの役割について議論する。さらに、閉じ込め非閉じ込め相転移を調べるためにポリヤコフループの振る舞いを調べ、ヒッグス相が安定な非閉じ込め相を持つことを見いだした。
Baccou, J.*; Glantz, T.*; Ghione, A.*; Sargentini, L.*; Fillion, P.*; Damblin, G.*; Sueur, R.*; Iooss, B.*; Fang, J.*; Liu, J.*; et al.
Nuclear Engineering and Design, 421, p.113035_1 - 113035_16, 2024/05
被引用回数:6 パーセンタイル:96.49(Nuclear Science & Technology)In the Best-Estimate Plus Uncertainty (BEPU) framework, the use of best-estimate code requires to go through a Verification, Validation and Uncertainty Quantification process (VVUQ). The relevance of the experimental data in relation to the physical phenomena of interest in the VVUQ process is crucial. Adequacy analysis of selected experimental databases addresses this problem. The outcomes of the analysis can be used to select a subset of relevant experimental data, to encourage designing new experiments or to drop some experiments from a database because of their substantial lack of adequacy. The development of a specific transparent and reproducible approach to analyze the relevance of experimental data for VVUQ still remains open and is the topic of this contribution. In this paper, the concept of adequacy initially introduced in the OECD/NEA SAPIUM (Systematic APproach for model Input Uncertainty quantification Methodology) activity is formalized. It is defined through two key properties, called representativeness and completeness, that allows considering the multifactorial dimension of the adequacy problem. A new systematic approach is then proposed to analyze the adequacy of a set of experimental databases. It relies on the introduction of two sets of criteria to characterize representativeness and completeness and on the use of multi-criteria decision analysis method to perform the analysis. Finally, the approach is applied in the framework of the new OECD/NEA ATRIUM activity which includes a set of practical IUQ exercises in thermal-hydraulics to test the SAPIUM guideline in determining input uncertainties and forward propagating them on an application case. It allows evaluating the adequacy of eight experimental databases coming from the Super Moby-dick, Sozzi-Sutherland and Marviken experiments and identifying the most adequate ones.
 SnSe
SnSe
Ren, Q.*; Gupta, M. K.*; Jin, M.*; Ding, J.*; Wu, J.*; Chen, Z.*; Lin, S.*; Fabelo, O.*; Rodriguez-Velamazan, J. A.*; 古府 麻衣子; et al.
Nature Materials, 22(8), p.999 - 1006, 2023/08
被引用回数:78 パーセンタイル:99.19(Chemistry, Physical)Ultralow thermal conductivity and fast ionic diffusion endow superionic materials with excellent performance both as thermoelectric converters and as solid-state electrolytes. Yet the correlation and interdependence between these two features remain unclear owing to a limited understanding of their complex atomic dynamics. Here we investigate ionic diffusion and lattice dynamics in argyrodite Ag SnSe
SnSe using synchrotron X-ray and neutron scattering techniques along with machine-learned molecular dynamics. We identify a critical interplay of the vibrational dynamics of mobile Ag and a host framework that controls the overdamping of low-energy Ag-dominated phonons into a quasi-elastic response, enabling superionicity. Concomitantly, the persistence of long-wavelength transverse acoustic phonons across the superionic transition challenges a proposed 'liquid-like thermal conduction' picture. Rather, a striking thermal broadening of low-energy phonons, starting even below 50 K, reveals extreme phonon anharmonicity and weak bonding as underlying features of the potential energy surface responsible for the ultralow thermal conductivity (
using synchrotron X-ray and neutron scattering techniques along with machine-learned molecular dynamics. We identify a critical interplay of the vibrational dynamics of mobile Ag and a host framework that controls the overdamping of low-energy Ag-dominated phonons into a quasi-elastic response, enabling superionicity. Concomitantly, the persistence of long-wavelength transverse acoustic phonons across the superionic transition challenges a proposed 'liquid-like thermal conduction' picture. Rather, a striking thermal broadening of low-energy phonons, starting even below 50 K, reveals extreme phonon anharmonicity and weak bonding as underlying features of the potential energy surface responsible for the ultralow thermal conductivity ( 0.5 Wm
0.5 Wm K
K ) and fast diffusion. Our results provide fundamental insights into the complex atomic dynamics in superionic materials for energy conversion and storage.
) and fast diffusion. Our results provide fundamental insights into the complex atomic dynamics in superionic materials for energy conversion and storage.
Barucci, M. A.*; Reess, J.-M.*; Bernardi, P.*; Doressoundiram, A.*; Fornasier, S.*; Le Du, M.*; 岩田 隆浩*; 中川 広務*; 中村 智樹*; Andr , Y.*; et al.
, Y.*; et al.
Earth, Planets and Space (Internet), 73(1), p.211_1 - 211_28, 2021/12
被引用回数:25 パーセンタイル:82.95(Geosciences, Multidisciplinary)MMX赤外線分光計(MIRS)は、宇宙航空研究開発機構(JAXA)のMMXミッションに搭載されているイメージング分光計である。MIRSは他の4つのフランス研究所との協力、フランス国立宇宙研究センター(CNES)の協力と財政支援、およびJAXAと三菱電機(MELCO)との緊密な協力によりパリ天文台で開発されている。この装置はMMXの科学的目的を完全に達成するべく設計されている。MIRSはフォボスとダイモスの表面組成の分析およびサンプリングサイトの選択時に使用される組成診断スペクトル機能を含む近赤外線スペクトルマップ機能をリモートで提供する。MIRSはまた、火星の大気、特に雲,塵,水蒸気などの空間的時間的変化についても観測を行う予定である。
大柳 洸一*; Gomez-Perez, J. M.*; Zhang, X.-P.*; 吉川 貴史*; Chen, Y.*; Sagasta, E.*; Chuvilin, A.*; Hueso, L. E.*; Golovach, V. N.*; Sebastian Bergeret, F.*; et al.
Physical Review B, 104(13), p.134428_1 - 134428_14, 2021/10
被引用回数:18 パーセンタイル:74.40(Materials Science, Multidisciplinary)We report the observation of the spin Hall magnetoresistance (SMR) in a paramagnetic insulator. By measuring the transverse resistance in a Pt/Gd Ga
Ga O
O (GGG) system at low temperatures, paramagnetic SMR is found to appear with an intensity that increases with the magnetic field aligning GGG's spins. The observed effect is well supported by a microscopic SMR theory, which provides the parameters governing the spin transport at the interface. Our findings clarify the mechanism of spin exchange at a Pt/GGG interface, and demonstrate tunable spin-transfer torque through the field-induced magnetization of GGG. In this regard, paramagnetic insulators offer a key property for future spintronic devices.
(GGG) system at low temperatures, paramagnetic SMR is found to appear with an intensity that increases with the magnetic field aligning GGG's spins. The observed effect is well supported by a microscopic SMR theory, which provides the parameters governing the spin transport at the interface. Our findings clarify the mechanism of spin exchange at a Pt/GGG interface, and demonstrate tunable spin-transfer torque through the field-induced magnetization of GGG. In this regard, paramagnetic insulators offer a key property for future spintronic devices.
Gens, A.*; Alcoverro, J.*; Blaheta, R.*; Hasal, M.*; Michalec, Z.*; 高山 裕介; Lee, C.*; Lee, J.*; Kim, G. Y.*; Kuo, C.-W.*; et al.
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 137, p.104572_1 - 104572_19, 2021/01
被引用回数:23 パーセンタイル:87.36(Engineering, Geological)放射性廃棄物を地層処分した際に、廃棄体やその周囲で起こる熱-水理-力学-化学が連成する現象を表現する連成モデルの開発と確証を目的に、国際共同研究「DECOVALEX 2019 (DEvelopment of COupled models and their VALidation against EXperiments 2019)」が実施された。DECOVALEX-2019の一つのタスクでは、スイスのモン・テリ岩盤研究所およびグリムゼル試験サイトで実施されている原位置試験(それぞれ、EB試験およびFEBEX試験)を対象とした解析課題であり、廃棄体定置後のベントナイト材料からなる緩衝材等の人工バリア及び岩盤を対象に緩衝材が不飽和から飽和に至る状態までの熱-水理-力学連成現象のモデル化に関する検討が行われた。このタスクでは4つのチームが様々なコンピューターコード、構成則を使用して水理-力学および熱-水理-力学の連成解析を実行し、計測データと解析結果の比較が行われた。本論文は、DECOVALEX-2019プロジェクトのこのタスクで得られた成果や課題等について取りまとめた論文である。
Gens, A.*; Alcoverro, J.*; Blaheta, R.*; Hasal, M.*; Michalec, Z.*; 高山 裕介; Lee, C.*; Lee, J.*; Kim, G. Y.*; Kuo, C.-W.*; et al.
LBNL-2001267 (Internet), 210 Pages, 2020/10
放射性廃棄物を地層処分した際に、廃棄体やその周囲で起こる熱-水理-力学-化学が連成する現象を表現する連成モデルの開発と確証を目的に、国際共同研究「DECOVALEX 2019 (DEvelopment of COupled models and their VALidation against EXperiments 2019)」が2016年4月から2019年12月までの期間で実施された。DECOVALEX-2019のタスクDは、スイスのモン・テリ岩盤研究所およびグリムゼル試験サイトで実施されている原位置試験(それぞれ、EB試験およびFEBEX試験)を対象とした解析課題であり、廃棄体定置後のベントナイト材料からなる緩衝材等の人工バリア及び岩盤を対象に緩衝材が不飽和から飽和に至る状態までの熱-水理-力学連成現象のモデル化に関する検討が行われた。タスクDの参加チームは、IGN(チェコ), KAERI(韓国), NCU/TP(台湾), JAEA(日本)の4チームである。本報告書は、DECOVALEX-2019プロジェクトのタスクDの最終レポートであり、得られた成果や課題等について取りまとめたものである。
Shaimerdenov, A.*; Gizatulin, S.*; Kenzhin, Y.*; Dyussambayev, D.*; 植田 祥平; 相原 純; 柴田 大受
Proceedings of 9th International Topical Meeting on High Temperature Reactor Technology (HTR 2018) (USB Flash Drive), 6 Pages, 2018/10
高温ガス炉燃料の100GWd/tへの高燃焼度化開発のため、原子力機構の協力の下、国際科学技術センター(ISTC)のプロジェクトにおいて、カザフスタン核物理研究所(INP)が高温ガス炉燃料試料の照射試験並びに照射後試験を実施している。新設計の四層三重(TRISO)被覆燃料粒子を円筒状の黒鉛マトリックス燃料コンパクトに成形した照射燃料試料は、日本において製作された。ヘリウムガススウィープ照射キャプセルの設計製作はINPが実施し、WWR-K照射炉を用いての照射試験が2015年4月から実施された。次の段階として、照射済み燃料試料の照射後試験が2017年2月にISTCの新規プロジェクトとして開始された。照射済み燃料試料の非破壊試験および破壊試験に係る様々な照射後試験技術がINPによって開発された。本報では、高燃焼度化TRISO燃料の照射後試験のために開発した技術並びに試験結果について中間報告する。
 NH
NH PbI
PbI
Li, B.; 川北 至信; Liu, Y.*; Wang, M.*; 松浦 直人*; 柴田 薫; 河村 聖子; 山田 武*; Lin, S.*; 中島 健次; et al.
Nature Communications (Internet), 8, p.16086_1 - 16086_9, 2017/06
被引用回数:83 パーセンタイル:90.06(Multidisciplinary Sciences)Perovskite CH NH
NH PbI
PbI exhibits outstanding photovoltaic performances, but the understanding of the atomic motions remains inadequate even though they take a fundamental role in transport properties. Here, we present a complete atomic dynamic picture consisting of molecular jumping rotational modes and phonons, which is established by carrying out high-resolution time-of-flight quasi-elastic and inelastic neutron scattering measurements in a wide energy window ranging from 0.0036 to 54 meV on a large single crystal sample, respectively. The ultrafast orientational disorder of molecular dipoles, activated at approximately 165 K, acts as an additional scattering source for optical phonons as well as for charge carriers. It is revealed that acoustic phonons dominate the thermal transport, rather than optical phonons due to sub-picosecond lifetimes. These microscopic insights provide a solid standing point, on which perovskite solar cells can be understood more accurately and their performances are perhaps further optimized.
exhibits outstanding photovoltaic performances, but the understanding of the atomic motions remains inadequate even though they take a fundamental role in transport properties. Here, we present a complete atomic dynamic picture consisting of molecular jumping rotational modes and phonons, which is established by carrying out high-resolution time-of-flight quasi-elastic and inelastic neutron scattering measurements in a wide energy window ranging from 0.0036 to 54 meV on a large single crystal sample, respectively. The ultrafast orientational disorder of molecular dipoles, activated at approximately 165 K, acts as an additional scattering source for optical phonons as well as for charge carriers. It is revealed that acoustic phonons dominate the thermal transport, rather than optical phonons due to sub-picosecond lifetimes. These microscopic insights provide a solid standing point, on which perovskite solar cells can be understood more accurately and their performances are perhaps further optimized.
Pitcher, C. S.*; Barnsley, R.*; Bertalot, L.*; Encheva, A.*; Feder, R.*; Friconneau, J. P.*; Hu, Q.*; Levesy, B.*; Loesser, G. D.*; Lyublin, B.*; et al.
Fusion Science and Technology, 64(2), p.118 - 125, 2013/08
被引用回数:5 パーセンタイル:36.22(Nuclear Science & Technology)ITERにおいて計測装置を設置するための基盤構造である上部及び水平ポートプラグの共通部分に関する統合設計をまとめたものである。本設計は、ITER機構が組織した各国数名からなる設計タスクフォースにより実施され、ポートプラグの成立に必要なすべての作業を網羅したものである。検討の結果、一つのポートプラグに複数の計測装置が入る水平ポートプラグでは、計測器毎の干渉を避けると同時に保守を考慮した3から6のユニット構造を提案し、さらに発生する電磁力の低減をはかった。また、真空容器外のインタースペースやポートセルへの設置についても考慮し、ポートプラグ及び計測装置の一体化の検討を行った。会議では懸案となっている中性子遮蔽性能の改善策についても併せて報告する。
Pitcher, C. S.*; Barnsley, R.*; Feder, R.*; Hu, Q.*; Loesser, G. D.*; Lyublin, B.*; Padasalagi, S.*; Pak, S.*; Reichle, R.*; 佐藤 和義; et al.
Fusion Engineering and Design, 87(5-6), p.667 - 674, 2012/08
被引用回数:12 パーセンタイル:63.74(Nuclear Science & Technology)The nuclear engineering infrastructure for port-based diagnostics on ITER is presented, including the equatorial and upper port plug generic designs, the adopted modular concept, the loads and associated load response and the remote handling.
河村 弘; Chakrov, P.*; 土谷 邦彦; Gizatulin, S.*; 竹本 紀之; Chakrova, Y.*; 木村 明博; Ludmila, C.*; 谷本 政隆; Asset, S.*; et al.
JAEA-Review 2011-042, 46 Pages, 2012/02
カザフスタン共和国の国立原子力センター(NNC)と日本原子力研究開発機構(JAEA)との原子力科学分野における研究開発協力のための実施取決め(試験研究炉に関する原子力技術)に基づき、4項目の特定協力課題を2009年6月から実施している。4つの特定協力課題は、(1)中性子照射場における計測機器の国際標準化、(2)RI製造に関する照射技術、(3)試験研究炉で使用するベリリウム製反射体の長寿命化、及び(4)シリコン半導体製造に関する技術であり、情報交換、人員派遣及び共同実験を行っている。本報告書は、これら4つの協力課題についてWWR-K炉を用いた照射技術開発の現状と今後の計画についてまとめたものである。
 P
P O
O
長谷 正司*; D nni, A.*; 小澤 清*; 北澤 英明*; 酒井 治*; Pomjakushin, V. Y.*; Keller, L.*; 金子 耕士; 目時 直人; 加倉井 和久; et al.
nni, A.*; 小澤 清*; 北澤 英明*; 酒井 治*; Pomjakushin, V. Y.*; Keller, L.*; 金子 耕士; 目時 直人; 加倉井 和久; et al.
Journal of Physics; Conference Series, 340, p.012066_1 - 012066_7, 2012/00
被引用回数:1 パーセンタイル:44.11(Physics, Condensed Matter)スピン5/2反強磁性Mn量子トリマーの[0,  , 0]インコメンシュレート構造(
, 0]インコメンシュレート構造( =0.316-0.331)を中性子粉末回折により明らかにし、
=0.316-0.331)を中性子粉末回折により明らかにし、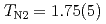 Kにおいて波数が急激に替わることから磁気秩序層が二つ存在することを明らかにした。非弾性散乱実験によって観察された分散を示さない励起(0.46, 0.68, and 1.02meV)が、この系の磁気励起が反強磁性量子トリマーモデルで説明できることを明らかにした。解析によって、量子トリマー形成に重要な最近接相互作用
Kにおいて波数が急激に替わることから磁気秩序層が二つ存在することを明らかにした。非弾性散乱実験によって観察された分散を示さない励起(0.46, 0.68, and 1.02meV)が、この系の磁気励起が反強磁性量子トリマーモデルで説明できることを明らかにした。解析によって、量子トリマー形成に重要な最近接相互作用
 =0.29meVが半強磁性的であることを明らかにした。
=0.29meVが半強磁性的であることを明らかにした。
Yan, Y.*; Lin, M.; 勝村 庸介*; 室屋 裕佐*; 山下 真一; 端 邦樹; Meesungnoen, J.*; Jay-Gerin, J.-P.*
Canadian Journal of Chemistry, 88(10), p.1026 - 1033, 2010/10
被引用回数:1 パーセンタイル:6.91(Chemistry, Multidisciplinary)パルスラジオリシス法及びレーザーフォトリシス法を用いて、亜臨界及び超臨界状態(220-270 C)におけるメタノール中溶媒和電子の光吸収スペクトル変化を計測した。溶媒和電子の吸収ピーク(
C)におけるメタノール中溶媒和電子の光吸収スペクトル変化を計測した。溶媒和電子の吸収ピーク(
 )は溶媒の密度に依存し、0.45-0.59g/cm
)は溶媒の密度に依存し、0.45-0.59g/cm の範囲で増加させると高エネルギー側へシフトした。水に関する過去の実験結果と同じく、
の範囲で増加させると高エネルギー側へシフトした。水に関する過去の実験結果と同じく、
 は圧力一定下においては臨界温度を超えてもなお単調減少するが、逆に密度一定下においては、臨界温度に極小点を持つことがわかった。このようなスペクトルの振る舞いを、メタノールの温度・圧力変化に伴う物性値や分子構造の変化により議論した。
は圧力一定下においては臨界温度を超えてもなお単調減少するが、逆に密度一定下においては、臨界温度に極小点を持つことがわかった。このようなスペクトルの振る舞いを、メタノールの温度・圧力変化に伴う物性値や分子構造の変化により議論した。
Chen, L. M.*; Wang, W. M.*; 神門 正城; Hudson, L. T.*; Liu, F.*; Lin, X. X.*; Ma, J. L.*; Li, Y. T.*; Bulanov, S. V.; 田島 俊樹*; et al.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 619, p.128 - 132, 2010/07
被引用回数:10 パーセンタイル:55.61(Instruments & Instrumentation)イメージング応用、特にX線変換効率が飽和する領域での画像品質に与える影響についてレーザー駆動の硬X線源についてレビューを行う。高コントラストのレーザーを用いることで固体薄膜から発生するX線への変換効率は改善し、また、イメージングの応用によってX線スペクトルの形状は最適化できる。さらにArガスを用いることで、不要なバックグラウンドを低減でき、高品質の画像をとることができる。これらの方法はシングルショットでの高速X線イメージングを可能にする技術である。
Loughlin, M. J.*; Batistoni, P.*; 今野 力; Fischer, U.*; 飯田 浩正; Petrizzi, L.*; Polunovskiy, E.*; Sawan, M.*; Wilson, P.*; Wu, Y.*
Fusion Science and Technology, 56(2), p.566 - 572, 2009/08
被引用回数:44 パーセンタイル:92.64(Nuclear Science & Technology)ITERでは700MWもの核融合出力が予定されている。そのため、毎秒2.48 10
10 個の14MeV中性子が発生し、第1壁に入射する中性子フラックスは非散乱中性子だけで約4
個の14MeV中性子が発生し、第1壁に入射する中性子フラックスは非散乱中性子だけで約4 10
10 n/cm
n/cm /sで、散乱中性子も含めると数10
/sで、散乱中性子も含めると数10 n/cm
n/cm /sにもなる。したがって、ITERは核施設として大掛かりなものであり、核解析に関する効率の良い、首尾一貫した戦略を立てることが不可欠である。この論文では、これまで用いられてきた手法をレビューし、ITERが採用すべき今後の戦略について述べる。具体的には、放射線輸送計算コード,計算モデル作成,情報工学の開発,管理ツールについて検討するとともに、新しいコード,技術を開発する必要がある分野についても提言する。
/sにもなる。したがって、ITERは核施設として大掛かりなものであり、核解析に関する効率の良い、首尾一貫した戦略を立てることが不可欠である。この論文では、これまで用いられてきた手法をレビューし、ITERが採用すべき今後の戦略について述べる。具体的には、放射線輸送計算コード,計算モデル作成,情報工学の開発,管理ツールについて検討するとともに、新しいコード,技術を開発する必要がある分野についても提言する。
乙坂 重嘉; 天野 光; 伊藤 集通; 川村 英之; 小林 卓也; 鈴木 崇史; 外川 織彦; Chaykovskaya, E. L.*; Lishavskaya, T. S.*; Novichkov, V. P.*; et al.
Journal of Environmental Radioactivity, 91(3), p.128 - 145, 2006/00
被引用回数:21 パーセンタイル:42.42(Environmental Sciences)1998年から2002年にかけて、日本海の22観測点で観測した堆積物中の放射性核種( Sr,
Sr,  Cs及び
Cs及び Pu)の存在量と存在比から、同海域における粒子状放射性核種の輸送と蓄積過程を明らかにした。日本海における堆積物中の
Pu)の存在量と存在比から、同海域における粒子状放射性核種の輸送と蓄積過程を明らかにした。日本海における堆積物中の Sr,
Sr,  Cs及び
Cs及び Puの存在量は、それぞれ0.6-87Bq/m
Puの存在量は、それぞれ0.6-87Bq/m , 5.9-379Bq/m
, 5.9-379Bq/m 及び0.6-78Bq/m
及び0.6-78Bq/m の範囲であった。日本海盆及び大和海盆では、深海(水深2km以深)部における堆積物中の放射性核種存在量は同程度であったが、堆積物中の平均
の範囲であった。日本海盆及び大和海盆では、深海(水深2km以深)部における堆積物中の放射性核種存在量は同程度であったが、堆積物中の平均 Pu/
Pu/ Cs比は大和海盆に比べて日本海盆で大きかった。特に西部日本海盆で見られた大きな
Cs比は大和海盆に比べて日本海盆で大きかった。特に西部日本海盆で見られた大きな Pu/
Pu/ Cs比は、この海域表層へのPu/Cs比の大きな粒子の生成と深海への急速な粒子沈降がもたらした結果であると結論付けられた。対馬海盆及び大和海盆縁辺部では、堆積物中の放射性核種の存在量及び
Cs比は、この海域表層へのPu/Cs比の大きな粒子の生成と深海への急速な粒子沈降がもたらした結果であると結論付けられた。対馬海盆及び大和海盆縁辺部では、堆積物中の放射性核種の存在量及び Pu/
Pu/ Cs比が大きかった。対馬暖流による粒子状放射性核種の水平輸送が南部及び東部日本海における堆積物への大きな放射性核種の蓄積をもたらしたと考えられた。
Cs比が大きかった。対馬暖流による粒子状放射性核種の水平輸送が南部及び東部日本海における堆積物への大きな放射性核種の蓄積をもたらしたと考えられた。
伊藤 集通; 荒巻 能史*; 乙坂 重嘉; 鈴木 崇史; 外川 織彦; 小林 卓也; 川村 英之; 天野 光; 千手 智晴*; Chaykovskaya, E. L.*; et al.
Journal of Nuclear Science and Technology, 42(1), p.90 - 100, 2005/01
被引用回数:14 パーセンタイル:66.47(Nuclear Science & Technology)1996-2002年の期間、日露の研究機関の協力で人工放射性核種の広域調査プロジェクトが日露の両排他的経済水域にまたがった日本海で実施された。本プロジェクトの目的は、 Sr,
Sr,  Cs,
Cs,  Pu等の核種の海洋中での移行を明らかにすることである。2001-2002年には4回の調査航海が実施された。これら調査で得られた放射性核種の濃度とその分布はこれまでに得られた知見の範囲内であったことから、現在日本海に対する新たな放射性核種源となるような事故,投棄あるいは過去の廃棄物からの漏洩等が発生していないことが確認された。また、海水中におけるインベントリは、グローバルフォールアウトで同緯度帯の海洋にもたらされた量の約2倍であり、日本海におけるそれら核種の蓄積が示された。さらに、亜表層における
Pu等の核種の海洋中での移行を明らかにすることである。2001-2002年には4回の調査航海が実施された。これら調査で得られた放射性核種の濃度とその分布はこれまでに得られた知見の範囲内であったことから、現在日本海に対する新たな放射性核種源となるような事故,投棄あるいは過去の廃棄物からの漏洩等が発生していないことが確認された。また、海水中におけるインベントリは、グローバルフォールアウトで同緯度帯の海洋にもたらされた量の約2倍であり、日本海におけるそれら核種の蓄積が示された。さらに、亜表層における Sr及び
Sr及び Cs濃度が日本海の広い範囲で時間変動していることが明らかとなり、溶存酸素データとの比較解析により、この時間変動は日本海の上部の水塊移動と関連付けられた。
Cs濃度が日本海の広い範囲で時間変動していることが明らかとなり、溶存酸素データとの比較解析により、この時間変動は日本海の上部の水塊移動と関連付けられた。