Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
新里 忠史; 佐々木 祥人; 雨宮 浩樹*
第32回社会地質学シンポジウム論文集, p.13 - 16, 2022/11
福島の森林斜面および渓流におけるセシウム137の流出観測に基づいて、河川のセシウム137流出における森林域に存在するセシウム137の寄与を検討し、土砂流出量およびセシウム137濃度の観点から、比較的寄与が低い可能性を指摘した。
新里 忠史; 佐々木 祥人; 渡辺 貴善; 雨宮 浩樹*
第31回社会地質学シンポジウム論文集, p.19 - 22, 2021/11
福島の山地森林における林床状況とセシウム137( Cs)流出量の関連を把握するため、除染地,未除染地および林野火災の延焼跡地において3年間の長期観測を実施した。除染や延焼により失われた林床被覆が回復するのに伴い
Cs)流出量の関連を把握するため、除染地,未除染地および林野火災の延焼跡地において3年間の長期観測を実施した。除染や延焼により失われた林床被覆が回復するのに伴い Cs流出量は減少し、除染地では除染直後の3.24%から0.61%へ、延焼跡地では延焼直後の2.79%から0.03%へと低下した。林床被覆が60%を超えると未除染地や非延焼地と同程度の流出量となり、林床被覆60%は、観測地における流出影響の閾値と考えられる。延焼跡地では林床被覆の回復に伴い、流出物の主体が土壌粒子からリター片に変化したことも、
Cs流出量は減少し、除染地では除染直後の3.24%から0.61%へ、延焼跡地では延焼直後の2.79%から0.03%へと低下した。林床被覆が60%を超えると未除染地や非延焼地と同程度の流出量となり、林床被覆60%は、観測地における流出影響の閾値と考えられる。延焼跡地では林床被覆の回復に伴い、流出物の主体が土壌粒子からリター片に変化したことも、 Cs流出量の低下に寄与した。山地森林の林床が本来有する土壌侵食に対する保護機能は、
Cs流出量の低下に寄与した。山地森林の林床が本来有する土壌侵食に対する保護機能は、 Cs流出抑制に効果的である。
Cs流出抑制に効果的である。
代永 佑輔; 佐野 直美*; 雨宮 浩樹*; 小北 康弘; 丹羽 正和; 安江 健一*
応用地質, 62(1), p.2 - 12, 2021/04
電子プローブマイクロアナライザ(EPMA)を用いた手法(重鉱物スクリーニング)の適用可能性を検証するため、堆積岩や苦鉄質岩が後背地となる北海道天塩郡幌延地域に分布する更新統更別層を事例対象として後背地解析を実施した。分析は16元素を測定対象として行い、得られた化学組成に基づいて鉱物種を判定した。加えて、薄片観察や礫種組成分析を行い、結果を比較した。その結果、薄片観察・礫種組成分析と重鉱物スクリーニングの結果は整合であることが確認された。更別層の後背地は宗谷丘陵・天塩山地であり、少なくとも1.5Ma以降に宗谷丘陵が隆起したことが推測される。一方で、宗谷丘陵や天塩山地で見られなかった角閃石が更別層から確認され、天塩川による運搬などで本地域より離れた所から供給された可能性が考えられる。これにより、重鉱物スクリーニングを用いることで礫種組成だけでは分からない新しい情報が得られることが確認された。
 第四系に挟在するテフラのジルコンU-Pbおよびフィッション・トラック年代
第四系に挟在するテフラのジルコンU-Pbおよびフィッション・トラック年代丹羽 正和; 雨宮 浩樹*; 代永 佑輔; 小北 康弘; 安江 健一*; 岩野 英樹*; 檀原 徹*; 平田 岳史*
地質学雑誌, 126(5), p.267 - 283, 2020/05
地層の堆積年代の決定や層序対比において有効な指標となるテフラの年代決定手法の高度化のため、北海道幌延地域の新第三系 第四系に狭在する3試料のテフラを事例対象として、ジルコンの同一粒子に対しU-Pb年代とフィッション・トラック(FT)年代を求め、堆積年代を推定する手法を適用した。このうち2試料は、最若粒子集団のU-PbとFTの加重平均年代が誤差2
第四系に狭在する3試料のテフラを事例対象として、ジルコンの同一粒子に対しU-Pb年代とフィッション・トラック(FT)年代を求め、堆積年代を推定する手法を適用した。このうち2試料は、最若粒子集団のU-PbとFTの加重平均年代が誤差2 で一致し、降灰テフラの噴出年代を示すと考えられた。もう1試料についても、多くのジルコンでFT年代がU-Pb年代と同等かそれ以上に若返っており、全粒子のFT加重平均年代と最若粒子集団のU-Pb加重平均年代が誤差2
で一致し、降灰テフラの噴出年代を示すと考えられた。もう1試料についても、多くのジルコンでFT年代がU-Pb年代と同等かそれ以上に若返っており、全粒子のFT加重平均年代と最若粒子集団のU-Pb加重平均年代が誤差2 で一致するので、それらがテフラの噴出年代を示すと考えられた。また、本研究で得られた結果は、東西圧縮の地殻変動により、同一層でも西部より東部の方が年代が古くなるという本地域の新第三系
で一致するので、それらがテフラの噴出年代を示すと考えられた。また、本研究で得られた結果は、東西圧縮の地殻変動により、同一層でも西部より東部の方が年代が古くなるという本地域の新第三系 第四系における傾向を支持する結果となった。
第四系における傾向を支持する結果となった。
石丸 恒存; 尾方 伸久; 島田 顕臣; 浅森 浩一; 國分 陽子; 丹羽 正和; 渡邊 隆広; 雑賀 敦; 末岡 茂; 小松 哲也; et al.
JAEA-Research 2018-015, 89 Pages, 2019/03
本報は、高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する研究開発のうち、深地層の科学的研究の一環として実施している地質環境の長期安定性に関する研究について、第3期中長期目標期間(平成27年度 平成33年度)における平成29年度に実施した研究開発に係る成果を取りまとめたものである。第3期中長期目標期間における研究の実施にあたっては、最終処分事業の概要調査や安全審査基本指針等の検討・策定に研究成果を適宜反映できるよう、(1)調査技術の開発・体系化、(2)長期予測・影響評価モデルの開発、(3)年代測定技術の開発の三つの枠組みで進めている。本報告では、それぞれの研究分野に係る科学的・技術的背景を解説するとともに、主な研究成果及び今後の課題等について述べる。
平成33年度)における平成29年度に実施した研究開発に係る成果を取りまとめたものである。第3期中長期目標期間における研究の実施にあたっては、最終処分事業の概要調査や安全審査基本指針等の検討・策定に研究成果を適宜反映できるよう、(1)調査技術の開発・体系化、(2)長期予測・影響評価モデルの開発、(3)年代測定技術の開発の三つの枠組みで進めている。本報告では、それぞれの研究分野に係る科学的・技術的背景を解説するとともに、主な研究成果及び今後の課題等について述べる。
野村 勝弘; 谷川 晋一*; 雨宮 浩樹; 安江 健一
JAEA-Data/Code 2016-015, 49 Pages, 2017/03
隆起は、侵食と合わさり、生活環境と処分施設との離間距離を短縮させることから、高レベル放射性廃棄物の地層処分を考える上で重要な自然現象である。これまで日本列島の過去十数万年間の隆起量は、海成段丘や河成段丘などを指標に取得されてきた。本資料では、過去十数万年間の隆起量に関連する情報として、位置座標、比高、比高の指標、指標の形成時期、比高の形成期間、隆起速度などを既存文献に基づいて抽出し、表形式で整理した。これらの情報は、隆起・沈降に関する調査技術の高度化・体系化や日本列島における大局的な地形発達の検討の基礎的な情報の一つになると考えられる。
桐島 陽*; 久野 温*; 雨宮 浩樹; 窪田 卓見*; 紀室 辰伍*; 天野 由記; 宮川 和也; 岩月 輝希; 水野 崇; 佐々木 隆之*; et al.
Chemosphere, 168, p.798 - 806, 2017/02
被引用回数:3 パーセンタイル:8.89(Environmental Sciences)高レベル放射性廃棄物地層処分における性能評価上重要な核種である3価マイナーアクチニド(MA(III))は、天然の地下水中に存在する懸濁粒子や溶存イオン、コロイドなどと吸着反応や錯形成反応などの相互作用を起こし、見かけ上の溶解度が増加する可能性が知られている。このため、これらの放射性核種と地下水中に含まれる物質との相互作用を理解しておくことは、地層中でのこれらの放射性核種の移行評価を行う上で重要である。本研究では、堆積岩地域である幌延地域の深部地下水を用いて、MA(III)のナチュラルアナログである希土類元素(REEs)を添加し、フィルターでろ過することにより、REEsの天然地下水中における挙動を調べた。その結果、イオン半径の小さいREEsほど地下水中に多く溶存している傾向が明らかになった。また、比較的大部分のREEsはリン酸塩として存在している可能性が強く示唆された。この結果は、高レベル放射性廃棄物の廃棄体から遠い将来に放出されると予想されているMA(III)の移行挙動を予測する上で、リン酸陰イオンが重要な役割を果たすことを示唆している。
桐島 陽*; 久野 温*; 雨宮 浩樹; 村上 裕晃; 天野 由記; 岩月 輝希; 水野 崇; 窪田 卓見*; 佐々木 隆之*; 佐藤 修彰*
no journal, ,
深部地下水中における元素の存在形態とその移行挙動を理解することを目的として、原子力機構幌延深地層研究所の地下水に含まれる懸濁物と希土類元素との相互作用について検討を行った。嫌気状態を維持したまま採水した地下水にマイナーアクチノイド(MA)のアナログ元素として希土類元素を添加(10ppb)した。この地下水を、複数の限外ろ過膜を孔径の大きいものから順に4段階(0.2 mから1kDa)セットした多連式ろ過システムを用いて限外ろ過した。各段階のフィルターを通過したろ液をICP-MSにて分析した。また、通水後のフィルター表面をSEM-EDXとTOF-SIMSによる元素マッピングにて分析し、フィルター上の捕集物を中性子放射化分析により定量分析した。その結果、希土類元素はリン酸塩粒子が溶解度制限固相となるとともに、リン酸塩粒子とならなかった希土類元素はフミン物質等の有機物と疑似コロイドを形成することがわかった。これらの結果は、MAのアナログとして参照可能であり、処分技術の信頼性向上に寄与する。
mから1kDa)セットした多連式ろ過システムを用いて限外ろ過した。各段階のフィルターを通過したろ液をICP-MSにて分析した。また、通水後のフィルター表面をSEM-EDXとTOF-SIMSによる元素マッピングにて分析し、フィルター上の捕集物を中性子放射化分析により定量分析した。その結果、希土類元素はリン酸塩粒子が溶解度制限固相となるとともに、リン酸塩粒子とならなかった希土類元素はフミン物質等の有機物と疑似コロイドを形成することがわかった。これらの結果は、MAのアナログとして参照可能であり、処分技術の信頼性向上に寄与する。
天野 由記; 雨宮 浩樹; 村上 裕晃; 岩月 輝希; 寺島 元基; 水野 崇; 桐島 陽*; 久野 温*; 佐々木 隆之*; 窪田 卓見*; et al.
no journal, ,
幌延URLにて、ボーリング掘削による汚染の影響を極力排除し、原位置環境条件を保持した状態で、限外濾過手法を用いてコロイドを採取した。コロイド粒子と微量元素の相互作用に関する基礎情報を得るために、地下水及びコロイドの化学特性について評価した。
鴻上 貴之*; 佐々木 隆之*; 雨宮 浩樹; 村上 裕晃; 天野 由記; 岩月 輝希; 水野 崇; 窪田 卓見*; 桐島 陽*
no journal, ,
高塩分濃度の地下水中の極微量元素であるU, Th及び希土類元素の定量法としてICP-MS分析フローを開発した。同法を幌延URLで採水した地下水に適用し、同元素濃度を測定した。
天野 由記; 佐々木 祥人; 南條 功*; 雨宮 浩樹; 水野 崇; 伊勢 孝太郎; 吉川 英樹
no journal, ,
地下環境における還元状態は、高レベル放射性廃棄物処分環境にとって非常に重要な条件である。しかしながら、地層処分のための地下施設建設時には、坑道周辺の酸化により鉱物と地下水の平衡状態が変化し、それに伴い微生物群集も影響を受けることが想定される。地下施設建設が周辺の地球化学状態変化に及ぼす影響を評価するための技術開発を目的として、地下施設建設過程における水理・地球化学・微生物学的特性についてモニタリングを実施した。その結果、周辺水圧の低下が確認されたが、塩分濃度についてはほとんど変化しないことが確認された。pHは時間の経過とともにわずかに上昇したが、酸化還元電位については還元状態のままほとんど変化が見られなかった。一方で、微生物群集組成については、初期には還元状態を好むFirmicutesおよびdelta-Proteobacteriaが優占していたが、時間の経過とともに比較的酸化還元ポテンシャルが高くても生息可能なbeta-Proteobacteriaが優占することが明らかになった。この結果は、坑道周辺が酸化の影響を受けているにもかかわらず、微生物の酸化還元反応により緩衝能力が機能し、還元状態が保持されていることを示唆している。
天野 由記; 伊勢 孝太郎; 寺島 元基; 佐々木 祥人; 雨宮 浩樹; 吉川 英樹
no journal, ,
天然バリア中の核種移行に関わる不確実性要因となりうる微生物影響評価の観点から、幌延地下施設を利用して地下環境における微生物群集の空間分布について調査を実施した。その結果、微生物分布は酸化還元状態や炭素源のような地球化学条件と密接に関連していることが示された。
雨宮 浩樹; 水野 崇; 岩月 輝希; 湯口 貴史; 村上 裕晃; 國分 陽子
no journal, ,
放射性廃棄物の地層処分において、地下深部の長期的な地球化学環境の変遷を推定することは重要な課題となっている。長期的な地球化学特性の変遷の調査解析は、地下水の滞留時間の範囲内においては、地下水を分析することにより直接的に地球化学的特性を把握することが可能である。一方、地下水の滞留時間を超える時間スケールを対象とする場合においては、過去の地球化学特性を反映した地下水を直接採取することができないため、地下水から沈殿した二次鉱物を利用し地球化学的特性(温度、塩分濃度、pHおよび酸化還元電位)を推測することが有効な方法のひとつである。演者は炭酸塩鉱物を用いて過去の地下水の地球化学特性を推定し地下深部における地球化学的条件の把握を試みたこれまでの研究をレビューした。その結果、炭酸塩鉱物沈殿時の地下水の温度と塩分濃度は定量的に評価できる一方、pHおよび酸化還元電位は定性的な評価しかできていないが、炭酸塩鉱物中のマンガン,鉄,ウランなどの重金属や希土類元素の含有量を用いて酸化還元電位を定量的に推定できる可能性が示唆された。
丹羽 正和; 清水 麻由子; 安江 健一; 西村 周作; 雨宮 浩樹; 植木 忠正; 堀内 泰治
no journal, ,
山地の隆起や削剥は地下水の動水勾配や流向に影響を及ぼすので、高レベル放射性廃棄物の地層処分のように地下水流動の長期的な変化を理解することが求められる分野においては、山地の発達過程を把握するための技術も重要である。本研究では山地の発達過程を把握するための後背地解析技術として、重鉱物の高速定量分析や石英の電子スピン共鳴信号測定に基づく後背地岩石の推定、および細粒砂の帯磁率異方性測定による古流向の推定の後背地解析への有効性を提示することができた。
新里 忠史; 佐々木 祥人; 伊藤 聡美; 渡辺 貴善; 雨宮 浩樹*
no journal, ,
東京電力ホールディングス福島第一原子力発電所事故に由来する放射性物質のうち、 Cs(以下、Cs)は半減期が約30年と長く、今後長期にわたり分布状況をモニタリングし、その影響を注視していく必要がある。森林のCs流出率は1%に満たず、森林は長期にCsを林内に留める機能を有すると考えられる。本研究では、林産物のCs濃度予測モデル構築で必要となる樹木のCs吸収量の推定結果を報告する。阿武隈山地の生活圏に隣接するコナラ林とスギ林において年間降雨量や樹木密度がほぼ同様の林分を選定し、2015年から2019年にかけて伐木により樹木試料を採取した。国際生物学事業計画における養分吸収量の算出方法に従い、植物体の生長に伴う吸収量及び植物体からの枯死及び溶脱により失われた量の総和を樹木のCs吸収量とした。樹木の生長に伴うCs吸収量は、バイオマスの増分に樹木各部のCs濃度を乗じて算出し、樹木からの枯死及び溶脱により失われたCs量は、リターフォール,樹幹流及び林内雨に伴うCs移動量の総和とした。樹木の生長に伴うCs吸収量はコナラ林とスギ林で年間あたりそれぞれ0.1及び0.06%、吸収量の総和は年間あたりそれぞれ1.37及び3.13%となった。IBPによる京都近郊の落葉広葉樹林におけるN, P, Kの吸収量(1.2-20.3%)と比較して低いCs吸収量は、本調査地における2015年以降のスギやコナラ立木のCs吸収が限定的であり、Cs濃度の大幅な上昇が生じにくいことを示す。今後、樹木のCs吸収量と他元素の移行量の差異の要因解明が課題である。
Cs(以下、Cs)は半減期が約30年と長く、今後長期にわたり分布状況をモニタリングし、その影響を注視していく必要がある。森林のCs流出率は1%に満たず、森林は長期にCsを林内に留める機能を有すると考えられる。本研究では、林産物のCs濃度予測モデル構築で必要となる樹木のCs吸収量の推定結果を報告する。阿武隈山地の生活圏に隣接するコナラ林とスギ林において年間降雨量や樹木密度がほぼ同様の林分を選定し、2015年から2019年にかけて伐木により樹木試料を採取した。国際生物学事業計画における養分吸収量の算出方法に従い、植物体の生長に伴う吸収量及び植物体からの枯死及び溶脱により失われた量の総和を樹木のCs吸収量とした。樹木の生長に伴うCs吸収量は、バイオマスの増分に樹木各部のCs濃度を乗じて算出し、樹木からの枯死及び溶脱により失われたCs量は、リターフォール,樹幹流及び林内雨に伴うCs移動量の総和とした。樹木の生長に伴うCs吸収量はコナラ林とスギ林で年間あたりそれぞれ0.1及び0.06%、吸収量の総和は年間あたりそれぞれ1.37及び3.13%となった。IBPによる京都近郊の落葉広葉樹林におけるN, P, Kの吸収量(1.2-20.3%)と比較して低いCs吸収量は、本調査地における2015年以降のスギやコナラ立木のCs吸収が限定的であり、Cs濃度の大幅な上昇が生じにくいことを示す。今後、樹木のCs吸収量と他元素の移行量の差異の要因解明が課題である。
渥美 澪香*; 新里 忠史; 竹内 真司*; 雨宮 浩樹*
no journal, ,
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東京電力福島第一原子力発電所事故で、環境中へ多量の放射性物質が放出された。福島県は約7割が森林であり、その多くが未除染のままである。既存研究では、自然状態での放射性セシウムの移行量は小さい。しかし、今後想定される浜通りを中心とした森林開発の再開により、自然状態では小さい放射性セシウムの移行量が、人が入ることで加速される可能性が考えられる。このため、人為的影響を評価することは今後の森林開発等において重要である。そこで、浜通りで典型的な森林植生である照葉樹林およびモミ-イヌブナ林を対象として、人為的影響の事前評価に係る基礎データ取得のため長期観測を実施した。本報告では、2022年から開始した森林内での林床における土砂および放射性セシウムの移行量の観測結果について述べる。
村上 裕晃; 天野 由記; 雨宮 浩樹; 佐々木 祥人; 岩月 輝希; 吉川 英樹
no journal, ,
地下深部が化学的及び生物化学的なプロセスにより還元環境に維持されている事例は多くの既往研究において示されている。他方、高レベル放射性廃棄物の地層処分において、処分場の閉鎖時に地表に保管して酸化したズリとベントナイトを混合した埋め戻し材を使用する場合は、酸化的な環境が形成されることが予想される。本研究では、酸化したズリを含んだ埋め戻し材がどのようなプロセスで還元環境へと回復していくのかを把握するため、特に生物化学的なプロセスに着目したボーリング孔規模での埋め戻し試験を実施した。その結果、埋め戻し材中の微生物数は、埋め戻し前の乾燥状態の試料よりも埋め戻し後に回収した試料の方が1 2桁オーダーで増加しており、微生物を介した反応が還元環境を形成する役割を担っている可能性が示唆された。しかし、微生物のDNA解析の結果から、本試験の期間(141日間)内では、酸化された埋戻し材は埋め戻し前のボーリング孔のような還元環境まで回復していないと推察される。今後は継時的な埋め戻し材の酸化還元環境の変化とそのプロセスの把握及び手法の開発を行っていく。
2桁オーダーで増加しており、微生物を介した反応が還元環境を形成する役割を担っている可能性が示唆された。しかし、微生物のDNA解析の結果から、本試験の期間(141日間)内では、酸化された埋戻し材は埋め戻し前のボーリング孔のような還元環境まで回復していないと推察される。今後は継時的な埋め戻し材の酸化還元環境の変化とそのプロセスの把握及び手法の開発を行っていく。
佐々木 祥人; 浅野 貴博*; 伊勢 孝太郎; 佐藤 智文; 村上 裕晃; 雨宮 浩樹; 天野 由記; 岩月 輝希; 吉川 英樹
no journal, ,
これまでにさまざまな地域で深部地下の微生物についての研究が進められ、微生物相や微生物活動に関する情報が蓄積されつつある。微生物は、地下水水中の化学状態に影響するひとつの因子である。岩石表面は地下水中に比べ、鉱物や有機物が多く存在しており微生物反応の場としては好適環境であると考えられる。しかしながら、これまでの多くの研究は帯水相における水中の微生物相に関する報告であり、亀裂表面における付着微生物に関する報告は少ない。われわれは岩石表面と地下水中の微生物相を調べ、堆積岩表面に付着する微生物と浮遊している微生物相の違いを明らかにした。
伊勢 孝太郎; 南條 功; 雨宮 浩樹; 天野 由記; 岩月 輝希; 浅野 貴博*; 景山 幸二*; 佐々木 祥人; 吉川 英樹
no journal, ,
幌延深地層研究センター250m水平坑道の2本の井戸の掘削後における微生物群集と地下水の解析を行った。微生物群集解析は250m水平坑道で水平方向に掘った井戸V250-M02(以下M02)と垂直方向に掘ったV250-M03(以下M03)の2箇所において行った。M02ではおもに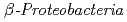 ,
,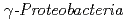 、M03では
、M03では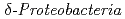 や
や ,
,  により構成されており、明らかに異なる菌相であった。同じ井戸において4か月後にはM02では
により構成されており、明らかに異なる菌相であった。同じ井戸において4か月後にはM02では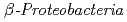 の割合が減少し、偏性嫌気性細菌である
の割合が減少し、偏性嫌気性細菌である などの
などの の割合が増加した。M03においても
の割合が増加した。M03においても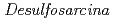 spp.などの硫酸還元細菌が減少し、
spp.などの硫酸還元細菌が減少し、 や
や などの割合が増加した。これらのことから、原位置において還元的環境へとシフトする際には微生物群集が変化し、その変化は時間的にも空間的にも依存することが示された。
などの割合が増加した。これらのことから、原位置において還元的環境へとシフトする際には微生物群集が変化し、その変化は時間的にも空間的にも依存することが示された。
桐島 陽*; 久野 温*; 雨宮 浩樹; 村上 裕晃; 天野 由記; 岩月 輝希; 水野 崇; 窪田 卓見*; 佐々木 隆之*; 佐藤 修彰*
no journal, ,
幌延URLにて採取した深部地下水に希土類元素(REE)を添加した。これを各種のフィルターで分画し、各フラクションを分析することで地下水中に含まれる懸濁物等とREEがどのように相互作用するかを検討した。