Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Chankin, A. V.*; Coster, D. P.*; 朝倉 伸幸; Bonnin, X.*; Conway, G. D.*; Corrigan, G.*; Erents, S. K.*; Fundamenski, W.*; Horacek, J.*; Kallenbach, A.*; et al.
Nuclear Fusion, 47(5), p.479 - 489, 2007/05
被引用回数:34 パーセンタイル:73.51(Physics, Fluids & Plasmas)スクレイプオフ層における径方向電場はプラズマ・ドリフト運動を発生する要因である。また、プラズマ・ドリフト運動の速度は、トロイダルプラズマでは内外非対称となり、そのトロイダル効果を打ち消す方向に磁力線に沿った高速プラズマ流が発生する。実験において観測されている高速プラズマ流の発生機構を理解するため、ドリフト効果を導入したダイバータ流体コード(SOLPS及びEDGE2D)による計算を、JETやASDEX-Upgradeの実験で測定された大きな電場分布を考慮し初めて行った。その結果、プラズマ流速は従来のシミュレーション結果よりも3倍程度増加し、従来のシミュレーションでは定量的に再現できなかった実験結果をほぼ説明できる。ドリフト効果が、プラズマ周辺部において高速プラズマ流が発生する大きな要因の一つであることが明らかとなった。
大山 直幸; 朝倉 伸幸; Chankin, A. V.; 及川 聡洋; 杉原 正芳; 竹永 秀信; 伊丹 潔; 三浦 幸俊; 鎌田 裕; 篠原 孝司; et al.
Nuclear Fusion, 44(5), p.582 - 592, 2004/05
被引用回数:46 パーセンタイル:80.03(Physics, Fluids & Plasmas)ELMによるペデスタル崩壊の物理機構を理解することは、ELMに伴う瞬間的な熱・粒子パルスによるダイバータ板の損傷を防ぐために重要である。このようなELM研究を行うため、マイクロ波反射計,FIR干渉計,D 線計測,磁気プローブ等の高時間分解を持つ計測器を組合せ、ELMにより密度分布が崩壊していく過程を詳細に計測した。その結果、ELMによる密度ペデスタルの崩壊が、前兆振動フェーズ,崩壊フェーズ,回復フェーズ,緩和フェーズの大きく4つに分けられること及びそれらの時間スケールを明らかにするとともに、崩壊が弱磁場側赤道面近傍に局在化していることを示した。ELMにより吐き出された熱・粒子について、スクレイプオフ層を観測する2本のマッハプローブとダイバータ領域を観測する高速赤外カメラにより計測した。弱磁場側赤道面とX点の2か所のプローブ間でイオン飽和電流のピークの時間が異なっており、この時間遅れはスクレイプオフ層を磁力線に沿って粒子が移動する時間と同程度である。また、ダイバータ板への瞬間的な熱負荷の時間幅は、X点プローブのイオン飽和電流が増加している時間と対応する。これらのことから、ELMによる熱負荷の主な部分は対流的な輸送によりダイバータ板へ到達するものと考えられる。
線計測,磁気プローブ等の高時間分解を持つ計測器を組合せ、ELMにより密度分布が崩壊していく過程を詳細に計測した。その結果、ELMによる密度ペデスタルの崩壊が、前兆振動フェーズ,崩壊フェーズ,回復フェーズ,緩和フェーズの大きく4つに分けられること及びそれらの時間スケールを明らかにするとともに、崩壊が弱磁場側赤道面近傍に局在化していることを示した。ELMにより吐き出された熱・粒子について、スクレイプオフ層を観測する2本のマッハプローブとダイバータ領域を観測する高速赤外カメラにより計測した。弱磁場側赤道面とX点の2か所のプローブ間でイオン飽和電流のピークの時間が異なっており、この時間遅れはスクレイプオフ層を磁力線に沿って粒子が移動する時間と同程度である。また、ダイバータ板への瞬間的な熱負荷の時間幅は、X点プローブのイオン飽和電流が増加している時間と対応する。これらのことから、ELMによる熱負荷の主な部分は対流的な輸送によりダイバータ板へ到達するものと考えられる。
Chankin, A. V.
Physics of Plasmas, 11(4), p.1484 - 1492, 2004/04
被引用回数:12 パーセンタイル:37.14(Physics, Fluids & Plasmas)実験的に観測されているMARFEの安定なポロイダル局在位置について考察した。MARFEはSOLに存在する新古典理論から予測される径電場による

 流によりその安定存在位置が決まる。つまり、磁場勾配によるイオンのドルフと方向がX点に向かうときにはMAEFEはX点近くに局在するが、磁場の方向を反転すると
流によりその安定存在位置が決まる。つまり、磁場勾配によるイオンのドルフと方向がX点に向かうときにはMAEFEはX点近くに局在するが、磁場の方向を反転すると

 流が変化し、X点と反対方向の安定点にシフトする。
流が変化し、X点と反対方向の安定点にシフトする。
B coulet, M.*; Huysmans, G.*; Sarazin, Y.*; Garbet, X.*; Ghendrih, P.*; Rimini, F.*; Joffrin, E.*; Litaudon, X.*; Monier-Garbet, P.*; An
coulet, M.*; Huysmans, G.*; Sarazin, Y.*; Garbet, X.*; Ghendrih, P.*; Rimini, F.*; Joffrin, E.*; Litaudon, X.*; Monier-Garbet, P.*; An , J.-M.*; et al.
, J.-M.*; et al.
Plasma Physics and Controlled Fusion, 45(12A), p.A93 - A113, 2003/12
被引用回数:84 パーセンタイル:91.10(Physics, Fluids & Plasmas)炉心級のプラズマにおけるELMに関する実験的,理論的な研究の進展をレビューした論文である。最近の理論的なアプローチでは、線形MHD安定性解析だけでなく、ELMを含んだ非線形輸送モデルが提案されている。これらのモデルと高速なペデスタル圧力分布の崩壊,磁気揺動,スクレイプオフ層の輸送といった実験的観測との比較が行われた。現在得られているtype I ELMのスケーリングをITERに外挿するとダイバータ板への熱負荷が問題となる。近年、高三角度及び高密度領域において、高閉じ込めを維持したまま小さなELMが得られる領域が各装置で見つかっており、これら小振幅ELMの特徴とITERへの適用性に関して議論している。一方、内部輸送障壁とELMの両立性が幾つかの装置で問題になっているが、ELMの振幅を低減することで両立することが可能になった事例を報告している。さらに、周辺電流,ペレット入射,不純物入射,外部磁場摂動等を用いたELMの動的制御法の開発とITERへの適用性について議論している。
大山 直幸; 三浦 幸俊; Chankin, A. V.; 竹永 秀信; 朝倉 伸幸; 鎌田 裕; 及川 聡洋; 篠原 孝司; 竹治 智
Nuclear Fusion, 43(10), p.1250 - 1257, 2003/10
被引用回数:16 パーセンタイル:46.39(Physics, Fluids & Plasmas)反射計によるtype I ELMの詳細測定の結果、ELMによる密度ペデスタルの崩壊はプラズマの弱磁場側に局在化していることが予想された。そこで、反射計とFIR干渉計を用いてプラズマの弱磁場側と強磁場側の同時密度計測を行い、ポロイダル非対称性を確認する実験を行った。反射計の位相変化から評価した弱磁場側反射層の変位は約5cmであった。この変位に対応する強磁場側干渉計の密度変化を評価したところ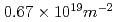 と見積もられたが、実際の観測では強磁場側における密度変化は観測されていない。つまり、ELMによる密度ペデスタルの崩壊は弱磁場側に局在化していることを示している。また、ELMに伴う周辺部密度増加の詳細を調べるため、プラズマを水平方向に動かした時の密度変化を測定した。その結果、強磁場側ではELMによる密度の吐き出しは観測されない、つまり強磁場側の密度ペデスタルは壊れていないことを確認するとともに、周辺部干渉計で観測された線積分密度の増加はスクレイプオフ層とペデスタル部における密度増加が支配的であることを明らかにした。
と見積もられたが、実際の観測では強磁場側における密度変化は観測されていない。つまり、ELMによる密度ペデスタルの崩壊は弱磁場側に局在化していることを示している。また、ELMに伴う周辺部密度増加の詳細を調べるため、プラズマを水平方向に動かした時の密度変化を測定した。その結果、強磁場側ではELMによる密度の吐き出しは観測されない、つまり強磁場側の密度ペデスタルは壊れていないことを確認するとともに、周辺部干渉計で観測された線積分密度の増加はスクレイプオフ層とペデスタル部における密度増加が支配的であることを明らかにした。
Chankin, A. V.; 朝倉 伸幸; 福田 武司; 諫山 明彦; 伊丹 潔; 鎌田 裕; 久保 博孝; 三浦 幸俊; 仲野 友英; 大山 直幸; et al.
Journal of Nuclear Materials, 313-316, p.828 - 833, 2003/03
被引用回数:21 パーセンタイル:78.32(Materials Science, Multidisciplinary)JT-60におけるタイプ1ELMでは、プラズマ中性粒子相互作用によりエッジプラズマ密度の過渡的上昇が起き、内側コードのプラズマ密度干渉計(FIR1)の数msのスパイクとして観測される。プラズマの密度上昇は、SOL及びセパラトリクスすぐ内側、ただしHモードのペデスタルより外側で起こる。中性粒子が即時にイオン化することによるエッジ密度の上昇はMHD安定性に影響を及ぼし、より低いペデスタル温度・圧力でトリガーされる2次的なELMあるいは、タイプ3ELMの連なり、あるいはLモード状態がもたらされる。これらの現象は壁のコンディションに依存することが観測された。
Loarte, A.*; Saibene, G.*; Sartori, R.*; Becoulet, M.*; Horton, L.*; Eich, T.*; Herrmann, A.*; Laux, M.*; Matthews, G.*; Jachmich, S.*; et al.
Journal of Nuclear Materials, 313-316, p.962 - 966, 2003/03
被引用回数:115 パーセンタイル:98.45(Materials Science, Multidisciplinary)Type I ELMによる熱流束はダイバータの損耗に大きく影響し、ITERの設計における大きな研究課題である。JET,DIII-D,ASDEX-U,JT-60Uから得られたType I ELM発生時の蓄積エネルギー,周辺ペデスタル部の温度,密度の変化のデータベースをもとに、ELM熱流(エネルギー損失量)のスケーリングを考察し結果をまとめた。(1)ELM熱流は、ペデスタルの衝突率の増加,磁場シアにより減少する。またELM粒子流は、おもにELMにより影響される領域の幅に比例し増減する。(2)JETとDIII-Dにおいて、ELM発生時、ペデスタルでの温度の減少が無い対流輸送的な小さなELM熱流が観測された。(3)ELM熱流束のダイバータへの照射時間は、ELM発生時間に依存せず、境界層でのイオン輸送時間に比例する。さらに、ELM熱流と粒子流のITERにおける予想について議論を行う。
Chankin, A. V.; Stangeby, P. C.*
Proceedings of 30th EPS Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics (CD-ROM), 4 Pages, 2003/00
多くのトカマク装置(JET, JT-60U, DIII-D, ASDEX-U)において観測されている、ダイバータの内外非対称性,スクレイプオフ層の流れ,プライベート領域のEXB流、及び最近のシミュレーション結果をドリフト流の観点から見直す。そして、スクレイプオフ層の巨視的なドリフト流がダイバータの内外非対称性を作り出しているメカニズムであることを提案する。
Chankin, A. V.; 朝倉 伸幸; 福田 武司; 諫山 明彦; 鎌田 裕; 三浦 幸俊; 大山 直幸; 竹治 智; 竹永 秀信
Nuclear Fusion, 42(6), p.733 - 742, 2002/06
被引用回数:21 パーセンタイル:55.68(Physics, Fluids & Plasmas)ELM時のD 光と線平均密度の振る舞いを解析した。ELMによりD
光と線平均密度の振る舞いを解析した。ELMによりD 光強度が5-20
光強度が5-20 秒で速く立ち上がる場合には、その変化が内側と外側のダイバータ部で同時に起こっている。これは、ELMで吐き出された熱がSOLを高速で移動してダイバータ部でプラズマ・壁相互作用を起こしているからである。そのため、線平均密度は、いったん上昇してから減少している。一方、D
秒で速く立ち上がる場合には、その変化が内側と外側のダイバータ部で同時に起こっている。これは、ELMで吐き出された熱がSOLを高速で移動してダイバータ部でプラズマ・壁相互作用を起こしているからである。そのため、線平均密度は、いったん上昇してから減少している。一方、D 光の立ち上がりがゆっくりしてる場合には、熱より粒子のSOL輸送でダイバータ部D
光の立ち上がりがゆっくりしてる場合には、熱より粒子のSOL輸送でダイバータ部D 光の変化が決められている(前者と比較してゆっくり起こる)。
光の変化が決められている(前者と比較してゆっくり起こる)。
Chankin, A. V.; 伊丹 潔; 朝倉 伸幸
Plasma Physics and Controlled Fusion, 44(5A), p.A399 - A405, 2002/05
被引用回数:10 パーセンタイル:33.03(Physics, Fluids & Plasmas)H-モードの密度限界は、非接触ダイバータにより決まるとのモデルがある。そこで、H-モードの密度限界のメカニズムを探るためにJT-60の高密度H-モード放電について解析を行った。MARFE及び非接触ダイバータに至る高放射損失のNBI加熱プラズマでは、非接触ダイバータとH-L遷移を切り分けることが可能であり、H-L遷移の近傍では、強い非接触ダイバータ状態がみられるが、それ自身は密度上昇を制限しない。つまり、JT-60の密度限界は、H-L遷移により引き起こされるハードな限界という見方はできるが、非接触ダイバータにより決まるとは結論できない。
Chankin, A. V.; Mukhovatov, V. S.*; 藤田 隆明; 三浦 幸俊
Europhysics Conference Abstracts (CD-ROM), 26B, 4 Pages, 2002/00
電流ホールのあるプラズマの平衡を解析するため、誘導電流+外部電流,自発電流及びPfirsh-Schluter電流を分けて扱うことができる新しいコードを開発した。電流ホール近傍をこのコードで解析した結果、電流ホールの端ではこのPfirsh-Schluter電流が支配的であり、実験的に観測されている、電流ホールのすぐ外側における急峻な電流勾配の大部分を占めていることがわかった。このような大きなPfirsh-Schluter電流は、電流ホールの強磁場側の端において局所的なX点形成を促進する負の電流を作り出すことが可能である。小半径方向に単調に増加するポロイダル磁場を有する現実的な平衡解を得るためには、Pfirsh-Schluter電流による負の電流を打ち消すために十分大きな誘導電流+外部駆動電流が電流ホールの端で流れてる必要がある。
朝倉 伸幸; Loarte, A.*; Porter, G.*; Philipps, V.*; Lipschultz, B.*; Kallenbach, A.*; Matthews, G.*; Federici, G.*; Kukushkin, A.*; Mahdavi, A.*; et al.
IAEA-CN-94/CT/P-01, 5 Pages, 2002/00
実験炉ITERダイバータ設計と運転に関する重要な以下の3つの物理課題について、既存装置(JET, JT-60U, ASDEX Upgrade, DIII-D, Alcator C-Mod and TEXTOR)の実験データやシミュレーション解析から得られた成果についてまとめた。(1)タイプ1ELMの熱負荷により、ダイバータ板の運転寿命が決まる可能性がある。ELM熱負荷のスケーリングモデルを決める物理ベースを理解するため、ELM熱流と粒子流の輸送過程に関する最新のデータから、各装置において対流熱輸送過程(convective transport)が重要であることを明らかにした。(2)境界層(SOL)におけるプラズマ流に関する各装置のデータと、ドリフト効果を導入したSOLプラズマ・シミュレーション(UEDGE)の計算結果が定性的に一致することを見いだした。ITERにおけるダイバータ設計の最適化のために、ドリフト効果の検討が必要であることを示唆した。(3)各装置における炭素ダイバータ板の化学損耗率のデータから、その表面温度,入射粒子束,吸着層の状態に関する依存性をまとめた。
三浦 幸俊; 藤田 隆明; 及川 聡洋; 鈴木 隆博; 井手 俊介; 坂本 宜照; 小出 芳彦; 波多江 仰紀; 内藤 磨; 諫山 明彦; et al.
IAEA-CN-94/EX/C3-1Ra (CD-ROM), 5 Pages, 2002/00
負磁気シア配位による先進トカマク運転では、凹状の電流分布により安全係数の極小値が磁気軸から外れて存在し、その極小値の内側に内部輸送障壁が形成されて閉じ込めが著しく改善される。この負磁気シア配位の極限状態では、トカマクの閉じ込めにとって必要不可欠であると考えられていたプラズマ電流がプラズマ中心近傍でほぼゼロとなっている(電流ホール)ことを世界で初めて発見した。しかも、半径の40%に至る領域でプラズマ電流がほぼゼロの状態が長時間安定に存在できることを世界で初めて示した。電流ホールは、内部輸送障壁部の圧力勾配による自発電流等の非誘導電流により発生する負の電場の拡散により、中心部の電流がゼロになっているように観測されており、電流ホール形成後は、ECHあるいはN-NBによる(順・逆方向)電流駆動でも電流ホール内部に(順・逆)電流が現れることはない。
藤田 隆明; 三浦 幸俊; 鈴木 隆博; 井手 俊介; 竹永 秀信; 及川 聡洋; Chankin, A. V.; 坂本 宜照; 小出 芳彦; 波多江 仰紀; et al.
Proceedings of 29th European Physical Society Conference on Plasma Physics and Controlled Fusion, 9 Pages, 2002/00
JT-60Uにおいて、モーショナルシュタルク効果(MSE)計測の測定精度の向上及び平衡コードの改良により、負磁気シアプラズマの中心部に電流がほとんど流れていない領域(「電流ホール」)が数秒間安定に存在することを明らかにした。電流ホールの半径はプラズマ半径の40%に及ぶ。これは従来必要と考えられていた磁気軸上電流がなくても安定にトカマクを運転できる可能性を示すものである。電流ホールは中心を外れた非誘導電流の増大によって形成される。興味深いのは、中心部で電流が負となる例が観測されていないことである。また、電流ホール内において、中性粒子ビームや電子サイクロトロン波による電流駆動を行った場合でも、中心部に電流が発生しない。このような電流ホールの硬直性は、それを維持する何らかの機構が働いていることを示唆している。