Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
 crystals
crystals高取 沙悠理*; Pimon, M.*; Pollitt, S.*; Bartokos, M.*; Beeks, K.*; Gr neis, A.*; 平木 貴宏*; 本間 徹生*; Hosseini, N.*; Leitner, A.*; et al.
neis, A.*; 平木 貴宏*; 本間 徹生*; Hosseini, N.*; Leitner, A.*; et al.
New Journal of Physics (Internet), 27(4), p.043024_1 - 043024_10, 2025/04
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Physics, Multidisciplinary)フッ化カルシウム単結晶中の低エネルギートリウム-229( Th)核異性体のレーザー励起に関する最近の報告は、この系が原子核時計の有望な候補であることを示している。しかし、ドープされた
Th)核異性体のレーザー励起に関する最近の報告は、この系が原子核時計の有望な候補であることを示している。しかし、ドープされた Th周辺の微視的なイオン配列とその電子状態は実験的に調べられていない。
Th周辺の微視的なイオン配列とその電子状態は実験的に調べられていない。 Th周辺のイオン配列と電子状態は、原子核時計の遷移を正確に制御し、その性能を評価するために極めて重要である。本研究では、
Th周辺のイオン配列と電子状態は、原子核時計の遷移を正確に制御し、その性能を評価するために極めて重要である。本研究では、 Th:CaF
Th:CaF のX線吸収微細構造分光を用いて、ドープされた
のX線吸収微細構造分光を用いて、ドープされた Thの電荷状態と配位環境を調べた。その結果、
Thの電荷状態と配位環境を調べた。その結果、 ThはCa
ThはCa イオンの置換サイトに4+価でドープされており、
イオンの置換サイトに4+価でドープされており、 Thに隣接する格子間サイトにある2個のF
Thに隣接する格子間サイトにある2個のF イオンによって電荷が補償されていることがわかった。
イオンによって電荷が補償されていることがわかった。
蓬田 匠; 橋本 直; 奥村 拓馬*; 山田 真也*; 竜野 秀行*; 野田 博文*; 早川 亮大*; 岡田 信二*; 高取 沙悠理*; 磯部 忠昭*; et al.
Analyst, 149(10), p.2932 - 2941, 2024/03
被引用回数:1 パーセンタイル:34.56(Chemistry, Analytical)本研究では、ウラン鉱山より採取した黒雲母に含まれるUの分布状態と化学種を分析するため、超電導転移端センサー(TES)をマイクロビーム蛍光X線分光分析時の検出器として用いる手法を開発した。通常のシリコンドリフト検出器(SDD)の約220eVのエネルギー分解能の蛍光X線スペクトルでは、13.615keVのU L
 線の蛍光X線と13.395keVのRb K
線の蛍光X線と13.395keVのRb K 線の蛍光X線を分離することは困難であった。一方、TESを用いることにより13keVのエネルギー領域で50eVのエネルギー分解能が達成され、U L
線の蛍光X線を分離することは困難であった。一方、TESを用いることにより13keVのエネルギー領域で50eVのエネルギー分解能が達成され、U L
 とRb K
とRb K の蛍光X線を完全に分離することができた。このTESを用いたピーク分離により、マイクロ蛍光X線分析における微量Uの正確なマッピング解析と、マイクロX線吸収端近傍構造分光における信号対バックグラウンド比の減少を達成できた。
の蛍光X線を完全に分離することができた。このTESを用いたピーク分離により、マイクロ蛍光X線分析における微量Uの正確なマッピング解析と、マイクロX線吸収端近傍構造分光における信号対バックグラウンド比の減少を達成できた。
 -edge for Ce in bauxites using transition-edge sensors; Implications for Ti-rich geological samples
-edge for Ce in bauxites using transition-edge sensors; Implications for Ti-rich geological samplesLi, W.*; 山田 真也*; 橋本 直; 奥村 拓馬*; 早川 亮大*; 新田 清文*; 関澤 央輝*; 菅 大暉*; 宇留賀 朋哉*; 一戸 悠人*; et al.
Analytica Chimica Acta, 1240, p.340755_1 - 340755_9, 2023/02
被引用回数:11 パーセンタイル:65.24(Chemistry, Analytical)希土類元素は放射性元素であるアクチノイドのアナログ元素としてしばしば利用される。セリウム(Ce)は希土類元素の中でも+3価と+4価の両方をとり得る特別な元素である。環境試料中のCeの+3価と+4価の比を調べる手段としてX線吸収端近傍構造(XANES)が有力であったが、チタン濃度が高いと蛍光X線の干渉のために測定ができないという問題があった。本研究では、L 吸収端だけでなくL
吸収端だけでなくL 吸収端を調べ、さらに新しい検出器であるtransition-edge sensor (TES)を利用することでこれまでは測定が難しかった試料も測定可能にした。この結果は様々な環境試料に応用可能である。
吸収端を調べ、さらに新しい検出器であるtransition-edge sensor (TES)を利用することでこれまでは測定が難しかった試料も測定可能にした。この結果は様々な環境試料に応用可能である。
樋口 恭子*; 栗田 圭輔; 酒井 卓郎; 鈴井 伸郎*; 佐々木 実莉*; 香取 摩耶*; 若林 優奈*; 間嶋 勇太*; 齋藤 彰宏*; 大山 卓爾*; et al.
Plants (Internet), 11(6), p.817_1 - 817_11, 2022/03
被引用回数:3 パーセンタイル:25.88(Plant Sciences)植物は様々な鉄獲得機構を発達させてきたが、植物による鉄獲得速度の遺伝的多様性については植物種や遺伝子型間で広く調査されていない。我々は、 Feを用いたライブオートラジオグラフィー技術を用いて、オオムギ品種における極低濃度のFe溶液からのFe吸収速度を直接評価した。この結果、オオムギの品種間において、低濃度Fe溶液からFeを獲得する能力が、必ずしもFe欠乏に対する耐性を決定する唯一の要因ではないことが明らかとなった。
Feを用いたライブオートラジオグラフィー技術を用いて、オオムギ品種における極低濃度のFe溶液からのFe吸収速度を直接評価した。この結果、オオムギの品種間において、低濃度Fe溶液からFeを獲得する能力が、必ずしもFe欠乏に対する耐性を決定する唯一の要因ではないことが明らかとなった。
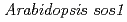 mutant in a salt-tolerant accession revealed an importance of salt acclimation ability in plant salt tolerance
mutant in a salt-tolerant accession revealed an importance of salt acclimation ability in plant salt tolerance有賀 裕剛*; 香取 拓*; 吉原 亮平*; 長谷 純宏; 野澤 樹; 鳴海 一成; 井内 聖*; 小林 正智*; 手塚 健二*; 坂田 洋一*; et al.
Plant Signaling & Behavior (Internet), 8(7), p.e24779_1 - e24779_5, 2013/07
シロイヌナズナの354系統の中には、NaCl濃度を0mMから225mmに急激に変化させる試験において、対照となるCol-0系統に比べて高い耐塩性を示す系統がある。また、Zu-Oを含む数系統では、中程度の塩ストレスに暴露された後に高い耐塩性が誘導される。したがって、シロイヌナズナは塩ショックに対する耐性と塩馴化による耐性の少なくとも2種類の耐性機構を有すると思われる。シロイヌナズナの耐塩性系統の耐性メカニズムを明らかにするため、われわれはイオンビームで変異処理したZu-0の実生から塩感受性の変異体を単離した。この変異体は、SOS1遺伝子の1塩基欠失によって塩ショックストレス下で著しい生育抑制を示し、Col-0よりも塩に感受性である。しかし、この変異体はZu-0と同様に、100mMのNaClに7日間暴露した後に750mMのソルビトールに20日間暴露した後も生育することができるが、Col-0は同条件において明らかな白化を示した。したがって、塩馴化に必要な遺伝子は塩ショック耐性に必要な遺伝子とは異なり、塩や浸透圧耐性の獲得に重要な役割を果たしていると考えられる。
 O
O
松田 雅昌; Chung, J.-H.*; Park, S.*; 佐藤 卓*; 松野 謙一郎*; 香取 浩子*; 高木 英典*; 加倉井 和久; 蒲沢 和也*; 角田 頼彦*; et al.
Europhysics Letters, 82(3), p.37006_1 - 37006_5, 2008/05
被引用回数:22 パーセンタイル:71.26(Physics, Multidisciplinary)GeNi O
O は立方晶スピネル構造を有しており、低温でNi
は立方晶スピネル構造を有しており、低温でNi モーメント(
モーメント( =1)が反強磁性長距離秩序を示す。(この物質は構造相転移を起こさず、磁気秩序相でも立方晶のままである。)比熱や磁化の測定により、磁気転移が
=1)が反強磁性長距離秩序を示す。(この物質は構造相転移を起こさず、磁気秩序相でも立方晶のままである。)比熱や磁化の測定により、磁気転移が =12.1Kと
=12.1Kと =11.4Kで起こることがわかっている。この逐次磁気相転移は、磁気フラストレーションに由来しているものと予想される。われわれは、中性子散乱実験により2つの磁気相における磁気構造を調べた。その結果、
=11.4Kで起こることがわかっている。この逐次磁気相転移は、磁気フラストレーションに由来しているものと予想される。われわれは、中性子散乱実験により2つの磁気相における磁気構造を調べた。その結果、 以下ではカゴメ格子面内のスピンのみが磁気秩序化することがわかった(部分無秩序相)。磁気配列は面内が強磁性的で、面間が反強磁性的である。
以下ではカゴメ格子面内のスピンのみが磁気秩序化することがわかった(部分無秩序相)。磁気配列は面内が強磁性的で、面間が反強磁性的である。 以下では三角格子面内のスピンの秩序化も加わることがわかった。
以下では三角格子面内のスピンの秩序化も加わることがわかった。
蓬田 匠; 山田 真也*; 一戸 悠人*; 佐藤 寿紀*; 早川 亮大*; 岡田 信二*; 外山 裕一*; 橋本 直; 野田 博文*; 磯部 忠昭*; et al.
no journal, ,
環境中でのウランの固定化に関する知見を得るため、層状ケイ酸塩鉱物である黒雲母によるウランの還元反応を研究している。黒雲母中に共存するルビジウムの干渉を除去し、ウランの化学種を調べるため、超伝導転移端センサーとX線発光分光器を利用して黒雲母中のウランの化学種を調べた。その結果、旧ウラン鉱床より採取した黒雲母の化学種を調べることが可能になり、黒雲母中のウランの一部が還元されていることを明らかにした。
香取 拓馬*; 小林 健太*; 安江 健一; 丹羽 正和; 小松 哲也; 細矢 卓志*; 笹尾 英嗣
no journal, ,
百万年以上の時間スケールの地形・地質モデルの構築において重要となる断層の発達史に関する調査技術の開発に資するため、東濃地域の屏風山断層を対象とした断層岩の構造解析および化学分析を行った。露頭および薄片観察の結果、断層破砕帯は複数の種類の断層岩に区分され、断層岩によって異なる運動センスを示すことが分かった。粉末X線回折分析による変質鉱物の分布や、蛍光X線分析による化学組成も断層岩ごとに明瞭な違いが見られる。以上の観察および分析に基づくと、断層破砕帯には異なる深度・応力場における複数のステージの活動が保存されている可能性が高い。
香取 拓馬*; 小林 健太*; 丹羽 正和; 清水 麻由子; 小松 哲也; 安江 健一; 堀内 泰治
no journal, ,
活断層とされる屏風山断層(活断層研究会, 1991)を事例に、その運動史を解明する調査技術開発を目的とした、断層岩の組織観察及び化学分析を行った。本研究では、断層活動に伴う変形・変質作用を検討するため、偏光顕微鏡及びSEMを用いた組織観察、RockJock(Eberl, 2003)を用いたXRD定量分析, XGT面分析, EPMA面分析を行った。これらの解析及び分析の結果から、屏風山断層を構成する断層ガウジ帯は、複数の運動履歴を記録しており、その変形・変質作用には優位な違いが存在することが分かった。特に流動変形が見られる断層ガウジの組織は、多量の流体の存在を示し、イライトに富むことから比較的高温(200 C前後)の地下水が流入して形成されたと考えられる。また、斜長石の溶脱組織は、反応軟化を促進させる環境下での変形を示唆する可能性がある。本発表では、屏風山断層の断層ガウジ帯に着目し、変形・変質作用の変遷について議論する。
C前後)の地下水が流入して形成されたと考えられる。また、斜長石の溶脱組織は、反応軟化を促進させる環境下での変形を示唆する可能性がある。本発表では、屏風山断層の断層ガウジ帯に着目し、変形・変質作用の変遷について議論する。
樋口 恭子*; 佐々木 実莉*; 香取 摩耶*; 栗田 圭輔; 酒井 卓郎; 鈴井 伸郎*; 河地 有木*; 齋藤 彰宏*; 大山 卓爾*
no journal, ,
硫黄輸送に関わる遺伝子の発現は、Feの枯渇によって低下する。そのパターンと時期はオオムギ品種によって異なり、その違いは鉄欠乏条件下での光化学系Iの維持に関係していると考えられる。しかし、これらのオオムギ品種の特性は、Fe欠乏に対する全体的な耐性や葉の総Fe濃度とは必ずしも相関していない。そこで、Fe欠乏オオムギの新葉へのFe流入とSUF機構の発現低下との関係を調べた。
太治 輝昭*; 香取 拓*; 有賀 裕剛*; 井内 聖*; 小林 正智*; 篠崎 一雄*; 吉原 亮平; 野澤 樹; 長谷 純宏; 鳴海 一成; et al.
no journal, ,
モデル植物シロイヌナズナは、世界中に1000種ものエコタイプが存在し、近年の研究から、さまざまな表現型に大きなバリエーションが観察されている。そこで、350種のエコタイプを用いて耐塩性評価を行ったところ、海水と同程度の塩濃度でも耐性を示すエコタイプの存在を明らかにした。塩耐性エコタイプが有する耐性メカニズムを生理学的に解析した結果、シロイヌナズナの耐塩性は、急激な塩濃度の変化に対応する「塩ショック耐性」と、生育に影響を与えない程度の塩ストレスを一定期間経ることで、海水程度の塩水(浸透圧)にも耐性を示す「塩馴化能」の2つで構成され、極めて高い耐塩性を示すには「塩馴化能」が重要であることが示唆された。これら2つの耐塩性メカニズムについて遺伝学的な解析を行ったところ、「塩ショック耐性」は複数の遺伝子座が寄与するのに対して、「塩馴化能」については、1遺伝子座の制御によることが示された。現在、genome-wide association studyを含む遺伝学的解析により塩馴化能遺伝子の同定を試みている。
蓬田 匠; 山田 真也*; 一戸 悠人*; 佐藤 寿紀*; 早川 亮大*; 岡田 信二*; 外山 裕一*; 橋本 直; 野田 博文*; 磯部 忠昭*; et al.
no journal, ,
黒雲母は、人形峠や東濃の旧ウラン鉱床中でウラン(U)を保持するホスト相として知られており、黒雲母中に含まれるUの分布を調べることでUの濃集・長期固定化に関する知見が得られると期待される。しかし、黒雲母は蛍光X線の分析時に測定妨害となるルビジウム(Rb)を含んでおり、通常の半導体検出器を用いた測定では、黒雲母中での正確なU-Rbの分布状態の把握が困難であった。本研究では、超電導転移端センサー(TES)をマイクロビーム蛍光X線分析時の検出器として用いる手法を開発した。TESを検出器として用いることにより、約20eV程度のエネルギー分解能での蛍光X線の検出が可能となり、従来通常の半導体検出器でピーク分離が困難だった13.373keVのRb K 線と13.612keVのU L
線と13.612keVのU L 線を完全に分離できた。そのため、開発した手法を用いることによって、黒雲母中での正確なU-Rbの分布状態の把握が可能になった。
線を完全に分離できた。そのため、開発した手法を用いることによって、黒雲母中での正確なU-Rbの分布状態の把握が可能になった。
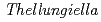 のイオンビーム照射種子を用いた塩高感受性変異株の単離
のイオンビーム照射種子を用いた塩高感受性変異株の単離堀口 茜*; 有賀 裕剛*; 五十嵐 純子*; 香取 拓*; 坂田 洋一*; 林 隆久*; 太治 輝昭*; 吉原 亮平; 野澤 樹; 長谷 純宏; et al.
no journal, ,
本研究では、自然界で高い塩耐性を示す植物の耐性メカニズムを遺伝学的に明らかにするため、イオンビーム照射により変異誘導させた種子を用いて、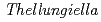 における塩高感受性変異株、耐塩性
における塩高感受性変異株、耐塩性 Zu-0における塩馴化欠損変異株及びアブシジン酸低感受性変異株を単離することを目的として研究を行った。これまでに、
Zu-0における塩馴化欠損変異株及びアブシジン酸低感受性変異株を単離することを目的として研究を行った。これまでに、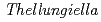 の塩高感受性変異候補株を11個体選抜した。
の塩高感受性変異候補株を11個体選抜した。 については、塩馴化欠損変異候補株を3個体、アブシジン酸低感受性変異候補株を7個体得た。現在、原因遺伝子のマッピングを行っている。
については、塩馴化欠損変異候補株を3個体、アブシジン酸低感受性変異候補株を7個体得た。現在、原因遺伝子のマッピングを行っている。