Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
吉村 宣倖*; 外山 毅*; 菖蒲田 義博; 中村 剛*; 大見 和史*; 小林 愛音*; 岡田 雅之*; 佐藤 洋一*; 中家 剛*
Proceedings of 20th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan (インターネット), p.260 - 264, 2023/11
-PARCメインリング(MR)の出力は1.3MWに増強される予定である。そのために、イントラバンチフィードバックシステム(IBFB)を最大約200MHzまでの高い周波数に対応できるようにアップグレードする必要がある。このアップグレード後の性能を評価し、最適なパラメータを理解するために、現在、必要なコンポーネントを含む粒子トラッキングシミュレーションを開発している。その結果、色収差によって引き起こされるビームのリコヒーレンス時間を、トラッキングシミュレーションと実験との間で比較し、それが単純なシミュレーションでは説明できないことを確認した。現在、この結果を説明するメカニズムを調査しているが、縦方向のインピーダンスの効果のみでは、この実験結果を説明できないことがわかった。
吉村 宣倖*; 外山 毅*; 小林 愛音*; 中村 剛*; 岡田 雅之*; 菖蒲田 義博; 中家 剛*
Proceedings of 19th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan (インターネット), p.936 - 941, 2023/01
大強度陽子シンクロトロンJ-PARC Main Ring (MR)は現在の510kW ( ppp, MRサイクル2.48秒)から1.3MW (
ppp, MRサイクル2.48秒)から1.3MW ( ppp, 1.16秒)へと大強度化する予定である。大強度のビームは、それが引き起こすウェイク場や電子雲などによりビームの振動が不安定になるために、ビーム損失が発生する。これを抑制するためにビーム位置モニター(BPM), FPGA, ストリップラインキッカーを用いたintra-bunch feedback system (IBFB)がMRに設置されている。ビーム強度が増強されると横方向不安定性がさらに増大してビームを実験施設に安定供給する制限要因となることが予想される。現在、対策として今後1,2年でIBFBを新システムに更新して200MHzの高周波の振動にも対応させることが計画されている。今回、この事前調査として(100MHzまでの振動に対応した)現行システムのIBFBの性能限界を6月に行われたビーム試験でのデータをもとに評価した。
ppp, 1.16秒)へと大強度化する予定である。大強度のビームは、それが引き起こすウェイク場や電子雲などによりビームの振動が不安定になるために、ビーム損失が発生する。これを抑制するためにビーム位置モニター(BPM), FPGA, ストリップラインキッカーを用いたintra-bunch feedback system (IBFB)がMRに設置されている。ビーム強度が増強されると横方向不安定性がさらに増大してビームを実験施設に安定供給する制限要因となることが予想される。現在、対策として今後1,2年でIBFBを新システムに更新して200MHzの高周波の振動にも対応させることが計画されている。今回、この事前調査として(100MHzまでの振動に対応した)現行システムのIBFBの性能限界を6月に行われたビーム試験でのデータをもとに評価した。
岡田 翔太; 村上 昌史; 河内山 真美; 出雲 沙理; 坂井 章浩
JAEA-Testing 2022-002, 66 Pages, 2022/08
日本原子力研究開発機構は、我が国の研究施設等から発生する低レベル放射性廃棄物の埋設事業の実施主体である。これらの廃棄物中の放射能濃度は、廃棄物埋設地の設計や埋設事業の許可申請をする上で必要な廃棄物情報である。埋設事業の処分対象となる廃棄物は、施設の解体に伴って発生する解体廃棄物が多くを占めている。このため、埋設事業センターでは、試験研究用原子炉の解体廃棄物を対象として、理論計算法による放射能濃度の評価手順の検討を行い、試験研究用原子炉に共通的な評価手順についてとりまとめた。本書で示す手順は、放射化計算により放射能インベントリを決定し、その妥当性を評価した後、処分区分の判定並びに処分区分毎の総放射能及び最大放射能濃度を整理するというものである。放射能インベントリの決定においては、まず2次元又は3次元の中性子輸送計算コードを用いて原子炉施設の各領域における中性子束及びエネルギースペクトルを計算する。その後、それらの計算結果に基づき、放射化計算コードを用いて、140核種を対象として放射化放射能を計算する。本書では、中性子輸送計算コードとして、2次元離散座標計算コードのDORT、3次元離散座標計算コードのTORT又はモンテカルロ計算コードのMCNPとPHITS、放射化計算コードとしてORIGEN-Sを使用することを推奨する。その他、利用を推奨する断面積データライブラリや計算条件等についても示す。評価手順のとりまとめに際しては、日本原子力研究開発機構外部の試験研究用原子炉の設置者と定期的に開催している会合において、各事業者が共通的に利用できるようについて意見交換を実施した。本書で示す手順は、今後の埋設事業の進捗や埋設事業に係る規制の状況等を反映して、適宜見直し及び修正をしていく予定である。
中川 明憲; 及川 敦; 村上 昌史; 吉田 幸彦; 佐々木 紀樹; 岡田 翔太; 仲田 久和; 菅谷 敏克; 坂井 章浩; 坂本 義昭
JAEA-Technology 2021-006, 186 Pages, 2021/06
日本原子力研究開発機構が保管する放射性廃棄物のうち、一部の放射性廃棄物については過去に未分別のまま圧縮等の処理が行われていた。このため、埋設処分に向けて圧縮されたものを分解して確認する等の作業に多くの時間が必要であると想定され、放射性廃棄物の早期のリスク低減を行う方策について、廃棄物処理及び埋設処分の2つの観点から検討を実施した。前処理,処理及び固型化といった廃棄物処理作業の中で時間を要している工程を分析し、放射能濃度評価、有害物等の分別、及び可燃物の分別といった課題を抽出した。放射能濃度評価に関しては、保守的な核種組成比と非破壊 線測定による廃棄体中の放射能濃度評価方法の検討、及びトレンチ埋設施設構造の高度化を図るとともに、評価対象核種の選定に一定の基準を設定することにより、評価対象核種を絞り込める可能性があることを明らかにした。有害物等の分別に関しては、非破壊検査と記録・有害物使用状況等による分別の要否の確認により、分別作業を大幅に削減できる見込みが得られた。また、廃棄物から地下水中に移行した重金属による地下水中濃度を評価し、水質に関する環境基準を遵守可能な廃棄体中に含有される濃度として受入基準を提示した。可燃物の分別に関しては、埋設施設内空隙増加による陥没の影響を評価し、覆土での事前対応が可能な可燃物含有量を評価するとともに、非破壊検査による可燃物量の確認と、解体で発生するコンクリートのような可燃物含有量が少ない廃棄物との混合埋設により、埋設処分場内の廃棄物層の平均的な可燃物の含有割合を20vol%とする定置管理を行い、分別作業を不要にできる見込みが得られた。原子力科学研究所の圧縮体を例に、これらの方策を施すことによる廃棄物処理加速の効果についての評価を実施し、廃棄物の分別処理作業を約5倍加速できる見込みが得られた。今後、検討した対策の実現に向けた対応を進める。
線測定による廃棄体中の放射能濃度評価方法の検討、及びトレンチ埋設施設構造の高度化を図るとともに、評価対象核種の選定に一定の基準を設定することにより、評価対象核種を絞り込める可能性があることを明らかにした。有害物等の分別に関しては、非破壊検査と記録・有害物使用状況等による分別の要否の確認により、分別作業を大幅に削減できる見込みが得られた。また、廃棄物から地下水中に移行した重金属による地下水中濃度を評価し、水質に関する環境基準を遵守可能な廃棄体中に含有される濃度として受入基準を提示した。可燃物の分別に関しては、埋設施設内空隙増加による陥没の影響を評価し、覆土での事前対応が可能な可燃物含有量を評価するとともに、非破壊検査による可燃物量の確認と、解体で発生するコンクリートのような可燃物含有量が少ない廃棄物との混合埋設により、埋設処分場内の廃棄物層の平均的な可燃物の含有割合を20vol%とする定置管理を行い、分別作業を不要にできる見込みが得られた。原子力科学研究所の圧縮体を例に、これらの方策を施すことによる廃棄物処理加速の効果についての評価を実施し、廃棄物の分別処理作業を約5倍加速できる見込みが得られた。今後、検討した対策の実現に向けた対応を進める。
 dosimetry system based on an optical fiber-coupled microsized photostimulable phosphor for stereotactic body radiation therapy
dosimetry system based on an optical fiber-coupled microsized photostimulable phosphor for stereotactic body radiation therapy矢田 隆一*; 前中 一介*; 宮本 修治*; 岡田 豪*; 笹倉 亜規*; 芦田 基*; 足立 真士*; 佐藤 達彦; Wang, T.*; 赤坂 浩亮*; et al.
Medical Physics, 47(10), p.5235 - 5249, 2020/10
被引用回数:9 パーセンタイル:50.10(Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging)光ファイバーとマイクロサイズ光刺激蛍光体を組み合わせた定位放射線治療のためのリアルタイム体内線量評価システムを開発した。開発したシステムの線量応答の線形性,線量率依存性,温度依存性などを医療用Linacを用いて検証した。また、測定値と粒子・重イオン輸送計算コードPHITSによる計算値を比較し、その妥当性を確認した。これらの結果より、開発したシステムが定位放射線治療のリアルタイム体内線量評価システムとして十分な性能を有することを確認した。
阿部 充志*; Bae, S.*; Beer, G.*; Bunce, G.*; Choi, H.*; Choi, S.*; Chung, M.*; da Silva, W.*; Eidelman, S.*; Finger, M.*; et al.
Progress of Theoretical and Experimental Physics (Internet), 2019(5), p.053C02_1 - 053C02_22, 2019/05
被引用回数:161 パーセンタイル:99.30(Physics, Multidisciplinary)この論文はJ-PARCにおける、ミューオン異常磁気モーメント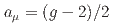 と電気双極子モーメント(EDM)
と電気双極子モーメント(EDM)  を測定する新しいアプローチを紹介する。我々の実験のゴールは、これまでと独立の、1/10の運動量と1/20のストレージリングを用いて、
を測定する新しいアプローチを紹介する。我々の実験のゴールは、これまでと独立の、1/10の運動量と1/20のストレージリングを用いて、 と
と をこれまでにない精密な磁場で測定することである。さらに過去の実験との顕著な違いは、1/1000の横エミッタンスミューオンビーム(サーマルミューオンビーム)を用い、効率的なソレノイドへ縦入射し、ミューオンからの崩壊陽電子をトラッキングし、その小さな運動量ベクトルを求める点である。
をこれまでにない精密な磁場で測定することである。さらに過去の実験との顕著な違いは、1/1000の横エミッタンスミューオンビーム(サーマルミューオンビーム)を用い、効率的なソレノイドへ縦入射し、ミューオンからの崩壊陽電子をトラッキングし、その小さな運動量ベクトルを求める点である。 は統計精度450ppb、系統誤差70ppb、EDMについては
は統計精度450ppb、系統誤差70ppb、EDMについては e
e cmの精度で測定することを目標とする。
cmの精度で測定することを目標とする。
岡田 雅之*; 仁木 和昭*; 平山 賀一*; 今井 伸明*; 石山 博恒*; Jeong, S. C.*; 片山 一郎*; 宮武 宇也*; 小柳津 充広*; 渡辺 裕*; et al.
Physical Review Special Topics; Accelerators and Beams, 15(3), p.030101_1 - 030101_10, 2012/03
被引用回数:5 パーセンタイル:31.92(Physics, Nuclear)A novel beam-bunching technique has been implemented at a heavy-ion linear accelerator facility by installing a compact two-gap prebuncher and a multi-layer beam chopper. A pulsed beam of 2 to 4 MHz, having kinetic energy up to 1.1 MeV/u, is realized by bunching 2 keV/u continuous beams just upstream of the linac. Around 40% of the continuous beam particles are successively gathered in a single micro-bunch with a time width of around 15 ns in units of full-width at one-tenth maximum. The number of background beam particles over 250 ns just before the bunched beam is well suppressed to less than 10 of the number of bunched particles. This technique has been adopted to generate intense
of the number of bunched particles. This technique has been adopted to generate intense  -particle beams for nuclear astrophysics experiments.
-particle beams for nuclear astrophysics experiments.
守田 幸路*; Zhang, S.*; 越塚 誠一*; 飛田 吉春; 山野 秀将; 白川 典幸*; 井上 方夫*; 油江 宏明*; 内藤 正則*; 岡田 英俊*; et al.
Nuclear Engineering and Design, 241(12), p.4672 - 4681, 2011/12
被引用回数:19 パーセンタイル:78.40(Nuclear Science & Technology)2005年から開始した研究プロジェクトでナトリウム冷却高速炉(SFR)の炉心損傷事故(CDA)の重点現象を詳細解析するためにMPS法に基づいたCOMPASSコードを開発している。その着目現象とは、燃料ピン破損・崩壊,溶融プール沸騰,融体固化・閉塞挙動,ダクト壁破損,低エネルギー崩壊炉心の運動,デブリベッド冷却性,金属燃料ピン破損を含んでいる。これらの主要現象に対して、COMPASSの検証研究が進められている。この論文では、幾つかの着目現象に対するCOMPASSによる詳細解析結果をまとめた。本結果は、COMPASSコードがSFRのCDAの重要現象を理解及び解明するのに有用であることを示している。
越塚 誠一*; 守田 幸路*; 有馬 立身*; 飛田 吉春; 山野 秀将; 伊藤 高啓*; 内藤 正則*; 白川 典幸*; 岡田 英俊*; 上原 靖*; et al.
Proceedings of 8th International Topical Meeting on Nuclear Thermal-Hydraulics, Operation and Safety (NUTHOS-8) (CD-ROM), 11 Pages, 2010/10
本論文では、COMPASSコード開発の2009年度成果を報告する。融体固化・閉塞形成,金属燃料の共晶反応,ダクト壁破損(熱流動解析),燃料ピン破損、及びダクト壁破損(構造解析)に関する検証計算が示される。位相計算,古典及び第一原理分子動力学研究は金属燃料とスティール及び制御棒材料とスティールの共晶反応の物性を調べるために用いられた。粒子法の基礎研究やSIMMER計算もまたCOMPASSコード開発に役立った。COMPASSは、SIMMERコードで用いられている実験相関式の基盤を明らかにするものと期待される。SIMMERとCOMPASSの結合はCDAの安全評価並びに炉心設計最適化に有効になるだろう。
守田 幸路*; Zhang, S.*; 有馬 立身*; 越塚 誠一*; 飛田 吉春; 山野 秀将; 伊藤 高啓*; 白川 典幸*; 井上 方夫*; 油江 宏明*; et al.
Proceedings of 18th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE-18) (CD-ROM), 9 Pages, 2010/05
2005年から開始した5年間の研究プロジェクトで、ナトリウム冷却高速炉の炉心損傷事故特有の現象を詳細解析するためにMPS法に基づいたCOMPASSコードを開発している。その特有の現象とは、(1)燃料ピン破損・崩壊,(2)溶融プール沸騰,(3)融体固化・閉塞挙動,(4)ダクト壁破損,(5)低エネルギー崩壊炉心の運動,(6)デブリベッド冷却性,(7)金属燃料ピン破損を含んでいる。これらの主要現象に対して、COMPASSの検証研究が進められている。この論文では、幾つかの特有現象に対するCOMPASSによる詳細解析結果をまとめた。
外山 毅*; 荒川 大*; 平松 成範*; 五十嵐 進*; Lee, S.*; 松本 浩*; 小田切 淳一*; 手島 昌己*; 飛山 真理*; 橋本 義徳*; et al.
Proceedings of 1st International Particle Accelerator Conference (IPAC '10) (Internet), p.981 - 983, 2010/05
J-PARC MRのビームコミッショニング中のBPMの運用経験について報告する。サブジェクトは、(1)特にビームダクトの段差の影響,(2)1秒平均に対し30ミクロンの位置分解能,(3)ビームを使った位置校正である。
越塚 誠一*; 守田 幸路*; 有馬 立身*; Zhang, S.*; 飛田 吉春; 山野 秀将; 伊藤 高啓*; 内藤 正則*; 白川 典幸*; 岡田 英俊*; et al.
Proceedings of 13th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal Hydraulics (NURETH-13) (CD-ROM), 11 Pages, 2009/09
COMPASSコードにより溶融炉心物質の分散・固化が計算され、GEYSER実験データと比較された。溶融炉心物質が配管内面を固化しながら流れていった。溶融プール挙動について、固体スティール球が固体燃料により囲まれた体系であるCABRI-TPA2実験が解析された。スティール球の溶融と沸騰を引き起こすために出力が印加された。SCARABEE-BE+3試験もダクト壁破損の検証としてCOMPASSコードにより解析された。
森 道昭; 桐山 博光; 吉村 政志*; 森 勇介*; 岡田 大; 重森 啓介*
プラズマ・核融合学会誌, 85(6), p.389 - 392, 2009/06
非線形光学結晶は汎用性の高いツールであるため、授業や参考書などを通じて比較的学問として触れる機会は多い。しかし、近年では非線形光学結晶においてはCLBOやYGCOBなどの短波長用非線形光学結晶の開発が行われるなど非常に多彩になってきており、また非線形光学結晶を用いた応用としても、10フェムト秒以下の高調波変換や縮退四光波混合によるOPCPA(光パラメトリックチャープパルス増幅)(増幅器)などの新たな進展。さらにこれらの進展に伴い、プラズマ物理研究でも例えば前述のOPCPAにおいては既存の増幅法と比較して高コントラスト性が期待できることから、それを導入したレーザーを用い超高強度レーザープラズマ相互作用によってMeV級陽子線発生が行われるなど、プラズマ研究に対しても大きく進展している。また、レーザー核融合においても非線形光学結晶から得られる高次高調波と基本波をハイブリッドさせ、基本波照射・高調波照射それぞれの長所を活かし効率的な爆縮を得る取り組みも行われている。このような動きも含め、本講座では「非線形光学結晶とプラズマ研究への応用」と題し、非線形光学結晶について基礎を中心に、最近のトレンドやプラズマ研究への利用など最近のトレンドについて取り上げる。
越塚 誠一*; 守田 幸路*; 有馬 立身*; Zhang, S.*; 飛田 吉春; 山野 秀将; 伊藤 高啓*; 白川 典幸*; 内藤 正則*; 岡田 英俊*; et al.
Proceedings of 16th Pacific Basin Nuclear Conference (PBNC-16) (CD-ROM), 6 Pages, 2008/10
ナトリウム冷却高速炉(SFR)における炉心損傷事故(CDA)のさまざまな複合現象に対して、COMPASSと名づけられたコンピューターコードを開発している。COMPASSコードは、Moving Particle Semi-implicit(MPS)手法という枠組みの中で、熱流動・構造・相変化を含むマルチフィジックス問題を解析するように設計されている。その開発プロジェクトが、2005年度から2009年度までの5年間で、6組織により実施されてきた。本論文では、2007年度におけるプロジェクトの成果が報告される。検証計画に従って、融体固化・閉塞形成,溶融プール沸騰,ダクト壁破損の3つの検証計算が行われた。また、COMPASSコード開発をサポートするため、数値計算手法の基礎研究,金属燃料の共晶反応に関する物質科学、及びSIMMER-IIIによる解析が行われた。
今井 伸明*; Jeong, S.-C.*; 小柳津 充広*; 新井 重昭*; 渕 好秀*; 平山 賀一*; 石山 博恒*; 宮武 宇也; 田中 雅彦*; 岡田 雅之*; et al.
Review of Scientific Instruments, 79(2), p.02A906_1 - 02A906_3, 2008/02
被引用回数:13 パーセンタイル:50.73(Instruments & Instrumentation)KEKCBは、18GHzの電子共鳴型(ECR)イオン源で、タンデムに設置された短寿命核分離加速実験装置(TRIAC)の一部として、上流で生成され質量分離された短寿命原子核の1+イオンを、ビーム軸上のECRプラズマに入射することで、多価のイオンへその場変換する装置である。これまでの開発研究によって、クリプトン,キセノン等のガス状元素やバリウム,インジウム等の非ガス状元素に対して、質量/電荷比が7以下の多価イオンにまで変換する効率を、それぞれ7%, 2%にまで向上することができた。また、短寿命な同位元素による測定と比較することで、この変換効率は、1秒程度の半減期を持つ同位元素に対しては、変わらないことを確かめた。従来見られていた出力ビーム中のバックグランドは、プラズマ壁及び電極の全アルミ化,高圧純水洗浄等により、10 ppsから600ppsにまで落とすことができた。
ppsから600ppsにまで落とすことができた。
松田 誠; 竹内 末広; 月橋 芳廣; 花島 進; 阿部 信市; 長 明彦; 石崎 暢洋; 田山 豪一; 仲野谷 孝充; 株本 裕史; et al.
Proceedings of 3rd Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan and 31st Linear Accelerator Meeting in Japan, p.275 - 277, 2006/00
2005年度のタンデム加速器の運転日数は182日であった。加速管の更新により最高端子電圧は19.1MVに達し18MVでの実験利用が開始された。利用イオン種は21元素(28核種)であり、 Oの利用が全体の約2割で、おもに核化学実験に利用された。p,
Oの利用が全体の約2割で、おもに核化学実験に利用された。p,  Li,
Li,  Xeの利用はそれぞれ約1割を占め、p,
Xeの利用はそれぞれ約1割を占め、p,  LiはおもにTRIACの一次ビームに利用された。超伝導ブースターの運転日数は34日で、昨年度から始まったTRIACの実験利用は12日であった。開発事項としては、タンデム加速器では加速管を更新し最高電圧が19MVに達した。また高電圧端子内イオン源の14.5GHzECRイオン源への更新計画が進行している。超伝導ブースターは1994年以来高エネルギービームの加速に利用されてきたが、近年になりインジウムガスケットに起因する真空リークが発生している。空洞のQ値も下がってきており、対策として空洞に高圧超純水洗浄を施し性能を復活させる試験を進めている。KEKと共同で進めてきたTRIACは2005年3月に完成し、10月から利用が開始された。TRIACからのビームを超伝導ブースターにて5
LiはおもにTRIACの一次ビームに利用された。超伝導ブースターの運転日数は34日で、昨年度から始まったTRIACの実験利用は12日であった。開発事項としては、タンデム加速器では加速管を更新し最高電圧が19MVに達した。また高電圧端子内イオン源の14.5GHzECRイオン源への更新計画が進行している。超伝導ブースターは1994年以来高エネルギービームの加速に利用されてきたが、近年になりインジウムガスケットに起因する真空リークが発生している。空洞のQ値も下がってきており、対策として空洞に高圧超純水洗浄を施し性能を復活させる試験を進めている。KEKと共同で進めてきたTRIACは2005年3月に完成し、10月から利用が開始された。TRIACからのビームを超伝導ブースターにて5 8MeV/uのエネルギーまで加速する計画を進めており、TRIACからの1.1MeV/uのビームを効率よく加速するため、low
8MeV/uのエネルギーまで加速する計画を進めており、TRIACからの1.1MeV/uのビームを効率よく加速するため、low 空洞の開発を行っている。
空洞の開発を行っている。
今井 伸明*; Jeong, S.-C.*; 小柳津 充広*; 新井 重昭*; 渕 好秀*; 平山 賀一*; 石山 博恒*; 宮武 宇也; 田中 雅彦*; 岡田 雅之*; et al.
no journal, ,
KEKCBはTRIACにおける一価のイオンを多価イオンに変換するためのECR型イオン源である。KEKCBを用いることで、一価の気体イオン及び非気体イオンを、A/q 7について、それぞれ7%及び2%の効率で多価イオンに変換することができた。これらの効率は秒オーダーでは半減期によらないことがわかった。また、3つのコリメータをKEKCBの前後に設置してビーム軸を規定することで、KEKCBへのビーム入射時のビームハンドリングが容易となった。さらに、電極及びプラズマチェンバー表面の研磨・洗浄により、KEKCBのECRプラズマからの不純物が劇的に減少した。
7について、それぞれ7%及び2%の効率で多価イオンに変換することができた。これらの効率は秒オーダーでは半減期によらないことがわかった。また、3つのコリメータをKEKCBの前後に設置してビーム軸を規定することで、KEKCBへのビーム入射時のビームハンドリングが容易となった。さらに、電極及びプラズマチェンバー表面の研磨・洗浄により、KEKCBのECRプラズマからの不純物が劇的に減少した。
 Li(d,t)
Li(d,t) Li reaction
Li reaction橋本 尚志; 宮武 宇也; 光岡 真一; 西尾 勝久; 佐藤 哲也; 市川 進一; 長 明彦; 松田 誠; 石山 博恒*; 渡辺 裕*; et al.
no journal, ,
宇宙初期での非一様ビッグバン模型や超新星爆発中の元素合成過程においては中性子過剰な環境が作られるため、原子核反応の経路は安定線よりややずれて中性子過剰核を経由して進むと予想される。この過程において Liは安定核の存在しない質量数8を越える鍵となる元素として注目されている。われわれのグループでは
Liは安定核の存在しない質量数8を越える鍵となる元素として注目されている。われわれのグループでは Liの関与する反応の断面積を測定することで反応経路を明らかにすることを目的として実験を行っている。最も注目される反応である
Liの関与する反応の断面積を測定することで反応経路を明らかにすることを目的として実験を行っている。最も注目される反応である Li(
Li( ,n)
,n) Bの測定に引き続き、TRIACで
Bの測定に引き続き、TRIACで Li(d,t)
Li(d,t) Li,
Li,  Li(d,p)
Li(d,p) Li,
Li,  Li(d,
Li(d, )
) Heの反応断面積の測定を行った。この実験で重心系1.5MeV以下のエネルギーにおける反応断面積を世界で初めて測定することができた。また、
Heの反応断面積の測定を行った。この実験で重心系1.5MeV以下のエネルギーにおける反応断面積を世界で初めて測定することができた。また、 Li(d,t)
Li(d,t) Li反応では重心系0.8MeVに異常に大きな断面積の増大が見られた。これは複合核である
Li反応では重心系0.8MeVに異常に大きな断面積の増大が見られた。これは複合核である Beに22.4MeVの新たな励起状態が存在することを示唆する。本講演ではこの
Beに22.4MeVの新たな励起状態が存在することを示唆する。本講演ではこの Li(d,t)
Li(d,t) Li反応の測定について報告する。
Li反応の測定について報告する。
岡田 雅之*; 石山 博恒*; 片山 一郎*; 仁木 和昭*; 宮武 宇也*; 渡辺 裕*; 牧井 宏之; 新井 重昭*
no journal, ,
TRIACは26MHz SCRFQと52MHz IH Linacからなる重イオン加速器である。現在、TRIACでは C(
C( )
) O反応の測定実験が計画されている。この実験では2-4MHzの大強度低バックグラウンドなパルスビームが要求され、そのためにプリバンチシステムが作製された。プリバンチシステムは2-4MHzの周波数可変で鋸歯状波によるバンチが可能な2Gap型プリバンチャーと多層チョッパーで構成されており、昨年試作機によるテストを行った。今回、試作機の結果をもとに実機を作製し
O反応の測定実験が計画されている。この実験では2-4MHzの大強度低バックグラウンドなパルスビームが要求され、そのためにプリバンチシステムが作製された。プリバンチシステムは2-4MHzの周波数可変で鋸歯状波によるバンチが可能な2Gap型プリバンチャーと多層チョッパーで構成されており、昨年試作機によるテストを行った。今回、試作機の結果をもとに実機を作製し O
O ビームを用いてバンチテストを行った。その結果、プリバンチャーによる中心バンチの増加率であるバンチゲインは4.5、全ビーム中バックグラウンドの比が約2%(実験上特に重要なパルス前250nsでは10
ビームを用いてバンチテストを行った。その結果、プリバンチャーによる中心バンチの増加率であるバンチゲインは4.5、全ビーム中バックグラウンドの比が約2%(実験上特に重要なパルス前250nsでは10 以下)であった。この値は十分実験の要求を満たしている。今後、大強度
以下)であった。この値は十分実験の要求を満たしている。今後、大強度 ビームによるテストを行う予定である。
ビームによるテストを行う予定である。
内田 伸一; 萩野谷 仁*; 山田 耕治*; 西野 克己*; 川瀬 啓一; 岡田 尚
no journal, ,
平成23年3月11日、東北地方太平洋沖地震に端を発し、東京電力福島第一原子力発電所事故が発生した。これに伴い、大量の放射性物質の放出による環境汚染が発生し、国により放射性物質の除染のための「放射性物質汚染対処特別措置法(特措法)」が制定された。日本原子力研究開発機構と東京電力は、内閣府・環境省からの要請を受け、平成23年9月28日に「除染推進専門家チーム」を発足させ、福島県内の各市町村における除染活動の円滑な推進のため、各自治体等への支援活動を開始し、1,862件(平成28年3月末まで)の案件を支援した。本報告は、これまでの「除染推進専門家チーム」の活動を紹介する。