Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
荒井 陽一; 渡部 創; 中原 将海; 船越 智雅; 星野 貴紀; 高畠 容子; 坂本 淳志; 粟飯原 はるか; 長谷川 健太; 吉田 稔生; et al.
Progress in Nuclear Science and Technology (Internet), 7, p.168 - 174, 2025/05
STRADプロジェクトの進捗に係る報告として、CPFホットセルの処理状況とともに、新たなターゲットに係る研究計画と最新のトピックスについて報告する。
吉田 純也; 赤石 貴也; 藤田 真奈美; 長谷川 勝一; 橋本 直; 細見 健二; 市川 真也; 市川 裕大; 今井 憲一*; Kim, S.; et al.
JPS Conference Proceedings (Internet), 33, p.011112_1 - 011112_8, 2021/03
J-PARC E07 is the most ambitious and complex emulsion experiment to date investigating double hypernuclei with Hybrid emulsion method. The physics run at the K1.8 beam line in the J-PARC hadron experimental facility have been completed in 2017. The emulsion sheets are presently being analyzed with dedicated optical microscopes. Current statistics are estimated to be more 3 times than that of previous experiments. Quantitative data on the  and
and  interaction are being accumulated successfully via analysis of double
interaction are being accumulated successfully via analysis of double  and
and  hypernuclei. Multiple
hypernuclei. Multiple  hypernucleus candidates suggests several features about
hypernucleus candidates suggests several features about  hypernucleus that the identification efficiency of
hypernucleus that the identification efficiency of  C is significantly higher than other mode, many daughters of
C is significantly higher than other mode, many daughters of  C are identified as He or Be, and multiple bound states of
C are identified as He or Be, and multiple bound states of  exist in the
exist in the  N nucleus. An analysis of X-ray spectroscopy of
N nucleus. An analysis of X-ray spectroscopy of  hyperatoms are ongoing.
hyperatoms are ongoing.
Kim, S. H.*; 市川 裕大; 佐甲 博之; 長谷川 勝一; 早川 修平*; 七村 拓野*; 佐藤 進; 谷田 聖; 吉田 純也; 他11名*
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 940, p.359 - 370, 2019/10
被引用回数:5 パーセンタイル:41.18(Instruments & Instrumentation)We have developed a gas electron multiplier (GEM)-based time projection chamber (TPC) for the H-dibaryon search experiment at J-PARC. High-rate  beam particles enter a TPC gas volume of approximately 0.2 m
beam particles enter a TPC gas volume of approximately 0.2 m , in a direction perpendicular to the electric field. A long-rectangular hollow section is located inside the TPC volume to accommodate a diamond target. We commissioned the TPC using 230 MeV protons with beam rates of up to 1 MHz. The TPC data acquisition system collected 5768 pad signals in full readout mode, with almost 100% efficiency, at a preset trigger rate of 230 Hz. We operated the TPC in an Ar/CH
, in a direction perpendicular to the electric field. A long-rectangular hollow section is located inside the TPC volume to accommodate a diamond target. We commissioned the TPC using 230 MeV protons with beam rates of up to 1 MHz. The TPC data acquisition system collected 5768 pad signals in full readout mode, with almost 100% efficiency, at a preset trigger rate of 230 Hz. We operated the TPC in an Ar/CH gas mixture (90/10) without a magnetic field. The spatial resolutions on the pad plane are measured to be 400-700
gas mixture (90/10) without a magnetic field. The spatial resolutions on the pad plane are measured to be 400-700  m, which correspond to 230-300
m, which correspond to 230-300  m in a magnetic field of 1 T. We confirmed high tracking capability at beam rates of up to 1 MHz.
m in a magnetic field of 1 T. We confirmed high tracking capability at beam rates of up to 1 MHz.
 hyperon capture at rest in nuclear emulsion
hyperon capture at rest in nuclear emulsionTheint, A. M. M.*; 江川 弘行; 吉田 純也; 他7名*
Progress of Theoretical and Experimental Physics (Internet), 2019(2), p.021D01_1 - 021D01_10, 2019/02
被引用回数:6 パーセンタイル:42.64(Physics, Multidisciplinary)In the E373 experiment at KEK-PS, we have located nearly  stopping events of
stopping events of  hyperon candidates in nuclear emulsion. Among them, the identification of
hyperon candidates in nuclear emulsion. Among them, the identification of  hyperon was performed with Constant Sagitta (CS) method by measuring multiple Coulomb scattering for 695 clearly stopping events. With use of Geant4 simulation, the parameters for the CS method were optimised and we obtained the number of real
hyperon was performed with Constant Sagitta (CS) method by measuring multiple Coulomb scattering for 695 clearly stopping events. With use of Geant4 simulation, the parameters for the CS method were optimised and we obtained the number of real  stopping events to be
stopping events to be 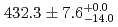 with 3.2% systematic error. The trapping probabilities of two
with 3.2% systematic error. The trapping probabilities of two  hyperons for light and heavy nuclei were found to be
hyperons for light and heavy nuclei were found to be  % and
% and  %, respectively. For at least one
%, respectively. For at least one  trapping, the probabilities were
trapping, the probabilities were  % and
% and  % for light and heavy nuclei. These results are the first time to present the trapping probabilities of
% for light and heavy nuclei. These results are the first time to present the trapping probabilities of  hyperons via
hyperons via  hyperon capture at rest in the emulsion.
hyperon capture at rest in the emulsion.
江川 弘行; 足利 沙希子; 長谷川 勝一; 橋本 直; 早川 修平; 細見 健二; 市川 裕大; 今井 憲一; 金原 慎二*; 七村 拓野; et al.
Progress of Theoretical and Experimental Physics (Internet), 2019(2), p.021D02_1 - 021D02_11, 2019/02
被引用回数:31 パーセンタイル:82.94(Physics, Multidisciplinary)A double- hypernucleus,
hypernucleus,  , was observed by the J-PARC E07 collaborationin nuclear emulsions tagged by the
, was observed by the J-PARC E07 collaborationin nuclear emulsions tagged by the  reaction. This event was interpreted as a production and decay of
reaction. This event was interpreted as a production and decay of  ,
, , or
, or  via
via  capture in
capture in  .By assuming the capture in the atomic 3D state, the binding energy of two
.By assuming the capture in the atomic 3D state, the binding energy of two  hyperons
hyperons (
( )of these double-
)of these double- hypernuclei are obtained to be
hypernuclei are obtained to be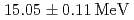 ,
, 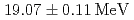 , and
, and 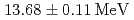 , respectively. Based on the kinematic fitting,
, respectively. Based on the kinematic fitting,  is the most likely explanation for the observed event.
is the most likely explanation for the observed event.
金原 慎二*; 江川 弘行; 早川 修平; 吉田 純也; 他12名*
Progress of Theoretical and Experimental Physics (Internet), 2019(1), p.011H01_1 - 011H01_9, 2019/01
被引用回数:6 パーセンタイル:37.62(Physics, Multidisciplinary)ダブルハイパー核の崩壊から放出された核種を識別してその親核種を同定するため、電荷1から5までの核種を識別する技術を開発した。この方法は基本的には原子核乾板中の飛跡体積を測定するもので、その太さ、乾板の表面からの深さ、角度を、 H,
H,  He,
He,  Li,
Li,  Be,
Be,  Bについて理研RIBFで照射したサンプルについて評価した。
Bについて理研RIBFで照射したサンプルについて評価した。 線を用いた較正ののち、
線を用いた較正ののち、 線飛跡との体積比を用いて5種類の電荷を識別する二次関数の関係式を得た。この手法を、過去に検出された複数解釈のあるグザイハイパー核候補について、その識別に用いた。その結果、シングルラムダハイパー核の崩壊の娘粒子の一つを、尤度比0.9で
線飛跡との体積比を用いて5種類の電荷を識別する二次関数の関係式を得た。この手法を、過去に検出された複数解釈のあるグザイハイパー核候補について、その識別に用いた。その結果、シングルラムダハイパー核の崩壊の娘粒子の一つを、尤度比0.9で Heと識別した。そして、この事象は
Heと識別した。そして、この事象は
 +
+  N
N 

 Be +
Be + 
 He +
He +  と一意に同定された。
と一意に同定された。
川崎 将亜; 中嶌 純也; 吉田 圭佑; 加藤 小織; 西野 翔; 野崎 天生; 中川 雅博; 角田 潤一; 菅谷 雄基; 長谷川 里絵; et al.
JAEA-Data/Code 2017-004, 57 Pages, 2017/03
原子力施設の事故発生時においては、事故による影響及びその範囲を迅速に把握するために、放出された放射性物質による一般公衆への影響や事故による作業者の個人被ばく線量を早期に評価し報告することが求められる。そのため、原子力科学研究所放射線管理部においては、事故発生時の迅速な対応に資するために、一般公衆及び作業者の被ばく線量評価について、評価方法及び必要となる各種パラメータ等を想定される事故事例ごとにまとめ、事例集を整備した。本事例集では、原子力科学研究所で想定される各種事故に加え、過去の原子力事故で放出された放射性物質による被ばく評価について扱っており、これらは緊急時における被ばく評価についての知見・技術の継承にも用いることができる。
山田 克典; 藤井 克年; 神田 浩志; 東 大輔; 小林 稔明; 中川 雅博; 深見 智代; 吉田 圭佑; 上野 有美; 中嶌 純也; et al.
JAEA-Review 2013-033, 51 Pages, 2013/12
平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故以降、放射線防護・放射線管理にかかわるさまざまな基準が策定された。インターネット等を通じて、これらの基準を調査した結果、下記13項目があげられた。(1)ヨウ素剤の服用基準値、(2)避難住民等に対するスクリーニングレベル、(3)避難区域、屋内退避等、(4)食品規制値(暫定規制値、基準値)、(5)放射線業務従事者の緊急時被ばく限度、(6)水浴場開設の判断基準、(7)学校・校庭の利用の判断基準、(8)作付基準、(9)飼料の暫定許容値、(10)堆肥の暫定許容値、(11)船舶、コンテナ等の除染基準、(12)廃棄物の取扱、処分等、(13)除染作業にかかわる基準。これらの基準の根拠を調査・整理し、今後の放射線防護、放射線管理の課題を検討した。
白石 淳也; 吉田 善章*; 古川 勝*
Astrophysical Journal, 697(1), p.100 - 105, 2009/03
被引用回数:5 パーセンタイル:17.25(Astronomy & Astrophysics)原始星などの中心天体近傍に形成される、ジェット放出を伴う降着円盤は、理想流体モデルの枠組みから見れば特異な構造を持っている。降着流とジェット流は、ケプラー回転している円盤に対する「特異摂動」とみなすことができる。ここで特異摂動とは、何らかの(微分階数に関して)高次な効果をいう。本論文では、原始星円盤の弱電離プラズマ中ではホール効果がそのような構造を形成することを示した。実際、特異摂動によって規定される特徴的なスケールを評価すると、ホール効果が支配的である。
片山 寿人*; 北村 治滋*; 森 真理*; 中川 淳也*; 吉田 貴宏*; 河合 敏彦*; 長谷 純宏; 田中 淳
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 94, 2007/02
滋賀県では、窒素による琵琶湖の富栄養化が重大な問題となっており、そのうち16%が農業排水からの流入と見積もられている。本研究では、イオンビーム突然変異技術を利用した少肥栽培向き水稲育種を目指し、水稲玄米に炭素イオンビームを照射した個体における生育への影響を調査した。供試材料は、滋賀県で育成した水稲品種「秋の詩」及び「大育1743」を用いた。イオンビーム照射区では、茎長と穂数に変化が認められたが、大きな形態変異が認められなかったことから、限定的な遺伝子の変異であると考えられた。今後は、穂数を指標にして変異体を選抜し、さらに窒素吸収能や窒素利用率が高い変異体を選抜する予定である。
 散乱事象の解析状況
散乱事象の解析状況七村 拓野; 市川 裕大; 早川 修平; 吉田 純也; 三輪 浩司*; 本多 良太郎*; 赤澤 雄也*; 山本 剛史
no journal, ,
核力を理解する上で、核子散乱実験は大きな役割を果たしてきた。核力をストレンジネスを含むバリオン(ハイペロン)に対して拡張した相互作用について調べる上でもハイペロン-核子散乱実験は強力な手段となるが、ハイペロンの寿命が sと短いことから十分な統計量を得られるような散乱実験は容易ではなかった。J-PARC E40実験はJ-PARCハドロン実験施設K1.8ビームラインにおいて、大強度の
sと短いことから十分な統計量を得られるような散乱実験は容易ではなかった。J-PARC E40実験はJ-PARCハドロン実験施設K1.8ビームラインにおいて、大強度の 中間子ビームを用いたp(
中間子ビームを用いたp(
 ,K
,K )
)
 反応により
反応により 粒子を大量に生成すること、液体水素標的とそれを囲む検出器システムCATCHを用いて二体反応の力学的再構成を行うことにより、これまで困難であった高統計の
粒子を大量に生成すること、液体水素標的とそれを囲む検出器システムCATCHを用いて二体反応の力学的再構成を行うことにより、これまで困難であった高統計の 散乱データを得ることを目的とした実験である。2019年4月までに
散乱データを得ることを目的とした実験である。2019年4月までに 散乱および予定量のおよそ半分の
散乱および予定量のおよそ半分の 散乱のデータの取得を行った。本講演では
散乱のデータの取得を行った。本講演では 散乱のデータについての解析について述べる。本講演では実験の概要、
散乱のデータについての解析について述べる。本講演では実験の概要、 散乱およびバックグラウンドとなる
散乱およびバックグラウンドとなる の崩壊粒子が関与する反応についての解析状況について紹介するとともに、2020年2月に行われる予定の残りの
の崩壊粒子が関与する反応についての解析状況について紹介するとともに、2020年2月に行われる予定の残りの 散乱データの取得に関しても述べる。
散乱データの取得に関しても述べる。
吉田 浩子*; 野村 直希*; 河野 恭彦; 迫田 晃弘; 黒田 佑次郎*; 内藤 航*; 廣田 誠子*; 工藤 伸一*; 恵谷 玲央*; 近本 一彦*; et al.
no journal, ,
本WGでは、IRPAが加盟学会に行ったコンサルテーションにおいてRP専門家・実務家からの意見として、放射線防護システムにおけるもっとも必要であるとされた項目(Key issues)の一つであるPublic Understandingをテーマとして、IRPAが加盟学会に向けて2020年に発行した"Practical Guidance for Engagement with the Public on Radiation and Risk"を日本語に翻訳し、国内の放射線防護専門家をはじめとした本テーマに関心を有する関係者へ提供することを目的とし活動を進めている。シンポジウムにおいては、各担当委員より、翻訳の進捗およびガイダンスの要点を紹介する。
北村 治滋*; 片山 寿人*; 森 真理*; 中川 淳也*; 吉田 貴宏*; 河合 敏彦*; 長谷 純宏; 田中 淳
no journal, ,
本研究では、イオンビーム突然変異技術を利用した少肥栽培向き水稲育種を目指し、水稲玄米に炭素イオンビームを照射した個体における生育への影響を調査した。供試材料は、滋賀県で育成した水稲品種「秋の詩」及び「大育1743」を用いた。イオンビーム照射による突然変異は、形態的に大きい変異が認められなかったことから、限定的な遺伝子の変異であると考えられた。今後は、窒素吸収能や窒素利用率が高い変異体を選抜する予定である。
高田 千恵; 中野 政尚; 宗像 雅広; 吉田 忠義; 横須賀 美幸; 山田 純也; 前田 英太; 渡邊 裕貴; 富岡 哲史; 百瀬 琢麿
no journal, ,
放射線安全規制研究戦略的推進事業費(放射線防護研究分野における課題解決型ネットワークとアンブレラ型統合プラットフォームの形成)事業(2017 2021年度)の一環として、万一の緊急事態発生時に専門性を活かした支援・指導・助言等が適切に実施できる、放射線防護分野の専門家の確保と育成に向け、教育・訓練、最新情報や課題に対する関係者間での認識共有等、平常時に行うべき活動(緊急時放射線防護ネットワーク活動。以下、「NW」という。)のあり方等を検討している。
2021年度)の一環として、万一の緊急事態発生時に専門性を活かした支援・指導・助言等が適切に実施できる、放射線防護分野の専門家の確保と育成に向け、教育・訓練、最新情報や課題に対する関係者間での認識共有等、平常時に行うべき活動(緊急時放射線防護ネットワーク活動。以下、「NW」という。)のあり方等を検討している。
 plasmas
plasmas白石 淳也; 宮戸 直亮; 松永 剛; 藤間 光徳; 本多 充; 鈴木 隆博; 吉田 麻衣子; 林 伸彦; 井手 俊介
no journal, ,
高エネルギー粒子のダイナミクスに回転の効果を自己無撞着に導入すると、高性能トカマクにおける抵抗性壁モード安定性が大きく影響を受けることが明らかになった。自己無撞着に回転の効果を導入し、運動論的MHD理論を拡張し、高エネルギー粒子へと応用した。本理論により、MHDモードと粒子運動との共鳴に伴うエネルギー変化を表す項が拡張される。本発表では、拡張された理論を用いて、JT-60SAにおける高ベータプラズマの抵抗性壁モード安定性解析を行った。高エネルギー粒子に関して新しいモデル平衡分布関数を導入し、拡張されたエネルギー変化項を計算した。その結果、高エネルギー粒子による抵抗性壁モードに対する安定化効果が強められることが明らかになった。
吉田 純也
no journal, ,
J-PARC E07実験は、J-PARCで写真乾板を用いてダブルハイパー核を検出するユニークな実験である。この実験は過去の統計量の10倍のダブルハイパー核を検出するべく設計された。さらにこの実験は、 粒子と原子核の束縛系である「
粒子と原子核の束縛系である「 原子」の脱励起により放出されるX線をゲルマニウム検出器を用い世界で初めて検出する目的もある。加速器ビーム照射と写真乾板の現像は成功裏に完了した。現在、写真乾板の解析により、いくつかのダブルハイパー核事象が検出されている。HYP2018では実験の現状、検出された事象、今後の展望について報告する。
原子」の脱励起により放出されるX線をゲルマニウム検出器を用い世界で初めて検出する目的もある。加速器ビーム照射と写真乾板の現像は成功裏に完了した。現在、写真乾板の解析により、いくつかのダブルハイパー核事象が検出されている。HYP2018では実験の現状、検出された事象、今後の展望について報告する。
吉田 純也
no journal, ,
J-PARC E07実験は、ハイブリッドエマルション法を用いてダブルハイパー核を系統的に研究するユニークな実験である。この実験は過去の統計量に対して10倍以上のダブルハイパー核を検出すべく設計された。さらにこの実験はグザイマイナス原子からのX線をゲルマニウム検出器を用い初検出することを狙っている。これらの実験データは、ラムダラムダ間相互作用、グザイ核子間相互作用の研究に本質的な情報をもたらす。この実験のビーム照射は2017年までに完了し、1500枚の写真乾板からなる118モジュールの検出器に情報を蓄積した。写真乾板の現像は完了し、現在は顕微鏡下で解析中である。解析の進捗状況は全体の1割程度で、約10例のダブルハイパー核事象が検出された。本講演では、解析の最新状況:探索作業、個々の事象の解析、展望について報告する。
吉田 純也; 大橋 正樹*; 後藤 良輔*; 長瀬 雄一*; 村井 李奈*; May, S.*; Aye, M. M. T.*; 金原 慎二*; 吉本 雅浩*; 仲澤 和馬*
no journal, ,
J-PARC E07実験は、2016年6月に1st physics run、2017年4月から6月に2nd physics runとしてK-ビームの照射を行い、準備した全ての原子核乾板モジュールに飛跡情報を蓄積した。現在、顕微鏡下でのダブルストレンジネス核を探索する解析作業を継続中である。本講演ではその解析状況について、質、速度、進捗、今後の展望について議論する。
吉田 純也; 江川 弘行; 早川 修平; 笠置 歩*; 西村 森*; Nyaw, A. N. L.*; 吉本 雅浩*; 仲澤 和馬*
no journal, ,
J-PARC E07は、写真乾板を用いてダブルハイパー核事象を過去最大の統計量(過去の10倍、検出数100例、そのうち核種同定事象を10例程度。)で検出する実験である。多様なダブルハイパー核の質量測定によって、
 相互作用、
相互作用、
 相互作用といったバリオン間相互作用に関する実験データを得る。E07は、2017年7月までに計画通りのK-粒子ビーム照射を、また2018年2月までに写真乾板の現像を全て終え、現在は写真乾板を光学顕微鏡下で解析中である。本講演では解析の現状、検出された事象の分類, 検出効率, 進捗速度と今後の展望について述べる。2019年1月現在、全118モジュール、1300枚の厚型乾板のうち、およそ5割強を解析した。検出されたダブルハイパー核事象候補は合計22例となった。
相互作用といったバリオン間相互作用に関する実験データを得る。E07は、2017年7月までに計画通りのK-粒子ビーム照射を、また2018年2月までに写真乾板の現像を全て終え、現在は写真乾板を光学顕微鏡下で解析中である。本講演では解析の現状、検出された事象の分類, 検出効率, 進捗速度と今後の展望について述べる。2019年1月現在、全118モジュール、1300枚の厚型乾板のうち、およそ5割強を解析した。検出されたダブルハイパー核事象候補は合計22例となった。
 -
- N interaction by measurement of twin hypernuclei with hybrid emulsion method at J-PARC
N interaction by measurement of twin hypernuclei with hybrid emulsion method at J-PARC早川 修平; 吉田 純也
no journal, ,
ハイペロン-核子およびハイペロン-ハイペロン相互作用の研究は、一般的なバリオン-バリオン相互作用の理解に重要である。 や
や などの
などの =-1セクターでも、利用可能なデータは限られており、
=-1セクターでも、利用可能なデータは限られており、 や
や Nなどの
Nなどの =-2セクターに関しては、実験データはほとんどない。J-PARC E07実験は、J-PARC K1.8ビームラインで
=-2セクターに関しては、実験データはほとんどない。J-PARC E07実験は、J-PARC K1.8ビームラインで =-2ハイパー核を調べるために実施された。1.81GeV/cの運動量を持つK-中間子ビームを使用して、ダイヤモンドターゲットで準自由
=-2ハイパー核を調べるために実施された。1.81GeV/cの運動量を持つK-中間子ビームを使用して、ダイヤモンドターゲットで準自由 , K
, K
 -反応で
-反応で -ハイペロンを生成する。ハイブリッドエマルジョン法と呼ばれる、2つの粒子スペクトロメータと原子核乾板の間の情報を組み合わせた手法により、シリコンストリップ検出器と118のエマルジョンモジュールを使用して行われた。IBUKIイベントと呼ばれるツイン
-ハイペロンを生成する。ハイブリッドエマルジョン法と呼ばれる、2つの粒子スペクトロメータと原子核乾板の間の情報を組み合わせた手法により、シリコンストリップ検出器と118のエマルジョンモジュールを使用して行われた。IBUKIイベントと呼ばれるツイン ハイパー核事象が、新しく開発されたスキャンシステムで発見された。エネルギーと運動量の保存則によって、
ハイパー核事象が、新しく開発されたスキャンシステムで発見された。エネルギーと運動量の保存則によって、 -吸収点から
-吸収点から
 Beと
Beと
 Heの2つの
Heの2つの ハイパー核が生成された事象であると識別され、反応過程は、
ハイパー核が生成された事象であると識別され、反応過程は、 - +
- +  N
N 

 Be +
Be + 
 Heであることが確認された。
Heであることが確認された。 - +
- +  N系の結合エネルギーは、1.27
N系の結合エネルギーは、1.27 0.21MeVであると決定した。励起状態の考慮から、
0.21MeVであると決定した。励起状態の考慮から、
 Beのエネルギーレベルは基底状態(2-)またはスピンダブレットの他の状態(1-)であると解釈が可能であった。これは、結合エネルギーがほとんど不定性なく決定された最初のイベントでした。結合エネルギーの大きさから、引力的な
Beのエネルギーレベルは基底状態(2-)またはスピンダブレットの他の状態(1-)であると解釈が可能であった。これは、結合エネルギーがほとんど不定性なく決定された最初のイベントでした。結合エネルギーの大きさから、引力的な N相互作用により
N相互作用により -
- Nシステムが
Nシステムが ハイパー核という束縛状態であったことを示す。本発表では、上記の事象の結果を報告する。
ハイパー核という束縛状態であったことを示す。本発表では、上記の事象の結果を報告する。