Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
水野 崇; 青才 大介; 新宮 信也; 山本 祐平; 福田 朱里; 萩原 大樹
no journal, ,
本報告では、これまでの研究坑道の掘削を伴う研究段階(第2段階)の結果に基づき、地表からの調査予測研究段階(第1段階)での調査研究結果の妥当性を評価するとともに、第1段階において用いた調査評価技術(調査手法や手順など)の適用性について考察した。その結果、第1段階での調査研究結果として得られた、地下水の塩分濃度分布,酸化還元環境及びpHの妥当性を第2段階の調査研究によって確認することにより、第1段階において適用した調査技術の信頼性を示すことができた。ただし、第2段階では、第1段階で予測していなかった水質分布の変化が認められたため、今後は、第2段階で得られる知見に基づき、研究坑道掘削に伴う水質分布の変化に関する予測解析手法の信頼性向上を図っていく予定である。
中山 浩成; 永井 晴康
no journal, ,
原子力機構では、現在、大気・陸域・海洋での放射性物質の移行挙動を包括的に予測するSPEEDI-MP(SPEEDI Multi-model Package)の開発に取り組んでいる。この中で、非定常現象の予測に優れたLES(Large-Eddy Simulation)乱流モデルの導入により、原子力施設から排出される放射性物質の拡散現象などを建物スケールで詳細評価できる高分解能大気拡散モデルの開発を目指している。今回は、実在都市域(オクラホマシティー)での乱流と拡散に関する風洞実験を対象にLES解析を実行し、乱流構造や濃度分布が良好に再現されていることを確認した。
竹見 哲也*; 中山 浩成; 永井 晴康
no journal, ,
本研究では、気象モデルとLES(Large-Eddy Simulation)モデルを融合することで、現実都市での風速変動を定量的に解析する技術を構築することを目的とする。解析対象領域を東京都心部(大手町・丸の内地区)とし、2009年台風18号の通過に伴って生じた強風・突風を定量的に評価することを試みる。気象モデルとしてWRF(Weather Research and Forecasting)モデルを用い、気象庁メソ客観解析値を初期値・境界値条件としてWRFモデルに与え、台風18号の領域気象シミュレーションを行った。次に、LESモデルにより都市キャノピー内部での風速変動のシミュレーションを実行し、気象庁観測点での風速変動を実際の観測値と比較した結果、変動性状や極大値をかなりよく再現することに成功した。
前田 耕志*; 長谷川 優介*; 福士 圭介*; 山本 祐平; 青才 大介; 水野 崇
no journal, ,
元素の岩盤への吸着特性を評価するには、さまざまな水質条件における岩盤への吸着挙動を理解する必要があり、元素の岩盤への吸着プロセスを定量的に取り扱う方法として表面錯体モデリングが挙げられる。ただし、表面錯体モデリングは単一鉱物を対象に開発された手法であり、花崗岩のような鉱物集合体への適用は世界的な課題となっている。本研究では、さまざまな水質条件における花崗岩への強吸着性元素の吸着挙動を表面錯体モデリングに基づいて理解するための手法の構築を目的としている。本研究で吸着体とした花崗岩試料は、日本原子力研究開発機構が岐阜県瑞浪市に建設を進めている瑞浪超深地層研究所の深度300mから掘削したボーリング孔より採取した岩石コアを利用した。吸着質は鉱物に対し強い吸着性を示す元素の1つであるEuをモデル吸着質として、pH及びイオン強度を変化させた際の花崗岩の表面電荷とEu吸着挙動の解析に基づき、Eu吸着モデルの構築を試みたので、その結果を報告する。
佐藤 達彦; 保田 浩志*; 片岡 龍峰*; 八代 誠司*; 桑原 孝夫*; 塩田 大幸*
no journal, ,
太陽の爆発事象から地球に向かって放出される高エネルギー放射線(SEP)は、最大規模のもので5mSvもの被ばく線量を航空機搭乗者に与える可能性がある。したがって、その予測は宇宙天気予報や放射線防護などの複数の研究分野で最重要課題として知られている。そこでわれわれは、太陽物理学や地球電磁気学などさまざまな分野の専門家と協力し、太陽コロナ衝撃波加速,太陽風磁気流体,空気シャワーに対する最新のシミュレーション技術を応用した理論的なSEP予報システムWASAVIES(WArning System for AVIation Exposure to SEP)を開発している。本発表では、原子力機構が中心となって開発した計算コードPHITSをSEPが引き起こす空気シャワーシミュレーションに応用した初期結果について報告する。
山崎 誠子; 山田 国見; 田上 高広*; Zwingmann, H.*
no journal, ,
断層の活動時期を推定するうえで、層序学的,地形学的な手法が適用困難な場合、断層岩そのものを年代測定する必要がある。近年、断層運動に伴う熱水活動により晶出した断層ガウジ中の雲母粘土鉱物を対象とした年代測定が試みられてきた。しかし、測定試料中に、活動後に破砕帯内で晶出した自生の雲母粘土鉱物のほかに、より古い母岩の砕屑物が混入することで年代値が古くなるなど、得られた年代値を解釈するうえでさまざまな問題点が指摘されてきた。本研究では、砕屑物に比べて細粒と考えられる自生鉱物を高純度で回収する分離法を検討するために、 0.1,
0.1,  0.4,
0.4,  2, 2-6
2, 2-6 mのサイズに分級した試料について、K-Ar年代測定を実施した。その結果、より細粒の試料ほど若い年代値が得られ、細粒分ほど高純度で自生鉱物が含まれていることが示唆された。また、細粒試料は母岩のジルコンのフィッショントラック(FT)年代とアパタイトのFT年代の間の年代値を示し、脆性破壊と粘土生成がこれら2手法の閉鎖温度の間の領域(約100-250
mのサイズに分級した試料について、K-Ar年代測定を実施した。その結果、より細粒の試料ほど若い年代値が得られ、細粒分ほど高純度で自生鉱物が含まれていることが示唆された。また、細粒試料は母岩のジルコンのフィッショントラック(FT)年代とアパタイトのFT年代の間の年代値を示し、脆性破壊と粘土生成がこれら2手法の閉鎖温度の間の領域(約100-250 C)で起こることと調和的であった。今後、本手法の確立に向けて、各サイズ試料の鉱物学的解析を併せた年代解析法の検討を進めていく。
C)で起こることと調和的であった。今後、本手法の確立に向けて、各サイズ試料の鉱物学的解析を併せた年代解析法の検討を進めていく。
阿部 淳; 関根 孝太郎*; Harjo, S.; 伊藤 崇芳*; 有馬 寛
no journal, ,
J-PARCのMLFに建設された工学材料回折装置「匠」は、中性子回折を用いた工学材料内の応力ひずみ測定を目的とした実験装置である。これまでの中性子回折を用いたひずみ測定は、金属材料を対象にしたものが主であったが、これを岩石材料へ展開することを目指す。そのために、中性子回折による岩石中の残留ひずみ測定と一軸圧縮下にある岩石のその場ひずみ測定を行った。残留ひずみ測定結果から、岩石試料内部からひずみ解析可能な中性子回折パターンが得られ、試験片の方向に関してひずみ量の異方性が見られた。また、一軸圧縮変形その場中性子回折実験では、ひずみゲージから求まる試験片全体のひずみと中性子回折パターンから求まるひずみ量に差が見られた。
片山 芳則; Yagafarov, O.; 服部 高典
no journal, ,
2010年の秋に稼働が予定されているJ-PARCの超高圧中性子回折装置PLANETを用いて、高温高圧下の水の構造研究を行うことを計画している。これまでの放射光実験及び分子動力学シミュレーションによる研究で、水の構造が圧力や温度によって大きく変化することが明らかにされてきた。しかし、水素に関する実験的な情報は限られており、水素結合の温度圧力変化を解明するには、中性子回折実験が不可欠である。本講演では、研究の背景及び、実験のためのセル開発や解析方法などの準備状況を紹介する。
Yagafarov, O.; 小原 真司*; Temleitner, L.*; 稲村 泰弘; 片山 芳則
no journal, ,
In the nearest future it will be possible to complement high pressure X-ray measurements at synchrotrons with neutron diffraction study at J-PARC. One possible way to analyze both experimental data in combination is to use the Reverse Monte Carlo (RMC) algorithm to derive structures of disordered materials. Here we analyze previously measured X-ray and neutron diffraction data on densified silica glass SiO . High pressure study of this archetypal glass is still challenging. One of the main issues is understanding of permanent densification mechanism under compression. In order to verify topological changes by analyzing structures directly, we used RMC simulation to build 3D structural models of normal (2.2g/cm
. High pressure study of this archetypal glass is still challenging. One of the main issues is understanding of permanent densification mechanism under compression. In order to verify topological changes by analyzing structures directly, we used RMC simulation to build 3D structural models of normal (2.2g/cm ) and densified (2.45g/cm
) and densified (2.45g/cm and 2.63g/cm
and 2.63g/cm ) glass. Derived RMC models (each made of 6000 atoms) accurately reproduces the experimental data and gives reasonable rings statistics and bond angle distributions.
) glass. Derived RMC models (each made of 6000 atoms) accurately reproduces the experimental data and gives reasonable rings statistics and bond angle distributions.
大貫 敏彦; 岩井 和加里*; 香西 直文; 鈴木 庸平*
no journal, ,
アクチノイドとしてU(VI)を用いてShewanella putrefaciens(グラム陰性菌)及びBacillus subtilis(グラム陽性菌)への吸着挙動を検討した。その結果、水溶液中に存在する陽イオン,有機酸などはU(VI)の微生物への吸着に影響することがわかった。さらに、その影響は微生物種、あるいは細胞表面の構造に依存する可能性がある。
杉野 朋弘*; 横堀 伸一*; Yang, Y.*; 河口 優子*; 長谷川 直*; 橋本 博文*; 今井 栄一*; 奥平 恭子*; 河合 秀幸*; 田端 誠*; et al.
no journal, ,
In this report, we will report whether aerogel that have been used for the collection of space debris and cosmic dusts can be used for microbe sampling in space. We will discuss how captured particles by aerogel can be detected with DNA-specific fluorescence dye, and how to distinguish microbes from other materials (i.e. aerogel and particles such as clay). The surface of microparticles captured by aerogel is often vitrified. The non-specific fluorescent light is often observed from vitrified materials. Therefore, we need to distinguish fluorescent light of stained microbes from that of spectral characteristics of vitrified materials and bleaching rate are going to be need to distinguish stained microbes with DNA-specific fluorescence dye and other materials such as clay and aerogel. We simulated the high-speed collision of micro-particles to the aerogel with the two stage light gas gun (ca. 4 km/s). The micro-particles containing dried cells of 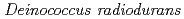 mixed with clay material were used for the collision experiment, and the captured particles, which was stained after collision experiment, were observed with a fluorescence microscope. This experiment suggests that the captured microbes can be detected and be distinguished from clay materials.
mixed with clay material were used for the collision experiment, and the captured particles, which was stained after collision experiment, were observed with a fluorescence microscope. This experiment suggests that the captured microbes can be detected and be distinguished from clay materials.
横堀 伸一*; Yang, Y.*; 杉野 朋弘*; 河口 優子*; 高橋 勇太*; 鳴海 一成; 橋本 博文*; 林 宣宏*; 今井 栄一*; 河合 秀幸*; et al.
no journal, ,
We proposed the "Tanpopo" mission to examine possible interplanetary migration of microbes, and organic compounds on Japan Experimental Module (JEM) of the International Space Station (ISS). Tanpopo consists of six subthemes. Two of them are on the possible interplanetary migration of microbes capture experiment of microbes at the ISS orbit and space exposure experiment of microbes. In this paper, we focus on the space exposure experiment of microbes. Microbes in space are assumed be exposed to the space environment with a kind of clay materials that might protect microbes from vacuum UV and cosmic rays, or exposed as the aggregates of which outer cells might protect inner cells from vacuum UV and cosmic rays. Dried vegetative cells of 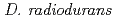 and our novel deinococcal species isolated from high altitude are candidates for the exposure experiment. In addition, we are planning to perform another space exposure experiments of microbes. In this paper, we discuss current status of exposure experiment of microorganisms defined for the Tanpopo mission and others.
and our novel deinococcal species isolated from high altitude are candidates for the exposure experiment. In addition, we are planning to perform another space exposure experiments of microbes. In this paper, we discuss current status of exposure experiment of microorganisms defined for the Tanpopo mission and others.
佐藤 峰南*; 尾上 哲治*; 中村 智樹*; 野口 高明*; 初川 雄一; 大澤 崇人; 藤 暢輔; 小泉 光生
no journal, ,
美濃帯南部にある上部トリアス系層状チャート中で発見された高ニッケル含有スピネル試料中にイリジウムの異常濃度を発見した。高濃度のイリジウムの起源として地球外物質衝突が最も有力な候補であり、この地層の年代(2億1550万年)よりカナダにある直径100キロメートルのマニコーガンクレータによる衝突事象において放出されたイジェクターと考えられる。イリジウム分析のみならず、シンクロトロンX線回折分析などを通して得られた知見の発表を行った。
梅田 浩司; 浅森 浩一
no journal, ,
2000年鳥取県西部地震は、それまで活断層が認定されていない地域で発生したM7クラスの内陸地震であり、変動地形学的手法による活断層の検出・認定が必ずしも十分ではないという問題を提起した。しかしながら、地震後の精力的な調査によって、地震を引き起こしたのは未成熟な断層であり、震源断層からの主破壊は地下1-2kmまで達したものの、地表では幾つかに分散するわずかな横ずれ変位しか生じなかったことが明らかにされた。このような未成熟な活断層や低活動性で変動地形が明瞭でない活断層等を概要調査等においてあらかじめ認定しておくことは、地層処分の長期的な安全性を確保するためにも重要となる。本報告では、このような断層を認定するため、地磁気・地電流法(MT法)による比抵抗構造解析及び地下水中の希ガス同位体測定を組合せた調査技術について紹介する。なお、本報告は、セッションS-CG66「断層帯の化学」における招待講演である。
丹羽 正和; 黒澤 英樹; 水落 幸広*; 棚瀬 充史*
no journal, ,
断層破砕帯の発達は岩盤の透水構造を大きく変化させる場合が多いので、しばしば地下での物質移動において大きな役割を果たす地下水流動に影響を及ぼす。したがって、放射性廃棄物の地層処分における安全評価などでは、断層活動と物質移動との関係を明らかにすることが非常に重要である。本研究では、詳細な露頭記載のある岐阜県の阿寺断層の破砕帯を対象に、断層岩の化学分析を行い、特に希土類元素や、ウラン,トリウムに着目した破砕帯における物質移動について考察した。その結果、粘土鉱物を形成するような破砕に伴う水-岩石反応に加え、破砕帯に沿って苦鉄質岩の角礫が混入しているという母岩の不均質性が、希土類元素の表面錯体反応やウランの溶解-沈殿というイベントを通じて、断層活動に伴う物質移動に大きく影響していることがわかった。
山田 国見; 小木曽 哲*; 上杉 健太朗*; 平田 岳史*
no journal, ,
(U-Th)/He年代測定のより正確な補正のために結晶中のU, Thの三次元分布を測定しなければならず、かつ、非破壊で行う必要がある。SPring-8の X線CTを用いてUの不均一分布を検出することに成功した。また、LA-ICP-MSを用いてウラン・トリウムの濃度測定を行い、差分像を用いたウラン・トリウムの三次元分布測定法の検出感度や、(U-Th)/He年代に与える影響を評価した。
X線CTを用いてUの不均一分布を検出することに成功した。また、LA-ICP-MSを用いてウラン・トリウムの濃度測定を行い、差分像を用いたウラン・トリウムの三次元分布測定法の検出感度や、(U-Th)/He年代に与える影響を評価した。
酒井 隆太郎; 宗像 雅広; 木村 英雄
no journal, ,
日本原子力研究開発機構では、放射性廃棄物の地層処分が予定されている深度300m以深を想定した地下水流動特性,流動範囲に関する地下水流動モデルの検証方法の検討を進めてきた。地下浅部 深部の長期的な地下水流動については、深部の水理データの欠如,緩慢な地下水流動のため、流動の認識が困難であるなどの理由から、まず、地形に支配された重力を駆動力とする天水起源の地下水の流動下限深度、地層の堆積当時に取り込まれて以降、現在に至るまではほとんど流動に関与していない停滞性地下水の分布域などの評価が重要となる。このため、本報告では、幌延浜里地域を対象に、これまで離散していた水質,水温,地下水年代など複数の有効な指標データを集約・分析することにより、検証に必要なこれらの地下水流動境界,流動特性の評価を行うことができた。
深部の長期的な地下水流動については、深部の水理データの欠如,緩慢な地下水流動のため、流動の認識が困難であるなどの理由から、まず、地形に支配された重力を駆動力とする天水起源の地下水の流動下限深度、地層の堆積当時に取り込まれて以降、現在に至るまではほとんど流動に関与していない停滞性地下水の分布域などの評価が重要となる。このため、本報告では、幌延浜里地域を対象に、これまで離散していた水質,水温,地下水年代など複数の有効な指標データを集約・分析することにより、検証に必要なこれらの地下水流動境界,流動特性の評価を行うことができた。
 Cを用いた堆積岩中の地下水の滞留時間推定の試み
Cを用いた堆積岩中の地下水の滞留時間推定の試み村上 裕晃; 天野 由記; 國分 陽子; 岩月 輝希
no journal, ,
高レベル放射性廃棄物の地層処分では、その安全性を評価するために深部地下水の流動状態を把握することが重要である。地下水の流動状態を把握する方法として、放射性同位体などを利用する地球化学的方法と岩盤の透水係数や動水勾配などに基づいて数値解析を行う水理学的な手法がある。本研究では、北海道幌延地域を対象として地下水中の放射性炭素同位体( C)濃度を測定し、地下水の滞留時間の推測を試みた。測定対象は、新第三系の声問層中に建設された深度140mと250mの調査坑道から得られる地下水湧水とした。採取した地下水中の
C)濃度を測定し、地下水の滞留時間の推測を試みた。測定対象は、新第三系の声問層中に建設された深度140mと250mの調査坑道から得られる地下水湧水とした。採取した地下水中の C濃度は0.39から1.04pMCと求められた。研究地域の深部の地下水は
C濃度は0.39から1.04pMCと求められた。研究地域の深部の地下水は Cを含まない化石海水と考えられているが、検出した
Cを含まない化石海水と考えられているが、検出した Cは計算結果から掘削水の混入や汚染ではないと判断される。この
Cは計算結果から掘削水の混入や汚染ではないと判断される。この C濃度から単純に計算した地下水の滞留時間は約四万年と見積もられる。一方、実際の地層中では
C濃度から単純に計算した地下水の滞留時間は約四万年と見積もられる。一方、実際の地層中では Cを含まないデッドカーボンの付加による
Cを含まないデッドカーボンの付加による C濃度の希釈や同位体分別反応が起きていると考えられるため、これらのプロセスを理解し
C濃度の希釈や同位体分別反応が起きていると考えられるため、これらのプロセスを理解し C濃度を補正する必要がある。今後、その要因について検討を行っていく。
C濃度を補正する必要がある。今後、その要因について検討を行っていく。
村上 亮*; 川村 淳*; 牧野 仁史; 下司 信夫*; 及川 輝樹*; 西村 卓也*; 梅田 浩司; 佐々木 寿*; 瀬尾 俊弘; 大井 貴夫*
no journal, ,
火山噴火活動の全期間を通じた時系列的な予測に関しては、火山噴火シナリオの適用による予測手法が注目されてきている。本研究では、地層処分の研究分野でのFEP解析の方法論を火山噴火活動に発展的に応用することにより、火山活動の進展の予測に資する火山噴火シナリオ構築手法の開発を目的とした。本研究は、既存火山の事例を参照し、そこでの噴火活動を構成すると考えられる現象を素過程に分割し、素過程を論理関数論的に整理し、活動の展開を関数の連鎖として表現することを基本コンセプトとした。このコンセプトに基づき検討した結果、想定される活動推移を可能な限り列挙した火山噴火シナリオをシステマティックに構築できる見通しを得た。また、本研究成果を観測にフィードバックすることにより、火山噴火の前兆現象の検出や進展の可能性の効率的な絞り込みに有効な観測項目の選択にも資するものと考えられる。
佐野 亜沙美; 小松 一生*; 鍵 裕之*; 永井 隆哉*; 服部 高典
no journal, ,
歪んだルチル構造をとる -AlOOHは地球の下部マントル条件でも安定な含水鉱物である。第一原理計算により、高圧下で水素が二つの酸素原子間の中点に位置する水素結合の対称化が起きると予言された。高圧下におけるX線回折実験では、対称化に伴うと考えられる圧縮挙動の変化が見つかったが、その圧力はAlOOHでは10GPa、AlOODでは12GPaと異なる。本研究ではこの同位体効果について明らかにするため、
-AlOOHは地球の下部マントル条件でも安定な含水鉱物である。第一原理計算により、高圧下で水素が二つの酸素原子間の中点に位置する水素結合の対称化が起きると予言された。高圧下におけるX線回折実験では、対称化に伴うと考えられる圧縮挙動の変化が見つかったが、その圧力はAlOOHでは10GPa、AlOODでは12GPaと異なる。本研究ではこの同位体効果について明らかにするため、 -AlOOHについての高圧下中性子散乱実験を米国SNSの高圧専用ビームラインSNAPにて行った。圧力はパリ-エジンバラプレスで発生し、各圧力で得たデータについてリートベルト解析を行い、水素位置を含む原子位置を精密化した。実験では0, 2.5, 4.1, 5.6, 6.7, 7.1GPaでデータを取得した。120反射の強度が圧力とともに小さくなり、6.7GPaではほぼ消滅した。このことはPnnmへの相転移を示唆しており、対称化直前に起きるディスオーダーが起きたと考えられる。また水素結合の圧力変化には大きな同位体効果がみられ、過去に求められた重水素化物における実験の結果と比較するとO-H距離はO-D距離よりも同じ圧力において長く、またH...O距離はD...O距離よりも短かった。
-AlOOHについての高圧下中性子散乱実験を米国SNSの高圧専用ビームラインSNAPにて行った。圧力はパリ-エジンバラプレスで発生し、各圧力で得たデータについてリートベルト解析を行い、水素位置を含む原子位置を精密化した。実験では0, 2.5, 4.1, 5.6, 6.7, 7.1GPaでデータを取得した。120反射の強度が圧力とともに小さくなり、6.7GPaではほぼ消滅した。このことはPnnmへの相転移を示唆しており、対称化直前に起きるディスオーダーが起きたと考えられる。また水素結合の圧力変化には大きな同位体効果がみられ、過去に求められた重水素化物における実験の結果と比較するとO-H距離はO-D距離よりも同じ圧力において長く、またH...O距離はD...O距離よりも短かった。