Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
島田 明彦; 箱田 照幸; 小嶋 拓治; 田久保 剛*; 岩崎 達行*; 木下 忍*
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 60, 2007/02
ホルムアルデヒド(HCHO)とメタノール(CH OH)を含む空気、いわゆるホルマリンガスは、薫蒸殺菌に使用した後の排出のためにその短時間での無害化処理が求められており、電子ビーム(EB)の応用を検討した。90-1230ppmvのHCHOと30-340ppmvのメタノール(CH
OH)を含む空気、いわゆるホルマリンガスは、薫蒸殺菌に使用した後の排出のためにその短時間での無害化処理が求められており、電子ビーム(EB)の応用を検討した。90-1230ppmvのHCHOと30-340ppmvのメタノール(CH OH)を含む空気を5-80kGyで電子ビーム照射し、吸収線量と照射後の残存HCHO濃度を測定した結果から、初期HCHO濃度とこれを10ppmvに減少させるために必要な線量の関係を求めた。HCHO初期濃度を[HCHO]
OH)を含む空気を5-80kGyで電子ビーム照射し、吸収線量と照射後の残存HCHO濃度を測定した結果から、初期HCHO濃度とこれを10ppmvに減少させるために必要な線量の関係を求めた。HCHO初期濃度を[HCHO] (ppmv)とし、必要な線量をD(kGy)とすると、CH
(ppmv)とし、必要な線量をD(kGy)とすると、CH OHを含む場合は、D=-4.2
OHを含む場合は、D=-4.2 10
10 [HCHO]
[HCHO]
 +1.2
+1.2 10
10 [HCHO]
[HCHO] -1.2、CH
-1.2、CH OHを含まない場合は、D=-3.8
OHを含まない場合は、D=-3.8 10
10 [HCHO]
[HCHO]
 +1.0
+1.0 10
10 [HCHO]
[HCHO] -1.0の関係が得られた。これらに基づいて、部屋の容積,初期濃度,加速器仕様をパラメータとして、CH
-1.0の関係が得られた。これらに基づいて、部屋の容積,初期濃度,加速器仕様をパラメータとして、CH OHを含む場合のHCHO含有空気をEB処理するために要する時間を算出する式を導出した。これから、EB処理プロセスは、従来の熱触媒法に比べて処理時間を1/4程度にできることがわかった。
OHを含む場合のHCHO含有空気をEB処理するために要する時間を算出する式を導出した。これから、EB処理プロセスは、従来の熱触媒法に比べて処理時間を1/4程度にできることがわかった。
藤巻 秀; 阪本 浩一; 河地 有木; 石井 里美; 鈴井 伸郎; 石岡 典子; 渡辺 智; 松橋 信平
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 126, 2007/02
アサの同一個体において、上下に隣接する2枚の葉に CO
CO を前後して投与し、葉から輸送される光合成産物の動きをそれぞれイメージングした。両ケースの輸送経路,輸送速度を比較・解析した結果、これらの輸送経路は一部で互いに逆向きの流れが平行して走っている部分があることが明らかになり、このことから相互の連絡が密でないことが推測された。
を前後して投与し、葉から輸送される光合成産物の動きをそれぞれイメージングした。両ケースの輸送経路,輸送速度を比較・解析した結果、これらの輸送経路は一部で互いに逆向きの流れが平行して走っている部分があることが明らかになり、このことから相互の連絡が密でないことが推測された。
田口 光正; 小嶋 拓治
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 62, 2007/02
OHラジカルとの反応速度定数が大きいフェノールについて、その濃度の異なる水溶液試料に50MeV Heイオン照射を行い、その生成物の分析からOHラジカル生成について、入射エネルギーで微分したG値を求めた。照射イオンの比エネルギーの増加に伴い微分G値が増加すること、また入射イオンの有功電荷あるいは照射後の経過時間の増加により微分G値が減少することがわかった。この結果は水溶液中のエネルギー付与分布及びラジカルの分布に起因すると考えられる。
高野 勝昌; 井上 愛知; 山本 春也; 吉川 正人
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 160, 2007/02
水素吸着により着色する特性(ガスクロミック特性)を有する酸化タングステン(WO )薄膜を利用して光学式水素センサーを作製する場合、その着色速度の低さがセンサーへの応用を困難なものにしていた。そこで、ガスクロミック特性の発現原因と考えられる酸素原子の欠損を意図的に導入する目的で、WO
)薄膜を利用して光学式水素センサーを作製する場合、その着色速度の低さがセンサーへの応用を困難なものにしていた。そこで、ガスクロミック特性の発現原因と考えられる酸素原子の欠損を意図的に導入する目的で、WO 薄膜にイオン照射を行い照射量と着色速度の関係を調べた結果、
薄膜にイオン照射を行い照射量と着色速度の関係を調べた結果、 ions/cm
ions/cm 以上でWO
以上でWO 薄膜の着色速度が2倍以上改善することがわかった。これにより、イオン照射による欠陥導入が着色速度の改善に有効であることが実験的に初めて裏づけられた。
薄膜の着色速度が2倍以上改善することがわかった。これにより、イオン照射による欠陥導入が着色速度の改善に有効であることが実験的に初めて裏づけられた。
 ) ion production
) ion production山田 圭介; 大越 清紀; 齋藤 勇一; 水橋 清; 横田 渉
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 189, 2007/02
高崎量子応用研究所TIARAのイオン注入装置ではフラーレン(C )イオンビームの提供を開始している。イオン注入装置で使用しているフリーマンイオン源では、フラーレンイオンの生成において、単原子イオン生成と異なる振る舞いが見られ通常のパラメータではビーム電流を最大にすることができない。そこでC
)イオンビームの提供を開始している。イオン注入装置で使用しているフリーマンイオン源では、フラーレンイオンの生成において、単原子イオン生成と異なる振る舞いが見られ通常のパラメータではビーム電流を最大にすることができない。そこでC
 生成のためのイオン源パラメータの最適化と大電流化を目的として、サポートガスの種類(Ne, Ar, Xe)及び流量とC
生成のためのイオン源パラメータの最適化と大電流化を目的として、サポートガスの種類(Ne, Ar, Xe)及び流量とC
 ビーム強度の関係を測定した。その結果、サポートガスとしてNeを使用した場合ではビーム電流はアーク放電が保たれる最少ガス流量付近で最大となった。一方、Ar及びXeを使用した場合では最少流量(0.2cm
ビーム強度の関係を測定した。その結果、サポートガスとしてNeを使用した場合ではビーム電流はアーク放電が保たれる最少ガス流量付近で最大となった。一方、Ar及びXeを使用した場合では最少流量(0.2cm /min)でさえアークが保たれておりこのときビーム電流が最大となった。また、同真空度ではXe, Ar, Neの順にビーム電流が大きくなることがわかった。この結果から質量数が大きいサポートガスの使用によりビーム電流をより大きくできる可能性が示唆される。今後、サポートガス流量をより微少に制御し、他のガスについても検討することでさらなるビーム電流の増大が望めると思われる。
/min)でさえアークが保たれておりこのときビーム電流が最大となった。また、同真空度ではXe, Ar, Neの順にビーム電流が大きくなることがわかった。この結果から質量数が大きいサポートガスの使用によりビーム電流をより大きくできる可能性が示唆される。今後、サポートガス流量をより微少に制御し、他のガスについても検討することでさらなるビーム電流の増大が望めると思われる。
千葉 敦也; 齋藤 勇一; 鳴海 一雅; 阿達 正浩; 金子 敏明*
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 176, 2007/02
炭素薄膜を透過した高速炭素クラスターイオンC
 (1MeV/atom)の電荷を測定した。薄膜透過により解離したC
(1MeV/atom)の電荷を測定した。薄膜透過により解離したC
 の構成イオンは平行平板電極(
の構成イオンは平行平板電極( 30kV)により電荷に比例して偏向され、CCDカメラでモニターした発光タイプの位置検出器(MCP)により検出される。検出された位置(C
30kV)により電荷に比例して偏向され、CCDカメラでモニターした発光タイプの位置検出器(MCP)により検出される。検出された位置(C
 を構成していた3つのイオンの分布)は電荷と解離前のクラスター構造の情報を含んでいるため、本測定系により構成イオンの平均電荷の構造依存性について議論することができる。その結果、薄膜透過後の平均電荷は鎖状構造の方が環状構造よりも大きく、さらに鎖状構造において、中心に位置するイオンよりも両端に位置するイオンの方が平均電荷は大きくなることがわかった。これらの実験結果は、薄膜中でのクーロン爆発と隣接するイオン場の影響を考慮したクラスター平均電荷の理論計算値と良い一致を見た。
を構成していた3つのイオンの分布)は電荷と解離前のクラスター構造の情報を含んでいるため、本測定系により構成イオンの平均電荷の構造依存性について議論することができる。その結果、薄膜透過後の平均電荷は鎖状構造の方が環状構造よりも大きく、さらに鎖状構造において、中心に位置するイオンよりも両端に位置するイオンの方が平均電荷は大きくなることがわかった。これらの実験結果は、薄膜中でのクーロン爆発と隣接するイオン場の影響を考慮したクラスター平均電荷の理論計算値と良い一致を見た。
鵜飼 光子*; 松浦 昌彰*; 久米 民和; 小林 泰彦; 菊地 正博; 坂下 哲哉
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 71, 2007/02
By electron spin resonance (ESR) spectroscopy, we revealed free radicals in irradiated foods. The representative ESR spectrum of irradiated food is composed of a sextet centered at g = 2.0, singlet at the same g-value and a singlet at g = 4.0. The first signal is attributable to a signal with hyperfine interactions of the Mn . The second signal is due to organic free radicals. The third signal may be originated from the Fe
. The second signal is due to organic free radicals. The third signal may be originated from the Fe . Upon
. Upon  -irradiation, new signals appeared. For the measure of irradiation effects, we proposed an advanced protocol for ESR detection of irradiated foods.
-irradiation, new signals appeared. For the measure of irradiation effects, we proposed an advanced protocol for ESR detection of irradiated foods.
城 昭典*; 柴田 良和*; 玉田 正男; 瀬古 典明; 片貝 秋雄
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 43, 2007/02
アミノメチルホスホン酸とスルホン酸基の2つの官能基をグラフト重合によりポリエチレン繊維に導入し、二官能性キレート繊維を合成した。0.01Mの亜鉛溶液を合成したキレート繊維を充填したカラムに流したところ、pH2においても、1000h の空間速度での破過特性は、50h
の空間速度での破過特性は、50h 亜鉛の場合と変わらず、高速に亜鉛イオンを吸着できることがわかった。また、この場合の吸着容量は0.72-0.85mmol/g-吸着材で、吸着した亜鉛は1Mの塩酸で定量的に溶離可能であった。
亜鉛の場合と変わらず、高速に亜鉛イオンを吸着できることがわかった。また、この場合の吸着容量は0.72-0.85mmol/g-吸着材で、吸着した亜鉛は1Mの塩酸で定量的に溶離可能であった。
近藤 孝文*; Yang, J.*; 菅 晃一*; 吉田 陽一*; 柴田 裕実*; 田口 光正; 小嶋 拓治
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 141, 2007/02
発光観測による重イオン照射初期活性種測定法の開発の一環として、重イオンが光源であると同時に励起源であることが原因となっている。分析光強度測定上の困難を克服するために、測定する波長領域で吸収も発光もほとんどないシクロヘキサンを溶媒として用いた。溶質としてピレン及びビフェニルを用いた。本手法では、ビーム強度が一定ならば、試料以外の光源や励起源やバックグランドは同一条件とみなせるので光吸収強度の計算が可能となることが期待された。しかし、今回の実験では分析光量,活性種濃度に直接関係するビームカレントの変動が大きく、光吸収強度を正確に求めることができなかった。
藤巻 秀; 中村 進一*; 鈴井 伸郎; 石岡 典子; 茅野 充男*; 松橋 信平
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 127, 2007/02
イネ,ソルガムなどを供試植物とし、生きた植物体におけるカドミウムの吸収・移行・蓄積の様子をPositron Emitting Tracer Imaging System(PETIS)を用いて非侵襲的・経時的・定量的に画像化する技術を確立した。
 Co
Co  -ray irradiations
-ray irradiations木村 敦; 田口 光正; 大谷 仁己*; 平塚 浩士*; 小嶋 拓治
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 61, 2007/02
水環境保全に関する研究の一環として、実排水中の内分泌撹乱化学物質(EDCs)の放射線照射による無害化処理技術の開発を行った。EDCsの中でも最も活性が高く人畜由来の女性ホルモンである17 -エストラジオール(E2)、及び工業目的として人工的に作られ、環境中の存在量が最も多いEDCsの一つとして挙げられる
-エストラジオール(E2)、及び工業目的として人工的に作られ、環境中の存在量が最も多いEDCsの一つとして挙げられる -ノニルフェノール(NPs)を放射線照射し、その分解挙動を明らかにするとともに、ヒト及びメダカレセプターを用いたYeast two-hybrid assayによってそれらの分解生成物を含めた毒性を評価した。この結果から、夾雑物の指標となる総有機炭素量(TOC)と無害化に必要となる線量の相関関係を明らかとした。さらに、これに基づき、実際にEDCsを含む実排水を電子ビームを用いて分解するモデルプロセスについて、コスト評価を行った。
-ノニルフェノール(NPs)を放射線照射し、その分解挙動を明らかにするとともに、ヒト及びメダカレセプターを用いたYeast two-hybrid assayによってそれらの分解生成物を含めた毒性を評価した。この結果から、夾雑物の指標となる総有機炭素量(TOC)と無害化に必要となる線量の相関関係を明らかとした。さらに、これに基づき、実際にEDCsを含む実排水を電子ビームを用いて分解するモデルプロセスについて、コスト評価を行った。
広田 耕一; 田口 光正; 箱田 照幸; 小嶋 拓治
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 59, 2007/02
ごみ焼却施設である高浜クリーンセンターから排出される1000m
 /hの排ガスに電子ビーム照射し、排ガス中のダイオキシン類を分解する試験を行った。その結果、所期の目的であった90%以上の分解率がダイオキシンでは12kGy、フランでは16kGyでそれぞれ得られた。この吸収線量の相違の原因を突き止めるため、同族体別にダイオキシン及びフランの分解挙動を調べた。その結果、ダイオキシンはおもに排ガスへの照射により生成するOHラジカルにより酸化分解しているのに対し、フランは照射後4塩素化同族体の濃度が増加したことなどから、おもに脱塩素反応を起こしていることを明らかにした。また、経済性評価を行い、既存施設に付設する場合現在普及しているバグフィルター法に比べ、電子ビーム法は7%程度年間コストを低く抑えることができることがわかった。
/hの排ガスに電子ビーム照射し、排ガス中のダイオキシン類を分解する試験を行った。その結果、所期の目的であった90%以上の分解率がダイオキシンでは12kGy、フランでは16kGyでそれぞれ得られた。この吸収線量の相違の原因を突き止めるため、同族体別にダイオキシン及びフランの分解挙動を調べた。その結果、ダイオキシンはおもに排ガスへの照射により生成するOHラジカルにより酸化分解しているのに対し、フランは照射後4塩素化同族体の濃度が増加したことなどから、おもに脱塩素反応を起こしていることを明らかにした。また、経済性評価を行い、既存施設に付設する場合現在普及しているバグフィルター法に比べ、電子ビーム法は7%程度年間コストを低く抑えることができることがわかった。
中川 清子*; 太田 信昭*; 田口 光正; 小嶋 拓治
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 142, 2007/02
ヒドロキシマレイミドを2-プロパノールに溶解し窒素置換した後、 線及び220MeV, Cイオンを照射し生成物収率の比較を行った。
線及び220MeV, Cイオンを照射し生成物収率の比較を行った。 線照射によるヒドロキシマレイミドの分解のG値は0.5であり、Cイオン照射ではその1/10以下であった。また、Cイオンの照射エネルギーが低いほど、G値はわずかに小さくなることがわかった。すなわち、LETが高くなると微分G値が小さくなると考えられる。また、
線照射によるヒドロキシマレイミドの分解のG値は0.5であり、Cイオン照射ではその1/10以下であった。また、Cイオンの照射エネルギーが低いほど、G値はわずかに小さくなることがわかった。すなわち、LETが高くなると微分G値が小さくなると考えられる。また、 線照射での主反応生成物であるヒドロキシスクシンイミドは、Cイオン照射ではほとんど生成せず、未同定の新しい生成物が観測されることが見いだされた。
線照射での主反応生成物であるヒドロキシスクシンイミドは、Cイオン照射ではほとんど生成せず、未同定の新しい生成物が観測されることが見いだされた。
百合 庸介; 宮脇 信正; 神谷 富裕; 横田 渉; 荒川 和夫; 福田 光宏*
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 188, 2007/02
高崎量子応用研究所放射線高度利用施設部では、均一照射システムの高度化として新たに、多重極電磁石を用いる方式について開発を行っている。本方式は、既存の均一照射システム(双極磁場による走査方式及び散乱体による拡大方式)の長所を併せ持つ。AVFサイクロトロンビーム輸送系における均一ビーム形成について、数値シミュレーションにより検討した。その結果、2台の8極電磁石を用いて、ターゲットにおいてガウスビームを均一化することが可能であることを確認した。数%の均一度の10cm四方の均一領域が形成できることがわかった。また、運動量分散や色収差など現実の輸送系やビームが有する性質が均一照射に及ぼす影響についても検討した。
上松 敬; 花屋 博秋
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 183, 2007/02
ガフフィルムとPC用イメージスキャナを用いた簡便なイオンビームの2次元フルエンス相対分布測定技術を開発した。感受層の薄いHD-810ガフフィルムは飛程の短い重イオンにも使うことができる。ガフを2MeVの電子線で照射し、各種モデルのスキャナを用い3色の色成分で測定を行うことで、それぞれの線量応答カーブを得た。各カーブはモデル及び色成分ごとに異なるものの、0から数百Gyの領域でリニアであることがわかった。この領域内において数ミクロンの高空間分解能で2次元のフルエンス測定を容易に行えることを、イオンビームスポットのフルエンス分布の測定で確かめた。
吉田 健一; 奈良 孝幸; 齋藤 勇一; 横田 渉
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 190, 2007/02
現在TIARAでは、プラズマの閉じ込めに電磁石を用いない全永久磁石型ECRイオン源(LECR)の開発を行っている。LECRの初期の運転では十分なビーム電流が得られなかった。この原因は、マイクロ波の出力を40W以上にすると引出し側の真空度が極端に悪化し、プラズマが維持できないことにあった。そこで引出し側の真空度の改善のため、新たに300L/minのTMPを設置した。また、導波管がプラズマから離れていたため、バイアス電位の効果が十分に得られていないことも原因の一つと考えられた。そこで導波管を60mm長くし、先端部を共鳴磁場付近まで到達するようにした。引出し側真空度の改善により、マイクロ波アンプの最高出力(125W)での連続運転が可能となりO5+のビーム電流値は15倍程度増加した。また導波管の改良により、改造前に確認できなかったO7+の生成を確認した。さらにLECRの特徴である可動磁石の効果を調べることができるようになり、本イオン源が電磁石型ECRイオン源でミラーコイルの電流を調整する場合と同様な効果を得られる見通しがついた。
横田 渉; 佐藤 隆博; 及川 将一*; 酒井 卓郎; 奥村 進; 倉島 俊; 宮脇 信正; 柏木 啓次; 神谷 富裕; 福田 光宏*
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 185, 2007/02
バイオ技術及び宇宙用半導体の研究開発のためにTIARAのサイクロトロンで進めている重イオンマイクロビーム形成技術の開発の、2005年度における進捗状況を報告する。260MeV- Ne
Ne ビームを用いて直径が約2
ビームを用いて直径が約2 mのマイクロビームを形成することに2004年度に成功した。2005年度には定常的に平均で1.7
mのマイクロビームを形成することに2004年度に成功した。2005年度には定常的に平均で1.7 mのマイクロビームを得た。これにより2
mのマイクロビームを得た。これにより2 m程度のマイクロビームを数時間の照射実験に提供できる見通しが立ったため、マイクロビームを大気に取出して照射する実験を初めて試みた。また、集束レンズが0.6
m程度のマイクロビームを数時間の照射実験に提供できる見通しが立ったため、マイクロビームを大気に取出して照射する実験を初めて試みた。また、集束レンズが0.6 m程度の振幅で振動していることをレーザー変位計による測定で確認したため、振動がビーム径に及ぼす影響を低減する方法を検討した。
m程度の振幅で振動していることをレーザー変位計による測定で確認したため、振動がビーム径に及ぼす影響を低減する方法を検討した。
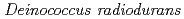 DNA repair-promoting protein; Applications to biotech industry
DNA repair-promoting protein; Applications to biotech industry鳴海 一成; 大庭 寛史; Sghaier, H.; 佐藤 勝也
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 69, 2007/02
放射線抵抗性細菌デイノコッカス・ラジオデュランスから分離した放射線高感受性変異株の放射線感受性の原因が、放射線誘導性の機能未知遺伝子に起こった点突然変異であることを明らかにした。この遺伝子から作られるPprA蛋白質は、DNA鎖切断部位に結合し、エキソヌクレアーゼから切断末端を保護すると同時に、DNAリガーゼによるDNA再結合修復反応を促進する作用があることを明らかにした。PprA蛋白質によるDNA修復促進作用についての技術移転を行い、高効率DNA修復試薬TA-Blunt Ligation Kitの製品化に成功した。この製品は、従来品に比べて約10倍のDNA再結合効率を持ち、DNA加工技術やDNA診断技術の高度化に有用である。
 遺伝子の放射線応答プロモーター
遺伝子の放射線応答プロモーター大庭 寛史; 佐藤 勝也; 柳沢 忠*; 鳴海 一成
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 70, 2007/02
放射線抵抗性細菌の優れたDNA2本鎖切断修復には、DNA損傷が生じた後に合成されるタンパク質が必要である。このことは、放射線抵抗性細菌には放射線誘導性のDNA修復機構があることを示している。しかしながら、放射線抵抗性細菌の放射線応答の分子機構を明らかにすることが重要であるにもかかわらず、放射線誘導性タンパク質遺伝子の発現に必要な放射線応答プロモーターについてはほとんど研究されていない。本研究では、放射線で発現が誘導される放射線抵抗性細菌デイノコッカス・ラジオデュランスの 遺伝子のプロモーターの放射線応答機構について、ルシフェラーゼ・レポーターアッセイを用いた解析を行った。その結果、放射線応答に必要最小プロモーター領域を同定することに成功した。本研究で同定した
遺伝子のプロモーターの放射線応答機構について、ルシフェラーゼ・レポーターアッセイを用いた解析を行った。その結果、放射線応答に必要最小プロモーター領域を同定することに成功した。本研究で同定した 遺伝子の放射線応答プロモーターは、今後デイノコッカス・ラジオデュランスの放射線応答機構を全容解明していくうえで非常に役立つものと考えられる。
遺伝子の放射線応答プロモーターは、今後デイノコッカス・ラジオデュランスの放射線応答機構を全容解明していくうえで非常に役立つものと考えられる。
前川 雅樹; Yu, R.; 河裾 厚男
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 152, 2007/02
イオン注入による各種の量子構造形成メカニズムは基礎・応用の両面において非常に重要である。われわれは、陽電子消滅法の量子構造研究への適用を試みている。まず2次元量子井戸構造として炭化ケイ素(SiC)への酸素イオン打ち込みによる埋め込み酸化膜の形成に着目した。このようなSiC-On-Insulator(SiC-OI)構造は実デバイス開発においても重要な技術であり多くの研究がなされている。試料作製時におけるイオン照射量や温度などの条件は、標準的な手法に則った。照射後は酸素打ち込み領域において多くの欠陥が生成したことが確認された。熱焼鈍によっても欠陥は完全に回復せず、また埋め込み酸化膜にも多くの欠陥が残留することが明らかとなった。このように本方式によって製作したSiC-OI構造は非常に多くの欠陥を含有した構造であるため、陽電子の量子的振る舞いを発現させるにいたらなかったが、一方でこれらの結果は、従来考えられていた埋め込み酸化膜層形成方法よりも高温での熱アニールやイオン注入を行うことで、より欠陥含有量の少ない高品質な基板作成が可能になることを示唆するものとなった。