Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
 (Al, Zn)
(Al, Zn) Approximant crystal; Influence of chemical disorder
Approximant crystal; Influence of chemical disorder清水 一行*; 山口 正剛; 赤丸 悟士*; 西村 克彦*; 阿部 李音*; 佐々木 泰祐*; Wang, Y.*; 戸田 裕之*
Scripta Materialia, 265, p.116730_1 - 116730_7, 2025/08
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Nanoscience & Nanotechnology)The approximant crystal Mg (Al, Zn)
(Al, Zn) (T-phase in Al-Zn-Mg alloys) holds the potential for enhancing both strength and hydrogen embrittlement resistance in aluminum alloys when present as nano-precipitates. Our previous computational exploration indicated strong hydrogen trapping but neglected the inherent chemical disorder of this approximant crystal. This study revisits hydrogen trapping in Mg
(T-phase in Al-Zn-Mg alloys) holds the potential for enhancing both strength and hydrogen embrittlement resistance in aluminum alloys when present as nano-precipitates. Our previous computational exploration indicated strong hydrogen trapping but neglected the inherent chemical disorder of this approximant crystal. This study revisits hydrogen trapping in Mg (Al, Zn)
(Al, Zn) , directly including chemical disorder via special quasirandom structures. Density functional theory calculations reveal that, while chemical disorder introduces variations in trapping energies, the overall trend of strong trapping persists. Tetrahedral sites coordinated by Mg atoms exhibit particularly strong trapping, with smaller tetrahedral volumes correlating with stronger trapping due to enhanced Mg-H interactions. Multiple hydrogen occupation of these sites is also calculated, resulting in high hydrogen densities. Experimental validation using thermal desorption spectroscopy on a bulk Mg
, directly including chemical disorder via special quasirandom structures. Density functional theory calculations reveal that, while chemical disorder introduces variations in trapping energies, the overall trend of strong trapping persists. Tetrahedral sites coordinated by Mg atoms exhibit particularly strong trapping, with smaller tetrahedral volumes correlating with stronger trapping due to enhanced Mg-H interactions. Multiple hydrogen occupation of these sites is also calculated, resulting in high hydrogen densities. Experimental validation using thermal desorption spectroscopy on a bulk Mg (Al, Zn)
(Al, Zn) sample confirms hydrogen trapping, reinforcing the potential of this phase for designing advanced, hydrogen-resistant aluminum alloys.
sample confirms hydrogen trapping, reinforcing the potential of this phase for designing advanced, hydrogen-resistant aluminum alloys.
清水 一行*; 戸田 裕之*; 平山 恭介*; 藤原 比呂*; 都留 智仁; 山口 正剛; 佐々木 泰祐*; 上椙 真之*; 竹内 晃久*
International Journal of Hydrogen Energy, 109, p.1421 - 1436, 2025/03
被引用回数:2 パーセンタイル:93.94(Chemistry, Physical)我々の先行研究では、MgZn 析出物の整合界面における複数の水素トラップが自発的な界面剥離を引き起こし、Al-Zn-Mg合金に水素誘起擬へき開割れを引き起こすことを明らかにした。本研究では、析出物の整合/半整合界面にトラップされた水素が時効を通じてMgZn
析出物の整合界面における複数の水素トラップが自発的な界面剥離を引き起こし、Al-Zn-Mg合金に水素誘起擬へき開割れを引き起こすことを明らかにした。本研究では、析出物の整合/半整合界面にトラップされた水素が時効を通じてMgZn の整合界面を調整し、マクロ的な水素脆化に影響を与えるメカニズムを識別するために定量的かつ体系的な調査を行った。析出物界面での水素捕捉に基づくこの水素脆化現象を調査するために、第一原理計算により半整合MgZn
の整合界面を調整し、マクロ的な水素脆化に影響を与えるメカニズムを識別するために定量的かつ体系的な調査を行った。析出物界面での水素捕捉に基づくこの水素脆化現象を調査するために、第一原理計算により半整合MgZn 界面の水素捕捉エネルギーを決定した。空孔、粒界、整合および半整合MgZn
界面の水素捕捉エネルギーを決定した。空孔、粒界、整合および半整合MgZn 界面を含むすべての水素捕捉サイトの水素分配は、過時効合金では90%を超える水素が半整合界面に隔離されていることを明らかにした。MgZn
界面を含むすべての水素捕捉サイトの水素分配は、過時効合金では90%を超える水素が半整合界面に隔離されていることを明らかにした。MgZn 界面の固有の特性により、半整合界面に隔離された水素は界面凝集エネルギーを減少させ、Al-Zn-Mg合金で界面の半自発的剥離と擬へき開破壊を引き起こした。これらの結果は、粒界破壊は粒界に捕捉された水素によって直接誘発されるのではなく、粒界に沿った析出物界面の剥離によって引き起こされることを示唆している。
界面の固有の特性により、半整合界面に隔離された水素は界面凝集エネルギーを減少させ、Al-Zn-Mg合金で界面の半自発的剥離と擬へき開破壊を引き起こした。これらの結果は、粒界破壊は粒界に捕捉された水素によって直接誘発されるのではなく、粒界に沿った析出物界面の剥離によって引き起こされることを示唆している。
阿部 陽介; 都留 智仁; 藤田 洋平*; 大友 政秀*; 佐々木 泰祐*; 山下 真一郎; 大久保 成彰; 鵜飼 重治
Journal of Nuclear Materials, 606, p.155606_1 - 155606_12, 2025/02
被引用回数:1 パーセンタイル:0.00(Materials Science, Multidisciplinary)軽水炉の事故耐性燃料被覆管用として開発中の酸化物分散強化型Fe-Cr-Al合金では、Crリッチ析出物( 相)に起因する脆化挙動の解明と予測が課題となっている。我々は、熱時効によるFe-Cr-Alモデル合金における
相)に起因する脆化挙動の解明と予測が課題となっている。我々は、熱時効によるFe-Cr-Alモデル合金における 相の形成に対するAl添加の影響を調査した。ビッカース硬さ試験と過去の研究のデータベースを用いて作成した機械学習モデルにより、低Al添加合金では
相の形成に対するAl添加の影響を調査した。ビッカース硬さ試験と過去の研究のデータベースを用いて作成した機械学習モデルにより、低Al添加合金では 相の形成が促進され、高Al添加合金では抑制されることが示された。第一原理計算では、Cr-Al-空孔複合体はCr-Cr対よりも安定であり、
相の形成が促進され、高Al添加合金では抑制されることが示された。第一原理計算では、Cr-Al-空孔複合体はCr-Cr対よりも安定であり、 相の核生成時にAl原子を取り込むことがエネルギー的に有利である可能性があることが示された。一方、Al-Al対の形成は非常に不安定である。Al添加量が少ない場合には、
相の核生成時にAl原子を取り込むことがエネルギー的に有利である可能性があることが示された。一方、Al-Al対の形成は非常に不安定である。Al添加量が少ない場合には、 相の界面付近でのAl-Al対の形成は回避できる。しかし、Al添加量が多量の場合には、Al-Al対の形成が避けられなくなり、
相の界面付近でのAl-Al対の形成は回避できる。しかし、Al添加量が多量の場合には、Al-Al対の形成が避けられなくなり、 相の不安定化につながることが示唆された。
相の不安定化につながることが示唆された。
阿部 陽介; 佐々木 泰祐*; 山下 真一郎; 大久保 成彰; 鵜飼 重治
Journal of Nuclear Materials, 600, p.155271_1 - 155271_12, 2024/11
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Materials Science, Multidisciplinary)軽水炉用燃料被覆管として開発中のFeCrAl-ODS (ODS:酸化物分散強化)合金のモデル合金として、CrとAlの組成を系統的に変化させた14種類のFe-Cr-Al合金を Cで10.5MeVの自己イオンにより0.24dpaまで照射した。中性子照射条件下でのCrリッチ析出物(CrRP)の生成挙動を予測するために、3水準の損傷速度を選択した。3次元アトムプローブ解析の結果、Cr組成の増加、Al組成の減少及び損傷速度の減少に伴い、CrRP数密度、体積率及びCr濃度が増加することがわかった。重回帰分析の結果、これらの主要な効果に加えて、CrRP体積率には次の交互作用があることが示された:(1)Al組成が高いほど、Cr組成の増加に伴うCrRP体積率の増加は小さく、(2)Cr組成が低いほど、Al組成および損傷速度の低下に伴うCrRP体積率の増加は小さい。また、中性子照射下でのCrRP生成挙動に対する損傷速度の影響を理解するためには、損傷量依存性の観点に加えて、損傷速度ゼロの限界として熱時効データを利用することが有効であることを強調した。本研究で構築した体系的なCrRP関連量のデータベースは、数値予測モデルのさらなる開発と検証に貢献するものと考えられる。
Cで10.5MeVの自己イオンにより0.24dpaまで照射した。中性子照射条件下でのCrリッチ析出物(CrRP)の生成挙動を予測するために、3水準の損傷速度を選択した。3次元アトムプローブ解析の結果、Cr組成の増加、Al組成の減少及び損傷速度の減少に伴い、CrRP数密度、体積率及びCr濃度が増加することがわかった。重回帰分析の結果、これらの主要な効果に加えて、CrRP体積率には次の交互作用があることが示された:(1)Al組成が高いほど、Cr組成の増加に伴うCrRP体積率の増加は小さく、(2)Cr組成が低いほど、Al組成および損傷速度の低下に伴うCrRP体積率の増加は小さい。また、中性子照射下でのCrRP生成挙動に対する損傷速度の影響を理解するためには、損傷量依存性の観点に加えて、損傷速度ゼロの限界として熱時効データを利用することが有効であることを強調した。本研究で構築した体系的なCrRP関連量のデータベースは、数値予測モデルのさらなる開発と検証に貢献するものと考えられる。
 Be and
Be and  Al under direct muon-induced spallation in granite quartz and its implications for past high-energy cosmic ray fluxes
Al under direct muon-induced spallation in granite quartz and its implications for past high-energy cosmic ray fluxes櫻井 敬久*; 紅林 泰*; 鈴木 颯一郎*; 堀内 一穂*; 高橋 唯*; 堂下 典弘*; 菊地 聡*; 門叶 冬樹*; 岩田 尚能*; 田島 靖*; et al.
Physical Review D, 109(10), p.102005_1 - 102005_18, 2024/05
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Astronomy & Astrophysics)銀河宇宙線の永年変化は銀河の活動に密接に関係しており、局所的な銀河磁場・星間雲・超新星残骸の近くの環境が反映される。高エネルギー銀河宇宙線によって大気中で生成される高エネルギーミューオンは、深い地層まで透過し、岩石中に放射性同位体を生成する。 Beや
Beや Alのような長寿命の放射性核種は岩石中に蓄積されるため、高エネルギーミューオンの収量の長期変動、ひいては数百万年間の高エネルギー銀河宇宙線(GCR)の長期変動の調査に利用できる。本研究では、CERN SPSのCOMPASS実験ラインにて、160GeV/cの正ミューオンを合成石英プレートと花崗岩コアに照射して、岩石中の
Alのような長寿命の放射性核種は岩石中に蓄積されるため、高エネルギーミューオンの収量の長期変動、ひいては数百万年間の高エネルギー銀河宇宙線(GCR)の長期変動の調査に利用できる。本研究では、CERN SPSのCOMPASS実験ラインにて、160GeV/cの正ミューオンを合成石英プレートと花崗岩コアに照射して、岩石中の Beと
Beと Alの生成断面積を測定した。更に、ミューオンが直接起こす核破砕反応とミューオンが生成した二次粒子が引き起こす反応が、岩石中での長寿命核種の生成にそれぞれどの程度寄与するかを明らかにした。
Alの生成断面積を測定した。更に、ミューオンが直接起こす核破砕反応とミューオンが生成した二次粒子が引き起こす反応が、岩石中での長寿命核種の生成にそれぞれどの程度寄与するかを明らかにした。
 )
) (Bi
(Bi Te
Te )
) superlattice films by Te desorption from a pristine Bi
superlattice films by Te desorption from a pristine Bi Te
Te film
film日下 翔太郎*; 佐々木 泰祐*; 角田 一樹; 一ノ倉 聖*; 出田 真一郎*; 田中 清尚*; 宝野 和博*; 平原 徹*
Applied Physics Letters, 120(17), p.173102_1 - 173102_5, 2022/04
被引用回数:4 パーセンタイル:33.23(Physics, Applied)We fabricated superlattice films composed of Bi bilayers (BLs) and Bi
bilayers (BLs) and Bi Te
Te quintuple layers (QLs) by annealing pure Bi
quintuple layers (QLs) by annealing pure Bi Te
Te films. It was found that Te desorbs from the QL to form the BL with an activation energy of 2.7 eV. Eventually two distinct stoichiometric phases were formed, Bi
films. It was found that Te desorbs from the QL to form the BL with an activation energy of 2.7 eV. Eventually two distinct stoichiometric phases were formed, Bi Te
Te (QL-BL-QL) and Bi
(QL-BL-QL) and Bi Te
Te (QL-BL), as evidenced by scanning transmission emission microscopy measurements. The surface-state dispersion was measured with angle-resolved photoemission spectroscopy and the topological nature of each sample is discussed. Our method offers a convenient and simple way to fabricate superlattice films with different topological properties.
(QL-BL), as evidenced by scanning transmission emission microscopy measurements. The surface-state dispersion was measured with angle-resolved photoemission spectroscopy and the topological nature of each sample is discussed. Our method offers a convenient and simple way to fabricate superlattice films with different topological properties.
淵田 知希*; 浦田 泰成*; 松山 嗣史*; 村上 昌史; 吉田 幸彦; 植田 昭彦; 町田 昌彦; 佐々木 紀樹; 辻 幸一*
X線分析の進歩,53, p.77 - 87, 2022/03
蛍光X線(XRF: X-ray fluorescence)分析法はX線を試料に照射し、発生した蛍光X線を検出することで試料の元素分析を行う手法である。試料を走査しながら連続的なXRF分析を行うことで、二次元の元素分布像の取得が可能である。本研究では、ベルトコンベア上を連続的に移動する試料に対して、二次元の元素分布像を迅速に取得するためのXRF分析装置を開発した。元素分布像の測定は、X線を広範囲に照射したベルトコンベアを横切る方向に、コリメーターを取り付けた検出器を走査することにより実施し、この方法における試料や検出器の移動方向の空間分解能や検出限界を検証した。また、2種類の金属試料について同時に元素分布像を測定し、開発した装置により多元素同時イメージングが実施できることを実証した。
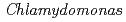 spp. microalgae in a pond near the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant
spp. microalgae in a pond near the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant佐々木 祥人; 舟木 泰智; 藤原 健壮
Limnology, 23(1), p.1 - 7, 2022/01
被引用回数:1 パーセンタイル:3.77(Limnology)福島第一原子力発電所近傍の池において微細藻類の生体および遺体への放射性セシウムの移行について調査した。生体においては、池内の微細藻類数と0.45 m以上の池内の浮遊物質の放射性セシウム濃度に相関がみられたことから、微細藻類がその池における0.45
m以上の池内の浮遊物質の放射性セシウム濃度に相関がみられたことから、微細藻類がその池における0.45 m以上の浮遊物質の放射性セシウム濃度の支配要因であることが示された。水に対する微細藻類の移行係数は、1.6
m以上の浮遊物質の放射性セシウム濃度の支配要因であることが示された。水に対する微細藻類の移行係数は、1.6 10
10 であった。また、微細藻類の遺体においても放射性セシウムが生体と同程度、吸着し沈殿することが明らかになった。
であった。また、微細藻類の遺体においても放射性セシウムが生体と同程度、吸着し沈殿することが明らかになった。
長尾 郁弥; 新里 忠史; 佐々木 祥人; 伊藤 聡美; 渡辺 貴善; 土肥 輝美; 中西 貴宏; 佐久間 一幸; 萩原 大樹; 舟木 泰智; et al.
JAEA-Research 2020-007, 249 Pages, 2020/10
2011年3月11日に発生した太平洋三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波により、東京電力(現東京電力ホールディングス)福島第一原子力発電所の事故が発生し、その結果、環境中へ大量の放射性物質が放出された。この事故により放出された放射性核種は、その大部分が森林に沈着している。これに対し、面積が広大であり大量の除去土壌などが生じる、多面的な森林の機能が損なわれる可能性があるなどの問題があり、生活圏近傍を除き、汚染された森林の具体的な除染計画はない。そのため、未除染の森林から放射性セシウムが流出し、既に除染された生活圏に流入することで空間線量率が上がってしまうのではないか(外部被ばくに関する懸念)、森林から河川に流出した放射性セシウムが農林水産物に取り込まれることで被ばくするのではないか、規制基準値を超えて出荷できないのではないか(内部被ばくに関する懸念)などの懸念があり、避難住民の帰還や産業再開の妨げとなる可能性があった。日本原子力研究開発機構では、環境中に放出された放射性物質、特に放射性セシウムの移動挙動に関する「長期環境動態研究」を2012年11月より実施している。この目的は、自治体の施策立案を科学的側面から補助する、住民の環境安全に関する不安を低減し、帰還や産業再開を促進するといった点にある。本報告書は、原子力機構が福島県で実施した環境動態研究におけるこれまでの研究成果について取りまとめたものである。
平原 徹*; Otrokov, M. M.*; 佐々木 泰祐*; 角田 一樹*; 友弘 雄太*; 日下 翔太郎*; 奥山 裕磨*; 一ノ倉 聖*; 小林 正起*; 竹田 幸治; et al.
Nature Communications (Internet), 11, p.4821_1 - 4821_8, 2020/09
被引用回数:53 パーセンタイル:90.85(Multidisciplinary Sciences)We fabricate a novel magnetic topological heterostructure Mn Bi
Bi Te
Te /Bi
/Bi Te
Te where multiple magnetic layers are inserted into the topmost quintuple layer of the original topological insulator Bi
where multiple magnetic layers are inserted into the topmost quintuple layer of the original topological insulator Bi Te
Te . A massive Dirac cone (DC) with a gap of 40-75 meV at 16 K is observed. By tracing the temperature evolution, this gap is shown to gradually decrease with increasing temperature and a blunt transition from a massive to a massless DC occurs around 200-250 K. Magnetic measurements show that there are two distinct Mn components in the system that corresponds to the two heterostructures; MnBi
. A massive Dirac cone (DC) with a gap of 40-75 meV at 16 K is observed. By tracing the temperature evolution, this gap is shown to gradually decrease with increasing temperature and a blunt transition from a massive to a massless DC occurs around 200-250 K. Magnetic measurements show that there are two distinct Mn components in the system that corresponds to the two heterostructures; MnBi Te
Te /Bi
/Bi Te
Te is paramagnetic at 6 K while Mn
is paramagnetic at 6 K while Mn Bi
Bi Te
Te /Bi
/Bi Te
Te is ferromagnetic with a negative hysteresis (critical temperature 20 K). This novel heterostructure is potentially important for future device applications.
is ferromagnetic with a negative hysteresis (critical temperature 20 K). This novel heterostructure is potentially important for future device applications.
長尾 郁弥; 新里 忠史; 佐々木 祥人; 伊藤 聡美; 渡辺 貴善; 土肥 輝美; 中西 貴宏; 佐久間 一幸; 萩原 大樹; 舟木 泰智; et al.
JAEA-Research 2019-002, 235 Pages, 2019/08
2011年3月11日に発生した太平洋三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生した津波により、東京電力福島第一原子力発電所の事故が発生し、その結果、環境中へ大量の放射性物質が放出され、その大部分が森林に沈着している。これに対し、面積が広大であり大量の除去土壌等が生じる、多面的な森林の機能が損なわれる可能性があるなどの問題があり、生活圏近傍を除き、汚染された森林の具体的な除染計画はない。そのため、未除染の森林から放射性セシウムが流出し、既に除染された生活圏に流入することに対する懸念があり、避難住民の帰還や産業再開の妨げとなる可能性があった。原子力機構では、環境中に放出された放射性物質、特に放射性セシウムの移動挙動に関する「長期環境動態研究」を2012年11月より実施している。この目的は、自治体の施策立案を科学的側面から補助する、住民の環境安全に関する不安を低減し、帰還や産業再開を促進するといった点にある。本報告書は、原子力機構が福島県で実施した環境動態研究におけるこれまでの研究成果について取りまとめたものである。
舟木 泰智; 高原 省五; 佐々木 美雪; 吉村 和也; 中間 茂雄; 眞田 幸尚
JAEA-Research 2018-016, 48 Pages, 2019/03
内閣府原子力災害対策本部は、平成34年から35年度までに避難指示解除が計画される「特定復興再生拠点区域」において、放射線防護対策を検討している。これにあたり、当該区域の汚染状況の把握と被ばく線量の評価は必要不可欠である。福島第一原子力発電所事故以降、数々のモニタリングにより空間線量率分布が評価され、それらを元に被ばく線量が推定されてきた。一方、当該区域は比較的空間線量率が高く、放射線防護に対してより慎重な配慮が必要であるため、被ばくに係る詳細な情報が求められている。そこで本研究では、詳細な汚染状況と当該区域の状況に即した被ばく線量を評価することを目的とし、(1)無人ヘリコプターによる空間線量率の測定、(2)大気中の放射性セシウム濃度の測定、(3)代表的な行動パターンにおける外部・内部実効線量の評価を実施した。併せて、空間線量率分布のモニタリング手法と被ばく線量評価方法の高度化を検討した。本調査により、空間線量率の3次元マップを提示し、当該区域における分布傾向を明らかにすると共に被ばく線量を推定し、吸入による内部被ばく線量は外部被ばく線量の1%未満であることを示した。また今後の放射線防護において有効かつ新たな空間線量率のモニタリング手法と被ばく線量評価方法の妥当性を示した。
 @C
@C ; Photoelectron spectroscopy of the Li
; Photoelectron spectroscopy of the Li @C
@C [PF
[PF
 ] salt and STM of the single Li
] salt and STM of the single Li @C
@C molecules on Cu(111)
molecules on Cu(111)山田 洋一*; Kuklin, A. V.*; 佐藤 翔*; 江坂 文孝; 角 直也*; Zhang, C.*; 佐々木 正洋*; Kwon, E.*; 笠間 泰彦*; Avramov, P. V.*; et al.
Carbon, 133, p.23 - 30, 2018/07
被引用回数:18 パーセンタイル:51.01(Chemistry, Physical)本研究では、超高真空中で高純度Li @C
@C [PF
[PF
 ]塩の蒸発によってLi
]塩の蒸発によってLi イオン内包フラーレンを調製し、走査型トンネル顕微鏡(STM)により明瞭に観察することに成功した。また、STM観察に先立って、光電子分光およびX線吸収分光などにより測定したところ、Liは正、PF
イオン内包フラーレンを調製し、走査型トンネル顕微鏡(STM)により明瞭に観察することに成功した。また、STM観察に先立って、光電子分光およびX線吸収分光などにより測定したところ、Liは正、PF は負のチャージを帯びており、C
は負のチャージを帯びており、C は中性であることが明らかとなった。
は中性であることが明らかとなった。
高屋 茂; 佐々木 直人*; 浅山 泰; 神島 吉郎*
Mechanical Engineering Journal (Internet), 4(3), p.16-00558_1 - 16-00558_12, 2017/06
本論文では、より合理的な容器の設計を可能にするために、荷重耐力係数設計法を用いて、地震による容器の座屈防止に関する新しい設計評価法を開発した。さらに、現行規定との比較により、提案手法の有効性を示した。
佐々木 祥人; 舟木 泰智; 伊利 沙汀; 土肥 輝美; 萩原 大樹
Limnology, 17(2), p.111 - 116, 2016/04
被引用回数:14 パーセンタイル:40.60(Limnology)福島第一原子力発電所周辺の河川(1地点)およびため池(4地点)に生育していた水草(5種)および藻類(3属)への放射性セシウムの移行挙動を調べた。堆積物-植物移行係数[( Cs Bq/kg-dry weight plant)
Cs Bq/kg-dry weight plant) (
(  Cs Bq/kg-dry weight sediment)
Cs Bq/kg-dry weight sediment) ]は、水草では河川に生育していたエビモが5.55と最も高く、ため池から採取したヒルムシロが3.34
]は、水草では河川に生育していたエビモが5.55と最も高く、ため池から採取したヒルムシロが3.34 10
10 と最も低く、同属の水草でも違いがあることが示された。糸状藻(
と最も低く、同属の水草でも違いがあることが示された。糸状藻( sp.)およびシアノバクテリアの水-植物移行係数[(
sp.)およびシアノバクテリアの水-植物移行係数[( Cs Bq/kg-dry weight plant)
Cs Bq/kg-dry weight plant)  (
( Cs Bq/L water)-1]は、それぞれ2.39
Cs Bq/L water)-1]は、それぞれ2.39 10
10 、1.26
、1.26 10
10 であることが示された。採取水中におけるシアノバクテリア画分のみの
であることが示された。採取水中におけるシアノバクテリア画分のみの Cs濃度は、4.87
Cs濃度は、4.87 10
10 Bq/Lであり、シアノバクテリアが生息していた水中のセシウム濃度と同オーダーであり、シアノバクテリアへの顕著な放射性セシウムの濃集は確認されなかった。
Bq/Lであり、シアノバクテリアが生息していた水中のセシウム濃度と同オーダーであり、シアノバクテリアへの顕著な放射性セシウムの濃集は確認されなかった。
佐々木 明; 加藤 進*; 高橋 栄一*; 岸本 泰明*; 藤井 隆*; 金澤 誠司*
Japanese Journal of Applied Physics, 55(2), p.026101_1 - 026101_10, 2016/02
被引用回数:2 パーセンタイル:8.67(Physics, Applied)放電の確率的な振る舞いを再現するパーコレーションモデルによるシミュレーションについて述べる。放電領域をマクロ的なセルに分割し、それぞれが絶縁体か導体かのいずれかの状態にあることを確率的に決定し、セルが構成するメッシュ上で回路方程式を解く方法で、電場や電流の構造の時間発展を計算した。空間の静電容量及び、各場所の電離のダイナミクスを考慮することと、電離領域の生成、消滅の確率を、電界や電流密度の大きさで重み付けすることで、印加電界の効果や媒質の特性を考慮した。電極・ストリーマ先端の電離と、媒質内部のランダムな電離の両方が放電の構造形成に重要な役割を持つことがわかった。計算は、電圧印加後、部分放電が起こるタイムラグがあって、そののちにステップドリーダが成長して短絡する様相を再現することができた。
佐々木 祐二; 佐伯 盛久; 須郷 由美; 池田 泰久*; 川崎 武志*; 鈴木 智也*; 大橋 朗*
Solvent Extraction Research and Development, Japan, 22(1), p.37 - 45, 2015/05
被引用回数:15 パーセンタイル:41.95(Chemistry, Multidisciplinary)新抽出剤のMIDOA(メチルイミノジオクチルアセトアミド)を用いて、Pd(II), Nb(V), Ta(V), Cr(VI), Mo(VI), W(VI), Tc(VII), Re(VII)等の溶媒抽出を行い、関連化合物のIDOA(イミノジオクチルアセトアミド)やMIDEHA(メチルイミノジエチルヘキシルアセトアミド)、TODGA(テトラオクチルジグリコールアミド)、TDGA(チアジグリコールアミド)等の結果を比較した。これらの結果より、MIDOAによる分配比はIDOAやMIDEHAよりやや高いこと、Pd, Re分配比はTODGA, TDGAより高いことを明らかにした。
佐々木 祐二; 北辻 章浩; 須郷 由美; 津幡 靖宏; 鈴木 智也; 木村 貴海; 森田 泰治
Proceedings of 20th International Solvent Extraction Conference (ISEC 2014), p.431 - 435, 2014/09
ポダンド系を含む8種の異なる抽出剤を開発し、アクチノイド元素に対する分配比を比較した。抽出に関して化合物の中心骨格が大きく影響し、この中でジグリコールアミド(DGA)化合物が最も高い分配比を示した。加えて、DGA化合物の窒素原子に結合する置換基の効果について検討した。立体障害や水素結合などを持つような化合物によるアクチノイドの分配比は低いことが示唆された。
佐々木 祐二; 津幡 靖宏; 北辻 章浩; 須郷 由美; 白数 訓子; 池田 泰久*; 川崎 武志*; 鈴木 智也*; 三村 均*; 臼田 重和*; et al.
JAEA-Research 2014-008, 220 Pages, 2014/06
文部科学省からの委託事業、原子力システム研究開発事業で行った研究「疎水性,親水性新規ジアミド化合物によるMA相互分離技術開発」3年間の成果をまとめる。本事業は次の3つのテーマからなる、(1)MA+Ln一括分離技術開発:DOODA基礎特性評価、(2)Am/Cm/Ln相互分離技術開発: Ln錯体の基礎特性評価,溶媒抽出分離法,抽出クロマトグラフィー法、(3)分離技術評価: プロセス評価。(1)では新規抽出剤であるDOODAの基礎特性の成果をまとめた。(2)では新規配位子が配位した金属錯体の構造解析結果、抽出剤を使った溶媒抽出結果、及び抽出クロマトグラフィーでのカラム分離結果をまとめた。(3)ではこれら結果を総合して相互分離フローを作成し、それぞれフラクションの元素量,放射能量,発熱量の評価を行った。
 ]) solution of [EMI]
]) solution of [EMI] [UO
[UO (NO
(NO )
) ]; First spectrophotometric evidence for existence of [UO
]; First spectrophotometric evidence for existence of [UO (NO
(NO )
) ]
]
佐々木 琴江*; 鈴木 智也*; 新井 剛*; 鷹尾 康一朗*; 鈴木 伸一; 矢板 毅; 池田 泰久*
Chemistry Letters, 43(5), p.670 - 672, 2014/05
被引用回数:8 パーセンタイル:27.32(Chemistry, Multidisciplinary)イオン性液体1-Ethyl-3-methylimidazolium nitrate溶液における[EMI] [UO
[UO (NO
(NO )
) ]中のウランの存在状態について吸収スペクトルを用いる解析を行った。ウランの最近接には、4つの硝酸イオンのみが存在する[UO
]中のウランの存在状態について吸収スペクトルを用いる解析を行った。ウランの最近接には、4つの硝酸イオンのみが存在する[UO (NO
(NO )
) ]
] のような構造を有することが明らかとなった。
のような構造を有することが明らかとなった。