Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
山本 風海; 金正 倫計; 林 直樹; Saha, P. K.; 田村 文彦; 山本 昌亘; 谷 教夫; 高柳 智弘; 神谷 潤一郎; 菖蒲田 義博; et al.
Journal of Nuclear Science and Technology, 59(9), p.1174 - 1205, 2022/09
被引用回数:7 パーセンタイル:74.40(Nuclear Science & Technology)J-PARC 3GeVシンクロトロン(RCS)は、最大1MWの大強度ビームを25Hzという早い繰り返しで中性子実験及び下流の主リングシンクロトロンに供給することを目的に設計された。2007年の加速器調整運転開始以降、RCSではビーム試験を通じて加速器の設計性能が満たされているかの確認を進め、必要に応じてより安定に運転するための改善を行ってきた。その結果として、近年RCSは1MWのビーム出力で連続運転を行うことが可能となり、共用運転に向けた最後の課題の抽出と対策の検討が進められている。本論文ではRCSの設計方針と実際の性能、および改善点について議論する。
佐々木 祐二; 森田 圭介; 伊藤 圭祐; 鈴木 伸一; 塩飽 秀啓; 高橋 優也*; 金子 昌章*; 大森 孝*; 浅野 和仁*
Proceedings of International Nuclear Fuel Cycle Conference (GLOBAL 2017) (USB Flash Drive), 4 Pages, 2017/09
高レベル廃液中のPd, Zr, Se, Csは長半減期核種のPd-107, Zr-93, Se-79, Cs-135を有している。高レベル廃液から除去し、核変換により処分することで、環境負荷低減に役立てることができる。これら元素について、PdはMIDOA, NTAアミド、Csはクラウンエーテル、ZrはTODGA, HDEHP, Seはフェニレンジアミンで抽出可能である。それぞれ元素の回収条件について検討した成果について述べる。
佐々木 祐二; 森田 圭介; 鈴木 伸一; 塩飽 秀啓; 伊藤 圭祐; 高橋 優也*; 金子 昌章*
Solvent Extraction Research and Development, Japan, 24(2), p.113 - 122, 2017/06
硝酸溶液からオクタノールまたはドデカン溶媒へのSe, Zr, Pd, Csの溶媒抽出を行った。これら元素は長半減期の核種を含み、高レベル廃液の処理にとってこれら元素の簡便な分離方法の開発が不可欠である。Seはフェニレンジアミン、ZrはHDEHP又はTODGA、PdはMIDOA又はNTAアミドで抽出可能である。CsはDtBuDB18C6を用いて、抽出溶媒を水相の10倍を用いることで90%回収を達成できることを確認した。
近藤 恭弘; 浅野 博之*; 千代 悦司; 平野 耕一郎; 石山 達也; 伊藤 崇; 川根 祐輔; 菊澤 信宏; 明午 伸一郎; 三浦 昭彦; et al.
Proceedings of 28th International Linear Accelerator Conference (LINAC 2016) (Internet), p.298 - 300, 2017/05
J-PARC加速器の要素技術開発に必要な3MeV H リニアックを構築した。イオン源にはJ-PARCリニアックと同じものを用い、RFQは、J-PARCリニアックで2014年まで使用したものを再利用している。設置作業の後、2016年6月からRFQのコンディショニングを開始した。このRFQは様々な問題を克服し、なんとか安定運転に達していたが、2年間運転できなかったので再度コンディショニングが必要であった。現状定格のデューティーファクタでは運転できてはいないが、短パルスならばビーム運転可能となっている。この論文では、この3MeV加速器のコミッショニングと最初の応用例であるレーザー荷電変換試験の現状について述べる。
リニアックを構築した。イオン源にはJ-PARCリニアックと同じものを用い、RFQは、J-PARCリニアックで2014年まで使用したものを再利用している。設置作業の後、2016年6月からRFQのコンディショニングを開始した。このRFQは様々な問題を克服し、なんとか安定運転に達していたが、2年間運転できなかったので再度コンディショニングが必要であった。現状定格のデューティーファクタでは運転できてはいないが、短パルスならばビーム運転可能となっている。この論文では、この3MeV加速器のコミッショニングと最初の応用例であるレーザー荷電変換試験の現状について述べる。
平野 耕一郎; 浅野 博之; 石山 達也; 伊藤 崇; 大越 清紀; 小栗 英知; 近藤 恭弘; 川根 祐輔; 菊澤 信宏; 佐藤 福克; et al.
Proceedings of 13th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan (インターネット), p.310 - 313, 2016/11
単位面積当たりの熱負荷を減らすため、67 のビーム入射角を有するビームスクレーパをJ-PARCリニアックのRFQとDTLの間のMEBTで使用している。67
のビーム入射角を有するビームスクレーパをJ-PARCリニアックのRFQとDTLの間のMEBTで使用している。67 ビームスクレーパは粒子数1.47E22個のH
ビームスクレーパは粒子数1.47E22個のH ビームによって照射された。レーザ顕微鏡を用いてスクレーパのビーム照射による損傷部を観察すると、高さ数百
ビームによって照射された。レーザ顕微鏡を用いてスクレーパのビーム照射による損傷部を観察すると、高さ数百 mの突起物が無数にあった。ビームスクレーパの耐電力を調べるため、3MeVリニアックを新たに構築した。2016年末にスクレーパ照射試験を実施する予定である。今回は、J-PARCリニアックのビームスクレーパの現状、及び、ビームスクレーパの照射試験に用いる3MeVリニアックについて報告する。
mの突起物が無数にあった。ビームスクレーパの耐電力を調べるため、3MeVリニアックを新たに構築した。2016年末にスクレーパ照射試験を実施する予定である。今回は、J-PARCリニアックのビームスクレーパの現状、及び、ビームスクレーパの照射試験に用いる3MeVリニアックについて報告する。
石山 達也; 伊藤 雄一; 菊澤 信宏; 鈴木 隆洋; 大井 元貴; 明午 伸一郎; 酒井 健二; 加藤 裕子
Proceedings of 9th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan (インターネット), p.714 - 716, 2013/08
J-PARCでは、MLFとMRの両施設へのビーム打ち分け時に、MLFにてMPSが発報すると全ビームが停止となり、正常運転状態にあるMRへのビーム供給も停止してしまう。特にミュオンターゲット移動時にはMPSが必ず発報する仕様となっているため、ビーム行先をMRのみに切り替えてターゲットを移動する運用を行っていた。このビーム行先切り替えの際にも全ビーム停止となる。これらによるMR運転稼働率の低下が問題となっていた。そこで、現状のMLFのMPS信号をMLFインヒビットとして扱い、MLFインヒビット発報時には、MLF行きのビームのみを停止し、MR運転稼働率の向上を図ることとした。勿論、MLFインヒビットを実現するにあたり、安全性を保つことが必須である。今回新たに、MLFインヒビット発報中にMLFにてビーム検出がされた際に、通常のMPSを発報し全ビーム停止を行うロジックを組み込むことで、稼働率向上、安全性確保を両立したMLFインヒビットシステムの構築を行った。
勅使河原 誠; 木下 秀孝; 涌井 隆; 明午 伸一郎; 関 正和; 原田 正英; 伊藤 学; 鈴木 徹; 池崎 清美; 前川 藤夫; et al.
JAEA-Technology 2012-024, 303 Pages, 2012/07
J-PARC構成施設のひとつ核破砕中性子源である物質・生命科学実験施設(MLF)では、中性子を発生するため3GeVまで加速された陽子ビームが、水銀ターゲットに入射する。高エネルギーの陽子や中性子に晒された機器(ターゲット容器,モデレータ,反射体及び陽子ビーム窓)は、照射損傷を受けるため、定期的な交換保守を必要とする。使用済み機器は高度に放射化され、遠隔による交換保守が必要となる。使用済みの機器の交換保守が行える保守シナリオを構築し、必要な設備をホットセル内及びMLF内に導入した。保守シナリオの整合性を確認するため実機を用いて予備試験を行った。本報告書では、使用済み機器(モデレータ・反射体,陽子ビーム窓を対象)について、予備試験を通して得られた知見をもとに、使用済み機器の取り扱いに反映することを目的とし、交換保守に関する問題点と解決策等を報告する。
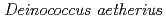 sp. nov., isolated from the stratosphere
sp. nov., isolated from the stratosphereYang, Y.*; 伊藤 隆*; 横堀 伸一*; 島田 治男*; 板橋 志保*; 佐藤 勝也; 大庭 寛史*; 鳴海 一成; 山岸 明彦*
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 60, p.776 - 779, 2010/04
被引用回数:27 パーセンタイル:50.16(Microbiology)A pink pigmented, non-motile, coccoid bacterial strain, ST0316, was isolated from dust samples collected from the stratosphere in Japan. Phylogenetic analysis based on 16S rRNA gene sequences showed that it belonged to the genus  . DNA G+C content, desiccation tolerance, and resistance to
. DNA G+C content, desiccation tolerance, and resistance to  -rays and UV radiation supported the affiliation of strain ST0316 to the genus
-rays and UV radiation supported the affiliation of strain ST0316 to the genus  . Strain ST0316 diverged from recognized species of the genus
. Strain ST0316 diverged from recognized species of the genus  , showing less than 93% similarity values to its closest relatives
, showing less than 93% similarity values to its closest relatives 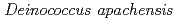 ,
,  ,
, 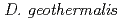 and
and  . We propose a new species of the genus
. We propose a new species of the genus  ,
, 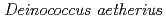 sp. nov.
sp. nov.
原田 正英; 明午 伸一郎; 伊藤 学; 壇辻 永治; 高際 勝徳; 高田 弘; 前川 藤夫; 二川 正敏; 中村 充孝; 三宅 康博*; et al.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 600(1), p.87 - 90, 2009/02
被引用回数:3 パーセンタイル:27.53(Instruments & Instrumentation)J-PARCのMLFでは、建屋(13万トン)や遮蔽体(8万トン)が非常に重いため、MLF建屋が大きく沈下することが予測される。長さ300mある3GeVシンクロトロンから中性子源までの陽子ビームライン(3NBT)でも、同様に沈下することが予測される。MLFの中に建設中の中性子ビームラインや3NBTでは、精度1mm以下の精密アライメントが要求される。そこで、建設中でも中性子ビームラインで高精度アライメントできるように、また、陽子ビームラインでのビーム損失を小さくするために、MLF建屋と3NBTの沈下を定期的に測量することを計画した。そこで、水準マーカーを多数設置し、2004年6月から沈下測量を始めた。MLF建屋が完成した2005年12月には、沈下量は、40mmであった。これまでの沈下量と荷重との関係から、将来設置される全中性子ビームライン遮蔽体の重量が加わった場合、MLFの沈下は、68mmになると予測した。また、MLF建屋の沈下が生じてもミュオンターゲットと中性子ターゲットが同じ高さになるように、ミュオンターゲットを5mm高く設置した。2007年末では、この実測値は、この予測値に近づいている。
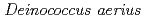 sp. nov., isolated from the high atmosphere
sp. nov., isolated from the high atmosphereYang, Y.*; 伊藤 隆*; 横堀 伸一*; 板橋 志保*; 島田 治男*; 佐藤 勝也; 大庭 寛史; 鳴海 一成; 山岸 明彦*
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 59, p.1862 - 1866, 2009/00
被引用回数:32 パーセンタイル:54.86(Microbiology)日本の高度大気圏で収集した塵から、橙色の色素を持ち運動性のない球菌TR0125株が分離された。16S rRNA遺伝子をもとにした系統解析によってこの菌はデイノコッカス属細菌であることが示された。強い乾燥耐性,UV耐性, 線耐性及び高いGC含量は、この菌株がデイノコッカス属細菌であることを支持している。TR0125株は、デイノコッカス・アパチェンシスの標準菌株の16S rRNA遺伝子配列と最も高い類似性(95.7%)をもち、系統解析の結果は、TR0125株が、デイノコッカス・ジオサーマリス以上に、デイノコッカス・アパチェンシスと進化的に離れていることを示しており、このことは、TR0125株がこれら2種のデイノコッカス属細菌に属するものではないことを表している。他にも、TR0125株と上記2種のデイノコッカス属細菌の標準菌株との間には、幾つかの表現型に違いがあった。よって、われわれは今回分離した菌株に適合するものとして、新種デイノコッカス・アエリウスという名前を提案する。
線耐性及び高いGC含量は、この菌株がデイノコッカス属細菌であることを支持している。TR0125株は、デイノコッカス・アパチェンシスの標準菌株の16S rRNA遺伝子配列と最も高い類似性(95.7%)をもち、系統解析の結果は、TR0125株が、デイノコッカス・ジオサーマリス以上に、デイノコッカス・アパチェンシスと進化的に離れていることを示しており、このことは、TR0125株がこれら2種のデイノコッカス属細菌に属するものではないことを表している。他にも、TR0125株と上記2種のデイノコッカス属細菌の標準菌株との間には、幾つかの表現型に違いがあった。よって、われわれは今回分離した菌株に適合するものとして、新種デイノコッカス・アエリウスという名前を提案する。
山内 俊彦; 小林 清二*; 伊藤 伸一*; 山崎 和彦; 亀井 康孝*; 管野 善則*
環境科学会誌, 19(6), p.507 - 515, 2006/11
Gaussian03を用いた密度汎関数法(B3LYP)計算を行い、ダイオキシン類の特性及び脱塩素化について明らかにした。まず、2個のベンゼン環の面構造は、Co-PCBでは2面が結合軸を中心に37.8度でねじれ、それ以外のPCBでは90度でねじれている。一方、ダイオキシンTCDD及びTCDFで構造最適化すると、2つのベンゼン環は同一平面構造である。また、ダイオキシンの赤外吸収光によるC-Clのストレッチ振動数778cm 等を決定した。次に、C-Clの結合性軌道エネルギー曲線から求めた結合エネルギーは4.1
等を決定した。次に、C-Clの結合性軌道エネルギー曲線から求めた結合エネルギーは4.1 5.5eVである。また、塩素原子エネルギーとダイオキシンラジカルエネルギーの和とダイオキシンエネルギーとの差から求めた結合解離エネルギーは3.8
5.5eVである。また、塩素原子エネルギーとダイオキシンラジカルエネルギーの和とダイオキシンエネルギーとの差から求めた結合解離エネルギーは3.8 3.9eVである。それゆえ零点エネルギーは0.38
3.9eVである。それゆえ零点エネルギーは0.38 1.65eVである。また、結合解離エネルギーは、塩素原子の個数に反比例している。最後に、ほかの脱塩素化のモデルとして水素原子の塩素への接近反応を試行したところ、水素原子による塩素原子引き抜きによる脱塩素化反応が見られた。脱塩素化(引き抜き反応及び光解離)の反応時間は、22
1.65eVである。また、結合解離エネルギーは、塩素原子の個数に反比例している。最後に、ほかの脱塩素化のモデルとして水素原子の塩素への接近反応を試行したところ、水素原子による塩素原子引き抜きによる脱塩素化反応が見られた。脱塩素化(引き抜き反応及び光解離)の反応時間は、22 40fsである。
40fsである。
戸井田 克*; 笹倉 剛*; 渥美 博行*; 須山 泰宏*; 小林 一三*; 川端 淳一*; 伊藤 圭二郎*; 森川 誠司*; 立川 伸一郎*
JNC TJ8400 2003-088, 254 Pages, 2004/02
わが国の地質環境条件に適応し得るこれら閉鎖システムの確立に資するため,室内試験及び原位置試験を通じてこれらの性能に関連するデータの取得,および,これらのデータを活用し評価手法を確立することが必要である。サイクル機構とカナダAECLとの共同研究としてこれまで実施してきた,カナダAECLにおけるトンネルシーリング性能試験が最終段階に至り,シーリング性能に関する基礎データが取得された。本年度は,これまでに実施した試験の総合的なデータ整理・解釈,トレーサ試験結果に対する数値解析的検討・評価を実施した。また,シーリングシステム性能評価上重要となるプラグの解体サンプリングに関する具体的計画案について検討を実施した。
 レーザー照射によるPCBの分解試験
レーザー照射によるPCBの分解試験山内 俊彦; 亀井 康孝*; 伊藤 伸一*; 古川 行夫*; 峰原 英介
環境科学会誌, 14(1), p.73 - 76, 2001/01
FELレーザーを照射する前実験として、同じ発振波長域(赤外)にあるCO レーザーをPCBに照射し、分解試験を行った。ここでは、約100種類の異性体を含むPCB試料にレーザーを照射した。レーザー出力5W及びパルス幅80
レーザーをPCBに照射し、分解試験を行った。ここでは、約100種類の異性体を含むPCB試料にレーザーを照射した。レーザー出力5W及びパルス幅80 sのレーザーを照射したところ分解し、質量分析型ガスクロマトグラフィ(GC/MS)の測定から、照射によるPCBの分解効率は80%以上であった。
sのレーザーを照射したところ分解し、質量分析型ガスクロマトグラフィ(GC/MS)の測定から、照射によるPCBの分解効率は80%以上であった。
山内 俊彦; 伊藤 伸一*; 峰原 英介
Technical Digest on 4th Pacific Rim Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO/Pacific Rim 2001), p.I_148 - I_149, 2001/00
赤外レーザー照射によるダイオキシン類の分解には、熱分解と多光子解離がある。この場合特に、分解するには高吸収率を持つレーザー波長の選択が重要である。さて、熱分解は低いレーザーパワーでも起き、その赤外吸収熱分解(無害化)のモデルとして、直接のレーザー吸収による熱分解に加えて、ダイオキシンの脱塩素化における水蒸気アシストの重要性を議論している。
山内 俊彦; 峰原 英介; 菊澤 信宏; 早川 岳人; 沢村 勝; 永井 良治; 西森 信行; 羽島 良一; 静間 俊行; 亀井 康孝*; et al.
環境科学会誌, 13(3), p.383 - 390, 2000/09
8塩化ダイオキシンであるOCDD及びOCDFの混合20ngにCO レーザー及び自由電子レーザーを照射し、ダイオキシンの分解実験を行った。入射波長22
レーザー及び自由電子レーザーを照射し、ダイオキシンの分解実験を行った。入射波長22 mと25
mと25 mでは照射による変化は見られなかったが、CO
mでは照射による変化は見られなかったが、CO レーザーの照射では危険なダイオキシンはなくなり、分解に成功した。8塩化ダイオキシン試料は、4-7塩化ダイオキシン類似外に分解したことがわかった。
レーザーの照射では危険なダイオキシンはなくなり、分解に成功した。8塩化ダイオキシン試料は、4-7塩化ダイオキシン類似外に分解したことがわかった。
横川 三津夫; 幅田 伸一*; 河合 伸一*; 伊藤 寛行*; 谷 啓二; 三好 甫*
Lecture Notes in Computer Science, 1615, p.269 - 280, 1999/00
地球シミュレータ研究開発が1997年に開始された。現在までに基本設計が終了している。基本設計の結果、地球シミュレータは、640台の計算ノードをクロスバスイッチで結合した分散メモリ型並列計算機である。各計算ノードは8台のベクトルプロセッサが共有メモリと結合されている。全体のピーク性能は40テラフロップス、総メモリ容量は10TBである。本稿では、地球シミュレータの概念、基本設計の結果について述べる。
瀬古 典明; 笠井 昇; 植木 悠二; 佐伯 誠一; 保科 宏行; 岩撫 暁生; 鈴木 伸一; 矢板 毅; 松橋 信平; 伊藤 久義; et al.
no journal, ,
飛散した放射性物質のうち、特に水中に溶けているセシウムに対して親和性の高い高分子除染材料の開発を試みた。セシウム用捕集材として、 線や電子線を用いた放射線グラフト重合法を適合して、リンモリブデン酸型の捕集材を合成し、得られた捕集材の性能は、1mg/Lの安定セシウム溶液を用いたバッチ吸着試験及びカラム吸着試験により評価を行った。バッチ吸着試験では、50mlの溶液に、50mg(1cm角)のセシウム捕集材を入れ、24時間攪拌した場合、ほぼ100%のセシウム捕集する性能を確認した。また、カラム吸着試験では、内径7mmのカラムに47mgのセシウム捕集材を充填することにより、捕集材体積の3,000倍量の安定セシウム溶液0.57Lからセシウムを除去できることが確認できた。福島県飯舘村内の溜池におけるフィールド試験では、可溶性の放射性セシウムが10Bq/L程度溶存している溜め水100Lを連続的に検出限界以下まで除去することに成功した。
線や電子線を用いた放射線グラフト重合法を適合して、リンモリブデン酸型の捕集材を合成し、得られた捕集材の性能は、1mg/Lの安定セシウム溶液を用いたバッチ吸着試験及びカラム吸着試験により評価を行った。バッチ吸着試験では、50mlの溶液に、50mg(1cm角)のセシウム捕集材を入れ、24時間攪拌した場合、ほぼ100%のセシウム捕集する性能を確認した。また、カラム吸着試験では、内径7mmのカラムに47mgのセシウム捕集材を充填することにより、捕集材体積の3,000倍量の安定セシウム溶液0.57Lからセシウムを除去できることが確認できた。福島県飯舘村内の溜池におけるフィールド試験では、可溶性の放射性セシウムが10Bq/L程度溶存している溜め水100Lを連続的に検出限界以下まで除去することに成功した。
佐々木 祐二; 鈴木 伸一; 小林 徹; 伊藤 圭祐*; 高橋 優也*; 金子 昌章*; 浅野 和仁*
no journal, ,
ImPACTプロジェクトでは、高レベル廃液から長半減期核種の分離回収後、核反応を用いる核変換処理を施し、より安全かつ効率的な処分を検討している。模擬廃液中の高濃度ZrをHDEHP又はTODGAを用いて溶媒抽出法で効率的に回収するため、ドデカンに代わる希釈剤の特性について調査した。ここではそれぞれの溶媒系にn-ドデカンを加えて、TODGAを溶解した抽出溶媒を用いて、 線照射を行い、耐放射線性を調べた。
線照射を行い、耐放射線性を調べた。 線照射した5種の抽出溶媒を用いてNd分配比を測定した結果、分配比は照射量が増えるに従い減少することを確認した。
線照射した5種の抽出溶媒を用いてNd分配比を測定した結果、分配比は照射量が増えるに従い減少することを確認した。
伊藤 光生*; 佐野 吉彦*; 桑原 不二朗*; 上澤 伸一郎; 吉田 啓之
no journal, ,
福島第一原子力発電所の格納容器内の燃料デブリの熱挙動を推定するため、空冷時における燃料デブリ熱挙動の解析手法の開発を進めている。燃料デブリが多孔質体と想定されることから、本研究では、多孔質体モデルを用いて、閉鎖容器内の一部分に多孔質体が存在する系の自然対流場を模擬する数値シミュレーションを実施した。本シミュレーションの妥当性については、原子力機構にて別途実施している実験との比較を行うことにより検証した。
明午 伸一郎; 大井 元貴; 甲斐 哲也; 池崎 清美; 原口 哲也; 圷 敦; 藤森 寛*; 坂元 眞一; 伊藤 学; 二川 正敏
no journal, ,
J-PARCの物質・生命科学実験施設(MLF)では平成22年の11月から約200kWの連続運転を開始した。パルス陽子ビームに起因する水銀ターゲット容器の損傷は陽子ビームのピーク密度の4乗に比例するためにターゲット上でのビームのピーク密度を減少させることが重要な鍵となりビームプロファイルの測定が不可欠である。そこでビーム運転終了後にイメージングプレート(IP)をターゲットに密着させ放射化法によるプロファイルの測定法の開発を行った。ピーク密度は、単純に四極電磁石の励磁を変化させターゲットでビームを広げることにより下げることが可能であるが、ターゲット周辺の構造体の発熱が大きくなるために周辺部の発熱を確認しながらプロファイルの調整をすることが重要となる。そこで、実際の運転において周辺部発熱密度を熱電対で測定する方法を開発し、これを用いてビーム運転を行った。この結果、200kW運転時のターゲットにおけるピーク発熱密度は1.7J/cc/pulse程度と十分に抑えることができ、またターゲット周辺部の発熱密度は0.3W/ccであり許容値(1W/cc)を十分に下回っていることが確認できた。以上より平成23年の夏季シャットダウンまで問題なく運転できる目処を得た。