Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
古田 琢哉; 橋本 慎太郎; 小川 達彦; 谷村 嘉彦
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 1086, p.171320_1 - 171320_8, 2026/06
物質に対する中性子照射から荷電粒子が放出される反応において、放出粒子と特定の励起状態にある残留核を同時に扱う核データライブラリを組み込むための新機能を、モンテカルロシミュレーションコードである 粒子・重イオン輸送計算コードPHITSに実装した。本機能により、残留核の生成および脱励起ガンマ線の放出を考慮しつつ、各事象における全エネルギーおよび運動量保存を満たした上で、核データライブラリに基づく放出粒子のエネルギースペクトルおよび角度分布の高精度な予測が可能となる。この機能を用いることで、検出器応答や材料中の放射線損傷の高精度シミュレーションが実施できる。
高柳 智弘; 植野 智晶*; 堀野 光喜*; 杉田 萌; 不破 康裕; 篠崎 信一
IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 36(3), p.4900905_1 - 4900905_5, 2026/05
Compared to DC magnets with constant current, pulsed magnets with instantaneous current flow are superior in terms of energy conservation because the time required to generate Joule heat due to the electrical resistance of the coil is limited. However, the magnetic field distribution that affects beam orbit control cannot be known accurately until the pulse power supply is excited, because the current path through the coil and the load resistance changes with time due to the current skin effect, respectively. For this reason, we have introduced model-based development (MBD), which integrates electromagnets and power supplies, whereas previous simulation analysis was performed separately for electromagnets and power supplies. For the simulation, we combined OPERA-3D transient analysis, which has a proven track record in the development of pulsed magnets for the J-PARC accelerator, and MATLAB/Simulink for circuit simulation. The introduction of MBD is expected to reduce the number of actual prototypes and development costs and shorten the development period because highly accurate results can be obtained in a short period of time. In addition, simulation of trouble cases that cannot be covered by verification of actual machines alone is possible, which is expected to improve safety. In this presentation, we will report the evaluation results compared to the actual machine.
茂木 孝介; 塩津 弘之; 松本 俊慶; 日引 俊詞*; 柴本 泰照
International Journal of Heat and Mass Transfer, 258, p.128275_1 - 128275_15, 2026/05
We established a methodology to quantify chemical kinetic uncertainties, specifically the uncertainty in reaction rate constants, in Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) simulations of turbulent premixed combustion. The methodology consists of three main steps. First, an uncertainty database for the hydrogen combustion reaction was constructed. Second, these uncertainties were propagated to the laminar flame speed, which served as the input data for the subsequent RANS simulation, through a freely propagating flat flame simulation. Third, the uncertainty in the laminar flame speed was propagated to quantities of interest (QoIs) through the RANS simulation. We employed the non-intrusive polynomial chaos method to reduce the number of demanding RANS simulation runs. The established methodology was applied to the flame acceleration benchmark experiments in the ENACCEF facility, revealing that the analysis successfully quantified the uncertainty within an acceptable computational cost. The uncertainty analysis showed that the uncertainty in the propagating flame was closely related to the physical mechanisms involved in the acceleration process. Finally, we discussed the factors influencing the results and examined the validity of the proposed uncertainty analysis.
Mohamad, A. B.; Chen, J.*; 井岡 郁夫*; 鈴木 恵理子; 近藤 啓悦; 阿部 陽介; 山下 真一郎; 大久保 成彰; 根本 義之; 岡田 裕史*; et al.
Journal of Nuclear Materials, 625, p.156513_1 - 156513_9, 2026/04
Ion irradiation was carried out on Cr coating Zry cladding to investigate their microstructure evolution and mechanical properties. The sample was irradiated at reactor noral operation conditions. Microstructural observation and mechanical testing of non-irradiated samples and irradiated samples were performed to understand irradiation damage to the Cr-coated Zry cladding. Results of High Resolution Transmission Electron Microscopy and chemical analysis revealed Fe enrichment at the Cr coating and Zr substrate interface of irradiated samples due to irradiation enhanced diffusion or irradiation induced mixing. Irradiation led to the formation of Fe enrichment at the Cr Zr interface approximately 15nm. Moreover, hardening of the Cr coating and Zr substrate regions was observed in the irradiated sample.
山田 逸平; 小島 邦洸; 地村 幹
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 1084, p.171261_1 - 171261_12, 2026/04
大強度粒子加速器の安定運転には、非破壊型のビーム形状(プロファイル)モニタが不可欠であり、ガスを導入してビームとの相互作用で形状を測るモニタ開発を進めている。ガス導入型は、高い二次粒子収量により高速かつ高精度なプロファイル計測を可能にする一方、ビームと導入したガスの相互作用がビーム品質に影響を与える可能性があるため、その非破壊性の定量的な評価が必須である。本研究では、3MeV負水素イオンビームを用いて、導入ガス流量に対するビーム電流値及び位相空間分布の変化を評価した。ビーム電流値については、予想通り導入ガス流量に対して線形に減少し、その減少率は荷電変換断面積と一致した。位相空間分布については、ビームライン圧力が10 Pa未満の範囲では変化が見られず、10
Pa未満の範囲では変化が見られず、10 Pa以上に増加させた場合には、逆に分布の広がりに約5%の減少が見られた。本測定結果を解析的および数値的に検証した結果、ビーム・ガス相互作用により生成された正イオンが水素負イオンビームの電気的斥力を中和し、負電荷同士の反発力を抑制したため、分布の広がりの相対的な減少を起こすことがわかった。以上により、開発したモニタは、使用に際してビームを広げることなく、逆にビーム品質を向上させる事が分かり、加速器の安定運転に貢献可能であると言える。
Pa以上に増加させた場合には、逆に分布の広がりに約5%の減少が見られた。本測定結果を解析的および数値的に検証した結果、ビーム・ガス相互作用により生成された正イオンが水素負イオンビームの電気的斥力を中和し、負電荷同士の反発力を抑制したため、分布の広がりの相対的な減少を起こすことがわかった。以上により、開発したモニタは、使用に際してビームを広げることなく、逆にビーム品質を向上させる事が分かり、加速器の安定運転に貢献可能であると言える。
三上 奈生; 相澤 康介; 栗原 成計; 植木 祥高*
AI Thermal Fluids (Internet), 5, p.100029_1 - 100029_15, 2026/03
Early detection of water/steam leakage is important in the prevention of failure propagation of heat transfer tubes in a steam generator of a sodium-cooled fast reactor. This study proposes an unsupervised learning-based acoustic method to detect gas leakage in liquid and evaluates its noise resistance based on parametric receiver operating characteristic (ROC) analysis. An autoencoder is trained, validated, and tested on time-frequency representations of simulated noise and leak signals for various signal-to-noise ratios (SNRs). To calculate a false positive rate and a true positive rate, the probability density function is assumed to be either as a normal distribution, a power transformed normal distribution, or a power normal distribution. As a result, the power normal distribution that shows the best goodness-of-fit was used as the probability density function to draw an ROC curve. The predictive ability of the autoencoder is evaluated as excellent for  ,
,  ,
,  , and
, and  dB, good for
dB, good for  dB, and poor for
dB, and poor for  dB. The autoencoder can detect leakage at relatively low-noise levels and has the potential to detect leakage at relatively high-noise levels equivalent to actual noise levels. Segmentation of the noise and leak signals can also be achieved from input, reconstructed, and residual images. These results suggest that the proposed method contributes to laying the foundation for detection and accident analysis of water/steam leakage in a steam generator of a sodium-cooled fast reactor.
dB. The autoencoder can detect leakage at relatively low-noise levels and has the potential to detect leakage at relatively high-noise levels equivalent to actual noise levels. Segmentation of the noise and leak signals can also be achieved from input, reconstructed, and residual images. These results suggest that the proposed method contributes to laying the foundation for detection and accident analysis of water/steam leakage in a steam generator of a sodium-cooled fast reactor.
 -ray beam measurements
-ray beam measurementsOmer, M.; 静間 俊行*; 小泉 光生; 平 義隆*; Zen, H.*; 大垣 英明*; 羽島 良一*
Radiation Physics and Chemistry, 240, p.113467_1 - 113467_8, 2026/03
Coaxial high-purity germanium detectors are widely used in applications requiring high-resolution  -ray spectroscopy. However, the internal structure of these detectors, particularly the geometry of the inactive volumes inside the detector core, can significantly influence their performance in beam detection configurations. This study investigates the impact of detector structure on the spectral response to pencil-like
-ray spectroscopy. However, the internal structure of these detectors, particularly the geometry of the inactive volumes inside the detector core, can significantly influence their performance in beam detection configurations. This study investigates the impact of detector structure on the spectral response to pencil-like  -ray beams, based on a comparison of
-ray beams, based on a comparison of  -ray spectra measured with two coaxial high-purity germanium detectors that have similar active volumes but distinct internal geometries. Experimental measurements were conducted at the UVSOR synchrotron facility using collimated laser Compton scattered
-ray spectra measured with two coaxial high-purity germanium detectors that have similar active volumes but distinct internal geometries. Experimental measurements were conducted at the UVSOR synchrotron facility using collimated laser Compton scattered  -ray beams with an energy of
-ray beams with an energy of  MeV. Monte Carlo simulations using the Geant4 toolkit were performed to refine the detector models and replicate experimental results. The results reveal that the front layer thickness and the presence of structural elements such as the cold finger strongly affect the spectral features, particularly the appearance of a coincidence sum peak of the annihilation radiation at 1.022 MeV. Off-axis irradiation significantly improves the detection efficiency and reduces undesired induced interactions within inactive volumes. Additionally, the observed pair production signatures are validated through the available theoretical cross section data, confirming the dominant role of internal structures in shaping the detector response under beam geometry. These findings are essential for optimizing detector configurations in precision
MeV. Monte Carlo simulations using the Geant4 toolkit were performed to refine the detector models and replicate experimental results. The results reveal that the front layer thickness and the presence of structural elements such as the cold finger strongly affect the spectral features, particularly the appearance of a coincidence sum peak of the annihilation radiation at 1.022 MeV. Off-axis irradiation significantly improves the detection efficiency and reduces undesired induced interactions within inactive volumes. Additionally, the observed pair production signatures are validated through the available theoretical cross section data, confirming the dominant role of internal structures in shaping the detector response under beam geometry. These findings are essential for optimizing detector configurations in precision  -ray beam experiments. This work is a contribution of the Japan Atomic Energy Agency (JAEA) to the International Atomic Energy Agency (IAEA) under the agreement of the coordinated research program (CRP), J02015 (Facilitation of Safe and Secure Trade Using Nuclear Detection Technology - Detection of RN and Other Contraband). A part of this work was conducted at the BL1U of UVSOR Synchrotron Facility, Institute for Molecular Science (IMS program 23IMS6602).
-ray beam experiments. This work is a contribution of the Japan Atomic Energy Agency (JAEA) to the International Atomic Energy Agency (IAEA) under the agreement of the coordinated research program (CRP), J02015 (Facilitation of Safe and Secure Trade Using Nuclear Detection Technology - Detection of RN and Other Contraband). A part of this work was conducted at the BL1U of UVSOR Synchrotron Facility, Institute for Molecular Science (IMS program 23IMS6602).
権 セロム*; 今野 力; 本田 祥梧*; 見城 俊介*; 佐藤 聡*
Fusion Engineering and Design, 223, p.115548_1 - 115548_8, 2026/02
核融合中性子源設計で使われる最新の核データライブラリ(FENDL-3.2b, JENDL-5, ENDF/B-VIII.0とJEFF-3.3)の鉄データの精度検証のため、QST/TIARAで行われた準単色40と65MeV中性子を用いた鉄実験とJAEA/FNSで行われたDT中性子を用いた鉄実験を使い、最新の核データライブラリのベンチマークテストを行なった。テストの結果、以下のことが判明した。(1)65MeV中性子を用いたTIARA実験で、FENDL-3.2bを用いた計算結果は10-60MeVの連続エネルギー領域の中性子束を40%過小評価、(2)FNS実験で、FENDL-3.2bを用いた計算結果は体系内70cmの深さで10MeV以上の中性子束を20%過小評価し、体系内10cmの深さで10keV以下の中性子束を30%過大評価。これらの問題を詳細に調べ、その原因を特定した。
滝藤 聖崇; 奥田 幸彦; 中村 いずみ*; 古屋 治*
配管技術, 68(2), p.1 - 7, 2026/02
自然災害起因の産業事故はNatech (Natural hazard triggered technological accidents)と呼ばれ、近年その重要性が認識されつつある。Natechリスクの評価と適切な対策には構造物の損傷モードの把握と損傷モードと維持機能との対応付けが必要であるが、産業施設で使用される機械設備類では試験データや解析事例が不足しており、そのような性能評価が難しい。そこで、産業施設で多用される配管系の地震時挙動を対象とし、試験による損傷モードの把握と維持機能との対応付けを試みる研究を実施した。まずは代表的な配管構成要素であるエルボ配管の動的載荷時における損傷モードを調査するために、加振レベルおよび自重をパラメタとした複数の動的載荷試験(加振試験)を実施した。本稿では研究の全体概要および配管エルボの加振試験結果について報告する。
近藤 諒一; 山本 章夫*; 遠藤 知弘*
Journal of Nuclear Science and Technology, 63(2), p.142 - 153, 2026/02
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00高詳細度のモンテカルロ計算における課題を解決するため、固有直交分解(POD)を用いた中性子束分布のタリー(PODタリー)が開発された。PODタリーは、次元数と統計誤差の両方を削減することが可能である。本研究では、2次元C5G7ベンチマークにおけるsub-pin levelに分割した中性子束分布へのPODタリーの適用可能性を検証する。また1回のモンテカルロ計算で中性子束の統計誤差を推定するために、PODタリーにcircular block bootstrap法を適用した統計誤差推定手法を提案する。検証計算の結果、従来のcellタリーと比較して、詳細に離散化された分布の次元数は90%以上削減され、全タリー領域における統計誤差は平均で半分以上削減された。提案手法により、世代間相関とPOD次数間の展開係数の相関の両方を考慮することで、中性子束分布の統計誤差を適切に推定できることを確認した。
 underwater radiation monitoring detector
underwater radiation monitoring detectorJi, W.*; Lee, E.*; Ji, Y.-Y.*; 越智 康太郎; 吉村 和也; 舟木 泰智; 眞田 幸尚
Nuclear Engineering and Technology, 58(2), p.103933_1 - 103933_6, 2026/02
汚染予測地点の河川や貯水池の堆積物中の Cs放射能濃度を推定するために、水中放射線in-situ検出器MARK-U1(Monitoring of Ambient Radiation of KAERI - Underwater)の性能を検証することを目的とした。さらに、高純度ゲルマニウム(HPGe)半導体検出器を用いて放射能を測定するため、コアサンプルを採取した。放射能を推定するために、測定されたスペクトルと試料中の
Cs放射能濃度を推定するために、水中放射線in-situ検出器MARK-U1(Monitoring of Ambient Radiation of KAERI - Underwater)の性能を検証することを目的とした。さらに、高純度ゲルマニウム(HPGe)半導体検出器を用いて放射能を測定するため、コアサンプルを採取した。放射能を推定するために、測定されたスペクトルと試料中の Cs放射能を比較して換算係数を導き出した。モンテカルロN粒子(MCNP)シミュレーションを実施し、in-situ測定に有効な線源形状を決定した。シミュレーション結果は、31.62%の偏差で、現場のMARK-U1モニタリング結果とよく相関した。これらの結果は、in-situ検出器の性能を検証するものである。したがって、この装置は、試料採取を必要とせず、in-situモニタリングによって水底堆積物中の
Cs放射能を比較して換算係数を導き出した。モンテカルロN粒子(MCNP)シミュレーションを実施し、in-situ測定に有効な線源形状を決定した。シミュレーション結果は、31.62%の偏差で、現場のMARK-U1モニタリング結果とよく相関した。これらの結果は、in-situ検出器の性能を検証するものである。したがって、この装置は、試料採取を必要とせず、in-situモニタリングによって水底堆積物中の Cs放射能濃度を推定するために使用することができる。
Cs放射能濃度を推定するために使用することができる。
藤原 理賀; 萩原 雅人; 石角 元志*; Sari, D. P.*; 渡邊 功雄*; 髭本 亘; 田端 千紘; 金子 耕士
Physical Review B, 113(6), p.064409_1 - 064409_8, 2026/02
We report a field-induced quantum first-order transition in the antiferromagnet KCoPO H
H O. Using highly oriented microcrystals with
O. Using highly oriented microcrystals with  , polarized neutron diffraction directly reveals coexistence of an incommensurate cycloid and a commensurate collinear state, together with a discontinuous jump of the ordering wave vector from incommensurate to commensurate. Magnetization and specific heat show a step and a collapse of the
, polarized neutron diffraction directly reveals coexistence of an incommensurate cycloid and a commensurate collinear state, together with a discontinuous jump of the ordering wave vector from incommensurate to commensurate. Magnetization and specific heat show a step and a collapse of the  anomaly near
anomaly near  ~T with no measurable hysteresis, while LF-
~T with no measurable hysteresis, while LF- SR detects two-component relaxation and slow fluctuations around
SR detects two-component relaxation and slow fluctuations around  . The
. The  -
- phase diagram exhibits a narrow coexistence region. Symmetry of space group
phase diagram exhibits a narrow coexistence region. Symmetry of space group  constrains the DM vector to the
constrains the DM vector to the  plane and, together with XY anisotropy, nearly degenerates the incommensurate and commensurate states, enabling a first-order switch in field. KCoPO
plane and, together with XY anisotropy, nearly degenerates the incommensurate and commensurate states, enabling a first-order switch in field. KCoPO H
H O thus serves as a platform for quantum first-order transitions in frustrated magnets.
O thus serves as a platform for quantum first-order transitions in frustrated magnets.
徳満 駿*; 松宮 正彦*; 佐々木 祐二
Separation and Purification Technology, 382(Part 2), p.135631_1 - 135631_9, 2026/02
Solvent extraction (SX) of Rh(III) and direct electrodeposition (ED) of Rh metal were carried out in five cycles using phosphonium-based ionic liquids (ILs). The comparatively high extraction performance (70.1%-86.2%) of Rh(III) was stably retained in each SX process. In the subsequent ED process, the electrodeposits were recovered on the cathode and the reasonable current efficiencies (74.9%-85.6%) were achieved in the IL system. The X-ray photoelectron spectroscopy revealed that the electrodeposits obtained during ED process were found to be in the metallic state.
永井 崇之; 青山 雄亮; 岡本 芳浩; 長谷川 毅彦*; 佐藤 誠一*; 菊池 哲也*; 畠山 清司*
JAEA-Research 2025-012, 43 Pages, 2026/01
高レベル放射性廃液のガラス固化プロセス研究において、模擬廃棄物ガラスに内在した析出物をXRDで検出しているが、析出物の状態(微細、極微量)によってXRDパターンに析出物ピークが観察されない場合がある。本研究は、ガラス中の廃棄物成分の溶存状態をより詳細に把握するため、溶融条件や凝固条件を変えて作製した模擬廃棄物ガラスを対象に、ラマン分光測定等によりガラス構造を評価した。XRDパターンで析出物ピークが観察されなかった模擬廃棄物ガラスをラマン分光測定した結果、ガラス相内の微細な異物を検出できることが分かった。また、ガラス作製において、溶融状態のガラスを撹拌することや、溶融状態からの冷却速度を速くすることによって、ガラス相内の異物生成を抑制する可能性が高いことを確認した。ラマン分光計を用いて模擬廃棄物ガラスのSi-O架橋組織を評価した結果、異物が内在する部位と異物が存在しない部位でSi-O架橋組織に違いはなかった。このため、ラマン分光測定で検出された異物はCeO やCaMoO
やCaMoO でなく、spinel等の化合物組成であると考えられる。高エネルギー加速器研究機構の放射光実験施設において、模擬廃棄物ガラス内部の状況をX線透過画像観察した結果、溶融状態のガラスを撹拌する操作は、ガラス相内に内在する気泡を低減する効果が認められた。また、ガラスに含まれるMo, Ce, SiのXAFS測定を行った結果、溶融状態での撹拌操作はガラスに含まれるMo, Ce, Siの化学状態に影響しないことを確認した。
でなく、spinel等の化合物組成であると考えられる。高エネルギー加速器研究機構の放射光実験施設において、模擬廃棄物ガラス内部の状況をX線透過画像観察した結果、溶融状態のガラスを撹拌する操作は、ガラス相内に内在する気泡を低減する効果が認められた。また、ガラスに含まれるMo, Ce, SiのXAFS測定を行った結果、溶融状態での撹拌操作はガラスに含まれるMo, Ce, Siの化学状態に影響しないことを確認した。
今野 力
JAEA-Data/Code 2025-016, 35 Pages, 2026/01
遮蔽計算等でのニーズに応えるため、FRENDYコードをベースに一部NJOYコードを使って作成した評価済み核データJENDL-5のMATXS形式ライブラリMATXS-J50を2025年8月に公開した。MATXS-J50の群構造は、中性子200群+ガンマ線42群と中性子48群+ガンマ線20群の2つである。本報告書ではMATXS-J50の作成方法、及びTRANSXコードを用いたMATXS-J50の使用方法について詳述する。MATXS-J50検証のためのテスト計算も行い、MATXS-J50に問題がないことを確認した。
國分 陽子; 西尾 和久*; 竹内 竜史; 池田 幸喜
JAEA-Data/Code 2025-014, 109 Pages, 2026/01
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構東濃地科学センターでは、瑞浪超深地層研究所の坑道の埋め戻しに伴う地下深部の地下水環境の回復状況を確認するため、環境モニタリング調査として瑞浪超深地層研究所用地および研究所用地周辺のボーリング孔等において地下水の水圧観測および水質観測を実施している。本報告書は、2024 年度に実施した地下水の水圧観測データおよび水質観測データを取りまとめたものである。
國分 陽子; 竹内 竜史; 西尾 和久*; 池田 幸喜
JAEA-Data/Code 2025-013, 66 Pages, 2026/01
日本原子力研究開発機構東濃地科学センターは、同センターが進める瑞浪超深地層研究所の坑道埋め戻し等事業において、瑞浪超深地層研究所の坑道の埋め戻しに伴い瑞浪超深地層研究所用地周辺の環境への影響の有無を確認することを目的とした環境モニタリング調査を実施している。本報告書は、2024年度の環境モニタリング調査のうち瑞浪超深地層研究所用地周辺の環境影響調査(研究所用地周辺の井戸における地下水位調査、研究所用地周辺河川流量測定、研究所用地放流先河川水の水質分析、研究所用地周辺騒音・振動調査、研究所用地周辺土壌調査)に関する記録を取りまとめたものである。
Rahim, A.*; 佐藤 達彦; 福田 寛*; Beni, M. S.*; 渡部 浩司*
Biomedical Physics & Engineering Express (Internet), 12(1), p.015056_1 - 015056_13, 2026/01
Proton boron fusion therapy (PBFT) aims to enhance proton therapy through  particles generated by the
particles generated by the 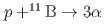 reaction. While early reports suggested large dose gains near the Bragg peak, later studies questioned its feasibility due to the low cross section and the need for unrealistically high boron concentrations. In this study, Monte Carlo microdosimetric analysis showed that protons dominate total dose delivery, with
reaction. While early reports suggested large dose gains near the Bragg peak, later studies questioned its feasibility due to the low cross section and the need for unrealistically high boron concentrations. In this study, Monte Carlo microdosimetric analysis showed that protons dominate total dose delivery, with  particles contributing only locally to high-LET deposition. The resulting RBE enhancement factors were negligible at 100-1000 ppm boron and modest (
particles contributing only locally to high-LET deposition. The resulting RBE enhancement factors were negligible at 100-1000 ppm boron and modest ( ) only at 10,000 ppm. These findings indicate that, under clinically realistic conditions, the therapeutic benefit of PBFT is minimal.
) only at 10,000 ppm. These findings indicate that, under clinically realistic conditions, the therapeutic benefit of PBFT is minimal.
國分 陽子; 大澤 崇人; 大澤 辰彦; 阿部 一英
第25回AMSシンポジウム報告集(インターネット), 2 Pages, 2026/01
有機元素分析装置に試料を入れるためには、スズなどの金属箔で試料を包む必要があり、これまでは作業者がピンセットを用いて手作業で折りたたみ、直径数mmの球状に成形していた。この作業は時間を有し、試料調製の律速になっている。今回、この作業を自動化する装置を開発したことを報告する。
金田 美優*; 榎本 貴允*; 古林 宏之*; 深田 幸正; 狩野 旬*; 青柳 佑海人*; 藤井 達生*; 池田 直*
Japanese Journal of Applied Physics, 65(2), p.028001_1 - 028001_4, 2026/01
反射率の低い材料は光学素子などにおいて重要な役割を果たす。この研究では、安価な原料と簡易的な合成装置を用いることで、極めて低い反射率を示すホウ素をドープしたカーボンナノウオールの合成に成功した。ナノ構造と表面状態の解析から、カーボンナノウオールにホウ素をドープすることで壁の密度が高くなり、グラファイト部分の割合が低くなることが分かった。我々はナノ構造に起因する迷光効果による光吸収の機構とキャリアドープの効果による電気伝導性の向上について議論する。ホウ素をドープしたカーボンナノウオールは極めて黒い材料への実装に有益である。