Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
宮川 晃尚*; 林 直輝*; 崩 愛昌*; 高橋 拓海*; 岩本 響*; 新井 剛*; 長友 重紀*; 宮崎 康典; 長谷川 健太; 佐野 雄一; et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 96(7), p.671 - 676, 2023/07
被引用回数:2 パーセンタイル:71.3(Chemistry, Multidisciplinary)HONTAおよびTOD2EHNTAとして知られるニトリロトリアセトアミド(NTA)抽出剤を含む単一ポリマー被覆シリカ粒子におけるEu(III)の分配機構を検討した。本研究は、「単一の抽出剤を含浸したポリマー被覆シリカ粒子」の機能性を評価・向上させるための貴重なアプローチを提供するものである。
長谷川 健太; 後藤 一郎*; 宮崎 康典; 安倍 弘; 渡部 創; 渡部 雅之; 佐野 雄一; 竹内 正行
Proceedings of 30th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE30) (Internet), 5 Pages, 2023/05
JAEA has been working on development of extraction chromatography technology for recovery of trivalent minor actinides (MA(III): Am, Cm) from high-level radioactive waste generated in reprocessing of spent fuel. The technology utilizes porous silica particles with about 50 micrometre diameter for support of adsorbents. The particles are coated by styrene-divinylbenzene copolymer, and an extractant for MA recovery is impregnated into the polymer. Pressure drop of the packed column depends on characteristics of the particle (diameter, uniformity and pore size). Large pressure drop of the column is not favorable for safety assessment of the technology although a certain level of the pressure drop is indispensable for excellent separation performance. In this study, spray drying granulation experiments and fundamental characterization of the product particle were carried out to find optimal specs of the particle and conditions of the granulation operation.
佐野 雄一; 坂本 淳志; 宮崎 康典; 渡部 創; 森田 圭介; 江森 達也; 伴 康俊; 新井 剛*; 中谷 清治*; 松浦 治明*; et al.
Proceedings of International Conference on Nuclear Fuel Cycle; Sustainable Energy Beyond the Pandemic (GLOBAL 2022) (Internet), 4 Pages, 2022/07
TBPを利用した溶媒抽出法によるMA(III)+Ln(III)共回収フローシート及び低圧損操作が可能な大粒径多孔質シリカ担体を使用したHONTA含浸吸着材を用いた擬似移動層型クロマトグラフィによるMA(III)/Ln(III)分離フローシートを組み合わせたハイブリッド型のMA(III)回収プロセスを開発した。
宮崎 康典; 佐野 雄一
放射線化学(インターネット), (112), p.27 - 32, 2021/11
使用済燃料再処理で発生する高レベル放射性廃液からマイナーアクチニド(MA: Am, Cm)を分離回収する抽出クロマトグラフィの技術開発を行っている。圧力損失を低減する大粒径吸着担体に対し、MAと希土類元素を相互分離する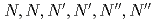 -ヘキサオクチルニトリロトリアセトアミド(HONTA)を含浸した吸着材の安全性を評価した。
-ヘキサオクチルニトリロトリアセトアミド(HONTA)を含浸した吸着材の安全性を評価した。 線照射後の熱的特性や吸着性能の変化、並びに水素ガスの発生量から、MAをランタニド(Ln)から分離可能な線量を1MGyに設定するとともに、分離操作において、現在の想定設備以外で冷却ユニットやオフガスユニット等の予防措置は必要ないことを示した。
線照射後の熱的特性や吸着性能の変化、並びに水素ガスの発生量から、MAをランタニド(Ln)から分離可能な線量を1MGyに設定するとともに、分離操作において、現在の想定設備以外で冷却ユニットやオフガスユニット等の予防措置は必要ないことを示した。
 -P column by neutron resonance absorption imaging
-P column by neutron resonance absorption imaging宮崎 康典; 渡部 創; 中村 雅弘; 柴田 淳広; 野村 和則; 甲斐 哲也; Parker, J. D.*
JPS Conference Proceedings (Internet), 33, p.011073_1 - 011073_7, 2021/03
中性子共鳴吸収イメージングを、抽出クロマトグラフィに使用するマイナーアクチノイド回収用CMPO/SiO -Pカラムで形成したEu吸着バンドの観測に適用した。軽水や重水で調製した湿潤カラムと乾燥吸着材を充填した乾燥カラムを比較し、中性子透過を評価した。中性子透過スペクトルから、乾燥カラムは45%、軽水調製カラムは20%、重水調製カラムは40%の中性子透過を確認した。得られた結果から、CMPO/SiO
-Pカラムで形成したEu吸着バンドの観測に適用した。軽水や重水で調製した湿潤カラムと乾燥吸着材を充填した乾燥カラムを比較し、中性子透過を評価した。中性子透過スペクトルから、乾燥カラムは45%、軽水調製カラムは20%、重水調製カラムは40%の中性子透過を確認した。得られた結果から、CMPO/SiO -Pカラムに形成したEu吸着バンドを観測するには、重水の使用によって、より鮮明になることを明らかにした。今後、カラム操作による吸着バンドのカラム内移行挙動を明らかにする。
-Pカラムに形成したEu吸着バンドを観測するには、重水の使用によって、より鮮明になることを明らかにした。今後、カラム操作による吸着バンドのカラム内移行挙動を明らかにする。
宮崎 康典; 佐野 雄一; 岡村 信生; 渡部 雅之; 江夏 昌志*
QST-M-29; QST Takasaki Annual Report 2019, P. 72, 2021/03
放射性廃棄物の減容化及び有害度低減に、使用済燃料再処理で発生する高レベル放射性廃液から長寿命のマイナーアクチノイドを分離回収する固相分離技術の開発を行っている。特に、大粒径の吸着材をカラム充填することで、分離性能を維持しつつ、分離操作の安全性向上を目指した低圧損抽出クロマトグラフィを進めている。本研究では、HONTA含浸吸着材を0.01M硝酸溶液に浸漬し、 線照射によるHONTAの劣化挙動を調査した。吸収線量0.51MGyの場合では劣化物が2種類であったが、吸収線量の増加によって、e.g. 2.09MGy、劣化物の種類が5種類となった。このうち、2種類は溶媒抽出では見られておらず、抽出クロマトグラフィに特有の劣化物であることが示唆された。今後、硝酸や水が関与する抽出剤の劣化機構を明らかにする。
線照射によるHONTAの劣化挙動を調査した。吸収線量0.51MGyの場合では劣化物が2種類であったが、吸収線量の増加によって、e.g. 2.09MGy、劣化物の種類が5種類となった。このうち、2種類は溶媒抽出では見られておらず、抽出クロマトグラフィに特有の劣化物であることが示唆された。今後、硝酸や水が関与する抽出剤の劣化機構を明らかにする。
宮崎 康典; 足立 純一*; 益田 遼太郎*; 下條 竜夫*; 星野 正光*
Photon Factory Activity Report 2021 (インターネット), 2 Pages, 2021/00
放射性廃棄物の減容化及び有害度低減の観点から、ガラス固化前の再処理高レベル放射性廃液からマイナーアクチノイド(MA; Am, Cm)を分離回収し、高速炉や加速器駆動システムによって、安定核種や短寿命核種に変換する「分離変換」の研究・技術開発を行っている。MA分離技術では、N,N,N',N', N",N"-hexaoctylnitrilotriacetamide(以降「HONTA」という。)に注目したプロセスを検討しているが、放射線分解に係る課題(e.g.放射線分解生成物の除去や使用済抽出剤の再利用等)が多く残されている。本研究では、硝酸とのコンディショニングによる水和錯体が抽出剤の放射線分解を阻害する効果を明らかにするため、有機相に形成する[(HONTA)(HNO )(H
)(H O)n]の光電子分光実験を行い、スペクトルパターンを取得した。また、量子化学計算で構造最適化したHMNTA + HNO
O)n]の光電子分光実験を行い、スペクトルパターンを取得した。また、量子化学計算で構造最適化したHMNTA + HNO の状態密度スペクトルと比較し、分子軌道から、HNO
の状態密度スペクトルと比較し、分子軌道から、HNO 付加による影響を考察した。
付加による影響を考察した。
 -P adsorbent for extraction chromatography
-P adsorbent for extraction chromatography宮崎 康典; 渡部 創; 佐野 雄一; 小藤 博英; 竹内 正行; 石神 龍哉*
no journal, ,
使用済み核燃料からマイナーアクチノイド(MA)を回収する方法として、抽出クロマトグラフィが用いられている。高分子ポリマーでコーティングした多孔SiO 粒子にCMPO等の抽出剤を添加した吸着剤をカラムに充てんし、AmやCmなどの特定元素の群分離及び単離を行う。これまで高レベル放射性廃液からの放射線を模擬したHe
粒子にCMPO等の抽出剤を添加した吸着剤をカラムに充てんし、AmやCmなどの特定元素の群分離及び単離を行う。これまで高レベル放射性廃液からの放射線を模擬したHe イオンや
イオンや 線を照射し、劣化した吸着剤の安全性評価が進められてきた。本研究では、近年開発が進められているMA抽出剤の一つであるTODGAに的を絞り、TODGA/SiO
線を照射し、劣化した吸着剤の安全性評価が進められてきた。本研究では、近年開発が進められているMA抽出剤の一つであるTODGAに的を絞り、TODGA/SiO -P吸着材の分解物の特定を行った。
-P吸着材の分解物の特定を行った。
下端 健吾*; 荒井 貴大*; 伊藤 大雄*; 平沢 泉*; 宮崎 康典; 竹内 正行
no journal, ,
わが国では原子力の利用にあたって、燃料サイクル政策を進めており、使用済核燃料の再処理プロセスが導入されている。このプロセスの導入により、ウラン資源の有効利用や放射性廃棄物の削減が可能となる。現状では硝酸溶液を使用したPUREX法が採用されているが、燃料溶解等の過程で生じる不溶解性残渣が配管内に沈積・付着し、配管閉塞を引き起こす点がプラントの安全運転における課題となっている。不溶解性残渣の主成分であるモリブデン酸ジルコニウム2水和物(ZMH)が付着した際の対応として、高圧水による物理的洗浄や酸・アルカリによる化学的洗浄が考えられるが、これらは汚染水の増加や配管の腐食を引き起こす。このことから、晶析的な見地に基づいたZMH析出・付着抑止が求められる。本研究では、ZMHに同伴した析出が知られているテルル(Te)に対し、Zr-Teの二成分系の析出物を調査した。その結果、Zr-Te系は高温になるほど溶解度が下がる傾向にあり、ZMHと共通した析出挙動が示された。また、析出物のZrとTeの比は1:1であった。構造解析に用いられるXRDスペクトルは析出物の焼成前後で大きく変化し、焼成後はZrTe3O8と一致するスペクトルが得られた。今後は焼成による影響を調べ、Zr-Mo-Teの三成分における析出物について詳しく調べていく予定である。
宮崎 康典; 渡部 創; 佐野 雄一; 小藤 博英; 竹内 正行; 石神 龍哉*; 江夏 昌志*; 佐藤 隆博*
no journal, ,
使用済燃料の再処理工程で発生する高レベル放射性廃棄物には、長寿命核種や発熱性核種であるマイナーアクチノイドが含まれており、これらを取り除くことで地層処分における廃棄物減容化や有害度低減に繋がる。そこで、抽出クロマトグラフィを用いたMAの選択的分離回収を検討している。これまでに、高分子ポリマーで塗布した多孔質SiO 粒子にCMPO等の抽出剤を含浸させた吸着材を作製し、カラム運転中に想定される放射線分解物の特定及び挙動調査を行ってきた。本研究では、
粒子にCMPO等の抽出剤を含浸させた吸着材を作製し、カラム運転中に想定される放射線分解物の特定及び挙動調査を行ってきた。本研究では、 線を模擬したTODGA/SiO
線を模擬したTODGA/SiO -P吸着材の放射線耐性評価と理論計算による結合解離メカニズムの解明を目的に、Heイオンの照射試験を実施した。Heイオン照射に対して、酸の有無による抽出剤の分解生成物に違いが見られた。硝酸を加えてスラリー状態で照射した場合、アミドC-N結合の解離のみが起きたが、乾燥状態ではアミドC-N結合に加えてエーテルC-O結合の解離も見られた。この違いはプロトン付加した分子構造に依存すると考え、量子化学計算を用いて結合解離エネルギー(BDE)を求めた。フリーのDGAのエーテル結合のBDEは、アミド結合よりも小さい。一方、プロトン付加した構造では、エーテル結合はアミド結合よりもBDEが大きくなる。つまり、結合解離が起きにくいと予想された。この結果は実験で得られた結合解離パターンと傾向が一致した。今後、照射線量と吸着材の劣化生成量における相関を調査し、抽出クロマトグラフィに用いる吸着材の再利用性を含めた研究を行う。
-P吸着材の放射線耐性評価と理論計算による結合解離メカニズムの解明を目的に、Heイオンの照射試験を実施した。Heイオン照射に対して、酸の有無による抽出剤の分解生成物に違いが見られた。硝酸を加えてスラリー状態で照射した場合、アミドC-N結合の解離のみが起きたが、乾燥状態ではアミドC-N結合に加えてエーテルC-O結合の解離も見られた。この違いはプロトン付加した分子構造に依存すると考え、量子化学計算を用いて結合解離エネルギー(BDE)を求めた。フリーのDGAのエーテル結合のBDEは、アミド結合よりも小さい。一方、プロトン付加した構造では、エーテル結合はアミド結合よりもBDEが大きくなる。つまり、結合解離が起きにくいと予想された。この結果は実験で得られた結合解離パターンと傾向が一致した。今後、照射線量と吸着材の劣化生成量における相関を調査し、抽出クロマトグラフィに用いる吸着材の再利用性を含めた研究を行う。
 結晶添加によるZMH壁面付着抑制
結晶添加によるZMH壁面付着抑制下端 健吾*; 伊藤 大雄*; 平沢 泉*; 宮崎 康典; 竹内 正行
no journal, ,
わが国では原子力の利用にあたって燃料サイクル政策を進めており、使用済核燃料の再処理によって、ウラン資源の有効活用を目指している。しかし、燃料溶解工程等で生じる不溶解性残渣の機器への付着・沈積が、伝熱効率の低下および配管閉塞の原因になることから、安全上の課題が残されている。中でも、核分裂生成物であるジルコニウム(Zr)とモリブデン(Mo)の反応で生成するモリブデン酸ジルコニウム2水和物(ZMH)は不溶解性残渣の主成分であり、プラントの長期安定運転には、再処理機器や配管等へのZMHの析出・付着を防がなくてはならない。現在、ZMHを除去するには二次廃棄物が生じるため、それらを低減させる方策が求められている。本研究で、ZMHの壁面析出を防ぐには、MoO 結晶の添加が効果的であることを明らかにした。最も抑制効果が見られたのは半水和物であり、特に針状結晶の場合で顕著であった。これは、表面で溶けだしたMoが溶液中のZrと反応してZMHを形成し、溶液中のZrを消費することで、壁面への付着が抑制されていると考えられる。今後は、再処理プロセスを模擬した溶液でMoO
結晶の添加が効果的であることを明らかにした。最も抑制効果が見られたのは半水和物であり、特に針状結晶の場合で顕著であった。これは、表面で溶けだしたMoが溶液中のZrと反応してZMHを形成し、溶液中のZrを消費することで、壁面への付着が抑制されていると考えられる。今後は、再処理プロセスを模擬した溶液でMoO 結晶の効果的な添加方法を検討する。
結晶の効果的な添加方法を検討する。
小藤 博英; 渡部 創; 後藤 一郎; 宮崎 康典; 野村 和則; 竹内 正行
no journal, ,
マイナーアクチニド(MA)等の分離法として、多孔質シリカに抽出剤を含浸させた吸着材を用いた抽出クロマトグラフィ法の開発を進めている。実廃液の処理においてはMoやZrが吸着材に優先的に吸着され、他の元素の吸着容量に影響することから、これらを事前に除去するフローを検討し、適用性を評価した。
 線照射耐性評価
線照射耐性評価宮崎 康典; 佐野 雄一; 小藤 博英; 渡部 創; 江夏 昌志*; 佐藤 隆博*
no journal, ,
経済産業省資源エネルギー庁の受託業務「平成28年度次世代再処理ガラス固化技術基盤研究事業」で量子科学技術研究開発機構高崎量子応用研究所に再委託した研究内容を発表する。本研究では、抽出クロマトグラフィを用いて高レベル放射性廃液からマイナーアクチノイド(MA)を分離回収した後、使用済吸着ガラスをガラス固化するまでの保管を想定した 線耐性評価試験を行った。具体的には、
線耐性評価試験を行った。具体的には、 線照射線量に対するEu漏出率を調査し、ガラス粒子のEu分布をPIXE分析によって明らかにすることで、吸着ガラスの劣化を定量的に評価した。劣化CMPO吸着ガラスは、溶出液のICP分析から約50%のEu漏出率(2MGy)を確認し、ガラス粒子のPIXE分析からもEuの表面密度の減少が確認できた。一方で、劣化HDEHP吸着ガラスは、溶出液に沈殿が起きており、ICP分析による定量評価ができなかった。今後、PIXE分析による定量評価を実施する予定である。まとめると、MA回収後に吸着ガラスで長期保管する場合、CMPOは分解しやすく、漏出率が高くなるため、使用には適していないことが明らかになった。HDEHPの利用に関しては今後の課題である。
線照射線量に対するEu漏出率を調査し、ガラス粒子のEu分布をPIXE分析によって明らかにすることで、吸着ガラスの劣化を定量的に評価した。劣化CMPO吸着ガラスは、溶出液のICP分析から約50%のEu漏出率(2MGy)を確認し、ガラス粒子のPIXE分析からもEuの表面密度の減少が確認できた。一方で、劣化HDEHP吸着ガラスは、溶出液に沈殿が起きており、ICP分析による定量評価ができなかった。今後、PIXE分析による定量評価を実施する予定である。まとめると、MA回収後に吸着ガラスで長期保管する場合、CMPOは分解しやすく、漏出率が高くなるため、使用には適していないことが明らかになった。HDEHPの利用に関しては今後の課題である。
宮崎 康典; 佐野 雄一; 小藤 博英; 渡部 創; 江夏 昌志*; 佐藤 隆博*
no journal, ,
高レベル放射性廃液からマイナーアクチノイド(MA)を分離回収する抽出クロマトグラフィの技術開発で、放射線劣化に関連した安全性評価を実施している。本研究では、MAおよび付随した核分裂生成物から放出される 線(Heイオン線)と
線(Heイオン線)と 線に対するCMPO吸着ガラスのEu保持能力や劣化挙動を調査した。照射線量に対するEu漏出率は、Heイオンと
線に対するCMPO吸着ガラスのEu保持能力や劣化挙動を調査した。照射線量に対するEu漏出率は、Heイオンと 線で異なる挙動を示した。例えば、Heイオンの場合は弾性散乱による吸着ガラス表面の劣化が予想され、
線で異なる挙動を示した。例えば、Heイオンの場合は弾性散乱による吸着ガラス表面の劣化が予想され、 線ではラジカル種の生成速度が重要になると考えられた。また、
線ではラジカル種の生成速度が重要になると考えられた。また、 線照射した吸着ガラスには大気PIXE分析を行い、照射線量に応じたEuの表面密度の減少を確認した。Heイオン照射後のEu密度分布を評価するPIXE-CT分析では、Eu漏出試験と同様に、ガラス粒子表面の密度分布が減少していることから、弾性散乱による劣化を強く示唆した。まとめると、CMPO吸着ガラスは放射線劣化が起きやすく、長期保管には適していない。金属イオンの密度分布を可視化するPIXE分析を用いることで、放射線分解を定性的に説明できるようになった。今後は、定量分析と理論計算の導入によって、CMPOの結合解離経路や分解生成物の発生割合等を明らかにする。
線照射した吸着ガラスには大気PIXE分析を行い、照射線量に応じたEuの表面密度の減少を確認した。Heイオン照射後のEu密度分布を評価するPIXE-CT分析では、Eu漏出試験と同様に、ガラス粒子表面の密度分布が減少していることから、弾性散乱による劣化を強く示唆した。まとめると、CMPO吸着ガラスは放射線劣化が起きやすく、長期保管には適していない。金属イオンの密度分布を可視化するPIXE分析を用いることで、放射線分解を定性的に説明できるようになった。今後は、定量分析と理論計算の導入によって、CMPOの結合解離経路や分解生成物の発生割合等を明らかにする。
竹内 正行; 宮崎 康典; 小藤 博英
no journal, ,
将来の再処理プラントで処理が必要となるMOX燃料では不溶解性残渣の発生量が増大するため、当課題を克服するため、遠心清澄機とフィルタ清澄を組み合わせた高性能清澄システムを提案した。本システムでは、遠心清澄機で大部分の残渣を捕集後、十分な捕集が困難と想定される微小粒径・低密度の残渣は後段のフィルタ清澄でほぼ完全に回収することを目指している。本システム概念の下、孔径0.05及び0.2ミクロンのセラミックフィルタ2種を選定し、後段のフィルタ清澄の基礎的性能を評価した結果、残渣捕集効率はほぼ100%であり、ろ過時の差圧上昇特性や逆洗浄時の差圧回復特性は良好であるなど、技術的に適用可能な見通しを得た。
宮崎 康典; 後藤 一郎*; 渡部 創; 佐野 雄一; 小藤 博英; 竹内 正行
no journal, ,
原子力機構では、放射性廃棄物減容化および環境負荷低減のため、使用済燃料の再処理で発生する高レベル放射性廃液からマイナーアクチノイド(MA)を分離回収する抽出クロマトグラフィの技術開発を行っている。平成29年度には、液柱振動切断法で多孔質シリカ粒子を製造し、原料液のシリカ含有量を調製した粒子の形状や性状を評価した。例えば、シリカ含有量の増加に伴って粒子骨格が安定し、耐久性が向上した。カラムの圧損を低下させることができ、ポンプを必要としないカラム操作や安全性な取扱いへの寄与が期待できる。また、細孔径の拡大を確認し、イオンの粒子内拡散に有利に働くと予想される。今後は、イオン吸着量をより増加させるための製造条件等を検討し、吸着材としての利用適用性を評価する。
阿部 りさこ*; 平沢 泉*; 宮崎 康典; 竹内 正行
no journal, ,
再処理技術開発において、不溶解性残渣の除去が課題となっている。それは、不溶解性残渣の主成分であるモリブデン酸ジルコニウム2水和物(ZMH)が、燃料溶解工程以降の再処理機器に付着または沈積し、安定なプラント運転を阻害するためである。これまでの共同研究で、ZMHの析出が溶解液の液性(硝酸濃度, 液温, MoとZrの濃度比等)や付着材料に依存すること、そして、ZMHの付着を抑制するには3酸化モリブデン(MoO )結晶の添加が有効であることを明らかにしている。本研究では、実系プロセスへの導入手法および適用性の検討を目的に、MoO
)結晶の添加が有効であることを明らかにしている。本研究では、実系プロセスへの導入手法および適用性の検討を目的に、MoO 結晶生成直後の懸濁液を添加し、ZMHの付着抑制効果を評価した。MoO
結晶生成直後の懸濁液を添加し、ZMHの付着抑制効果を評価した。MoO の結晶懸濁液の添加量に応じてZMHの付着抑制効果を示すデータが得られ、ZMHの核化反応がMoO
の結晶懸濁液の添加量に応じてZMHの付着抑制効果を示すデータが得られ、ZMHの核化反応がMoO の結晶表面で起きていることを再確認した。今後は模擬廃液を用いて、MoO
の結晶表面で起きていることを再確認した。今後は模擬廃液を用いて、MoO (結晶および混濁液)の添加に伴うZMHの付着抑制効果を評価する。
(結晶および混濁液)の添加に伴うZMHの付着抑制効果を評価する。
下端 健吾*; 平沢 泉*; 宮崎 康典; 竹内 正行
no journal, ,
溶解槽で使用済燃料を溶かした硝酸溶液は核分裂生成物等を含んでおり、溶解性元素と難溶解性元素が混在することになる。難溶解性であるMoやZrは、高温酸性溶液中でモリブデン酸ジルコニウム・2水和物(ZMH)を形成し、配管やパイプに強く付着するため、再処理機器周辺の熱伝導率の低下や閉塞等を引き起こす。付着したZMHの物理的・化学的な洗浄では2次廃棄物の発生が懸念されることから、添加物による抑制策を考える必要がある。我々は、早稲田大学との共同研究で、ZMHと同伴した析出が示唆されているTe添加の影響を評価した。Zr, Mo, Teの混合溶液で得られた実験データをもとに考察した内容を以下に示す。(1)実液の相対濃度比に合わせたTe添加量では、溶液中の[Mo]と[Zr]に与える影響は小さい。得られた析出物のXRDスペクトルはベースラインが上昇しており、これはZr-Te錯体を形成したためと考えられる。(平成29年度の成果から、TeはMoよりもZrと反応しやすいことが分かっている。)(2)実液の相対濃度比よりも過剰量のTe添加によって、ZMHがSUS板に付着しなくなった。これは、Zr-Te錯体が優先的に形成されて、ZMHの析出に必要なZrが消費されたためと考えられる。よって、過剰量のTeを添加することで、ZMHの析出および壁面付着を抑制できる可能性を見出した。今後は、溶液中のZr-Te錯体の挙動評価や模擬廃液を用いたZMH析出の抑制評価を行う。
宮崎 康典; 渡部 創; 中村 雅弘; 柴田 淳広; 野村 和則
no journal, ,
使用済燃料再処理で発生する高レベル放射性廃液はガラス固化体として地層処分されるが、放射性廃棄物減容化および有害度低減の観点から、マイナーアクチノイドの分離変換が望まれる。我々は、マイナーアクチノイドを選択的に分離回収する抽出クロマトグラフィの技術開発を行っている。これまでにイオンの分離挙動をシミュレーションする計算コードの整備を進めてきたが、クロマトグラムを再現するまでに至っていない。そこで、J-PARCのパルス中性子照射ビームラインを活用した共鳴中性子イメージングの実施によって、イオン(または吸着バンド)が相互分離する様子を非破壊観測する。多孔質の粒子内拡散や分散等の情報を計算コードに反映し、シミュレーションを高度化するとともに、実プロセスにおけるカラム分離性能の向上を図る。
小藤 博英; 宮崎 康典; 渡部 創; 後藤 一郎*; 大山 孝一; 竹内 正行
no journal, ,
抽出クロマトグラフィによるMA分離操作において、HDEHP含浸吸着材によるMo, Zrの事前除去を検討している。HDEHP吸着材を用いる場合、吸着材の膨潤によるカラムの圧力損失上昇を避けるため大粒径で細孔径が大きい多孔質シリカ担体の使用を検討している。このようなシリカ粒子を用いた場合の使用済吸着材のガラス化及びガラス固化体の化学的安定性に与える影響を評価した。