Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
中堂 博之; 横井 直人*; 松尾 衛; 針井 一哉*; 鈴木 淳*; 今井 正樹; 佐藤 正寛*; 前川 禎通*; 齊藤 英治*
Physical Review Letters, 134(13), p.130603_1 - 130603_5, 2025/04
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Physics, Multidisciplinary)A spin 1/2 is the simplest system that has been believed to support a single two-level quantum system, represented by a single resonance. We experimentally demonstrate that a spin-1/2 nucleus of  F in C
F in C F
F exhibits an extra resonance corresponding to the emergence of the states, by mechanically rotating a sample and a coil in nuclear magnetic resonance (NMR) measurements. On the basis of the Floquet formalism, we identify the emergence of the extra two-level state due to the temporal periodicity generated by the mechanical rotation (mechanical spin multiplexing) and derive an operator algebra analogous to the planar rotor algebra in an effective description of the system. The observed multiplexing allows a single spin 1/2 to carry more than two states and potentially enabling the processing of multiple quantum bits on a single spin.
exhibits an extra resonance corresponding to the emergence of the states, by mechanically rotating a sample and a coil in nuclear magnetic resonance (NMR) measurements. On the basis of the Floquet formalism, we identify the emergence of the extra two-level state due to the temporal periodicity generated by the mechanical rotation (mechanical spin multiplexing) and derive an operator algebra analogous to the planar rotor algebra in an effective description of the system. The observed multiplexing allows a single spin 1/2 to carry more than two states and potentially enabling the processing of multiple quantum bits on a single spin.
 F
F勝又 哲裕*; 鈴木 涼*; 佐藤 直人*; 小田 良哉*; 本山 慎吾*; 鈴木 俊平*; 中島 護*; 稲熊 宜之*; 森 大輔*; 相見 晃久*; et al.
Chemistry of Materials, 36(8), p.3697 - 3704, 2024/04
被引用回数:1 パーセンタイル:30.18(Chemistry, Physical)ペロブスカイト型酸窒化物のBaFeO Fを高圧合成によって作製した。得られた物質はSHGシグナルが観測されたことから自発分極の存在を示唆していたため、分極発現機構を放射光高エネルギーX線回折で調べた。得られた2体相関分布関数をフィットした結果、方位の異なる局所的な分極発現機構を見出した。BaFeO
Fを高圧合成によって作製した。得られた物質はSHGシグナルが観測されたことから自発分極の存在を示唆していたため、分極発現機構を放射光高エネルギーX線回折で調べた。得られた2体相関分布関数をフィットした結果、方位の異なる局所的な分極発現機構を見出した。BaFeO Fは磁性材料でもあるため、磁気ドメインと強誘電ドメインが共存していると考えられる。
Fは磁性材料でもあるため、磁気ドメインと強誘電ドメインが共存していると考えられる。
 Sr
Sr CoO
CoO at initial electrochemical process in an alkaline solution
at initial electrochemical process in an alkaline solution松崎 陽*; 平山 雅章*; Oguchi, Shoya*; 粉生 守*; 池澤 篤憲*; 鈴木 耕太*; 田村 和久; 荒井 創*; 菅野 了次*
Electrochemistry (Internet), 90(10), p.107001_1 - 107001_8, 2022/10
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Electrochemistry)ペロブスカイト型構造を持つLa Sr
Sr CoO
CoO 酸素還元(ORR)および酸素発生(OER)反応について、様々な面方位を持つ2次元モデル電極を用いて調べた。パルスレーザー堆積法で合成した薄膜電極を用いることで、ORR反応の面方位依存性を明らかにした。電気化学測定より、1回目のORR/OERサイクルでは、ORRの反応活性は(001)面で最も高かったが、2回目のサイクルでは、活性が著しく低下した。放射光を用いた結晶構造解析を行い、La
酸素還元(ORR)および酸素発生(OER)反応について、様々な面方位を持つ2次元モデル電極を用いて調べた。パルスレーザー堆積法で合成した薄膜電極を用いることで、ORR反応の面方位依存性を明らかにした。電気化学測定より、1回目のORR/OERサイクルでは、ORRの反応活性は(001)面で最も高かったが、2回目のサイクルでは、活性が著しく低下した。放射光を用いた結晶構造解析を行い、La Sr
Sr CoO
CoO のバルクと表面の構造が変化していることがわかった。また、構造変化は酸素欠損サイトの形成によることが明らかになった。さらに、La
のバルクと表面の構造が変化していることがわかった。また、構造変化は酸素欠損サイトの形成によることが明らかになった。さらに、La Sr
Sr CoO
CoO の表面が部分的に分解されることも分かった。したがって、ORRおよびOER反応の活性を上げるには、電気化学反応に伴い形成される界面の構造が重要である。
の表面が部分的に分解されることも分かった。したがって、ORRおよびOER反応の活性を上げるには、電気化学反応に伴い形成される界面の構造が重要である。
 scattering length from
scattering length from  photoproduction on the proton near the reaction threshold
photoproduction on the proton near the reaction threshold石川 貴嗣*; 藤村 寿子*; 深澤 宏司*; 橋本 亮*; He, Q.*; 本多 佑記*; 保坂 淳; 岩田 高広*; 甲斐田 俊*; 笠木 治郎太*; et al.
Physical Review C, 101(5), p.052201_1 - 052201_6, 2020/05
被引用回数:4 パーセンタイル:36.67(Physics, Nuclear)Photoproduction of the omega meson on the proton has been experimentally studied near the threshold. The total cross sections are determined at incident energies ranging from 1.09 to 1.15 GeV. The 1/2 and 3/2 spin-averaged scattering length 
 and effective range
and effective range 
 between the CO meson and proton are estimated from the shape of the total cross section as a function of the incident photon energy:
between the CO meson and proton are estimated from the shape of the total cross section as a function of the incident photon energy: 
 = (-0.97
= (-0.97 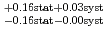 +
+  (0.07
(0.07 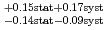 ) fm and
) fm and 
 = (+2.78
= (+2.78 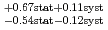 ) +
) +  (-0.01
(-0.01 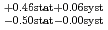 ) fm, resulting in a repulsive force. The real and imaginary parts for
) fm, resulting in a repulsive force. The real and imaginary parts for 
 and
and 
 are determined separately for the first time. A small
are determined separately for the first time. A small  -wave contribution does not affect the obtained values.
-wave contribution does not affect the obtained values.
 F and comparison of the structure among perovskite-type oxyfluorides
F and comparison of the structure among perovskite-type oxyfluorides勝又 哲裕*; 鈴木 涼*; 佐藤 直人*; 鈴木 俊平*; 中島 護*; 稲熊 宜之*; 森 大輔*; 相見 晃久*; 米田 安宏
Journal of Solid State Chemistry, 279, p.120919_1 - 120919_8, 2019/11
被引用回数:12 パーセンタイル:56.06(Chemistry, Inorganic & Nuclear)A new perovskite-type fluoride, BaInO F was synthesized and compared with other perovskite-type oxyfluorides. The atomic size of anions influences on the local structure and the average structure obtained from the refinement of the diffraction pattern is the cubic for most perovskite-type oxyfluorides.
F was synthesized and compared with other perovskite-type oxyfluorides. The atomic size of anions influences on the local structure and the average structure obtained from the refinement of the diffraction pattern is the cubic for most perovskite-type oxyfluorides.
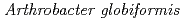 ; Assignment of bound diatomic molecules as O
; Assignment of bound diatomic molecules as O
村川 武志*; 林 秀行*; 角南 智子; 栗原 和男; 玉田 太郎; 黒木 良太; 鈴木 守*; 谷澤 克行*; 岡島 俊英*
Acta Crystallographica Section D, 69(12), p.2483 - 2494, 2013/12
被引用回数:14 パーセンタイル:67.17(Biochemical Research Methods)アルスロバクター-グロビフォルミス由来銅アミン酸化酵素の結晶構造を抗凍結剤として低分子ポリエチレングリコール(LMW PEG; 平均分子量 200)を用いて1.08
200)を用いて1.08 分解能で決定した。最終的な結晶構造学的
分解能で決定した。最終的な結晶構造学的 因子と
因子と
 値は、それぞれ13.0%と15.0
値は、それぞれ13.0%と15.0 であった。LMW PEGの幾つかの分子は、活性部位を含むタンパク質内部の空洞を占めており、それが分子全体の温度因子の著しい低下をもたらし、結果として、単量体分子量が約70,000と比較的大きなタンパク質にも拘わらず原子分解能の構造に至ったことがわかった。推定される全水素原子の約40%は、
であった。LMW PEGの幾つかの分子は、活性部位を含むタンパク質内部の空洞を占めており、それが分子全体の温度因子の著しい低下をもたらし、結果として、単量体分子量が約70,000と比較的大きなタンパク質にも拘わらず原子分解能の構造に至ったことがわかった。推定される全水素原子の約40%は、
 -
-
 差図中に明確な電子密度を持って観察され、複数のマイナーな配座異性体も多くの残基に対して同定された。また、翻訳後に誘導されたキノン補因子と銅原子を含む活性部位における異方的な変位の揺らぎを見積った。さらに、複数の二原子分子、恐らく分子性酸素がタンパク質と結合し、そのうちの一つは二量体界面の中央に位置する空洞から活性部位まで基質である二原子酸素のための進入経路として以前から提案されている領域に位置していた。
差図中に明確な電子密度を持って観察され、複数のマイナーな配座異性体も多くの残基に対して同定された。また、翻訳後に誘導されたキノン補因子と銅原子を含む活性部位における異方的な変位の揺らぎを見積った。さらに、複数の二原子分子、恐らく分子性酸素がタンパク質と結合し、そのうちの一つは二量体界面の中央に位置する空洞から活性部位まで基質である二原子酸素のための進入経路として以前から提案されている領域に位置していた。
川瀬 啓悟; 神門 正城; 早川 岳人; 大東 出; 近藤 修司; 本間 隆之; 亀島 敬; 小瀧 秀行; Chen, L.*; 福田 祐仁; et al.
Nuclear Physics Review, 26(Suppl.), p.94 - 99, 2009/07
SPring-8とKPSI-JAEAにおいて、それぞれMeV領域,sub-MeV領域の逆コンプトン散乱による光源を開発した。MeV光源は光励起型遠赤外レーザーと8GeV電子ビームとからなっている。sub-MeV光源はNd:YAGパルスレーザーとマイクロトロンで加速された150MeV電子ビームからなっている。どちらの光源も逆コンプトン光の発生に成功した。ここでは、これらの光源の特徴と今後の展望について発表する。
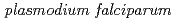 enolase
enolase奥 浩之*; 山田 圭一*; 小林 京子*; 片貝 良一*; Ashfaq, M.*; 花岡 宏史*; 飯田 靖彦*; 遠藤 啓吾*; 長谷川 伸; 前川 康成; et al.
Peptide Science 2008, p.439 - 442, 2009/03
マラリアは、熱帯及び亜熱帯地域における主な死因の一つである。これまでの研究において、エノラーゼ基質結合部位の部分配列に由来する人工ペプチド抗原としてマラリアワクチン抗原の有用性を検証してきた。人工抗原ペプチドは、抗原性ペプチドに5(6)-カルボキシフルオロセインを用いて蛍光ラベルして合成した。合成したペプチドは、乳酸とグリコール酸の共重合体(PLGA)を用いて乳化重合後、ホモジナイズし、ナノ粒子化した。この粒子へ再度0.5%ポリビニルアルコールを加えた後、乳化,ホモジナイズして粒子径0.3から1.5mmのナノ粒子を調製した。蛍光強度からみた生体外での徐放試験において、ペプチド抗原のみから作製したナノ球体を用いた場合、薬剤は、保留日数に対してほぼ0次で急激に放出されるのに比べ、PLGAナノ粒子に調製した試料は、1 g/7日間で徐放されることがわかった。1.0mg(蛍光入り薬剤4.0
g/7日間で徐放されることがわかった。1.0mg(蛍光入り薬剤4.0 g)のナノ粒子を用いたハダカネズミによる生体内試験において、蛍光強度は、12日間かけ次第に減少し、今回調製されたナノ微粒子は持続的に抗原を徐放することがわかった。
g)のナノ粒子を用いたハダカネズミによる生体内試験において、蛍光強度は、12日間かけ次第に減少し、今回調製されたナノ微粒子は持続的に抗原を徐放することがわかった。
 -ray generation from backward Compton scattering at SPring-8
-ray generation from backward Compton scattering at SPring-8川瀬 啓悟; 有本 靖*; 藤原 守; 岡島 茂樹*; 小路 正純*; 鈴木 伸介*; 田村 和宏*; 依田 哲彦*; 大熊 春夫*
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 592(3), p.154 - 161, 2008/07
被引用回数:20 パーセンタイル:76.06(Instruments & Instrumentation)SPring-8において8GeV電子ビームと遠赤外レーザーとの正面衝突によって逆コンプトン散乱を発生させるための試験ビームラインを構築した。遠赤外レーザーとして、ここでは炭酸ガスレーザーで光励起させるメタノールレーザーを用いている。遠赤外レーザーの出力は波長118.8 mで1.6Wを達成している。
mで1.6Wを達成している。 線の直接測定により、発生させた
線の直接測定により、発生させた 線強度は10
線強度は10 photons/sであった。この値は入射したレーザー強度とレーザー輸送光学系の伝送効率とを考慮して評価した
photons/sであった。この値は入射したレーザー強度とレーザー輸送光学系の伝送効率とを考慮して評価した 線発生強度とよく一致している。
線発生強度とよく一致している。
二宮 博正; 秋場 真人; 藤井 常幸; 藤田 隆明; 藤原 正巳*; 濱松 清隆; 林 伸彦; 細金 延幸; 池田 佳隆; 井上 信幸; et al.
Journal of the Korean Physical Society, 49, p.S428 - S432, 2006/12
現在検討が進められているJT-60のコイルを超伝導コイルに置き換える計画(トカマク国内重点化装置計画)の概要について述べる。本計画はITER及び原型炉への貢献を目指しているが、その位置づけ,目的,物理設計及び装置設計の概要,今後の計画等について示す。物理設計については、特に高い規格化ベータ値を実現するためのアスペクト比,形状因子及び臨界条件クラスのプラズマや完全非誘導電流駆動のパラメータ領域等について、装置については物理設計と整合した設計の概要について示す。
菊池 満; 玉井 広史; 松川 誠; 藤田 隆明; 高瀬 雄一*; 櫻井 真治; 木津 要; 土屋 勝彦; 栗田 源一; 森岡 篤彦; et al.
Nuclear Fusion, 46(3), p.S29 - S38, 2006/03
被引用回数:13 パーセンタイル:40.56(Physics, Fluids & Plasmas)トカマク国内重点化装置(NCT)計画は、大学における成果を取り込みつつJT-60Uに引き続き先進トカマクを進めるための国内計画である。NCTのミッションは発電実証プラントに向けて高ベータ定常運転を実現するとともに、ITERへの貢献を図ることである。高ベータ定常運転を実現するために、装置のアスペクト比,形状制御性,抵抗性壁モードの帰還制御性,電流分布と圧力分布の制御性の機動性と自由度を追求した。
土屋 勝彦; 秋場 真人; 疇地 宏*; 藤井 常幸; 藤田 隆明; 藤原 正巳*; 濱松 清隆; 橋爪 秀利*; 林 伸彦; 堀池 寛*; et al.
Fusion Engineering and Design, 81(8-14), p.1599 - 1605, 2006/02
被引用回数:1 パーセンタイル:9.58(Nuclear Science & Technology)JT-60定常高ベータ装置(トカマク国内重点化装置)は、経済的な核融合炉の実現を目指した定常高ベータプラズマ運転の実証が重要なミッションの一つである。現在、プラズマ形状及びアスペクト比について広いパラメータ領域で研究を行えるように、装置の物理的・技術的設計検討を進めている。本装置の目標とする高ベータプラズマは、自由境界MHD安定性限界を超えた領域にあるため、電子サイクロトロン加熱による新古典テアリングモードの抑制に加えて、安定化板及び容器内コイルを用いた壁不安定性モードの抑制など、さまざまなMHD不安定性の制御手法を駆使する必要がある。それらを踏まえて、今回は、高ベータと臨界条件クラスのプラズマを同時に達成できるプラズマパラメータの解析評価、及び自由境界MHD安定性限界を超えた高ベータプラズマの非誘導電流駆動制御シナリオの検討結果について報告する。また、広いパラメータ領域で定常高ベータプラズマ運転を実現させるための装置設計の現状に関して、超伝導コイル及び放射線遮へい材を中心に報告する。
 plasma operation
plasma operation玉井 広史; 秋場 真人; 疇地 宏*; 藤田 隆明; 濱松 清隆; 橋爪 秀利*; 林 伸彦; 堀池 寛*; 細金 延幸; 市村 真*; et al.
Nuclear Fusion, 45(12), p.1676 - 1683, 2005/12
被引用回数:15 パーセンタイル:44.52(Physics, Fluids & Plasmas)トカマク国内重点化装置の設計研究をまとめた。装置の設計は、プラズマのアスペクト比と形状制御性に関して自由度を広く確保できることが求められている。これは、ITERと平行して研究を進めるとともに、定常高ベータプラズマ運転についての科学的なデータベースをDEMOへ提供する観点から重要である。この目標に合致するように、プラズマのアスペクト比と形状の自由度の確保について、これまで比較的困難であったダイバータ排気性能との両立が図られるように装置設計を行った。この装置設計に基づいて、閉じ込め,安定性,電流駆動,ダイバータプラズマ等の物理性能を評価し、主目的である定常高ベータプラズマを実現するための制御方法を検討した。
此村 守; 小川 隆; 岡野 靖; 山口 浩之; 村上 勤; 高木 直行; 西口 洋平; 杉野 和輝; 永沼 正行; 菱田 正彦; et al.
JNC TN9400 2004-035, 2071 Pages, 2004/06
ナトリウム冷却炉、鉛ビスマス冷却炉、ヘリウムガス冷却炉及び水冷却炉について、革新技術を導入し炉型の特徴を活かした炉システム概念を構築し、その概念の成立の見通しを得るための検討を行うとともに、設計要求への適合性を評価した。その結果、2015年頃に高速増殖炉技術を実用化するためには、現状の知見で課題とされた項目で画期的な技術革新がないかぎり、ナトリウムを冷却材して選択することが合理的であることが明らかとなった。
玉井 広史; 松川 誠; 栗田 源一; 林 伸彦; 浦田 一宏*; 三浦 友史; 木津 要; 土屋 勝彦; 森岡 篤彦; 工藤 祐介; et al.
Plasma Science and Technology, 6(1), p.2141 - 2150, 2004/02
被引用回数:2 パーセンタイル:6.31(Physics, Fluids & Plasmas)JT-60定常高ベータ化計画(JT-60改修計画)の最重要課題は高ベータ,臨界クラスのパラメータを持つ高性能プラズマの100秒程度以上の維持を実証することである。このため、高ベータプラズマを達成するためのプラズマパラメータや運転シナリオ,制御手法の検討を行うとともに、超伝導磁場コイルの要素技術の開発を始め、放射線遮蔽や真空容器等の設計検討及び試験開発を行い、その成立性を確認した。本発表は、以上の物理・工学設計と試験開発の進捗状況を詳述する。
牛草 健吉; 井手 俊介; 及川 聡洋; 鈴木 隆博; 鎌田 裕; 藤田 隆明; 池田 佳隆; 内藤 磨; 松岡 守*; 近藤 貴; et al.
Fusion Science and Technology (JT-60 Special Issue), 42(2-3), p.255 - 277, 2002/09
被引用回数:11 パーセンタイル:12.12(Nuclear Science & Technology)JT-60における非誘導電流駆動及び高性能定常運転に関する研究成果をまとめた。低域混成波電流駆動(LHCD)により3.5MAの大電流駆動,3.6 1019m-2A/Wの高効率電流駆動,自在な電流分布制御性を実証した。近接条件,高速電子挙動等の基礎研究によりLHCD物理の解明に貢献した。負イオン源中性粒子ビーム電流駆動(N-NBCD)実験により、中性粒子ビーム電流駆動に関する研究を著しく進展させた。駆動効率1.5
1019m-2A/Wの高効率電流駆動,自在な電流分布制御性を実証した。近接条件,高速電子挙動等の基礎研究によりLHCD物理の解明に貢献した。負イオン源中性粒子ビーム電流駆動(N-NBCD)実験により、中性粒子ビーム電流駆動に関する研究を著しく進展させた。駆動効率1.5 1019m-2A/Wを達成し、1MAの電流駆動に成功した。弱磁場励起Oモード電子サイクロトロン波による局所電流駆動を実証し、駆動効率0.5
1019m-2A/Wを達成し、1MAの電流駆動に成功した。弱磁場励起Oモード電子サイクロトロン波による局所電流駆動を実証し、駆動効率0.5 1019m-2A/W,0.2MAの電流駆動を達成するとともに、新古典テアリング不安定性の抑制に成功した。これらの成果に基づき、高
1019m-2A/W,0.2MAの電流駆動を達成するとともに、新古典テアリング不安定性の抑制に成功した。これらの成果に基づき、高 pHモード及び負磁気シアプラズマという2つの高性能定常運転方式を開発した。これらの運転方式は、高い閉じ込め性能を有するほぼ定常状態の電流分布を完全電流駆動の状態で持続できるものである。高い規格化密度や高い核融合積を有する完全電流駆動高性能定常運転方式で達成した。
pHモード及び負磁気シアプラズマという2つの高性能定常運転方式を開発した。これらの運転方式は、高い閉じ込め性能を有するほぼ定常状態の電流分布を完全電流駆動の状態で持続できるものである。高い規格化密度や高い核融合積を有する完全電流駆動高性能定常運転方式で達成した。
 ion source for the JT-60U negative-ion-based neutral beam injector
ion source for the JT-60U negative-ion-based neutral beam injector奥村 義和; 花田 磨砂也; 井上 多加志; 栗山 正明; 前野 修一*; 松岡 守; 宮本 賢治; 水野 誠; 小原 祥裕; 鈴木 哲; et al.
Proceedings of 15th IEEE/NPSS Symposium on Fusion Engineering, p.466 - 469, 1993/00
JT-60Uの負イオンNBI用の大型負イオン源の設計と開発状況について発表する。JT-60U負イオンNBIのためには、500keV、22Aという従来のイオン源の性能を遙かに上回る負イオン源が必要である。原研におけるこれまでの大電流負イオン源開発の集大成として本イオン源を設計しており、大型プラズマ源、独自の磁気フィルター、高エネルギー静電加速系などに工夫がこらされている。設計の基になった実験結果と計算機シミュレーションの結果、製作の現状を述べる。
Suzuki, Kazuhisa; 山内 勘; Tani, Satoshi; Ichige, Akio; Naito, Takeshi; 原田 守; Ito, Masahiko; Osugi, Shoichi*; Shibata, Kenichi*
PNC TN951 76-05, 70 Pages, 1976/03
None
鈴木 達也; 堂野前 寧; 原田 守
松本 武志*; 角田 俊也*; 佐藤 康士*
【課題】廃棄物の高周波加熱を促進し、効率よく焼却処理を行えるようにし、しかも焼却筒の長寿命化を図ることができるようにする。また、廃棄物が破砕したプレス缶と可燃物の混合物であっても、高周波加熱による焼却処理の際にプレス缶同士の固着が生じず、そのため、再破砕などの後処理工程を要しないようにする。 【解決手段】高周波加熱装置10の内部に焼却器12が装着されており、該焼却器は、非磁性材料からなる焼却筒18と、該焼却筒を受ける焼却筒受け皿20と、前記焼却筒内に組み込まれている火格子22を備え、該火格子上に位置する廃棄物Wを高周波加熱により焼却し、火格子から落下する焼却灰を焼却筒受け皿で受ける構造であって、焼却筒内の火格子の下方に、強磁性の導電性材料からなり、落下する焼却灰を通過させる複数の空隙を備えた加熱促進体28が設置されている。
高野 雅人; 伊藤 義之; 鈴木 達也*; 滝本 真佑美*; 松倉 実*; 三村 均*; 森 浩一*; 岩崎 守*
no journal, ,
東海・再処理施設から発生する低放射性廃液は、低放射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)で処理される計画であり、LWTFのCs及びSr吸着塔で使用する吸着材の検討を行っている。Cs及びSr吸着材は、処理対象廃液のpHの影響を受け吸着性能が低下する等の特徴を有するため、実機(LWTF)への適用にあたっては、吸着性能を十分発揮させる吸着プロセスを検討する必要がある。このため、実機を模擬した連結カラム試験を行い、Cs及びSr吸着材の通液順序による各吸着材の破過特性を調査し、最適な吸着プロセスを検討した。その結果、各吸着材の使用順序として、1Sr吸着材 2Cs吸着材の順に通液することで、Cs及びSr吸着材の破過特性は向上することが分かった。
2Cs吸着材の順に通液することで、Cs及びSr吸着材の破過特性は向上することが分かった。