Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
下村 浩一郎*; 幸田 章宏*; Pant, A. D.*; 名取 寛顕*; 藤森 寛*; 梅垣 いづみ*; 中村 惇平*; 反保 元伸*; 河村 成肇*; 手島 菜月*; et al.
Journal of Physics; Conference Series, 2462, p.012033_1 - 012033_5, 2023/03
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Physics, Applied)At J-PARC MUSE, since the  SR2017 conference and up to FY2022, there have been several new developments at the facility, including the completion of a new experimental area S2 at the surface muon beamline S-line and the first muon beam extraction to the H1 area in the H-line, mainly to carry out high-statistics fundamental physics experiments. Several new studies are also underway, such as applying negative muon non-destructive elemental analysis to the analysis of samples returned from the asteroid Ryugu in the D2 area of the D-line. This paper reports on the latest status of MUSE.
SR2017 conference and up to FY2022, there have been several new developments at the facility, including the completion of a new experimental area S2 at the surface muon beamline S-line and the first muon beam extraction to the H1 area in the H-line, mainly to carry out high-statistics fundamental physics experiments. Several new studies are also underway, such as applying negative muon non-destructive elemental analysis to the analysis of samples returned from the asteroid Ryugu in the D2 area of the D-line. This paper reports on the latest status of MUSE.
山川 光稀*; 猿田 正明*; 森谷 寛*; 山崎 宏晃*; 西田 明美; 川田 学; 飯垣 和彦
Proceedings of 28th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE 28) (Internet), 6 Pages, 2021/08
中越沖地震や東北地方太平洋沖地震等、近年大規模地震が多く発生し、原子力施設の耐震評価は重要課題となっている。原子力施設の耐震評価をより高い精度で行うためには、原子炉建屋の局部応答を考慮して施設内の機器への入力を精緻に評価する必要がある。このため、近年では原子炉建屋の現実的な局部応答を評価可能な、3次元有限要素モデルが耐震評価へ活用されつつある。原子炉建屋の3次元有限要素モデルについては、柏崎刈羽原子力発電所を対象として2007年新潟県中越沖地震の観測記録を用いたベンチマーク解析なども行われている。しかしながら、その結果は解析者によって異なり、3次元モデルを用いた地震応答解析手法はまだ確立されていないのが現状である。原子炉建屋の壁や床の局部応答評価など、3次元有限要素モデルの精度を向上させるためには、地震観測記録を活用したモデルの妥当性確認が重要となる。本研究では、原子炉建屋の固有振動数や固有モードなどの基本的な応答特性を分析するとともに、地震動の強さの違いによる応答特性への影響評価を行い、原子炉建屋の地震時挙動を明らかにする。これらの分析を通して、原子炉建屋の固有振動数と地震動の強さとの関係を定量的に評価する。さらに、原子炉建屋の回転変位と固有モードに対応する建屋変形に起因する変位の比を比較する。
日野 竜太郎; 竹上 弘彰; 山崎 幸恵; 小川 徹
JAEA-Review 2016-038, 294 Pages, 2017/03
福島第一原子力発電所事故後に、シビアアクシデント時の水素対策は、我が国において大きな技術的課題として認識されるにいたった。しかし、原子力技術者と燃焼・爆発の専門家との間で共通の知識基盤を形成し、将来の原子力安全を確保、向上させていく努力は始まったばかりである。そのような活動の一つとして、「原子力における水素安全対策高度化ハンドブック」を、資源エネルギー庁受託事業「水素安全対策高度化」の一環として作成した。本ハンドブックでは以下を目指した:(1)原子力の技術者が理解しておくべき水素安全技術の先端を示す、(2)原子力技術者に協力すべき燃焼、爆発専門家向けに、原子力における水素安全の要点が示されているものとする、(3)事故後廃棄物管理までを視野に入れて、放射線分解水素に関する情報を拡充する、(4)過酷事故解析等の特定・狭義の専門家を対象にするものではなく、高度な解析式なしに迅速に図表で判断を助けるものとする、(5)解析技術者にも役立つように、詳細なデータベースの所在や、最新の解析ツールのオーバービューを添える。
澤畑 洋明; 島崎 洋祐; 石塚 悦男; 山崎 和則; 柳田 佳徳; 藤原 佑輔; 高田 昌二; 篠崎 正幸; 濱本 真平; 栃尾 大輔
Proceedings of 24th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE-24) (DVD-ROM), 8 Pages, 2016/06
HTTRでは、起動用中性子源として Cfが使用され、定期的に交換を行っている。本交換作業において、2つの課題が挙げられていた。1つは、中性子線漏洩による作業員の被ばくであり、もう一つは、中性子源輸送容器の取扱性能の信頼性である。中性子線漏洩による被ばく線量の低減については、PHITSコードを用いて漏洩源である燃料交換機の解析を行い、効果的な遮へい方法を考案し、簡易に取付・取外しができるポリエチレン製のブロックと粒子を冷却流路に設置した。その結果、集団線量を約700人・
Cfが使用され、定期的に交換を行っている。本交換作業において、2つの課題が挙げられていた。1つは、中性子線漏洩による作業員の被ばくであり、もう一つは、中性子源輸送容器の取扱性能の信頼性である。中性子線漏洩による被ばく線量の低減については、PHITSコードを用いて漏洩源である燃料交換機の解析を行い、効果的な遮へい方法を考案し、簡易に取付・取外しができるポリエチレン製のブロックと粒子を冷却流路に設置した。その結果、集団線量を約700人・ Svから約300人・
Svから約300人・ Svまで低減できた。中性子源輸送容器については、容器を小さくすることにより、取扱性能を改善して取扱作業を安全に完遂した。
Svまで低減できた。中性子源輸送容器については、容器を小さくすることにより、取扱性能を改善して取扱作業を安全に完遂した。
 in a greenhouse for tomato cultivation
in a greenhouse for tomato cultivation石井 里美; 山崎 治明*; 鈴井 伸郎; 尹 永根; 河地 有木; 島田 浩章*; 藤巻 秀
JAEA-Review 2015-022, JAEA Takasaki Annual Report 2014, P. 93, 2016/02
Tomato is popularly grown in environmentally controlled system such as a greenhouse for improvement of bioproduction. It is important to control the condition in the greenhouse for increasing the translocation of fixed carbon from the leaves to the growing fruits. Elevation of CO concentration is widely employed for that purpose; however, it is difficult to estimate its effect quantitatively because tomato plants have too large inter-individual variations with developing fruits. In this study, we employed a PETIS which is a live-imaging system of nutrients in plant body using short-lived radioisotopes including
concentration is widely employed for that purpose; however, it is difficult to estimate its effect quantitatively because tomato plants have too large inter-individual variations with developing fruits. In this study, we employed a PETIS which is a live-imaging system of nutrients in plant body using short-lived radioisotopes including  C. We also established a closed cultivation system to feed a test plant with CO
C. We also established a closed cultivation system to feed a test plant with CO at set concentrations of 400, 1,500 and 3,000 ppm and a pulse of
at set concentrations of 400, 1,500 and 3,000 ppm and a pulse of  CO
CO .
.
 concentration in a closed cultivation system for the improvement of bioproduction in tomato fruits
concentration in a closed cultivation system for the improvement of bioproduction in tomato fruits山崎 治明*; 鈴井 伸郎; 尹 永根; 河地 有木; 石井 里美; 島田 浩章*; 藤巻 秀
Plant Biotechnology, 32(1), p.31 - 37, 2015/04
被引用回数:17 パーセンタイル:51.68(Biotechnology & Applied Microbiology)To maximize fruit yield of tomatoes cultivated in a controlled, closed system such as a greenhouse or a plant factory at a limited cost, it is important to raise the translocation rate of fixed carbon to fruits by tuning the cultivation conditions. Elevation of atmospheric  CO
CO concentration is a good candidate. In this study, we employed a positron-emitting tracer imaging system (PETIS), which is a live-imaging technology for plant studies, and a short-lived radioisotope
concentration is a good candidate. In this study, we employed a positron-emitting tracer imaging system (PETIS), which is a live-imaging technology for plant studies, and a short-lived radioisotope  C to quantitatively analyze immediate responses of carbon fixation and translocation in tomatoes in elevated CO
C to quantitatively analyze immediate responses of carbon fixation and translocation in tomatoes in elevated CO conditions. We also developed a closed cultivation system to feed a test plant with CO
conditions. We also developed a closed cultivation system to feed a test plant with CO at concentrations of 400, 1500 and 3000 ppm and a pulse of
at concentrations of 400, 1500 and 3000 ppm and a pulse of  CO
CO . As a result, we obtained serial images of
. As a result, we obtained serial images of  C fixation by leaves and subsequent translocation into fruits. Carbon fixation was enhanced steadily by increasing the CO
C fixation by leaves and subsequent translocation into fruits. Carbon fixation was enhanced steadily by increasing the CO concentration, but the amount translocated into fruits saturated at 1500 ppm on average. The translocation rate had larger inter-individual variation and showed less consistent responses to external CO
concentration, but the amount translocated into fruits saturated at 1500 ppm on average. The translocation rate had larger inter-individual variation and showed less consistent responses to external CO conditions compared with carbon fixation.
conditions compared with carbon fixation.
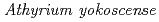 and tobacco plants
and tobacco plants吉原 利一*; 鈴井 伸郎; 石井 里美; 北崎 真由*; 山崎 治明*; 北崎 一義*; 河地 有木; 尹 永根; 七夕 小百合*; 橋田 慎之介*; et al.
Plant, Cell & Environment, 37(5), p.1086 - 1096, 2014/05
被引用回数:27 パーセンタイル:66.15(Plant Sciences)Cadmium (Cd) accumulations in a Cd hyper-accumulator fern, 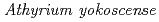 (
( ), and tobacco,
), and tobacco, 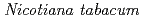 (
( ), were kinetically analysed using the positron-emitting tracer imaging system under two medium conditions (basal and no-nutrient). In
), were kinetically analysed using the positron-emitting tracer imaging system under two medium conditions (basal and no-nutrient). In  , maximumly 50% and 15% of the total Cd accumulated in the distal roots and the shoots under the basal condition, respectively. Interestingly, a portion of the Cd in the distal roots returned to the medium. In comparison with
, maximumly 50% and 15% of the total Cd accumulated in the distal roots and the shoots under the basal condition, respectively. Interestingly, a portion of the Cd in the distal roots returned to the medium. In comparison with  , a little fewer Cd accumulations in the distal roots and clearly higher Cd migration to the shoots were observed in
, a little fewer Cd accumulations in the distal roots and clearly higher Cd migration to the shoots were observed in  under the basal condition (maximumly 40% and 70% of the total Cd, respectively). The no-nutrient condition down-regulated the Cd migration in both species, although the regulation was highly stricter in
under the basal condition (maximumly 40% and 70% of the total Cd, respectively). The no-nutrient condition down-regulated the Cd migration in both species, although the regulation was highly stricter in  than in
than in  (almost no migration in
(almost no migration in  and around 20% migration in
and around 20% migration in  ). In addition, the present work enabled to estimate physical and physiological Cd accumulation capacities in the distal roots, and demonstrated condition-dependent changes especially in
). In addition, the present work enabled to estimate physical and physiological Cd accumulation capacities in the distal roots, and demonstrated condition-dependent changes especially in  . These results clearly suggested occurrences of species-/condition-specific regulations in each observed parts. It is probable that integration of these properties govern the specific Cd tolerance/accumulation in
. These results clearly suggested occurrences of species-/condition-specific regulations in each observed parts. It is probable that integration of these properties govern the specific Cd tolerance/accumulation in  and
and  .
.
 2010年度)
2010年度)天野 由記; 山本 陽一; 南條 功; 村上 裕晃; 横田 秀晴; 山崎 雅則; 國丸 貴紀; 大山 隆弘*; 岩月 輝希
JAEA-Data/Code 2011-023, 312 Pages, 2012/02
日本原子力研究開発機構幌延深地層研究センターでは、幌延深地層研究計画に基づきボーリング孔の掘削を伴う地上からの調査研究(第1段階)の一環として、平成13年度から表層水,地下水などの水質分析を行ってきた。分析の対象は、ボーリング孔から採取した地下水,掘削水,掘削リターン水,岩石コアからの抽出水,河川水及び雨水などである。また、平成18年度から幌延深地層研究計画における地下施設建設時の調査研究(第2段階)が進められており、立坑内の集水リング,立坑壁面湧水やボーリング孔などから地下水を採取し、水質分析を実施している。本報告書は、平成13年度から平成22年度までの水質分析データを取りまとめたものである。
山崎 治明; 鈴井 伸郎; 河地 有木; 石井 里美; 島田 浩章*; 藤巻 秀
JAEA-Review 2011-043, JAEA Takasaki Annual Report 2010, P. 98, 2012/01
Improvement in crop yield is expected by understanding "source-sink regulation system" of higher plants. In this study, we analyzed the photoassimilate distribution system to two sink organs, the root and the shoot apex, using positron-emitting tracer imaging system (PETIS) and cold-girdling technique, which is known as a method to inhibit photoassimilate translocation.  CO
CO exposure and PETIS imaging were conducted two times with the same test plant. Cold-girdling was treated only in the second run by cooling the boundary region on the stem between shoot and root. Time-activity curves were generated from the regions of the root, shoot apex and source leaf in the PETIS data. Then, three indices were analyzed; the influx rates of photoassimilate into the two sink organs, the root and the shoot apex, and the efflux rate from the source leaf. As the results, the influx rate was decreased drastically into the root. On the other hand, influx into the shoot apex hardly changed. And the efflux rate from the leaf was decreased. These results suggest that the "source supply" is adjusted so as to keep influx rate of photoassimilate into the untreated sink.
exposure and PETIS imaging were conducted two times with the same test plant. Cold-girdling was treated only in the second run by cooling the boundary region on the stem between shoot and root. Time-activity curves were generated from the regions of the root, shoot apex and source leaf in the PETIS data. Then, three indices were analyzed; the influx rates of photoassimilate into the two sink organs, the root and the shoot apex, and the efflux rate from the source leaf. As the results, the influx rate was decreased drastically into the root. On the other hand, influx into the shoot apex hardly changed. And the efflux rate from the leaf was decreased. These results suggest that the "source supply" is adjusted so as to keep influx rate of photoassimilate into the untreated sink.
岩月 輝希; 佐藤 治夫; 棚井 憲治; 稲垣 学; 澤田 淳; 新沼 寛明; 石井 英一; 前川 恵輔; 戸村 豪治; 真田 祐幸; et al.
JAEA-Research 2009-002, 156 Pages, 2009/05
「高レベル放射性廃棄物の地層処分基盤研究開発に関する全体計画」及び研究技術開発の現状に基づいて既往の研究計画を更新し、幌延深地層研究計画第2段階における平成20 21年度の具体的な研究計画を作成した。計画検討にあたっては、施設建設工程などの制約条件を踏まえたうえで、深地層の科学的研究,地層処分研究開発にかかわる研究技術開発(地質環境特性調査評価技術,地下施設建設に伴う地質環境変化の調査評価技術,深地層における工学技術,地層処分に必要な工学技術,安全評価技術など)の今後の実施計画として、ボーリング調査計画やモニタリング計画,工学試験などの計画検討を行ったうえで、各課題の現中期計画終了時の達成目標を明確化した。
21年度の具体的な研究計画を作成した。計画検討にあたっては、施設建設工程などの制約条件を踏まえたうえで、深地層の科学的研究,地層処分研究開発にかかわる研究技術開発(地質環境特性調査評価技術,地下施設建設に伴う地質環境変化の調査評価技術,深地層における工学技術,地層処分に必要な工学技術,安全評価技術など)の今後の実施計画として、ボーリング調査計画やモニタリング計画,工学試験などの計画検討を行ったうえで、各課題の現中期計画終了時の達成目標を明確化した。
山崎 雅直; 舟木 泰智; 山口 雄大*; 新沼 寛明; 藤川 大輔; 真田 祐幸; 平賀 正人; 津坂 仁和
JAEA-Data/Code 2008-023, 136 Pages, 2008/11
本データ集は、(1)幌延深地層研究計画における地下施設建設時に取得した調査・計測データの共有化並びに逸散防止を図ること,(2)当該切羽や後続施工箇所の設計・施工にフィードバックする情報化施工プログラムを実施していくための基礎データとすることを目的として、2007年度(平成19年度)に実施した地下施設建設時の調査結果を取りまとめたものである。
濱本 真平; 飯垣 和彦; 清水 厚志; 澤畑 洋明; 近藤 誠; 小山 直; 河野 修一; 小林 正一; 川本 大樹; 鈴木 尚; et al.
JAEA-Technology 2006-030, 58 Pages, 2006/03
日本原子力研究開発機構が所有する高温工学試験研究炉(HTTR)の反応度制御設備は、制御棒系と後備停止系の、動作原理の異なる二つの独立した系統で構成されている。通常運転時、原子炉の反応度を制御するとともに、運転時の異常な過渡変化時及び事故時に安全かつ確実に原子炉を停止させるものである。後備停止系は、万一制御棒系のみで原子炉を停止できない場合に、中性子吸収材である炭化ホウ素ペレットを炉心内に重力落下させ、いかなる運転状態からも原子炉を停止する機能を有するものであり、炭化ホウ素ペレットと、ペレットを収めるホッパ,電動プラグ,後備停止系駆動機構,ガイドチューブ等で構成されている。HTTRでは、平成16年7月26日から平成17年3月4日までの計画で、施設定期検査を実施してきたところ、2月21日の後備停止系の作動試験時に、本装置の16基のうち1基が正常に動作しないことがわかった。調査の結果、後備停止系が正常に動作しなかった原因は、後備停止系を駆動するモータの上部のオイルシールが変形したことによってグリースから分離した油がブレーキに到達し、ブレーキの磨耗した粉と混合することによって粘着物となり、粘着物がブレーキの解除を阻害したことによって、モータの駆動を妨げたことがわかった。
伊東 秀明; 則次 明広; 鈴木 寿章; 山崎 学; 大川 敏克
サイクル機構技報, (21), p.77 - 97, 2004/00
高速実験炉「常陽」の高度化計画(MK-III計画)に向けて実施してきた、各種運転技術の高度化について述べるとともに、MK-III総合機能試験結果について報告する。
後藤 俊治*; 竹下 邦和*; 鈴木 芳生*; 大橋 治彦*; 浅野 芳裕; 木村 洋昭*; 松下 智裕*; 八木 直人*; 一色 康之*; 山崎 裕史*; et al.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 467-468(Part1), p.682 - 685, 2001/07
イメージング技術開発や、X線光学素子開発,物性研究のためのトモグラフィーや医学イメージング,トポグラフィー研究等を目的とした、最初の中央ビームラインをSPring-8で構築した。この結果、大視野でコヒーレントな光ビームを得ることに成功した。またこのビームラインを用いて、300mmのシリコンクリスタルのone-shotトポグラフのような、予備実験を成功裡に終わることができた。これらについて論じた。
後藤 俊治*; 竹下 邦和*; 鈴木 芳生*; 大橋 治彦*; 浅野 芳裕; 木村 洋昭*; 松下 智裕*; 八木 直人*; 一色 麻衣子*; 山崎 裕史*; et al.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 467-468(Part1), p.682 - 685, 2001/07
被引用回数:145 パーセンタイル:99.12(Instruments & Instrumentation)大型放射光施設SPring-8には、発光点から実験ステーションまでの距離が215メートルある中尺ビームラインがある。そのうちの、偏向電磁石ビームラインであるBL20B2の建設及びコミッショニングをおこなった。
Kuwabara, K.*; 栗下 裕明*; 鵜飼 重治; 鳴井 實*; 水田 俊治; 山崎 正徳*; Kayano, H.*
Journal of Nuclear Materials, 258-263(Part 2), p.1236 - 1241, 1998/10
被引用回数:29 パーセンタイル:88.09(Materials Science, Multidisciplinary)大型高速炉を対象とした長寿命燃料被覆管材料として注目されている酸化物分散強化型(ODS)フェライト鋼を高速炉燃料被覆管として適用するには、照射脆化の少ないことが要求される。このため、平成元年度に試作されたODSフェライト鋼のシャルピー衝撃特性に及ぼす中性子照射効果をVノッチ付きの微小試験片(1.5 1.5
1.5 20mm)を用いて調べた。試験片は高速炉実験炉「常陽」において、照射温度は646
20mm)を用いて調べた。試験片は高速炉実験炉「常陽」において、照射温度は646 845k、照射量は0.3
845k、照射量は0.3 3.8
3.8 E(+26)n/m
E(+26)n/m まで照射された。シャルピー衝撃試験の結果は、照射後においても照射前と同様の優れた特性を示した。
まで照射された。シャルピー衝撃試験の結果は、照射後においても照射前と同様の優れた特性を示した。
山崎 康平*; 大竹 浩靖*; 長谷川 浩司*; 長谷部 吉昭*; 山路 達也*; 小泉 安郎; 大貫 晃*; 西 弘昭*
no journal, ,
上昇蒸気流と凝縮液膜流下流の共存する管内気液対向二相流実験を行った。加圧水型軽水炉(PWR)の中小破断冷却材喪失事故時の蒸気発生器(SG)U字管内上昇流側の蓄水挙動の機構解明と蓄水量評価モデルの開発を目的とした一連の研究の報告である。本報では、内径18mm、長さ4mの垂直単管内凝縮共存気液対向流現象の実験を行った。凝縮量を幅広くとれるよう、管壁伝熱抵抗の大きなポリカーボネート製試験流路から、伝熱抵抗の小さい真鍮管へ試験流路を変えた。今回の実験条件は比較的蒸気流速の速い条件が主であったため、凝縮液は全て上方へ流れる上向き環状二相流状態であった。測定された管路入口-出口間の圧力損失は、Lockhart-Martinelli二相流圧力損失計算法により求めた値とよく一致した。今後のパラメータ実験及び取得データ評価に向かって見通しを得ることができた。
山路 達也*; 小泉 安郎; 山崎 康平*; 大竹 浩靖*; 長谷川 浩司*; 長谷部 吉昭*; 大貫 晃*; 西 弘昭*
no journal, ,
上昇蒸気流と凝縮液膜流下流の共存する管内気液対向二相流実験を行った。加圧水型軽水炉(PWR)の中小破断冷却材喪失事故時の蒸気発生器(SG)U字管内上昇流側の蓄水挙動の機構解明と蓄水量評価モデルの開発を目的とした一連の研究の報告である。本報では、内径18mm、長さ4mの垂直単管内凝縮共存気液対向流現象の観察実験を行った。流動状況観察を主目的としていたため、試験流路は透明ポリカーボネイト製であった。蒸気流速が低い状態では流下液膜状態で凝縮水は流路下端から流下し、排水されていたが、蒸気流速の上昇に伴い、長さ方向管中央付近でスラグ流状態が現れるようになり、凝縮水は上方へ運ばれるようになった。このとき、これより下部では凝縮液の上方への移動は起きず、下方に流れ流路下端から流出していた。このようなフラッディング状況は、これまでの水-空気系では観察されていないため、新たな現象の可能性を含めて検討中である。
 施用効果の評価; ポジトロンイメージング技術を用いた炭素栄養の動態解析
施用効果の評価; ポジトロンイメージング技術を用いた炭素栄養の動態解析鈴井 伸郎; 山崎 治明*; 尹 永根; 河地 有木; 石井 里美; 島田 浩章*; 藤巻 秀
no journal, ,
炭素栄養の転流率の増加は果実収量の向上に直結するため、温室や植物工場などの閉鎖環境におけるトマト栽培では、転流率を増加させるための様々な条件検討がなされている。特にCO 施用濃度の最適化は転流率の増加に最も効果的であると言えるが、CO
施用濃度の最適化は転流率の増加に最も効果的であると言えるが、CO 濃度に対する転流率の応答を正確に評価することは技術的に困難であった。そこで本研究では、炭素11(半減期:20分)で標識したCO
濃度に対する転流率の応答を正確に評価することは技術的に困難であった。そこで本研究では、炭素11(半減期:20分)で標識したCO (
( CO
CO )とポジトロンイメージング技術を用いて、トマトの同一個体における異なるCO
)とポジトロンイメージング技術を用いて、トマトの同一個体における異なるCO 濃度での炭素動態をそれぞれ可視化し、CO
濃度での炭素動態をそれぞれ可視化し、CO 濃度の上昇に対する炭素の固定量と転流率の応答を解析した。まず、異なるCO
濃度の上昇に対する炭素の固定量と転流率の応答を解析した。まず、異なるCO 濃度の環境下でトマト(Micro-Tom)に
濃度の環境下でトマト(Micro-Tom)に CO
CO をパルス投与する実験システムを開発した。本実験システムを用いて、400, 1,500, 3,000ppmのCO
をパルス投与する実験システムを開発した。本実験システムを用いて、400, 1,500, 3,000ppmのCO 濃度の環境に曝されたトマトにおける
濃度の環境に曝されたトマトにおける C-光合成産物の動態画像を取得した。3段階のCO
C-光合成産物の動態画像を取得した。3段階のCO 濃度の環境に曝された6個体のトマトにおける動態画像を解析したところ、炭素固定量はCO
濃度の環境に曝された6個体のトマトにおける動態画像を解析したところ、炭素固定量はCO 濃度の上昇と共に単調に増加していたが、果実への炭素移行量は1,500ppmで飽和に達していた。果実への転流率(移行量/固定量)については、個体間で大きなばらつきが見られたものの、CO
濃度の上昇と共に単調に増加していたが、果実への炭素移行量は1,500ppmで飽和に達していた。果実への転流率(移行量/固定量)については、個体間で大きなばらつきが見られたものの、CO 濃度の上昇に伴って減少する傾向が認められた。
濃度の上昇に伴って減少する傾向が認められた。
石井 里美; 山崎 治明*; 鈴井 伸郎; 尹 永根; 河地 有木; 島田 浩章*; 藤巻 秀
no journal, ,
トマトの生産性の向上のためには、温室等で栽培環境を制御し、炭素栄養の転流率を増加させる必要がある。このために、高濃度のCO を施用する方法が用いられているが、二酸化炭素濃度に対する転流率の応答を定量的に評価することは技術的に困難であった。そこで、本研究では、炭素11(半減期: 20分)で標識した二酸化炭素とポジトロンイメージング技術を用いて、同一個体のトマトにおける異なる二酸化炭素濃度での炭素動態を可視化し、二酸化炭素濃度の上昇に対する炭素の固定量と転流率の応答を解析した。
を施用する方法が用いられているが、二酸化炭素濃度に対する転流率の応答を定量的に評価することは技術的に困難であった。そこで、本研究では、炭素11(半減期: 20分)で標識した二酸化炭素とポジトロンイメージング技術を用いて、同一個体のトマトにおける異なる二酸化炭素濃度での炭素動態を可視化し、二酸化炭素濃度の上昇に対する炭素の固定量と転流率の応答を解析した。