Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
吉田 一雄; 桧山 美奈*; 玉置 等史
JAEA-Research 2025-003, 24 Pages, 2025/06
再処理施設の過酷事故の一つである高レベル放射性廃液貯槽の冷却機能喪失による蒸発乾固事故では、沸騰により廃液貯槽から発生する硝酸-水混合蒸気とともにルテニウム(RuO )の揮発性の化学種が放出される。このためリスク評価の観点からは、Ruの定量的な放出量の評価が重要な課題である。揮発性Ruは施設内を移行する過程で床面に停留するプール水中の亜硝酸によって化学吸収が促進されることが想定され、施設内の硝酸-水混合蒸気の凝縮水量がRuの施設内での移行に重要な役割を担う。当該事故の施設内の熱流動解析では、水の熱流動を解析対象とするMELCORコードを用いている。解析では、凝縮の支配因子である蒸発潜熱が、事故時での施設内の温度帯域で同程度であることから硝酸をモル数が等しい水として扱っている。本報では、この解析モデルの妥当性を確認するために、MELCORの制御関数機能を用いて硝酸-水混合蒸気を水蒸気で近似することによって生じる誤差を補正する解析モデルを作成し解析を実施し補正効果を比較することで従来の解析モデルの妥当性を確認した。その結果、補正解析モデルの適用によって各区画のプール水量の分布は変化するものの施設内のプール水量の総和には影響しないことを確認した。
)の揮発性の化学種が放出される。このためリスク評価の観点からは、Ruの定量的な放出量の評価が重要な課題である。揮発性Ruは施設内を移行する過程で床面に停留するプール水中の亜硝酸によって化学吸収が促進されることが想定され、施設内の硝酸-水混合蒸気の凝縮水量がRuの施設内での移行に重要な役割を担う。当該事故の施設内の熱流動解析では、水の熱流動を解析対象とするMELCORコードを用いている。解析では、凝縮の支配因子である蒸発潜熱が、事故時での施設内の温度帯域で同程度であることから硝酸をモル数が等しい水として扱っている。本報では、この解析モデルの妥当性を確認するために、MELCORの制御関数機能を用いて硝酸-水混合蒸気を水蒸気で近似することによって生じる誤差を補正する解析モデルを作成し解析を実施し補正効果を比較することで従来の解析モデルの妥当性を確認した。その結果、補正解析モデルの適用によって各区画のプール水量の分布は変化するものの施設内のプール水量の総和には影響しないことを確認した。
吉田 一雄; 桧山 美奈*; 玉置 等史
JAEA-Research 2024-007, 24 Pages, 2024/08
再処理施設の過酷事故の一つである高レベル放射性廃液貯槽の冷却機能喪失による蒸発乾固事故では、沸騰により廃液貯槽から発生する硝酸-水混合蒸気とともにルテニウム(Ru)の揮発性の化学種(RuO )が放出される。このためリスク評価の観点からは、Ruの定量的な放出量の評価が重要な課題である。RuO
)が放出される。このためリスク評価の観点からは、Ruの定量的な放出量の評価が重要な課題である。RuO の発生現象には、廃液の溶媒である硝酸の放射線分解で発生する亜硝酸が沸騰段階でのRuO
の発生現象には、廃液の溶媒である硝酸の放射線分解で発生する亜硝酸が沸騰段階でのRuO の発生を抑制することが実験的に示されている。この現象を解析的に取り扱うには、廃液の当該事故時の硝酸及び亜硝酸を含めた窒素化合物の化学変化の解析が必要となる。廃液貯槽沸騰模擬コード:SHAWEDでは、硝酸-水-FP硝酸塩系での気液平衡の仮定に基づき廃液の温度上昇、硝酸及び水の蒸発量、気泡破裂に伴う飛沫生成量を計算する。現状の解析では、廃液中の亜硝酸濃度等の変化を模擬できない。より現象に即した模擬を可能にするため当該事故時の施設内の化学的な挙動を解析するSCHERNをSHAWEDと結合させ、放射線分解による亜硝酸の生成も考慮した廃液貯槽内の熱流動挙動解析及び化学挙動解析を同時に可能とするよう改良した。本報では、両計算コードを結合した計算の流れ、両者間でのデータの授受を概説し模擬結果の一例を示す。
の発生を抑制することが実験的に示されている。この現象を解析的に取り扱うには、廃液の当該事故時の硝酸及び亜硝酸を含めた窒素化合物の化学変化の解析が必要となる。廃液貯槽沸騰模擬コード:SHAWEDでは、硝酸-水-FP硝酸塩系での気液平衡の仮定に基づき廃液の温度上昇、硝酸及び水の蒸発量、気泡破裂に伴う飛沫生成量を計算する。現状の解析では、廃液中の亜硝酸濃度等の変化を模擬できない。より現象に即した模擬を可能にするため当該事故時の施設内の化学的な挙動を解析するSCHERNをSHAWEDと結合させ、放射線分解による亜硝酸の生成も考慮した廃液貯槽内の熱流動挙動解析及び化学挙動解析を同時に可能とするよう改良した。本報では、両計算コードを結合した計算の流れ、両者間でのデータの授受を概説し模擬結果の一例を示す。
吉田 一雄; 玉置 等史; 桧山 美奈*
JAEA-Research 2023-001, 26 Pages, 2023/05
再処理施設の過酷事故の一つである高レベル放射性廃液貯槽の冷却機能喪失による蒸発乾固事故では、沸騰により廃液貯槽から発生する硝酸-水混合蒸気とともにルテニウム(Ru)の揮発性の化学種が放出される。このためリスク評価の観点からは、Ruの定量的な放出量の評価が重要な課題である。再処理施設のリスク評価の精度向上に資するため、計算プログラムを用いて当該事故時でのソースタームを解析的に評価する手法の整備を進めている。提案する解析手法では、まず廃液貯槽の沸騰をSHAWEDで模擬する。模擬結果の蒸気発生量等を境界条件としてMELCORにより施設内の蒸気等の流れに沿って各区画内の熱流動状態を模擬する。さらに各区画内の熱流動状態を境界条件としてSCHERNを用いてRuを含む硝酸、NO 等の化学挙動を模擬し、施設外への放射性物質の移行量(ソースターム)を求める。本報では、仮想の実規模施設での当該事故を想定して、これら3つの計算プログラム間でのデータの授受を含めて解析事例を示す。
等の化学挙動を模擬し、施設外への放射性物質の移行量(ソースターム)を求める。本報では、仮想の実規模施設での当該事故を想定して、これら3つの計算プログラム間でのデータの授受を含めて解析事例を示す。
吉田 一雄; 玉置 等史; 桧山 美奈*
JAEA-Research 2022-011, 37 Pages, 2022/12
再処理施設の過酷事故の一つとして高レベル放射性廃液貯槽の冷却機能喪失による蒸発乾固事故が想定される。再処理廃液の沸騰段階での放射性物質の気相部への移行のメカニズムは、沸騰によって生成される飛沫のうち比較的小さい粒径の液滴のエアロゾル化と、揮発性化学種の温度上昇に伴う気化である。気相に移行した放射性物質は、沸騰により発生する硝酸-水混合蒸気や硝酸塩の熱分解による脱硝反応で生じるNO などとともに貯槽から流出し、施設内を移行し一部は施設外に放出されると想定される。当該事故で生じるこれらの諸事象は、すべて貯槽内の廃液の沸騰を起源とするため、それによって生じるリスクを精度良く評価するには、汎用性のある計算プログラムを用いた貯槽内の熱水力的及び化学的挙動の定量的な模擬が不可欠である。これを目的として再処理廃液の沸騰を模擬する計算プログラム: SHAWED (
などとともに貯槽から流出し、施設内を移行し一部は施設外に放出されると想定される。当該事故で生じるこれらの諸事象は、すべて貯槽内の廃液の沸騰を起源とするため、それによって生じるリスクを精度良く評価するには、汎用性のある計算プログラムを用いた貯槽内の熱水力的及び化学的挙動の定量的な模擬が不可欠である。これを目的として再処理廃液の沸騰を模擬する計算プログラム: SHAWED ( imulation of
imulation of  igh-level radio
igh-level radio ctive
ctive  aste
aste  vaporation and
vaporation and  ryness)を開発した。本報では、当該事故のリスク評価に資するために、模擬対象とする事象の特徴をもとに沸騰及びそれに伴う諸事象の模擬に必要な主要な解析モデルを説明するとともに、具体的な模擬事例を示す。
ryness)を開発した。本報では、当該事故のリスク評価に資するために、模擬対象とする事象の特徴をもとに沸騰及びそれに伴う諸事象の模擬に必要な主要な解析モデルを説明するとともに、具体的な模擬事例を示す。
片岡 龍峰*; 佐藤 達彦; 加藤 千尋*; 門倉 昭*; 小財 正義*; 三宅 晶子*; 村瀬 清華*; 吉田 理人*; 冨川 喜弘*; 宗像 一起*
Journal of Space Weather and Space Climate (Internet), 12, p.37_1 - 37_11, 2022/11
被引用回数:3 パーセンタイル:28.94(Astronomy & Astrophysics)2019 2020年の太陽活動極小期における銀河宇宙線の変動は、2次中性子及びミューオンで異なる傾向を示す。その違いの原因を明らかにするため、Echo State Network (ESN)と呼ばれる機械学習法を用いて、中性子モニタ及びミューオン検出器計数率から周辺環境による依存性を取り除く補正方法を構築した。その結果、周辺環境の影響を補正した後であっても、ミューオン検出器の計数率は2019年後半から減少し始め、その年の前半から減少し始めていた中性子モニタの計数率とは異なる傾向を示すことが確認できた。この結果は、太陽活動による宇宙線フラックスの変動が、そのリジディティに依存していることを示唆している。
2020年の太陽活動極小期における銀河宇宙線の変動は、2次中性子及びミューオンで異なる傾向を示す。その違いの原因を明らかにするため、Echo State Network (ESN)と呼ばれる機械学習法を用いて、中性子モニタ及びミューオン検出器計数率から周辺環境による依存性を取り除く補正方法を構築した。その結果、周辺環境の影響を補正した後であっても、ミューオン検出器の計数率は2019年後半から減少し始め、その年の前半から減少し始めていた中性子モニタの計数率とは異なる傾向を示すことが確認できた。この結果は、太陽活動による宇宙線フラックスの変動が、そのリジディティに依存していることを示唆している。
山口 晃範*; 横塚 宗之*; 古田 昌代*; 久保田 和雄*; 藤根 幸雄*; 森 憲治*; 吉田 尚生; 天野 祐希; 阿部 仁
日本原子力学会和文論文誌(インターネット), 21(4), p.173 - 182, 2022/09
確率論的リスク評価(PRA)から得られるリスク情報は、原子力施設におけるシビアアクシデント対策の有効性を評価するために有用である。再処理施設に対するPRA手法は原子力発電所のそれと比べて未成熟と考えられ、本手法を成熟させるためには事故シナリオの不確実性を低減することが重要となる。本論文では、再処理施設におけるシビアアクシデントである高レベル廃液の沸騰による蒸発乾固への事象進展と、それに伴う放射性物質の移動挙動に関する文献調査の結果をまとめた。Ruの重要な特徴の一つは、事象進展の過程で揮発性化合物を形成することであり、本稿ではその移動挙動を温度に基づいて4段階に分類した。高温まで至った乾固物からはRuは放出されない一方、Csのような他の揮発性元素が放出される可能性がある。実験データは未だに不十分な状態であり、放射性物質の移行挙動の温度依存性を明らかにすることが求められる。
近藤 恭弘; 北村 遼; 不破 康裕; 森下 卓俊; 守屋 克洋; 高柳 智弘; 大谷 将士*; Cicek, E.*; 恵郷 博文*; 深尾 祥紀*; et al.
Proceedings of 31st International Linear Accelerator Conference (LINAC 2022) (Internet), p.636 - 641, 2022/09
J-PARCにおいて、現代の素粒子物理学で最も重要な課題の一つである、ミューオン異常磁気モーメント、電気双極子モーメントを精密測定する実験のためのミューオンリニアック計画が進行中である。J-PARCミューオン施設からのミューオンはいったん室温まで冷却され、212MeVまで加速される。横エミッタンスは1.5 mm mradであり、運動量分散は1%である。高速で規格化した粒子の速度で0.01から0.94におよぶ広い範囲で効率よく加速するため、4種類の加速構造が用いられる。計画は建設段階に移行しつつあり、初段の高周波四重極リニアックによるミューオン再加速はすでに2017年に実証済である。次段の交差櫛形Hモードドリフトチューブリニアックのプロトタイプによる大電力試験が完了し、ディスクアンドワッシャ型結合セルリニアックの第一モジュールの製作が進行中である。さらに円盤装荷型加速管の設計もほぼ終了した。本論文ではこれらミューオンリニアックの最近の進捗について述べる。
mm mradであり、運動量分散は1%である。高速で規格化した粒子の速度で0.01から0.94におよぶ広い範囲で効率よく加速するため、4種類の加速構造が用いられる。計画は建設段階に移行しつつあり、初段の高周波四重極リニアックによるミューオン再加速はすでに2017年に実証済である。次段の交差櫛形Hモードドリフトチューブリニアックのプロトタイプによる大電力試験が完了し、ディスクアンドワッシャ型結合セルリニアックの第一モジュールの製作が進行中である。さらに円盤装荷型加速管の設計もほぼ終了した。本論文ではこれらミューオンリニアックの最近の進捗について述べる。
吉田 一雄; 玉置 等史; 桧山 美奈*
JAEA-Research 2021-013, 20 Pages, 2022/01
再処理施設の過酷事故の一つである高レベル放射性廃液貯槽の冷却機能喪失による蒸発乾固事故では、沸騰により廃液貯槽から発生する硝酸-水混合蒸気とともにルテニウム(Ru)の揮発性の化学種が放出される。そのための事故対処策の一つとして貯槽から発生する混合蒸気を積極的に凝縮する凝縮器の設置案が示されている。この事故対策では、硝酸蒸気の拡散防止、Ruの除去率の向上などが期待できる。本報では、実規模の仮想的な再処理施設を対象に凝縮器を設けて施設内での蒸気及びRuの移行挙動の模擬を試行した。模擬解析では、MELCORを用いて施設内の熱流動解析を行い、得られた熱流動状態を境界条件として硝酸、窒素酸化物等の化学挙動を解析するSCHERNコードを用いてRuの定量的な移行挙動を模擬した。解析から、凝縮器による蒸気拡散防止及びRuの除去効率の向上効果を定量的に分析するとともに、凝縮器の解析モデル上の課題を明らかにすることができた。
草野 完也*; 一本 潔*; 石井 守*; 三好 由純*; 余田 成男*; 秋吉 英治*; 浅井 歩*; 海老原 祐輔*; 藤原 均*; 後藤 忠徳*; et al.
Earth, Planets and Space (Internet), 73(1), p.159_1 - 159_29, 2021/12
被引用回数:7 パーセンタイル:38.33(Geosciences, Multidisciplinary)PSTEPとは、2015年4月から2020年3月まで日本国内の太陽・地球惑星圏に携わる研究者が協力して実施した科研費新学術領域研究である。この研究枠組みから500以上の査読付き論文が発表され、様々なセミナーやサマースクールが実施された。本論文では、その成果をまとめて報告する。
 の化学挙動を考慮したRuの移行挙動解析
の化学挙動を考慮したRuの移行挙動解析吉田 一雄; 玉置 等史; 桧山 美奈*
JAEA-Research 2021-005, 25 Pages, 2021/08
再処理施設の過酷事故の一つである高レベル放射性廃液貯槽の冷却機能喪失による蒸発乾固事故では、沸騰により廃液貯槽から発生する硝酸-水混合蒸気とともにルテニウム(Ru)の揮発性の化学種が放出される。このためリスク評価の観点からは、Ruの定量的な放出量の評価が重要な課題である。課題解決に向け当該施設での蒸気凝縮を伴う環境でのRuの移行挙動に係る小規模実験のデータ分析の結果から気液界面でのRuの物質移行係数の相関式を導出した。この相関式を用いて実規模の仮想的な再処理施設を対象に施設内でのRuの移行挙動の模擬を試行した。解析では、窒素酸化物の化学挙動を解析するSCHERNコードにこの相関式を組み込み、施設内の熱流動解析で得られた条件を境界条件としてRuの定量的な移行挙動を模擬し、その有効性を確認した。
吉田 一雄; 玉置 等史; 桧山 美奈*
JAEA-Data/Code 2021-008, 35 Pages, 2021/08
再処理施設で想定される重大事故の一つに高レベル廃液貯槽の蒸発乾固事故がある。高レベル廃液には、再処理の過程で取り除かれた核分裂生成物の硝酸塩が含まれ、それらの崩壊熱で発熱するため常時冷却する必要がある。このため全電源の喪失などにより冷却機能が全喪失した状態が継続した場合、廃液が沸騰しいずれ乾固する。この間、ルテニウムの揮発性化学種が硝酸-水混合蒸気とともに気相へ移行し、施設外へ放出される可能性がある。乾固時には、廃液に含まれる硝酸塩の熱分解による脱硝反応が進行しNO ガスが発生する。NO
ガスが発生する。NO はルテニウムの施設内での移行挙動に影響することが実験的に確認されており、硝酸及び水が共存する環境では気液各相で複雑に化学変化することが知られている。そこで建屋区画内での熱流動条件を境界条件としてRuを含む各化学種の濃度変化を解析する計算プログラム: SCHERNの開発を進めている。本報は、SCHERN-V2として新たに整備した解析モデルを含め、当該プログラムが解析対象とする事故の概要、解析モデル、連立微分方程式、使い方等を説明する解説書である。
はルテニウムの施設内での移行挙動に影響することが実験的に確認されており、硝酸及び水が共存する環境では気液各相で複雑に化学変化することが知られている。そこで建屋区画内での熱流動条件を境界条件としてRuを含む各化学種の濃度変化を解析する計算プログラム: SCHERNの開発を進めている。本報は、SCHERN-V2として新たに整備した解析モデルを含め、当該プログラムが解析対象とする事故の概要、解析モデル、連立微分方程式、使い方等を説明する解説書である。
丸山 結; 吉田 一雄
日本原子力学会誌ATOMO , 63(7), p.517 - 522, 2021/07
, 63(7), p.517 - 522, 2021/07
確率論的リスク評価(PRA)は合理的かつ定量的にリスクを評価する強力な手法である。しかしながら、PRAを実践しつつ、得られた結果を分析し、様々な意思決定に活用する上では、多様な分野の専門的な知識や技術,経験を必要とする。原子力施設のリスク評価においては、シビアアクシデントに至る過程やその進展を評価することが不可欠であり、それらに強く関連する熱流動は、PRAにおける重要な専門分野の一つである。本稿では、軽水炉のレベル2PRAにおけるソースターム評価及び再処理施設のシビアアクシデント時ソースターム評価を中心に、リスク評価における熱流動解析の役割について概説する。
北里 宏平*; Milliken, R. E.*; 岩田 隆浩*; 安部 正真*; 大竹 真紀子*; 松浦 周二*; 高木 靖彦*; 中村 智樹*; 廣井 孝弘*; 松岡 萌*; et al.
Nature Astronomy (Internet), 5(3), p.246 - 250, 2021/03
被引用回数:60 パーセンタイル:96.18(Astronomy & Astrophysics)2019年4月「はやぶさ2」ミッションは、地球に近い炭素質の小惑星(162173)リュウグウの人工衝撃実験を成功させた。これは露出した地下物質を調査し、放射加熱の潜在的な影響をテストする機会を提供した。はやぶさ2の近赤外線分光器(NIRS3)によるリュウグウの地下物質の観測結果を報告する。発掘された材料の反射スペクトルは、表面で観測されたものと比較して、わずかに強くピークがシフトした水酸基(OH)の吸収を示す。これは、宇宙風化や放射加熱が最上部の表面で微妙なスペクトル変化を引き起こしたことを示している。ただし、このOH吸収の強度と形状は、表面と同様に、地下物質が300 Cを超える加熱を経験したことを示している。一方、熱物理モデリングでは、軌道長半径が0.344AUに減少しても、推定される掘削深度1mでは放射加熱によって温度が200
Cを超える加熱を経験したことを示している。一方、熱物理モデリングでは、軌道長半径が0.344AUに減少しても、推定される掘削深度1mでは放射加熱によって温度が200 Cを超えて上昇しないことが示されている。これは、リュウグウ母天体が放射加熱と衝撃加熱のいずれか、もしくは両方により熱変化が発生したという仮説を裏付けている。
Cを超えて上昇しないことが示されている。これは、リュウグウ母天体が放射加熱と衝撃加熱のいずれか、もしくは両方により熱変化が発生したという仮説を裏付けている。
角田 直文*; 大塚 孝治; 高柳 和雄*; 清水 則孝*; 鈴木 俊夫*; 宇都野 穣; 吉田 聡太*; 上野 秀樹*
Nature, 587, p.66 - 71, 2020/11
被引用回数:68 パーセンタイル:94.99(Multidisciplinary Sciences)与えられた陽子数に対し、どれだけの中性子数の原子核が存在可能であるかという問いは、原子核物理における最も基本的な問題の一つである。原子核は独立粒子描像がよく成り立つため、従来は陽子数で決まるポテンシャルが作る束縛状態の個数で決まると考えられてきた。この研究では、最近実験で確定した、フッ素からナトリウムに対する中性子ドリップ線(最も中性子数の多い同位体)を、核力から出発した第一原理的な大規模殻模型計算によって再現し、そのメカニズムを理論的に解析した。ハミルトニアンを単極相互作用と多重極相互作用に分解し、さらに多重極相互作用を対相互作用と残りの部分に分け、基底状態におけるそれぞれの項の寄与を調べた。その結果、多重極相互作用の変形エネルギーに相当する部分が中性子ドリップ線を決めるのに非常に重要な役割を果たしていることがわかった。すなわち、中性子数が増えていくと徐々に変形エネルギーが増大するものの、ある中性子数でそれが飽和し、その後は減少していくが、その減少過程で中性子ドリップ線が決まるというシナリオである。本研究は、ドリップ線に対する新しい見方を与え、天体中の元素合成過程の理解に重要な貢献をすることが期待される。
吉田 一雄
エネルギーレビュー, 40(4), p.19 - 20, 2020/03
核燃料施設では、様々な事故が想定される。このようなリスクの特徴を踏まえ、我が国ではリスク情報の活用に向けてリスク評価手法及び評価のために必要な基礎的データの整備が積極的に進められてきた。リスク評価の実施基準では、リスクのレベルに応じた詳細さの評価を行う「Graded Approach」の考え方に基づき、比較的簡略な手法による「概略的なリスク評価」と、発電炉のPRAに準じた「詳細なリスク評価」の組み合わせが採用されている。核燃料施設の事故は発電炉に比べると公衆への影響としては比較的小さいと考えられ、リスク情報は安全設備の設計や運転管理の計画を支援するために使われるべきものと考える。英国,米国において核燃料施設のリスク評価は、安全対策に抜け落ちや弱点がないか確認すること等を目的として利用されている。我が国の規制でのリスク情報の活用として安全性向上評価の実施が求められている。さらに検査制度の見直しも進められている。今後は、安全を確保する上でリスク評価の意義が正しく理解され実務の中に定着していくことが重要であり、安全性向上や新検査制度での活用をうまく進めることが、その鍵になると考えられる。
中沢 雄河*; 飯沼 裕美*; 岩田 佳之*; 岩下 芳久*; 大谷 将士*; 河村 成肇*; 三部 勉*; 山崎 高幸*; 吉田 光宏*; 北村 遼; et al.
Journal of Physics; Conference Series, 1350, p.012054_1 - 012054_7, 2019/12
被引用回数:7 パーセンタイル:94.56(Physics, Particles & Fields)J-PARC E34実験用の交差櫛形Hモードドリフトチューブリニアック(IH-DTL)を開発している。このIH-DTLはミューオンを0.34MeVから4.5MeVまで加速周波数324MHzで加速する。さらに、交換収束法を用いるため、横方向の収束が電場のみでなされ、磁場収束に比べて収束力が弱い。そのため、入射マッチングが重要になる。そのためプロトタイプを製作し、ビーム特性を検証する計画である。この論文では、IH-DTLプロトタイプのためのチューナーやカップラーの開発、特に低電力測定結果について述べる。
桧山 美奈*; 玉置 等史; 吉田 一雄
JAEA-Data/Code 2019-006, 17 Pages, 2019/07
再処理施設で想定される重大事故の一つに高レベル廃液貯槽の蒸発乾固事故がある。高レベル廃液には、再処理の過程で取り除かれた核分裂生成物の硝酸塩が含まれ、それらの崩壊熱で発熱するため常時冷却する必要がある。このため全電源の喪失などにより冷却機能が全喪失した状態が継続した場合、廃液が沸騰しいずれ乾固する。この間、ルテニウムの揮発性化学種が硝酸-水混合蒸気とともに気相へ移行し、施設外へ放出される可能性がある。乾固時には、廃液に含まれる硝酸塩の熱分解による脱硝反応が進行しNOxガスが発生する。NOxはルテニウムの施設内での移行挙動に大きく影響することが実験的に確認されており、硝酸及び水が共存する環境では気液各相で複雑に化学変化することが知られている。そこで建屋区画内での熱流動条件を境界条件として各化学種の濃度変化を解析する計算プログラムを開発した。
中沢 雄河*; 飯沼 裕美*; 岩下 芳久*; 岩田 佳之*; 大谷 将士*; 河村 成肇*; 北村 遼; 近藤 恭弘; 齊藤 直人; 須江 祐貴*; et al.
Proceedings of 16th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan (インターネット), p.404 - 407, 2019/07
J-PARCミューオンg-2/EDM精密測定実験を実現するためのミューオン線形加速器の1つであるAPF方式IH-DTLのプロトタイプでは、ミューオンを =0.08から0.15まで加速するために運転周波数324MHzが採用された。加速性能を満たすためには60kWの高周波電力を投入する必要がある。ビーム電流はほぼゼロかつデューティーが0.25%と低いことから、構造を単純化するために一台のRF入力カップラーを介して電力を投入する。カップラーは同軸導波管をベースに設計し、空洞との整合にはループアンテナを用いる。ループアンテナを空洞に挿入した場合、インピーダンス不整合や空洞内の電磁場歪みにより、加速性能が低下する恐れがある。電磁場歪みを抑制するためにループアンテナの挿入量を必要最低限にしつつ、空洞との電力反射が最小(VSWR(電圧定在波比)
=0.08から0.15まで加速するために運転周波数324MHzが採用された。加速性能を満たすためには60kWの高周波電力を投入する必要がある。ビーム電流はほぼゼロかつデューティーが0.25%と低いことから、構造を単純化するために一台のRF入力カップラーを介して電力を投入する。カップラーは同軸導波管をベースに設計し、空洞との整合にはループアンテナを用いる。ループアンテナを空洞に挿入した場合、インピーダンス不整合や空洞内の電磁場歪みにより、加速性能が低下する恐れがある。電磁場歪みを抑制するためにループアンテナの挿入量を必要最低限にしつつ、空洞との電力反射が最小(VSWR(電圧定在波比) 1)となるようにループアンテナを最適化する必要がある。我々はループを最適化するためのテストカップラーを用いた低電力試験を行うことで、VSWR=1.01かつ電磁場歪みを7%以内に抑制するループ形状を確認した。本発表では、テストカップラーによるループアンテナの最適化の結果を報告すると共に、実機カップラー開発に向けた高周波窓の設計について述べる。
1)となるようにループアンテナを最適化する必要がある。我々はループを最適化するためのテストカップラーを用いた低電力試験を行うことで、VSWR=1.01かつ電磁場歪みを7%以内に抑制するループ形状を確認した。本発表では、テストカップラーによるループアンテナの最適化の結果を報告すると共に、実機カップラー開発に向けた高周波窓の設計について述べる。
吉田 一雄; 玉置 等史; 吉田 尚生; 吉田 涼一朗; 天野 祐希; 阿部 仁
日本原子力学会和文論文誌, 18(2), p.69 - 80, 2019/06
再処理施設で想定される重大事故の一つに高レベル廃液貯槽の蒸発乾固事故がある。高レベル廃液には、再処理で取り除かれた核分裂生成物の硝酸塩が含まれ、それらの崩壊熱で発熱するため常時冷却する必要がある。このため全電源の喪失により冷却機能が全喪失した状態が継続した場合、廃液が沸騰しいずれ乾固する。乾固時には、廃液に含まれる硝酸塩の熱分解による脱硝反応が進行しNOxガスが発生する。本報では、硝酸-水混合蒸気系の雰囲気でのNOx系の化学種の化学変化をレビューし、それに基づき再処理施設の高レベル廃液の蒸発乾固事故での建屋区画内での熱流動及び各化学種の濃度変化の解析モデルを提案し、実規模体系での解析を試行した結果を示す。その結果を基にRuの施設外への移行量評価の高度化に向けた課題を提言する。
阿部 充志*; Bae, S.*; Beer, G.*; Bunce, G.*; Choi, H.*; Choi, S.*; Chung, M.*; da Silva, W.*; Eidelman, S.*; Finger, M.*; et al.
Progress of Theoretical and Experimental Physics (Internet), 2019(5), p.053C02_1 - 053C02_22, 2019/05
被引用回数:161 パーセンタイル:99.30(Physics, Multidisciplinary)この論文はJ-PARCにおける、ミューオン異常磁気モーメント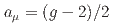 と電気双極子モーメント(EDM)
と電気双極子モーメント(EDM)  を測定する新しいアプローチを紹介する。我々の実験のゴールは、これまでと独立の、1/10の運動量と1/20のストレージリングを用いて、
を測定する新しいアプローチを紹介する。我々の実験のゴールは、これまでと独立の、1/10の運動量と1/20のストレージリングを用いて、 と
と をこれまでにない精密な磁場で測定することである。さらに過去の実験との顕著な違いは、1/1000の横エミッタンスミューオンビーム(サーマルミューオンビーム)を用い、効率的なソレノイドへ縦入射し、ミューオンからの崩壊陽電子をトラッキングし、その小さな運動量ベクトルを求める点である。
をこれまでにない精密な磁場で測定することである。さらに過去の実験との顕著な違いは、1/1000の横エミッタンスミューオンビーム(サーマルミューオンビーム)を用い、効率的なソレノイドへ縦入射し、ミューオンからの崩壊陽電子をトラッキングし、その小さな運動量ベクトルを求める点である。 は統計精度450ppb、系統誤差70ppb、EDMについては
は統計精度450ppb、系統誤差70ppb、EDMについては e
e cmの精度で測定することを目標とする。
cmの精度で測定することを目標とする。