Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
大沼 敏治*; 宮下 敦巳; 吉川 正人; 土田 秀一*; 岩沢 美佐子*
平成21年度先端研究施設共用促進事業「地球シミュレータ産業戦略利用プログラム」利用成果報告書, p.21 - 27, 2010/07
ワイドギャップ半導体である炭化珪素(SiC)は従来のシリコン(Si)半導体に比べて飛躍的な性能向上を実現するパワー半導体デバイスの材料として期待されている。また、SiC半導体デバイスは低損失の省エネデバイスとして開発が進められているとともに、Si半導体デバイスと同様に熱酸化により酸化絶縁膜を作製できるため、次世代のMOS型パワーデバイスとして有望である。しかし、従来のSiC MOS型パワーデバイスは、界面トラップの存在等によりチャネル移動度が理論的な予想値より遥かに小さく、優れた特性を発揮できていなかった。これらの特性を改善するためには、原子レベルで界面の構造と熱酸化の機構を明らかにすることが重要となる。SiCの熱酸化過程のシミュレーションにおいては、化学反応を伴うことと、界面においてさまざまな結合があることから、経験的なパラメータを一切用いない第一原理法が強力なツールとなるが、計算量が膨大なためこれまで行われてこなかった。地球シミュレータによる大規模な第一原理分子動力学計算によりSiCの熱酸化過程・アニーリング及び界面準位のシミュレーションが可能になったのでここに報告する。
Bian, Z.*; 石井 裕剛*; 下田 宏*; 吉川 榮和*; 森下 喜嗣; 兼平 宜紀; 泉 正憲
IEICE Transactions on Information and Systems, E90-D(6), p.963 - 974, 2007/06
被引用回数:4 パーセンタイル:32.88(Computer Science, Information Systems)拡張現実感技術とは、作業対象物上にコンピュータグラフィックスによる作業情報を重ねて表示(重畳表示)させる技術で、作業員に作業の直感的理解を促すことができる。原子力発電プラントの定期検査の際にこの拡張現実感技術を用いて、作業に関連する情報を提示すれば、ヒューマンエラーの防止と作業の効率が上がると期待される。拡張現実感技術の実現に際しては、正確な位置・方向で重畳表示させるために、ユーザと情報提示対象物との位置・方向を求めるトラッキング技術が重要である。これまでマーカを用いたさまざまなトラッキング手法が提案されているが、原子力発電プラントへの適用を想定した場合、放射線の影響により、安全上作業対象物からできるだけ離れた位置の場合でもマーカの認識とトラッキング精度を確保しなければならないことである。本研究では、新たなトラッキング手法として、原子力発電所に多数存在する配管に着目し、その特徴を考慮して、配管や機器などに比較的貼りやすい縦長のラインコードマーカを開発した。本マーカを使用することで、作業対象物からの距離を遠方にしてもマーカの認識を確保できるようにした。本研究では、マーカを開発し、その評価実験を実験室で実施した。その結果、ユーザと作業対象物との距離が約10mの場合でも、約20cmの誤差範囲で認識することができ、従来のマーカよりも遠方でマーカを認識できることが確認された。
 /SiC interface structure by the first-principles molecular dynamics simulation
/SiC interface structure by the first-principles molecular dynamics simulation宮下 敦巳; 大沼 敏治*; 岩沢 美佐子*; 土田 秀一*; 吉川 正人
Materials Science Forum, 556-557, p.521 - 524, 2007/00
SiCデバイスは宇宙や原子炉等の極限環境下で動作する素子として期待されている。しかしながら現状のSiCデバイスは理論的に予想されている性能を発揮しているとは言いがたい。その理由はSiCとその酸化膜であるSiO との界面に存在する欠陥が素子の性能を低下させているからだと考えられる。実デバイスにある界面欠陥構造を計算機シミュレーションで再現しようとするなら、現実の界面にあるようなアモルファスSiO
との界面に存在する欠陥が素子の性能を低下させているからだと考えられる。実デバイスにある界面欠陥構造を計算機シミュレーションで再現しようとするなら、現実の界面にあるようなアモルファスSiO /SiCの構造を計算機上に再現することが非常に重要となってくる。われわれは444原子からなる結晶/結晶界面構造を計算機上に構築し、それに対して加熱・急冷計算を行うことでアモルファスSiO
/SiCの構造を計算機上に再現することが非常に重要となってくる。われわれは444原子からなる結晶/結晶界面構造を計算機上に構築し、それに対して加熱・急冷計算を行うことでアモルファスSiO /SiC構造を生成した。加熱温度,加熱時間,急冷速度はそれぞれ4000K, 3ps, -1000K/psである。得られた界面構造のSiO
/SiC構造を生成した。加熱温度,加熱時間,急冷速度はそれぞれ4000K, 3ps, -1000K/psである。得られた界面構造のSiO 領域はバルクのアモルファスSiO
領域はバルクのアモルファスSiO 構造とよく適合し、界面におけるダングリングボンド欠陥も消滅していることが確かめられた。
構造とよく適合し、界面におけるダングリングボンド欠陥も消滅していることが確かめられた。
 /4H-SiC(0001) interface oxidation process; From first-principles
/4H-SiC(0001) interface oxidation process; From first-principles大沼 敏治*; 宮下 敦巳; 岩沢 美佐子*; 吉川 正人; 土田 秀一*
Materials Science Forum, 556-557, p.615 - 620, 2007/00
平面波近似とスーパーセルモデルを用い、SiO /4H-SiC(0001)酸化過程の第一原理分子動力学計算による動的シミュレーションを行った。反応の初期構造の生成には加熱・急冷法を用いた。この初期構造は界面ダングリングボンドのないSiO
/4H-SiC(0001)酸化過程の第一原理分子動力学計算による動的シミュレーションを行った。反応の初期構造の生成には加熱・急冷法を用いた。この初期構造は界面ダングリングボンドのないSiO /SiC構造である。酸化反応の引き金とするために、界面付近のSiC層に炭素空孔を導入した。酸化反応シミュレーションは界面付近の空隙に酸素分子を一つずつ置いて行くことによって行った。酸化反応シミュレーションは2500Kの下で行った。酸素分子は解離しSiO
/SiC構造である。酸化反応の引き金とするために、界面付近のSiC層に炭素空孔を導入した。酸化反応シミュレーションは界面付近の空隙に酸素分子を一つずつ置いて行くことによって行った。酸化反応シミュレーションは2500Kの下で行った。酸素分子は解離しSiO 中のSi原子と結合を組み、また、界面付近にいるSiC層中のSi原子も酸化されSiO
中のSi原子と結合を組み、また、界面付近にいるSiC層中のSi原子も酸化されSiO 層を形成した。界面欠陥の候補の一つと考えられている炭素クラスタ構造が界面に形成され、さらに、酸素分子は炭素クラスターと反応しCO分子を形成した。
層を形成した。界面欠陥の候補の一つと考えられている炭素クラスタ構造が界面に形成され、さらに、酸素分子は炭素クラスターと反応しCO分子を形成した。
 ドライ酸化膜中の界面欠陥の電気特性とその熱アニーリング効果
ドライ酸化膜中の界面欠陥の電気特性とその熱アニーリング効果吉川 正人; 石田 夕起*; 直本 保*; 土方 泰斗*; 伊藤 久義; 奥村 元*; 高橋 徹夫*; 土田 秀一*; 吉田 貞史*
電子情報通信学会論文誌, C, 86(4), p.426 - 433, 2003/04
1200 ドライ酸化やそれに引き続いて行われる熱アニーリングが、酸化膜と4積層周期六方晶炭化ケイ素(4H-SiC)基板の界面に与える影響を調べた。n型及びp型4H-SiC基板を1200
ドライ酸化やそれに引き続いて行われる熱アニーリングが、酸化膜と4積層周期六方晶炭化ケイ素(4H-SiC)基板の界面に与える影響を調べた。n型及びp型4H-SiC基板を1200 の乾燥酸素雰囲気中で3時間酸化して50nmの酸化膜を作製した後、酸化膜を500から950
の乾燥酸素雰囲気中で3時間酸化して50nmの酸化膜を作製した後、酸化膜を500から950 のアルゴン雰囲気中で3時間熱アニーリングした。その酸化膜を用いて金属/酸化膜/半導体(MOS)構造を形成してC-V特性を測定し、酸化膜と4H-SiC界面の電気特性に及ぼす熱アニーリング効果を調べた。1200
のアルゴン雰囲気中で3時間熱アニーリングした。その酸化膜を用いて金属/酸化膜/半導体(MOS)構造を形成してC-V特性を測定し、酸化膜と4H-SiC界面の電気特性に及ぼす熱アニーリング効果を調べた。1200 ドライ酸化膜を用いて形成した4H-SiC MOS構造のC-V特性は、電圧軸に沿って正方向へ大きくシフトした。界面には負電荷が蓄積していた。600
ドライ酸化膜を用いて形成した4H-SiC MOS構造のC-V特性は、電圧軸に沿って正方向へ大きくシフトした。界面には負電荷が蓄積していた。600 で3時間の熱アニーリングを行うとC-V特性が負方向へシフトしはじめ、950
で3時間の熱アニーリングを行うとC-V特性が負方向へシフトしはじめ、950 3時間の熱アニーリングで電圧シフトが消失した。一方、p型4H-SiC MOS構造のC-V特性を調べると、n型とは反対に電圧軸に沿って負方向へ大きくシフトした。界面には正電荷が蓄積していた。n型とp型のシフト方向の違いと界面欠陥の荷電状態の関連性について調べ、界面欠陥の熱アニーリングのメカニズムを議論した。
3時間の熱アニーリングで電圧シフトが消失した。一方、p型4H-SiC MOS構造のC-V特性を調べると、n型とは反対に電圧軸に沿って負方向へ大きくシフトした。界面には正電荷が蓄積していた。n型とp型のシフト方向の違いと界面欠陥の荷電状態の関連性について調べ、界面欠陥の熱アニーリングのメカニズムを議論した。
文沢 元雄; 亀田 晃之*; 中川 隆志*; Wu, W.*; 吉川 榮和*
Nuclear Technology, 141(1), p.78 - 87, 2003/01
被引用回数:5 パーセンタイル:36.13(Nuclear Science & Technology)原子炉運転制御盤の操作性の改善を図るため、運転員の行動様式に着目した、客観的データを検討することは重要である。原子炉運転員のヒューマンエラーを左右する主要なファクター(客観的データ)の1つにワークロードがある。ワークロードは運転員の身体的,精神的な負担の指標であり、本研究ではワークロードとして、移動距離,タスク実行時間,記憶量などを扱う。ワークロードの低減を図るには、原子炉制御盤(Human Machine Interfaces: HMI)を操作する運転員のワークロードを定量的並びに正確に評価する必要がある。本研究では、複数運転員(運転クルー)が操作する原子炉プラントのHMI設計を対象に、反復設計を効率的に実施するための計算機システム,SEAMAID(Simulation-based Evaluation and Analysis support system for MAn-machine Interface Design)を開発した。すなわち、HMI設計をワークロードという指標により評価するためのシステム開発を行った。併せて、CRT(記録計の監視可能なモニター)を旧来の制御盤に導入することで、運転員のワークロード(移動距離,視点移動距離など)がどの程度低減できる制御盤設計が可能であるかを検討した。
 interfaces by optical and electrical measurements
interfaces by optical and electrical measurements石田 夕起*; 高橋 徹夫*; 奥村 元*; 直本 保*; 土田 秀和*; 吉川 正人; 富岡 雄一*; 緑川 正彦*; 土方 泰斗*; 吉田 貞史*
Materials Science Forum, 389-393, p.1013 - 1016, 2002/00
被引用回数:5 パーセンタイル:23.54(Materials Science, Multidisciplinary)1200 の乾燥酸素中で作製した酸化膜と4H-SiC基板界面の光学並びに電気特性の関連性を、容量-電圧(CV)、分光エリプソ(SE)、フーリエ変換赤外(FTIR)測定法を用いて追求した。CV特性からは、1200
の乾燥酸素中で作製した酸化膜と4H-SiC基板界面の光学並びに電気特性の関連性を、容量-電圧(CV)、分光エリプソ(SE)、フーリエ変換赤外(FTIR)測定法を用いて追求した。CV特性からは、1200 の乾燥酸素中で作製した酸化膜内部に多量の界面準位と負電荷が存在することがわかった。同じ酸化膜をSEで測定したところ、界面近傍に極めて屈折率の高い界面中間層が存在することが明らかとなった。同じ部位をFTIRで測定すると、溶融石英に比べて結合角の小さいSi-O-Si結合が多数存在する可能性が示唆された。これらの結果から、金属/酸化膜/半導体(MOS)構造のCV特性を大きく変化させている原因は界面中間層にあり、界面中間層の正体は、不完全な酸化で生ずるSuboxide層であると結論された。
の乾燥酸素中で作製した酸化膜内部に多量の界面準位と負電荷が存在することがわかった。同じ酸化膜をSEで測定したところ、界面近傍に極めて屈折率の高い界面中間層が存在することが明らかとなった。同じ部位をFTIRで測定すると、溶融石英に比べて結合角の小さいSi-O-Si結合が多数存在する可能性が示唆された。これらの結果から、金属/酸化膜/半導体(MOS)構造のCV特性を大きく変化させている原因は界面中間層にあり、界面中間層の正体は、不完全な酸化で生ずるSuboxide層であると結論された。
福永 栄*; 吉川 英樹; 藤木 喜市*; 朝野 英一*
Materials Research Society Symposium Proceedings, Vol.353, p.173 - 180, 1995/00
処分場における微生物活動を推定する事を目的として硫酸塩還元菌の培養装置を設作し、耐性図を作成した。処分環境の高pH低Eh条件で菌の生存を初めて確認した。
間野 正; 吉川 英樹; 福永 栄*; 油井 三和; 山形 順二*; 朝野 英一*; 山中 裕美子*
PNC TN8410 94-117, 60 Pages, 1993/03
深地層においても微生物が存在する可能性があることから、放射性物質の地層処分の研究開発では、処分環境の変化や核種移行の評価に対し、微生物の影響を検討する必要がある。本研究は、処分場で微生物が活動するための条件のうち、環境への耐性を実験的に検討したものである。微生物としては、金属・コンクリート腐食への影響が心配される硫酸塩還元細菌を用いた。これをpHおよびEhが自動制御できる容量0.6-の培養容器に接種し、35 Cにて、pH7
Cにて、pH7 10.3、Eh-350
10.3、Eh-350 0mVの範囲内で条件設定して、硫化水素の発生を測定して硫酸塩還元細菌の増殖の有無を確認した。その結果、pHが7に近くEhが-300mVに近いほど増殖しやすいという耐性領域図(chartofactiverange)が得られた。pHは最大9.6(Eh-300mVのとき)まで、Ehは最大-100mV前後(pH7のとき)まで増殖が確かめられた。結論として、pH及びEhを制御した条件で耐性領域図を作る手法を確立した。また、硫酸塩還元細菌は処分場で想定されるpH及びEhの環境条件では増殖が可能なことが示された。
0mVの範囲内で条件設定して、硫化水素の発生を測定して硫酸塩還元細菌の増殖の有無を確認した。その結果、pHが7に近くEhが-300mVに近いほど増殖しやすいという耐性領域図(chartofactiverange)が得られた。pHは最大9.6(Eh-300mVのとき)まで、Ehは最大-100mV前後(pH7のとき)まで増殖が確かめられた。結論として、pH及びEhを制御した条件で耐性領域図を作る手法を確立した。また、硫酸塩還元細菌は処分場で想定されるpH及びEhの環境条件では増殖が可能なことが示された。
吉川 英樹; 油井 三和; 佐々木 憲明; 福永 栄*; 朝野 英一*; 若松 久夫*
PNC TN8410 92-013, 232 Pages, 1992/01
放射性廃棄物の地層処分では処分環境の変化や核種移行の評価において微生物の存在を考慮する必要があると言われているが、その具体的な挙動や影響については不明な部分が多い。そこで本テーマに関して、地層処分における微生物の挙動や影響に関する情報の整理、研究の現状、今後の課題などについて文献調査を行った。またあわせて関連する学会、講演会および海外の主要な原子力研究機関の研究内容についてアンケート調査を行った。本調査により、微生物の代謝活動に基づく材料の生物的な劣化、物理的な破壊、ガス生成、地下水の化学的特性の変化および核種の直接取り込みなどの作用が考えられ、それらが廃棄体やバリア材の劣化、処分場の化学的な環境の変化、放射性核種の移行などを通じて処分場の閉込め性能に影響することが明らかとなり研究の重要性が確認できた。また研究の進捗度について世界的な観点からの知見が得られた。
 /SiCモデルにおける界面構造
/SiCモデルにおける界面構造宮下 敦巳; 大沼 敏治*; 岩沢 美佐子*; 土田 秀一*; 吉川 正人
no journal, ,
Siに比べ優れた物理特性を持つSiCを用いた半導体デバイスは、従来のSiやGaAs半導体デバイスでは動作が困難な極限環境下で用いられる素子として期待されているが、SiCと酸化膜の界面にはSiCデバイス特性を劣化させる界面欠陥が多く存在しており、その欠陥構造とデバイス特性との関連性を追求することは非常に重要である。本研究では実際の界面を模擬した原子構造モデルを計算機上に生成し、電子状態が界面電気特性に与える影響を理論的側面から追求している。1017原子界面構造モデルに対して4000Kでの加熱及び-2000K/psの速度で室温までの急冷を行った結果、生成された界面構造モデルでは、従来の計算機モデルにおいて想定されていたような、Si原子が界面にある2つないしは3つのSi-O結合をまとめる構造以外にも、Si原子が一つのSi-O結合にのみ接続する構造ができていた。加えて従来モデルでは想定されていなかった、Siダングリングボンド,Si-Si結合,5配位Si等の欠陥構造が観察された。このような構造が界面に存在することで、界面でのO濃度の異常な上昇を抑えていると考えられる。
 /4H-SiC C面における酸化過程の動的シミュレーション; 温度の効果
/4H-SiC C面における酸化過程の動的シミュレーション; 温度の効果大沼 敏治*; 宮下 敦巳; 岩沢 美佐子*; 吉川 正人; 土田 秀一*
no journal, ,
ワイドギャップ半導体であるSiCはSi同様熱酸化により絶縁膜を作製できるため次世代のMOS型パワーデバイスとして有望である。しかしSiC/SiO 界面においては、Si/SiO
界面においては、Si/SiO 界面に比べて界面トラップ密度が高いことやMOSデバイスのチャンネル移動度が低いことが知られている。本報告では平面波基底のPAW法による第一原理分子動力学計算を行い実験温度である1500Kにおける熱酸化過程の動的シミュレーションを行った。計算は地球シミュレーターで行った。界面モデルはスラブモデルを用い、界面の初期構造は加熱及び急冷法により作成した。界面モデルは急峻かつダングリングボンドのない綺麗な界面を用いた。酸化過程のシミュレーションは酸素分子を一つずつ15psごとにSiO
界面に比べて界面トラップ密度が高いことやMOSデバイスのチャンネル移動度が低いことが知られている。本報告では平面波基底のPAW法による第一原理分子動力学計算を行い実験温度である1500Kにおける熱酸化過程の動的シミュレーションを行った。計算は地球シミュレーターで行った。界面モデルはスラブモデルを用い、界面の初期構造は加熱及び急冷法により作成した。界面モデルは急峻かつダングリングボンドのない綺麗な界面を用いた。酸化過程のシミュレーションは酸素分子を一つずつ15psごとにSiO 層に追加することにより行った。酸素分子はSiO
層に追加することにより行った。酸素分子はSiO 層中及びSiC界面のC原子と反応し解離した。解離した酸素原子はSiC界面のC原子を酸化するだけではなく、SiC層のSi原子も酸化した。2500Kにおいては一層ずつ酸化される単層酸化であったが1500KにおいてはC層とSi層の二層酸化により酸化が進むことがわかった。
層中及びSiC界面のC原子と反応し解離した。解離した酸素原子はSiC界面のC原子を酸化するだけではなく、SiC層のSi原子も酸化した。2500Kにおいては一層ずつ酸化される単層酸化であったが1500KにおいてはC層とSi層の二層酸化により酸化が進むことがわかった。
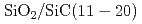 原子構造モデルにおける界面欠陥
原子構造モデルにおける界面欠陥宮下 敦巳; 大沼 敏治*; 土田 秀一*; 吉川 正人
no journal, ,
SiC半導体デバイスは、従来のデバイスでは動作が困難な極限環境でも使えるデバイスとして期待されている。SiC MOS-FETにおいては、ゲート酸化膜とSiC結晶との界面に多くの欠陥が存在しておりデバイス性能を劣化させているが、実験的にそれらを解析することは困難であるため、原子構造モデルを計算機上に生成することで欠陥準位の同定を目指している。近年、4H-SiC(11-20)面で非常に良いチャネル移動度が得られることが報告されたことから、計算機上で当該面上にアモルファスSiO (
( -SiO
-SiO )を生成し、その界面構造を調べた。まず、シリコン240個,炭素120個,酸素228個,水素48個を含む636原子による原子構造モデルに対して、4000K・2ps及び3500K・2psの加熱を行いSiO
)を生成し、その界面構造を調べた。まず、シリコン240個,炭素120個,酸素228個,水素48個を含む636原子による原子構造モデルに対して、4000K・2ps及び3500K・2psの加熱を行いSiO 層を溶融した後、-1000K/psの速度で室温までの急冷を行い、
層を溶融した後、-1000K/psの速度で室温までの急冷を行い、 -SiO
-SiO /4H-SiC(11-20)界面原子構造を生成した。SiO
/4H-SiC(11-20)界面原子構造を生成した。SiO 中にはSi及びCダングリングボンド、3配位のO等の欠陥が存在した。生成された原子構造の状態密度を解析した結果、3配位Oの近傍のSi、及び、sp
中にはSi及びCダングリングボンド、3配位のO等の欠陥が存在した。生成された原子構造の状態密度を解析した結果、3配位Oの近傍のSi、及び、sp 結合を持つSiからの欠陥準位が伝導帯下端付近に存在していることが確認された。
結合を持つSiからの欠陥準位が伝導帯下端付近に存在していることが確認された。
 /SiC界面構造の第一原理計算による生成
/SiC界面構造の第一原理計算による生成宮下 敦巳; 大沼 敏治*; 岩沢 美佐子*; 吉川 正人; 土田 秀一*
no journal, ,
Siに比べ優れた物理特性を持つSiCを用いた半導体デバイスは、従来のSiやGaAs半導体デバイスでは動作が困難な、原子炉や宇宙環境等,極限環境下で用いられる素子として期待されている。しかしながら、SiCの酸化膜とSiCの界面には、SiCデバイスのチャネル移動度低下の原因となる界面欠陥が多く存在しており、その構造とデバイス特性との関連性を追求することは非常に重要である。本研究では実際の界面に近い状態の原子構造を計算機上で生成し、その電子状態が界面電気特性に与える影響を追求している。実際のデバイス絶縁膜を模擬するために、加熱・急冷計算によりアモルファスSiO /SiC界面構造を計算機上に構築し電子構造を決定した。計算には第一原理分子動力学計算コードであるVASPを用い、地球シミュレータ上で行った。444原子構造モデルを用いた加熱・急冷計算によって、初期構造では界面Si原子に存在していたダングリングボンドが完全に消滅した急峻界面が再現された。この時の条件は、加熱温度4000K,加熱時間3ps,急冷速度-1000K/psであり、さらに、急冷時の2200Kにおいて加熱中は固定してあったSiO
/SiC界面構造を計算機上に構築し電子構造を決定した。計算には第一原理分子動力学計算コードであるVASPを用い、地球シミュレータ上で行った。444原子構造モデルを用いた加熱・急冷計算によって、初期構造では界面Si原子に存在していたダングリングボンドが完全に消滅した急峻界面が再現された。この時の条件は、加熱温度4000K,加熱時間3ps,急冷速度-1000K/psであり、さらに、急冷時の2200Kにおいて加熱中は固定してあったSiO 終端を自由端とすることによって、SiO
終端を自由端とすることによって、SiO 層での歪を低減させるとともにアモルファス化を促進させた。バンドギャップ中にはなお欠陥準位が存在したが、これはアモルファスSiO
層での歪を低減させるとともにアモルファス化を促進させた。バンドギャップ中にはなお欠陥準位が存在したが、これはアモルファスSiO 中の酸素のダングリングボンドに起因していることがわかった。
中の酸素のダングリングボンドに起因していることがわかった。
宮下 敦巳; 大沼 敏治*; 岩沢 美佐子*; 土田 秀一*; 吉川 正人
no journal, ,
第一原理分子動力学計算コードであるVASPコードを用いた加熱・急冷計算法による計算機シミュレーションによりアモルファスSiO /SiC界面構造の生成を行った。444原子界面構造モデルに対して、4000K, 3psで加熱融解、-1000K/psで室温までの急冷を行った。生成したSiO
/SiC界面構造の生成を行った。444原子界面構造モデルに対して、4000K, 3psで加熱融解、-1000K/psで室温までの急冷を行った。生成したSiO 層の動径分布関数を評価したところ、全原子によるRDFでは長周期構造を反映した微細構造は認められず良好なアモルファス状態となっていた。部分RDFを評価したところ、Si-O結合距離は0.165nmであった。SiとSiの近接距離は約0.23nmに小さなピーク,0.315nmに大きなピークが認められる。0.23nmはSi-Si結合によるものでSiO
層の動径分布関数を評価したところ、全原子によるRDFでは長周期構造を反映した微細構造は認められず良好なアモルファス状態となっていた。部分RDFを評価したところ、Si-O結合距離は0.165nmであった。SiとSiの近接距離は約0.23nmに小さなピーク,0.315nmに大きなピークが認められる。0.23nmはSi-Si結合によるものでSiO 中にSi-Si欠陥構造が存在することがわかる。0.315nmはSi-O-Si結合でのSi間距離に相当しSi-O-Si結合角は145
中にSi-Si欠陥構造が存在することがわかる。0.315nmはSi-O-Si結合でのSi間距離に相当しSi-O-Si結合角は145 である。また、OとOの近接距離は0.266nmにピークを持ちO-Si-O結合角に換算すると107
である。また、OとOの近接距離は0.266nmにピークを持ちO-Si-O結合角に換算すると107 となった。これらの値はアモルファスSiO
となった。これらの値はアモルファスSiO の条件に適合し、加熱・急冷計算によって良好なアモルファスSiO
の条件に適合し、加熱・急冷計算によって良好なアモルファスSiO /SiC界面構造が生成されていることが確かめられた。
/SiC界面構造が生成されていることが確かめられた。
 /SiC interface defect structure generated with first-principles molecular dynamics simulation
/SiC interface defect structure generated with first-principles molecular dynamics simulation宮下 敦巳; 大沼 敏治*; 岩沢 美佐子*; 土田 秀一*; 吉川 正人
no journal, ,
Siに比べ優れた物理特性を持つSiCを用いた半導体デバイスは、従来のSiやGaAs半導体デバイスでは動作が困難な極限環境下で用いられる素子として期待されているが、SiCと酸化膜の界面にはSiCデバイス特性を劣化させる界面欠陥が多く存在しており、その欠陥構造とデバイス特性との関連性を追求することは非常に重要である。本研究では実際の界面を模擬した原子構造モデルを計算機上に生成し、電子状態が界面電気特性に与える影響を理論的側面から追求している。表面固定の1017原子界面構造モデルに対して、4000K 3psでの加熱,固定解放後3500K
3psでの加熱,固定解放後3500K 2psでの継続加熱,-2000K/psの速度で室温までの急冷を行った結果、生成されたモデルはSi-O結合距離が0.165nm, O-Si-O結合角が109
2psでの継続加熱,-2000K/psの速度で室温までの急冷を行った結果、生成されたモデルはSi-O結合距離が0.165nm, O-Si-O結合角が109 , Si-O-Si結合角が135
, Si-O-Si結合角が135 となり、SiO
となり、SiO 層が良好なアモルファス構造になったことが確かめられた。室温冷却後の界面構造では、従来モデルで想定されていた、Si原子が界面にある2つないしは3つのSi-O結合をまとめる構造以外にも、Si原子が一つのSi-O結合にのみ接続する構造,Si-Si結合を含む構造,界面Siのダングリングボンドが認められた。
層が良好なアモルファス構造になったことが確かめられた。室温冷却後の界面構造では、従来モデルで想定されていた、Si原子が界面にある2つないしは3つのSi-O結合をまとめる構造以外にも、Si原子が一つのSi-O結合にのみ接続する構造,Si-Si結合を含む構造,界面Siのダングリングボンドが認められた。
 界面構造の第一原理計算による生成,3
界面構造の第一原理計算による生成,3宮下 敦巳; 大沼 敏治*; 岩沢 美佐子*; 土田 秀一*; 吉川 正人
no journal, ,
第一原理分子動力学計算コードを用いた加熱・急冷計算によってアモルファス 界面構造を構築し、電子状態が界面電気特性に与える影響を理論的側面から追求した。1017原子界面構造モデルに対して、冷却速度を従来用いていた-2000K/psから、-1000K/ps, -500K/psと変化させた所、室温冷却後の全エネルギーは-2000K/psの時を基準にして、それぞれ-7.2eV, -13.9eV低くなり安定化した。また、SiO
界面構造を構築し、電子状態が界面電気特性に与える影響を理論的側面から追求した。1017原子界面構造モデルに対して、冷却速度を従来用いていた-2000K/psから、-1000K/ps, -500K/psと変化させた所、室温冷却後の全エネルギーは-2000K/psの時を基準にして、それぞれ-7.2eV, -13.9eV低くなり安定化した。また、SiO 層中でのSi-O-Si結合角も、135
層中でのSi-O-Si結合角も、135 から、それぞれ137
から、それぞれ137 , 140
, 140 と広くなり、よりシリカガラスでのSi-O-Siの結合角(145
と広くなり、よりシリカガラスでのSi-O-Siの結合角(145 10)
10) に近くなった。これらの結果から、冷却速度が遅い方が安定で実デバイスに近い界面構造を得られることがわかった。
に近くなった。これらの結果から、冷却速度が遅い方が安定で実デバイスに近い界面構造を得られることがわかった。
 -
- C面における酸化過程の第一原理分子動力学計算
C面における酸化過程の第一原理分子動力学計算大沼 敏治*; 宮下 敦巳; 岩沢 美佐子*; 吉川 正人; 土田 秀一*
no journal, ,
ワイドギャップ半導体であるSiCは次世代のMOS型パワーデバイスとして有望である。しかし 界面においては界面トラップ密度が高いことやMOSデバイスのチャンネル移動度が低いことが知られている。また
界面においては界面トラップ密度が高いことやMOSデバイスのチャンネル移動度が低いことが知られている。また 界面においては界面遷移層が存在することが知られており、その存在が界面トラップ密度の高さやチャンネル移動度の低下に影響を及ぼしている可能性がある。界面遷移層の形成過程を解明するには、
界面においては界面遷移層が存在することが知られており、その存在が界面トラップ密度の高さやチャンネル移動度の低下に影響を及ぼしている可能性がある。界面遷移層の形成過程を解明するには、 界面の熱酸化過程のメカニズムを明らかにすることが重要である。本報告では、C面における熱酸化過程の動的シミュレーションについて報告する。酸化過程のシミュレーションは酸素分子を一つずつSiO
界面の熱酸化過程のメカニズムを明らかにすることが重要である。本報告では、C面における熱酸化過程の動的シミュレーションについて報告する。酸化過程のシミュレーションは酸素分子を一つずつSiO 層に追加することにより行った。C面の熱酸化過程において酸素分子はSiO
層に追加することにより行った。C面の熱酸化過程において酸素分子はSiO 層中及びSiC界面のSi原子と反応し解離した。SiC界面のSi原子が酸化されることによりSi原子とC原子との結合が切れてCダングリングボンドが生成される。界面の炭素原子が酸化されてCO及びCO
層中及びSiC界面のSi原子と反応し解離した。SiC界面のSi原子が酸化されることによりSi原子とC原子との結合が切れてCダングリングボンドが生成される。界面の炭素原子が酸化されてCO及びCO 分子,C-C-O複合体が生成した。生成したCO
分子,C-C-O複合体が生成した。生成したCO 分子はCダングリングボンドと反応しない場合にSiO
分子はCダングリングボンドと反応しない場合にSiO 層を拡散する。酸化が進むと炭素の5員環構造などが生じるのが観察された。
層を拡散する。酸化が進むと炭素の5員環構造などが生じるのが観察された。
 界面の大規模数値解析
界面の大規模数値解析宮下 敦巳; 大沼 敏治*; 岩沢 美佐子*; 土田 秀一*; 吉川 正人
no journal, ,
Siに比べ優れた物理特性を持つSiCを基板に用いたSiC-MOSFETは、従来のSi半導体デバイスでは動作が困難な極限環境下で用いられる素子として期待されている。しかしSiCと酸化膜の界面には、SiC-MOSFETのデバイス特性を劣化させる原因である界面欠陥が多く存在しており、欠陥の原子構造とデバイス特性との関連性を追求することは非常に重要な問題となっている。本研究では実際のデバイスの酸化膜界面を模擬するようなアモルファス 界面を計算機上に構築して、その原子構造を解析することで、電子状態が界面電気特性に与える影響を追求している。1017原子界面構造モデル(加熱・急冷時693原子)に対して、4000K
界面を計算機上に構築して、その原子構造を解析することで、電子状態が界面電気特性に与える影響を追求している。1017原子界面構造モデル(加熱・急冷時693原子)に対して、4000K 3psの固定終端加熱,終端解放後、3500K
3psの固定終端加熱,終端解放後、3500K 2psの継続加熱、-2000K/psで室温までの急冷を行った。生成したSiO
2psの継続加熱、-2000K/psで室温までの急冷を行った。生成したSiO 層の動径分布関数を評価した所、Si-O結合距離は0.165nm、Si-O-Si結合角は135deg、O-Si-O結合角は109degと得られ、かつ、局所密度分布からも良好なアモルファス特性を示していることが確かめられた。
層の動径分布関数を評価した所、Si-O結合距離は0.165nm、Si-O-Si結合角は135deg、O-Si-O結合角は109degと得られ、かつ、局所密度分布からも良好なアモルファス特性を示していることが確かめられた。
 /SiC原子構造モデルの界面欠陥
/SiC原子構造モデルの界面欠陥宮下 敦巳; 大沼 敏治*; 土田 秀一*; 吉川 正人
no journal, ,
SiC半導体デバイスは耐熱性・耐電圧性・耐放射線性の面で非常に優れているが、SiCと酸化膜の界面に欠陥が発生するとデバイス性能が劣化するため、界面欠陥の解析が非常に重要となっている。本研究では実際のデバイス界面を模擬した原子構造モデルを計算機上に構築し電子構造を導出することで、界面欠陥が界面電気特性に与える影響を理論的側面から追求している。4H-SiC(0001)面(Si面)及び(000 )面(C面)上に
)面(C面)上に 水晶を接続した2種類の界面原子構造モデルに対して、4000Kでの加熱を行った後、-1000K/psの速度で室温までの急冷を行い、アモルファスSiO
水晶を接続した2種類の界面原子構造モデルに対して、4000Kでの加熱を行った後、-1000K/psの速度で室温までの急冷を行い、アモルファスSiO /SiC界面原子構造を生成した。それぞれのモデルはシリコン252個,炭素144個,酸素216個,水素36個の648原子を含む。生成された界面では、Si面界面はほとんどがSi-O結合で接続しているが、他にもSi-Si結合やSiダングリングボンド(DB)が観察された。他方、C面界面ではC-Si結合が多いが、ほかにもC-O結合やC DBが観察され、面方位による界面構造の違いが認められた。
/SiC界面原子構造を生成した。それぞれのモデルはシリコン252個,炭素144個,酸素216個,水素36個の648原子を含む。生成された界面では、Si面界面はほとんどがSi-O結合で接続しているが、他にもSi-Si結合やSiダングリングボンド(DB)が観察された。他方、C面界面ではC-Si結合が多いが、ほかにもC-O結合やC DBが観察され、面方位による界面構造の違いが認められた。