Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
大井 元貴; 酒井 健二; 神永 雅紀; 加藤 崇
no journal, ,
JSNS SNSなどのパルス中性子源では、冷減速材として液体水素が使用される。液体水素減速材の中性子特性は、水素分子のオルソ・パラ比や温度変化によって変動することが実験的に明らかになっている。特にパルス特性の変化は、加速器トリップや放射線等の影響によって否応なく変化すると予想される。このような問題に対処するために、パルス中性子源診断システムを提案する。本システムは、中性子ビームライン上に小型の中性子検出器を設置して、減速材から放出される中性子スペクトルの連続測定を行い、陽子ビーム電流値や、その他中性子源の状態と合わせて評価することで、減速材から放出される中性子特性の評価を行い、一定時間ごとの減速材内部の状態を記録することで、中性子散乱実験における入射中性子特性の違いを把握することができる。さらに、加速器や中性子源施設の運転情報と減速材内部の情報の時系列を比較してパターン化することで、中性子特性の変化をリアルタイムで予測し、長期間の観測を続けることで、デカップラーやポイゾンの燃焼の過程を追跡することも期待される。
SNSなどのパルス中性子源では、冷減速材として液体水素が使用される。液体水素減速材の中性子特性は、水素分子のオルソ・パラ比や温度変化によって変動することが実験的に明らかになっている。特にパルス特性の変化は、加速器トリップや放射線等の影響によって否応なく変化すると予想される。このような問題に対処するために、パルス中性子源診断システムを提案する。本システムは、中性子ビームライン上に小型の中性子検出器を設置して、減速材から放出される中性子スペクトルの連続測定を行い、陽子ビーム電流値や、その他中性子源の状態と合わせて評価することで、減速材から放出される中性子特性の評価を行い、一定時間ごとの減速材内部の状態を記録することで、中性子散乱実験における入射中性子特性の違いを把握することができる。さらに、加速器や中性子源施設の運転情報と減速材内部の情報の時系列を比較してパターン化することで、中性子特性の変化をリアルタイムで予測し、長期間の観測を続けることで、デカップラーやポイゾンの燃焼の過程を追跡することも期待される。
酒井 健二; 木下 秀孝; 甲斐 哲也; 大井 元貴; 星野 吉廣; 神永 雅紀; 加藤 崇
no journal, ,
物質・生命科学実験施設(MLF)は、ミュオンや中性子ビームを安全かつ効率よく利用者に供給する役割を要求される。その実現のために、施設内の線源設備の運転を独自に行うと同時に、加速器や他実験施設との協調制御にも対応できるMLF制御システム(MLF-GCS)の構築を進めてきた。現段階では、概要設計はほぼ終了し、MLF運転状態に基づいた施設全体や各設備の運転項目の最終検討と、それに対するMLF-GCSの役割分担の明確化を進めている。本発表では、MLF-GCSの概要と構築現状について報告する。
高橋 伸明; 柴田 薫; 佐藤 卓*; 新井 正敏; Mezei, F.*
no journal, ,
J-PARC/MLFに設置が計画されている生物試料やソフトマテリアルをターゲットにした低エネルギーダイナミクス解析装置(DIANA)は、3種類の結晶アナライザー(PG, Ge, Si)を搭載する逆転配置型の非弾性散乱装置である。本装置は、パルス中性子源を線源とした飛行時間型分光器であるため、エネルギー分解能は検出器に到達する中性子の飛行時間に依存する。そのため、原子炉に設置される三軸分光器に用いられるエネルギー集光型とは異なる形状のアナライザーが求められる。われわれはDIANAに搭載するアナライザーのために結晶ピースの新しい配置法を構築した。その特長は以下の通りである。(1)異なる飛行距離を有する結晶ピースを経由した中性子が同時刻に検出器に到達する「時間集光性能」を有すること,(2)アナライザー単結晶の熱散漫性散乱に起因するバックグラウンド低減のため、「空間集光性能」を有すること,(3)Q分解能を向上させるため、それぞれの検出器に対応するアナライザーユニットが試料を見込む散乱角を最小になるよう配置位置をデバイ・シェラーコーン上へ補正することである。この配置の設計方法及び、McStasを用いた計算機シミュレーションによる性能評価について考察する。
玉田 太郎
no journal, ,
X線結晶構造解析では1 以上の高分解能でなければ決定できない水素原子の位置決定を、中性子結晶構造解析では通常の分解能(2.5
以上の高分解能でなければ決定できない水素原子の位置決定を、中性子結晶構造解析では通常の分解能(2.5 程度)で容易に決定できる。よって、中性子解析による蛋白質の構造情報から蛋白質を取り巻く水和水の構造や水素結合・プロトン化の状態などの興味深い情報が得られる。しかしながら、中性子線の強度がX線と比べてはるかに弱く回折データ収集には少なくとも2mm
程度)で容易に決定できる。よって、中性子解析による蛋白質の構造情報から蛋白質を取り巻く水和水の構造や水素結合・プロトン化の状態などの興味深い情報が得られる。しかしながら、中性子線の強度がX線と比べてはるかに弱く回折データ収集には少なくとも2mm 以上の大きさの結晶を必要とすることから、これまでの中性子解析は「水素・水和水がその機能発現に重要な役割を果たす」蛋白質よりも「大きな結晶ができやすい」蛋白質がその解析対象であった。「水素・水和水がその機能発現に重要な役割を果たす」蛋白質を対象とした研究に取り組むために、われわれは「効果的な大型結晶作成技術の開発」、中性子解析に必要な結晶サイズを小さくするために「完全重水素化試料の作成」に取り組んでいる。これらの課題克服により、中性子解析がめざすべき重要な研究対象の1つは「創薬標的蛋白質」である。われわれの試みはまだその緒についたばかりであるが、これまでに得られた結果、及び今後の展開を紹介する。
以上の大きさの結晶を必要とすることから、これまでの中性子解析は「水素・水和水がその機能発現に重要な役割を果たす」蛋白質よりも「大きな結晶ができやすい」蛋白質がその解析対象であった。「水素・水和水がその機能発現に重要な役割を果たす」蛋白質を対象とした研究に取り組むために、われわれは「効果的な大型結晶作成技術の開発」、中性子解析に必要な結晶サイズを小さくするために「完全重水素化試料の作成」に取り組んでいる。これらの課題克服により、中性子解析がめざすべき重要な研究対象の1つは「創薬標的蛋白質」である。われわれの試みはまだその緒についたばかりであるが、これまでに得られた結果、及び今後の展開を紹介する。
前川 藤夫
no journal, ,
J-PARC物質・生命科学実験施設(MLF)の1MWパルス核破砕中性子源(JSNS)を構成する主要機器は、平成14, 15年度からの5か年契約で発注が行われ、平成18年度末から19年度初頭の据付完了を目指し、目下製作,据付の最終段階にある。その後、平成19年度にさまざまな試運転を行い、平成20年5月には初の陽子ビームを受け入れ、中性子源の運転を開始する計画である。中性子源本体は、水銀ターゲット,3台(結合型,非結合型,ポイズン型)の極低温水素モデレータ,反射体,ヘリウムベッセル,陽子ビーム窓,中性子ビームシャッター,遮蔽体等で構成され、それぞれの機器に水銀,極低温水素,冷却水,ガス等の供給システムが備わっている。また、水銀ターゲット容器,モデレータ,ベッセル窓等は遠隔操作で交換するため、専用の遠隔操作装置や汎用のマニュピレータも同時に製作している。本発表では、これらのJSNSを構成する主要機器の製作,据付の最新状況を紹介する。
栗原 和男; 玉田 太郎; 大原 高志; 黒木 良太
no journal, ,
BIX-3, 4(原子力機構 JRR-3)を用い、2006年度は茨城大学田中助教授ら、大阪府立大学木下助手らと共同で下記タンパク質の中性子回折データを収集し、現在構造精密化中である。ブタ膵臓インスリン(正方晶)では2.5
JRR-3)を用い、2006年度は茨城大学田中助教授ら、大阪府立大学木下助手らと共同で下記タンパク質の中性子回折データを収集し、現在構造精密化中である。ブタ膵臓インスリン(正方晶)では2.5 分解能のデータを得た。この晶系で観測されるpHに依存したヒスチジン残基のコンフォメーション変化をそのプロトン化状態から解析していく。同タンパク質
分解能のデータを得た。この晶系で観測されるpHに依存したヒスチジン残基のコンフォメーション変化をそのプロトン化状態から解析していく。同タンパク質 2Zn含有型結晶では2.0
2Zn含有型結晶では2.0 分解能のデータを得た。インスリンは膵臓でZnイオンと結合した6量体で保存される一方、単量体の形でホルモンとして働くため、正方晶と2Zn含有型での構造比較から生物作用on/off機構の理解を目指す。ウシ膵臓リボヌクレアーゼA(RNA加水分解酵素)では1.5
分解能のデータを得た。インスリンは膵臓でZnイオンと結合した6量体で保存される一方、単量体の形でホルモンとして働くため、正方晶と2Zn含有型での構造比較から生物作用on/off機構の理解を目指す。ウシ膵臓リボヌクレアーゼA(RNA加水分解酵素)では1.5 の高分解能データを取得した。その触媒,基質認識機構での水素・水和水の役割を解明する。ブタ膵臓エラスターゼ(1.75
の高分解能データを取得した。その触媒,基質認識機構での水素・水和水の役割を解明する。ブタ膵臓エラスターゼ(1.75 分解能データ取得)はセリンプロテアーゼの一種で各種炎症性疾患を引き起こし、その阻害剤開発のため構造を基盤とした創薬研究に使われてきた。これは中性子回折法で解析する初めての薬物標的タンパク質で、薬物・タンパク質間相互作用を中性子解析で検証する重要な例となると思われる。
分解能データ取得)はセリンプロテアーゼの一種で各種炎症性疾患を引き起こし、その阻害剤開発のため構造を基盤とした創薬研究に使われてきた。これは中性子回折法で解析する初めての薬物標的タンパク質で、薬物・タンパク質間相互作用を中性子解析で検証する重要な例となると思われる。
松田 雅昌
no journal, ,
フラストレート反強磁性体は、磁性と構造の自由度が相互に深くかかわり合い、興味ある現象を示すことが大きな特徴である。われわれは、JRR-3の三軸型中性子分光器TAS-1に設置された三次元偏極解析装置(CRYOPAD)を利用して、これらフラストレート反強磁性体の複雑な磁気構造の詳細解析を行っている。今回は、過去2, 3年間に得られた新しい結果の報告を行う。一つがスピネル磁性体CdCr O
O に関する研究であり、Crモーメントが
に関する研究であり、Crモーメントが 面内で楕円スパイラル構造を示すことを示した。もう一つはマルチフェロイック物質TbMnO
面内で楕円スパイラル構造を示すことを示した。もう一つはマルチフェロイック物質TbMnO に関する研究であり、MnモーメントがSDW相からスパイラル相へ連続的に変化することを、偏極度の非対角成分の測定により初めて明らかにした。
に関する研究であり、MnモーメントがSDW相からスパイラル相へ連続的に変化することを、偏極度の非対角成分の測定により初めて明らかにした。
 N
N 微粒子の偏極中性子回折法による磁気形状因子の測定
微粒子の偏極中性子回折法による磁気形状因子の測定石井 佑弥; 老谷 聖樹; 武田 全康; 加倉井 和久; 菊池 隆之; 奥 隆之; 篠原 武尚; 鈴木 淳市; 佐々木 勇治*; 岸本 幹雄*; et al.
no journal, ,
現在使用されている磁気テープ材料は粒径100nm程度の針状メタルが使用されているが、さらに高容量化・高密度化のために微細化又は球状化が必要である。窒化鉄Fe N
N は最近20nm程度の球状試料が得られるようになり、次世代の磁気テープ材料として有望である。ところが、一般的に強磁性体が微粒子状になると熱振動により自発磁化が減少し、磁気モーメントの値が小さくなることが知られている(超常磁性)。さらに、磁気テープ材料としてのFe
は最近20nm程度の球状試料が得られるようになり、次世代の磁気テープ材料として有望である。ところが、一般的に強磁性体が微粒子状になると熱振動により自発磁化が減少し、磁気モーメントの値が小さくなることが知られている(超常磁性)。さらに、磁気テープ材料としてのFe N
N は酸化防止のためラミネート層を持っており、通常の磁気測定法では正確な磁化の値を決めることが難しい。そこでFe
は酸化防止のためラミネート層を持っており、通常の磁気測定法では正確な磁化の値を決めることが難しい。そこでFe N
N 微粒子の正確な磁気モーメントの大きさを決定するために、偏極中性子回折法を用いた磁気形状因子の測定を行った。実験は試料に1Tの磁場をかけて磁化を飽和させて行った。スピンフリッパーを用いて飽和磁化と中性子スピンの向きを平行(ON)/反平行(OFF)にすることで回折強度に差が現れる。もし結晶構造因子が既知であれば、ON/OFFの各ピークでの反転比(flipping ratio)を測定することで磁気形状因子を求めることができる。
微粒子の正確な磁気モーメントの大きさを決定するために、偏極中性子回折法を用いた磁気形状因子の測定を行った。実験は試料に1Tの磁場をかけて磁化を飽和させて行った。スピンフリッパーを用いて飽和磁化と中性子スピンの向きを平行(ON)/反平行(OFF)にすることで回折強度に差が現れる。もし結晶構造因子が既知であれば、ON/OFFの各ピークでの反転比(flipping ratio)を測定することで磁気形状因子を求めることができる。
 鉄及びCoFeの磁気形状因子の測定
鉄及びCoFeの磁気形状因子の測定老谷 聖樹; 石井 佑弥; 武田 全康; 加倉井 和久; 菊池 隆之; 奥 隆之; 篠原 武尚; 鈴木 淳市; 横山 淳*; 西原 美一*; et al.
no journal, ,
磁気テープへの応用という観点から、強磁性微粒子に対する注目が集まっている。偏極中性子回折法は微粒子の磁化を決定するのに有望と思われるが、これまであまり例のない粉末に対する偏極中性子回折実験を行い、磁気形状因子を測定し、磁化を決定した。試料として典型的な強磁性体である 鉄と、磁気テープとして既に実用化されているCoFeの微粒子を選んだ。実験では、試料に10kOeの磁場を散乱ベクトルに垂直にかけ、試料の磁化を飽和させた。偏極中性子回折では磁化ベクトルと中性子スピンの向きが平行か反平行かで回折強度に差が現れる。その回折ピークの反転比Rを測定することで、結晶の(原子核)構造因子が既知であれば、磁気形状因子を求めることができる。一般に回折強度は、装置の分解能や試料の形状などによる補正を受けるが、反転比Rではそのような補正係数が打ち消され、測定精度はほとんど統計誤差のみとなり磁気形状因子を精度よく求めることができる。この実験により、純鉄の磁化が、ほぼ文献値の2.15Tであることが確かめられた。偏極中性子粉末回折法による磁気構造解析の有用性、及びその信頼性についてCoFeの結果も併せて報告する。
鉄と、磁気テープとして既に実用化されているCoFeの微粒子を選んだ。実験では、試料に10kOeの磁場を散乱ベクトルに垂直にかけ、試料の磁化を飽和させた。偏極中性子回折では磁化ベクトルと中性子スピンの向きが平行か反平行かで回折強度に差が現れる。その回折ピークの反転比Rを測定することで、結晶の(原子核)構造因子が既知であれば、磁気形状因子を求めることができる。一般に回折強度は、装置の分解能や試料の形状などによる補正を受けるが、反転比Rではそのような補正係数が打ち消され、測定精度はほとんど統計誤差のみとなり磁気形状因子を精度よく求めることができる。この実験により、純鉄の磁化が、ほぼ文献値の2.15Tであることが確かめられた。偏極中性子粉末回折法による磁気構造解析の有用性、及びその信頼性についてCoFeの結果も併せて報告する。
朝岡 秀人; 武田 全康; 山崎 大; 山崎 竜也; 田口 富嗣; 社本 真一; 鳥飼 直也*
no journal, ,
SrTiO のテンプレートとなるSrやSrO薄膜と、Si基板との格子不整合の緩衝域として水素単原子によるバッファー層を挿入し、12%の格子不整合を克服した薄膜成長に成功した。本研究では、埋もれた微小領域の水素界面層を実測する目的で、水素界面層を重水素に置換し中性子に対するコントラストを変化させ、解析精度を上げた中性子反射率測定を行うとともに、多重内部反射赤外分光(MIR-FTIR)法を用いたその場観察による基板直上の埋もれた水素・重水素界面での原子振動・結合状態の精密評価や、透過型電子顕微鏡(TEM)による不整合界面の構造評価を行っている。これら複合的な手法による埋もれた界面解析の試みを紹介する。
のテンプレートとなるSrやSrO薄膜と、Si基板との格子不整合の緩衝域として水素単原子によるバッファー層を挿入し、12%の格子不整合を克服した薄膜成長に成功した。本研究では、埋もれた微小領域の水素界面層を実測する目的で、水素界面層を重水素に置換し中性子に対するコントラストを変化させ、解析精度を上げた中性子反射率測定を行うとともに、多重内部反射赤外分光(MIR-FTIR)法を用いたその場観察による基板直上の埋もれた水素・重水素界面での原子振動・結合状態の精密評価や、透過型電子顕微鏡(TEM)による不整合界面の構造評価を行っている。これら複合的な手法による埋もれた界面解析の試みを紹介する。
 Sb
Sb におけるラットリングの可視化
におけるラットリングの可視化金子 耕士; 目時 直人; 木村 宏之*; 野田 幸男*; 松田 達磨; 神木 正史*
no journal, ,
大きなカゴに内包された原子が示す特異な熱振動「ラットリング」が、カゴ状構造を持つスクッテルダイト化合物PrOs Sb
Sb における非磁性の重い電子系超伝導の発現に重要な役割を担っていると報告された。原子核により散乱される中性子は、熱振動の検出に高い感度を有している。そこで中性子回折により詳細な構造を調べた。単結晶中性子回折実験は、3号炉に設置された4軸回折装置 FONDERで行った。最小二乗法による構造解析から、室温でのPrの熱振動パラメーターが他の構成元素と比べて5倍以上と非常に大きく、平均変位で0.2
における非磁性の重い電子系超伝導の発現に重要な役割を担っていると報告された。原子核により散乱される中性子は、熱振動の検出に高い感度を有している。そこで中性子回折により詳細な構造を調べた。単結晶中性子回折実験は、3号炉に設置された4軸回折装置 FONDERで行った。最小二乗法による構造解析から、室温でのPrの熱振動パラメーターが他の構成元素と比べて5倍以上と非常に大きく、平均変位で0.2 に及ぶことを明らかにした。異方性などの詳細を調べる目的で、PRIMAを用いた最大エントロピー法(MEM)による解析を行った結果、空間的に大きく拡がるPrの核度密度分布が、
に及ぶことを明らかにした。異方性などの詳細を調べる目的で、PRIMAを用いた最大エントロピー法(MEM)による解析を行った結果、空間的に大きく拡がるPrの核度密度分布が、 111
111 方向に伸びた異方性を有していることを明らかにした。さらに最大密度が、オフセンター位置にあることを見いだした。一方で低温の8Kでは、Os, Sbと比較してその分布は拡がってはいるが、分解能の範囲で異方性はなく、重心がカゴの中心にあることを明らかにした。
方向に伸びた異方性を有していることを明らかにした。さらに最大密度が、オフセンター位置にあることを見いだした。一方で低温の8Kでは、Os, Sbと比較してその分布は拡がってはいるが、分解能の範囲で異方性はなく、重心がカゴの中心にあることを明らかにした。
石垣 徹; 星川 晃範; 米村 雅雄*; 神山 崇*; 森 一広*; 茂筑 高士*; 相澤 一也; 新井 正敏; 江幡 一弘*; 高野 佳樹*; et al.
no journal, ,
茨城県はJ-PARCの産業利用を推進することを目的として、汎用型粉末散乱装置(茨城県材料構造解析装置)を建設することを決定した。この回折計はハイスループット回折装置として考えられており、材料の開発・研究者は、この装置を材料の開発過程の中で化学分析装置のように手軽に用いることが可能である。この装置は、背面バンクで0.18 d(
d( )
) 5の
5の 範囲を分解能
範囲を分解能 %で測定することが可能であり、5
%で測定することが可能であり、5 d(
d( )
) 800の
800の 範囲については徐々に変化する分解能でカバーしている。リートベルト解析が可能なデータを測定するための標準的な測定時間は実験室X線装置程度の量で数分である。産業利用を促進するためには、利用システムの整備が必要である。装置の建設は、既に開始されており、2008年には、J-PARCのデイワン装置の一つとして完成の予定である。今回は装置の建設状況についての報告を行う。
範囲については徐々に変化する分解能でカバーしている。リートベルト解析が可能なデータを測定するための標準的な測定時間は実験室X線装置程度の量で数分である。産業利用を促進するためには、利用システムの整備が必要である。装置の建設は、既に開始されており、2008年には、J-PARCのデイワン装置の一つとして完成の予定である。今回は装置の建設状況についての報告を行う。
目時 直人; 金子 耕士
no journal, ,
平成18年度よりJRR-3ガイドホールのT2-3ビームポートに建設された多目的単色熱中性子ビームポート「武蔵」の目的,ビームポートの概要,装置の現状,今年度の実績について報告する。「武蔵」は2本のビームポートを持ち、長期の準備を要し、技術的に困難な実験に潤沢な中性子ビームを割り当てるとともに、J-PARCの建設に必要な検出器,中性子光学デバイスの開発,残留応力解析など産業利用-トライアルユースに使用される。本年度は低角高角二本のビームポート及び付属回折計が順調に立ち上がり、極端条件実験が開始された。また、多くの種類の検出器のテスト、開発、校正などにもビームを提供した。さらに付属回折計を残留応力解析装置RESA-IIとして提供し、施設供用、トライアルユースも開始された。来年度以降も多くのユーザーからの積極的な提案に、中性子ビームをふんだんに提供していきたいと考えている。
梶本 亮一; 横尾 哲也*; 中島 健次; 中村 充孝; 稲村 泰弘; 丸山 龍治; 曽山 和彦; 鈴谷 賢太郎; 猪野 隆*; 大山 研司*; et al.
no journal, ,
4次元空間中性子探査装置(4SEASONS、四季)は大強度陽子加速器(J-PARC)の核破砕中性子研究施設に建設されるチョッパー型非弾性散乱装置の一つである。本装置は高温超伝導体及び関連物質のダイナミクスの研究を目的としており、入射エネルギー範囲( -300meV)や分解能(エネルギー遷移
-300meV)や分解能(エネルギー遷移 のとき
のとき -6%)はこれらの系の観測に必要十分な値を選択している。このように分解能を緩和し、かつ高効率の中性子光学デバイスを備えることで試料位置での高い中性子束を実現する。さらに、新型Fermiチョッパー(MAGICチョッパー)によるRRM法測定によって測定効率のさらなる向上を図り、併せて既存のチョッパー型分光器に比べて2桁高い測定効率の実現を目指している。本発表では、本装置の予想性能及び、最近の開発状況について紹介する。
-6%)はこれらの系の観測に必要十分な値を選択している。このように分解能を緩和し、かつ高効率の中性子光学デバイスを備えることで試料位置での高い中性子束を実現する。さらに、新型Fermiチョッパー(MAGICチョッパー)によるRRM法測定によって測定効率のさらなる向上を図り、併せて既存のチョッパー型分光器に比べて2桁高い測定効率の実現を目指している。本発表では、本装置の予想性能及び、最近の開発状況について紹介する。
梶本 亮一; 中島 健次; 中村 充孝; 曽山 和彦; 横尾 哲也*; 及川 健一; 新井 正敏
no journal, ,
4次元空間中性子探査装置(4SEASONS、四季)は大強度陽子加速器(J-PARC)の核破砕中性子研究施設に建設されるチョッパー型非弾性散乱装置の一つである。この装置での減速材-試料間の距離( )は18m、入射中性子のエネルギー範囲は5-300meVであるが、試料位置での中性子線束を増強するために減速材-試料間に収束形状の中性子スーパーミラー・ガイド管を備える予定である。本研究ではMcStasによるモンテカルロ・シミュレーションなどにより、ガイド管のデザインについて検討した。その結果、楕円形状のガイド管配置をとることにより、上記の広いエネルギー範囲にわたって十分な強度ゲインが得られることがわかった。
)は18m、入射中性子のエネルギー範囲は5-300meVであるが、試料位置での中性子線束を増強するために減速材-試料間に収束形状の中性子スーパーミラー・ガイド管を備える予定である。本研究ではMcStasによるモンテカルロ・シミュレーションなどにより、ガイド管のデザインについて検討した。その結果、楕円形状のガイド管配置をとることにより、上記の広いエネルギー範囲にわたって十分な強度ゲインが得られることがわかった。
 Y
Y MnO
MnO の電気分極と磁気構造
の電気分極と磁気構造梶本 亮一; 横尾 哲也*; 古府 麻衣子*; 野田 耕平*; 桑原 英樹*
no journal, ,
 MnO
MnO は長周期磁気秩序相で強誘電性を示すことで最近注目されているが、その多くでは自発電気分極
は長周期磁気秩序相で強誘電性を示すことで最近注目されているが、その多くでは自発電気分極 は長周期磁気秩序がらせん秩序となる時に出現している。Eu
は長周期磁気秩序がらせん秩序となる時に出現している。Eu Y
Y MnO
MnO は
は K以下で反強磁性転移を示す。
K以下で反強磁性転移を示す。 K以下で
K以下で 軸に平行な自発電気分極が生じるが、その向きは
軸に平行な自発電気分極が生じるが、その向きは K以下で
K以下で 軸方向へと変化する。この電気分極の変化と磁気構造の関係を実験的に調べるためにEu
軸方向へと変化する。この電気分極の変化と磁気構造の関係を実験的に調べるためにEu Y
Y MnO
MnO の単結晶試料に対して中性子回折実験を行った。磁気反射は
の単結晶試料に対して中性子回折実験を行った。磁気反射は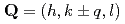 ,
,  の位置に観測された。散乱ベクトル
の位置に観測された。散乱ベクトル が
が 軸にほぼ平行な
軸にほぼ平行な と
と 軸にほぼ平行な
軸にほぼ平行な の2つの磁気反射強度の温度変化の比較から磁気構造の変化を考察した。両者ともに
の2つの磁気反射強度の温度変化の比較から磁気構造の変化を考察した。両者ともに ,
,  で変化が見られ、
で変化が見られ、 の向きの変化に対応してスピンの向きが変化していることがわかった。らせん秩序及びサイン波秩序を仮定したモデルを元に2つの磁気反射強度を解析し、
の向きの変化に対応してスピンの向きが変化していることがわかった。らせん秩序及びサイン波秩序を仮定したモデルを元に2つの磁気反射強度を解析し、 の向きとの関係について考察した。
の向きとの関係について考察した。
鈴木 淳市; 篠原 武尚; 奥 隆之; 清水 裕彦; Pynn, R.*
no journal, ,
われわれはこれまでに磁気屈折集光素子(磁気レンズ)を開発し、単色ビームを利用する集光型偏極中性子小角散乱装置への応用に成功してきたが、現在、この磁気レンズの白色中性子への応用研究に取り組んでいる。磁気レンズは、ビーム経路に物質を有しないので余計な散乱や吸収がない、得られる集光ビームが偏極ビームである、直線配置できる等の利点があるが、ビーム経路に物質を有しない点や直線配置性はBragg条件を満足する最長波長以下の短波長中性子を含む白色中性子利用にとって重要な利点となる。われわれは白色中性子を集光するために飛行時間法と組合せて磁気レンズ内部に発生する磁場勾配を時間的に変化させる方法と磁気レンズの有効長を時間的に変化させる方法の開発に取り組み、最近、その原理実証実験に成功した。また、パルス中性子小角散乱法への応用の可能性の追求も進めており、長波長帯域だけでなく短波長帯域の中性子の集光が、広波長帯域の中性子の同時利用による利得の向上をq分解能の低下なく実現するために極めて有効であることを確認した。
 の偏極中性子による5f電子状態の研究
の偏極中性子による5f電子状態の研究目時 直人; 本多 史憲; 金子 耕士; 浄念 信太郎; 山本 悦嗣; 芳賀 芳範; 青木 大*; 本間 佳哉*; 塩川 佳伸; 大貫 惇睦
no journal, ,
スピン偏極中性子散乱実験による遍歴多体5f電子系NpTGa の磁気構造の研究を紹介し、この手法がアクチノイド化合物の5f電子状態を明らかにするうえでいかに有効かを紹介する。また、講演では遍歴多体5f電子系における多極子秩序について議論する。
の磁気構造の研究を紹介し、この手法がアクチノイド化合物の5f電子状態を明らかにするうえでいかに有効かを紹介する。また、講演では遍歴多体5f電子系における多極子秩序について議論する。
奥 隆之; 山田 悟*; 篠原 武尚; 鈴木 淳市; 三島 賢二*; 広田 克也*; 佐藤 広海*; 清水 裕彦
no journal, ,
四極磁石を用いた中性子偏極装置の開発研究を行っている。中性子が四極磁石内に入射すると、磁石が形成する磁場勾配により、正極性成分と負極性成分が空間的に分離する。そこで、そのうちの一成分を抽出することにより、偏極中性子ビームを得るものである。この方法では、中性子が物質により散乱されたり、吸収されたりすることがないため、非常に高い偏極度の中性子ビームを高効率で得ることが可能である。これまでに、四極永久磁石を用いて冷中性子ビームの偏極実験を行った結果、P 0.999の偏極度を達成することに成功した。会議では、実験結果の詳細について発表するほか、この偏極装置の中性子散乱実験への応用方法について議論する予定である。
0.999の偏極度を達成することに成功した。会議では、実験結果の詳細について発表するほか、この偏極装置の中性子散乱実験への応用方法について議論する予定である。
篠原 武尚; 鈴木 淳市; 奥 隆之; 岩下 秀徳*; 加美山 隆*; 岩佐 浩克*; 平賀 富士夫*; 鬼柳 善明*; 佐藤 孝一*; 清水 裕彦*
no journal, ,
パルス中性子ビームの集光を目的として、パルス六極電磁石を開発し、その性能評価実験を行った。その結果、パルス中性子の集光を確認し、パルス六極電磁石が中性子磁気レンズとして機能することを実証した。また、パルス電流波形及びタイミングを変化させることにより、集光条件を変化させることが可能であることを示した。