Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
筒井 健二; 遠山 貴己*; 前川 禎通
no journal, ,
ニッケル不純物を含む銅酸化物高温超伝導物質に対する共鳴X線散乱スペクトルのクラスター計算を行い、不純物よりもホールが多い場合の電子状態や共鳴X線散乱スペクトルを議論する。
小泉 光生; 後藤 淳*; 松木 征史*
no journal, ,
短寿命核の核磁気モーメントの測定を行うため、動的自己核偏極(DYNASP: DYnamic NucleAr Self Polarization)法を用いた核偏極技術を開発している。DYNASPとはDyakonovらが予言した現象である。III-V族半導体の電子を直線偏向した レーザーで励起し、数K程度の臨界温度以下とすることにより、大きな核偏極が得られる現象である。われわれはDyakonovらの理論を、円偏光したレーザーを用いて電子を励起した場合に拡張し、それによる核偏極への影響を理論的に解析した。その結果、円偏光を用いると臨界温度以上においても核偏極が現れることや、レーザーの偏向度を変化させると臨界温度以下で核偏極がヒステリシス曲線を描くことなどを見いだした。
森林 健悟
no journal, ,
低エネルギーの重粒子線が細胞に照射されると衝突電離で生じた水イオンの電場で二次電子が粒子線の軌道付近にトラップされることを以前、明らかにしたが、本発表では軌道付近の電子の密度,電子の温度を示し、それによって再結合が起きる時間を議論する。3MeV/uのエネルギーの炭素線が照射させると軌道から1nm以内に10 /cm
/cm -10
-10 /cm
/cm の密度、5-10eVの温度の電子が存在する。この電子が再結合を起こす時間は数10fsから100fs程度であることがわかり、100fsを超えるシミュレーションでは再結合過程が不可欠であることを明らかにした。
の密度、5-10eVの温度の電子が存在する。この電子が再結合を起こす時間は数10fsから100fs程度であることがわかり、100fsを超えるシミュレーションでは再結合過程が不可欠であることを明らかにした。
浅井 雅人; 塚田 和明; 笠松 良崇*; 豊嶋 厚史; 佐藤 哲也; 永目 諭一郎; 佐藤 望; 石井 哲朗
no journal, ,
アクチノイド偶々核の第一励起準位エネルギーを、高分解能 線測定並びに
線測定並びに -
- 同時計数測定によって精密に決定した。Pu, Cm, Cf, Fm同位体の合計8核種について系統的に測定し、アクチノイド領域の偶々核の第一励起準位エネルギーの陽子数・中性子数依存性を系統的に明らかにした。第一励起準位エネルギーは、Cm及びCf同位体において最小値を取り、その後陽子数の増加とともに増大することが明らかとなった。この傾向は、陽子数114の球形閉殻の存在を考慮することで定性的に説明できる。また、
同時計数測定によって精密に決定した。Pu, Cm, Cf, Fm同位体の合計8核種について系統的に測定し、アクチノイド領域の偶々核の第一励起準位エネルギーの陽子数・中性子数依存性を系統的に明らかにした。第一励起準位エネルギーは、Cm及びCf同位体において最小値を取り、その後陽子数の増加とともに増大することが明らかとなった。この傾向は、陽子数114の球形閉殻の存在を考慮することで定性的に説明できる。また、 Fmにおいて極小値を取り、陽子数100と中性子数152の二重変形閉殻の存在を実験的に明らかにした。
Fmにおいて極小値を取り、陽子数100と中性子数152の二重変形閉殻の存在を実験的に明らかにした。
目時 直人; 山本 悦嗣; 酒井 宏典; 芳賀 芳範; 松田 達磨; 池田 修悟*
no journal, ,
US は、低温で結晶場励起,温度が上昇して電気抵抗が8桁減少するに伴い、混成効果によって磁気的な準弾性散乱を示す。磁気励起ギャップ(
は、低温で結晶場励起,温度が上昇して電気抵抗が8桁減少するに伴い、混成効果によって磁気的な準弾性散乱を示す。磁気励起ギャップ( 80K)と伝導ギャップ(
80K)と伝導ギャップ( 90K)が、電気伝導の金属-絶縁体クロスオーバーや準弾性散乱が生じる温度スケール(
90K)が、電気伝導の金属-絶縁体クロスオーバーや準弾性散乱が生じる温度スケール( 100K)と等しいため、局在5f電子系が温度上昇に伴って遍歴的となることが、電気伝導性と相関を持つと考えられる。今回、磁気励起スペクトルのクラマース・クロニッヒ変換を行ったところ、SQUIDで観察された静帯磁率を非常によく再現できることがわかった。これは、(1)測定範囲12meVのエネルギーを越えた励起が存在しない、(2)磁気相関が弱く局所帯磁率が支配的であることを意味している。さらに(3)非弾性散乱を結晶場(局在パート)と準弾性(遍歴パート)に分離することで、静帯磁率に対する各々の寄与を見積もることができた。低温で局在モデルは良い近似であるが、温度上昇に伴って連続的な準弾性散乱が支配的となり、結晶場モデルの前提である不連続のシャープな準位と励起が存在しなくなる。結晶場モデルはこの条件で漸近する低温極限であることが明らかになった。
100K)と等しいため、局在5f電子系が温度上昇に伴って遍歴的となることが、電気伝導性と相関を持つと考えられる。今回、磁気励起スペクトルのクラマース・クロニッヒ変換を行ったところ、SQUIDで観察された静帯磁率を非常によく再現できることがわかった。これは、(1)測定範囲12meVのエネルギーを越えた励起が存在しない、(2)磁気相関が弱く局所帯磁率が支配的であることを意味している。さらに(3)非弾性散乱を結晶場(局在パート)と準弾性(遍歴パート)に分離することで、静帯磁率に対する各々の寄与を見積もることができた。低温で局在モデルは良い近似であるが、温度上昇に伴って連続的な準弾性散乱が支配的となり、結晶場モデルの前提である不連続のシャープな準位と励起が存在しなくなる。結晶場モデルはこの条件で漸近する低温極限であることが明らかになった。
乙部 智仁
no journal, ,
時間依存密度汎関数法の基礎方程式である時間依存Kohn-Sham方程式をブロッホの定理に基づいて実時間実空間法で解くことで強いレーザーによる透明材料(ダイアモンド)中での高次高調波発生のシミュレーションを行った。その結果バンドギャップを超えるエネルギーの光のスペクトルは基本波より広い幅を持つことがわかった。さらに光学絶縁破壊が起きることで基本波とともに高調波も青方偏移することが明らかとなった。
池田 隆司; Hou, Z.*; Wang, X.*; 寺倉 清之*; 尾嶋 正治*; 柿本 雅明*; 宮田 清蔵*
no journal, ,
窒素をドープしたカーボンアロイ触媒が固体高分子形燃料電池の正極における酸素分子還元反応の有力な白金代替触媒として注目を集めている。触媒活性のさらなる向上のためには、触媒活性点と反応機構のミクロな理解が必須である。われわれはこれまでに、炭素材を端のあるグラフェンシートとして簡素化したモデルを用いて第一原理電子状態計算を基盤とした分子動力学計算を行い、グラフェンにおける触媒活性に寄与する窒素の配置及び触媒活性点での酸素分子還元反応の反応機構を調べてきた。その結果、窒素をグラフェンの特定の位置にドープすると金属がなくても触媒活性を示すことを見いだしている。一方、東京大学の尾嶋グループにより実際に合成されたカーボンアロイ触媒の分光実験が放射光を用いて精力的に行われ、われわれの提案した触媒活性点モデルを支持する実験結果が得られている。本講演では、シミュレーションから示唆されたカーボンアロイ触媒における酸素還元反応の反応機構をまとめて議論する。
池田 隆司
no journal, ,
液体の水はH Oという簡単な分子の集合体であり、理論解析も容易そうに見えながら、ごく最近の研究においても、なお十分な理解に至っているという状況ではない。液体の水の性質を分子動力学法によって調べる際に、水分子間の相互作用を経験的に与えてシミュレーションを行うことも盛んに行われてきた。しかし、水分子の分極率が大きいため、周囲の水の配置によって電気双極子モーメントの大きさが敏感に変化する、などの様子を経験的に与えることは容易ではない。第一原理分子動力学法は1985年にCarとParrinelloによって提唱され、それ以後、物質科学の多くの分野において幅広く使われている。水への適用はParrinelloグループによって開始され、それ以降盛んに行われている。本講演では、まず、水の第一原理分子動力学シミュレーションの現状をまとめ、次に、高温高圧下の水に関するわれわれの最近の結果を紹介し、今後の展望について触れる。
Oという簡単な分子の集合体であり、理論解析も容易そうに見えながら、ごく最近の研究においても、なお十分な理解に至っているという状況ではない。液体の水の性質を分子動力学法によって調べる際に、水分子間の相互作用を経験的に与えてシミュレーションを行うことも盛んに行われてきた。しかし、水分子の分極率が大きいため、周囲の水の配置によって電気双極子モーメントの大きさが敏感に変化する、などの様子を経験的に与えることは容易ではない。第一原理分子動力学法は1985年にCarとParrinelloによって提唱され、それ以後、物質科学の多くの分野において幅広く使われている。水への適用はParrinelloグループによって開始され、それ以降盛んに行われている。本講演では、まず、水の第一原理分子動力学シミュレーションの現状をまとめ、次に、高温高圧下の水に関するわれわれの最近の結果を紹介し、今後の展望について触れる。
湊 太志
no journal, ,
Spin-flip型のM1遷移に対するテンソル力の効果を、乱雑位相近似法(RPA法)を用いて理論的に調べた。特にM1遷移の和則に着目し、ピークの位置と の強さの関係を調べた。テンソル力はE1遷移に対する和則(
の強さの関係を調べた。テンソル力はE1遷移に対する和則( )に影響を与えない一方で、M1遷移の和則には強い影響を与える(T42パラメータの場合:
)に影響を与えない一方で、M1遷移の和則には強い影響を与える(T42パラメータの場合:  =158
=158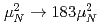 )。それと関連し、テンソル力はE1遷移分布をほとんど変化させないが、M1遷移分布を大きく変化させる。
)。それと関連し、テンソル力はE1遷移分布をほとんど変化させないが、M1遷移分布を大きく変化させる。 を一粒子準位の全軌道角運動量、
を一粒子準位の全軌道角運動量、 を軌道角運動量とすると、
を軌道角運動量とすると、 軌道(
軌道( )と
)と 軌道(
軌道( )の占有率によって和則は増減し、各々の原子核によって異なるテンソル力の影響が現れることがわかった。また、和則の増減にかかわらず
)の占有率によって和則は増減し、各々の原子核によって異なるテンソル力の影響が現れることがわかった。また、和則の増減にかかわらず の強さはほぼ同程度である一方で、ピーク位置が増減していることがわかった。つまり和則の増減はピーク位置の増減に比較的強く左右されていることがわかった。
の強さはほぼ同程度である一方で、ピーク位置が増減していることがわかった。つまり和則の増減はピーク位置の増減に比較的強く左右されていることがわかった。
 の磁性
の磁性山本 悦嗣; 広瀬 雄介*; 榎 健太郎*; 三田村 勝哉*; 杉山 清寛*; 竹内 徹也*; 萩原 政幸*; 金道 浩一*; 芳賀 芳範; 摂待 力生*; et al.
no journal, ,
UCd は格子定数a=9.29
は格子定数a=9.29 のBaHg
のBaHg 型立方晶をとり、その最近接U-U間距離は6.56
型立方晶をとり、その最近接U-U間距離は6.56 と大きい。また、UCd
と大きい。また、UCd は
は =5Kとこの系の化合物では転移温度が高く、また常磁性領域における電子比熱係数は840mJ/K
=5Kとこの系の化合物では転移温度が高く、また常磁性領域における電子比熱係数は840mJ/K molと大きい。これまでに単結晶による物性測定が行われ、
molと大きい。これまでに単結晶による物性測定が行われ、 //
// 100
100 方向の磁気相図が得られている。今回新たに、UCd
方向の磁気相図が得られている。今回新たに、UCd の
の //
// 100
100 ,
,  110
110 ,
,  111
111 の1.3Kにおける強磁場磁化曲線を測定し、転移磁場及び磁場誘起強磁性相における磁気異方性を見いだした。
の1.3Kにおける強磁場磁化曲線を測定し、転移磁場及び磁場誘起強磁性相における磁気異方性を見いだした。
本多 充; 林 伸彦; 藤田 隆明
no journal, ,
径電場とトロイダル回転はトカマクプラズマにおけるさまざまな輸送現象に大きな影響を与えるため、輸送シミュレーションにおいてその正確な評価は極めて重要となる。しかし、1.5次元輸送コードTOPICSを始め、主要な輸送コードでそれらの時間発展を解けるものはほとんどなかった。そこで、基本的な運動方程式から出発し、仮定を極力排してトロイダル運動量方程式を導出した。この方程式は全粒子で和を取った全トロイダル運動量を解いている。また、TOPICSで計算した背景分布を高速イオン軌道追跡コードOFMCに与えて評価した衝突減速トルクと径方向電流トルクをTOPICSに入力することで、自己無撞着にトロイダル運動量輸送の時間発展が計算可能となった。さらに、輸送計算で求められた全トロイダル運動量から、モーメント法に基づく新古典輸送計算モジュールMatrix Inversionを用い、径電場とそれに依存するポロイダル・トロイダル回転や平行流を反復収束計算なしに決定する手法を開発しTOPICSに導入した。
藤城 興司; 井田 瑞穂; Groeshel, F.*; 近藤 浩夫; 若井 栄一; 杉本 昌義
no journal, ,
IFMIF(国際核融合材料照射施設)は核融合炉原型炉等の開発を目指して計画されている核融合中性子(14MeV)を模擬した大強度中性子源である。2007年からは、日欧協力のもと、IFMIFの工学実証・工学設計活動(EVEDA)を実施している。ターゲットアセンブリについては高真空(10 Pa)に安定したリチウム噴流(ノズル出口速度20m/s,厚み精度25
Pa)に安定したリチウム噴流(ノズル出口速度20m/s,厚み精度25 2mm)を形成する要件に加え、中性子生成に伴う核発熱,その除熱,凹面背板に関係した流体の安定性,加速器側へのリチウム蒸散量など、種々の評価を進めている。本研究ではリチウム流の安定性に重要な役割を果たす整流器について、設計製作した技術仕様の詳細検討を、有限体積法(FLUENT)を用い、おもに負庄環境下で評価した。矩形断面の整流器は円形断面の配管から、断面形状変換部を通じて接続され、一つのハニカムと多孔板とから構成されていることから、解析の結果、乱流強度の減衰は最下流の多孔板とノズル入口の距離を適切に設定することで得られ、この調整を行うことで好ましい整流状態が得られることがわかった。
2mm)を形成する要件に加え、中性子生成に伴う核発熱,その除熱,凹面背板に関係した流体の安定性,加速器側へのリチウム蒸散量など、種々の評価を進めている。本研究ではリチウム流の安定性に重要な役割を果たす整流器について、設計製作した技術仕様の詳細検討を、有限体積法(FLUENT)を用い、おもに負庄環境下で評価した。矩形断面の整流器は円形断面の配管から、断面形状変換部を通じて接続され、一つのハニカムと多孔板とから構成されていることから、解析の結果、乱流強度の減衰は最下流の多孔板とノズル入口の距離を適切に設定することで得られ、この調整を行うことで好ましい整流状態が得られることがわかった。
横田 光史
no journal, ,
三角格子反強磁性イジング模型は、フラストレーションの効果が最もはっきり表れる系である。最近接相互作用の系では、3次元的に積層すると有限温度で部分無秩序構造などの秩序相が現れる。他方、スピングラス相の出現にはフラストレーションの他にランダムネスも重要になってくる。ここでは、基本的にフラストレーションの効果が非常に強い反強磁性三角格子イジング系において、相互作用にランダムネスが加わったときの系の相図などについて調べる。ある種のクラスター近似を用いて、クラスター内でのゆらぎを取り入れたときに、単純な平均場近似と比べた場合の変化などを調べる。
 イオン照射と単原子イオン照射による負2次イオン放出の比較
イオン照射と単原子イオン照射による負2次イオン放出の比較平田 浩一*; 齋藤 勇一; 鳴海 一雅; 千葉 敦也; 山田 圭介
no journal, ,
クラスターイオン照射では、複数の原子が同時に試料表面の狭い領域にエネルギーを付与するため、単原子イオン照射と比較して2次イオン放出量が増大する現象が観測される。これを表面分析法に応用する技術開発の一環として、C イオン照射と単原子イオン照射による有機高分子薄膜からの負2次イオン放出量について比較した。C
イオン照射と単原子イオン照射による有機高分子薄膜からの負2次イオン放出量について比較した。C イオンとArイオンを1次イオンとして用いて、PMMA高分子薄膜試料の負2次イオンを飛行時間型質量分析器で分析したところ、以下の知見が得られた。(1)C
イオンとArイオンを1次イオンとして用いて、PMMA高分子薄膜試料の負2次イオンを飛行時間型質量分析器で分析したところ、以下の知見が得られた。(1)C イオンの入射エネルギーが高くなる程、分析に有用な2次イオンが増大し、30keVと540keVで比較すると、十数倍から数十倍、540keVの2次イオン強度が高い。(2)同一入射エネルギーのC
イオンの入射エネルギーが高くなる程、分析に有用な2次イオンが増大し、30keVと540keVで比較すると、十数倍から数十倍、540keVの2次イオン強度が高い。(2)同一入射エネルギーのC とAr1次イオンを比較したところ、C
とAr1次イオンを比較したところ、C 入射イオンあたりの放出される総2次イオン量は、Arイオンに比べて2桁程度高い。(3)C
入射イオンあたりの放出される総2次イオン量は、Arイオンに比べて2桁程度高い。(3)C とAr1次イオンで、2次イオンスペクトルの時間変化を調べたところ、Arでは、試料の帯電により2次イオン強度が急激に減少するが、C
とAr1次イオンで、2次イオンスペクトルの時間変化を調べたところ、Arでは、試料の帯電により2次イオン強度が急激に減少するが、C イオンでは、スペクトルに変化が見られず、安定に2次イオンスペクトルを得ることができる。これらにより、クラスターイオンは高分子膜などの絶縁物の表面2次イオン分析に有効であることを明らかにした。
イオンでは、スペクトルに変化が見られず、安定に2次イオンスペクトルを得ることができる。これらにより、クラスターイオンは高分子膜などの絶縁物の表面2次イオン分析に有効であることを明らかにした。
森 道康; Spencer-Smith, A.*; Sushkov, O. P.*; 前川 禎通
no journal, ,
非磁性絶縁体に温度勾配を与え、それと垂直な方向に磁場を加えたとき、両者に垂直な方向に温度勾配が現れる現象をフォノンホール効果と呼ぶ。次の組成式Tb Gd
Gd O
O で表されるTb-Gdガーネット(TGG)で観測されている。測定はバンドギャップより十分に小さい温度(約5K)で行われているため、熱励起された電荷の寄与は考えにくい。また、反強磁性転移温度は0.24Kなので磁気秩序はなく、パイロクロア酸化物で観測されているマグノンの寄与は期待できない。本講演では、TGGで観測されたフォノンホール効果の起源が、過剰に含まれた磁性イオン(Tb
で表されるTb-Gdガーネット(TGG)で観測されている。測定はバンドギャップより十分に小さい温度(約5K)で行われているため、熱励起された電荷の寄与は考えにくい。また、反強磁性転移温度は0.24Kなので磁気秩序はなく、パイロクロア酸化物で観測されているマグノンの寄与は期待できない。本講演では、TGGで観測されたフォノンホール効果の起源が、過剰に含まれた磁性イオン(Tb )によるフォノンのスキュー散乱によるものである可能性を提案する。Tbイオンの最低エネルギー準位が擬二重項であることを考慮し、簡単のためJ=1を仮定して、磁場(B)下でのフォノンの散乱振幅(kp)を見積もると、B・p
)によるフォノンのスキュー散乱によるものである可能性を提案する。Tbイオンの最低エネルギー準位が擬二重項であることを考慮し、簡単のためJ=1を仮定して、磁場(B)下でのフォノンの散乱振幅(kp)を見積もると、B・p kに比例する項が残ることがわかる。得られた散乱振幅をフォノンのボルツマン方程式に用いて、熱伝導度の横成分(kxy)を計算し、縦成分(kxx)との比(S=kxy/kxx)を見積もると温度(T)に関してTb
kに比例する項が残ることがわかる。得られた散乱振幅をフォノンのボルツマン方程式に用いて、熱伝導度の横成分(kxy)を計算し、縦成分(kxx)との比(S=kxy/kxx)を見積もると温度(T)に関してTb に比例する結果が得られた。もし、5K以上の温度依存性を測ることができたなら、フォノンホール効果がより顕著になることが期待される。講演では、ほかの散乱機構の可能性についても議論する。
に比例する結果が得られた。もし、5K以上の温度依存性を測ることができたなら、フォノンホール効果がより顕著になることが期待される。講演では、ほかの散乱機構の可能性についても議論する。
 Si
Si の電子構造研究
の電子構造研究保井 晃; 藤森 伸一; 川崎 郁斗; 岡根 哲夫; 竹田 幸治; 斎藤 祐児; 山上 浩志; 関山 明*; 摂待 力生*; 松田 達磨; et al.
no journal, ,
YbCu Si
Si は典型的な価数揺動物質として古くから知られている。この物質については、これまでにドハース・ファンアルフェン(dHvA)効果の測定が行われており、その結果とLDA+
は典型的な価数揺動物質として古くから知られている。この物質については、これまでにドハース・ファンアルフェン(dHvA)効果の測定が行われており、その結果とLDA+ をもとにしたバンド計算を比較することにより、フェルミ面形状が予測されている。しかし、その計算では過去の価電子帯角度積分光電子スペクトルを説明できないことから、バンド構造とフェルミ面を統一的に理解できていない。われわれはYbCu
をもとにしたバンド計算を比較することにより、フェルミ面形状が予測されている。しかし、その計算では過去の価電子帯角度積分光電子スペクトルを説明できないことから、バンド構造とフェルミ面を統一的に理解できていない。われわれはYbCu Si
Si のバルクの価電子帯構造を実験的に調べるために、軟X線角度分解光電子分光(ARPES)実験を行った。発表では、本研究で得られたYbCu
のバルクの価電子帯構造を実験的に調べるために、軟X線角度分解光電子分光(ARPES)実験を行った。発表では、本研究で得られたYbCu Si
Si の価電子帯バンド分散及びフェルミ面と、Yb3価状態の参照物質であるYCu
の価電子帯バンド分散及びフェルミ面と、Yb3価状態の参照物質であるYCu Si
Si 、また、以前報告したYb2価に近い価数揺動物質であるYbCu
、また、以前報告したYb2価に近い価数揺動物質であるYbCu Ge
Ge のものとの比較を示す。
のものとの比較を示す。
大西 弘明
no journal, ,
イリジウム化合物Sr IrO
IrO は、強いスピン軌道相互作用により誘起される新奇モット絶縁体として注目を集めている。その基底状態は有効全角運動量
は、強いスピン軌道相互作用により誘起される新奇モット絶縁体として注目を集めている。その基底状態は有効全角運動量 =
= で記述されることが明らかにされたが、スピンと軌道が複合化した励起ダイナミクスに関しては詳細な知見が得られていない。本研究では、イリジウム化合物に対する有効多体電子模型としてスピン軌道相互作用を含む
で記述されることが明らかにされたが、スピンと軌道が複合化した励起ダイナミクスに関しては詳細な知見が得られていない。本研究では、イリジウム化合物に対する有効多体電子模型としてスピン軌道相互作用を含む 軌道縮退ハバード模型を採用して、光学伝導度などの動的物理量を厳密対角化によって調べる。クーロン相互作用やスピン軌道相互作用の大きさを変化させた場合の励起スペクトルのピーク構造を議論する。
軌道縮退ハバード模型を採用して、光学伝導度などの動的物理量を厳密対角化によって調べる。クーロン相互作用やスピン軌道相互作用の大きさを変化させた場合の励起スペクトルのピーク構造を議論する。
福田 竜生; Baron, A. Q. R.*; 内山 裕士*; 石角 元志*; 中村 博樹; 社本 真一; 町田 昌彦; 水木 純一郎; 新井 正敏; 伊豫 彰*; et al.
no journal, ,
鉄砒素超伝導関連物質のフォノン分散は、鉄スピンを考慮した第一原理計算によって比較的よく説明できる。しかしわれわれは、なお実験と計算の不一致が残留することを示し、2つの修正モデルを提唱した。この両モデルは磁性や鉄砒素面内異方性,砒素原子の鉄面からの距離等に関連していることが予想されるため、高圧合成したPrFeAsO を用い、SPring-8のBL35XUで非弾性X線散乱測定法を用いた音響フォノンの精密測定を行った。この実験では高い波数分解能を得るために、アナライザ・スリットを通常の1/10程度にまで絞っている。
を用い、SPring-8のBL35XUで非弾性X線散乱測定法を用いた音響フォノンの精密測定を行った。この実験では高い波数分解能を得るために、アナライザ・スリットを通常の1/10程度にまで絞っている。 =(
=( 0)(
0)( 0)の位置で縦波,横波2種類の音響フォノンが観測されたが、
0)の位置で縦波,横波2種類の音響フォノンが観測されたが、 =0付近で縦波に比べた横波音響フォノン強度の急激な減少が観測された。これは横波音響フォノンが縦波と混合されることなく純粋に存在していることを表しており、われわれの提唱している2つのモデルのうち、面内ソフトモデルの方に近いという結果となっている。
=0付近で縦波に比べた横波音響フォノン強度の急激な減少が観測された。これは横波音響フォノンが縦波と混合されることなく純粋に存在していることを表しており、われわれの提唱している2つのモデルのうち、面内ソフトモデルの方に近いという結果となっている。
 におけるイオントラック形成
におけるイオントラック形成石川 法人; 園田 健*; 澤部 孝史*; 左高 正雄
no journal, ,
高エネルギー核分裂片による照射が継続的に発生している軽水炉UO 燃料では、高燃焼度になるに従い高燃焼度組織(HBS)と呼ばれる組織変化が生じ、燃料特性が変化する。この組織変化の高精度予測のためには、100MeVオーダーの高エネルギー重イオンがUO
燃料では、高燃焼度になるに従い高燃焼度組織(HBS)と呼ばれる組織変化が生じ、燃料特性が変化する。この組織変化の高精度予測のためには、100MeVオーダーの高エネルギー重イオンがUO 中を通過する際の照射損傷メカニズムの解明が必須である。本研究では、(1)イオンが通過する軌跡に沿って形成されるイオントラックと呼ばれる柱状欠陥の寸法が既存の熱スパイクモデルなどで予測可能かどうかを検証すること、さらに(2)照射損傷同士が多重にオーバーラップする高照射量領域で、微細組織がどのように変化するのかを調べることが目的である。イオン照射後の透過型電子顕微鏡観察により、イオントラックの寸法の電子的阻止能(Se)依存性を調べた結果、Seの増加に伴って寸法が増加する傾向があることを確認することができた。本研究の結果では、100MeVオーダーのエネルギー領域において、イオントラックの寸法の実験値は、モデルの予測値より小さい値が観測され、既存の予測モデルを修正する必要性が示唆された。
中を通過する際の照射損傷メカニズムの解明が必須である。本研究では、(1)イオンが通過する軌跡に沿って形成されるイオントラックと呼ばれる柱状欠陥の寸法が既存の熱スパイクモデルなどで予測可能かどうかを検証すること、さらに(2)照射損傷同士が多重にオーバーラップする高照射量領域で、微細組織がどのように変化するのかを調べることが目的である。イオン照射後の透過型電子顕微鏡観察により、イオントラックの寸法の電子的阻止能(Se)依存性を調べた結果、Seの増加に伴って寸法が増加する傾向があることを確認することができた。本研究の結果では、100MeVオーダーのエネルギー領域において、イオントラックの寸法の実験値は、モデルの予測値より小さい値が観測され、既存の予測モデルを修正する必要性が示唆された。
山根 結太; 家田 淳一; 前川 禎通
no journal, ,
近年、スピントロニクス分野においてスピン起電力と呼ばれる現象が注目を集めている。スピン起電力生成のためには時間・空間双方に依存した磁化ダイナミクスを誘起する必要があり、磁壁移動を利用してスピン起電力の観測が可能であることが理論的に予測され、のちに実験によって確かめられている。磁壁移動に伴うスピン起電力の大きさは印加磁場の大きさに比例することが知られているが、パーマロイのような磁気的にソフトな物質では磁壁は非常に非線形な振舞を示し、数百Oe程度の磁場下では逆向きに進む磁壁が新たに導入されスピン起電力はキャンセルされてしまう。このため印加磁場の大きさに制限があり、数 Vの観測値に留まっている。われわれは、垂直磁化膜を用いることでこうした困難を克服できることを数値解析により明らかにした。
Vの観測値に留まっている。われわれは、垂直磁化膜を用いることでこうした困難を克服できることを数値解析により明らかにした。