Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
 Ni
Ni D
D at high
at high  conditions
conditions市東 力*; 鍵 裕之*; 柿澤 翔*; 青木 勝敏*; 小松 一生*; 飯塚 理子*; 阿部 淳*; 齋藤 寛之*; 佐野 亜沙美; 服部 高典
American Mineralogist, 108(4), p.659 - 666, 2023/04
被引用回数:5 パーセンタイル:71.52(Geochemistry & Geophysics)Fe Ni
Ni H
H (D
(D )の12GPa, 1000Kまでの高温高圧下における相関係と結晶構造をその場X線及び中性子回折測定により明らかにした。今回実験した温度圧力下において、Fe
)の12GPa, 1000Kまでの高温高圧下における相関係と結晶構造をその場X線及び中性子回折測定により明らかにした。今回実験した温度圧力下において、Fe Ni
Ni H
H (D
(D )ではFeH
)ではFeH (D
(D )とは異なり、重水素原子は面心立方構造(fcc)中の四面体サイトを占有しないことが明らかになった。単位重水素あたりの水素誘起膨張体積
)とは異なり、重水素原子は面心立方構造(fcc)中の四面体サイトを占有しないことが明らかになった。単位重水素あたりの水素誘起膨張体積 は、fcc相で2.45(4)
は、fcc相で2.45(4)  、hcp相で3.31(6)
、hcp相で3.31(6)  であり、FeD
であり、FeD におけるそれぞれの値より著しく大きいことが明らかになった。また、
におけるそれぞれの値より著しく大きいことが明らかになった。また、 は温度の上昇に伴いわずかに増加した。この結果は、鉄に10%ニッケルを添加するだけで、金属中の水素の挙動が劇的に変化することを示唆している。
は温度の上昇に伴いわずかに増加した。この結果は、鉄に10%ニッケルを添加するだけで、金属中の水素の挙動が劇的に変化することを示唆している。 が圧力に関係なく一定であると仮定すると、地球内核の最大水素含有量は海洋の水素量の1-2倍であると推定される。
が圧力に関係なく一定であると仮定すると、地球内核の最大水素含有量は海洋の水素量の1-2倍であると推定される。
湯口 貴史*; 湯浅 春香*; 五十公野 裕也*; 中島 和夫*; 笹尾 英嗣; 西山 忠男*
American Mineralogist, 107(3), p.476 - 488, 2022/03
被引用回数:2 パーセンタイル:19.86(Geochemistry & Geophysics)本研究は花崗岩体内で広く産出するミルメカイトを研究対象とし、その解析手法と生成に関する知見を提示した。本研究では、瑞浪超深地層研究所周辺に分布する土岐花崗岩体のミルメカイト中に微小孔を見出した。これはミルメカイト生成時に体積が減少していることを示す。その結果から(1)ミルメカイト生成に際して体積変化を考慮した元素移動メカニズム、(2)ミルメカイト化に際して微小孔の生成要因、(3)熱水の化学的特徴の時間的を論じた。微小孔は熱水や地下水の拡散経路となり得るため、将来的な物質移動を考える上でも有用な知見となる。
大橋 智典*; 坂巻 竜也*; 舟越 賢一*; 服部 高典; 久野 直樹*; 阿部 淳*; 鈴木 昭夫*
American Mineralogist, 107(3), p.325 - 335, 2022/03
被引用回数:2 パーセンタイル:19.86(Geochemistry & Geophysics)マグマの物性を知るために、室温で加圧されたバサルトガラスの構造をX線および中性子回折により約18GPaまで調べた。加圧によりバサルトガラスは圧縮挙動を変化させた。つまり約2-4GPaにおいて、平均酸素間距離(r )を保ったまま、酸素の平均配位数(CN
)を保ったまま、酸素の平均配位数(CN )は上昇しはじめる。さらに加圧すると9GPaでCN
)は上昇しはじめる。さらに加圧すると9GPaでCN の上昇はとまり、Al周りの酸素配位数(CN
の上昇はとまり、Al周りの酸素配位数(CN )を上昇させながら、r
)を上昇させながら、r が縮み始める。9GPaでの変化は ガラスの圧縮機構が、四面体ネットワークの変形から、CN
が縮み始める。9GPaでの変化は ガラスの圧縮機構が、四面体ネットワークの変形から、CN の増大を伴った酸素充填率の上昇に変わることで解釈できる。高圧下の酸素の充填率(
の増大を伴った酸素充填率の上昇に変わることで解釈できる。高圧下の酸素の充填率( )を解析すると、その値がデンスランダムパッキングの限界値を超えることが分かった。このことは、石英やケイ酸塩ガラスの構造相転移が酸素充填限界説では説明できないことを示している。2-4GPaに見られたCN
)を解析すると、その値がデンスランダムパッキングの限界値を超えることが分かった。このことは、石英やケイ酸塩ガラスの構造相転移が酸素充填限界説では説明できないことを示している。2-4GPaに見られたCN の上昇は四配位ケイ酸塩ガラスのソフト化と対応しており、過去にLiu and Lin (2014)によって報告された約2GPaでのバサルトガラスの弾性異常の起源であるかもしれない。
の上昇は四配位ケイ酸塩ガラスのソフト化と対応しており、過去にLiu and Lin (2014)によって報告された約2GPaでのバサルトガラスの弾性異常の起源であるかもしれない。
湯口 貴史*; 松木 貴伸*; 五十公野 裕也*; 笹尾 英嗣; 西山 忠男*
American Mineralogist, 106(7), p.1128 - 1142, 2021/07
被引用回数:6 パーセンタイル:40.44(Geochemistry & Geophysics)花崗岩体で生じる熱水変質では、普遍的に緑泥石化、斜長石の変質、炭酸塩鉱物の晶出が生じる。本研究では、中部日本に分布する土岐花崗岩体を対象として、ホルンブレンドの緑泥石化、カリ長石の緑泥石化、脈状緑泥石の生成をもたらす熱水-鉱物間の元素移動について論じた。既往研究ならびに本研究の統合的な知見により、熱水変質に伴う岩体内の元素移動を包括的に捉えることが可能になった。本研究では、緑泥石化に伴い微小空隙が生じることを見出した。この知見と反応物と生成物の化学組成から、反応式を構築し、約180 350
350 Cの温度範囲で生じる熱水流体中の元素移動について論じた。
Cの温度範囲で生じる熱水流体中の元素移動について論じた。
湯口 貴史*; 菖蒲澤 花穂*; 小北 康弘*; 八木 公史*; 石橋 正祐紀; 笹尾 英嗣; 西山 忠男*
American Mineralogist, 104(4), p.536 - 556, 2019/04
被引用回数:23 パーセンタイル:74.87(Geochemistry & Geophysics)結晶質岩内部における過去の流体の化学的特性を復元するためには、流体の化学的特性を記録しつつ形成された変質鉱物を研究対象とすることが有効となる。そこで本研究は、中部日本の土岐花崗岩体中に認められる斜長石の熱水変質プロセスを斜長石中の微小孔の役割、物質移動、反応速度の観点から論じ、斜長石の変質をもたらす熱水の化学的特徴の変遷について検討した。斜長石の変質はアルバイト化,カリ長石化、およびイライトの形成により特徴づけられる。本研究では、(1)変質領域と非変質領域の微小孔の分布特性の相違、(2)反応式の構築による斜長石変質に伴う流入・流出成分の解明、(3)イライトK-Arの年代決定に基づく変質年代・温度条件の推定、(4)斜長石の変質をもたらす年代・温度条件における熱水の化学的特徴の時間的な推移について論じた。
湯口 貴史; 笹尾 英嗣; 石橋 正祐紀; 西山 忠男*
American Mineralogist, 100(5-6), p.1134 - 1152, 2015/05
被引用回数:40 パーセンタイル:77.17(Geochemistry & Geophysics)花崗岩における地球化学的特徴の将来的な変遷を予測するためには、今日にいたるまでの花崗岩体で生じた現象(たとえば熱水変質や岩石-水反応)の長期的変遷を理解することが、重要な視点の1つとなる。そこで、本論文では中部日本に位置する土岐花崗岩体において黒雲母から緑泥石への熱水変質プロセスの解明を行った。花崗岩体の熱水変質の中で、黒雲母の緑泥石化は広い温度条件で生ずることが報告されており、かつ花崗岩体を通して普遍的に観察される。このため、変質に伴う鉱物と熱水流体間の物質移動に着目することで、花崗岩体内の熱水流体の化学的特徴の長期的な変遷を明らかにした。土岐花崗岩体中における緑泥石化に伴って生じる鉱物の組み合わせの違いは、熱水から流入する成分の相違に支配されることが明らかとなった。このことは、熱水に含有する化学成分の不均質性を示す。また、緑泥石化が進行するにつれ、熱水流体中のケイ素とカリウム,塩素が増大し、金属成分とカルシウムが減少する化学的特徴の経時的な変化を明らかにした。
 -bearing Mg-perovskite and its crystal chemistry at high pressure
-bearing Mg-perovskite and its crystal chemistry at high pressure増野 いづみ*; 大谷 栄治*; 平尾 直久*; 三井 隆也; 増田 亮*; 瀬戸 誠*; 境 毅*; 高橋 豪*; 中野 聡志*
American Mineralogist, 99(8-9), p.1555 - 1561, 2014/08
被引用回数:7 パーセンタイル:22.25(Geochemistry & Geophysics)Valence, spin states, and crystallographic sites of Fe in (Mg,Fe)SiO perovskite were investigated using energy-domain
perovskite were investigated using energy-domain  Fe-synchrotron M
Fe-synchrotron M ssbauer spectroscopy and powder X-ray diffraction up to 86 GPa. The volumes of Fe
ssbauer spectroscopy and powder X-ray diffraction up to 86 GPa. The volumes of Fe bearing perovskite in this study are slightly smaller than those of Mg endmember perovskite. Our M
bearing perovskite in this study are slightly smaller than those of Mg endmember perovskite. Our M ssbauer data suggest that Fe
ssbauer data suggest that Fe prefers A sites coupled with Mg vacancies, which is consistent with previous data at ambient conditions. Fe
prefers A sites coupled with Mg vacancies, which is consistent with previous data at ambient conditions. Fe in the A site remains in a high spin state up to 86 GPa, and some fraction of the A site is occupied by Fe
in the A site remains in a high spin state up to 86 GPa, and some fraction of the A site is occupied by Fe at pressures above 30 GPa. Fe
at pressures above 30 GPa. Fe in the A sites is also in a high spin state up to 86 GPa. The coupled substitution from Mg
in the A sites is also in a high spin state up to 86 GPa. The coupled substitution from Mg to a high spin state of Fe
to a high spin state of Fe and Mg
and Mg vacancy would make the volume of perovskite smaller than that of Mg endmember perovskite.
vacancy would make the volume of perovskite smaller than that of Mg endmember perovskite.
 -Al(OH)
-Al(OH) ; Neutron diffraction measurements and ab initio calculations
; Neutron diffraction measurements and ab initio calculations松井 正典*; 小松 一生*; 池田 恵美*; 佐野 亜沙美; 後藤 弘匡*; 八木 健彦*
American Mineralogist, 96(5-6), p.854 - 859, 2011/05
被引用回数:16 パーセンタイル:41.81(Geochemistry & Geophysics)中性子回折実験により、 -Al(OD)
-Al(OD) の結晶構造は以前X線回折実験に基づいて報告された
の結晶構造は以前X線回折実験に基づいて報告された ではなく
ではなく 2
2 2
2 2
2 であることが明らかになった。AlとOの位置はX線回折実験により求めた値を使用し、水素位置は第一原理計算により求めた値を用いて解析を行ったところ、第一原理計算の結果は中性子回折実験の結果とよく一致するものであった。また67GPa付近で
であることが明らかになった。AlとOの位置はX線回折実験により求めた値を使用し、水素位置は第一原理計算により求めた値を用いて解析を行ったところ、第一原理計算の結果は中性子回折実験の結果とよく一致するものであった。また67GPa付近で 2
2 2
2 2
2 構造から
構造から 構造へと相転移し、水素が二つの酸素間の中心に位置する対称化が起きることが第一原理計算から示唆された。
構造へと相転移し、水素が二つの酸素間の中心に位置する対称化が起きることが第一原理計算から示唆された。
西田 圭佑*; 大谷 栄治*; 浦川 啓*; 鈴木 昭夫*; 坂巻 竜也*; 寺崎 英紀*; 片山 芳則
American Mineralogist, 96(5-6), p.864 - 868, 2011/05
被引用回数:34 パーセンタイル:68.37(Geochemistry & Geophysics)X線吸収法を用いて液体硫化鉄(FeS)の密度が圧力3.8GPa,温度1800Kまで測定された。液体FeSの圧縮曲線はVinetの状態方程式を使うことでフィットすることが可能であった。非線形最小二乗法を用いることによって、等温体積圧縮率とその圧力微分が決定された。液体FeSは鉄が多いFe-S液体よりも圧縮されやすかった。
坂巻 竜也*; 大谷 栄治*; 浦川 啓*; 寺崎 英紀*; 片山 芳則
American Mineralogist, 96(4), p.553 - 557, 2011/04
被引用回数:33 パーセンタイル:65.95(Geochemistry & Geophysics)X線吸収法によって炭酸塩ペリドタイトマグマの密度が3.8GPa, 2100Kまで測定された。炭酸塩ペリドタイトマグマの体積弾性率は含水ペリドタイトマグマのそれよりも大きい。高温高圧条件下のマグマのCO の部分モル体積が計算された。われわれの結果は、CO
の部分モル体積が計算された。われわれの結果は、CO の部分モル体積はH
の部分モル体積はH Oのそれよりも圧縮されにくいことを示している。すなわち、同じモル数であれば、H
Oのそれよりも圧縮されにくいことを示している。すなわち、同じモル数であれば、H Oに比べCO
Oに比べCO のほうがより効果的にペリドタイトマグマの密度を高圧下で下げることを示唆している。
のほうがより効果的にペリドタイトマグマの密度を高圧下で下げることを示唆している。
坂巻 竜也*; 大谷 栄治*; 浦川 啓*; 鈴木 昭夫*; 片山 芳則
American Mineralogist, 95(1), p.144 - 147, 2010/01
被引用回数:39 パーセンタイル:70.48(Geochemistry & Geophysics)X線吸収法を用いて、ペリドタイトマグマの密度を2.5GPa, 2300Kまで測定した。この方法によって、ペリドタイト融体の密度を7つの異なった条件で測定することができ、密度の温度圧力依存性が明らかになった。圧力-密度-温度のデータを高温Birch-Murnagan状態方程式にフィットすることによって、2100Kでの等温体積弾性率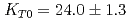 GPa,その圧力微分,
GPa,その圧力微分,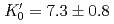 ,体積弾性率の温度微分
,体積弾性率の温度微分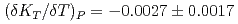 GPa/Kが得られた。玄武岩融体に比べ、ペリドタイト融体が大きな体積弾性率とその圧力微分を持つことは、これまでの浮沈法による実験結果と調和的である。
GPa/Kが得られた。玄武岩融体に比べ、ペリドタイト融体が大きな体積弾性率とその圧力微分を持つことは、これまでの浮沈法による実験結果と調和的である。
福士 圭介*; 佐藤 努*; 柳瀬 信之; 湊 淳一*; 山田 裕久*
American Mineralogist, 89(11-12), p.1728 - 1734, 2004/11
シュベルトマナイトによるAs(V)収着機構が酸性条件下におけるAs(V)濃度の関数としたバッチ収着実験と結晶学的考察から検討された。シュベルトマナイトの結晶構造シミュレーションから、シュベルトマナイトのAs(V)収着のための潜在的な表面サイトは、幾つかの配位環境の異なる表面水酸基及び表面硫酸基であることが推測された。バッチ収着実験から、As(V)イオンは表面吸着硫酸基及び表面に配位する構造由来の硫酸基と選択的に配位子交換を行うことでシュベルトマナイトに収着されることが示唆された。また、As(V)は表面吸着硫酸サイトに対しては単座的に配位子交換を行い、構造由来硫酸サイトに対しては二座的に配位子交換を行うことが示唆された。さらに実験結果から見積もられた配位子交換反応の平衡定数は実験結果をうまく再現した。
村上 隆*; 小暮 敏博*; 門原 博行*; 大貫 敏彦
American Mineralogist, 83, p.1209 - 1219, 1998/00
アノーサイトの溶解と二次鉱物の関係を調べるため、アノーサイトの熱水条件下での溶解実験を行った。この結果、二次鉱物としてはベーマイト、ベーマイト様鉱物、カオリナイトが観察された。一方、アノーサイトの構成元素は、水溶液に溶出した。溶出元素濃度から、アノーサイトの溶解はインコングルーエンドであることがわかり、さらに、二次鉱物の生成と関係していることがわかった。アノーサイトのギブス自由エネルギーの経時変化から、二次鉱物の形成がアノーサイトの溶解を促進させていることが明らかとなった。
村上 隆*; 大貫 敏彦; 磯部 博志; 佐藤 努
American Mineralogist, 82, p.888 - 899, 1997/00
オーストラリア、クンガラ鉱床の2次鉱床の酸化条件におけるウランの固定機構について透過電子顕微鏡、走査電子顕微鏡により検討し、熱力学データに基づく予測と比較した。その結果、ウランは、地下水の上流域ではケイ酸塩鉱物がリン酸塩鉱物に置き換わっていること、下流域では鉄鉱物中にリン酸塩鉱物として析出しているのが確認された。これらの結果を、熱力学的データに基づく予測と比較した結果、上流域では局所的な飽和条件によるウラン鉱物の析出が機構として考えられた。しかし、下流域では、上流域のような局所的飽和からはウラン鉱物の生成が予測されず、他の機構、例えば触媒作用、により生成したものと考えた。
村上 隆; 佐藤 努; 渡辺 隆*
American Mineralogist, 78(3), p.465 - 468, 1993/00
スメクタイト イライト反応は続成あるいは熱水変質によって起こり、地球表面の低温地球化学を理解する上で重要な反応の一つである。高分解能電子顕微鏡(HRTEM)はその反応機構を調べる有力な一手段であるが、スメクタイトがHRTEMの高真空下で収縮し、イライトと区別できなくなるため有効な活用ができなかった。試料を鏡筒に入れる前から液体窒素温度にし、その温度のまま観察することにより、イライト/スメクタイトの微細構造が明確に調べられる手法が開発された。観察された微細構造から、スメクタイト
イライト反応は続成あるいは熱水変質によって起こり、地球表面の低温地球化学を理解する上で重要な反応の一つである。高分解能電子顕微鏡(HRTEM)はその反応機構を調べる有力な一手段であるが、スメクタイトがHRTEMの高真空下で収縮し、イライトと区別できなくなるため有効な活用ができなかった。試料を鏡筒に入れる前から液体窒素温度にし、その温度のまま観察することにより、イライト/スメクタイトの微細構造が明確に調べられる手法が開発された。観察された微細構造から、スメクタイト イライト反応機構として、溶解・核成長と固相転移両方の可能性が考えられる。
イライト反応機構として、溶解・核成長と固相転移両方の可能性が考えられる。
村上 隆; B.C.Chakoumakos*; R.C.Ewing*; G.R.Lumpkin*; W.J.Weber*
American Mineralogist, 76, p.1510 - 1532, 1991/00
密度測定、X線回折、透過電子顕微鏡の結果に基づき、ジルコンの放射線損傷の過程と機構を明らかにした。損傷は10 の崩壊/mgまでは蓄積される。損傷の第1段階では(
の崩壊/mgまでは蓄積される。損傷の第1段階では( 3
3 10
10
 /mg)
/mg) 粒子により生成した点欠陥により結晶格子が膨張し歪められる。欠陥は地質時代を通じ一部アニールされる。第2段階では(3-8
粒子により生成した点欠陥により結晶格子が膨張し歪められる。欠陥は地質時代を通じ一部アニールされる。第2段階では(3-8 10
10
 /mg)反跳核による結晶構造の破壊が進む過程である。非晶質構造も一部アニールされる。第3段階は(
/mg)反跳核による結晶構造の破壊が進む過程である。非晶質構造も一部アニールされる。第3段階は( 8
8 10
10
 /mg)完全に非晶質化した状態である。非晶質領域の密度変化は非晶質構造の変化を表している。Pu入りの人工ジルコンとの比較から照射率による損傷機構の変化はないことがわかった。
/mg)完全に非晶質化した状態である。非晶質領域の密度変化は非晶質構造の変化を表している。Pu入りの人工ジルコンとの比較から照射率による損傷機構の変化はないことがわかった。