Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
 Coガンマ線照射試験結果と計算結果との比較
Coガンマ線照射試験結果と計算結果との比較武田 遼真; 柴田 裕司; 武内 伴照; 中野 寛子; 関 美沙紀; 井手 広史
JAEA-Testing 2024-007, 33 Pages, 2025/03
日本原子力研究開発機構及び日本原子力研究所では過去30年以上、自己出力型の中性子検出器(Self-Powered Neutron Detector: SPND)やガンマ線検出器(Self-Powered Gamma Detector: SPGD)の開発・照射試験が行われており、複数の研究成果が報告されている。本稿では、これらの試験結果に対して、JAEA報告書『自己出力型放射線検出器の出力電流値計算コードの作成(JAEA-Data/Code 2021-018)』において作成した計算コードによる理論的な出力結果との比較・検証を行った。比較対象はコバルト60ガンマ線照射施設SPGDの照射試験結果とした。その結果、ガンマ線によるコンプトン散乱電子の飛程に対して比較的にエミッタ径が細い場合には計算結果は試験結果を良く再現することが分かった。一方、比較的にエミッタ径が太い場合には計算結果と比較して試験結果における出力電流値は半分程度にとどまった。エミッタ径の違いによる差異が生じた要因としてエミッタによる自己遮蔽効果が考えられ、エミッタ径が太い場合や 線場が等方的でない条件に由来する自己遮蔽による影響を、計算コードにおける電子の平均飛程や平均最小エネルギーの変化として採り入れる等の新たな定式化が必要であると思われる。
線場が等方的でない条件に由来する自己遮蔽による影響を、計算コードにおける電子の平均飛程や平均最小エネルギーの変化として採り入れる等の新たな定式化が必要であると思われる。
宮川 和也; 下茂 道人*; 丹羽 正和; 天野 健治; 徳永 朋祥*; 戸野倉 賢一*
深田地質研究所年報, (22), p.139 - 153, 2021/00
深田地質研究所と東京大学,原子力機構は、共同研究の一環として、地下深部で生成したガス(地下ガス)が断層を通じて地表へ放出されることに着目し、キャビティーリングダウン分光法を用いた可搬型分析装置による大気環境中のメタンや二酸化炭素濃度の時空間変化を迅速に捉えることで、断層の地表分布の調査手法の開発に取り組んでいる。大気環境中のガス濃度の微小変化には、地下ガスのみでなく、動植物や自動車などの複数の放出源の影響が含まれており、測定結果から地下ガス以外による影響を取り除くことで(スクリーニング)、断層の地表分布の推定精度の向上および調査の効率化が期待される。本稿では、各起源ガスの影響調査とスクリーニングの試行例を報告する。自動車の排ガスや人の呼気の影響については、そのほとんどを除外できたが、微生物発酵ガスの影響については、地下ガスとの区別が困難な場合があることが分かった。本共同研究で得られた断層の情報は、令和2年度以降の幌延深地層研究計画において日本原子力研究開発機構(原子力機構)が取り組んでいる課題「地下水の流れが非常に遅い領域を調査・評価する技術の高度化」において地質環境モデルを検討する際に活用できるものである。
萩原 開人*; 矢野 孝臣*; Das, P. K.*; Lorenz, S.*; 王 岩*; 作田 誠*; 木村 敦; 中村 詔司; 岩本 信之; 原田 秀郎; et al.
Progress of Theoretical and Experimental Physics (Internet), 2019(2), p.023D01_1 - 023D01_26, 2019/02
被引用回数:42 パーセンタイル:88.42(Physics, Multidisciplinary)We have measured the  -ray energy spectrum from the thermal neutron capture,
-ray energy spectrum from the thermal neutron capture, 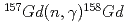 , on an enriched
, on an enriched  Gd target (
Gd target ( ) in the energy range from 0.11 MeV up to about 8 MeV. The target was placed inside the germanium spectrometer of the ANNRI detector at J-PARC and exposed to a neutron beam from the Japan Spallation Neutron Source (JSNS). Radioactive sources (
) in the energy range from 0.11 MeV up to about 8 MeV. The target was placed inside the germanium spectrometer of the ANNRI detector at J-PARC and exposed to a neutron beam from the Japan Spallation Neutron Source (JSNS). Radioactive sources ( Co,
Co,  Cs, and
Cs, and  Eu) and the reaction
Eu) and the reaction  were used to determine the spectrometer's detection efficiency for
were used to determine the spectrometer's detection efficiency for  rays at energies from 0.3 to 8.5 MeV. Using a Geant4-based Monte Carlo simulation of the detector and based on our data, we have developed a model to describe the
rays at energies from 0.3 to 8.5 MeV. Using a Geant4-based Monte Carlo simulation of the detector and based on our data, we have developed a model to describe the  -ray spectrum from the thermal
-ray spectrum from the thermal 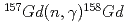 reaction. While we include the strength information of 15 prominent peaks above 5 MeV and associated peaks below 1.6 MeV from our data directly into the model, we rely on the theoretical inputs of nuclear level density and the photon strength function of
reaction. While we include the strength information of 15 prominent peaks above 5 MeV and associated peaks below 1.6 MeV from our data directly into the model, we rely on the theoretical inputs of nuclear level density and the photon strength function of  Gd to describe the continuum
Gd to describe the continuum  -ray spectrum from the
-ray spectrum from the 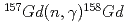 reaction. The results of the comparison between the observed
reaction. The results of the comparison between the observed  -ray spectra from the reaction and the model are reported in detail.
-ray spectra from the reaction and the model are reported in detail.
 Gd(n,
Gd(n, ) induced by thermal and epithermal neutrons
) induced by thermal and epithermal neutronsMastromarco, M.*; Manna, A.*; Aberle, O.*; Andrzejewski, J.*; 原田 秀郎; 木村 敦; n_TOF Collaboration*; 他116名*
European Physical Journal A, 55(1), p.9_1 - 9_20, 2019/01
被引用回数:27 パーセンタイル:89.73(Physics, Nuclear)Neutron capture cross section measurements on  Gd and
Gd and  Gd were performed using the time-of-flight technique at the n_TOF facility at CERN on isotopically enriched samples. The measurements were carried out in the n TOF experimental area EAR1, at 185m from the neutron source, with an array of 4 C
Gd were performed using the time-of-flight technique at the n_TOF facility at CERN on isotopically enriched samples. The measurements were carried out in the n TOF experimental area EAR1, at 185m from the neutron source, with an array of 4 C D
D liquid scintillation detectors. At a neutron kinetic energy of 0.0253eV, capture cross sections of 62.2(2.2) and 239.8(8.4) kilobarn have been derived for
liquid scintillation detectors. At a neutron kinetic energy of 0.0253eV, capture cross sections of 62.2(2.2) and 239.8(8.4) kilobarn have been derived for  Gd and
Gd and  Gd, respectively, with up to 6% deviation relative to values presently reported in nuclear data libraries, but consistent with those values within 1.6 standard deviations. A resonance shape analysis has been performed in the resolved resonance region up to 181eV and 307eV, respectively for
Gd, respectively, with up to 6% deviation relative to values presently reported in nuclear data libraries, but consistent with those values within 1.6 standard deviations. A resonance shape analysis has been performed in the resolved resonance region up to 181eV and 307eV, respectively for  Gd and
Gd and  Gd, where on average, resonance parameters have been found in good agreement with evaluations. Above these energies and up to 1keV, the observed resonance-like structure of the cross section has been analysed and characterised. From a statistical analysis of the observed neutron resonances we deduced: neutron strength function of 2.01(28)
Gd, where on average, resonance parameters have been found in good agreement with evaluations. Above these energies and up to 1keV, the observed resonance-like structure of the cross section has been analysed and characterised. From a statistical analysis of the observed neutron resonances we deduced: neutron strength function of 2.01(28)  10
10 and 2.17(41)
and 2.17(41)  10
10 ; average total radiative width of 106.8(14)meV and 101.1(20)meV and s-wave resonance spacing 1.6(2)eV and 4.8(5)eV for n +
; average total radiative width of 106.8(14)meV and 101.1(20)meV and s-wave resonance spacing 1.6(2)eV and 4.8(5)eV for n +  Gd and n +
Gd and n +  Gd systems, respectively.
Gd systems, respectively.
 -decay half-lives of new neutron-rich rare-earth isotopes
-decay half-lives of new neutron-rich rare-earth isotopes  Pm,
Pm,  Sm, and
Sm, and  Gd
Gd市川 進一; 浅井 雅人; 塚田 和明; 羽場 宏光*; 永目 諭一郎; 柴田 理尋*; 阪間 稔*; 小島 康明*
Physical Review C, 71(6), p.067302_1 - 067302_4, 2005/06
被引用回数:19 パーセンタイル:74.38(Physics, Nuclear)ガスジェット搬送装置と結合したオンライン同位体分離器を用い、ウランの陽子誘起核分裂で生成する中性子過剰未知希土類核、 Pm,
Pm,  Sm,
Sm,  Gdを発見し、それぞれの半減期を1.5
Gdを発見し、それぞれの半減期を1.5 0.2s, 2.4
0.2s, 2.4 0.5s, 4.8
0.5s, 4.8 1.0sと決定した。また、
1.0sと決定した。また、 Gdについては部分崩壊図式を構築した。さらに、以前に見いだした
Gdについては部分崩壊図式を構築した。さらに、以前に見いだした Tbの半減期を精度よく再測定し25.6
Tbの半減期を精度よく再測定し25.6 2.2sと決定した。本研究で見いだした新核種の半減期は、大局的理論で予測された半減期と良い一致を見た。
2.2sと決定した。本研究で見いだした新核種の半減期は、大局的理論で予測された半減期と良い一致を見た。
遠藤 聖*; 柴田 靖*; 吉田 文代*; 中井 啓*; 山本 哲哉*; 松村 明*; 石井 慶造*; 酒井 卓郎; 佐藤 隆博; 及川 将一*; et al.
Proceedings of 11th World Congress on Neutron Capture Therapy (ISNCT-11) (CD-ROM), 2 Pages, 2004/10
原研の高崎研究所にあるシングルエンド加速器(Micro PIXE)を用いて細胞内でのホウ素及びガドリニウムの定量を試みた。Micro PIXEは直径1 m以下のマイクロビームを用いて元素分布の分析を可能にするものである。実験の結果、P, S, Gd等の分布を分析することが可能であることがわかった。しかし、K及びGdが細胞周辺に分布していることから、細胞壁の破壊や細胞内への取り込み不全が考えられた。今後、これらの問題に対処するとともに、細胞内のホウ素分布を求め、BNCTの有効活用に資する予定である。
m以下のマイクロビームを用いて元素分布の分析を可能にするものである。実験の結果、P, S, Gd等の分布を分析することが可能であることがわかった。しかし、K及びGdが細胞周辺に分布していることから、細胞壁の破壊や細胞内への取り込み不全が考えられた。今後、これらの問題に対処するとともに、細胞内のホウ素分布を求め、BNCTの有効活用に資する予定である。
Krasznahorkay, A.*; 秋宗 秀俊*; Van den Berg, A. M.*; Blasi, N.*; Brandenburg, S.*; Csatl s, M.*; 藤原 守; Guly
s, M.*; 藤原 守; Guly s, J.*; Harakeh, M. N.*; Hunyadi, M.*; et al.
s, J.*; Harakeh, M. N.*; Hunyadi, M.*; et al.
Nuclear Physics A, 731, p.224 - 234, 2004/02
被引用回数:75 パーセンタイル:94.25(Physics, Nuclear)中性子スキン厚を測定する方法を議論し、最新の実験結果をSnと Pbについて紹介する。巨大双極子共鳴を励起する方法がその一つである。この方法では中性子スキンの相対的大きさを測定した。スピン反転双極子共鳴を励起するのが二つ目の方法で、Sn原子核に対して行った(
Pbについて紹介する。巨大双極子共鳴を励起する方法がその一つである。この方法では中性子スキンの相対的大きさを測定した。スピン反転双極子共鳴を励起するのが二つ目の方法で、Sn原子核に対して行った( He,t)反応から得た結果は、以前の実験結果や理論と良い一致を示している。
He,t)反応から得た結果は、以前の実験結果や理論と良い一致を示している。
 O
O -ZrO
-ZrO system
systemWang, J.*; 音部 治幹; 中村 彰夫; 竹田 満洲雄*
Journal of Solid State Chemistry, 176(1), p.105 - 110, 2003/11
被引用回数:14 パーセンタイル:43.66(Chemistry, Inorganic & Nuclear)メスバウア分光法及び粉末X線回折法,点電荷モデルによる計算を用いて、蛍石型及びパイロクロア型構造を持つGd Zr
Zr O
O (0.18
(0.18 x
x 0.62)の結晶構造とGd周りの電場勾配の相関を調べた。 理想的なパイロクロア構造(x=0.5)の時、四極子結合係数は特徴的に最大になることがわかった。また、点電荷モデルによる計算と電場勾配を比較することにより、提案されているパイロクロア構造を基礎にした構造モデルの有効性を検討した。
0.62)の結晶構造とGd周りの電場勾配の相関を調べた。 理想的なパイロクロア構造(x=0.5)の時、四極子結合係数は特徴的に最大になることがわかった。また、点電荷モデルによる計算と電場勾配を比較することにより、提案されているパイロクロア構造を基礎にした構造モデルの有効性を検討した。
 O
O -ZrO
-ZrO system xGdO
system xGdO -(1-x)ZrO
-(1-x)ZrO with 0.18
with 0.18  x
x  0.62
0.62Wang, J.*; 中村 彰夫; 竹田 満洲雄*
Solid State Ionics, 164(3-4), p.185 - 191, 2003/11
被引用回数:36 パーセンタイル:79.79(Chemistry, Physical)ガドリニアージルコニア系(xGdO -(1-x)ZrO
-(1-x)ZrO : x=0.18-0.62)の構造を155Gdメスバウア分光法と粉末X線回折により調べた。この結果、x=0.18-0.50の組成域では、螢石型及びパイロクロア型化合物の両相で、Gdイオンの周りの局所構造(局所的な酸素配置)は似通っていることがわかった。他方、x=0.50-0.62の組成域では、これらは少し違ってくる。48f-サイトにある6個の酸素イオンの螢石型構造の理想位置からの変位(ずれ)は、x=0.18-0.50で大きくなり、x=0.50-0.62でわずかに小さくなる。つまり、酸素変位は、定比パイロクロア相Gd
: x=0.18-0.62)の構造を155Gdメスバウア分光法と粉末X線回折により調べた。この結果、x=0.18-0.50の組成域では、螢石型及びパイロクロア型化合物の両相で、Gdイオンの周りの局所構造(局所的な酸素配置)は似通っていることがわかった。他方、x=0.50-0.62の組成域では、これらは少し違ってくる。48f-サイトにある6個の酸素イオンの螢石型構造の理想位置からの変位(ずれ)は、x=0.18-0.50で大きくなり、x=0.50-0.62でわずかに小さくなる。つまり、酸素変位は、定比パイロクロア相Gd Zr
Zr O
O (x=0.5)で最も大きくなる。
(x=0.5)で最も大きくなる。
 -ray spectroscopy for neutron-rich A
-ray spectroscopy for neutron-rich A 160-170 nuclei; The
160-170 nuclei; The  decay of
decay of  Pm,
Pm,  Sm,
Sm,  Eu,
Eu,  Gd, and
Gd, and  Tb
Tb浅井 雅人; 市川 進一; 塚田 和明; 長 明彦; 西中 一朗; 永目 諭一郎; 小島 康明*; 柴田 理尋*
Fission and Properties of Neutron-Rich Nuclei; Proceedings of 3rd International Conference, p.227 - 232, 2003/10
陽子誘起核分裂で生成する質量数160-170領域の中性子過剰核をオンライン同位体分離装置を用いて質量分離し、 崩壊
崩壊 線核分光の手法により核構造を研究した。
線核分光の手法により核構造を研究した。 Pm,
Pm, Sm,
Sm, Gdの観測に初めて成功し半減期を決定するとともに、娘核のエネルギー準位を明らかにした。また
Gdの観測に初めて成功し半減期を決定するとともに、娘核のエネルギー準位を明らかにした。また Eu,
Eu, Gdの崩壊
Gdの崩壊 線の測定にも成功し、その結果から
線の測定にも成功し、その結果から Euの基底状態のスピンが5あるいは6であると推定された。
Euの基底状態のスピンが5あるいは6であると推定された。
松田 敬子*; 西岡 孝明*; 木下 賢吾*; 川端 猛*; 郷 信広
Protein Science, 12(10), p.2239 - 2251, 2003/10
被引用回数:10 パーセンタイル:16.75(Biochemistry & Molecular Biology)蛋白質のスーパーファミリーの分類はアミノ酸配列,グローバルフォード,部分構造または機能などさまざまな基準でなされている。私達はグローバルフォールドと機能の関係だけでスーパーファミリーを定義できるかどうか調べた。はじめに、ベーターシートのトポロジーにもとづいて蛋白質のドメインを分類した。そして、分子進化の過程においてベーターシートの両端にストランドが1本だけ付加あるいは削除されて新しいベーターシートが作り出された、という仮定をしてベーターシート間の類縁関係を定義することにした。このベーターシート間の類縁関係に基づいて、あるドメインが他のドメインに進化するのに必要な進化的イベントの数が2つのドメイン間の距離を表すように、蛋白質ドメインのネットワークを構築した。その後、core chemical functionが既知であるATP関連ドメインについてネットワーク上にマップした。解析の結果、ネットワーク上に分布したドメインは20個強の分離したクラスターを形成した。この結果は20個強のATP結合蛋白質のスーパーファミリーは各々独立に分子進化の過程で創成されたことを示している。このようにドメインのグルーバルフォールドと機能を保存しながら進化したことが、今日みられる蛋白質の構造と機能の関係が生まれた原因である。
 Gd
Gd早川 岳人; 藤 暢輔; 大島 真澄; 松田 誠; 初川 雄一; 篠原 伸夫; 飯村 秀紀; 静間 俊行; Zhang, Y.*; 菅原 昌彦*; et al.
Physics Letters B, 551(1-2), p.79 - 85, 2003/01
被引用回数:11 パーセンタイル:57.41(Astronomy & Astrophysics)原研のタンデム加速器を用いて加速した136Xeビームを、157Gdの金属薄膜に照射した。157Gdは多重クーロン励起反応によって高スピン状態まで励起された。励起された157Gdから放出された 線を多重
線を多重 線検出装置を用いてインビーム
線検出装置を用いてインビーム 線核分光の手法で測定を行った。157Gdのサイドバンド及び、サイドバンドと基底状態バンド間の多数のE1遷移の
線核分光の手法で測定を行った。157Gdのサイドバンド及び、サイドバンドと基底状態バンド間の多数のE1遷移の 線を発見した。これらの計測によって157Gdの正と負のパリティを持つ2つのイラストバンドが明確になった。基底状態バンドの励起状態の半減期はわれわれの過去の研究によって測定されていたので、E1遷移強度を導出することができた。この2つのバンド間のE1遷移は原子核の高励起状態で観測される中では相対的に大強度であり、さらに強い角運動量依存性が存在することを発見した。これらは、E1遷移オペレーターに八重極振動の影響を現象論的に加えることで理解できる。
線を発見した。これらの計測によって157Gdの正と負のパリティを持つ2つのイラストバンドが明確になった。基底状態バンドの励起状態の半減期はわれわれの過去の研究によって測定されていたので、E1遷移強度を導出することができた。この2つのバンド間のE1遷移は原子核の高励起状態で観測される中では相対的に大強度であり、さらに強い角運動量依存性が存在することを発見した。これらは、E1遷移オペレーターに八重極振動の影響を現象論的に加えることで理解できる。
小西 哲之; 時松 宏治*
プラズマ・核融合学会誌, 78(11), p.1192 - 1198, 2002/11
今世紀後半の核融合エネルギーの寄与を、エネルギーモデルを用いて評価した。核融合の経済的なインパクトは、将来のエネルギー支出の削減,エネルギー市場での売り上げによるGDPの増加,核融合発電関連機器の売り上げの面から評価できる。エネルギー市場での核融合のシェアは、導入時期により大きく異なり、導入時期は核融合が市場での競合可能となるコストを達成する時期によって決められる。この競合可能コストは、他のエネルギー源に対する環境制約の影響が大きい。モデル計算の結果、核融合は環境制約のある場合には大きな市場可能性を持っていること、ことにエネルギー需要が大きく増加する途上国地域への機器輸出の効果が大きいことが見いだされた。この経済効果と比較することにより現在の研究開発の意義を分析することも可能であるが、将来価値は割引率により現在に換算すると大きく減ずる。
井上 登美夫*; 早川 和重*; 塩足 春隆*; 高田 栄一*; 取越 正己*; 永澤 清*; 萩原 一男*; 柳澤 和章
Journal of Nuclear Science and Technology, 39(10), p.1114 - 1119, 2002/10
被引用回数:4 パーセンタイル:28.58(Nuclear Science & Technology)本件は、平成11年度及び平成12年度に調査した「我が国の放射線利用経済規模」、「我が国と米国の放射線利用経済規模」に関連して、医学・医療利用についての報告である。調査の結果は次のとおりである。(1)米国医療費132兆円の89%を占める個人医療費117兆円に対し我が国の国民医療費29兆円である。両者には4倍の差異がある。(2)放射線利用項目のうち経済規模が大きい順に並べると、(a)画像診断(X線,CT,核医学),(b)医療機器,(c)造影剤,(d)放射線医薬品,(e)前立腺がん(粒子線治療を含む),(f)RI,(g)EDGPET等の順となる。(3)日米の放射線利用経済規模は、米国5.9兆円に対して日本は1.4兆円である。両者で約4倍の差異がある。医療費総額に対する割合は、米国5.9/117 100=5%、我が国は1.4/29
100=5%、我が国は1.4/29 100=4.8%となる。即ち、医学・医療における放射線利用率は日米ほとんど変わらず約5%となっている。
100=4.8%となる。即ち、医学・医療における放射線利用率は日米ほとんど変わらず約5%となっている。
柳澤 和章; 久米 民和; 幕内 恵三; 田川 精一*; 茅野 光男*; 井上 登美夫*; 武久 正昭*; 萩原 幸*; 清水 雅彦*
Journal of Nuclear Science and Technology, 39(10), p.1120 - 1124, 2002/10
被引用回数:3 パーセンタイル:22.58(Nuclear Science & Technology)本件は、日本原子力学会からの投稿依頼に応えたものである。発表内容は、平成11年度に調査した「我が国の放射線利用経済規模」及び平成12年度に実施した「我が国と米国の放射線利用経済規模」をとりまとめたものである。調査対象が膨大であるので、(1)工業利用,(2)農業利用,(3)医学・医療利用,(4)原発と放射線利用の4つに仕分けした。本件は(4)原発と放射線利用についての報告である。なお、上記調査はいずれも文部科学省の委託調査(特会)であり、成果の発表にあたっては相手方の了解を得ている。主な成果; 1997年における米国の原子力売上は158b$であり、内訳は放射線利用が119b$(75%),原発売上が39b$(25%)であった。此に対して我が国の原子力売上は99b$で、内訳は放射線利用が52b$(53%),原発売上が47b$(47%)であった。米国の原子力売上は我が国の約1.6倍となったが、米国では工業と医学・医療の分野で放射線利用が積極的になされていることが一つの理由である。相対的であるが、原発売上額は米国よりも我が国の方が大きい。
久米 民和; 天野 悦夫*; 中西 友子*; 茅野 光男*
Journal of Nuclear Science and Technology, 39(10), p.1106 - 1113, 2002/10
被引用回数:4 パーセンタイル:28.58(Nuclear Science & Technology)本件は、平成11年度及び平成12年度に調査した「我が国の放射線利用経済規模」、「我が国と米国の放射線利用経済規模」に関連して、農業利用についての報告である。調査の結果は次のとおりである。(1)食品照射: 米国の食品照射経済規模はスパイス価格で幅が出る。最小(スパイス1.5$/lb)で206億円,最大(スパイス34$/lb)で3,903億円である(1999年度データ)である。いずれにしても我が国19億円の11倍から205倍の規模である。種類も馬鈴薯だけの我が国とは対照的にスパイス,果実・野菜,トリ肉と種類が多い。(2)突然変異育種: 米国128品種,日本120品種とほぼ同じ数の品種が育成されている。本調査推奨値は、最大のケースである。この場合、米国は1兆3,593億円であり、稲中心の突然変異品種17品種から得た我が国の経済規模973億円の14倍となる。(3)日米農業の放射線利用比較: 米国は17,496億円(対GDP比0.2%)であった。一方、我が国は992億円(対GDP比0.02%)であった。米国の放射線農業利用経済規模は我が国の18倍であった。
幕内 恵三; 田川 精一*; 柏木 正之*; 釜田 敏光*; 関口 正之*; 細淵 和成*; 富永 洋*; 大岡 紀一
Journal of Nuclear Science and Technology, 39(9), p.1002 - 1007, 2002/09
被引用回数:6 パーセンタイル:38.77(Nuclear Science & Technology)本件は、平成11年度及び平成12年度に実施した「我が国の放射線利用経済規模」、「我が国と米国の放射線利用経済規模」に関連し、工業利用についての報告である。調査の結果は次のとおりである。(1)米国放射線利用項目を経済規模が大きい順に並べると、(a)半導体加工(4.5兆円),(b)タイヤ(1.6兆円),(c)医療用具の滅菌(約5,800億円),(d)非破壊検査(約780億円)の順となる。傾向は我が国も同じである。この(a)から(d)の合計(特化項目の合計)は、米国が約6.7兆円,我が国が約4.7兆円となる。この規模比率は1.4である。全体的に見ると放射線工業利用製品を、米国は大量に安く生産している。(2)1997年における米国のGDPは1,006兆円、此に対する日本のGDPは512兆円である。米国は日本の約2倍である。米国特化項目の合計の対GDP比は0.7%,我が国限定項目の合計の対GDP比は0.9%となる。両者はほとんど差がない。
藤原 守; 川畑 貴裕*; Mohr, P.*
Journal of Physics G; Nuclear and Particle Physics, 28(4), p.643 - 648, 2002/04
被引用回数:13 パーセンタイル:57.78(Physics, Nuclear)太陽ニュートリノ検出器としてYbやGd金属を使用し、20~30トンもの巨大な検出器を作ろうとの計画がある。このような場合に 崩壊がYbやGdから発生するとバックグラウンドとなり測定に支障が発生する。論文では
崩壊がYbやGdから発生するとバックグラウンドとなり測定に支障が発生する。論文では Gdが問題となることを指摘し、かつ、
Gdが問題となることを指摘し、かつ、 Ybが極端な長寿命
Ybが極端な長寿命 崩壊核であり、この寿命が測定可能なも知れないことを指摘した。また、希土類アイソトープに対しての
崩壊核であり、この寿命が測定可能なも知れないことを指摘した。また、希土類アイソトープに対しての 崩壊寿命に対する公式を導出した。
崩壊寿命に対する公式を導出した。
Wang, S. C.*; Wong, H. T.*; 藤原 守
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 479(2-3), p.498 - 510, 2002/03
被引用回数:24 パーセンタイル:79.81(Instruments & Instrumentation)GSO結晶中に含まれる極めて微量の放射性同位体元素を測定した。GSO中に含まれるものは Thや
Thや Uがあり、太陽ニュートリノ検出器のためにこれらの放射性元素をどの程度、減少すべきかを議論した。
Uがあり、太陽ニュートリノ検出器のためにこれらの放射性元素をどの程度、減少すべきかを議論した。 Gdは二重
Gdは二重 崩壊核であり、この原子核の半減期の上限を求めた。
崩壊核であり、この原子核の半減期の上限を求めた。
久米 民和
Proceedings of 24th JAIF-KAIF Seminar on Nuclear Industry, p.RI_1_1 - RI_1_12, 2002/00
日本における放射線利用の現状について、平成11年度に実施した放射線利用経済規模調査結果に基づき紹介する。平成9年度におけるわが国の放射線利用経済規模は8兆5699億円であり、GDP比約1.7%であった。内訳は、工業利用7兆2627億円(85%),医学・医療1兆1905億円(14%),農業1167億円(1%)である。工業利用分野の主なものは、イオンビーム処理製品,放射線加工処理製品,放射線滅菌,照射施設などであり、とくにIC製造などのイオンビーム処理が全体の75%を占めていた。放射線医学・医療分野では、大部分が医科利用と歯科治療であり、その比率は91%:9%であった。農業利用分野は、馬鈴薯照射の食品照射,不妊虫放飼法によるウリミバエの根絶,コメやナシなどの突然変異育種,RI利用が主なものであるが、他の分野に比べ規模が小さいことが明らかとなった。