Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
伊藤 孝; 門野 良典*
Journal of the Physical Society of Japan, 93(4), p.044602_1 - 044602_7, 2024/04
被引用回数:0We propose a model to describe the fluctuations in the internal magnetic field due to ion dynamics observed in muon spin relaxation ( SR) by an Edwards-Anderson-type autocorrelation function that separates the quasi-static and dynamic components of the correlation by the parameter
SR) by an Edwards-Anderson-type autocorrelation function that separates the quasi-static and dynamic components of the correlation by the parameter  (where
(where  ). Our Monte Carlo simulations for this model showed that the time evolution of muon spin polarization deviates significantly from the Kubo-Toyabe function. To further validate the model, the results of simulations were compared with the
). Our Monte Carlo simulations for this model showed that the time evolution of muon spin polarization deviates significantly from the Kubo-Toyabe function. To further validate the model, the results of simulations were compared with the  SR spectra observed in a hybrid organic-inorganic perovskite FAPbI
SR spectra observed in a hybrid organic-inorganic perovskite FAPbI [with FA referring to HC(NH
[with FA referring to HC(NH )
) ], where local field fluctuations associated with the rotational motion of FA molecules and quasi-static fields from the PbI
], where local field fluctuations associated with the rotational motion of FA molecules and quasi-static fields from the PbI lattice are presumed to coexist. The least-squares curve fitting showed reasonable agreement with the model with
lattice are presumed to coexist. The least-squares curve fitting showed reasonable agreement with the model with 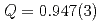 , and the fluctuation frequency of the dynamical component was obtained. This result opens the door to the possibility of experimentally distinguishing fluctuations due to the dynamics of ions around muons from those due to the self-diffusion of muons. On the other hand, it suggests the need to carefully consider the spin relaxation function when applying
, and the fluctuation frequency of the dynamical component was obtained. This result opens the door to the possibility of experimentally distinguishing fluctuations due to the dynamics of ions around muons from those due to the self-diffusion of muons. On the other hand, it suggests the need to carefully consider the spin relaxation function when applying  SR to the issue of ion dynamics.
SR to the issue of ion dynamics.
高性能計算技術利用推進室
JAEA-Review 2023-018, 159 Pages, 2023/12
日本原子力研究開発機構では、原子力の総合的研究開発機関として原子力に係わるさまざまな分野の研究開発を行っており、これらの研究開発の多くにおいて計算科学技術が活用されている。日本原子力研究開発機構における計算科学技術を活用した研究開発の論文発表は、過去十数年にわたり、毎年度、全体の約2割を占めている。大型計算機システムはこの計算科学技術を支える重要なインフラとなっている。大型計算機システムは、優先課題として位置付けられたカーボンニュートラルに貢献する軽水炉、高温ガス炉、高速炉の研究開発や、原子力科学技術に関する多様な研究開発、東京電力福島第一原子力発電所事故対応に関する研究開発、高レベル放射性廃棄物の処理・処分技術の開発、原子力安全規制・原子力防災支援、そのための安全研究等といった主要事業に利用された。本報告は、令和4年度における大型計算機システムを利用した研究開発の成果を中心に、それを支える利用支援、利用実績、システムの概要等をまとめたものである。
永井 晴康; 古田 禄大*; 中山 浩成; 佐藤 大樹
Journal of Nuclear Science and Technology, 60(11), p.1345 - 1360, 2023/11
被引用回数:0 パーセンタイル:0.01(Nuclear Science & Technology)放射性プルームの3次元分布を定量的に可視化するとともに放射性核種の放出量を推定する革新的なモニタリング手法を提案し、その実現性を予備的な試験により確認した。提案する手法は、電子飛跡検出型コンプトンカメラ(ETCC)によるガンマ線画像分光測定とドップラーライダーによる3次元風速測定に基づくリアルタイム高分解能大気拡散シミュレーションを組み合わせている。複数箇所に設置したETCCで測定された放射性プルーム中の個々の放射性核種からのラインガンマ線画像とリアルタイム大気拡散計算による大気中濃度分布情報を融合した逆解析により、放射性核種ごとの3次元濃度分布を再構成する。大気拡散シミュレーションと放射線輸送計算で生成した仮想的な実験データを用いた試験により、試作した解析手法が十分な性能を有することを示した。
涌井 隆; 高岸 洋一*; 二川 正敏
Materials, 16(17), p.5830_1 - 5830_16, 2023/09
被引用回数:0 パーセンタイル:0(Chemistry, Physical)水銀ターゲット容器は、陽子ビームの入射に伴い、キャビテーション損傷を受けるため、キャビテーションバブルの位置や衝撃圧力分布の不確実さを考慮して、モンテカルロ・シミュレーションを用いたキャビテーション損傷を予測する手法を提案した。本手法では、個々のキャビテーション気泡の崩壊に起因する衝撃圧力の分布はガウス分布とし、衝撃圧力の最大値の確率密度分布は3種類の分布: デルタ関数、ガウス分布、ワイブル分布と仮定した。衝撃圧力の分布を記述する方程式の2つのパラメータについて、実験から得られたキャビテーション損傷の分布とシミュレーションから得られた累積塑性ひずみの分布を比較し、ベイズ最適化を使用して推定することができた。また、ワイブル分布を用いて得られた結果が、他の結果に比べて、実際のキャビテーションエロージョン現象を再現することが分かった。
 sp
sp HRL
HRL澤田 淳; 坂本 和彦*; 綿引 孝宜*; 今井 久*
SKB P-17-06, 154 Pages, 2023/08
An aim of Task 8, which was 8th modeling task of the SKB Task Forces on Groundwater Flow and Transport of Solutes, was to improve the knowledge of the bedrock-bentonite interface with regard to groundwater flow, mainly based on a set of data obtained by Bentonite Rock Interaction Experiment (BRIE) at  sp
sp . JAEA had developed an approach to Task 8 assuming that the discrete features dominate the delivery of groundwater to the bentonite columns emplaced into the vertically drilled boreholes from TASO tunnel floor, resulting in heterogeneous bentonite wetting behavior. This assumption was implemented as a FracMan Discrete Fracture Network (DFN) model for groundwater flow. Due to the assumption, no permeable rock matrix was implemented. The variability and uncertainty of this stochastic "HydroDFN" model was constrained by conditioning the model to match measured fracture location and orientation, and specific capacity (transmissivity) data observed at five probe boreholes. Groundwater from the HydroDFN being delivered to the bentonite columns, was modeled using Thames code with implementing a specific feature at the interface between the fractured rock mass and the bentonite. This modeling approach and the assumption of fracture dominated bentonite wetting appears to be able to provide a reasonable approximation to the observed heterogeneous bentonite wetting behavior of BRIE. We would suggest that a systematic investigation at pilot holes, including both geological mapping of the fractures and also testing of the hydraulic properties, might be required to get more practical prediction of heterogeneous wetting behavior in bentonite, as observed in BRIE.
. JAEA had developed an approach to Task 8 assuming that the discrete features dominate the delivery of groundwater to the bentonite columns emplaced into the vertically drilled boreholes from TASO tunnel floor, resulting in heterogeneous bentonite wetting behavior. This assumption was implemented as a FracMan Discrete Fracture Network (DFN) model for groundwater flow. Due to the assumption, no permeable rock matrix was implemented. The variability and uncertainty of this stochastic "HydroDFN" model was constrained by conditioning the model to match measured fracture location and orientation, and specific capacity (transmissivity) data observed at five probe boreholes. Groundwater from the HydroDFN being delivered to the bentonite columns, was modeled using Thames code with implementing a specific feature at the interface between the fractured rock mass and the bentonite. This modeling approach and the assumption of fracture dominated bentonite wetting appears to be able to provide a reasonable approximation to the observed heterogeneous bentonite wetting behavior of BRIE. We would suggest that a systematic investigation at pilot holes, including both geological mapping of the fractures and also testing of the hydraulic properties, might be required to get more practical prediction of heterogeneous wetting behavior in bentonite, as observed in BRIE.
システム計算科学センター
JAEA-Evaluation 2023-001, 38 Pages, 2023/07
システム計算科学センターでは、「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の中長期目標を達成するための計画(中長期計画)」に基づき、原子力分野における計算科学技術研究に関する研究開発を実施してきた。その計算科学技術研究の実績については、計算科学技術研究・評価委員会(以下「委員会」という。)により評価された。本報告は、システム計算科学センターにおいて実施された計算科学技術研究の、令和4年度における業務の実績及びそれらに対する委員会による評価結果をとりまとめたものである。
安部 諭; 柴本 泰照
Nuclear Engineering and Technology, 55(5), p.1742 - 1756, 2023/05
被引用回数:0 パーセンタイル:0.01(Nuclear Science & Technology)The hydrogen behavior in a nuclear containment vessel is a significant issue when discussing the potential of hydrogen combustion during a severe accident. After the Fukushima-Daiichi accident in Japan, we have investigated in-depth the hydrogen transport mechanisms by utilizing experimental and numerical approaches. Computational fluid dynamics is a powerful tool for better understanding the transport behavior of gas mixtures, including hydrogen. This paper describes a large-eddy simulation of gas mixing driven by a high-buoyancy flow. We focused on the interaction behavior of heat and mass transfers driven by the horizontal high-buoyant flow during density stratification. For validation, the experimental data of the Containment InteGral effects Measurement Apparatus (CIGMA) facility were used. With a high-power heater for the gas-injection line in the CIGMA facility, a high temperature flow of approximately 390 C was injected into the test vessel. By using the CIGMA facility, we can extend the experimental data to the high temperature region. The phenomenological discussion in this paper help understand the heat and mass transfer induced by the high-buoyancy flow in the containment vessel during a severe accident.
C was injected into the test vessel. By using the CIGMA facility, we can extend the experimental data to the high temperature region. The phenomenological discussion in this paper help understand the heat and mass transfer induced by the high-buoyancy flow in the containment vessel during a severe accident.
石井 克典; 青木 健; 井坂 和義; 野口 弘喜; 清水 厚志; 佐藤 博之
Proceedings of 30th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE30) (Internet), 9 Pages, 2023/05
JAEA initiated High Temperature engineering Test Reactor (HTTR) heat application test project to establish coupling technologies between HTGR and a hydrogen production plant necessary to achieve large-scale, low cost, and carbon-free hydrogen production. One important element for the coupling technologies is a system analysis code which can simulate dynamic behavior of a HTGR hydrogen production system to design a plant control system for the effects of circulated helium heat through both facilities. The code is required to deal with a complex system which involves several subsystems and different physics with different timescales. As a first step of the development, we developed a heat and mass balance evaluation model of a helium-heated steam reformer. This report will present the outline of the developed model and simulation results with comparison to the experimental results.
Rodriguez, D.; Rossi, F.
Proceedings of INMM & ESARDA Joint Annual Meeting 2023 (Internet), 9 Pages, 2023/05
Under the MEXT subsidy for the improvement of nuclear security related activities, we will present on the current and future progress of the delayed gamma-ray spectroscopic analysis development. We highlight a paper soon to be released and the plan for finalizing the project goal.
久保 光太郎; Jang, S.*; 高田 孝*; 山口 彰*
Journal of Nuclear Science and Technology, 60(4), p.359 - 373, 2023/04
被引用回数:5 パーセンタイル:83.25(Nuclear Science & Technology)確率論的リスク評価(PRA)は、原子力発電所の安全性を向上させるための重要なアプローチである。しかし、この手法では、複合ハザードのモデル化は困難である。地震に起因した溢水シナリオでは、地震による炉心損傷、溢水による炉心損傷、地震と溢水が組み合わさった炉心損傷といった複数の炉心損傷シーケンスを含んでいる。溢水に係るフラジリティは、溢水がタンクなどの水源から区画に伝播するため、時間依存性を有している。そのため、現実的なリスク評価及び定量化を行うためには、動的リスク評価を用いる必要がある。本研究では、地震,溢水,熱水力シミュレーションを連成させ、複数ハザード間の依存関係を明示的に考慮し、地震起因溢水のリスク評価を行った。特に、福島第一原子力発電所事故を踏まえた安全性向上対策に注目し、システムの耐力に関する感度解析と可搬型ポンプを用いた蒸気発生器代替注水の効果を評価した。我々は、シミュレーションに基づく動的PRA手法の複合ハザード起因のリスクの評価への使用を実証した。
安部 諭; 岡垣 百合亜
Nuclear Engineering and Design, 404, p.112165_1 - 112165_14, 2023/04
被引用回数:0 パーセンタイル:0.01(Nuclear Science & Technology)Pressurized Thermal Shock (PTS) is induced potentially by the rapid cooling of the cold-leg and downcomer wall in the primary system of a Pressurized Water Reactor (PWR) due to the initiation of Emergency Core Cooling System (ECCS). Thus, fluids mixing in a horizontal cold-leg and downcomer should be predicted accurately; however, turbulence production and damping often hinders this prediction due to the presence of the density gradients. Hence, the Fifth International Benchmark Exercise, the cold-leg mixing Computational Fluid Dynamics (CFD) Benchmark, was conducted under the support of OECD/NEA. The experiment was designed for visualization of the mixing phenomena of two liquids with different densities. The heavy liquid was a simulant of cold water from ECCS, in a horizontal leg and downcomer. We used the Large-eddy Simulation (LES) to investigate the time fluctuation behaviors of velocity and liquid concentration. The CFD simulation was performed with two turbulence models and three different numerical meshes. We investigated the characteristics of the appearance frequency of the heavy liquid concentration with the statistical method. Based on our findings, we propose further experiments and numerical investigations to understand the fluid mixing phenomena related to PTS.
廃炉環境国際共同研究センター; 東京大学*
JAEA-Review 2022-057, 98 Pages, 2023/02
日本原子力研究開発機構(JAEA)廃炉環境国際共同研究センター(CLADS)では、令和3年度英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業(以下、「本事業」という)を実施している。本事業は、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の廃炉等を始めとした原子力分野の課題解決に貢献するため、国内外の英知を結集し、様々な分野の知見や経験を、従前の機関や分野の壁を越えて緊密に融合・連携させた基礎的・基盤的研究及び人材育成を推進することを目的としている。平成30年度の新規採択課題から実施主体を文部科学省からJAEAに移行することで、JAEAとアカデミアとの連携を強化し、廃炉に資する中長期的な研究開発・人材育成をより安定的かつ継続的に実施する体制を構築した。本研究は、研究課題のうち、令和2年度に採択された「合理的な処分のための実機環境を考慮した汚染鉄筋コンクリート長期状態変化の定量評価」の令和3年度の研究成果について取りまとめたものである。本研究は、原子炉建屋内の鉄筋コンクリート部材における汚染濃度分布定量予測データベース構築を目的としている。令和3年度は、コンクリートのメソスケールのひび割れ挙動を評価するため、モルタルの乾燥、再吸水によって生じる変形および水分移動に関するデータを取得した。並行して、剛体バネモデルを用いて、コンクリートの材齢変化および温度・水・応力条件を考慮できるプログラムの開発を進めた。コンクリートマトリクスへの長期的な核種の浸透挙動を評価するため、収着に関するデータ取得および数理モデルの構築を行った。ひび割れを介したコンクリートへの核種の浸透挙動を評価するために、ひび割れ幅の異なるモルタル試験体に対する、事故直後の冷却水相当濃度でのCs、Srの浸透状況をオートラジオグラフィにより評価した。さらに、模擬ひび割れを導入したコンクリート試料を用意した。また、 核種のコンクリートマトリクスへの浸透挙動を調べるため、セメントペースト試験片の長期浸漬試験を開始するとともに、骨材、塗料、鉄筋に対する
核種のコンクリートマトリクスへの浸透挙動を調べるため、セメントペースト試験片の長期浸漬試験を開始するとともに、骨材、塗料、鉄筋に対する 核種の分配比を測定した。
核種の分配比を測定した。
廃炉環境国際共同研究センター; 東京工業大学*
JAEA-Review 2022-043, 52 Pages, 2023/01
日本原子力研究開発機構(JAEA)廃炉環境国際共同研究センター(CLADS)では、令和3年度英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業(以下、「本事業」という)を実施している。本事業は、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の廃炉等を始めとした原子力分野の課題解決に貢献するため、国内外の英知を結集し、様々な分野の知見や経験を、従前の機関や分野の壁を越えて緊密に融合・連携させた基礎的・基盤的研究及び人材育成を推進することを目的としている。平成30年度の新規採択課題から実施主体を文部科学省からJAEAに移行することで、JAEAとアカデミアとの連携を強化し、廃炉に資する中長期的な研究開発・人材育成をより安定的かつ継続的に実施する体制を構築した。本研究は、研究課題のうち、令和3年度に採択された「非接触測定法を用いた燃料デブリ臨界解析技術の高度化」の令和3年度の研究成果について取りまとめたものである。本研究は、非接触のアクティブ中性子法を用いた燃料デブリ臨界特性測定システムと多領域積分型動特性解析コードの開発による燃料デブリ臨界解析技術の高度化を目的とし、令和3年度から令和6年度の4年計画の1年目として日本側は東京工業大学(東工大)、産業技術総合研究所(産総研)が連携して実施し、ロシア側はロシア国立原子力研究大学(MEPhI)が実施した。日本側とロシア側でそれぞれが開発する臨界特性測定システムについて、計算精度向上のために、これまでの実験データの整理と予備解析を実施した。多領域積分型動特性解析コードの開発については、開発環境として開発専用メニーコアマルチノード並列計算・データサーバーを構築した。ロシア側が令和5年度に実施予定のコード検証に用いる代表的な解析条件を決定した。また、東工大とMEPhI間でオンラインによるワークショップを開催し、研究の今後の進め方に関する意見交換を行った。日本側の3機関は緊密に連携して研究を実施した。以上の活動により本研究の令和3年度の目的を達成することができた。
高性能計算技術利用推進室
JAEA-Review 2022-035, 219 Pages, 2023/01
日本原子力研究開発機構では、原子力の総合的研究開発機関として原子力に係わるさまざまな分野の研究開発を行っており、これらの研究開発の多くにおいて計算科学技術が活用されている。日本原子力研究開発機構における計算科学技術を活用した研究開発の論文発表は、全体の約2割を占めている。大型計算機システムはこの計算科学技術を支える重要なインフラとなっている。大型計算機システムは、優先課題として位置付けられた福島復興(環境の回復・原子炉施設の廃止措置)に向けた研究開発や、高速炉サイクル技術に関する研究開発、原子力の安全性向上のための研究、原子力基礎基盤研究等といった主要事業に利用された。本報告は、令和3年度における大型計算機システムを利用した研究開発の成果を中心に、それを支える利用支援、利用実績、システムの概要等をまとめたものである。
Zhang, T.*; 守田 幸路*; Liu, X.*; Liu, W.*; 神山 健司
Annals of Nuclear Energy, 179, p.109389_1 - 109389_10, 2022/12
被引用回数:1 パーセンタイル:29.26(Nuclear Science & Technology)The ID1 test was the final target test of the EAGLE experimental framework program. It was used to verify that during a core disruptive accident, the molten fuel could be discharged via wall failure of an inner duct in FAIDUS, a design concept for the sodium-cooled fast reactor. The ID1 results revealed that the wall failure behavior owed to the large heat flow from the surrounding fuel/steel mixture. The present study numerically investigated the heat transfer mechanisms in the test using the finite volume particle method in the three-dimensional domain. The thermal hydraulic behaviors during wall failure were reproduced reasonably. The present three-dimensional simulation mitigated inherent defects of our previous two-dimensional calculation and clarified that the solid fuel and liquid steel close to the outer surface of the duct can expose the duct to high thermal loads, resulting in the wall failure.
齋藤 龍郎; 山澤 弘実*; 望月 陽人
Journal of Environmental Radioactivity, 255, p.107035_1 - 107035_14, 2022/12
被引用回数:0 パーセンタイル:0(Environmental Sciences)琵琶湖の溶存ウラン(DU)の季節変動を、以下のモデル・パラメータ研究により再現した。導入したモデルは、水-DUの物質収支と、湖岸土壌におけるUO
 とH
とH のイオン交換である。最適化されたパラメータは4つであり、湖岸の陽イオン交換容量(CEC)、DUとAU(土壌吸着U)の和である全ウランTU、Uの急速な土壌吸着と脱着時の一次反応速度係数(kadsとkdes)であった。DUを構成する化学平衡を表し、各化学種の寄与を分析した結果、DUの季節変動はpHの季節変動に起因していることが示された。イオン交換平衡に、1日のAU比がkads以上に増加したとき、あるいはkdes以下に減少したときのみ1次速度反応に移行する補正を加えることにより、DU測定の再現性が向上し、DUピークがpHピークから遅れることが再現された。
のイオン交換である。最適化されたパラメータは4つであり、湖岸の陽イオン交換容量(CEC)、DUとAU(土壌吸着U)の和である全ウランTU、Uの急速な土壌吸着と脱着時の一次反応速度係数(kadsとkdes)であった。DUを構成する化学平衡を表し、各化学種の寄与を分析した結果、DUの季節変動はpHの季節変動に起因していることが示された。イオン交換平衡に、1日のAU比がkads以上に増加したとき、あるいはkdes以下に減少したときのみ1次速度反応に移行する補正を加えることにより、DU測定の再現性が向上し、DUピークがpHピークから遅れることが再現された。
廃炉環境国際共同研究センター; 京都大学*
JAEA-Review 2022-027, 85 Pages, 2022/11
日本原子力研究開発機構(JAEA)廃炉環境国際共同研究センター(CLADS)では、令和2年度英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業(以下、「本事業」という)を実施している。本事業は、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所(1F)の廃炉等をはじめとした原子力分野の課題解決に貢献するため、国内外の英知を結集し、様々な分野の知見や経験を、従前の機関や分野の壁を越えて緊密に融合・連携させた基礎的・基盤的研究及び人材育成を推進することを目的としている。平成30年度の新規採択課題から実施主体を文部科学省からJAEAに移行することで、JAEAとアカデミアとの連携を強化し、廃炉に資する中長期的な研究開発・人材育成をより安定的かつ継続的に実施する体制を構築した。本研究は、研究課題のうち、平成30年度に採択された「ガンマ線画像スペクトル分光法による高放射線場環境の画像化による定量的放射能分布解析法」の平成30年度から令和3年度の研究成果について取りまとめたものである(令和3年度まで契約延長)。本課題は令和3年度が最終年度となるため4年度分の成果を取りまとめた。本研究では、ガンマ線イメージング装置であるETCCを1F廃炉事業での使用可能な可搬型装置でかつ高線量環境下で動作可能なように改良し、廃炉の現場に導入できるようにした。ETCCは世界初の光学カメラと同じ全単射撮像が可能なガンマ線カメラである。そのためETCCは一般的な定量的画像解析法を放射線にも適用可能とすることが可能で、1Fの廃炉に係る解決すべき6つの重点課題に革新的進展をもたらす。例えば廃炉工事で発生する汚染の飛散を3次元ガンマ線イメージングによりオンラインで検知、さらに拡散の動的な検知から精度の高い拡散予想を可能にする。それを実証するため令和元年に、1F敷地内1㎞四方を一度に画像モニタリングし、同時に100か所以上のスペクトル観測を実現し、今まで不明だったスカイシャインガンマ線スペクトル及び分布の計測に成功した。さらに京都大学複合原子力科学研究所原子炉建屋内の3次元線量計測を実施、微量なAr41の大気拡散を3次元の動画撮像に成功。廃炉を超え一般の原子炉での高精度な放射線3次元画像モニタリング及び放射能拡散予想システムが実現できることを示す画期的な成果が得られた。
システム計算科学センター
JAEA-Evaluation 2022-004, 38 Pages, 2022/11
システム計算科学センターでは、「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の中長期目標を達成するための計画(中長期計画)」に基づき、原子力分野における計算科学技術研究に関する研究開発を実施してきた。その計算科学技術研究の実績については、計算科学技術研究・評価委員会(以下「委員会」という。)により評価された。本報告は、システム計算科学センターにおいて実施された計算科学技術研究の、令和3年度における業務の実績及びそれらに対する委員会による評価結果をとりまとめたものである。
システム計算科学センター
JAEA-Evaluation 2022-003, 61 Pages, 2022/11
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という)は、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(平成28年12月21日内閣総理大臣決定)及びこの大綱的指針を受けて作成された「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(平成29年4月1日文部科学大臣最終改定)、並びに原子力機構の「研究開発課題評価実施規程」(平成17年10月1日制定、令和4年1月20日改正)等に基づき、計算科学技術研究に関する事後評価及び事前評価を計算科学技術研究・評価委員会に諮問した。これを受けて、計算科学技術研究・評価委員会は、本委員会によって定められた評価方法に従い、原子力機構から提出されたシステム計算科学センターの運営及び計算科学技術研究の実施に関する説明資料の口頭発表と質疑応答を基に評価を実施した。本報告書は、計算科学技術研究・評価委員会より提出された事後評価及び事前評価の内容をまとめるとともに、事後評価及び事前評価の「評価結果(答申書)」を添付したものである。
Omer, M.; 静間 俊行*; 羽島 良一*; 小泉 光生
第43回日本核物質管理学会年次大会会議論文集(インターネット), 3 Pages, 2022/11
Gamma-rays originated from laser Compton scattering (LCS) are convenient photon sources for nondestructive interrogation of nuclear materials. LCS can be used with nuclear resonance fluorescence (NRF) and X-ray fluorescence (XRF), the two of which are considered photon-based active interrogation techniques. However, an accurate estimation of the incident LCS  -ray flux is crucial. The
-ray flux is crucial. The  -ray flux is customarily measured using high purity germanium (HPGe) detectors, usually calibrated using standard point-like radioactive
-ray flux is customarily measured using high purity germanium (HPGe) detectors, usually calibrated using standard point-like radioactive  -ray sources. These standard sources are entirely different from LCS beams in terms of detection geometry. Therefore, the calibration process must be corrected to meet the LCS beam conditions. Here, we demonstrate how to implement the required corrections and provide experimental validation of these corrections.
-ray sources. These standard sources are entirely different from LCS beams in terms of detection geometry. Therefore, the calibration process must be corrected to meet the LCS beam conditions. Here, we demonstrate how to implement the required corrections and provide experimental validation of these corrections.