Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
榎枝 幹男; 谷川 尚; 廣瀬 貴規; 鈴木 哲; 落合 謙太郎; 今野 力; 河村 繕範; 山西 敏彦; 星野 毅; 中道 勝; et al.
Fusion Engineering and Design, 87(7-8), p.1363 - 1369, 2012/08
被引用回数:36 パーセンタイル:91.19(Nuclear Science & Technology)核融合ブランケットの開発においては、ITERの核融合環境を用いて、モジュール規模で増殖ブランケットの試験を行う、ITERテストブランケット・モジュール(TBM)試験は、原型炉へ向けた重要なマイルストンである。我が国は、水冷却固体増殖TBMを主案として試験を実施するためにその製作技術開発を進めている。我が国は、これまでに開発した接合技術を用いて、実規模のモジュールの第一壁,側壁,増殖材充填容器、の製作に成功するとともに、第一壁と側壁の組合せ試験にも成功した。さらに、厚さ90mmの後壁の製作技術についても、模擬材料を用いたモックアップの製作を終了した。モジュール製作技術をほぼ見通した。また、トリチウム生産のために必要な技術として、先進増殖・増倍材ペブル製作技術の開発や、核融合中性子を用いたトリチウム生成回収試験による、トリチウム生産技術開発についても進展した。本報告ではこれらのTBM開発の最新の成果を報告する。
関 洋治; 吉河 朗; 谷川 尚; 廣瀬 貴規; 江里 幸一郎; 榎枝 幹男; 坂本 健作
第17回動力・エネルギー技術シンポジウム講演論文集, p.265 - 266, 2012/06
固体増殖方式の核融合炉ブランケットでは、チタン酸リチウム(Li TiO
TiO )の増殖材微小球を容器に充填し、増殖したトリチウムをヘリウム(He)パージガスによって回収するシステムを採用している。国際熱核融合実験炉の中性子環境下で総合的な機械機能試験が実施予定の固体増殖方式のテストブランケットモジュールや同方式を採用した原型炉のパージガス補器系統の設計において、微小球充填体内を通過するHeパージガスの圧力損失やその流動現象を予測するためのツールを確立することは重要である。本報では、増殖材微小球充填体に対して、過去実施されていない幅広い流量域(
)の増殖材微小球を容器に充填し、増殖したトリチウムをヘリウム(He)パージガスによって回収するシステムを採用している。国際熱核融合実験炉の中性子環境下で総合的な機械機能試験が実施予定の固体増殖方式のテストブランケットモジュールや同方式を採用した原型炉のパージガス補器系統の設計において、微小球充填体内を通過するHeパージガスの圧力損失やその流動現象を予測するためのツールを確立することは重要である。本報では、増殖材微小球充填体に対して、過去実施されていない幅広い流量域(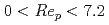 )で圧力損失試験を行い、一様な空隙率で構成された実験式との比較により予測精度を検証する。他方、増殖材充填体容器のHeパージガス導入部は、スエリング等で増殖材微小球が破砕し、閉塞に陥ることを防ぐため、底面から流入口を離す必要がある。本研究では、実機を模擬し、千鳥型に多孔を配した入口配管を用いて、底面から多孔部を離し、試験を実施した。入口配管の本数依存性と入口配管を含む予測精度の検証を報告する。
)で圧力損失試験を行い、一様な空隙率で構成された実験式との比較により予測精度を検証する。他方、増殖材充填体容器のHeパージガス導入部は、スエリング等で増殖材微小球が破砕し、閉塞に陥ることを防ぐため、底面から流入口を離す必要がある。本研究では、実機を模擬し、千鳥型に多孔を配した入口配管を用いて、底面から多孔部を離し、試験を実施した。入口配管の本数依存性と入口配管を含む予測精度の検証を報告する。
廣瀬 貴規; 谷川 尚; 吉河 朗; 関 洋治; 鶴 大悟; 横山 堅二; 江里 幸一郎; 鈴木 哲; 榎枝 幹男; 秋場 真人
Fusion Engineering and Design, 86(9-11), p.2265 - 2268, 2011/10
被引用回数:5 パーセンタイル:36.74(Nuclear Science & Technology)原子力機構では、日本のITERテストブランケット(TBM)の第一候補として、水冷却固体増殖方式のテストブランケットの開発を、中心となって進めている。TBM試験を実現するためには、ITER運転スケジュールに遅れることなく、TBMのプロトタイプの製作と構造健全性の確証を行う必要がある。本報告では、日本における水冷却固体増殖(WCCB)テストブランケットモジュール(TBMの製作技術開発の最新の成果を報告する。これまでに、製作技術の最も重要な技術として、熱間等方圧加圧(HIP)接合法を開発し、実規模冷却チャンネル内蔵第一壁適用して実規模のTBMの第一壁の製作と高熱負荷による評価試験に成功した。また、TBM内部にトリチウム増殖材を格納する充填容器についても実機大のモックアップの製作に成功し気密試験に成功した。さらに、モジュール構造を形成する側壁についても実機大のモックアップ製作に成功するとともに、第一壁との組合せ施工による箱構造政策に成功した。以上のことから、日本においては、TBM製作技術開発と評価試験が順調に進展しているものと評価することができる。
関 洋治; 大西 陽一*; 吉河 朗; 谷川 尚; 廣瀬 貴規; 大図 章; 江里 幸一郎; 鶴 大悟; 鈴木 哲; 横山 堅二; et al.
Progress in Nuclear Science and Technology (Internet), 2, p.139 - 142, 2011/10
日本原子力研究開発機構は、ITERでの核融合環境下で総合的機能試験が実施される予定のテストブランケットモジュール( )として、水冷却方式固体増殖ブランケットの研究開発を進めてきた。
)として、水冷却方式固体増殖ブランケットの研究開発を進めてきた。 は、おもに第一壁,2つの側壁,後壁と増殖材充填に必要な隔壁であるメンブレンパネルによって構成される。また、冷却材である高温高圧水(入口温度553K,出口温度598K, 15MPa)は、TBM内部の並行多流路管群を流動する。本研究では、数値流体計算の結果を実規模大並列多流路の実験値と比較することにより、実現象との整合性を実証し、機器設計に際する流体挙動及び侵食腐食の予測手法の確立を目的とする。TBM側壁内部に存在する並列多流路管内を流れる冷却材を対象に、乱流モデル及びLES(標準スマゴリンスキーモデル)を用いて、数値流体計算を実施した。流体計算による室温条件での各流量分配は、複雑流路である実規模大並列多流路の実験値とほぼ一致することを確認した。数値流体計算の予測手法の妥当性を示したことにより、高温高圧水条件の設計に際しても有効な予測手段の一つとして実証した。
は、おもに第一壁,2つの側壁,後壁と増殖材充填に必要な隔壁であるメンブレンパネルによって構成される。また、冷却材である高温高圧水(入口温度553K,出口温度598K, 15MPa)は、TBM内部の並行多流路管群を流動する。本研究では、数値流体計算の結果を実規模大並列多流路の実験値と比較することにより、実現象との整合性を実証し、機器設計に際する流体挙動及び侵食腐食の予測手法の確立を目的とする。TBM側壁内部に存在する並列多流路管内を流れる冷却材を対象に、乱流モデル及びLES(標準スマゴリンスキーモデル)を用いて、数値流体計算を実施した。流体計算による室温条件での各流量分配は、複雑流路である実規模大並列多流路の実験値とほぼ一致することを確認した。数値流体計算の予測手法の妥当性を示したことにより、高温高圧水条件の設計に際しても有効な予測手段の一つとして実証した。
関 洋治; 大西 陽一*; 吉河 朗; 谷川 尚; 廣瀬 貴規; 大図 章; 江里 幸一郎; 鶴 大悟; 鈴木 哲; 横山 堅二; et al.
Proceedings of Joint International Conference of 7th Supercomputing in Nuclear Application and 3rd Monte Carlo (SNA + MC 2010) (USB Flash Drive), 4 Pages, 2010/10
日本原子力研究開発機構は、ITERでの核融合環境下で総合的機能試験が実施される予定のテストブランケットモジュール(TBM)として、水冷却方式固体増殖ブランケットの研究開発を進めてきた。TBMは、おもに第一壁,2つの側壁,後壁と増殖材充填に必要な隔壁であるメンブレンパネルによって構成される。また、冷却材である高温高圧水(入口温度553K,出口温度598K,15MPa)は、TBM内部の並行多流路管群を流動する。本研究では、数値流体計算の結果を実規模大並列多流路の実験値と比較することにより、実現象との整合性を実証し、機器設計に際する流体挙動及び侵食腐食の予測手法の確立を目的とする。TBM側壁内部に存在する並列多流路管内を流れる冷却材を対象に、乱流モデル及びLES(標準スマゴリンスキーモデル)を用いて、数値流体計算を実施した。流体計算による室温条件での各流量分配は、複雑流路である実規模大並列多流路の実験値とほぼ一致することを確認した。数値流体計算の予測手法の妥当性を示したことにより、高温高圧水条件の設計に際しても有効な予測手段の一つとして実証した。
榎枝 幹男; 廣瀬 貴規; 谷川 尚; 鶴 大悟; 吉河 朗; 関 洋治; 西 宏; 横山 堅二; 江里 幸一郎; 鈴木 哲
Proceedings of 18th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE-18) (CD-ROM), p.645 - 649, 2010/05
本報告は、日本における水冷却固体増殖(WCCB)ブランケットの開発の現状を報告するものである。日本は、WCCBブランケットを核融合原型炉の主案として、その開発を進めている。特に、ブランケットモジュール製作技術開発に関しては、実規模の第一壁モックアップを、実機構造材料である低放射化フェライト鋼(RAFMS)のF82Hを実際に使用して製作することに成功した。さらに製作した第一壁モックアップを用いて、実機の冷却水条件の15MPa, 300度の水で冷却しつつ、実機熱負荷条件0.5MW/m での熱負荷試験に80回試験を行い、変形やホットスポットなどがないことを確認した。また、ブランケットのモジュールを構成する側壁部の実規模モックアップの製作にも成功し、さらに、第一壁モックアップと側壁モックアップの組合せ接合に成功して、初めてテストブランケット実規模筐体モックアップの試作に成功した。これらの開発により、筐体製作技術の主要課題の解決の見通しが得られた。
での熱負荷試験に80回試験を行い、変形やホットスポットなどがないことを確認した。また、ブランケットのモジュールを構成する側壁部の実規模モックアップの製作にも成功し、さらに、第一壁モックアップと側壁モックアップの組合せ接合に成功して、初めてテストブランケット実規模筐体モックアップの試作に成功した。これらの開発により、筐体製作技術の主要課題の解決の見通しが得られた。
吉河 朗; 谷川 尚; 関 洋治; 廣瀬 貴規; 鶴 大悟; 江里 幸一郎; 横山 堅二; 西 宏; 鈴木 哲; 丹澤 貞光; et al.
JAEA-Technology 2009-077, 23 Pages, 2010/03
固体増殖水冷却方式のテストブランケットモジュール(TBM)における側壁内の冷却流路は、2本の母管の間を複数の枝管で平行に接続する管路網(平行多流路)としているため、各枝管を流れる冷却水には流量の分布が生じると予想される。本研究では、平行多流路における流量分布を予測し、TBMの使用条件において構造材料を使用制限温度以下に保持するために必要となる管路網を設計することを目的とした。1次元熱計算により、必要となる冷却流量を評価した。また、圧力損失計算に基づく簡易評価により、必要な流量が得られるような管路網を設計した。塩化ビニル管を用いた試験体を用いて流量分布を測定し、設計の妥当性を確認した。この設計に基づき、F82H製の実規模試験体を製作し、流量分布と圧力損失とを計測したところ、枝管における流量の低下は最大でも平均流量の12%であり、除熱の観点からは十分に余裕があることを確認した。また、圧力損失についても計算値と実測値でよく一致した。以上の結果から、TBMの側壁における冷却管路網について、除熱の観点から必要となる流量を確保するための設計を確立することができた。
中畑 俊彦*; 吉河 朗*; 小柳津 誠*; 大矢 恭久*; 石本 祐樹*; 木津 要; 柳生 純一; 芦川 直子*; 西村 清彦*; 宮 直之; et al.
Journal of Nuclear Materials, 367-370(2), p.1170 - 1174, 2007/08
被引用回数:4 パーセンタイル:30.34(Materials Science, Multidisciplinary)JT-60Uにて行われているボロニゼーションを模擬し、静岡大学のP-CVDにて膜調整を行った高純度ボロン膜に対して飽和量の重水素を照射した後、加熱とSIMS測定を繰り返し行い、膜中に捕捉された水素同位体放出過程に関する以下の知見を得た。重水素脱離を支配する要素は試料温度である。第1期、すなわち573K以下では、B-D-B結合からの重水素の脱離が支配的であり、その温度領域においては、拡散が律速過程であった。573Kを上回ると、重水素はBD結合からおもに脱離し、その温度領域においては、再結合が律速過程であった。BD結合として捕捉された重水素の実効的な再結合定数は等温加熱実験によって算出した。
芦川 直子*; 木津 要; 柳生 純一; 中畑 俊彦*; 信太 祐二; 西村 清彦*; 吉河 朗*; 石本 祐樹*; 大矢 恭久*; 奥野 健二*; et al.
Journal of Nuclear Materials, 363-365, p.1352 - 1357, 2007/06
被引用回数:11 パーセンタイル:59.87(Materials Science, Multidisciplinary)LHD真空容器内で主放電6081ショット,ボロニゼイション3回に曝された。ステンレス(SS316)サンプル、及び同様にJT-60U真空容器ポート内で主放電1896ショット,ボロニゼイション2回に曝された。SS316サンプル表面の元素分布状態をX線光電子分光装置(XPS)を用いて分析し、LHDとJT-60Uの結果を比較した。(1)LHDでは最表面において炭素が20%,酸素が45%であり、それ以降基板界面に至るまで80%のボロン膜が保持されている。JT-60Uでは最表面において炭素が60%であり、その後55%程度のボロン膜が保持されている。このようにLHDと比較するとJT-60Uでは壁材による堆積層が顕著である。(2)JT-60Uでのボロン膜上の堆積層はトーラス方向に非均一であり、C1s及びO1sのXPSスペクトルピークシフトの結果においても場所により異なる傾向を示す。これはトーラス方向の酸素捕捉能力が非均一であることを示唆している。(3)ボロン膜厚は、LHDではグロー電極の位置に依存するが、JT-60Uではそのような傾向は見受けられなかった。理由の一つとして炭素による堆積層がトーラス方向に非均一であることが考えられる。(4)ボロン膜の厚みは実験サイクル中十分に保持されているため、ボロン化壁による酸素軽減効果はおもにボロン膜の最表面の特性に起因すると考えられる。
柴原 孝宏*; 田辺 哲朗*; 広畑 優子*; 大矢 恭久*; 小柳津 誠*; 吉河 朗*; 大西 祥広*; 新井 貴; 正木 圭; 奥野 健二*; et al.
Journal of Nuclear Materials, 357(1-3), p.115 - 125, 2006/10
被引用回数:20 パーセンタイル:77.74(Materials Science, Multidisciplinary)JT-60UのW型ダイバータで、重水素放電に曝された炭素材タイルからポロイダル方向に試料をサンプリングし、昇温脱離(TDS)実験を行うことでタイル中の水素同位体の蓄積量をTDS及びSIMSで評価した。外側ダイバータタイルは、厚い再堆積層に覆われており、その再堆積層中の水素濃度は場所によらずほぼ一定で(D+H)/Cの原子比で約0.03であった。このように水素濃度が低いのはタイル表面の再堆積層がプラズマ入熱によりかなり温度があがっていたためである。DD放電終了後トリチウム除去のために行われたHH放電により、さらに再堆積層の厚さが増加するとともに、先に蓄積されていたDの一部はHに置き換えられていることがわかった。放電中の温度の上昇,ダイバータの幾何学的構造が水素の蓄積に大きな影響を持つことを明らかにした。
柴原 孝宏*; 田辺 哲朗*; 廣畑 優子*; 大矢 恭久*; 小柳津 誠*; 吉河 朗*; 大西 祥広*; 新井 貴; 正木 圭; 奥野 健二*; et al.
Nuclear Fusion, 46(10), p.841 - 847, 2006/10
被引用回数:18 パーセンタイル:51.06(Physics, Fluids & Plasmas)JT-60でダイバータタイルとして使用され、軽水素放電に曝された黒鉛タイルからポロイダル方向に試料をサンプリングし、昇温脱離(TDS)実験を行うことでタイル中の水素蓄積量を評価した。なお、タイルのプラズマ対向面のほとんどは再堆積層で覆われていた。得られたTDSスペクトルの構造は、再堆積層の非常に薄い試料を除けば試料による差は少なく、タイル中に蓄積されていた水素の大部分は水素分子の形態で、970K付近に脱離のピークが存在した。全脱離水素量は再堆積層の厚さにほぼ比例していた。この結果は、ほとんどの水素原子が再堆積層中に均一に蓄積されていたことを示している。求めた水素濃度はH/C=0.03となり、飽和水素濃度(H/C=0.4-1.0)に比べて非常に低かった。水素濃度が低くなった原因として、水素蓄積時に再堆積層の温度が関係していたと考えられ、壁温度を高くすることで水素蓄積量を大幅に減少できる。
木村 博美*; 佐々木 政義*; 森本 泰臣*; 竹田 剛*; 児玉 博*; 吉河 朗*; 小柳津 誠*; 高橋 幸司; 坂本 慶司; 今井 剛; et al.
Journal of Nuclear Materials, 337-339, p.614 - 618, 2005/03
被引用回数:8 パーセンタイル:47.85(Materials Science, Multidisciplinary)本研究では、炭素材料中でのトリチウムの化学的挙動をさらに理解するため、多結晶ダイアモンド(PD)に打ち込まれた重水素の脱離過程に注目し、同様の実験を行ったグラファイト単結晶(HOPG)からの重水素脱離挙動と比較した。HOPG及びPDから得られた重水素のTDSスペクトルの比較から、HOPGからの重水素脱離は、sp2C及びsp3Cからの脱捕捉であり、PDからのそれはsp3Cからの脱捕捉であることが示唆される。一方、メタンの脱離スペクトルをそれぞれ比較すると、それぞれの試料において、ピーク温度がそれぞれの重水素脱離ピーク温度と同じであった。このことより、メタンの脱離には重水素の脱離が関与していると考えられる。つまり、メタンの脱離過程は、CD3とDの表面での再結合律速過程であることを示唆している。これらの結果より、打ち込まれた重水素の脱離には材料中の炭素の化学状態、つまり、混成軌道の違いが関与しているものと考えられる。
谷川 尚; 吉河 朗; 榎枝 幹男
no journal, ,
固体増殖水冷却方式のブランケットにおいては、構造材料を透過して冷却水へと漏洩するトリチウム量を評価することが重要な課題である。そこで本研究では、構造材料であるF82Hを透過する重水素の挙動と、それに及ぼす酸化膜の影響を明らかにすることを目的とし、オートクレーブとガス導入系,真空排気系とを組合せた装置を用いて実験を行った。15MPa, 573Kの高温高圧水中において、F82H鋼製の試験体の内側から外側へと透過する重水素の挙動を観察し、重水素の透過量を評価した。腐食によって生成した酸化膜によって透過量が減少することを明らかにした。また、試験体の外側における腐食によって生成した水素が、試験体の内側へと透過することを明らかにした。
 TiO
TiO ペブル充填体の挙動
ペブル充填体の挙動谷川 尚; 吉河 朗; 榎枝 幹男
no journal, ,
日本がITERでの試験を計画している固体増殖,水冷却方式のブランケットモジュールを対象とし、増殖材ペブル充填体の充填状態の経時変化を明らかにすることを目的とする。室温から973Kの温度領域、及び、0.1MPaから3MPaまでの機械荷重条件において、Li TiO
TiO ペブル充填体に繰り返し熱機械負荷を与え、圧縮ひずみの進展挙動を観察した。機械荷重の負荷により生じた充填体の圧縮変形は、荷重を除いた後の熱処理により部分的に回復した。初期充填率が67.3%の充填体に対して多数回の熱機械負荷を与えた結果、圧縮の進展により充填率が68.5%となった。このような圧縮の進展により、実機においては充填体の上部に空隙が生じることが予想される。したがって、初期充填率として高い値を実現することが重要である。
ペブル充填体に繰り返し熱機械負荷を与え、圧縮ひずみの進展挙動を観察した。機械荷重の負荷により生じた充填体の圧縮変形は、荷重を除いた後の熱処理により部分的に回復した。初期充填率が67.3%の充填体に対して多数回の熱機械負荷を与えた結果、圧縮の進展により充填率が68.5%となった。このような圧縮の進展により、実機においては充填体の上部に空隙が生じることが予想される。したがって、初期充填率として高い値を実現することが重要である。
広畑 優子*; 田辺 哲朗*; 杉山 一慶*; 柴原 孝宏*; 大矢 恭久*; 小柳津 誠*; 吉河 朗*; 奥野 健二*; 正木 圭; 新井 貴; et al.
no journal, ,
JT-60Uの両側排気方式ダイバータ領域における炭素堆積・損耗及び水素同位体の保持特性について分析した。分析には、走査型顕微鏡,昇温脱離法,二次イオン質量分析計,イメージングプレート法及び燃焼法等を利用した。その結果を以下にまとめる。(1)JT-60Uのダイバータ領域ではおもに内側ダイバータ及び外側ドームウィングタイルで炭素堆積が見られ、外側ダイバータタイルでは損耗していた。(2)ダイバータタイルのプラズマ対向面のD+Hの保持量は堆積層の厚さに比例して増加した。その水素濃度(H+D)/Cは約0.02であった。これは、片側排気の内側ダイバータタイルやJT-60とほぼ同程度であり、JETや他の低温で運転されている装置(0.4 0.1)よりも小さかった。(3)外側ドームウィングタイルの排気口に面しているタイル上には厚い再堆積層が存在していた。しかし、その濃度は大きく見積もっても0.13であった。(4)H+D保持量のポロイダル側面の分布は外側ドームウィングの排気口に面している以外は少なかった。(5)H+D保持量のトロイダル側面の分布は、面によって約2倍の違いがあったが、堆積膜の膜厚によって強く影響を受けていた。
0.1)よりも小さかった。(3)外側ドームウィングタイルの排気口に面しているタイル上には厚い再堆積層が存在していた。しかし、その濃度は大きく見積もっても0.13であった。(4)H+D保持量のポロイダル側面の分布は外側ドームウィングの排気口に面している以外は少なかった。(5)H+D保持量のトロイダル側面の分布は、面によって約2倍の違いがあったが、堆積膜の膜厚によって強く影響を受けていた。
榎枝 幹男; 廣瀬 貴規; 谷川 尚; 鶴 大悟; 吉河 朗; 西 宏; 鈴木 哲; 江里 幸一郎; 横山 堅二
no journal, ,
核融合炉のブランケットは、真空容器内に、プラズマに面する位置におかれ、核融合反応で発生する中性子を受けて、内蔵する増殖材との核反応により核融合燃料のトリチウムを生産し、また中性子照射により発生する核発熱をエネルギーとして冷却水によりとりだすと同時に、中性子の遮蔽を行うものである。増殖ブランケットは、原型炉の実現に向けて開発段階にあり、要素技術の開発成果をふまえて、現在、工学的な試験が進められている。特にITERの核融合環境下で、モジュール規模の増殖ブランケットの試験モジュールの機能を総合的に実証するための、ITERテストブランケット試験計画は、最も重要なマイルストンと位置づけられている。本報告は、日本において開発が進められているブランケットのうち、主案である水冷却固体増殖方式のテストブランケットモジュール(TBM)について、構造設計の進展,製作技術開発と性能評価試験の現状について報告をする。
鶴 大悟; 谷川 尚; 廣瀬 貴規; 吉河 朗; 関 洋治; 鈴木 哲; 榎枝 幹男
no journal, ,
ITERにおいてTBM実験遂行上、熱的安全確保が必要であるが、冷却材の水と中性子増倍材であるBeペブルの化学反応による熱的エクスカージョンを防止する必要がある。本報では安全上熱的評価が必要な2つの起因事象である、TBM冷却喪失事象、及び冷却材のTBM内漏洩事象に対して一次元モデルを用いて解析を行った結果、以下のような安全設計の方策が有効であることを明らかにした。(1)冷却系の流量及び圧力をモニターすることにより、冷却能力喪失発生時には速やかに(60秒以内に)検知して、プラズマを停止させるものとする。(2)TBM内に冷却材が浸入しても冷却能力が喪失しないように、(i)パージガス循環系の圧力変動を検知して、遮断弁を閉止する。(ii)冷却材リザーブタンク等を備えることにより、冷却材が一部失われた際に速やかに補充できるような機構を備える。
関 洋治; 吉河 朗; 榎枝 幹男; 深田 智*
no journal, ,
ITERでの試験を予定している固体増殖水冷却方式テストブランケットモジュール(TBM)のトリチウム生成率を見積もるため、トリチウム増殖比(TBR)に注目しつつ、層の厚さと配置を最適化するために一次元核熱計算を実施した。さらに、増殖材充填層内におけるヘリウムパージガス流動の数値解析及び実験を実施した。本研究によって得られた代表的な知見を以下に示す。(1)「増倍材をSingle Packingで充填する場合、増殖材層の背面に増倍材層を2層配置することで、Binary Packingと同等のトリチウム生成率取得が可能である」(2)「Heパージガスの流動が非常に緩やかであるため、対流拡散の影響が少なく、第一壁及びメンブレンパネル近傍では、トリチウムの高濃度領域が存在する」(3)充填体内の圧力損失のデータベースを構築した。本成果は、原型炉を見据えたTBM設計の研究開発に資するものである。
谷川 尚; 廣瀬 貴規; 吉河 朗; 関 洋治; 横山 堅二; 江里 幸一郎; 鶴 大悟; 西 宏; 鈴木 哲; 榎枝 幹男
no journal, ,
原子力機構が開発している固体増殖水冷却方式のテストブランケットモジュールについて、実規模の部分試験体を製作した。このテストブランケットモジュールの筐体は箱型で、内部に粒状に加工した増殖材及び増倍材を充填する構造としている。側壁と、増殖材及び増倍材の充填容器とについて製作方法を確立し、実規模の試験体を製作した。また、これらの試験体を用いた機能試験によって設計の妥当性を確認した。さらに、これまでに製作していたコの字型の第一壁と、2枚の側壁とを電子ビーム溶接によって接合し、5面の箱構造に組み立てた。これらの製作技術は後壁の製作及び組立て工程にも適用可能であることから、6面の箱構造の製作に見通しを得ることができた。
谷川 尚; 廣瀬 貴規; 鶴 大悟; 鈴木 哲; 江里 幸一郎; 西 宏; 関 洋治; 吉河 朗; 毛利 憲介; 横山 堅二; et al.
no journal, ,
固体増殖水冷却方式のテストブランケットモジュールについて、側壁と微小球充填容器の実規模試験体を製作した。機能実証試験の結果から、これらの機器について製作法と設計とが妥当であることを明らかにした。側壁内の冷却流路は、圧損を小さくするために並列多流路構造としている。母管を側壁の厚み内に納めるために母管の直径が制限されるが、模擬試験体を用いた通水試験により、流量分布の大きさは除熱の観点から許容できる範囲であることを明らかにした。充填容器については、構造材料の量をなるべく減らすためにメンブレン構造を採用している。肉厚1mmの管と1.5mmの板とをファイバーレーザー溶接により接合し、メンブレン構造を製作できることを示した。増殖材の微小球を充填し、設計値に相当する充填率及びヘリウムパージガスの圧損が得られることを確認した。