Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
本田 充紀; 金田 結依; 村口 正和*; 早川 虹雪*; 小田 将人*; 飯野 千秋*; 石井 宏幸*; 後藤 琢也*
AIP Advances (Internet), 14(5), p.055034_1 - 055034_6, 2024/05
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Nanoscience & Nanotechnology)本研究は、希少かつ有毒な物質から得られる従来の熱電材料に代わるものとして、福島風化黒雲母(WB)を利用することを検討したものである。WBは粉砕、分級、溶融塩処理による熱処理を経て650 Cから850
Cから850 Cの範囲で半導体に類似した導電性を示す結晶を生成した。WBと得られた結晶の電気伝導度とゼーベック係数を評価した結果、高温熱電応用への可能性が示された。その結果、WBは無次元特性値(ZT)0.015を達成し、650
Cの範囲で半導体に類似した導電性を示す結晶を生成した。WBと得られた結晶の電気伝導度とゼーベック係数を評価した結果、高温熱電応用への可能性が示された。その結果、WBは無次元特性値(ZT)0.015を達成し、650 Cを超える熱電材料としての可能性を示した。
Cを超える熱電材料としての可能性を示した。

本田 充紀; 後藤 琢也*; 坂中 佳秀*; 矢板 毅; 鈴木 伸一*
AIMS Electronics and Electrical Engineering (Internet), 3(2), p.102 - 110, 2019/03
粘土鉱物である風化黒雲母(WB)からCsの除去と結晶生成を制御する可能性について、溶融NaCl-CaCl 中で溶融塩電気化学法(EC)を用いて検討した。0.5Vから-2.2Vの範囲でサイクリックボルタモグラム(CV)測定を行ったところ、CVスペクトルに複数のピークが確認された。1.4VのピークはWB中のFeの還元反応を表しているため、-1.4Vで2時間の実験を行いFeを還元した。EC処理後のCs除去率を蛍光X線分析で測定したところ、ほぼ100%のCs除去が確認された。還元効果を把握するため、X線吸着微細構造(XAFS)分析を行った。EC処理前のWBのFeは、Fe
中で溶融塩電気化学法(EC)を用いて検討した。0.5Vから-2.2Vの範囲でサイクリックボルタモグラム(CV)測定を行ったところ、CVスペクトルに複数のピークが確認された。1.4VのピークはWB中のFeの還元反応を表しているため、-1.4Vで2時間の実験を行いFeを還元した。EC処理後のCs除去率を蛍光X線分析で測定したところ、ほぼ100%のCs除去が確認された。還元効果を把握するため、X線吸着微細構造(XAFS)分析を行った。EC処理前のWBのFeは、Fe とFe
とFe が混存していた。EC処理後は、XAFS分析によりFe
が混存していた。EC処理後は、XAFS分析によりFe の存在が確認された。この結果から、EC処理はWB中のFeの還元に有効であることが分かった。この結果から、Fe
の存在が確認された。この結果から、EC処理はWB中のFeの還元に有効であることが分かった。この結果から、Fe O
O の生成が抑制され、還元反応が結晶生成の抑制に有効であることを示している。
の生成が抑制され、還元反応が結晶生成の抑制に有効であることを示している。
 -rays at the ANNRI in the MLF of the J-PARC
-rays at the ANNRI in the MLF of the J-PARC高田 秀佐*; 奥平 琢也*; 後藤 文也*; 広田 克也*; 木村 敦; 北口 雅暁*; 古賀 淳*; 中尾 太郎*; 酒井 健二; 清水 裕彦*; et al.
Journal of Instrumentation (Internet), 13(2), p.P02018_1 - P02018_21, 2018/02
被引用回数:8 パーセンタイル:34.38(Instruments & Instrumentation)In this study, the germanium detector assembly, installed at the Accurate Neutron Nuclear Reaction measurement Instruments (ANNRI) in the Material and Life Science Facility (MLF) operated by the Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC), has been characterized for extension to the measurement of the angular distribution of individual  -ray transitions from neutron-induced compound states. We have developed a Monte Carlo simulation code using the GEANT4 toolkit, which can reproduce the pulse-height spectra of
-ray transitions from neutron-induced compound states. We have developed a Monte Carlo simulation code using the GEANT4 toolkit, which can reproduce the pulse-height spectra of  -rays from radioactive sources and (n,
-rays from radioactive sources and (n, ) reactions. The simulation is applicable to the measurement of
) reactions. The simulation is applicable to the measurement of  -rays in the energy region of 0.5-11.0 MeV.
-rays in the energy region of 0.5-11.0 MeV.
大江 一弘*; Attallah, M. F.*; 浅井 雅人; 後藤 尚哉*; Gupta, N. S.*; 羽場 宏光*; Huang, M.*; 金谷 淳平*; 金谷 佑亮*; 笠松 良崇*; et al.
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 303(2), p.1317 - 1320, 2015/02
被引用回数:10 パーセンタイル:60.46(Chemistry, Analytical)超重元素化学にむけ、ガスジェット法によって搬送された核反応生成物を連続溶解する新規方法を開発した。本方法では、疎水性メンブレンフィルターを用い、気相と水相を分離する。本手法を用いて短寿命放射性核種 Moならびに
Moならびに Wの溶解効率を測定した結果、水溶液流速0.1-0.4mL/minで80%以上の収率が得られた。一方、1.0-2.0L/minの範囲内では、ガス流速への依存性は観測されなかった。以上の結果から、本手法が超重元素の溶液化学研究に適用可能であることが示された。
Wの溶解効率を測定した結果、水溶液流速0.1-0.4mL/minで80%以上の収率が得られた。一方、1.0-2.0L/minの範囲内では、ガス流速への依存性は観測されなかった。以上の結果から、本手法が超重元素の溶液化学研究に適用可能であることが示された。
笠田 竜太*; 後藤 拓也*; 藤岡 慎介*; 日渡 良爾*; 大山 直幸; 谷川 博康; 宮澤 順一*; 核融合炉実用化若手検討会*
プラズマ・核融合学会誌, 89(4), p.193 - 198, 2013/04
核融合炉若手実用化検討会等において技術成熟度評価(TRL)を若手有志により行ってきた。本報では、TRL評価法の概要を説明するとともに、本活動によって行われた我が国の核融合炉開発に対するTRL評価結果を示す。
 2表面の急速初期酸化現象と表面再配列
2表面の急速初期酸化現象と表面再配列富樫 秀晃*; 山本 喜久*; 後藤 成一*; 高橋 裕也*; 中野 卓哉*; 今野 篤史*; 末光 眞希*; 朝岡 秀人; 吉越 章隆; 寺岡 有殿
no journal, ,
O 分子によるSi(110)-16
分子によるSi(110)-16 2清浄表面の初期酸化過程をリアルタイム放射光光電子分光法(SR-XPS)及び走査型トンネル顕微鏡(STM)により観察し、Si(110)初期酸化過程を研究した。SR-XPS実験はSPring-8-BL23SUにて、STM実験はJAEA東海で行った。Si(110)-16
2清浄表面の初期酸化過程をリアルタイム放射光光電子分光法(SR-XPS)及び走査型トンネル顕微鏡(STM)により観察し、Si(110)初期酸化過程を研究した。SR-XPS実験はSPring-8-BL23SUにて、STM実験はJAEA東海で行った。Si(110)-16 2表面とSi(001)-2
2表面とSi(001)-2 1表面の酸素吸着曲線の比較から、Si(110)では急速初期酸化現象が生じることと、Layer-by-Layer成長様式を示すことを見いだした。走査トンネル顕微鏡による「その場」観察の結果、急速初期酸化現象は16
1表面の酸素吸着曲線の比較から、Si(110)では急速初期酸化現象が生じることと、Layer-by-Layer成長様式を示すことを見いだした。走査トンネル顕微鏡による「その場」観察の結果、急速初期酸化現象は16 2再配列構造の構成要素であるペンタゴンペアへの酸素優先吸着に起因すること、占有/非占有状態イメージの比較から、同表面には少なくとも4種類の酸化状態が存在すること、このうちDDサイトと呼ぶ構造は凝集酸化状態であることを明らかにした。
2再配列構造の構成要素であるペンタゴンペアへの酸素優先吸着に起因すること、占有/非占有状態イメージの比較から、同表面には少なくとも4種類の酸化状態が存在すること、このうちDDサイトと呼ぶ構造は凝集酸化状態であることを明らかにした。
 2表面上準安定酸化状態の観察
2表面上準安定酸化状態の観察山本 喜久*; 富樫 秀晃*; 後藤 成一*; 高橋 裕也*; 中野 卓哉*; 加藤 篤*; 長谷川 智*; 今野 篤史*; 末光 眞希*; 吉越 章隆; et al.
no journal, ,
われわれはSi(110)表面の室温初期酸化過程とその極薄酸化膜の熱的安定性を放射光光電子分光(SR-PES),走査トンネル顕微鏡(STM)により調査した。SR-PES実験の結果、Si(110)室温酸化のごく初期では局所的に酸素が凝集した準安定な構造が形成されることがわかった。この酸化表面を573Kで15分加熱すると、Si2pスペクトルの高次酸化成分Si , Si
, Si は増大したが、低次酸化状態Si
は増大したが、低次酸化状態Si は減少した。これは酸化膜に存在する歪んだ準安定酸化構造が加熱によって緩和され、より安定な高次酸化構造に変化したためである。さらに、室温酸化表面で観察された準安定構造が加熱によってさらに安定なクラスタ構造に変化することをSTMによって直接観察した。
は減少した。これは酸化膜に存在する歪んだ準安定酸化構造が加熱によって緩和され、より安定な高次酸化構造に変化したためである。さらに、室温酸化表面で観察された準安定構造が加熱によってさらに安定なクラスタ構造に変化することをSTMによって直接観察した。
 2室温酸化表面上の準安定状態の観察
2室温酸化表面上の準安定状態の観察富樫 秀晃*; 山本 喜久*; 後藤 成一*; 高橋 裕也*; 中野 卓哉*; 今野 篤史*; 末光 眞希*; 朝岡 秀人; 吉越 章隆; 寺岡 有殿
no journal, ,
室温で酸素吸着させたSi(110)-16 2表面と熱処理した表面を、リアルタイム放射光・光電子分光法(SR-PES)、及び、走査型トンネル顕微鏡(STM)により観察し、Si(110)室温酸素吸着表面の熱的安定性を明らかにした。室温で10Lの酸素に暴露したSi(110)表面を573Kで15分間加熱すると、Si
2表面と熱処理した表面を、リアルタイム放射光・光電子分光法(SR-PES)、及び、走査型トンネル顕微鏡(STM)により観察し、Si(110)室温酸素吸着表面の熱的安定性を明らかにした。室温で10Lの酸素に暴露したSi(110)表面を573Kで15分間加熱すると、Si 及びSi
及びSi 成分のピーク位置がそれぞれ0.20eV, 0.12eV高エネルギー側にシフトし、熱酸化膜の位置に近づいた。このような振る舞いはSi酸化に伴うSi-O-Si結合角やSi-O結合長の変化によるものである。Si(110)表面のSTM観察では、酸素分子の吸着構造が加熱によって凝集酸化構造に変化することが見いだされた。これらSR-PESとSTMの結果から、Si(110)-16
成分のピーク位置がそれぞれ0.20eV, 0.12eV高エネルギー側にシフトし、熱酸化膜の位置に近づいた。このような振る舞いはSi酸化に伴うSi-O-Si結合角やSi-O結合長の変化によるものである。Si(110)表面のSTM観察では、酸素分子の吸着構造が加熱によって凝集酸化構造に変化することが見いだされた。これらSR-PESとSTMの結果から、Si(110)-16 2表面上の酸素分子吸着構造は準安定状態であり、加熱によってより安定な凝集酸化構造に変化することが明らかになった。
2表面上の酸素分子吸着構造は準安定状態であり、加熱によってより安定な凝集酸化構造に変化することが明らかになった。
豊嶋 厚史; 大江 一弘*; 浅井 雅人; Attallah, M. F.*; 後藤 尚哉*; Gupta, N. S.*; 羽場 宏光*; 金子 政志*; 金谷 佑亮; 笠松 良崇*; et al.
no journal, ,
シーボーギウム(Sg)より重い超アクチノイド元素は重イオン核反応で生成されるが、半減期が十秒以下であり、さらに生成率が低いため一時間に一原子しか生成できない。そのため、これらの元素の溶液化学的研究には迅速な化学分離を連続的に行うことができる分析装置が必要となる。本研究ではSgの化学研究に向け、ガスジェット搬送物を溶液に迅速溶解するために新たに開発したメンブレンデガッサー、酸化還元反応を制御するためのフロー電解カラム、そして連続溶媒抽出装置(SISAK)を連結して用い、Sgの軽同族元素であるMoならびにWの模擬実験を行った。学会ではこれらの開発状況について発表する。
本田 充紀; 後藤 琢也*; 坂中 佳秀*; 下山 巖; 岡本 芳浩; 鈴木 伸一; 矢板 毅
no journal, ,
福島における汚染土壌の除染と再生に向けた研究を推進している。我々は溶融塩電気化学法を用いて複数の結晶の電解による分離・回収の可能性について探索する。本研究では溶融塩電気化学法を用いて電気化学的に酸素ポテンシャルを制御する。今回カソード電極で想定する反応を、電気化学的な還元雰囲気下である-1.4Vの還元電位に固定し、700 Cで2時間反応を行った。溶融塩電気化学処理後のWBについてX線回折法(XRD)を用いて構造変化を検討した。XRDによる構造解析の結果では、WBのみと-1.4V/700
Cで2時間反応を行った。溶融塩電気化学処理後のWBについてX線回折法(XRD)を用いて構造変化を検討した。XRDによる構造解析の結果では、WBのみと-1.4V/700 Cで2時間反応後および700
Cで2時間反応後および700 C加熱のみのXRDパターンを比較した。WBのみのパターンと比べ、溶融塩電気化学反応を用いて-1.4V電位/700
C加熱のみのXRDパターンを比較した。WBのみのパターンと比べ、溶融塩電気化学反応を用いて-1.4V電位/700 Cで2時間反応後は新たなパターンを確認した。これは電位をかけないで700
Cで2時間反応後は新たなパターンを確認した。これは電位をかけないで700 Cで2時間反応させた時と大きく異なっており、Cs除去後の生成物が異なっていることを示している。電位が無い場合では生成物は4つの結晶から構成されているが溶融塩電気化学反応後は生成物が3つで構成されることを確認した。これは還元雰囲気ではない条件の場合と比較して得られた生成物に変化が生じることを意味する。以上から溶融塩電気化学法を用いた電解による分離・回収へ向けた可能性を示せた。今後異なる電位反応による生成物の変化について検討する。
Cで2時間反応させた時と大きく異なっており、Cs除去後の生成物が異なっていることを示している。電位が無い場合では生成物は4つの結晶から構成されているが溶融塩電気化学反応後は生成物が3つで構成されることを確認した。これは還元雰囲気ではない条件の場合と比較して得られた生成物に変化が生じることを意味する。以上から溶融塩電気化学法を用いた電解による分離・回収へ向けた可能性を示せた。今後異なる電位反応による生成物の変化について検討する。

本田 充紀; 坂中 佳秀*; 後藤 琢也*; 鈴木 伸一; 矢板 毅
no journal, ,
Separation and collection of Cs-sorbing weathered biotite (WB) has been investigated by using molten salt electrochemistry under an electrochemical reductive condition. In the cyclic voltammogram measurement, several oxidation-reduction peaks were observed in the range of +0.5 V to -2.2 V. The peak at -1.4 V was assigned to a reduction reaction of Fe. The sample was fixed at -1.4 V in order to reduce Fe for 2 hours at 700 degree. X-ray fluorescence analysis indicates that Cs was completely removed from the WB. The structure of the WB was determined using X-ray diffraction techniques and local structure of Fe was analyzed using X-ray absorption fine structure (XAFS). The WB completely decomposed and hematite formation was suppressed after the electrochemical reaction and calcite, augite, and wadalite formation were confirmed. On the basis of this finding, we propose the separation / collection method by using molten salt electrochemistry.
 を用いた粘土鉱物からのCs除去とその電解還元効果
を用いた粘土鉱物からのCs除去とその電解還元効果本田 充紀; 後藤 琢也*; 坂中 佳秀*; 長谷川 友里; 鈴木 伸一; 矢板 毅
no journal, ,
溶融塩電気化学法を用いた汚染土壌からのセシウム除去と新規材料創製技術の開発に取り組んでいる。土壌主成分である鉄(Fe)を、溶融塩電気化学法により電解還元処理することで新規材料創製の可能性や機能性の付与を目指しているが、電解還元によるFeの構造変化について分かっていない。そこで放射光によるX線吸収分光法(XAFS)により(a)風化黒雲母(WB)のみの場合、(b)WB+混合塩添加/700 Cの場合、および(c)-1.4V(WB+混合塩添加/700
Cの場合、および(c)-1.4V(WB+混合塩添加/700 C)処理した場合を比較検討した。FeのK吸収端のXAFSスペクトルのpre-edgeピークから、(a)Fe
C)処理した場合を比較検討した。FeのK吸収端のXAFSスペクトルのpre-edgeピークから、(a)Fe /Fe
/Fe の混合状態が、(b)ではFe
の混合状態が、(b)ではFe になり、(c)溶融塩電気化学法による電解還元によりFe
になり、(c)溶融塩電気化学法による電解還元によりFe に還元されていることを明らかにした。
に還元されていることを明らかにした。
本田 充紀; 後藤 琢也*; 坂中 佳秀*; 鈴木 伸一; 矢板 毅
no journal, ,
放射能汚染土壌の減容および再利用化へ向け、溶融塩電気化学法を用いた汚染土壌からのCs除去と電解還元処理によるエネルギー材料の創製実現へ向けた研究を推進している。溶融塩電気化学を用いた還元処理を行うことで、土壌中のFeの構造変化について放射光XAFS分析により検討した。FeのXAFSスペクトルにおいては価数変化に敏感であるpre-edgeピークに注目し構造解析を行った。ピーク位置を詳細に検討した結果、還元処理前のpre-edgeピークに対して、還元処理後のpre-edgeピークでは低エネルギーシフトを確認し、土壌中のFeのFe(3価)からFe(2価)への還元反応を明らかにした。これは、Fe O
O からFe
からFe O
O へ結晶が変化する結果を示唆している。以上より溶融塩電気化学法により結晶生成過程を制御できる可能性を示せた。
へ結晶が変化する結果を示唆している。以上より溶融塩電気化学法により結晶生成過程を制御できる可能性を示せた。
本田 充紀; 後藤 琢也*; 金田 結依; 矢板 毅
no journal, ,
福島環境回復に係る研究を推進している。解決すべき課題の1つに福島の除去土壌が挙げられるが、その除去土壌は路盤材などへの再生利用が検討されている。福島の土壌からセシウムを除去する技術を研究してきた中で、除去後の粘土鉱物に新たな機能(例えば熱電物性など)を付与することで、再生利用が加速できると考えた。土壌粘土鉱物はSi, Al, Feなどから構成されており、低環境負荷材料である。そこで、土壌粘土鉱物を溶融塩電解により還元処理し、その特性を検討した。熱拡散率測定の結果、溶融塩電解未処理の試料では温度依存性を示さなかったのに対し、-1.4Vの溶融塩電解処理試料では温度依存性を示し、熱電物性に有意な差を示した。
本田 充紀; 金田 結依; 村口 正和*; 早川 虹雪*; 小田 将人*; 飯野 千秋*; 石井 宏幸*; 後藤 琢也*; 矢板 毅
no journal, ,
2011年に発生した福島第一原子力発電所(1F)事故から12年が経過し、福島県内で発生した汚染土壌は除去土壌として管理されている。除去土壌からCsを除去する技術開発の過程で得た複数の結晶鉱物の機能性に着目し熱電変換材料としての可能性を検討している。本研究では、結晶鉱物についての熱電特性評価(電気伝導率,熱拡散率,ゼーベック係数)について報告する。
本田 充紀; 金田 結依; 早川 虹雪*; 村口 正和*; 飯野 千秋*; 小田 将人*; 石井 宏幸*; 後藤 琢也*; 矢板 毅
no journal, ,
本研究では、WBおよび溶融塩法の各条件を系統的に変えてできた多結晶鉱物に対し種々の熱電変換特性を調べるために、熱電3物性特性評価(OZMA-1-S1)を同一試料により実施した。マクロおよびミクロな構造は、種々のX線分析と第一原理計算により同定した。WBの電気伝導特性について、黒雲母系は通常室温では電気的絶縁体として知られているが、粉砕,分級,溶融塩処理後に焼結した結果、650-850 Cの温度領域において1.49E-04 [
Cの温度領域において1.49E-04 [ V/K]オーダーの値を示し半導体程度の電気伝導特性であることが分かった。また同温度領域のゼーベック係数測定では、-2.0E+05 [
V/K]オーダーの値を示し半導体程度の電気伝導特性であることが分かった。また同温度領域のゼーベック係数測定では、-2.0E+05 [ V/K]と高い値を観測した。得られた結果から無次元性能指数
V/K]と高い値を観測した。得られた結果から無次元性能指数 を算出すると、
を算出すると、 =0.29が得られた。溶融塩処理した多結晶鉱物についての熱電特性評価結果については、同温度領域の電気伝導特性評価ではWBよりも高い電気伝導特性を得た。これらの結果から、WBを利用することで、650
=0.29が得られた。溶融塩処理した多結晶鉱物についての熱電特性評価結果については、同温度領域の電気伝導特性評価ではWBよりも高い電気伝導特性を得た。これらの結果から、WBを利用することで、650 C以上の高温領域では有用な熱電変換特性を示すことを示唆された。
C以上の高温領域では有用な熱電変換特性を示すことを示唆された。
Snow, W. M.*; Auton, C.*; 遠藤 駿典; 藤岡 宏之*; 井出 郁央*; 猪野 隆*; 後藤 優*; 河村 しほり*; 北口 雅暁*; 小林 龍珠*; et al.
no journal, ,
本研究では(n, )チャネルを通るparity-oddな断面積を測定する技術を使用して、いくつかの重い原子核における新しいp波共鳴を探索することを目指している。これらのいずれかの原子核において、大きなparity violationが発見されれば、NOPTREX collaborationによる偏極中性子-偏極原子核の透過測定 における時間反転対称性の破れ探索計画の新たな候補となる可能性がある。この情報は、重い原子核におけるparity oddな混合に関する既存の理論をテストするのにも役立つ。本研究では質量数が
)チャネルを通るparity-oddな断面積を測定する技術を使用して、いくつかの重い原子核における新しいp波共鳴を探索することを目指している。これらのいずれかの原子核において、大きなparity violationが発見されれば、NOPTREX collaborationによる偏極中性子-偏極原子核の透過測定 における時間反転対称性の破れ探索計画の新たな候補となる可能性がある。この情報は、重い原子核におけるparity oddな混合に関する既存の理論をテストするのにも役立つ。本研究では質量数が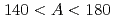 の核のうちスピンがゼロでない約15個の原子核において新しいp波共鳴、並びにparity violationの存在を探すことを目的としている。近年J-PARCにおいて開発された偏極中性子生成デバイス、Heスピンフィルタを用いた高い偏極率を持つ中性子、及びMLF・BL04のGe検出器群を用い、高感度なparity violationの探索が可能となっている。本年は測定のテストとして、すでに大きなparity violationの存在が知られているLa-139の0.75eV共鳴での測定を行い、先行研究と一致する10%程度の有意なparity violationを得た。さらに目的とする
の核のうちスピンがゼロでない約15個の原子核において新しいp波共鳴、並びにparity violationの存在を探すことを目的としている。近年J-PARCにおいて開発された偏極中性子生成デバイス、Heスピンフィルタを用いた高い偏極率を持つ中性子、及びMLF・BL04のGe検出器群を用い、高感度なparity violationの探索が可能となっている。本年は測定のテストとして、すでに大きなparity violationの存在が知られているLa-139の0.75eV共鳴での測定を行い、先行研究と一致する10%程度の有意なparity violationを得た。さらに目的とする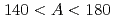 のうちの一部の原子核の中性子捕獲反応の測定を行なったとともに、2024年3月にはこれら核のparity violationの最初の測定を予定している。本発表ではNOPTREXをはじめとしたプロジェクトの概要、並びに最新の成果と今後の展望について発表する。
のうちの一部の原子核の中性子捕獲反応の測定を行なったとともに、2024年3月にはこれら核のparity violationの最初の測定を予定している。本発表ではNOPTREXをはじめとしたプロジェクトの概要、並びに最新の成果と今後の展望について発表する。
 2初期酸化過程のリアルタイム光電子分光
2初期酸化過程のリアルタイム光電子分光山本 喜久*; 富樫 秀晃*; 加藤 篤*; 長谷川 智*; 後藤 成一*; 中野 卓哉*; 末光 眞希*; 成田 克*; 吉越 章隆; 寺岡 有殿
no journal, ,
放射光光電子分光法を用いてSi(110)-16 2表面の初期酸化過程を調べた。この表面特有で他の面方位には見られない急激な初期酸化が観察された。O1s光電子スペクトルの解析から、Si-Si結合への酸素の挿入が初期酸化で主要な過程であることがわかった。その急速初期酸化はSi2pのサブピークの減少を伴う課程である。これはペンタゴンペアの優先的な酸化に伴うSi(110)-16
2表面の初期酸化過程を調べた。この表面特有で他の面方位には見られない急激な初期酸化が観察された。O1s光電子スペクトルの解析から、Si-Si結合への酸素の挿入が初期酸化で主要な過程であることがわかった。その急速初期酸化はSi2pのサブピークの減少を伴う課程である。これはペンタゴンペアの優先的な酸化に伴うSi(110)-16 2表面の再配列を意味している。
2表面の再配列を意味している。
本田 充紀; 金田 結依; 村口 正和*; 早川 虹雪*; 小田 将人*; 飯野 千秋*; 石井 宏幸*; 後藤 琢也*
no journal, ,
本研究は、従来希少かつ有毒な元素から作られてきた熱電材料に代わる代替材料として、風化黒雲母(WB)の利用に焦点を当てたものである。WBを粉砕・分級した後、溶融塩法で熱処理することで、650度から850度の温度範囲においてSi半導体と同程度の伝導率を持つ結晶を得た。本研究では、高温域の伝導率、ゼーベック係数および熱拡散測定結果と比熱、比重から算出した熱伝導率から無次元評価指数ZTを算出した結果について報告する。
 2表面初期酸化過程の放射光光電子分光
2表面初期酸化過程の放射光光電子分光富樫 秀晃*; 山本 喜久*; 後藤 成一*; 高橋 裕也*; 中野 卓哉*; 加藤 篤*; 長谷川 智*; 今野 篤史*; 末光 眞希*; 朝岡 秀人; et al.
no journal, ,
本研究では、Si(110)-16 2清浄表面の酸素ガスによる初期酸化過程を放射光光電子分光法(SR-XPS)によって調べた。SR-XPS測定はSPring-8の原子力機構専用表面化学実験ステーションにて行った。使用した基板はBドープp型Si(110)基板で、抵抗率は8
2清浄表面の酸素ガスによる初期酸化過程を放射光光電子分光法(SR-XPS)によって調べた。SR-XPS測定はSPring-8の原子力機構専用表面化学実験ステーションにて行った。使用した基板はBドープp型Si(110)基板で、抵抗率は8 cmから12
cmから12 cmである。基板をウェット洗浄処理後に超高真空中で数回1200
cmである。基板をウェット洗浄処理後に超高真空中で数回1200 Cまでフラッシング加熱することにより清浄表面を得た。酸化は酸素圧力10
Cまでフラッシング加熱することにより清浄表面を得た。酸化は酸素圧力10 Paから10
Paから10 Pa、基板温度500
Pa、基板温度500 Cから670
Cから670 Cで行った。同様の酸化条件におけるSi(001)面の酸素吸着曲線に比べて有意に速い初期酸化を示すことがわかった。その急速初期酸化において、Si2pバルク成分のうちSi(110)-16
Cで行った。同様の酸化条件におけるSi(001)面の酸素吸着曲線に比べて有意に速い初期酸化を示すことがわかった。その急速初期酸化において、Si2pバルク成分のうちSi(110)-16 2表面の基本構成要素であるペンタゴンペアに関連付けられる成分が著しく減少した。このことから、Si(110)-16
2表面の基本構成要素であるペンタゴンペアに関連付けられる成分が著しく減少した。このことから、Si(110)-16 2表面で見られる急速初期酸化現象は、ペンタゴンペアが優先的に酸化されることで生じたと結論した。
2表面で見られる急速初期酸化現象は、ペンタゴンペアが優先的に酸化されることで生じたと結論した。