Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
高田 昌二; 本多 友貴*; 稲葉 良知; 関田 健司; 根本 隆弘; 栃尾 大輔; 石井 俊晃; 佐藤 博之; 中川 繁昭; 沢 和弘*
Proceedings of 9th International Topical Meeting on High Temperature Reactor Technology (HTR 2018) (USB Flash Drive), 7 Pages, 2018/10
HTGRに接続する核熱利用システムの設計では、化学プラント会社の容易な参入を可能にするため、非原子炉級で設計されるが、熱利用システムで異常が発生した場合でも原子炉の運転を継続できることとしている。需要地近接立地で負荷追従運転を実現するため、原子炉入口および出口冷却材温度を一定に保ちながら一次系ガス圧力を変化させるインベントリ制御は原子炉出力を制御する方法の候補の1つとされている。HTTRを用いた非核加熱運転による熱負荷変動吸収試験結果をもとに、異なる一次系ガス圧力で原子炉入口温度をステップ状に変動させた。数値解析の結果、圧力の低下により変動吸収特性が劣化しないことが明らかになった。また、原子炉出力の80%でも、原子炉出口温度がスクラムレベルに達しないことも明らかにした。
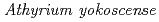 and tobacco plants
and tobacco plants吉原 利一*; 鈴井 伸郎; 石井 里美; 北崎 真由*; 山崎 治明*; 北崎 一義*; 河地 有木; 尹 永根; 七夕 小百合*; 橋田 慎之介*; et al.
Plant, Cell & Environment, 37(5), p.1086 - 1096, 2014/05
被引用回数:27 パーセンタイル:66.15(Plant Sciences)Cadmium (Cd) accumulations in a Cd hyper-accumulator fern, 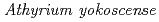 (
( ), and tobacco,
), and tobacco, 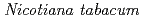 (
( ), were kinetically analysed using the positron-emitting tracer imaging system under two medium conditions (basal and no-nutrient). In
), were kinetically analysed using the positron-emitting tracer imaging system under two medium conditions (basal and no-nutrient). In  , maximumly 50% and 15% of the total Cd accumulated in the distal roots and the shoots under the basal condition, respectively. Interestingly, a portion of the Cd in the distal roots returned to the medium. In comparison with
, maximumly 50% and 15% of the total Cd accumulated in the distal roots and the shoots under the basal condition, respectively. Interestingly, a portion of the Cd in the distal roots returned to the medium. In comparison with  , a little fewer Cd accumulations in the distal roots and clearly higher Cd migration to the shoots were observed in
, a little fewer Cd accumulations in the distal roots and clearly higher Cd migration to the shoots were observed in  under the basal condition (maximumly 40% and 70% of the total Cd, respectively). The no-nutrient condition down-regulated the Cd migration in both species, although the regulation was highly stricter in
under the basal condition (maximumly 40% and 70% of the total Cd, respectively). The no-nutrient condition down-regulated the Cd migration in both species, although the regulation was highly stricter in  than in
than in  (almost no migration in
(almost no migration in  and around 20% migration in
and around 20% migration in  ). In addition, the present work enabled to estimate physical and physiological Cd accumulation capacities in the distal roots, and demonstrated condition-dependent changes especially in
). In addition, the present work enabled to estimate physical and physiological Cd accumulation capacities in the distal roots, and demonstrated condition-dependent changes especially in  . These results clearly suggested occurrences of species-/condition-specific regulations in each observed parts. It is probable that integration of these properties govern the specific Cd tolerance/accumulation in
. These results clearly suggested occurrences of species-/condition-specific regulations in each observed parts. It is probable that integration of these properties govern the specific Cd tolerance/accumulation in  and
and  .
.
豊嶋 厚史; 笠松 良崇*; 塚田 和明; 浅井 雅人; 石井 康雄; 當銘 勇人*; 西中 一朗; 佐藤 哲也; 永目 諭一郎; Sch del, M.; et al.
del, M.; et al.
Journal of Nuclear and Radiochemical Sciences, 11(1), p.7 - 11, 2010/06
本研究では、ラザホージウム(Rf)並びに同族元素Zr, Hfの2.0-7.0M塩酸水溶液からトリオクチルホスフィンオキシド(TOPO)への抽出挙動を調べた。塩酸水溶液の濃度増加に伴ってこれらの元素の抽出率は増加し、その抽出順はZr Hf
Hf Rfであることを明らかにした。この実験結果から、RfCl
Rfであることを明らかにした。この実験結果から、RfCl
 2(TOPO)錯体の安定性は同族元素の同じ錯体よりも低いことが考えられる。
2(TOPO)錯体の安定性は同族元素の同じ錯体よりも低いことが考えられる。
笠松 良崇*; 豊嶋 厚史; 浅井 雅人; 塚田 和明; Li, Z.; 石井 康雄; 當銘 勇人*; 佐藤 哲也; 菊池 貴宏; 西中 一朗; et al.
Chemistry Letters, 38(11), p.1084 - 1085, 2009/10
被引用回数:17 パーセンタイル:50.85(Chemistry, Multidisciplinary)105番元素ドブニウム(Db)のフッ化水素酸と硝酸混合水溶液中における陰イオン交換挙動を、新規に開発した迅速イオン交換分離装置を用いて調べた。Dbのフッ化物陰イオン錯体の挙動は、近接の第6周期同族元素タンタル(Ta)の挙動とは大きく異なり、第5周期のニオブ(Nb)の挙動と似ているという特徴的な性質を示すことがわかった。
豊嶋 厚史; 笠松 良崇*; 塚田 和明; 浅井 雅人; 北辻 章浩; 石井 康雄; 當銘 勇人; 西中 一朗; 羽場 宏光*; 大江 一弘*; et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(26), p.9180 - 9181, 2009/07
被引用回数:16 パーセンタイル:48.04(Chemistry, Multidisciplinary)新たに開発したフロー電解カラムクロマトグラフ装置を用い、0.1M -ヒドロキシイソ酪酸(
-ヒドロキシイソ酪酸( -HIB)水溶液中における102番元素ノーベリウム(No)の酸化反応をシングルアトムレベルで調べた。最も安定なNo
-HIB)水溶液中における102番元素ノーベリウム(No)の酸化反応をシングルアトムレベルで調べた。最も安定なNo がNo
がNo に酸化され、1.0V以上の印加電圧において酸化された
に酸化され、1.0V以上の印加電圧において酸化された -HIB錯体がカラム中で三価状態を保持することを明らかとした。
-HIB錯体がカラム中で三価状態を保持することを明らかとした。
鈴木 貞明; 関 正美; 篠崎 信一; 佐藤 文明; 平内 慎一; 石井 和宏*; 長谷川 浩一; 森山 伸一
JAEA-Technology 2007-055, 27 Pages, 2007/09
JT-60U高周波加熱装置の一つである低域混成波(LHRF)加熱装置では、過大なプラズマからの熱負荷によるダメージを避けるために、アンテナ先端部に炭素製グリルを取り付けた新たな取り組みでプラズマ実験が行われている。しかし、プラズマ実験後の観察では、一部に放電痕が見つかったために、アーク検出器及び可視画像検出の高性能化による保護インターロックの強化に取り組んだ。アーク検出器では、光検出の応答速度及び分解能を高めるために増幅回路の改良を行った。また、可視画像検出では、PC画像処理を導入しプラズマによる発光と放電光を区別してon-off制御する機能を新たに追加した。本報告書は、LHRF加熱装置における保護インターロックシステムの改良についてまとめたものである。
横倉 賢治; 森山 伸一; 長谷川 浩一; 鈴木 貞明; 平内 慎一; 石井 和宏*; 佐藤 文明
JAEA-Technology 2007-045, 22 Pages, 2007/07
大電力用ミリ波電力測定装置は、主伝送路の導波管内を伝搬する高周波を直接誘電体に透過させ、誘電体で損失する高周波エネルギーから透過電力を算出する新しい発想の高周波計器であり、高次モードや偏波の変化に計測値が鈍感な特徴を持つ。また、検出素子を適切に選択することで、kW MW級の広範囲の電力測定に柔軟に対応することができる。本報告では、大電力ミリ波による高周波損失が極めて小さい材料を検出素子として選択し、その発熱特性と耐電力性能を評価した結果について記述する。これらの検討結果をもとに、JT-60U, JT-60SA電子サイクロトロン加熱装置への実用化に向けたプロトタイプ電力測定装置の設計と製作を実施したので報告する。
MW級の広範囲の電力測定に柔軟に対応することができる。本報告では、大電力ミリ波による高周波損失が極めて小さい材料を検出素子として選択し、その発熱特性と耐電力性能を評価した結果について記述する。これらの検討結果をもとに、JT-60U, JT-60SA電子サイクロトロン加熱装置への実用化に向けたプロトタイプ電力測定装置の設計と製作を実施したので報告する。
石井 和宏; 関 正美; 篠崎 信一; 長谷川 浩一; 平内 慎一; 鈴木 貞明; 佐藤 文明; 森山 伸一; 横倉 賢治
JAEA-Technology 2007-036, 30 Pages, 2007/07
JT-60UのLHアンテナは、効率的に高周波(RF)をプラズマへ入力するために、プラズマと近い位置に設置され、常にプラズマと相互作用している。そのため、ステンレス鋼製のLHアンテナ先端の開口部は、プラズマからの過大な熱負荷による損傷やRF放電による損傷が発生し、問題となっていた。その対策としてLHアンテナ先端部に耐熱性に優れた炭素製グリルを取付けることにより、先端部の損傷を軽減できる耐熱化LHアンテナを開発し、プラズマへのパワー入射実験を世界で初めて行った。炭素製グリルからの放出ガスによるRF放電が懸念されたので、初期のRFコンディショニングは慎重に行い、十分な脱ガスを実施した。その結果、RF電力として16MJの入射エネルギーの達成に成功した。また、電流駆動用LHアンテナとして要求される、十分に高いプラズマ電流駆動性能(約1.6 10
10 A/W/m
A/W/m )を持つことを実証した。
)を持つことを実証した。
滑川 卓志; 川口 浩一; 小池 和宏; 原口 信吾; 石井 暁
Proceedings of International Conference on Nuclear Energy System for Future Generation and Global Sustainability (GLOBAL 2005) (CD-ROM), 6 Pages, 2005/10
実用化戦略調査研究における低除染TRU燃料製造システムについてプラント概念を構築し、システム評価を実施した。簡素化ペレット法は従来法の実績経験を有するため早期の実用化が期待される。ゲル化法は溶液及び顆粒として物質取扱するため微粉飛散が少ない利点がある一方、多量の工程廃液処理によるコスト増大が課題である。射出鋳造法は小規模施設での経済性に優れるが、TRU金属合金スラグ製造性の立証を要する。窒化物燃料に関しては、N-15回収再利用に関する技術開発が必要である。特に、被覆粒子燃料製造においては、コーティング及び集合体形成プロセスで更なる技術開発が求められている。
高橋 正己*; 関 正美; 下野 貢; 寺門 正之; 五十嵐 浩一*; 石井 和宏*; 春日井 敦
JAERI-Tech 2003-080, 27 Pages, 2003/11
JT-60Uでは、局所的な加熱・電流駆動によるプラズマの安定性改善や予備電離の実験を行うことを目的として、電子サイクロトロン加熱(ECH)装置を導入してきた。JT-60UのECH装置は、動作周波数110GHz・高周波出力約1MWの発振管(ジャイロトロン)4基を持ち、2基の可動ミラー型アンテナを使用してJT-60Uプラズマへ入射するシステムである。110GHzを含む極めて高い周波数のミリ波帯での高出力発振は10年前まではなく、近年ITER用に開発されてきたジャイロトロンで初めて実現された。そのため、ジャイロトロンの運転にはさまざまな調整が必要である。ヒーターエージング後に、磁場調整,アノード電圧調整により1MWの発振条件を見つけ、その後、パルス幅を伸ばすエージングを行い、秒オーダーの運転を実現した。さらに、高出力,長パルスで安定な運転を行うため、ジャイロトロン管内で発生する不要高周波を吸収するRF吸収体を内蔵する改良を行った。その結果、1MW-5秒の設計目標を達成するとともに、4基のジャイロトロンでプラズマに約10MJの世界最高のミリ波エネルギーを入射できた。
植田 祥平; 江森 恒一; 飛田 勉*; 高橋 昌史*; 黒羽 操; 石井 太郎*; 沢 和弘
JAERI-Research 2003-025, 59 Pages, 2003/11
高温工学試験研究炉(HTTR)の出力上昇試験を実施した。HTTRの燃料性能を評価するため、原子炉保護設備の1次冷却材放射能計装,燃料破損検出装置(FFD),1次冷却材サンプリング設備により1次冷却材中の放射能濃度を測定した。その結果、1次冷却材中放射能濃度は10 Bq/cm
Bq/cm 以下であり、Kr及びXe核種の濃度は0.1Bq/cm
以下であり、Kr及びXe核種の濃度は0.1Bq/cm 以下であった。
以下であった。 Kr放出率(R/B)値は、原子炉出力60%以下において約2
Kr放出率(R/B)値は、原子炉出力60%以下において約2 10
10 、定格30MW出力時において約7
、定格30MW出力時において約7 10
10 であった。事前解析による
であった。事前解析による Kr放出率の予測値は、測定値とよく一致し、希ガスの放出機構が、燃料コンパクトマトリックス部の汚染ウランの核分裂により生成し、反跳から拡散へと変化することが示された。
Kr放出率の予測値は、測定値とよく一致し、希ガスの放出機構が、燃料コンパクトマトリックス部の汚染ウランの核分裂により生成し、反跳から拡散へと変化することが示された。
石井 和宏*; 関 正美; 下野 貢; 寺門 正之; 五十嵐 浩一*; 高橋 正己*
JAERI-Tech 2003-079, 22 Pages, 2003/10
JT-60Uでは、定常化運転を目指した開発研究の一つとして、低域混成波帯(LHRF)の高周波を用いた電流駆動の研究を行っている。その研究において、装置技術的課題は、LHRF加熱装置の重要な機器である大電力LHRFアンテナの開発である。LHRFアンテナは、効率的に高周波をプラズマに入射するために、プラズマから近い位置に置かれている。そのためLHRFアンテナは常にプラズマからの熱にさらされ、また大電力高周波の入射が要請されるため、先端部におけるプラズマからの熱負荷による溶融や高周波放電による溶融・変形が問題となっていた。その結果、プラズマへの入射パワーは徐々に減少してきた。この対策として、LHRFアンテナのエージングを行って、耐高周波電界性能の向上を図った。また、赤外線カメラによるLHRFアンテナの温度監視,LHRFアンテナ位置の調整,入射パワーを断続的に変調する電流駆動法の開発、そしてアークセンサによる高周波放電を検知して、LHRFアンテナ先端部の損傷を防止する保護対策を実施してきた。
下野 貢; 関 正美; 寺門 正之; 五十嵐 浩一*; 石井 和宏*; 高橋 正己*; 篠崎 信一; 平内 慎一; 佐藤 文明*; 安納 勝人
JAERI-Tech 2003-075, 29 Pages, 2003/09
第一壁洗浄に有効な電子サイクロトロン共鳴(ECR)放電洗浄(DC)をJT-60Uで実証するために、高周波源としてJT-60U低域混成波(LHRF)加熱装置用クライストロンの低出力・長パルス試験を行った。LHRF加熱装置用クライストロンは、2GHz帯で単管当たり1MW-10秒出力性能を持つが、長パルス運転のために動作条件を変更しなければならない。そのために、まず電源性能から長パルス運転が可能となるビーム電流を評価した。この結果、ビーム電圧72kV,ビーム電流4.4Aにおいて電源は定常運転が可能であることが判明した。このビーム電圧及び電流において空洞共振器を調整した結果、クライストロン出力40kWを得た。さらに、出力40kWレベルで模擬負荷を用いて60秒の長パルス試験を行い、クライストロンのコレクター温度が約20秒で120 Cの飽和温度になり、コレクター冷却性能から定常運転が可能と判断した。JT-60UでのECR-DC実験では、約30kW-45分の運転に成功した。
Cの飽和温度になり、コレクター冷却性能から定常運転が可能と判断した。JT-60UでのECR-DC実験では、約30kW-45分の運転に成功した。
五十嵐 浩一*; 関 正美; 下野 貢; 寺門 正之; 石井 和宏*; 高橋 正己*
JAERI-Tech 2003-030, 40 Pages, 2003/03
JT-60Uにおける電子サイクロトロン加熱(ECH)装置は、局所加熱あるいは電流駆動をすることが可能であり、動作周波数110GHzにおいて、出力約1MW,最大パルス幅5秒を出力するジャイロトロン4基を用いる。電子サイクロトロン波によるジャイロトロンが110GHzの高周波を発振するために必要な超伝導コイル(以降SCMと記す)は、ジャイロトロン内部のキャビティ付近に最大4.5Tの強磁場を発生する。この超伝導コイルの特徴は、4Kヘリウム冷凍機をコイルに搭載することによって、液体窒素を全く使用することなく運転することが可能であり、メンテナンス性が非常に優れていることである。ジャイロトロン用超伝導コイルを高出力・長パルスの環境で長期間継続運転した経験の報告は、これまであまりなく、大変貴重である。ジャイロトロン用超伝導コイルの運転経験から、ECH装置の運転における以下のような重要な知見を得た。4Kヘリウム冷凍機の交換時期の推定方法を試案して、ECH装置の順調な運転に寄与した。さらに、4Kヘリウム冷凍機停止が、150時間以下の場合には再起動後200時間程度以内でSCMの温度が通電可能温度(5.0K以下)まで到達することを実証できた。
寺門 正之; 下野 貢; 五十嵐 浩一*; 高橋 正己*; 石井 和宏*; 関 正美
平成14年度東京大学総合技術研究会技術報告集, 3 Pages, 2003/03
JT-60電子サイクロトロン加熱(ECH)装置は、周波数110GHz,出力約1MWの大電力電子管(ジャイロトロン)を使用した発振器を4系統有している。ECH装置は、局所的な加熱・電流駆動によるプラズマの安定性改善や予備電離の実験に使用されている。現在使用しているジャイロトロンは3電極を持ち、ビーム加速電源から分圧されたアノード電圧を変調することで、その発振パワーを可変できる。すなわち、アノード電圧を分圧するために使用しているツェナーダイオードの数を制御することによって、数十 数百Hzで変調制御できるようにした。これにより、ジャイロトロンの出力を変調できる運転を実現した。
数百Hzで変調制御できるようにした。これにより、ジャイロトロンの出力を変調できる運転を実現した。
下野 貢; 関 正美; 寺門 正之; 五十嵐 浩一*; 石井 和宏*; 梶原 健; 安納 勝人
NIFS-MEMO-36, p.382 - 385, 2002/06
臨界プラズマ試験装置(JT-60)では、局所的な加熱・電流駆動によるプラズマの安定性改善や予備電離の実験を行うため、平成10年度から電子サイクロトロン加熱装置(ECH)を導入してきた。JT-60 ECHは、周波数110GHzで高周波出力1MWの発振管(ジャイロトロン)を4本持ち、内径31.75mmのコルゲート導波管約60mにて高周波電力を伝送して、入射角度を変えられるミラー型のアンテナ(2基)からJT-60 プラズマへ入射するシステムである。電源の最適化やジャイロトロンの改良、伝送系の敷設精度の改善を実施して、2.8MW-3.6s(-10MJ)の世界最高レベルの入射を実現できた。本研究会では、ECHの運転おいて発生した問題(ノイズよる誤動作等)とその対策、ジャイロトロン寄生発振の抑制による長パルス時のビーム電流安定化と準定常運転化、さらに、モニター系の充実によって運転の省力化を試みたことなどを述べる。また、今後の課題についても報告する。
豊嶋 厚史; 笠松 良崇; 塚田 和明; 北辻 章浩; 羽場 宏光*; 浅井 雅人; 石井 康雄; 當銘 勇人; 秋山 和彦*; 大江 一弘*; et al.
no journal, ,
電気化学的分析法を用いた102番元素ノーベリウムの酸化反応について報告する。作用電極表面でのクロマトグラフ挙動によってノーベリウムの酸化状態を同定するために、イオン交換膜(Nafion)をカーボンファイバーに被覆した化学修飾電極を開発し、これを作用電極とするフロー電解カラム装置を作製した。原子力機構タンデム加速器施設において Cm(
Cm( C,5n)反応により合成した
C,5n)反応により合成した Noをガスジェット法によってフロー電解カラム装置まで迅速搬送し、
Noをガスジェット法によってフロー電解カラム装置まで迅速搬送し、 -ヒドロキシイソ酪酸水溶液に溶解したのち、印加電圧に対するフロー電解カラム電極での溶離挙動を調べた。印加電圧0.2Vにおける
-ヒドロキシイソ酪酸水溶液に溶解したのち、印加電圧に対するフロー電解カラム電極での溶離挙動を調べた。印加電圧0.2Vにおける Noの溶出挙動はSr
Noの溶出挙動はSr と同じであったことから、この条件では最も安定なNo
と同じであったことから、この条件では最も安定なNo として存在することを確認した。一方、印加電圧-1.2 Vにおける
として存在することを確認した。一方、印加電圧-1.2 Vにおける Noの溶離挙動はYb
Noの溶離挙動はYb と同じでNo
と同じでNo での挙動とは全く異なっていた。これはNoがNo
での挙動とは全く異なっていた。これはNoがNo として存在することを顕著に示している。本研究によって電気化学的にNo
として存在することを顕著に示している。本研究によって電気化学的にNo からNo
からNo へ酸化することに初めて成功した。
へ酸化することに初めて成功した。
 水溶液中での陰イオン交換挙動
水溶液中での陰イオン交換挙動塚田 和明; 笠松 良崇; 浅井 雅人; 豊嶋 厚史; 石井 康雄; Li, Z.; 菊池 貴宏; 佐藤 哲也; 西中 一朗; 永目 諭一郎; et al.
no journal, ,
原子力機構のタンデム加速器を利用した核反応 Cm(
Cm( F,5n)により105番元素ドブニウムの同位体
F,5n)により105番元素ドブニウムの同位体 Db(半減期:34秒)を合成し、新たに開発したオンライン実験装置を利用して、HF/HNO
Db(半減期:34秒)を合成し、新たに開発したオンライン実験装置を利用して、HF/HNO 水溶液系での陰イオン交換実験を行った。その結果、Dbは同族元素Taと比較し、陰イオン交換樹脂への吸着が弱く、また、Nbと同等かより弱い傾向が明らかになった。このことから、Dbのフッ化物錯形成が同族元素に比べ弱いことが期待される。
水溶液系での陰イオン交換実験を行った。その結果、Dbは同族元素Taと比較し、陰イオン交換樹脂への吸着が弱く、また、Nbと同等かより弱い傾向が明らかになった。このことから、Dbのフッ化物錯形成が同族元素に比べ弱いことが期待される。
鈴木 貞明; 長谷川 浩一; 篠崎 信一; 佐藤 文明; 平内 慎一; 石井 和宏; 関 正美; 森山 伸一; 横倉 賢治
no journal, ,
JT-60高周波加熱装置(LHRF)は、アンテナ先端部に耐熱性を高めるために開発した炭素製グリルを取り付けて実験運転を行ってきた。その後、先端部を観察したところ、炭素製グリルには損傷はなかったが、炭素製グリルを取り付けるステンレス製ベース部に溶融が見られた。その原因の一つとして、先端部付近での放電がアーク検出器で正常に検出されず、放電が持続し、ベース部を保護できなかったと考えられた。そこで、こうした損傷等を最小限に抑えるためにアーク検出器の改良や可視画像による保護システムの開発を行った。
三浦 健太*; 菊地 秀輔*; 桐生 弘武*; 稲田 和紀*; 小澤 優介*; 花泉 修*; 山本 春也; 杉本 雅樹; 吉川 正人; 川口 和弘; et al.
no journal, ,
イオンビーム照射による発光デバイス及び光スイッチ等の光機能素子の形成技術の開発を行った。発光デバイスの開発では、これまでの成果からSiO 部材にSi
部材にSi の注入と、その後の1200
の注入と、その後の1200 C前後でのアニールにより青色発光することを見いだしており、本研究ではこの部材を用いてより低温のアニールで発光する部材の開発を目指した。Si
C前後でのアニールにより青色発光することを見いだしており、本研究ではこの部材を用いてより低温のアニールで発光する部材の開発を目指した。Si とC
とC の注入、及び大気中での700
の注入、及び大気中での700 C、25分間のアニールを行うことで、可視領域での発光を観測できた。さらに、Si
C、25分間のアニールを行うことで、可視領域での発光を観測できた。さらに、Si 及びC
及びC の注入量の比によって、発光ピーク波長がシフトすることも確認し、発光色を制御できる可能性も示した。一方、光スイッチの開発では、波長1.55
の注入量の比によって、発光ピーク波長がシフトすることも確認し、発光色を制御できる可能性も示した。一方、光スイッチの開発では、波長1.55 m帯のマッハツェンダー(Mach-Zehnder: MZ)型光スイッチの実現を目指し、PMMAにプロトンビーム描画(Proton Beam Writing: PBW)技術で光導波路を描画することでMZ型導波路の製作を試みた。試料として、Si基板上に下部クラッド層のSiO
m帯のマッハツェンダー(Mach-Zehnder: MZ)型光スイッチの実現を目指し、PMMAにプロトンビーム描画(Proton Beam Writing: PBW)技術で光導波路を描画することでMZ型導波路の製作を試みた。試料として、Si基板上に下部クラッド層のSiO 膜(15
膜(15 m)及び光導波路製作層のPMMA膜(8
m)及び光導波路製作層のPMMA膜(8 m)を製作した。これに1.7MeV、1
m)を製作した。これに1.7MeV、1 m
m のH
のH ビームを用いてPBWにより8
ビームを用いてPBWにより8 m幅の左右対称に対向したY分岐型の導波路を描画し、さらに、上部クラッド層としてこの照射後の試料にPMMAを10
m幅の左右対称に対向したY分岐型の導波路を描画し、さらに、上部クラッド層としてこの照射後の試料にPMMAを10 m厚で成膜した。製作した導波路に対して波長1.55
m厚で成膜した。製作した導波路に対して波長1.55 mの光を通した結果、出射光が一つであることを確認し、MZ型光導波路として光波の分岐及び合流が行えることを示した。
mの光を通した結果、出射光が一つであることを確認し、MZ型光導波路として光波の分岐及び合流が行えることを示した。