Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
下村 浩一郎*; 幸田 章宏*; Pant, A. D.*; 砂川 光*; 藤森 寛*; 梅垣 いづみ*; 中村 惇平*; 藤原 理賀; 反保 元伸*; 河村 成肇*; et al.
Interactions (Internet), 245(1), p.31_1 - 31_6, 2024/12
J-PARC Muon Facility: MUSE (Muon Science Establishment) is responsible for the inter-university user program and the operation, maintenance, and construction of the muon beamlines, namely D-line, S-line, U-line, and H-line, along with the muon source at J-PARC Materials and Life Science Facility (MLF). In this paper, recent developments are briefly presented.
下村 浩一郎*; 幸田 章宏*; Pant, A. D.*; 名取 寛顕*; 藤森 寛*; 梅垣 いづみ*; 中村 惇平*; 反保 元伸*; 河村 成肇*; 手島 菜月*; et al.
Journal of Physics; Conference Series, 2462, p.012033_1 - 012033_5, 2023/03
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Physics, Applied)At J-PARC MUSE, since the  SR2017 conference and up to FY2022, there have been several new developments at the facility, including the completion of a new experimental area S2 at the surface muon beamline S-line and the first muon beam extraction to the H1 area in the H-line, mainly to carry out high-statistics fundamental physics experiments. Several new studies are also underway, such as applying negative muon non-destructive elemental analysis to the analysis of samples returned from the asteroid Ryugu in the D2 area of the D-line. This paper reports on the latest status of MUSE.
SR2017 conference and up to FY2022, there have been several new developments at the facility, including the completion of a new experimental area S2 at the surface muon beamline S-line and the first muon beam extraction to the H1 area in the H-line, mainly to carry out high-statistics fundamental physics experiments. Several new studies are also underway, such as applying negative muon non-destructive elemental analysis to the analysis of samples returned from the asteroid Ryugu in the D2 area of the D-line. This paper reports on the latest status of MUSE.
横内 浩志*; 稲垣 厚至*; 神田 学*; 小野寺 直幸
土木学会論文集,B1(水工学)(インターネット), 76(2), p.I_253 - I_258, 2020/00
格子ボルツマン法LESモデルを用いた都市大気境界層の大規模数値計算モデルを用いて、都市の自動車由来大気汚染物質を想定したスカラーの動態評価を行った。スカラーはパッシブスカラーを仮定し、その動態計算をLagrange的手法により表現した。本モデルを移動排出源由来の大気汚染が深刻化しているジャカルタを対象に計算を実施した。計算条件として、ジャカルタで以前計画されていた沿岸巨大建造物GARUDAの有無による2通りの条件を設定し、それが下流の都市に及ぼす影響を評価した。計算結果より、地表面付近において、GARUDAの有無に由来する主流方向風速分布,粒子濃度分布に顕著な差は確認できなかった。一方で建物レベル(10[m]-30[m])では、GARUDAの影響による風速の低下に伴い、粒子密度が増加していることを確認した。
阿部 充志*; Bae, S.*; Beer, G.*; Bunce, G.*; Choi, H.*; Choi, S.*; Chung, M.*; da Silva, W.*; Eidelman, S.*; Finger, M.*; et al.
Progress of Theoretical and Experimental Physics (Internet), 2019(5), p.053C02_1 - 053C02_22, 2019/05
被引用回数:156 パーセンタイル:99.31(Physics, Multidisciplinary)この論文はJ-PARCにおける、ミューオン異常磁気モーメント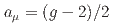 と電気双極子モーメント(EDM)
と電気双極子モーメント(EDM)  を測定する新しいアプローチを紹介する。我々の実験のゴールは、これまでと独立の、1/10の運動量と1/20のストレージリングを用いて、
を測定する新しいアプローチを紹介する。我々の実験のゴールは、これまでと独立の、1/10の運動量と1/20のストレージリングを用いて、 と
と をこれまでにない精密な磁場で測定することである。さらに過去の実験との顕著な違いは、1/1000の横エミッタンスミューオンビーム(サーマルミューオンビーム)を用い、効率的なソレノイドへ縦入射し、ミューオンからの崩壊陽電子をトラッキングし、その小さな運動量ベクトルを求める点である。
をこれまでにない精密な磁場で測定することである。さらに過去の実験との顕著な違いは、1/1000の横エミッタンスミューオンビーム(サーマルミューオンビーム)を用い、効率的なソレノイドへ縦入射し、ミューオンからの崩壊陽電子をトラッキングし、その小さな運動量ベクトルを求める点である。 は統計精度450ppb、系統誤差70ppb、EDMについては
は統計精度450ppb、系統誤差70ppb、EDMについては e
e cmの精度で測定することを目標とする。
cmの精度で測定することを目標とする。
檜山 和久; 塙 信広; 黒澤 昭彦; 江口 祥平; 堀 直彦; 楠 剛; 植田 久男; 島田 浩; 神田 博明*; 齊藤 勇*
JAEA-Technology 2013-045, 32 Pages, 2014/02
本報告書は、炉室内で作業する者の入域管理と被ばく管理を同時に行い、さらに、炉室内での位置情報と作業員が倒れていないか等の情報を取得できるリアルタイム多機能入域管理システムの開発についてまとめたものである。
山田 克典; 藤井 克年; 神田 浩志; 東 大輔; 小林 稔明; 中川 雅博; 深見 智代; 吉田 圭佑; 上野 有美; 中嶌 純也; et al.
JAEA-Review 2013-033, 51 Pages, 2013/12
平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故以降、放射線防護・放射線管理にかかわるさまざまな基準が策定された。インターネット等を通じて、これらの基準を調査した結果、下記13項目があげられた。(1)ヨウ素剤の服用基準値、(2)避難住民等に対するスクリーニングレベル、(3)避難区域、屋内退避等、(4)食品規制値(暫定規制値、基準値)、(5)放射線業務従事者の緊急時被ばく限度、(6)水浴場開設の判断基準、(7)学校・校庭の利用の判断基準、(8)作付基準、(9)飼料の暫定許容値、(10)堆肥の暫定許容値、(11)船舶、コンテナ等の除染基準、(12)廃棄物の取扱、処分等、(13)除染作業にかかわる基準。これらの基準の根拠を調査・整理し、今後の放射線防護、放射線管理の課題を検討した。
神田 征夫*; 沖 雄一*; 横山 須美; 佐藤 薫; 野口 宏; 田中 進*; 飯田 孝夫*
Radiation Physics and Chemistry, 74(5), p.338 - 340, 2005/12
被引用回数:5 パーセンタイル:34.88(Chemistry, Physical)高エネルギー加速器の運転に伴い発生するビームライン周辺の高エネルギー放射線場では、空気の放射線分解により窒素酸化物やオゾンが生成される。窒素酸化物のうち、硝酸は強い酸化力を持つことから、機器類の腐食の原因となる。J-PARCのような大強度陽子加速器施設では、空気中に大量に硝酸が生成され、放射線と同時に腐食による機器類の損傷が問題となる。しかし、高エネルギー放射線場での線量や線量率と硝酸の生成との関係についてはほとんど報告されていない。そこで、本研究では、高エネルギー陽子照射により、空気中に生成される硝酸量を定量的に評価するため、硝酸のG値(100eVあたりの生成分子数)を測定した。48MeV陽子を5分間、2nAでガラス容器に封入した室内空気を照射した結果、高エネルギー陽子照射に対する硝酸のG値は1.46 0.12となった。この値は、以前に陽子シンクロトロンの放射線場で得られた放射線分解生成物の相対的な生成比から推定した硝酸のG値よりも高かった。しかし、2000及び4300R/hの線量率でCo-60の
0.12となった。この値は、以前に陽子シンクロトロンの放射線場で得られた放射線分解生成物の相対的な生成比から推定した硝酸のG値よりも高かった。しかし、2000及び4300R/hの線量率でCo-60の 線を空気に照射した場合の硝酸のG値と非常に近い値となった。
線を空気に照射した場合の硝酸のG値と非常に近い値となった。
横山 須美; 佐藤 薫; 野口 宏; 田中 進; 飯田 孝夫*; 古市 真也*; 神田 征夫*; 沖 雄一*; 金藤 泰平*
Radiation Protection Dosimetry, 116(1-4), p.401 - 405, 2005/12
被引用回数:1 パーセンタイル:10.20(Environmental Sciences)高エネルギー陽子加速器施設における内部被ばく線量評価法及び空気モニタリング技術を開発するためには、高エネルギー陽子の加速に伴い、2次的に発生する中性子や陽子と空気構成成分との核破砕反応により空気中に生成される放射性核種の性状を明らかにしておく必要がある。このため、これらの核種のうち、まだ十分なデータが得られていない放射性塩素及び硫黄ガスの物理化学的性状を明らかにするために、Arと空気を混合したガスまたはエアロゾルを添加したArガスへの中性子照射実験を実施した。この結果、浮遊性放射性塩素は非酸性ガスとして、放射性硫黄は酸性ガスとして存在すること,放射性塩素及び硫黄ともにエアロゾルに付着すること,放射性塩素は壁面へ付着しやすいことが明らかとなった。
松田 誠; 竹内 末広; 月橋 芳廣; 堀江 活三*; 大内 勲*; 花島 進; 阿部 信市; 石崎 暢洋; 田山 豪一; 仲野谷 孝充; et al.
第18回タンデム加速器及びその周辺技術の研究会報告集, p.11 - 14, 2005/11
2004年度の原研タンデム加速器の運転日数は、7月に高電圧端子との通信トラブルが発生したが、例年並の214日(約5000時間)を維持できた。そのうちブースターの利用運転は42日であった。最高端子電圧は高圧超純水洗浄を施したコンプレスドジオメトリ型加速管の更新により、約1年余りでビーム無しで18.7MV、ビーム有りで18.0MVを記録し建設以来の最高となった。KEKと共同で進めてきた短寿命核加速実験施設(TRIAC)の設置に伴い、新たなインターロックシステムを構築した。一方TRIACは3月に施設検査を終了し、ウランの陽子誘起核分裂反応で生成された Xe(T
Xe(T =14min)ビームの加速に初めて成功した。本研究会では、2004年度における運転,整備及び利用状況について報告する。
=14min)ビームの加速に初めて成功した。本研究会では、2004年度における運転,整備及び利用状況について報告する。
松田 誠; 竹内 末広; 月橋 芳廣; 堀江 活三; 大内 勲; 花島 進; 阿部 信市; 石崎 暢洋; 田山 豪一; 仲野谷 孝充; et al.
第17回タンデム加速器及びその周辺技術の研究会報告集, p.1 - 4, 2004/00
原研タンデム加速器では昨年度、加速管をコンプレスドジオメトリ型の加速管へ更新した。加速管内の超音波及び高圧純水洗浄の効果により、わずか1週間程のコンディショニングで更新前の約16MVの端子電圧を達成することができた。充分なコンディショニング時間を確保できなかったが、1MV及び2MVユニットでは平均で110%の電圧を達成し、フルカラムによる電圧上昇試験で18.2MVを達成した。そのほか強力なターミナルイオン源への更新のために入射系の改造を行うべく準備を進めており、昨年度ガスストリッパー装置の撤去を行った。短寿命核加速施設は昨年度までの3年間で施設の建設及び装置の設置はほぼ終了し、今年度中の短寿命核の加速実験を目指して装置全体の立ち上げ及びインターロックなどの安全装置の製作を現在行っている。また短寿命核加速施設からの1MeV/uのビームを既存の超電導ブースターで加速できるように現在のブースターの前段部に
 =6%のlow
=6%のlow 空洞を設置し最大5
空洞を設置し最大5 7MeV/uまで加速する計画を進めている。研究会ではこのほかに昨年度のタンデム加速器施設の運転、整備の状況について報告する。
7MeV/uまで加速する計画を進めている。研究会ではこのほかに昨年度のタンデム加速器施設の運転、整備の状況について報告する。
遠藤 章; 佐藤 薫; 野口 宏; 田中 進; 飯田 孝夫*; 古市 真也*; 神田 征夫*; 沖 雄一*
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 256(2), p.231 - 237, 2003/05
被引用回数:7 パーセンタイル:45.09(Chemistry, Analytical)高エネルギー中性子場で発生する放射性エアロゾルの生成機構を解明するために、DOPエアロゾルを浮遊させたアルゴン及びクリプトンガスを45MeV及び65MeVの準単色中性子ビームを用いて照射し、生成される Cl,
Cl,  Cl,
Cl,  Br 及び
Br 及び  Br エアロゾルの粒径分布を測定した。生成される放射性エアロゾルの粒径分布に対して、添加するDOPの粒径,照射に用いる中性子ビームのエネルギーの影響,また、生成される核種による粒径分布の違いを検討した。その結果、実測された放射性エアロゾルの粒径分布は、中性子照射による核反応で生成された放射性核種がDOPエアロゾルの表面に付着するモデルを用いて解析できることを明らかにした。
Br エアロゾルの粒径分布を測定した。生成される放射性エアロゾルの粒径分布に対して、添加するDOPの粒径,照射に用いる中性子ビームのエネルギーの影響,また、生成される核種による粒径分布の違いを検討した。その結果、実測された放射性エアロゾルの粒径分布は、中性子照射による核反応で生成された放射性核種がDOPエアロゾルの表面に付着するモデルを用いて解析できることを明らかにした。
吉田 忠; 神田 将; 竹内 末広; 堀江 活三; 大内 勲; 月橋 芳廣; 花島 進; 阿部 信市; 石崎 暢洋; 田山 豪一; et al.
第15回タンデム加速器及びその周辺技術の研究会報告集, p.51 - 53, 2003/03
原研タンデム加速器は1982年実験利用が開始された。当初は高エネルギーの放電に対し加速器内部の機器健全性が保ちきれず、度重なる整備をしてきた。その結果、現在では非常に安定した運転を継続しており、年間5000時間の運転を継続している。一昨年から高電圧端子にはECRイオン源を設置し、タンデム加速器では初めての希ガスイオン加速を果たし、多くの実験研究に利用されてきた。現在の加速器は、約40核種の安定核イオンを発生,加速できるが、平成13年度から不安定核及び負イオンでは発生不可能なあるいは電流値の低さから利用されてこなかったイオン種の加速を可能にするRNB(放射性核種ビーム)加速計画が実施されており、平成15年度には設置完了する見込みである。この計画は原研とKEK(高エネルギー加速器研究機構)との共同研究であり、近い将来不安定核を利用した研究を開始する予定である。本報告はこれらの研究環境整備の報告を交え最近行った加速器開発を報告する。
竹内 末広; 仲野谷 孝充; 株本 裕史; 石崎 暢洋; 松田 誠; 月橋 芳廣; 神田 将; 田山 豪一; 阿部 信市; 吉田 忠
第14回加速器科学研究発表会報告集, p.308 - 310, 2003/00
原研タンデム加速器は端子電圧を改善するためコンプレスドジオメトリの加速管に更新した。更新にあたって加速管内を高圧純水洗浄するアイデアを検証するための種種の簡単な試験と1MV及び3MVの高電圧試験を行った。その結果加速管セラミック表面は剥がれやすい微粒子がかなり付着していて、高圧純水洗浄等で清浄化することで高電圧性能が飛躍的に改善されることがわかった。加速管更新については経過を述べる。
遠藤 章; 野口 宏; 田中 進; 神田 征夫*; 沖 雄一*; 飯田 孝夫*; 佐藤 薫; 津田 修一
Applied Radiation and Isotopes, 56(4), p.615 - 620, 2002/04
被引用回数:3 パーセンタイル:22.59(Chemistry, Inorganic & Nuclear)高エネルギー加速器施設における内部被ばく評価のために、高エネルギー中性子照射場で発生する放射性エアロゾルの生成機構及び粒径分布を解析した。TIARAの65MeV準単色中性子照射場を用い、DOPエアロゾルを添加したArガスを照射した。照射後、エレクトリカルロープレッシャインパクタを用いて、DOPエアロゾルの個数基準の粒径分布、 Arの(n, 2np),(n, np)反応からそれぞれ生成される
Arの(n, 2np),(n, np)反応からそれぞれ生成される C,
C, Clエアロゾルの放射能基準の粒径分布を測定した。実験で得られた放射性エアロゾルの粒径分布は、核反応で生成された
Clエアロゾルの放射能基準の粒径分布を測定した。実験で得られた放射性エアロゾルの粒径分布は、核反応で生成された Cl,
Cl, Cl原子が、DOPエアロゾル表面に付着すると仮定し評価した粒径分布と、良く一致することが明らかとなった。
Cl原子が、DOPエアロゾル表面に付着すると仮定し評価した粒径分布と、良く一致することが明らかとなった。
坪井 裕; 神田 啓治*
日本原子力学会誌, 43(8), p.806 - 822, 2001/08
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Nuclear Science & Technology)現在、濃縮ウラン等の核物質を、多量かつ継続的に、国と国の間で移転が行われるような場合には、その二国間で原子力協力協定を締結し、移転された核物質やそれから生成された核物質等に対して、平和非爆発利用目的への限定、保障措置の適用、第3国移転の事前同意といった、さまざま規制を設定した上で行われることが一般的である。我が国は、現在、米、英、加、豪、仏及び中国の6ヶ国と、このような原子力協力協定を締結している。このような二国間協定に基づく規制を担保する上で、協定の対象となる、協定に基づき移転された核物質等に対して、二国間協定の相手国の国籍を立てて規制が行われている。本稿では、二国間協定の歴史、背景についての分析を行い、二国間協定で求められる規制の内容の整理を行うとともに、二国間協定が核不拡散に果たしている役割、核物質等の国籍管理にかかわる課題についての考察を行った。
坪井 裕; 神田 啓治*
日本原子力学会誌, 43(1), p.67 - 82, 2001/01
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Nuclear Science & Technology)核不拡散条約(NPT)が、非核兵器国に対してはすべての核物質にIAEAの保障措置を要求する一方、核兵器国に対しては、このような義務付けがない点をとらえて、不均衡性、不平等性の問題が指摘される。核兵器国は自主的に保障措置協定を締結しているものの、査察は一部の施設に対してしか実施されていない。英仏は民生用核物質のみではあるがユーラトムの保障措置を受け入れている。最近は解体核兵器等からの余剰核物質に対して保障措置を適用することの検討や、カットオフ条約の検証措置としての保障措置も検討されている。核物質が核兵器等に使用されることのないようにする国際的な制度は恒久的に必要であり、そのためにはすべての国が受け入れられるような普遍性が必要である。本論文では、核兵器国における保障措置の実態を分析し、非核兵器国との不均衡性、不平等性を実質的に解消し、保障措置を普遍化させるための方策案を提示する。
横山 須美; 佐藤 薫; 真辺 健太郎; 遠藤 章; 野口 宏; 金子 広久; 沖 雄一*; 長田 直之*; 神田 征夫*; 飯田 孝夫*; et al.
no journal, ,
高エネルギー陽子加速器施設では、2次的に発生する高エネルギー陽子と空気との核破砕反応等により、空気中に浮遊性放射性核種や放射線分解生成物が生成される。後者は核種の性状(粒径や化学形)に影響を与える。このため、浮遊性核種の性状と生成機構の解明は、高エネルギー加速器施設での内部被ばく線量評価法及び空気モニタリング技術を確立するうえで必要不可欠である。そこで、平成15 17年に連携重点研究「陽子加速器施設における線量評価に関する研究」の一環として、知見が十分ではない空気中のAr-40から生成される放射性塩素(Cl-38及びCl-39)のエアロゾル・ガス比,非放射性エアロゾルの粒径分布,硝酸生成率(G値)等をTIARAの陽子照射場を用いて明らかにした。この結果、放射性塩素は、50%以上がエアロゾルで存在すること,生成初期段階の非放射性エアロゾルの中央径は12
17年に連携重点研究「陽子加速器施設における線量評価に関する研究」の一環として、知見が十分ではない空気中のAr-40から生成される放射性塩素(Cl-38及びCl-39)のエアロゾル・ガス比,非放射性エアロゾルの粒径分布,硝酸生成率(G値)等をTIARAの陽子照射場を用いて明らかにした。この結果、放射性塩素は、50%以上がエアロゾルで存在すること,生成初期段階の非放射性エアロゾルの中央径は12 20nmであること,陽子照射により空気中に生成された硝酸のG値は1.46
20nmであること,陽子照射により空気中に生成された硝酸のG値は1.46 0.12であること等を明らかにした。これらの結果より、性状ごとの線量評価が可能になった。
0.12であること等を明らかにした。これらの結果より、性状ごとの線量評価が可能になった。
西村 昭彦; 上地 宏*; 山田 知典; 神田 清人*
no journal, ,
ピコ秒レーザ加工により製作した耐熱FBGセンサを活用し、高温溶融塩の圧力計測を実施する。高温溶融塩は再生可能エネルギーの変動分を熱として平準化するための蓄熱材料である。ステンレス小型容器の一端にダイヤフラムを取り付け、炭酸ナトリウムを充填する。これを通電加熱し溶融させ、アルゴンガスによる加圧を行う。ダイヤフラムの変形測定にはレーザー干渉・変位計測計による測定も実施し、耐熱FBGセンサによる計測値との比較を行う。また、この蓄熱を活用し熱起電力による発電を行い、小消費電力の計測装置の駆動も試みる。これらを取り纏めた研究開発プロジェクトの意義について述べる。
神田 大徳; 江沼 康弘; 二神 敏; 近澤 佳隆; 岡野 靖; 吉岡 直樹*; 宇敷 洋*
no journal, ,
GIFの安全設計ガイドライン(SDG)では第4世代炉としてのナトリウム-水反応に対する安全対策が議論されている。本報では、次世代ナトリウム冷却高速炉の蒸気発生器(SG)でのナトリウム-水反応事象に対し、多重性・多様性を拡張した設計対策を実施し、多重故障に対する安全性を評価・確認した。
小野田 忍; 山本 卓; 阿部 浩之; 花屋 博秋; 大島 武; 谷口 尚*; 寺地 徳之*; 渡邊 賢司*; 小泉 聡*; 神田 久生*; et al.
no journal, ,
量子情報素子や磁気センサーへの応用,超伝導キュービットとのハイブリッド系が注目されている窒素-空孔(NV)センターでは、電子スピンを持つ不純物窒素や欠陥による双極子場, C核スピンの双極子場,他のNVセンターの双極子場など、コヒーレンス時間を短くする要因をできるだけ排除して、最適の濃度あるいは配列を作成するエンジニアリングが求められる。窒素濃度,同位体濃度の異なる結晶にイオン照射や熱処理,高温電子線照射を行い、それぞれの応用に対して最適のものを求める試みを行った。熱処理を800から1200
C核スピンの双極子場,他のNVセンターの双極子場など、コヒーレンス時間を短くする要因をできるだけ排除して、最適の濃度あるいは配列を作成するエンジニアリングが求められる。窒素濃度,同位体濃度の異なる結晶にイオン照射や熱処理,高温電子線照射を行い、それぞれの応用に対して最適のものを求める試みを行った。熱処理を800から1200 Cまで変化させてNVセンターやそれ以外の欠陥を調べた結果、1000
Cまで変化させてNVセンターやそれ以外の欠陥を調べた結果、1000 Cの熱処理が最も優れていることを明らかにできた。また、マイクロビームとシングルイオンヒット技術を利用して、量子情報素子の最も基本的なNVセンターのペアを作成することに成功した。さらに、空孔が格子中を動き回るような高温(700
Cの熱処理が最も優れていることを明らかにできた。また、マイクロビームとシングルイオンヒット技術を利用して、量子情報素子の最も基本的なNVセンターのペアを作成することに成功した。さらに、空孔が格子中を動き回るような高温(700 C)の電子線照射を用いることにより、NVセンターの広い濃度領域(2
C)の電子線照射を用いることにより、NVセンターの広い濃度領域(2 30ppm)に渡って、コヒーレンス時間が、残存する窒素の双極子場の搖動ではなく、NVセンター同士の双極子双極子相互作用で決まるような作成法に成功した。
30ppm)に渡って、コヒーレンス時間が、残存する窒素の双極子場の搖動ではなく、NVセンター同士の双極子双極子相互作用で決まるような作成法に成功した。