Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
奈良 郁子*; 渡邊 隆広; Lougheed, B.*; Obrochta, S.*
Radiocarbon, 66(6), p.1940 - 1957, 2024/12
被引用回数:1 パーセンタイル:14.77(Geochemistry & Geophysics)南シベリアのバイカル湖堆積物の放射性炭素年代測定結果を新たに取得しコア試料の年代軸を再構築した。コア試料の年代値と堆積深度の不確実性を考慮するために、本研究では新しい年代-深度モデル(age-depth modeling routine, undatable)を使用した。その結果、19cal kaBPと14cal kaBPのメルトウォーターパルス時期、及び21-20cal kaBPの最終氷期最盛期において堆積速度の著しい変動が認められた。
丹羽 正和; 島田 顕臣; 浅森 浩一; 末岡 茂; 小松 哲也; 中嶋 徹; 小形 学; 内田 真緒; 西山 成哲; 田中 桐葉; et al.
JAEA-Review 2024-035, 29 Pages, 2024/09
本計画書では、高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する研究開発のうち、深地層の科学的研究の一環として実施している地質環境の長期安定性に関する研究について、第4期中長期目標期間(令和4年度 令和10年度)における令和6年度の研究開発計画を取りまとめた。本計画の策定にあたっては、これまでの研究開発成果や大学等で行われている最新の研究成果に加え、地層処分事業実施主体や規制機関等の動向を考慮した。研究の実施にあたっては、地層処分事業における概要・精密調査や国の安全規制に対し研究成果を適時反映できるよう、(1)調査技術の開発・体系化、(2)長期予測・影響評価モデルの開発、(3)年代測定技術の開発の三つの枠組みで研究開発を推進する。
令和10年度)における令和6年度の研究開発計画を取りまとめた。本計画の策定にあたっては、これまでの研究開発成果や大学等で行われている最新の研究成果に加え、地層処分事業実施主体や規制機関等の動向を考慮した。研究の実施にあたっては、地層処分事業における概要・精密調査や国の安全規制に対し研究成果を適時反映できるよう、(1)調査技術の開発・体系化、(2)長期予測・影響評価モデルの開発、(3)年代測定技術の開発の三つの枠組みで研究開発を推進する。
 Be analysis of the rock samples from the northeastern shore of Lake Pumoyum Co in south Tibetan Plateau
Be analysis of the rock samples from the northeastern shore of Lake Pumoyum Co in south Tibetan Plateau奈良 郁子*; 渡邊 隆広; 國分 陽子; Zhu, L.*
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 539, p.28 - 32, 2023/06
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Instruments & Instrumentation)チベット高原はその広大な面積、及び地形学的な特徴から、地球規模の気候変動及び物質循環に対して重要な役割を果たしている。現在のチベット高原南部における降水量の変動は、特に南西からのインドモンスーンによる影響を受けることが知られている。したがって、この地域の降水量変動を復元することにより、アジアにおける過去のモンスーン活動の変動に関する情報が得られると期待される。チベット高原南部の標高約5,030mに位置するプマユムツォ湖は世界で最も高所に存在する湖の一つである。これまでにプマユムツォ湖の湖底堆積物を用いて過去の湖水面変動や環境変動の推測に関する研究が行われてきた。本研究では湖の北東側の湖岸から岩石試料を採取し、岩石中で生成する宇宙線生成核種である Be等の測定を実施することで、湖水面変動に伴う岩石の露出年代の推定を試みた。プマユムツォ湖湖岸の岩石中の
Be等の測定を実施することで、湖水面変動に伴う岩石の露出年代の推定を試みた。プマユムツォ湖湖岸の岩石中の Be濃度は、3.78-10.8
Be濃度は、3.78-10.8 10
10 (atoms/g)の範囲を示した。仮に岩石中の
(atoms/g)の範囲を示した。仮に岩石中の Be濃度が、湖水面変動に影響されているとすれば、
Be濃度が、湖水面変動に影響されているとすれば、 Be濃度は湖から離れるに従い増加するはずである。しかし、プマユムツォ湖湖岸の岩石中の
Be濃度は湖から離れるに従い増加するはずである。しかし、プマユムツォ湖湖岸の岩石中の Be濃度の分布は、湖から離れるに従って減少する傾向を示した。したがって、プマユムツォ湖の湖岸段丘から採取された岩石中の
Be濃度の分布は、湖から離れるに従って減少する傾向を示した。したがって、プマユムツォ湖の湖岸段丘から採取された岩石中の Be濃度の分布は、岩石の露出年代よりも、侵食速度もしくはテクトニックな変動に影響されている可能性が高いと考えられる。
Be濃度の分布は、岩石の露出年代よりも、侵食速度もしくはテクトニックな変動に影響されている可能性が高いと考えられる。
奈良 郁子*; 渡邊 隆広; 松中 哲也*; 山崎 慎一*; 土屋 範芳*; 瀬戸 浩二*; 山田 和芳*; 安田 喜憲*
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 592, p.110907_1 - 110907_11, 2022/04
被引用回数:4 パーセンタイル:52.59(Geography, Physical)小川原湖は、下北半島の太平洋沿岸に位置した汽水湖である。これまでの研究により、完新世の後期に海水準が低下したことで小川原湖が汽水化したと推測されているが、これまでに正確な年代は明らかにされていなかった。小川原湖が汽水化した年代を明らかにすることにより、過去の海水準変動の時期や規模に関する情報が得られると期待される。本研究では、小川原湖から採取した柱状堆積物(長さ約280m)中の、植物片と全有機炭素の放射性炭素年代測定、及びテフラの同定により堆積層の形成年代を決定した。また、堆積物中のハロゲン元素(臭素およびヨウ素)の鉛直分布を明らかにし、小川原湖の過去の塩分濃度変化を推定した。海水由来と考えられる堆積物中の臭素およびヨウ素濃度の増加時期から、約2200cal BPに小川原湖が汽水化したことが示唆された。
奈良 郁子*; 横山 立憲; 山崎 慎一*; 南 雅代*; 淺原 良浩*; 渡邊 隆広; 山田 和芳*; 土屋 範芳*; 安田 喜憲*
Geochemical Journal, 55(3), p.117 - 133, 2021/00
被引用回数:6 パーセンタイル:39.58(Geochemistry & Geophysics)白頭山噴火年代は西暦946年であることが広く認められている。噴火で分散した白頭山-苫小牧(B-Tm)テフラは、精確な年代を示す鍵層となる。従来は、このテフラを同定するため、火山ガラス片の屈折率と主成分元素組成が使われていた。しかし、希土類元素に着目した微量元素分析やテフラ層の全堆積物に対する微量元素分析はこれまでほとんど報告例がない。本論文では、東北地方の小河原湖の堆積物コアから採取したB-Tmテフラ及び十和田カルデラ(To-a)テフラについて、火山ガラス片と全堆積物の主要元素及び微量元素分析結果を示す。主要元素及び微量元素の深度プロファイルでは、B-Tmテフラ層においてK Oと微量元素の増加が確認されたが、To-aテフラ層においては、これらの元素の増加は確認されなかった。B-Tmテフラ層で検出された高濃度の微量元素は全堆積物だけではなく、ガラス片にも確認された。B-Tmテフラ層のガラス片にみられる元素(特に希土類元素)の組成パターンは、他の日本のテフラガラスとは明らかに異なる。ガラス片と全堆積物の微量元素組成は、B-Tmテフラと他の日本のテフラを区別する上で、有用な指標となると考えられる。
Oと微量元素の増加が確認されたが、To-aテフラ層においては、これらの元素の増加は確認されなかった。B-Tmテフラ層で検出された高濃度の微量元素は全堆積物だけではなく、ガラス片にも確認された。B-Tmテフラ層のガラス片にみられる元素(特に希土類元素)の組成パターンは、他の日本のテフラガラスとは明らかに異なる。ガラス片と全堆積物の微量元素組成は、B-Tmテフラと他の日本のテフラを区別する上で、有用な指標となると考えられる。
渡邊 隆広; 土屋 範芳*; 北村 晃寿*; 山崎 慎一*; 奈良 郁子*
Geochemical Journal, 55(6), p.325 - 340, 2021/00
被引用回数:4 パーセンタイル:26.51(Geochemistry & Geophysics)過去の津波浸水域に関する情報は、今後の防災や減災計画の基礎データとして利用されることが期待されている。しかし、津波堆積物を用いて過去の津波浸水域を復元するにあたり、津波堆積物の供給源の推定、洪水や高潮堆積物との区別等が現状で解決すべき課題となっている。これらの問題を解決する一つの手段として、津波堆積物の地球化学判別手法が有効と考えられるが、国内では東北地方以外での適用例は限られている。特に中部地方太平洋沿岸でのデータはこれまでに得られていない。したがって、本研究では既に採取されている静岡平野の津波堆積物の化学分析を実施し、津波堆積物の判別手法の改良を試みた。分析の結果、ナトリウムとチタンとの相対比およびクラスター分析等の統計解析を用いることによって海由来の物質で形成された堆積層を検出できる可能性が高いことが示唆された。
渡邊 隆広; 石井 千佳子; 石坂 千佳; 丹羽 正和; 島田 耕史; 澤井 祐紀*; 土屋 範芳*; 松中 哲也*; 落合 伸也*; 奈良 郁子*
Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 116(3), p.140 - 158, 2021/00
被引用回数:5 パーセンタイル:32.44(Mineralogy)携帯型成分分析計(potable XRF:ポータブル蛍光エックス線分析装置)は、迅速な化学分析、及びオンサイトでのデータ取得において重要な役割を果たす。しかし、これまでに地質試料に含まれる化学成分の定量分析の実例は限られていた。定量分析を目的として、本研究ではマグネシウムからウランまでの24元素について、地球化学標準試料等を用いて検量線を作成した。さらに、本装置の天然試料への適用性評価のため、敦賀半島等から採取された断層岩試料,能登半島の湖底堆積物、及び仙台平野の津波堆積物の定量分析を実施した。携帯型成分分析計を用いて各試料から得られた定量分析結果は、一部の試料を除き既報値とよく一致した。
渡邊 隆広; 土屋 範芳*; 山崎 慎一*; 澤井 祐紀*; 細田 憲弘*; 奈良 郁子*; 中村 俊夫*; 駒井 武*
Applied Geochemistry, 118, p.104644_1 - 104644_11, 2020/07
被引用回数:18 パーセンタイル:71.44(Geochemistry & Geophysics)地層中の津波堆積物の分布から、過去の津波浸水域を推定することが可能である。津波浸水域に関する情報は、今後の防災や減災計画の基礎データとして利用することが期待されている。しかし、津波堆積物を用いて過去の津波浸水域を復元するにあたり、形成年代の決定、津波堆積物の供給源の特定、洪水や高潮堆積物との区別、及び目視で判別困難な泥質津波堆積物の検出等が現状で解決すべき課題となっている。本研究では上記の問題を解決する一つの手段として、津波堆積物の地球化学判別手法を提案した。仙台平野において採取された堆積物の化学分析を実施し、津波堆積物の判別手法の改良を試みた。分析の結果、カルシウム等の単成分による津波層検出は、後背地の特徴や貝殻の有無などの影響を強く受けることから必ずしも有効ではなく、ケイ素とアルミニウムとの相対比についても、砂層の検出には有効であるが、その供給源に関する情報は乏しいことが示された。一方、ナトリウムとチタンとの相対比を用いることによって海由来の物質で形成された堆積層を検出できる可能性が高いことが示唆された。
 Be測定結果
Be測定結果奈良 郁子*; 渡邊 隆広; 國分 陽子; 堀内 一穂*
JAEA-Conf 2018-002, p.124 - 127, 2019/02
チベット高原はその広大な面積(約2,500,000km )から、世界の高度4km以上の地域の82%を占め、その地形学的特徴から、地球規模の気候変動および物質循環に対して重要な役割を果たしている。プマユムツォ湖は、チベット南部に位置する、湖面標高5020m、表面積281km
)から、世界の高度4km以上の地域の82%を占め、その地形学的特徴から、地球規模の気候変動および物質循環に対して重要な役割を果たしている。プマユムツォ湖は、チベット南部に位置する、湖面標高5020m、表面積281km 、最大水深約65mの高山湖であり、この規模の湖としては世界最高の高度に位置する湖である。プマユムツォ湖の東側には湖岸段丘が形成されており、このことから過去に湖水深が変動していたことが予測されている。本研究では、チベット高原における水循環変動の解明を目的とし、プマユムツォ湖周辺にて採取された岩石試料中の宇宙線生成核種であるベリリウム-10の測定を行った。ベリリウム-10の測定は日本原子力研究開発機構東濃地科学センターが所有するペレトロン年代測定装置を用いて実施した。チベット・プマユムツォ湖湖岸岩石中のベリリウム-10濃度は5.5-7.5
、最大水深約65mの高山湖であり、この規模の湖としては世界最高の高度に位置する湖である。プマユムツォ湖の東側には湖岸段丘が形成されており、このことから過去に湖水深が変動していたことが予測されている。本研究では、チベット高原における水循環変動の解明を目的とし、プマユムツォ湖周辺にて採取された岩石試料中の宇宙線生成核種であるベリリウム-10の測定を行った。ベリリウム-10の測定は日本原子力研究開発機構東濃地科学センターが所有するペレトロン年代測定装置を用いて実施した。チベット・プマユムツォ湖湖岸岩石中のベリリウム-10濃度は5.5-7.5 10
10 (atoms/g)の範囲を示した。また、ベリリウム-10濃度は、湖から離れるに従って減少する傾向を示し、既報のチベット南部地域における浸食速度よりも遅い浸食速度が算出された。
(atoms/g)の範囲を示した。また、ベリリウム-10濃度は、湖から離れるに従って減少する傾向を示し、既報のチベット南部地域における浸食速度よりも遅い浸食速度が算出された。
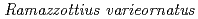 to extreme environments
to extreme environments堀川 大樹*; 山口 理美*; 坂下 哲哉; 田中 大介*; 浜田 信行*; 行弘 文子*; 桑原 宏和*; 國枝 武和*; 渡邊 匡彦*; 中原 雄一*; et al.
Astrobiology, 12(4), p.283 - 289, 2012/04
被引用回数:25 パーセンタイル:68.99(Astronomy & Astrophysics)クマムシの乾燥休眠状態である卵の孵化率について、宇宙空間の特徴的な極限環境要因である放射線(Heイオン線),極低温,高真空に対する耐性を調べた。その結果、50%が孵化できない線量が約500Gy, -196度に曝されても70%以上が孵化し、6 10
10 Paの高真空においた後でも孵化することができることがわかった。以上の結果から、宇宙空間であってもクマムシの耐性能力により、乾眠状態であるならば、存在できる可能性が示唆された。
Paの高真空においた後でも孵化することができることがわかった。以上の結果から、宇宙空間であってもクマムシの耐性能力により、乾眠状態であるならば、存在できる可能性が示唆された。
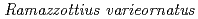 ; A New model animal for astrobiology
; A New model animal for astrobiology堀川 大樹*; 國枝 武和*; 阿部 渉*; 渡邊 匡彦*; 中原 雄一*; 行弘 文子*; 坂下 哲哉; 浜田 信行*; 和田 成一*; 舟山 知夫; et al.
Astrobiology, 8(3), p.549 - 556, 2008/06
被引用回数:109 パーセンタイル:92.02(Astronomy & Astrophysics)クマムシの一種、ヨコヅナクマムシ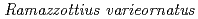 が藻類
が藻類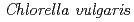 を餌として培養可能であることを報告する。本飼育条件にて、クマムシの平均寿命は35日、卵の孵化に要する時間が5.7日、孵化後9日で排卵した。本種の培養個体の乾眠能力を調査したところ、卵,幼体,成体のいずれの発生段階においても乾眠に移行できることがわかった。さらに、乾眠状態の成体は-196
を餌として培養可能であることを報告する。本飼育条件にて、クマムシの平均寿命は35日、卵の孵化に要する時間が5.7日、孵化後9日で排卵した。本種の培養個体の乾眠能力を調査したところ、卵,幼体,成体のいずれの発生段階においても乾眠に移行できることがわかった。さらに、乾眠状態の成体は-196 Cの超低温や100
Cの超低温や100 Cの高温,99.8%のアセトニトリル,1GPaの超高圧,5000Gyの
Cの高温,99.8%のアセトニトリル,1GPaの超高圧,5000Gyの Heイオン照射にも耐えうることがわかった。以上の結果から、ヨコヅナクマムシは、宇宙生物学における多細胞生物研究のモデルとして有用であると考えられる。
Heイオン照射にも耐えうることがわかった。以上の結果から、ヨコヅナクマムシは、宇宙生物学における多細胞生物研究のモデルとして有用であると考えられる。
長沼 毅*; 岩月 輝希; 村上 由記; 濱 克宏; 岡本 拓士*; 谷本 大輔*; 藤田 夕佳*; 渡辺 史子*; 足立 奈保美*; 佐藤 誠*
JNC TY7400 2003-001, 116 Pages, 2003/05
本報告書は、核燃料サイクル開発機構東濃地科学センターと広島大学生物生産学部間で行われた先行基礎工学共同研究「深部地質環境に対する微生物の影響に関する研究-地下微生物群集の種組成と代謝の多様性に関する研究」の成果を取りまとめるものである。概要を以下に示す。岐阜県東濃地域において、地下深部の微生物の存在量と多様性に関する研究を行った。蛍光染色法による全菌数の計測、呼吸活性やエステラーゼ活性等に基づいて、生菌数を調査したところ、全菌数の約0.001%-100%と求められた。これらの微生物の存在量は、環境要因(岩盤中の割れ目本数、地下水の水理・地球化学条件等)に依存していた。ウラン鉱床を含む堆積岩深部においては、地下水中の酸化還元化学種、微生物生息数、硫酸イオンの硫黄同位体比から、硫酸還元菌による硫酸還元反応が主要な酸化還元反応であることが明らかになった。また、硫酸イオンと塩酸イオンが良い相関を示しながら震度とともに増加しており、硫酸イオンの期限は堆積岩上部の海成層であると考えられた。このような地下水-鉱物-微生物システムにおける酸化還元プロセスは、海成層が陸地化してからも、硫酸還元菌が海成層から供給される硫酸イオンを堆積岩下部に豊富に存在する有機物で還元することで長期間続いてきたと推察される。硫酸イオンの供給速度と岩層中の硫酸態硫黄の含有量から、現在の水理条件が続く場合、硫酸還元菌による硫酸還元反応は今後数十万年間以上にわたって継続し、ウランを保持する還元環境が維持されると推察される。一方、花崗岩中の地下水においては、鉄関連細菌が鉄による酸化還元状態の形成に重要な役割を果たしていると考えられる。特に、花崗岩上部では鉄酸化菌が鉄コロイドの沈没に関与していると推察される。
石野 雅彦; 依田 修; 葉石 靖之*; 有元 史子*; 武田 光博*; 渡辺 精一*; 大貫 惣明*; 阿部 弘亨
Japanese Journal of Applied Physics, Part 1, 41(5A), p.3052 - 3056, 2002/05
被引用回数:12 パーセンタイル:45.31(Physics, Applied)軟X線反射鏡用Mo/Si多層膜の構造を評価するため、高分解能断面TEM観察及びX線回折測定を行った。また、TEM観察から示唆される多層膜モデルを用いて、X線反射率測定結果に対するシミュレーション計算を行い、多層膜の界面構造及び各層の膜厚,密度を定量的に評価した。その結果、Mo層の結晶性であり、Mo層厚が8nm以下のときは、Mo結晶粒径が層厚に一致することを見いだした。また、Mo/Si多層膜の界面に形成される混合層は、Si層側に形成されること,混合層の層厚は、Mo層とSi層の膜厚比にかかわらず約1.4nmであることがわかった。そして、Mo-on-Si界面に形成される混合層の層厚と密度は、Si-on-Mo界面に形成される混合層よりも大きく、Mo層とSi層の密度は、それぞれのバルク密度に比べて僅かに小さいことを見いだした。
奈良 郁子; 木田 福香; 落合 伸也*; 渡邊 隆広; 松中 哲也*; 橋野 虎太郎*; 山崎 慎一*; 土屋 範芳*
no journal, ,
最終氷期最盛期終了後、極域に張り出していた氷床の融解により全球的な相対海水準は最大で約130メートル上昇した。日本沿岸においても約7300年ごろに海水準が極大を迎え、その後の海底面変動(アイソスタシー)により低下した。このような変動は、日本沿岸の地形的な研究によりその時期や規模が報告されているが、時間連続的な考察を深めるためには、連続した堆積物を用いた研究手法が効果的である。私たちは石川県小松市の木場潟堆積物を用いて、過去約11,100年から4,300年前までの過去の海水準変動復元に焦点を当て研究を進めている。これまでの研究成果において、木場潟堆積物の詳細な年代モデルが確立され、かつ過去約7,300年前に急激な含水率変動が発生していたことが明らかとなっている。これらのデータに加え、マルチセンサーコアロガーを用いて堆積物の物性特性および地球化学的データ(ハロゲン元素、微量元素)から後期完新世に発生した海水準変動について報告を行う。
奈良 郁子*; 山崎 慎一*; 渡邊 隆広; 土屋 範芳*; 宮原 ひろ子*; 加藤 丈典*; 箕浦 幸治*; 掛川 武*
no journal, ,
地質試料や湖沼堆積物試料を用いて過去の環境変動を推定するためには、物質の循環と供給源を把握する必要がある。本研究ではロシアのバイカル湖から採取した堆積物の無機化学分析を実施した。特に、ルビジウム、ストロンチウムおよびカリウムの相対量から、バイカル湖の集水域での冬季東アジアモンスーンによる水循環変動、化学風化、物質循環、および物質の供給源の推定を試みた。本研究で得られたバイカル湖のルビジウム/ストロンチウム比の変動は、既報である中国のレス堆積物から推定されている冬季東アジアモンスーンの変動とよく一致した。したがって、湖沼堆積物中のルビジウム/ストロンチウム比は過去の冬季東アジアモンスーン変動の指標となることが示唆された。
渡邊 隆広; 奈良 郁子*
no journal, ,
加速器質量分析法を用いた放射性炭素年代測定手法の発展により、湖沼堆積物や陸成堆積物の年代推定に関する多くの研究成果が報告されている。特に、湖沼の堆積物は撹乱の影響が少なく、古環境変動の推定や、過去に発生した津波等の痕跡について研究が進められている。本発表では、執筆者らによってこれまでに報告した堆積物の放射性炭素年代測定結果について集約し、湖沼や陸成堆積物試料の標準的な年代推定手法の構築に向けて新たな提案を試みる。現在の湖周辺の炭素の供給源を安定同位体比により推定し、かつ植物片と全有機態炭素の年代値の差を把握することにより、湖底堆積物試料の年代値の補正が可能になる。また、湖底や陸域の津波堆積物を用いた災害科学に関する研究例についても紹介する。津波堆積物は海底や沿岸からの物質移動に加え引き波による影響もあり、かつ現生植物の根の混入により、有機物試料の供給源の推定は極めて困難である。湖沼堆積物の研究で確立した手法を応用し、津波堆積物の年代推定を実施した結果について紹介する。
奈良 郁子*; 渡邊 隆広; 國分 陽子; 中村 俊夫*
no journal, ,
大陸域における水循環変動の解析は、貴重な水資源である淡水の確保に繋がる重要な課題である。ユーラシア大陸南東部、南シベリア地域に位置するバイカル湖には、地球上の約20%の淡水(氷床を除く)が貯水されている。特に、気候変動に対応したバイカル湖の長期的な水位変動を推定し、将来の予測に繋げることが重要である。本研究では、バイカル湖の湖底堆積物試料(VER99G12、堆積物試料長さ466cm)を用いて、放射性炭素年代測定から算出した堆積年代値より、最終氷期後期(約3万年前から1万年前)における河川流入量変化の推定を行った。放射性炭素年代測定は、堆積物中の全有機態炭素(TOC)を対象に行った。VER99G12堆積物試料の年堆積速度は、概ね一定であったが、約19ka BP、約14ka BP、約11ka BPにおいて、3回の堆積速度の急激な上昇が見られた。また、堆積速度が上昇する直前に、明瞭な堆積速度の低下が見られた。約14ka BP、約11ka BPにおける堆積速度の上昇期は、地球規模で温暖化した時期に対応していることから、堆積速度の上昇は、温暖化に伴い湖内へ流入する河川水の増加によって引き起こされたと考えられる。
奈良 郁子*; 松中 哲也*; 山崎 慎一*; 土屋 範芳*; 渡邊 隆広; 山田 和芳*; 安田 喜憲*
no journal, ,
小川原湖は、縄文後期の海水準低下により、太平洋の内海であった古小川原湖が後退したことで形成された汽水湖である。小川原湖の汽水化時期を明らかにすることは、縄文後期における東北地域の気候環境変動や汽水化が与える湖内生態系への影響を推測するために重要である。本研究では、小川原湖から採取した柱状堆積物(長さ280m)を用いて、植物片と全有機炭素の放射性炭素年代測定、テフラの同定、鉛-210、およびセシウム-137年代測定により、高精度な年代モデルを構築し、かつ堆積物中の微量元素分析結果を併せることにより、小川原湖の汽水化時期を推定した。堆積物から発見された二つのテフラ層は、屈折率および鉱物組成結果からB-TmテフラおよびTo-aテフラと同定された。植物片の放射性炭素年代測定結果は、B-Tmテフラが示す白頭山噴火年代(946年)と整合的であった。上記の年代測定結果および臭素等の微量元素濃度の変動から、小川原湖は約2000cal BPに汽水化したことが示唆された。
渡邊 隆広; 奈良 郁子*; 植木 忠正*; 土屋 範芳*
no journal, ,
地層中の津波堆積物を用いて過去に繰り返し発生した歴史津波の規模を明らかにすることにより、将来起こりうる津波災害の防災、減災につなげる試みが検討されている。津波堆積物とその他の堆積層を区別するため試料の化学組成が用いられている。津波堆積物の化学分析については、迅速かつ大量の試料を処理する必要がある。しかし、陸域の堆積物はかく乱されるケースが多く、かつ堆積環境が不安定であるため、堆積物の組成は単純ではない。広範囲において適用できる汎用的な化学分析手法および解析手法は未だ確立されていない。そこで本研究では、走査型X線分析顕微鏡を用いた津波堆積物の化学分析手法および得られたデータの解析手法について検討結果を報告する。測定結果は、既報の蛍光X線分析による化学組成データとよく一致しており問題なくデータの蓄積が可能であることが示された。各元素のX線強度の主成分分析を実施した結果、形成過程の異なる津波堆積物砂層と浜堤堆積物砂層の区別ができる可能性が示唆された。今後はより明確に区別するため、多地点のデータの蓄積が必要になる。
渡邊 隆広; 奈良 郁子*; 松中 哲也*; 箕浦 幸治*; 掛川 武*; 山崎 慎一*; 土屋 範芳*; 中村 俊夫*; Junbo, W.*; Liping, Z.*
no journal, ,
湖沼堆積物や石筍試料を用いた高時間解像度(百年から千年スケール)での古環境変動に関する成果がこれまでに報告されている。特に、将来の表層環境や水循環の変動を推測するために、化学組成や同位体組成などの地球化学的手法を用いた過去のモンスーン活動の変遷に関する研究が進められている。過去のモンスーン活動、およびその変動メカニズムの把握に必要な研究対象地域として、日本を含む東アジアなどに加えて、チベット高原が注目されている。しかし、チベット高原における高時間解像度での環境変動解析例は極めて少ない。したがって、本研究ではチベット高原の湖沼堆積物の平均粒径および無機化学組成から推定された過去のモンスーン変動について周期解析を実施し、他地域から得られている解析結果と比較した。本研究では完新世のモンスーン変動におおよそ1000年から1500年の周期が見られ、これまでに報告されている東アジアおよび西アジアの石筍の酸素同位体比から推定されている気候変動の特徴とよく一致した。