Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
 3-
3- 相転移の研究
相転移の研究深谷 有喜; 橋本 美絵; 河裾 厚男; 一宮 彪彦
no journal, ,
Ge(111)表面上に1/3原子層のSn原子を吸着させると、室温において 構造を形成する。この表面は、220K以下になると3
構造を形成する。この表面は、220K以下になると3 3構造へと相転移することが知られている。当初この表面は、2次元系のパイエルス転移として興味がもたれたが、その後の研究からSn原子が熱的に揺らいでいる相転移モデルが提唱されており、未解決な問題として残されている。本研究では、反射高速陽電子回折(RHEPD)を用いて、220Kで見られるSn/Ge(111)表面の
3構造へと相転移することが知られている。当初この表面は、2次元系のパイエルス転移として興味がもたれたが、その後の研究からSn原子が熱的に揺らいでいる相転移モデルが提唱されており、未解決な問題として残されている。本研究では、反射高速陽電子回折(RHEPD)を用いて、220Kで見られるSn/Ge(111)表面の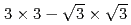 構造相転移について調べた。相転移温度前後においてRHEPDロッキング曲線を測定したところ、両者の曲線には顕著な違いは見られなかった。この結果は、Sn原子の平衡位置が相転移前後で変化しないことを示唆している。また、全反射条件下におけるRHEPD強度の温度依存性を測定したところ、相転移温度以下で、温度が減少するにつれて強度が減少する特異な変化が見られた。以上の結果から、この相転移は秩序・無秩序型であるものの、相転移温度以下ではフォノンのソフト化を伴っていると考えている。
構造相転移について調べた。相転移温度前後においてRHEPDロッキング曲線を測定したところ、両者の曲線には顕著な違いは見られなかった。この結果は、Sn原子の平衡位置が相転移前後で変化しないことを示唆している。また、全反射条件下におけるRHEPD強度の温度依存性を測定したところ、相転移温度以下で、温度が減少するにつれて強度が減少する特異な変化が見られた。以上の結果から、この相転移は秩序・無秩序型であるものの、相転移温度以下ではフォノンのソフト化を伴っていると考えている。
中川 洋; 城地 保昌*; 北尾 彰朗*; 柴田 薫; 郷 信広; 片岡 幹雄
no journal, ,
タンパク質のダイナミクスは周りの水和環境に影響を受けることはよく知られている。本研究では、中性子非弾性散乱によりタンパク質ダイナミクスの特徴であるボソンピークや動力学転移が水和とどのようにかかわっているのかを調べた。極低温では3 4meVにボソンピークが観測され、ピーク位置は水和により高エネルギー側へシフトすることがわかった。これは水素結合を介した水和水とタンパク質の相互作用によってタンパク質の低振動モードのエネルギー地形がより凸凹になったことに起因する。一方、水和量が約0.2(g water/g protein)以上で240K付近において動力学転移が観測された。なぜ動力学転移が水和依存的に生じるのかを調べるために、中性子散乱の同位体効果を利用して水和水のダイナミクスを直接観測した。タンパク質表面の水分子の特異的なダイナミクスが、タンパク質と水分子の界面に存在する水素結合ネットワークを介してタンパク質の振動モードと相互作用し、その結果動力学転移が生じると結論した。
4meVにボソンピークが観測され、ピーク位置は水和により高エネルギー側へシフトすることがわかった。これは水素結合を介した水和水とタンパク質の相互作用によってタンパク質の低振動モードのエネルギー地形がより凸凹になったことに起因する。一方、水和量が約0.2(g water/g protein)以上で240K付近において動力学転移が観測された。なぜ動力学転移が水和依存的に生じるのかを調べるために、中性子散乱の同位体効果を利用して水和水のダイナミクスを直接観測した。タンパク質表面の水分子の特異的なダイナミクスが、タンパク質と水分子の界面に存在する水素結合ネットワークを介してタンパク質の振動モードと相互作用し、その結果動力学転移が生じると結論した。
 の磁気構造の三次元偏極中性子解析
の磁気構造の三次元偏極中性子解析梶本 亮一; 松田 雅昌; 武田 全康; 加倉井 和久; 三井 由佳利*; 吉澤 英樹*; 木村 剛*; 十倉 好紀*
no journal, ,
TbMnO は
は Kでスピンが
Kでスピンが 軸方向を向いて波数
軸方向を向いて波数 で変調するcollinearなサイン波的磁気秩序を示すが、
で変調するcollinearなサイン波的磁気秩序を示すが、 K以下では
K以下では 面内で回転するらせん配列へと変化する。このとき、スピン変調の振幅の大きさは異方的で楕円形のらせん秩序を形成していると言われている。一方、
面内で回転するらせん配列へと変化する。このとき、スピン変調の振幅の大きさは異方的で楕円形のらせん秩序を形成していると言われている。一方、 以下では自発電気分極を生じ、磁性との関係が注目されている。われわれはTbMnO
以下では自発電気分極を生じ、磁性との関係が注目されている。われわれはTbMnO におけるスピン配列のサイン波秩序かららせん秩序への変化を詳細に調べるため、三次元偏極中性子解析装置CRYOPADを用いた偏極中性子回折実験を行った。磁気Bragg 反射
におけるスピン配列のサイン波秩序かららせん秩序への変化を詳細に調べるため、三次元偏極中性子解析装置CRYOPADを用いた偏極中性子回折実験を行った。磁気Bragg 反射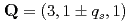 での中性子の偏極率
での中性子の偏極率 (入射中性子のスピンの向きが
(入射中性子のスピンの向きが 、散乱中性子のスピンの向きが
、散乱中性子のスピンの向きが のときの偏極率。
のときの偏極率。 )を観測した結果、TbMnO
)を観測した結果、TbMnO ではcollinearなスピン秩序が
ではcollinearなスピン秩序が で一度にらせんになるのではなく、温度の低下とともに徐々に「膨らんで」らせん秩序に変化していることがわかった。その変化の様子は
で一度にらせんになるのではなく、温度の低下とともに徐々に「膨らんで」らせん秩序に変化していることがわかった。その変化の様子は 以下での自発電気分極の発達と対応しており、非常に興味深い。そして、楕円形のらせん秩序とは、完全な(円形の)らせん秩序になりきれなかったもの、と見ることができる。
以下での自発電気分極の発達と対応しており、非常に興味深い。そして、楕円形のらせん秩序とは、完全な(円形の)らせん秩序になりきれなかったもの、と見ることができる。
 Y
Y MnO
MnO の電気分極と磁気構造
の電気分極と磁気構造梶本 亮一; 横尾 哲也*; 古府 麻衣子*; 野田 耕平*; 桑原 英樹*
no journal, ,
Eu Y
Y MnO
MnO は
は K以下で反強磁性転移を示す。
K以下で反強磁性転移を示す。 K以下で
K以下で 軸に平行な自発電気分極が生じるが、その向きは
軸に平行な自発電気分極が生じるが、その向きは K以下で
K以下で 軸方向へと変化する。強誘電性を示す
軸方向へと変化する。強誘電性を示す MnO
MnO の多くは長周期磁気秩序相がらせん秩序となるときに自発電気分極
の多くは長周期磁気秩序相がらせん秩序となるときに自発電気分極 が出現している。Eu
が出現している。Eu Y
Y MnO
MnO における電気分極の変化と磁気構造の関係を調べるためにEu
における電気分極の変化と磁気構造の関係を調べるためにEu Y
Y MnO
MnO の単結晶試料に対してパルス中性子回折実験を行った。散乱ベクトル
の単結晶試料に対してパルス中性子回折実験を行った。散乱ベクトル の向きが大きく異なる2つの磁気反射
の向きが大きく異なる2つの磁気反射 と
と (
( )の強度の温度変化を測定したところ、両者は
)の強度の温度変化を測定したところ、両者は と
と を境に異なる変化を示し、
を境に異なる変化を示し、 の向きの変化に対応してスピンの向きが変化していることがわかった。その温度変化は、スピン秩序が
の向きの変化に対応してスピンの向きが変化していることがわかった。その温度変化は、スピン秩序が
 T
T
 (
( )では
)では 面内でらせんを描き、T
面内でらせんを描き、T
 (
( )では
)では 面内でらせんを描いている、と考えることで説明できる。
面内でらせんを描いている、と考えることで説明できる。
寺内 正己*; 小池 雅人
no journal, ,
特定したナノスケール領域から、物質の価電子帯状態密度分布を測定することを目的とした電子顕微鏡用軟X線発光分光器を開発した。この装置開発の目的は、大きなバルク単結晶作製が困難な場合や、単相の試料作製が困難な物質に対して、回折コントラスト像観察,電子回折等の電子顕微鏡実験で結晶性を評価した領域から価電子帯の電子状態に関する情報を得ることである。不等間隔回折格子を用いた斜入射平面結像型分光系とCCD検出器を組合せた小型かつ稼動部のない装置において通常の電子顕微鏡実験との両立を前提とし、かつエネルギー分解能の向上を目指した。さらにこの分光器では、3つの不等間隔回折格子を用いて60-1200eVの発光スペクトル測定が可能である。この装置を用い、 ボロンと
ボロンと ボロンの価電子帯DOS形状の違いの測定に初めて成功した。また、さらなる回折効率の向上のため、165-500eV域用の回折格子にNiコートを施し、これまでのAuコートに比べて2-3倍の検出効率向上にも成功した。この装置開発は、TEM用SXES装置の汎用化を目指した、文部科学省のリーディングプロジェクトの一環として行われている(H16-H18)ものである。
ボロンの価電子帯DOS形状の違いの測定に初めて成功した。また、さらなる回折効率の向上のため、165-500eV域用の回折格子にNiコートを施し、これまでのAuコートに比べて2-3倍の検出効率向上にも成功した。この装置開発は、TEM用SXES装置の汎用化を目指した、文部科学省のリーディングプロジェクトの一環として行われている(H16-H18)ものである。
横田 光史
no journal, ,
イジングスピングラス模型について、ベーテ近似と正方形のカクタス近似を用いて、磁場中でのレプリカ対称性の破れを表すAT線を相転移点近傍で求めると、レプリカ対称性の破れている領域は、ベーテ近似では平均場近似よりも狭くなっているのに対して、正方形のカクタス近似では広くなっている。この磁場中でのベーテ近似と正方形のカクタス近似の違いが、近似におけるループの有無と関係するかどうかを調べるために、fcc格子上の模型に対する近似としての三角形のカクタス近似を用いて、秩序関数とAT線を求めた。結果は、定性的には、正方形のカクタス近似の場合と同様の振る舞いを示している。
 P
P のNMR
のNMR徳永 陽; 青木 大*; 酒井 宏典; 藤本 達也; 神戸 振作; 本間 佳哉*; 松田 達磨; 池田 修悟; 山本 悦嗣; 中村 彰夫; et al.
no journal, ,
昨年、東北大学の青木らによって超ウラン元素を初めて含むネプツニウム系充填スクッテルダイト化合物NpFe P
P が発見された。これはThFe
が発見された。これはThFe P
P , UFe
, UFe P
P に続き3つ目の5f電子系のスクッテルダイト化合物となる。講演ではわれわれが最近行った単結晶試料における
に続き3つ目の5f電子系のスクッテルダイト化合物となる。講演ではわれわれが最近行った単結晶試料における P核のNMR測定の結果を報告し、微視的観点からこの物質の電子状態について議論する。
P核のNMR測定の結果を報告し、微視的観点からこの物質の電子状態について議論する。
三井 隆也; 瀬戸 誠; 東谷口 聡*
no journal, ,
 Feを富化した高品質の反強磁性体
Feを富化した高品質の反強磁性体 FeBO
FeBO 単結晶をネール温度直前で純核共鳴ブラッグ反射させると、放射光の優れたビーム特性「狭発散角,微小サイズ,偏光性,パルス性」を維持したまま、neV程度のバンド幅を持つシングルラインの超単色X線を高出力で取り出すことが可能になる。これをプローブ光に利用すれば、放射光によるエネルギー領域のメスバウアー分析が可能だが、これまでの研究ではエネルギー走査法として試料をドップラー振動させて測定する必要があった。しかしながら、極端条件下測定や回折実験を行う場合には、試料を固定して測定できることが望まれる。このためわれわれは、結晶・核モノクロメーター自身をドップラー振動させることで、試料を固定した状態でのメスバウアー分析の可能性を検証した。本発表では、この分光法の原理と実験結果を紹介する。
単結晶をネール温度直前で純核共鳴ブラッグ反射させると、放射光の優れたビーム特性「狭発散角,微小サイズ,偏光性,パルス性」を維持したまま、neV程度のバンド幅を持つシングルラインの超単色X線を高出力で取り出すことが可能になる。これをプローブ光に利用すれば、放射光によるエネルギー領域のメスバウアー分析が可能だが、これまでの研究ではエネルギー走査法として試料をドップラー振動させて測定する必要があった。しかしながら、極端条件下測定や回折実験を行う場合には、試料を固定して測定できることが望まれる。このためわれわれは、結晶・核モノクロメーター自身をドップラー振動させることで、試料を固定した状態でのメスバウアー分析の可能性を検証した。本発表では、この分光法の原理と実験結果を紹介する。
乙部 智仁; 山極 満; 矢花 一浩*; 岩田 潤一*; 中務 孝*; Bertsch, G. F.*
no journal, ,
物質のレーザーによる加工及び制御において重要な過程である、電子の励起過程を時間依存密度汎関数法を用いて第一原理的に計算をした。その結果、透明な誘電体がレーザーによって絶縁崩壊を起こし、金属的振る舞いをする過程の詳細がわかってきた。特に絶縁崩壊後において励起電子が自由電子として振舞いプラズマ振動を起こしていることがわかった。その詳細とエネルギー吸収,光学応答の時間変化について発表を行う。
匂坂 明人; 大道 博行; Pirozhkov, A. S.; 小倉 浩一; 織茂 聡; 森 道昭; 余語 覚文; 中村 衆*; 岩下 芳久*; 白井 敏之*; et al.
no journal, ,
超短パルス高強度レーザーと物質との相互作用により、高エネルギーのイオンや電子,X線,テラヘルツ領域の電磁波などが発生する。高エネルギー粒子とテラヘルツ波を同時に発生させることで、粒子単独で発生させた場合とは異なる利用研究が期待される。本研究では、プロトンとテラヘルツ波の同時発生を目的として実験を行った。日本原子力研究開発機構設置のチタンサファイアレーザー(JLITE-X)を用いて、チタンの薄膜ターゲットに照射した。集光強度は、ビームウエストで2 3
3 10
10 W/cm
W/cm であった。プロトン計測と同時にレーザーのプリパルスにより生成されるプリフォームドプラズマを干渉計測により測定した。プリフォームドプラズマサイズに対するプロトン発生の依存性を調べた結果、プリフォームドプラズマを抑制することでプロトンの発生量が大きく変化することがわかった。そして、プロトン発生に最適なプリフォームドプラズマ条件において、テラヘルツ波の発生していることがわかった。講演では、得られた実験結果とその解析結果について報告する予定である。
であった。プロトン計測と同時にレーザーのプリパルスにより生成されるプリフォームドプラズマを干渉計測により測定した。プリフォームドプラズマサイズに対するプロトン発生の依存性を調べた結果、プリフォームドプラズマを抑制することでプロトンの発生量が大きく変化することがわかった。そして、プロトン発生に最適なプリフォームドプラズマ条件において、テラヘルツ波の発生していることがわかった。講演では、得られた実験結果とその解析結果について報告する予定である。
 における重い電子状態の起源
における重い電子状態の起源神戸 振作; 酒井 宏典; 徳永 陽; 松田 達磨; 藤本 達也; 池田 修悟; 芳賀 芳範; 大貫 惇睦*
no journal, ,
USn はAuCu
はAuCu 構造の立方対称性を持ち、最低温まで磁気秩序を示さない。この化合物の比熱係数
構造の立方対称性を持ち、最低温まで磁気秩序を示さない。この化合物の比熱係数 は170mJ/K
は170mJ/K molと大きく、Wilson比も1のオーダーである。静磁化率は高温でC.W.的で20K付近に極大を持ち、その後フラットになっている。これらの挙動は、低温でこの化合物が重い電子系になっていることを示している。一方、Uサイトは立方対称であることから5f電子の軌道縮退の効果が低温で現れている可能性がある。本研究は、このU化合物の低温での静的動的挙動が、従来の縮退度2の遍歴磁性体理論(SCR)だけで説明できるか、軌道縮退効果が現れるのかを明らかにすることを目的としている。
molと大きく、Wilson比も1のオーダーである。静磁化率は高温でC.W.的で20K付近に極大を持ち、その後フラットになっている。これらの挙動は、低温でこの化合物が重い電子系になっていることを示している。一方、Uサイトは立方対称であることから5f電子の軌道縮退の効果が低温で現れている可能性がある。本研究は、このU化合物の低温での静的動的挙動が、従来の縮退度2の遍歴磁性体理論(SCR)だけで説明できるか、軌道縮退効果が現れるのかを明らかにすることを目的としている。
立岩 尚之; 芳賀 芳範; 山本 悦嗣; 松田 達磨; 池田 修悟; 大貫 惇睦*
no journal, ,
UIrはキュリー温度T =46Kの強磁性物質である。高圧下ではFM1, FM2, FM3の複数の強磁性相が存在し、FM3の臨界圧力2.6GPa近傍では圧力誘起超伝導の存在が報告されている。本研究では高圧下比熱測定を通して熱力学的観点から圧力相図を検討した。高圧下比熱測定はピストンシリンダー型圧力セルを使用して熱電対を用いて交流比熱測定を高圧下で行った。1.58GPaまでの比熱測定から、T
=46Kの強磁性物質である。高圧下ではFM1, FM2, FM3の複数の強磁性相が存在し、FM3の臨界圧力2.6GPa近傍では圧力誘起超伝導の存在が報告されている。本研究では高圧下比熱測定を通して熱力学的観点から圧力相図を検討した。高圧下比熱測定はピストンシリンダー型圧力セルを使用して熱電対を用いて交流比熱測定を高圧下で行った。1.58GPaまでの比熱測定から、T における比熱異常の存在を確認し、その圧力依存性からFM1相の存在を同定した。さらに比熱曲線の弱い異常からFM3相の相領域の存在を確認した。しかし、FM2相に関しては本熱力学的測定からその相境界に何の異常も観測されなかった。過去の電気抵抗・交流磁化率測定から得られた圧力相図と本研究の相図を比較検討する。
における比熱異常の存在を確認し、その圧力依存性からFM1相の存在を同定した。さらに比熱曲線の弱い異常からFM3相の相領域の存在を確認した。しかし、FM2相に関しては本熱力学的測定からその相境界に何の異常も観測されなかった。過去の電気抵抗・交流磁化率測定から得られた圧力相図と本研究の相図を比較検討する。
坂井 徹; 利根川 孝*; 岡本 清美*
no journal, ,
最近合成された金属錯体からなる一次元混合スピンフェリ磁性体における磁化過程を数値的厳密対角化と有限サイズスケーリング及び密度行列繰り込み群によって理論的に解析した結果、量子効果により飽和磁化の3分の2のところに新しい磁化プラトー状態が実現することが示された。また、この磁化プラトー状態が生じる機構には3種類あることも判明し、異方性パラメータを変化させた場合の磁化3分の2における相図を得た。
森林 健悟
no journal, ,
この研究の目的は、重粒子線と生体との間の相互作用で生じる原子分子データの評価を行い、そのデータをもとにブラッグピーク付近での重粒子線のエネルギー付与の空間分布(飛跡構造)及び重粒子・生体間の相互作用から生じる二次電子のエネルギー分布,X線の計算を行い、DNA損傷の解析に必要なデータを生産するコードを作成し、データを生産することである。今回の発表では、固体密度程度(10 /cm
/cm )の水素分子中でのヘリウム,リチウム,炭素イオンの振舞いに関して、ブラッグピーク付近での飛跡構造計算を行い、原子分子過程の役割に関して議論する。原子分子過程としてイオン衝突電離過程(A
)の水素分子中でのヘリウム,リチウム,炭素イオンの振舞いに関して、ブラッグピーク付近での飛跡構造計算を行い、原子分子過程の役割に関して議論する。原子分子過程としてイオン衝突電離過程(A +B
+B A
A +B
+B , A
, A :入射イオン, B:標的分子)のみを考慮した場合とその他電荷移行(A
:入射イオン, B:標的分子)のみを考慮した場合とその他電荷移行(A +B
+B A
A +B
+B ),電子損失(A
),電子損失(A +B
+B A
A +B)過程を考慮した場合の計算を行った。ブラッグピーク付近で粒子の阻止能を評価したところ原子番号が大きくなるほど両者の差が大きくなることがわかった。炭素イオンの場合、ブラッグピークの位置,飛程において両者の計算で数10
+B)過程を考慮した場合の計算を行った。ブラッグピーク付近で粒子の阻止能を評価したところ原子番号が大きくなるほど両者の差が大きくなることがわかった。炭素イオンの場合、ブラッグピークの位置,飛程において両者の計算で数10 mから100
mから100 m程度の差が生じた。この長さは、細胞一個分程度の大きさである。生体研究の場合、標的は、おもに水で、今回対象とした水素分子とは異なるが、マイクロビームを用いた一細胞照射実験では、原子分子過程による電荷数の変化が大きく影響する可能性があることを示唆している。
m程度の差が生じた。この長さは、細胞一個分程度の大きさである。生体研究の場合、標的は、おもに水で、今回対象とした水素分子とは異なるが、マイクロビームを用いた一細胞照射実験では、原子分子過程による電荷数の変化が大きく影響する可能性があることを示唆している。
 Cu
Cu O
O の共鳴非弾性X線散乱
の共鳴非弾性X線散乱石井 賢司; 筒井 健二*; 遠山 貴己*; 稲見 俊哉; 水木 純一郎; 村上 洋一*; 遠藤 康夫*; 前川 禎通*; 工藤 一貴*; 小池 洋二*; et al.
no journal, ,
(La,Sr,Ca) Cu
Cu O
O は銅酸化物高温超伝導体との関連で注目されている物質である。ほとんどの銅酸化物超伝導体の共通ユニットであるCuO
は銅酸化物高温超伝導体との関連で注目されている物質である。ほとんどの銅酸化物超伝導体の共通ユニットであるCuO 面を持たないにもかかわらず、Sr
面を持たないにもかかわらず、Sr Ca
Ca Cu
Cu O
O は高圧下で超伝導体となる。銅の
は高圧下で超伝導体となる。銅の 吸収端で行った(La,Sr,Ca)
吸収端で行った(La,Sr,Ca) Cu
Cu O
O の共鳴非弾性X線散乱の結果について報告する。モットギャップを越えるバンド間励起とギャップ内に現れるバンド内励起の運動量依存性がホール濃度に対してどのように変化するかに注目する。得られた実験結果は理論の予想とよく一致している。
の共鳴非弾性X線散乱の結果について報告する。モットギャップを越えるバンド間励起とギャップ内に現れるバンド内励起の運動量依存性がホール濃度に対してどのように変化するかに注目する。得られた実験結果は理論の予想とよく一致している。
大場 洋次郎; 佐藤 徹哉*; 篠原 武尚
no journal, ,
われわれはこれまでPdナノ粒子における強磁性の発現を実験的に確認し、その強磁性の起源を調べてきた。実験結果から、強磁性領域は表面と内部の2つに分かれ、粒子表面における強磁性の出現は表面効果に起因することがわかったが、粒子内部の強磁性の起源は明らかになっていない。結晶欠陥がPdに強磁性を誘起する可能性が種々の理論計算により示唆されている。そこで、Pdナノ粒子中の結晶欠陥を定量的に解析して磁化との関係を検討した。不純物や酸化物などの影響を除き、清浄な試料を得るため、Pdナノ粒子(平均粒径 20nm)の作製にはガス中蒸発法を用いた。結晶構造及び結晶欠陥はX線回折より見積られた。解析の結果、不均一ひずみが増加するほど飽和磁化が大きくなる傾向が見られた。これより、不均一ひずみがナノ粒子内部における強磁性の起源であると考えることができる。しかしながら、見積られた不均一ひずみの大きさは理論計算結果による見積りと比較して小さいため、従来の予測よりも小さいひずみや、不均一ひずみによる対称性の局所的な変化などが強磁性に寄与する可能性が考えられる。
20nm)の作製にはガス中蒸発法を用いた。結晶構造及び結晶欠陥はX線回折より見積られた。解析の結果、不均一ひずみが増加するほど飽和磁化が大きくなる傾向が見られた。これより、不均一ひずみがナノ粒子内部における強磁性の起源であると考えることができる。しかしながら、見積られた不均一ひずみの大きさは理論計算結果による見積りと比較して小さいため、従来の予測よりも小さいひずみや、不均一ひずみによる対称性の局所的な変化などが強磁性に寄与する可能性が考えられる。
石川 法人; 知見 康弘; 道上 修*; 太田 靖之*; 齋藤 勇一; 千葉 敦也; 福住 正文*; 堀 史説*; 岩瀬 彰宏*
no journal, ,
本研究では、弾性衝突効果が支配的であるクラスターを利用して、単原子ビームでは発現しないクラスタービーム特有の欠陥生成について調べた。照射後の欠陥評価の際に、X線回折法を用いて調べた結果、形成される欠陥量としては単原子ビームとクラスタービームとは違いはないが、その欠陥分布に違いがあり、結晶歪にその違いが現れることがわかった。
 薄膜の光照射及びイオン照射によるポリマー化の比較
薄膜の光照射及びイオン照射によるポリマー化の比較山田 海成; 谷本 久典*; 水林 博*; 境 誠司; 楢本 洋; 鳴海 一雅
no journal, ,
C 結晶は、高圧の印加や光照射などによって重合化(ポリマー化)することが知られている。最近、超極限環境下における固体の原子制御と新奇物質の探索グループで、C
結晶は、高圧の印加や光照射などによって重合化(ポリマー化)することが知られている。最近、超極限環境下における固体の原子制御と新奇物質の探索グループで、C 薄膜にイオン照射を行った際に既知のポリマー化現象と類似のラマンピークのシフトが生じることが見いだされ、イオン照射誘起ポリマー化を提唱したが、詳細なラマンスペクトルの特徴がポリマー化現象と異なるなど、イオン照射効果の詳細は不明であった。今回、炭素イオン照射及びUV光の照射によるC
薄膜にイオン照射を行った際に既知のポリマー化現象と類似のラマンピークのシフトが生じることが見いだされ、イオン照射誘起ポリマー化を提唱したが、詳細なラマンスペクトルの特徴がポリマー化現象と異なるなど、イオン照射効果の詳細は不明であった。今回、炭素イオン照射及びUV光の照射によるC の状態変化の過程をC
の状態変化の過程をC 薄膜の弾性的特性変化により追究した。イオン照射について、ラマンスペクトルに変化が生じるよりも低い照射量の領域で弾性率の増大が見られ、それ以上の照射量領域では、照射量の増大とともに弾性率が低下した。内部摩擦について、低照射領域でC
薄膜の弾性的特性変化により追究した。イオン照射について、ラマンスペクトルに変化が生じるよりも低い照射量の領域で弾性率の増大が見られ、それ以上の照射量領域では、照射量の増大とともに弾性率が低下した。内部摩擦について、低照射領域でC の分子回転に起因する内部摩擦ピーク強度に減少傾向が見られたことから、弾性率の増大は、膜中の少量のC
の分子回転に起因する内部摩擦ピーク強度に減少傾向が見られたことから、弾性率の増大は、膜中の少量のC 分子について重合が生じている可能性が高い。一方、より照射量が大きな領域でヤング率の減少と格子定数の減少が同時に生じることから、ラマンピークのシフトはポリマー化に起因しないことが結論でき、同シフトはC
分子について重合が生じている可能性が高い。一方、より照射量が大きな領域でヤング率の減少と格子定数の減少が同時に生じることから、ラマンピークのシフトはポリマー化に起因しないことが結論でき、同シフトはC 分子への欠陥導入との関連が推察される。
分子への欠陥導入との関連が推察される。
 の磁気構造
の磁気構造浄念 信太郎; 目時 直人; 本多 史憲; 金子 耕士; 青木 大*; 山本 悦嗣; 芳賀 芳範; 塩川 佳伸*; 大貫 惇睦
no journal, ,
Np-115化合物は重い電子系超伝導Ce-115及びPu-115化合物と同じ結晶構造である。NpFeGa はq=(1/2 1/2 0), NpCoGa
はq=(1/2 1/2 0), NpCoGa 及びNpRhGa
及びNpRhGa はq=(0 0 1/2)の反強磁性体であり、NpNiGa
はq=(0 0 1/2)の反強磁性体であり、NpNiGa は強磁性とq=(1/2 1/2 1/2)のキャント反強磁性であることが明らかになっている。このようにNpTGa
は強磁性とq=(1/2 1/2 1/2)のキャント反強磁性であることが明らかになっている。このようにNpTGa (T=Fe, Co, Ni, Rh)は磁気構造及び相関が遷移金属によって異なることが大きな特徴であり、5f電子が持つ軌道の自由度が重要な役割を担っていると考えられる。またNpRhGa
(T=Fe, Co, Ni, Rh)は磁気構造及び相関が遷移金属によって異なることが大きな特徴であり、5f電子が持つ軌道の自由度が重要な役割を担っていると考えられる。またNpRhGa 及びNpNiGa
及びNpNiGa では5f電子状態の変化に伴う2段の磁気転移が観察され、5f電子状態・軌道の間の磁気的及び四極子相互作用の競合が重要であることが考えられる。NpPtGa
では5f電子状態の変化に伴う2段の磁気転移が観察され、5f電子状態・軌道の間の磁気的及び四極子相互作用の競合が重要であることが考えられる。NpPtGa は、
は、 =27K以下ではq=(0 0 1/2)に対応する反強磁性秩序を示すことが明らかになった。さらに、面内[100]方向に磁場をかけた場合の帯磁率の異常が磁場中実験により磁気ドメイン構造の変化に対応していることを明らかにした。また、磁気ドメイン構造を変化させるために必要な磁場は、10T以上と非常に大きいことがわかり、NpPtGa
=27K以下ではq=(0 0 1/2)に対応する反強磁性秩序を示すことが明らかになった。さらに、面内[100]方向に磁場をかけた場合の帯磁率の異常が磁場中実験により磁気ドメイン構造の変化に対応していることを明らかにした。また、磁気ドメイン構造を変化させるために必要な磁場は、10T以上と非常に大きいことがわかり、NpPtGa と同じ磁気構造を持つNpRhGa
と同じ磁気構造を持つNpRhGa と共通し、磁気モーメントと四極子の結合が磁気ドメイン構造を安定させると指摘した。
と共通し、磁気モーメントと四極子の結合が磁気ドメイン構造を安定させると指摘した。
菊池 隆之; 奥 隆之; 篠原 武尚; 鈴木 淳市; 石井 佑弥; 武田 全康; 加倉井 和久; 佐々木 勇治*; 岸本 幹雄*; 横山 淳*; et al.
no journal, ,
Fe N
N を主成分とする球状Fe-N磁性微粒子は、磁気異方性が大きいなどの良好な磁気特性を示すことから、テープ状磁気記憶媒体の新材料として注目され、企業による開発研究が進められている。また、Fe
を主成分とする球状Fe-N磁性微粒子は、磁気異方性が大きいなどの良好な磁気特性を示すことから、テープ状磁気記憶媒体の新材料として注目され、企業による開発研究が進められている。また、Fe N
N については過去に巨大磁気モーメントが発現したとの報告があることから、この材料の磁気モーメントの評価は工学的のみならず物理的にも興味の対象となるところである。しかし、Fe-N微粒子の表面は、酸化及び焼結防止のための非磁性ラミネート層で覆われており、この厚みを正確に求めることができないことから磁性部分の体積を正確に決定することができない。よって、マクロな磁化測定の結果より、Fe-N微粒子の磁気モーメントの大きさを評価することは困難とされている。そこでわれわれは、Fe-N微粒子の内部磁気構造を調べることを目的として偏極中性子小角散乱実験を行った。実験には、中性子集光素子として磁気レンズを搭載した原子力機構の偏極中性子集光型小角散乱装置(SANS-J-II)を用いた。得られた小角散乱強度を、コアシェル構造をとる球状粒子モデルを用いて解析し、微粒子の磁化部分の体積や表面非磁性層の厚さ等を定量的に評価した。
については過去に巨大磁気モーメントが発現したとの報告があることから、この材料の磁気モーメントの評価は工学的のみならず物理的にも興味の対象となるところである。しかし、Fe-N微粒子の表面は、酸化及び焼結防止のための非磁性ラミネート層で覆われており、この厚みを正確に求めることができないことから磁性部分の体積を正確に決定することができない。よって、マクロな磁化測定の結果より、Fe-N微粒子の磁気モーメントの大きさを評価することは困難とされている。そこでわれわれは、Fe-N微粒子の内部磁気構造を調べることを目的として偏極中性子小角散乱実験を行った。実験には、中性子集光素子として磁気レンズを搭載した原子力機構の偏極中性子集光型小角散乱装置(SANS-J-II)を用いた。得られた小角散乱強度を、コアシェル構造をとる球状粒子モデルを用いて解析し、微粒子の磁化部分の体積や表面非磁性層の厚さ等を定量的に評価した。