Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
丸山 修平; 山本 章夫*; 遠藤 知弘*
Annals of Nuclear Energy, 205, p.110591_1 - 110591_13, 2024/09
This study developed a new method for evaluating the uncertainty in reactor core/shielding characteristics attributable to the scattering angle distribution, employing a random sampling (RS) technique integrated with continuous energy Monte Carlo (CEMC) calculations. The impact of neutron scattering angle is not negligible in the analysis of fast reactor cores and shielding. Recent advancements have enabled the high-accuracy assessment of nuclear data-induced uncertainty by merging CEMC calculations and the RS technique. Nonetheless, a method to quantify uncertainty due to scattering angle distribution remains unestablished. This study introduces a new approach for uncertainty quantification related to scattering angle distribution in CEMC-RS, utilizing the maximum entropy method. The effectiveness of this method was verified through comparison with results from the classical deterministic uncertainty quantification approach based on generalized perturbation theory. Overall, this method offers a more accurate tool for nuclear engineers and researchers in evaluating and managing uncertainties in reactor design and safety analysis.
Li, L.*; 宮本 吾郎*; Zhang, Y.*; Li, M.*; 諸岡 聡; 及川 勝成*; 友田 陽*; 古原 忠*
Journal of Materials Science & Technology, 184, p.221 - 234, 2024/06
被引用回数:0 パーセンタイル:0(Materials Science, Multidisciplinary)Dynamic transformation (DT) of austenite ( ) to ferrite (
) to ferrite ( ) in the hot deformation of various carbon steels was widely investigated. However, the nature of DT remains unclear due to the lack of quantitative analysis of stress partitioning between two phases and the uncertainty of local distribution of substitutional elements at the interface in multi-component carbon steels used in the previous studies. Therefore, in the present study, a binary Fe-Ni alloy with
) in the hot deformation of various carbon steels was widely investigated. However, the nature of DT remains unclear due to the lack of quantitative analysis of stress partitioning between two phases and the uncertainty of local distribution of substitutional elements at the interface in multi-component carbon steels used in the previous studies. Therefore, in the present study, a binary Fe-Ni alloy with  +
+ duplex microstructure in equilibrium was prepared and isothermally compressed in
duplex microstructure in equilibrium was prepared and isothermally compressed in  +
+ two-phase region to achieve quantitative analysis of microstructure evolution, stress partitioning and thermodynamics during DT.
two-phase region to achieve quantitative analysis of microstructure evolution, stress partitioning and thermodynamics during DT.  to
to  DT during isothermal compression and
DT during isothermal compression and  to
to  reverse transformation on isothermal annealing under unloaded condition after deformation were accompanied by Ni partitioning. The lattice strains during thermomechanical processing were obtained via in-situ neutron diffraction measurement, based on which the stress partitioning behavior between
reverse transformation on isothermal annealing under unloaded condition after deformation were accompanied by Ni partitioning. The lattice strains during thermomechanical processing were obtained via in-situ neutron diffraction measurement, based on which the stress partitioning behavior between  and
and  was discussed by using the generalized Hooke's law. A thermodynamic framework for the isothermal deformation in solids was established based on the basic laws of thermodynamics, and it was shown that the total Helmholtz free energy change in the deformable material during the isothermal process should be smaller than the work done to the deformable material. Under the present thermodynamic framework, the microstructure evolution in the isothermal compression of Fe-14Ni alloy was well explained by considering the changes in chemical free energy, plastic and elastic energies and the work done to the material. In addition, the stabilization of the soft
was discussed by using the generalized Hooke's law. A thermodynamic framework for the isothermal deformation in solids was established based on the basic laws of thermodynamics, and it was shown that the total Helmholtz free energy change in the deformable material during the isothermal process should be smaller than the work done to the deformable material. Under the present thermodynamic framework, the microstructure evolution in the isothermal compression of Fe-14Ni alloy was well explained by considering the changes in chemical free energy, plastic and elastic energies and the work done to the material. In addition, the stabilization of the soft  phase in Fe-14Ni alloy by deformation was rationalized since the
phase in Fe-14Ni alloy by deformation was rationalized since the  to
to  transformation decreased the total Helmholtz free energy by decreasing the elastic and dislocation energies.
transformation decreased the total Helmholtz free energy by decreasing the elastic and dislocation energies.
佐藤 優樹; 角藤 壮*; 田中 孝幸*; 嶋野 寛之*; 諸橋 裕子; 畠山 知圭*; 中島 準作; 石山 正弘
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 1063, p.169300_1 - 169300_7, 2024/06
A system for locating radioactive substances using a hexapod robot equipped with a Compton camera and light detection and ranging camera was developed, and its performance evaluation test was conducted at FUGEN, a nuclear facility owned by Japan Atomic Energy Agency. In the test, by projecting images of radioactive substances acquired with the Compton camera onto a three-dimensional model of the work environment acquired with a light detection and ranging camera, the locations where radioactive substances have accumulated and the dose rate is higher than the surrounding area were successfully visualized and identified.
遠藤 章
JAEA-Research 2024-002, 90 Pages, 2024/05
本報告書は、光子、中性子、電子、陽電子、陽子、ミューオン、パイ中間子及びヘリウムイオンによる外部被ばくについて、エリアモニタリングに用いられる3つの量である周辺線量当量 (10)、最大線量当量
(10)、最大線量当量 及び周辺線量
及び周辺線量
 と実効線量との関係を包括的に分析した結果を示す。分析のための計算は、PHITS (Particle and Heavy Ion Transport code System)とICRU球を用いて行った。その結果、ICRP Publication 116で対象としている幅広いエネルギー範囲における外部被ばくに対して、
と実効線量との関係を包括的に分析した結果を示す。分析のための計算は、PHITS (Particle and Heavy Ion Transport code System)とICRU球を用いて行った。その結果、ICRP Publication 116で対象としている幅広いエネルギー範囲における外部被ばくに対して、 (10)と
(10)と は実効線量の評価に大きな差を生じる場合がある一方、
は実効線量の評価に大きな差を生じる場合がある一方、
 はエリアモニタリングに許容される範囲で実効線量を保守的に評価できることが分かった。すなわち、実効線量を評価するために、
はエリアモニタリングに許容される範囲で実効線量を保守的に評価できることが分かった。すなわち、実効線量を評価するために、 (10)と
(10)と には限界があり、より適切な量として
には限界があり、より適切な量として
 の使用が推奨される。この結論は、多様な被ばく状況における実効線量の評価に
の使用が推奨される。この結論は、多様な被ばく状況における実効線量の評価に
 を導入したICRU Report 95の提案を支持するものである。周辺線量
を導入したICRU Report 95の提案を支持するものである。周辺線量
 の利用は、医療や学術研究における放射線利用や航空機搭乗時の被ばく等の様々な種類の放射線により被ばくする状況で特に重要であり、放射線防護の対象の拡大に伴う放射線モニタリングの新たなニーズに応えることができる。
の利用は、医療や学術研究における放射線利用や航空機搭乗時の被ばく等の様々な種類の放射線により被ばくする状況で特に重要であり、放射線防護の対象の拡大に伴う放射線モニタリングの新たなニーズに応えることができる。
孫 昊旻; 功刀 資彰*; 横峯 健彦*; Shen, X.*; 日引 俊*
Experimental Thermal and Fluid Science, 154, p.111171_1 - 111171_24, 2024/05
被引用回数:0 パーセンタイル:0.03Taking the importance of gas-liquid two-phase flows in large square channels for advanced nuclear reactors, such as ESBWR, we experimented with upward cap-bubbly flows in a large square channel. Local void fractions, axial gas velocities, and interfacial area concentrations for two bubble-size groups were measured at three axial locations. Based on the database, cap-bubbly flow characteristics in a large square channel were understood. The existing drift-flux and interfacial area concentration correlations were validated. The void fraction covariances were obtained and used to validate their existing correlations.
石角 元志*; 高橋 竜太*; 山内 康弘*; 中村 雅俊*; 石丸 宙*; 山内 沙羅*; 河村 聖子; 吉良 弘*; 坂口 佳史*; 渡辺 真朗; et al.
JPS Conference Proceedings (Internet), 41, p.011010_1 - 011010_7, 2024/05
Recent status of cryogenic sample environment equipment at the Materials and Life Science Experimental Facility (MLF) of the Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC) has been reported. We have reviewed the specifications and performance of cryogenic sample environment equipment and a newly installed Gifford-McMahon (GM) cryofurnace, which are mainly managed by the Cryogenic and Magnet group in the sample environment team at the MLF. Moreover, the recent maintenance and update of each piece of equipment, the improved temperature-control function, and the expansion of the usable beamline of the cryogenic sample environment equipment are described.
木村 敦; 遠藤 駿典; 中村 詔司
EPJ Web of Conferences, 294, p.01002_1 - 01002_7, 2024/04
The total and double differential scattering cross sections (DDSCS) of graphite have been measured in the Materials and Life Science Experimental Facility (MLF) in the J-PARC. The DDSCS were measured using the Beam Line No.14 (AMATERAS) in the MLF. The data were normalized using those of vanadium as a standard. Small angle scattering and Bragg edges were observed, and their intensities varied among the samples. The neutron total cross sections in the energy region from 1 to 100 meV were measured using Beam Line No.04 (ANNRI) in the MLF. In the epithermal range (over 40 meV), all samples tended to have values close to the free atom cross-section of graphite. However, at the first Bragg edge, the deduced total cross sections by those samples started to separate from each other. The difference became more significant with decreasing the neutron energy, and the value tended to increase with the grain size of the sample. The results of these measurements suggest that the discrepancies between the derived total cross sections in the low-energy region are due to small-angle scattering caused by grains of graphite with uniform size.
Deng, Y.*; 渡辺 幸信*; 真鍋 征也*; Liao, W.*; 橋本 昌宜*; 安部 晋一郎; 反保 元伸*; 三宅 康博*
IEEE Transactions on Nuclear Science, 71(4, Part 2), p.912 - 920, 2024/04
半導体の微細化・省電力化に伴い、地上環境で生じるシングルイベントアップセット(SEU)へのミューオンの寄与に対する関心が高まっている。中性子起因SEUに関しては、半導体への照射方向がSEU断面積へ影響を及ぼすことが報告されている。そこで、ミューオン起因SEUにおける照射方向の影響について、実験およびシミュレーションによる研究を行った。その結果、パッケージ側照射で得らSEU断面積は、基板側照射で得たSEU断面積と比べて2倍程度高いことがわかった。また両者の差は、エネルギー分散に起因する透過深さの揺らぎ幅が、照射方向に応じて異なることが原因であることを明らかにした。
越智 康太郎; Barker, E.*; 中間 茂雄; Gleizes, M.*; Manach, E.*; Vincent, F.*; 眞田 幸尚
Journal of Disaster Research, 19(2), p.429 - 445, 2024/04
周辺線量当量率(空間線量率)分布のマッピング技術は、各国で統一された明確な基準はない。本研究では、日本原子力研究開発機構とフランス放射線防護・原子力安全研究所が共同で、福島第一原子力発電所周辺において、歩行サーベイ、車両サーベイ、無人ヘリコプターサーベイを実施し、各機関のモニタリング手法の有効性を確認した。例えば、歩行サーベイでは、検出器で得られた計数率を空間線量率に換算する際に、ガンマ線エネルギーの異なる放射性核種からの寄与を考慮するかどうかで、両機関が測定した空間線量率の間にずれが生じることが確認された。本研究のように、各国のマッピング技術を比較し、相互にフィードバックすることで、原子力発電所事故後のゾーニングシナリオの精度を向上させることができると思われる。
伊藤 孝; 門野 良典*
Journal of the Physical Society of Japan, 93(4), p.044602_1 - 044602_7, 2024/04
被引用回数:0 パーセンタイル:0.01We propose a model to describe the fluctuations in the internal magnetic field due to ion dynamics observed in muon spin relaxation ( SR) by an Edwards-Anderson-type autocorrelation function that separates the quasi-static and dynamic components of the correlation by the parameter
SR) by an Edwards-Anderson-type autocorrelation function that separates the quasi-static and dynamic components of the correlation by the parameter  (where
(where  ). Our Monte Carlo simulations for this model showed that the time evolution of muon spin polarization deviates significantly from the Kubo-Toyabe function. To further validate the model, the results of simulations were compared with the
). Our Monte Carlo simulations for this model showed that the time evolution of muon spin polarization deviates significantly from the Kubo-Toyabe function. To further validate the model, the results of simulations were compared with the  SR spectra observed in a hybrid organic-inorganic perovskite FAPbI
SR spectra observed in a hybrid organic-inorganic perovskite FAPbI [with FA referring to HC(NH
[with FA referring to HC(NH )
) ], where local field fluctuations associated with the rotational motion of FA molecules and quasi-static fields from the PbI
], where local field fluctuations associated with the rotational motion of FA molecules and quasi-static fields from the PbI lattice are presumed to coexist. The least-squares curve fitting showed reasonable agreement with the model with
lattice are presumed to coexist. The least-squares curve fitting showed reasonable agreement with the model with 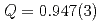 , and the fluctuation frequency of the dynamical component was obtained. This result opens the door to the possibility of experimentally distinguishing fluctuations due to the dynamics of ions around muons from those due to the self-diffusion of muons. On the other hand, it suggests the need to carefully consider the spin relaxation function when applying
, and the fluctuation frequency of the dynamical component was obtained. This result opens the door to the possibility of experimentally distinguishing fluctuations due to the dynamics of ions around muons from those due to the self-diffusion of muons. On the other hand, it suggests the need to carefully consider the spin relaxation function when applying  SR to the issue of ion dynamics.
SR to the issue of ion dynamics.
福島マップ事業対応部門横断グループ
JAEA-Technology 2023-024, 176 Pages, 2024/03
東京電力(株)福島第一原子力発電所(福島第一原発)事故による放射性物質の分布状況を平成23年6月より調査してきた。本報告書は、令和4年度の調査において得られた結果をまとめたものである。空間線量率については、走行サーベイ、平坦地上でのサーベイメータによる定点サーベイ、歩行サーベイ及び無人ヘリコプターサーベイを実施し、測定結果から空間線量率分布マップを作成するとともにその経時変化を分析した。放射性セシウムの土壌沈着量に関しては、in-situ測定及び土壌中深度分布調査をそれぞれ実施した。さらに、これまで蓄積した測定結果を基に空間線量率及び沈着量の実効半減期を評価した。モニタリングの重要度を相対的に評価するスコアマップを福島県及び福島第一原発から80km圏内について作成するとともに、多年度のモニタリングデータを使用した場合のスコアの変化要因について考察した。過去の海水中トリチウムの濃度データの変動幅を把握しその要因について考察した。総合モニタリング計画に基づき実施された海域モニタリングについて令和4年度の測定結果を集約するとともに、過去からの変動などに関して解析評価を行った。階層ベイズ統計手法を用いて、走行サーベイや歩行サーベイ等の調査により取得した空間線量率分布データを統合し、80km圏内を対象とした統合マップ及び解析対象を福島県全域に広げた統合マップを作成した。これらの他、「放射性物質モニタリングデータの情報公開サイト」への令和4年度の測定結果の公開、総合モニタリング計画に基づく放射線モニタリング及び環境試料分析測定データのCSV化を実施した。
廃炉環境国際共同研究センター; 岡山大学*
JAEA-Review 2023-038, 48 Pages, 2024/03
日本原子力研究開発機構(JAEA)廃炉環境国際共同研究センター(CLADS)では、令和4年度英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業(以下、「本事業」という)を実施している。本事業は、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の廃炉等をはじめとした原子力分野の課題解決に貢献するため、国内外の英知を結集し、様々な分野の知見や経験を、従前の機関や分野の壁を越えて緊密に融合・連携させた基礎的・基盤的研究及び人材育成を推進することを目的としている。平成30年度の新規採択課題から実施主体を文部科学省からJAEAに移行することで、JAEAとアカデミアとの連携を強化し、廃炉に資する中長期的な研究開発・人材育成をより安定的かつ継続的に実施する体制を構築した。本研究は、令和4年度に採択された研究課題のうち、「耐放射線プロセッサを用いた組み込みシステムの開発」の令和4年度分の研究成果について取りまとめたものである。本研究は、集積回路に光技術を導入し、10MGyのトータルドーズ耐性を持つ耐放射線光電子プロセッサ、既存の集積回路のみで4MGyのトータルドーズ耐性を持つ耐放射線プロセッサ、同4MGyのトータルドーズ耐性の耐放射線メモリ、そして、それらに必要となる1MGyのトータルドーズ耐性を持つ耐放射線電源ユニットの4つを開発する。マンチェスター大学とはロボットやLiDARに対する耐放射線プロセッサ、耐放射線FPGA、耐放射線メモリ、耐放射線電源ユニットの面で連携し、これまでに無い高いトータルドーズ耐性を持つ耐放射線ロボットを実現していく。また、ランカスター大学とは耐放射線FPGA、耐放射線電源ユニットの面で連携し、放射線の種類、強度を正確に特定できるセンサー類を開発していく。
廃炉環境国際共同研究センター; 東北大学*
JAEA-Review 2023-030, 80 Pages, 2024/03
日本原子力研究開発機構(JAEA)廃炉環境国際共同研究センター(CLADS)では、令和4年度英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業(以下、「本事業」という)を実施している。本事業は、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の廃炉等をはじめとした原子力分野の課題解決に貢献するため、国内外の英知を結集し、様々な分野の知見や経験を、従前の機関や分野の壁を越えて緊密に融合・連携させた基礎的・基盤的研究及び人材育成を推進することを目的としている。平成30年度の新規採択課題から実施主体を文部科学省からJAEAに移行することで、JAEAとアカデミアとの連携を強化し、廃炉に資する中長期的な研究開発・人材育成をより安定的かつ継続的に実施する体制を構築した。本研究は、令和3年度に採択された研究課題のうち、「連携計測による線源探査ロボットシステムの開発研究」の令和4年度分の研究成果について取りまとめたものである。本研究は、ガンマ線の飛来方向を検出可能な検出器を開発し、これを搭載した複数のロボットの連携により、単一センサーでは得られない広視野・迅速・安価な放射線源探査を実現するロボットシステム(Cooperative Operation Robot system for RAdiation Source Exploration: CORRASE、コラッセ)を開発することを目的とする。東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所の現場への投入に資することを目的として、線源探査を行う小型ロボットに放射線計測機器を搭載したシステムを3年間の計画終了時に完成させるための研究を行う。令和4年度は以下の成果を得た。多面体型とコーデットキューブ型のガンマ線イメージャーの製作を行い、点線源の位置推定に成功した。LiDARを用いた周囲環境測定結果に基づく環境地図作成システムの開発および環境地図上に放射線源分布推定結果を融合して表示するシステムの開発を行った。環境地図と粗い放射線源分布推定結果に基づき、検出器の特性に応じて複数台のロボットが指定した箇所の詳細な測定を行うための観測地点計画手法の開発を行った。小型ロボットに搭載する放射線測定器の評価のために検出器姿勢自動制御システムを製作した。また、多面体型検出器による線源探査のシミュレーションを行った。複数の線源がある場合でもほぼ線源位置を特定することができた。
 線透過率差を利用した構造体内調査法の開発(委託研究); 令和4年度英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業
線透過率差を利用した構造体内調査法の開発(委託研究); 令和4年度英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業廃炉環境国際共同研究センター; 京都大学*
JAEA-Review 2023-028, 54 Pages, 2024/03
日本原子力研究開発機構(JAEA)廃炉環境国際共同研究センター(CLADS)では、令和4年度英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業(以下、「本事業」という)を実施している。本事業は、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所(1F)の廃炉等をはじめとした原子力分野の課題解決に貢献するため、国内外の英知を結集し、様々な分野の知見や経験を、従前の機関や分野の壁を越えて緊密に融合・連携させた基礎的・基盤的研究及び人材育成を推進することを目的としている。平成30年度の新規採択課題から実施主体を文部科学省からJAEAに移行することで、JAEAとアカデミアとの連携を強化し、廃炉に資する中長期的な研究開発・人材育成をより安定的かつ継続的に実施する体制を構築した。本研究は、令和4年度に採択された研究課題のうち、「3次元線量拡散予測法の確立と 線透過率差を利用した構造体内調査法の開発」の令和4年度分の研究成果について取りまとめたものである。我々は核ガンマ線の方向を完全に決定、光学カメラと同じ全単射によるガンマ線画像(線形画像)が測定できる電子飛跡検出型コンプトンカメラ(ETCC)を実現、今年、世界初の銀河拡散ガンマ線の直接観測に成功した。この特徴を生かし平成30年度英知事業に採択された「ガンマ線画像スペクトル分光法による高放射線場環境の画像化による定量的放射能分布解析法」(以下、前研究)では、1F免振棟から炉を含む1km四方を一度に撮像、約100か所のスペクトル測定を一度に実現、空からはスカイシャイン、炉からは662keVガンマ線が明瞭に測定でき、見晴台50
線透過率差を利用した構造体内調査法の開発」の令和4年度分の研究成果について取りまとめたものである。我々は核ガンマ線の方向を完全に決定、光学カメラと同じ全単射によるガンマ線画像(線形画像)が測定できる電子飛跡検出型コンプトンカメラ(ETCC)を実現、今年、世界初の銀河拡散ガンマ線の直接観測に成功した。この特徴を生かし平成30年度英知事業に採択された「ガンマ線画像スペクトル分光法による高放射線場環境の画像化による定量的放射能分布解析法」(以下、前研究)では、1F免振棟から炉を含む1km四方を一度に撮像、約100か所のスペクトル測定を一度に実現、空からはスカイシャイン、炉からは662keVガンマ線が明瞭に測定でき、見晴台50 Sv/hでも無遮蔽で撮像に成功した。令和3年度には京都大学複合原子力科学研究所の原子炉建屋内の3次元線量測定を実施し、動作中の原子炉からのガンマ線の3次元撮像に成功した。さらに炉壁から放出された微量な
Sv/hでも無遮蔽で撮像に成功した。令和3年度には京都大学複合原子力科学研究所の原子炉建屋内の3次元線量測定を実施し、動作中の原子炉からのガンマ線の3次元撮像に成功した。さらに炉壁から放出された微量な Arのガンマ線(1290keV)を動画で捉え、放射性物質拡散のガンマ線画像モニタリングが可能であることを実証した。本研究は、前研究の成果を基にサブmSv/h環境での3次元汚染物質飛散検知・予測システムの1F内で使用可能な実用化を行う。またETCCのMeV以上のガンマ線撮像能力を生かし透過性の高い
Arのガンマ線(1290keV)を動画で捉え、放射性物質拡散のガンマ線画像モニタリングが可能であることを実証した。本研究は、前研究の成果を基にサブmSv/h環境での3次元汚染物質飛散検知・予測システムの1F内で使用可能な実用化を行う。またETCCのMeV以上のガンマ線撮像能力を生かし透過性の高い Csガンマ線を利用した炉建屋内の3次元透視Cs分布測定法を開発する。
Csガンマ線を利用した炉建屋内の3次元透視Cs分布測定法を開発する。
外川 織彦; 外間 智規; 平岡 大和; 齊藤 将大
JAEA-Research 2023-011, 78 Pages, 2024/03
原子力災害時に大気へ放射性物質が放出された場合には、住民等の被ばくを低減するための防護措置として、自家用車やバス等の車両を利用して避難や一時移転が実施される。避難等を実施した住民等や使用した車両の汚染状況を確認することを目的として、原子力災害対策重点区域の境界周辺から避難所までの経路途中において避難退域時検査が行われる。その際に、我が国では表面汚染密度の測定によるOIL4=40,000cpmという値が除染を講じる基準として用いられる。しかし、この値が設定された経緯や導出方法については、系統的かつ詳細な記述や説明は公式文書には見受けられず、また原子力防災の専門家でさえも全体に亘って詳細に説明できる人はほとんどいないことを認識した。本報告書では、我が国の避難退域時検査における除染の基準として用いられるOIL4を科学的・技術的に説明するために、その導出方法を調査・推定するとともに、それらの結果について検討と考察を行うことを目的とした。この目的を達成するために、我が国における除染基準を設定する上での根拠を示すとともに、被ばく経路毎の線量基準に対応した表面汚染密度限度を導出する方法を調査・推定した。さらに、我が国におけるOIL4の位置付けと特徴、OIL4の改定時における留意点という観点から、OIL4に関する考察と提言を行った。
中村 啓太; 羽成 敏秀; 松本 拓; 川端 邦明; 八代 大*
Journal of Robotics and Mechatronics, 36(1), p.115 - 124, 2024/02
During the decommissioning activities, a movie was shot inside the reactor building during the investigation of the primary containment vessel by applying photogrammetry, which is one of the methods for three-dimensional (3D) reconstruction from images, to the images from this movie, it is feasible to perform 3D reconstruction of the environment around the primary containment vessel. However, the images from this movie may not be suitable for 3D reconstruction because they were shot remotely by robots owing to limited illumination, high-dose environments, etc. Moreover, photogrammetry has the disadvantage of easily changing 3D reconstruction results by simply changing the shooting conditions. Therefore, this study investigated the accuracy of the 3D reconstruction results obtained by photogrammetry with changes in the camera angle of view under shooting conditions. In particular, we adopted 3D computer graphics software to simulate shooting target objects for 3D reconstruction in a dark environment while illuminating them with light for application in decommissioning activities. The experimental results obtained by applying artificial images generated by simulation to the photogrammetry method showed that more accurate 3D reconstruction results can be obtained when the camera angle of view is neither too wide nor too narrow when the target objects are shot and surrounded. However, the results showed that the accuracy of the obtained results is low during linear trajectory shooting when the camera angle of view is wide.
畑 浩二*; 丹生屋 純夫*; 青柳 和平; 宮良 信勝*
Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 16(2), p.365 - 378, 2024/02
山岳トンネルや地下備蓄基地などの地下空洞の掘削時には、応力再配分の影響により空洞周辺岩盤に損傷が生じる。このような領域では、亀裂や不連続面が発生することから、発生に伴う振動(アコースティックエミッション、AE)が生じる。本研究では、長期的な立坑周辺岩盤のモニタリングのために、光ファイバー式のAEセンサー,間隙水圧計を1つのボーリング孔に設置できるプローブを開発した。計測の結果、立坑掘削に伴ってAEの発生数が顕著となり、さらに立坑壁面から1.5mの範囲で2から4桁の透水係数の増大を確認した。さらに、数値解析の結果、間隙水圧変化と割れ目の発達領域を適切に再現できた。これらの結果を踏まえ、立坑周辺の掘削損傷領域の概念モデルを構築した。なお、この成果は、高レベル放射性廃棄物処分時の安全評価の信頼性の向上に資するものである。
原子力人材育成センター
JAEA-Review 2023-034, 67 Pages, 2024/01
本報告書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「機構」という。)原子力人材育成センターにおける令和4年度の活動をまとめたものである。令和4年度は、年間計画に基づく国内研修の他、外部ニーズに対応した随時の研修、大学との連携協力、国際研修、原子力人材育成ネットワーク等に関して積極的な取組を行った。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を徹底した上で、対面形式で研修等を実施することができた。国内研修については、年間計画に基づくRI・放射線技術者、原子力エネルギー技術者、国家試験受験者向けの研修に加え、外部ニーズへの対応として、日本原子力発電株式会社等、機構外組織を対象とした出張講習等を実施した。大学等との連携協力については、東京大学大学院工学系研究科原子力専攻の学生受入れを含む連携大学院方式に基づく協力や特別研究生等の受入れを行った。また、大学連携ネットワークでは、7大学との遠隔教育システムによる通年の共通講座に対応したほか、夏期集中講座や核燃料サイクル実習を行った。国際研修については、文部科学省からの受託事業「放射線利用技術等国際交流(講師育成)」として、原子炉工学等の講師育成研修及び講師育成アドバンス研修並びに放射線基礎教育等の原子力技術セミナーを対面形式で実施した。原子力人材育成ネットワークについては、共同事務局として運営を着実に推進するとともに、オンラインセミナー及び対面形式での研修や学生対象の施設見学会を積極的に開催した。人材育成コンシェルジュについては、機構内外からの人材育成に係る窓口を新規に開設し、問合せや相談に回答するなどの活動を開始した。
佐藤 優樹
Applied Radiation and Isotopes, 203, p.111083_1 - 111083_9, 2024/01
被引用回数:0 パーセンタイル:0.01(Chemistry, Inorganic & Nuclear)At the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station (FDNPS), radioactive substances released during the accident were deposited on various equipment and building structures. During the decommissioning work, an investigation of the deposition of radioactive substances inside the contaminated equipment and structures can provide information on the cause and progression of the accident. This study introduces a quantitative evaluation method of radioactivity using a Compton camera, a type of gamma-ray imager, to investigate the deposition and contamination level of radioactive substances on contaminated objects at the FDNPS. Multiple  Cs radiation sources with varying radioactivity were placed horizontally in one dimension within the field of view of the Compton camera, and a proof-of-principle study was conducted to evaluate the radioactivity of each source quantitatively.
Cs radiation sources with varying radioactivity were placed horizontally in one dimension within the field of view of the Compton camera, and a proof-of-principle study was conducted to evaluate the radioactivity of each source quantitatively.
堀井 雄太; 廣岡 瞬; 宇野 弘樹*; 小笠原 誠洋*; 田村 哲也*; 山田 忠久*; 古澤 尚也*; 村上 龍敏; 加藤 正人
Journal of Nuclear Materials, 588, p.154799_1 - 154799_20, 2024/01
被引用回数:1 パーセンタイル:63.33(Materials Science, Multidisciplinary)MOX燃料の照射により生成する主要なFPであるNd O
O 及びSm
及びSm O
O 、模擬FPとして添加したMOXの熱伝導率を評価した。MOX中の模擬FPの均質性の観点から熱伝導率を評価するため、ボールミル法及び溶融法で作製した2種類の粉末を用いて、Nd及びSmの均質性が異なる試料を作製した。模擬FPが均質に固溶した試料では含有量が増加するにしたがってMOXの熱伝導率が低下するが、不均質な模擬FPは影響を及ぼさないことが分かった。熱伝導率に対するNd及びSmの影響を古典的フォノン輸送モデル
、模擬FPとして添加したMOXの熱伝導率を評価した。MOX中の模擬FPの均質性の観点から熱伝導率を評価するため、ボールミル法及び溶融法で作製した2種類の粉末を用いて、Nd及びSmの均質性が異なる試料を作製した。模擬FPが均質に固溶した試料では含有量が増加するにしたがってMOXの熱伝導率が低下するが、不均質な模擬FPは影響を及ぼさないことが分かった。熱伝導率に対するNd及びSmの影響を古典的フォノン輸送モデル =(A+BT)
=(A+BT) を用いてNd/Sm依存性を定量的に評価した結果、A(mK/W)=1.70
を用いてNd/Sm依存性を定量的に評価した結果、A(mK/W)=1.70 10
10 + 0.93C
+ 0.93C + 1.20C
+ 1.20C , B(m/W)=2.39
, B(m/W)=2.39 10
10 と表された。
と表された。