Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
出井 俊太郎; 柴田 真仁*; 根岸 久美*; 杉浦 佑樹; 天野 由記; Bateman, K.*; Wilson, J.*; 横山 立憲; 鏡味 沙耶; 武田 匡樹; et al.
Results in Earth Sciences (Internet), 3, p.100097_1 - 100097_16, 2025/12
高レベル放射性廃棄物の地層処分において、セメントと泥岩の相互作用による化学的擾乱領域が形成され、岩盤中の核種移行特性に影響を及ぼす可能性がある。本研究では、11年前に幌延深地層研究センターの140m調査坑道に施工されたセメント(普通ポルトランドセメント(OPC)および低アルカリ性セメント(LAC))と泥岩の界面における変質状態について調査した。複数の分析手法を組み合わせることで、セメントの溶解、方解石やC-(A-)S-H相などの二次鉱物の析出、モンモリロナイトの陽イオン交換、泥岩の空隙率の低下など、セメントと岩石の界面における主要な反応が特定された。また、空隙率の低下による拡散の低下や、変質した泥岩中の二次鉱物への取り込みによる収着の促進など、セメントと泥岩の相互作用が放射性核種の移行に及ぼす影響についても明らかになった。
望月 陽人; 松井 裕哉; 中山 雅; 坂本 亮*; 柴田 真仁*; 本島 貴之*; 城 まゆみ*
Case Studies in Construction Materials, 22, p.e04648_1 - e04648_20, 2025/07
被引用回数:0放射性廃棄物の地層処分で使用される低アルカリ性セメントは、長期にわたる処分場の操業期間中に大気中の二酸化炭素による炭酸化や地下水との接触によってその特性が変化する可能性がある。本研究では、フライアッシュとシリカヒュームを混合した低アルカリ性セメント(HFSC)を用いた吹付けコンクリートの化学的特性、微細構造ならびに輸送特性に対して大気中での炭酸化および地下水との接触が与える影響を、幌延の地下研究施設において16年間にわたり調査した。HFSC吹付けコンクリートの炭酸化領域と溶出領域のいずれにおいても、直径約300nm未満の細孔の毛細管空隙率が増加し、全空隙率は非変質領域よりも高くなった。これらの空隙構造の変化は、ケイ酸カルシウム水和物(C-S-H)の脱灰とエトリンガイトの分解に関連していると考えられる。このような変化は、OPC吹付けコンクリートの変質領域では軽微であったことから、本研究の調査条件下において、HFSC吹付けコンクリートは炭酸化や地下水溶出に対する抵抗性が相対的に低いことが示された。しかしながら、HFSCの透水係数は、地層処分に用いられる低pHセメントに求められる機能要件を満たす程度に低かった。
Birkholzer, J. T.*; Graupner, B. J.*; Harrington, J.*; Jayne, R.*; Kolditz, O.*; Kuhlman, K. L.*; LaForce, T.*; Leone, R. C.*; Mariner, P. E.*; McDermott, C.*; et al.
Geomechanics for Energy and the Environment, 42, p.100685_1 - 100685_17, 2025/06
The DECOVALEX initiative is an international research collaboration (www.decovalex.org), initiated in 1992, for advancing the understanding and modeling of coupled thermo-hydro-mechanical-chemical (THMC) processes in geological systems. DECOVALEX stands for "DEvelopment of COupled Models and VALidation against EXperiments". DECOVALEX emphasizes joint analysis and comparative modeling of the complex perturbations and coupled processes in geologic repositories and how these impact long-term performance predictions. More than fifty research teams associated with 17 international DECOVALEX partner organizations participated in the comparative evaluation of eight modeling tasks covering a wide range of spatial and temporal scales, geological formations, and coupled processes. This Virtual Special Issue on DECOVALEX-2023 provides an in-depth overview of these collaborative research efforts and how these have advanced the state-of-the-art of understanding and modeling coupled THMC processes. While primarily focused on radioactive waste, much of the work included here has wider application to many geoengineering topics.
杉田 裕; 大野 宏和; Beese, S.*; Pan, P.*; Kim, M.*; Lee, C.*; Jove-Colon, C.*; Lopez, C. M.*; Liang, S.-Y.*
Geomechanics for Energy and the Environment, 42, p.100668_1 - 100668_21, 2025/06
国際共同プロジェクトDECOVALEX-2023は、数値解析を使用してベントナイト系人工バリアの熱-水-応力(または熱-水)相互作用を研究するためのタスクDとして、幌延人工バリア性能確認試験を対象とした。このタスクは、モデル化のために、1つの実物大の原位置試験と、補完的な4つの室内試験が選択された。幌延人工バリア性能確認試験は、人工的な地下水注入と組み合わせた温度制御非等温の試験であり、加熱フェーズと冷却フェーズで構成されている。6つの研究チームが、さまざまなコンピューターコード、定式化、構成法則を使用して、熱-水-応力または熱-水(研究チームのアプローチによって異なる)数値解析を実行した。
 sp. nov., a novel hydrogen-producing bacterium isolated from a deep diatomaceous shale formation
sp. nov., a novel hydrogen-producing bacterium isolated from a deep diatomaceous shale formation上野 晃生*; 佐藤 聖*; 玉村 修司*; 村上 拓馬*; 猪股 英紀*; 玉澤 聡*; 天野 由記; 宮川 和也; 長沼 毅*; 五十嵐 敏文*
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 75(6), p.006802_1 - 006802_11, 2025/06
幌延深地層研究センターの地下施設内に掘削されたボーリング孔を用い、深度350mの新第三紀堆積層中の地下水から、グラム陰性、非運動性、桿菌株の偏性嫌気性細菌を単離した。これをZ1-71 株と呼ぶ。細胞は長さ2.7-4.8
株と呼ぶ。細胞は長さ2.7-4.8 m、幅0.4
m、幅0.4 mであり、温度10-42
mであり、温度10-42 C、pH 6.0-9.0及びNaCl濃度0-3.0%(w/v)で生育が認められた。Z1-71
C、pH 6.0-9.0及びNaCl濃度0-3.0%(w/v)で生育が認められた。Z1-71 株は、D-グルコースを基質として生育した場合、水素の生成が認められた。16S rRNA遺伝子配列の系統解析により、Z1-71
株は、D-グルコースを基質として生育した場合、水素の生成が認められた。16S rRNA遺伝子配列の系統解析により、Z1-71 株は
株は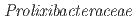 科の
科の 属に分類されることが示された。系統学的および表現型の特徴に基づき、Z1-71
属に分類されることが示された。系統学的および表現型の特徴に基づき、Z1-71 株は
株は 属の新種細菌であると考えられ、
属の新種細菌であると考えられ、 sp. nov.と命名する。Z1-71
sp. nov.と命名する。Z1-71 株を水素資化性メタン生成菌(
株を水素資化性メタン生成菌( T10
T10 株)とグルコースを基質として30
株)とグルコースを基質として30 Cの嫌気環境下で4週間共培養した結果、各単離株のみでの培養では見られなかったメタンの生成が認められた。このことは、Z1-71
Cの嫌気環境下で4週間共培養した結果、各単離株のみでの培養では見られなかったメタンの生成が認められた。このことは、Z1-71 株より生成したギ酸塩と水素がメタン生成菌により利用されることでメタンが生成したことを示していると考えられた。
株より生成したギ酸塩と水素がメタン生成菌により利用されることでメタンが生成したことを示していると考えられた。
青柳 和平; 尾崎 裕介; 早野 明; 大野 宏和; 舘 幸男
日本原子力学会誌ATOMO , 67(6), p.354 - 358, 2025/06
, 67(6), p.354 - 358, 2025/06
日本原子力研究開発機構は、幌延深地層研究センターの地下施設を活用した"幌延国際共同プロジェクト(Horonobe International Project: HIP)"を開始した。本プロジェクトの主要な目的は、地層処分のための先進的な安全評価技術や工学技術に関わる研究開発の成果の最大化や、次世代の研究者や技術者の育成と知識の継承である。本解説では、日本原子力学会2024年秋の大会におけるバックエンド部会の企画セッション"幌延国際共同プロジェクトの現状と今後の展開"の流れに沿って、本プロジェクトの概要を紹介する。
長田 翔平*; 市田 雄行*; 藤枝 大吾; 青柳 和平
Tunnelling into a Sustainable Future; Methods and Technologies; Proceedings of the ITA-AITES World Tunnel Congress 2025 (WTC 2025), p.3517 - 3524, 2025/05
幌延深地層研究センターの深度500mまでの立坑掘削に先立ち、支保パターン選定のために、覆工コンクリートの強度や厚さ、打設長をさまざまに設定した三次元逐次掘削解析を行い、コンクリートに作用する応力状態を評価した。この結果に基づき、支保パターンを選定し、立坑の掘削を開始した。掘削中のコンクリートに作用する応力の実際の計測結果も参照しながら、東立坑の深度500mまでの掘削を完了させることができた。また、事前の解析や実際のコンクリートに作用する応力の計測結果を踏まえて、適切な支保パターンを選定できることを実証できた。この成果は、立坑掘削を対象とした情報化施工手法の信頼性向上に資するものとなる。
大野 宏和; 高山 裕介*
Geomechanics for Energy and the Environment, 41, p.100636_1 - 100636_14, 2025/03
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Energy & Fuels)In the geological disposal of high-level radioactive waste, the overpack lifetime and initial conditions of radionuclide migration are essential considerations along with the assessments of the environmental conditions, including study of the evolution of near-field thermal, hydrological, mechanical, and chemical processes following the emplacement of an engineered barrier system. In this study, experimental data from an in situ full-scale engineered barrier experiment at Horonobe Underground Research Laboratory were used to assess the applicability of a simulation model to evaluate near-field coupled processes.
Kim, M.*; Lee, C.*; 杉田 裕; Kim, J.-S.*; Jeon, M.-K.*
Geomechanics for Energy and the Environment, 41, p.100628_1 - 100628_9, 2025/03
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Energy & Fuels)この研究では、DECOVALEX-2023プロジェクトの一環として幌延の地下研究施設で実施された実規模大の人工バリア試験の数値解析を使用して、非等温二相流のモデリングに対する主要変数の選択の影響を調査した。検証済みの数値モデルを使用して、人工バリアシステム内の不均質多孔質媒体の熱-水連成挙動を解析した。支配方程式を離散化する際の2つの異なる主要変数スキームを比較したところ、結果に大きな違いがあることが明らかになった。
竹内 竜史; 國分 陽子; 西尾 和久*
JAEA-Data/Code 2024-015, 68 Pages, 2025/02
日本原子力研究開発機構東濃地科学センターは、同センターが進める瑞浪超深地層研究所の坑道埋め戻し等事業において、瑞浪超深地層研究所の坑道の埋め戻しに伴い瑞浪超深地層研究所用地周辺の環境への影響の有無を確認することを目的とした環境モニタリング調査を実施している。本報告書は、2023年度の環境モニタリング調査のうち瑞浪超深地層研究所用地周辺の環境影響調査(研究所用地周辺の井戸における地下水位調査、研究所用地周辺河川流量測定、研究所用地放流先河川水の水質分析、研究所用地周辺騒音・振動調査、研究所用地周辺土壌調査)に関する記録を取りまとめたものである。
 長期透水試験に対する再現シミュレーション
長期透水試験に対する再現シミュレーション末武 航弥*; 緒方 奨*; 安原 英明*; 青柳 和平; 乾 徹*; 岸田 潔*
第16回岩の力学国内シンポジウム講演論文集(インターネット), p.304 - 309, 2025/01
地層処分の安全性評価において、廃棄体処分坑道の掘削に伴うEDZ(掘削損傷領域)の進展範囲や、掘削後の岩盤の透水性変化挙動を予測することは非常に重要である。本研究では、三次元坑道掘削シミュレーターを用いて、幌延深地層研究センターで実施されている原位置坑道掘削とその後の透水試験を対象とした再現解析を試みた。その結果、掘削によるEDZの進展範囲と透水試験の結果について、原位置試験と類似する結果が得られた。このことから、本シミュレーターがわが国の大深度泥岩帯においての掘削に伴う力学的影響や、掘削後の岩盤変形-浸透といった連成現象とそれによる透水性変化などの予測評価に関して、有効であることが確認された。
青柳 和平; 尾崎 裕介; 大野 宏和; 石井 英一
第16回岩の力学国内シンポジウム講演論文集(インターネット), p.269 - 274, 2025/01
幌延深地層研究センターでは、実際の処分事業を想定し、実規模大の緩衝材や炭素鋼製の模擬オーバーパックで構成される人工バリアを底盤に掘削した模擬処分孔に定置したうえで坑道の一部を埋め戻し、人工バリア及び周辺岩盤の長期的な挙動をモニタリングしている。本研究では、模擬処分孔を掘削した際の掘削損傷領域の発達を、ボアホールテレビ観察、弾性波・比抵抗トモグラフィ調査により検討するとともに、三次元逐次掘削解析により評価した。結果として、模擬処分孔の浅い深度では、坑道底盤部の掘削の影響を受けて壁面から0.8mから1.6m程度の範囲で割れ目が発達し、深度が深くなるにつれて、割れ目の発達領域が徐々に小さくなり、最深部では最大でも0.3m程度の発達であることを示した。
 U/
U/ U isotope ratios in deep groundwater and its potential application as a groundwater mixing indicator
U isotope ratios in deep groundwater and its potential application as a groundwater mixing indicator栗林 千佳*; 宮川 和也; 伊藤 茜*; 谷水 雅治*
Geochemical Journal, 59(2), p.35 - 44, 2025/00
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Geochemistry & Geophysics)地下水の流動や分布域の把握に有用な同位体トレーサーの1つとして U/
U/ U放射能比(AR)が用いられている。地下水中におけるARは周囲の母岩との岩石・水反応により変動することが知られているが、深部地下水における研究例は限られている。北海道幌延地域には新第三紀堆積層である珪質泥岩の稚内層および珪藻質泥岩の声問層が分布し、そこには地層堆積時に間隙に取り込まれた海水を起源として埋没続成作用により変質した塩水系地下水(化石海水)が分布する。本研究では酸化還元電位の低い滞留性の深部地下水におけるARの変動について把握するとともに、ARのトレーサーとしての有用性について検討した。その結果、天水浸透率が小さい深部地下水ほど低いARを示した。天水浸透により化石海水が希釈され、イオン強度が低下した結果、収着イオンの脱離や沈殿物の溶解による
U放射能比(AR)が用いられている。地下水中におけるARは周囲の母岩との岩石・水反応により変動することが知られているが、深部地下水における研究例は限られている。北海道幌延地域には新第三紀堆積層である珪質泥岩の稚内層および珪藻質泥岩の声問層が分布し、そこには地層堆積時に間隙に取り込まれた海水を起源として埋没続成作用により変質した塩水系地下水(化石海水)が分布する。本研究では酸化還元電位の低い滞留性の深部地下水におけるARの変動について把握するとともに、ARのトレーサーとしての有用性について検討した。その結果、天水浸透率が小さい深部地下水ほど低いARを示した。天水浸透により化石海水が希釈され、イオン強度が低下した結果、収着イオンの脱離や沈殿物の溶解による Uの選択的な脱離・溶解が進行し、ARが増加したと考えられた。さらに、稚内層に産する炭酸塩脈のU-Th年代から炭酸塩沈澱時の地下水のARを推定し、本地域の地下水流動環境の長期変化に関するより詳細な知見を得た。このことから、ARは水質の変動プロセスを把握するトレーサーとして有用であると考えられる。
Uの選択的な脱離・溶解が進行し、ARが増加したと考えられた。さらに、稚内層に産する炭酸塩脈のU-Th年代から炭酸塩沈澱時の地下水のARを推定し、本地域の地下水流動環境の長期変化に関するより詳細な知見を得た。このことから、ARは水質の変動プロセスを把握するトレーサーとして有用であると考えられる。
竹内 竜史; 國分 陽子; 西尾 和久*
JAEA-Data/Code 2024-011, 120 Pages, 2024/12
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構東濃地科学センターでは、瑞浪超深地層研究所の坑道の埋め戻しに伴う地下深部の地下水環境の回復状況を確認するため、環境モニタリング調査として瑞浪超深地層研究所用地および研究所用地周辺のボーリング孔等において地下水の水圧観測および水質観測を実施している。本報告書は、2023年度に実施した地下水の水圧観測データおよび水質観測データを取りまとめたものである。
天野 由記; Sachdeva, R.*; Gittins, D.*; Anantharaman, K.*; Lei, S.*; Valentin-Alvarado, L. E.*; Diamond, S.*; 別部 光里*; 岩月 輝希; 望月 陽人; et al.
Environmental Microbiome (Internet), 19, p.105_1 - 105_17, 2024/12
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Genetics & Heredity)Underground research laboratories (URLs) provide a window on the deep biosphere and enable investigation of potential microbial impacts on nuclear waste, CO and H
and H stored in the subsurface. We carried out the first multi-year study of groundwater microbiomes sampled from defined intervals between 140 and 400 m below the surface of the Horonobe and Mizunami URLs, Japan. The Horonobe and Mizunami microbiomes are dissimilar, likely because the Mizunami URL is hosted in granitic rock and the Horonobe URL in sedimentary rock. Despite this, hydrogen metabolism, rubisco-based CO
stored in the subsurface. We carried out the first multi-year study of groundwater microbiomes sampled from defined intervals between 140 and 400 m below the surface of the Horonobe and Mizunami URLs, Japan. The Horonobe and Mizunami microbiomes are dissimilar, likely because the Mizunami URL is hosted in granitic rock and the Horonobe URL in sedimentary rock. Despite this, hydrogen metabolism, rubisco-based CO fixation, reduction of nitrogen compounds and sulfate reduction are well represented functions in microbiomes from both URLs, although methane metabolism is more prevalent at the organic- and CO
fixation, reduction of nitrogen compounds and sulfate reduction are well represented functions in microbiomes from both URLs, although methane metabolism is more prevalent at the organic- and CO -rich Horonobe URL. We detected near-identical genotypes for approximately one third of all genomically defined organisms at multiple depths within the Horonobe URL. This cannot be explained by inactivity, as in situ growth was detected for some bacteria, albeit at slow rates. Given the current low hydraulic conductivity and groundwater compositional heterogeneity, ongoing inter-site strain dispersal seems unlikely. Alternatively, the Horonobe URL microbiome homogeneity may be explained by higher groundwater mobility during the last glacial period. Genotypically-defined species closely related to those detected in the URLs were identified in three other subsurface environments in the USA. Thus, dispersal rates between widely separated underground sites may be fast enough relative to mutation rates to have precluded substantial divergence in species composition. Species overlaps between subsurface locations on different continents constrain expectations regarding the scale of global subsurface biodiversity. Overall, microbiome and geochemical stability over the study period has important implications for underground storage applications.
-rich Horonobe URL. We detected near-identical genotypes for approximately one third of all genomically defined organisms at multiple depths within the Horonobe URL. This cannot be explained by inactivity, as in situ growth was detected for some bacteria, albeit at slow rates. Given the current low hydraulic conductivity and groundwater compositional heterogeneity, ongoing inter-site strain dispersal seems unlikely. Alternatively, the Horonobe URL microbiome homogeneity may be explained by higher groundwater mobility during the last glacial period. Genotypically-defined species closely related to those detected in the URLs were identified in three other subsurface environments in the USA. Thus, dispersal rates between widely separated underground sites may be fast enough relative to mutation rates to have precluded substantial divergence in species composition. Species overlaps between subsurface locations on different continents constrain expectations regarding the scale of global subsurface biodiversity. Overall, microbiome and geochemical stability over the study period has important implications for underground storage applications.
尾崎 裕介
原子力バックエンド研究(CD-ROM), 31(2), p.128 - 133, 2024/12
幌延国際共同プロジェクトのタスクAでは、幌延深地層研究センターの地下施設の深度250mの声問層において物質移行に関する調査を実施している。タスクAでは高レベル放射性廃棄物の地層処分の安全評価に不可欠な物質移行評価に資するため、原位置トレーサー試験結果から岩盤内における物質移行時の現象をより適切に表現可能なモデルを構築するとともに、異なる地質環境で得られたデータやモデルの適用可能性について議論することを目的としている。タスクAのフェーズ1は、原位置試験の計画立案、室内試験、原位置試験の実施、解析評価の4つのサブタスクから構成される。これらのサブタスクは、参加機関が協力して取り組んでおり、本発表では、タスクAのサブタスクの現状と協力状況を紹介する。
青柳 和平; 舘 幸男
原子力バックエンド研究(CD-ROM), 31(2), p.124 - 127, 2024/12
日本原子力研究開発機構は、幌延深地層研究センターの地下施設を活用した「幌延国際プロジェクト(Horonobe International Project: HIP)」を、8つの国・地域から11の機関の参加を得て開始した。本プロジェクトの主要な目的は、地層処分のための先進的な安全評価技術や工学技術に関わる研究開発の成果の最大化や、次世代の研究者/技術者の育成による知識の継承である。本プロジェクトでは、1)物質移行試験、2)処分技術の実証と体系化、3)実規模の人工バリアシステムの解体試験の3つの研究タスクに取り組んでいる。これらのタスクでは、実際に坑道を掘削して原位置試験を実施しながら、解析手法や調査手法の妥当性を検証していく。この点は、HIPの特徴的で独創的な側面であり、上記の3つの研究課題は国際的にみても難易度の高いチャレンジングなものである。以上の点から、HIPは地下研究施設を活用した国際協力の良好事例となり得る。
宮川 和也; 石井 英一; 今井 久*; 平井 哲*; 大野 宏和; 中田 弘太郎*; 長谷川 琢磨*
原子力バックエンド研究(CD-ROM), 31(2), p.82 - 95, 2024/12
高レベル放射性廃棄物の処分地の選定過程における概要調査では、地下水の涵養域から流出域までを包含する数km-数十kmの広域を対象とした地下水流動解析により、地下水の移行時間・経路が評価される。亀裂の発達する岩盤中の地下水の移行時間を解析的に求める上で、岩盤の水理学的有効間隙率は感度の高いパラメータである。堆積岩ではボーリング調査における原位置水理試験から得られた亀裂の透水性を岩盤の透水性として扱う一方で、コア試料を用いて浮力法などの室内試験から得られた健岩部の間隙率を水理学的有効間隙率として扱うなど、有効間隙率の考え方が明確ではない。本研究では亀裂の発達する堆積岩である声問層および稚内層浅部を例として、亀裂の開口幅を基に推定した有効間隙率を用いた場合の移行時間を、観測結果と比較することで、有効間隙率の推定方法を検討した。その結果、亀裂の開口幅を基に推定した有効間隙率を用いた場合、観測結果と整合的な移行時間が得られた。その時の有効間隙率は、健岩部の間隙率と比較して1-3桁小さい値であった。多孔質な健岩部と割れ目からなる水みちネットワークを有する堆積岩の場合、亀裂の開口幅を基に有効間隙率を推定することが有効であることが示された。
尾崎 裕介; 石井 英一
Geoenergy (Internet), 2(1), p.geoenergy2023-056_1 - geoenergy2023-056_11, 2024/12
本研究では、幌延深地層研究センターにおける約10年間の研究坑道の掘削時の坑内への湧水データおよびHDB-6孔で観測された水圧変化を再現解析することで、幌延深地層研究センター周辺における稚内層内部における有効透水係数を推定した。求めた有効透水係数をLandau-Lifshitz-Matheronの式により断層の透水量係数や断層における流れの次元と定量的に関連付けた。これらの結果、稚内層における有効透水係数は、透水量係数のダクタリティインデックスに対する依存性と透水量係数の次元への依存性の双方を考慮した場合に推定される透水量係数と整合的であることが示された。
大野 宏和; 石井 英一; 武田 匡樹
Geoenergy (Internet), 2(1), p.geoenergy2023-047_1 - geoenergy2023-047_10, 2024/12
Faults in some deep mudstones have poor hydraulic connectivity owing to high normal stress on the fault planes. Designing a method for modeling solute transport pathways in such faults/fractures using available data is a critical issue vis-a-vis the safety assessment of radioactive waste disposal. In this study, faults in deep siliceous mudstones with low swelling capacity are investigated using cross-hole hydraulic and tracer tests between two boreholes. These results indicate that transport pathways in faults with low hydraulic connectivity can be modeled using a highly tortuous 1D pipe flow path.