Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
 のIn-NMR
のIn-NMR神戸 振作; 徳永 陽; 酒井 宏典; 中堂 博之; 松田 達磨; 安岡 弘志; 芳賀 芳範; 大貫 惇睦
no journal, ,
重い電子系超伝導体CeIrIn のIn-NMRを行い、ナイトシフト,スピン格子緩和時間T1の温度依存,異方性を決定した。ナイトシフトやT1は異方的であり、磁気揺らぎに強い異方性があることがわかった。またナイトシフトと静磁化率のプロットは低温で直線とはならず、超微細相互作用に温度依存があることが明らかになった。超微細相互作用の起原と温度依存,スピン揺らぎの異方性について議論する。
のIn-NMRを行い、ナイトシフト,スピン格子緩和時間T1の温度依存,異方性を決定した。ナイトシフトやT1は異方的であり、磁気揺らぎに強い異方性があることがわかった。またナイトシフトと静磁化率のプロットは低温で直線とはならず、超微細相互作用に温度依存があることが明らかになった。超微細相互作用の起原と温度依存,スピン揺らぎの異方性について議論する。
安武 伸俊*; 丸山 敏毅; 巽 敏隆*; 木内 健太*; 固武 慶*
no journal, ,
表面張力や電場の遮蔽効果を考慮したクォーク-ハドロン相転移における混合相の状態方程式とそれが強磁場中性子星の構造に与える影響について考察する。ハドロン相を表す状態方程式は や
や といったハイペロンを含むBruekner-Hartree-Fockモデルに基づいたものを、クォーク相についてはMITバッグ模型を用い、パスタ構造を考慮した混合相の状態方程式を計算する。これを用いて、回転する中性子星の構造と磁場のプロファイルを平衡形状の方程式を解くことで求めた。クォーク-ハドロン混合相における表面張力の不定性を考慮しても、明らかに特徴的な中性子星の磁場分布を得た。この結果は混合相が中性子星の熱的進化に影響を与える可能性を示唆している。
といったハイペロンを含むBruekner-Hartree-Fockモデルに基づいたものを、クォーク相についてはMITバッグ模型を用い、パスタ構造を考慮した混合相の状態方程式を計算する。これを用いて、回転する中性子星の構造と磁場のプロファイルを平衡形状の方程式を解くことで求めた。クォーク-ハドロン混合相における表面張力の不定性を考慮しても、明らかに特徴的な中性子星の磁場分布を得た。この結果は混合相が中性子星の熱的進化に影響を与える可能性を示唆している。
 Gd核異性体の寿命測定
Gd核異性体の寿命測定浅井 雅人; 林 裕晃*; 長 明彦; 佐藤 哲也; 乙川 義憲; 長江 大輔; 塚田 和明; 宮下 裕次*; 大内 裕之*; 泉 さやか*; et al.
no journal, ,
 崩壊で励起される長寿命核異性体の半減期を、全吸収検出器を用いて測定する方法を新たに開発し、
崩壊で励起される長寿命核異性体の半減期を、全吸収検出器を用いて測定する方法を新たに開発し、 Gd及び
Gd及び GdのKアイソマーの半減期を初めて決定した。原子力機構タンデム加速器に設置されたオンライン同位体分離装置ISOLを用いて、短寿命中性子過剰核
GdのKアイソマーの半減期を初めて決定した。原子力機構タンデム加速器に設置されたオンライン同位体分離装置ISOLを用いて、短寿命中性子過剰核 Eu及び
Eu及び Euを合成・分離し、
Euを合成・分離し、 Euの
Euの 崩壊で放出される
崩壊で放出される 線や
線や 線を全吸収測定した。検出された事象ごとに時間情報を付加して記録することで、100
線を全吸収測定した。検出された事象ごとに時間情報を付加して記録することで、100 秒以上の寿命を持つ核異性体の寿命測定を可能にした。
秒以上の寿命を持つ核異性体の寿命測定を可能にした。
余語 覚文; 佐藤 克俊*; 錦野 将元; 森 道昭; 手島 昭樹*; 沼崎 穂高*; 村上 昌雄*; 小倉 浩一; 匂坂 明人; 織茂 聡; et al.
no journal, ,
高強度レーザー-プラズマ相互作用を用いて、最大エネルギー約2.5MeVの陽子線を発生させ、これを培養状態(in-vitro)のヒト肺腺がん細胞に照射して、その生物学的効果を評価した。 H2AX免疫蛍光染色法によるDNA損傷評価を行った結果、陽子線20Gyを照射したサンプルに対して、DNA2本鎖切断の発生を示す結果を得た。講演では、レーザー駆動陽子線の特徴についても議論する。
H2AX免疫蛍光染色法によるDNA損傷評価を行った結果、陽子線20Gyを照射したサンプルに対して、DNA2本鎖切断の発生を示す結果を得た。講演では、レーザー駆動陽子線の特徴についても議論する。
佐藤 真一郎; 齋 均*; 今泉 充*; 島崎 一紀*; 大島 武
no journal, ,
荷電粒子線照射による水素化アモルファスシリコン(a-Si:H)薄膜の光伝導度変化について調べた。プラズマ化学気相成長(PECVD)法によりガラス基板上に製膜したa-Si:H薄膜(300nmt)に、0.10, 1.0, 10MeV H を最大10
を最大10 /cm
/cm 程度まで室温照射し、そのときの光伝導度の変化を照射チャンバー内で測定した。その結果、いずれの条件においても光伝導度はH
程度まで室温照射し、そのときの光伝導度の変化を照射チャンバー内で測定した。その結果、いずれの条件においても光伝導度はH 照射量の増大とともにいったん上昇し、その後減少するという特異な現象が観察された。一方、2.8MeV Si
照射量の増大とともにいったん上昇し、その後減少するという特異な現象が観察された。一方、2.8MeV Si を室温照射した場合には増加は見られなかった。また、試料電極間に5.00kV/cmのバイアス電圧を印加し、暗伝導度(暗電流)をモニターしながら10MeV H
を室温照射した場合には増加は見られなかった。また、試料電極間に5.00kV/cmのバイアス電圧を印加し、暗伝導度(暗電流)をモニターしながら10MeV H 照射を行うと、照射中に暗伝導度は急激に増大した。さらに、照射前と比べて5桁程度高い暗伝導度を示した時点で照射を止めても(3
照射を行うと、照射中に暗伝導度は急激に増大した。さらに、照射前と比べて5桁程度高い暗伝導度を示した時点で照射を止めても(3 10
10 /cm
/cm )、この高い暗伝導度はその後も長時間にわたって持続した。
)、この高い暗伝導度はその後も長時間にわたって持続した。
坂井 徹; 利根川 孝*; 岡本 清美*
no journal, ,
スピン1/2歪んだダイヤモンド鎖について、密度行列繰り込み群と有限系の数値的厳密対角化により理論的に解析した。その結果、1/3磁化プラトーの上側に磁場によって誘起される非整合長距離秩序が現れることが判明した。われわれはこの結果により、アズライトで観測されている磁場誘起非整合秩序を理論的に説明する。
河裾 厚男; 前川 雅樹
no journal, ,
シリコンは融液からの引上法(チョクラルスキー成長)で製造されるため、固有欠陥の性質を解明するには、融液の固化過程を調べることが必要である。大嶋らは、電顕観察から、固化過程における四面体積層欠陥の形成や、融解に伴う前駆状態の発現を明らかにしている。本研究では、融点直下での陽電子消滅測定を行った。チョクラルスキー法で成長したPドープ(ドープ量:約1E+14/cc)又はSbドープ(ドープ量:約1E+18/cc)のn型シリコンを幅1mm程度の短冊状に成形し、通電により融解まで加熱した。試料に20keVの陽電子マイクロビームを照射し、消滅 線のドップラースペクトルを測定した。その結果いずれの試料でも、融点直下20K程度の領域で物質密度自体の増加を示唆するスペクトルの広幅化が観測された。融液は近似的に
線のドップラースペクトルを測定した。その結果いずれの試料でも、融点直下20K程度の領域で物質密度自体の増加を示唆するスペクトルの広幅化が観測された。融液は近似的に -Sn構造とCmca構造であると考えられているので、これらの構造を仮定してスペクトルを理論的に計算した。その結果、実験結果がよく再現できることが明らかになった。さらにSbドープ試料では、融解直前にスペクトルが著しく狭小化し、空孔構造が形成されることが示唆された。スペクトル狭小化の程度から、複空孔よりも大きな寸法の空孔構造であると推定される。
-Sn構造とCmca構造であると考えられているので、これらの構造を仮定してスペクトルを理論的に計算した。その結果、実験結果がよく再現できることが明らかになった。さらにSbドープ試料では、融解直前にスペクトルが著しく狭小化し、空孔構造が形成されることが示唆された。スペクトル狭小化の程度から、複空孔よりも大きな寸法の空孔構造であると推定される。
横田 光史
no journal, ,
ガラス転移の統計力学的模型としても用いられているポッツグラス模型では、普通、それぞれの局所状態は同等に扱われる。すなわち、それぞれの局所変数で表される状態と他の局所変数で表される状態との相互作用は、すべて同一の形を用いている。ここでは、ポッツ変数で表現される状態が、少し広がりをもった範囲での状態を表していると考え、ポッツ変数に対して同一でない2種類の状態を導入する。したがって、相互作用もそれらの状態に依存する。相互作用の一部にランダム相互作用を導入すると、グラス模型になる。このような模型のうちで比較的単純な模型を考えて、平均場近似でその系の相図を調べた。可能な状態の種類や、レプリカ対称性の破れを表すAT線を求めた。
 のNi-3d電子状態変化の直接観測
のNi-3d電子状態変化の直接観測水牧 仁一朗*; 安居院 あかね; 齊藤 高志*; 東 正樹*; 島川 祐一*; 高野 幹夫*; 魚住 孝幸*
no journal, ,
希土類Niペロブスカイト酸化物(RNiO )は温度により金属絶縁体(MI)転移を示す。本研究ではこの機構を明らかにするためにR=PrのRNiO
)は温度により金属絶縁体(MI)転移を示す。本研究ではこの機構を明らかにするためにR=PrのRNiO を対象とし、Ni-L吸収端において共鳴X線発光分光測定(RXES)及びX線吸収測定(XAS)を行った。その結果はMI転移機構には、Ni-3d電子状態が強くかかわっていることを示唆している。
を対象とし、Ni-L吸収端において共鳴X線発光分光測定(RXES)及びX線吸収測定(XAS)を行った。その結果はMI転移機構には、Ni-3d電子状態が強くかかわっていることを示唆している。
 のNQR
のNQR徳永 陽; 藤本 達也*; 酒井 宏典; 中堂 博之; 神戸 振作; 松田 達磨; 芳賀 芳範; 大貫 惇睦
no journal, ,
六方晶TiNi 型の結晶構造を持つUPd
型の結晶構造を持つUPd は、低温で連続した3つの相転移を示す。これらの相転移の起源は基本的にquasi-cubic対称性を持った局在f電子の四極子自由度によるものと考えられている。最近の共鳴X線散乱実験からは、高温側の秩序相について
は、低温で連続した3つの相転移を示す。これらの相転移の起源は基本的にquasi-cubic対称性を持った局在f電子の四極子自由度によるものと考えられている。最近の共鳴X線散乱実験からは、高温側の秩序相について 型の四極子秩序の存在が示唆されているが、それ以外については詳細は明らかになっていない。そこでわれわれはこのUPd
型の四極子秩序の存在が示唆されているが、それ以外については詳細は明らかになっていない。そこでわれわれはこのUPd の複雑な相図を理解すべく、新たに
の複雑な相図を理解すべく、新たに Pdを97%に濃縮した試料を作成し、
Pdを97%に濃縮した試料を作成し、 Pd-NQRによる研究を進めている。当日は
Pd-NQRによる研究を進めている。当日は Pd-NQR周波数の温度依存性,秩序相におけるPdサイトの対称性等について報告する。
Pd-NQR周波数の温度依存性,秩序相におけるPdサイトの対称性等について報告する。
飯村 秀紀; Buchinger, F.*
no journal, ,
Finite Range Droplet模型(FRDM)は原子核の質量や変形等の特性をすべての原子核について統一的に予測するために最近開発された核構造模型である。この模型で使用されるパラメータは原子核質量を再現するように最適化されているので、最適化で考慮されていない核荷電半径は模型の予測力を検証するのに良い物理量である。本研究では、反転対称でない変形が予想される原子核の荷電半径をFRDMに非反転対称性を取入れて計算した。また、模型で含まれていない零点振動の影響を取入れるために、B(E2)の実験値から得られる四重極変形パラメータを用いて、核荷電半径をFRDMで計算した。これらの結果、実験値との一致は改善されたものの依然として差が残り、FRDMの限界が示された。
大西 弘明; Dagotto, E.*
no journal, ,
量子ドット系の輸送特性に対する電子格子相互作用の効果について、時間依存密度行列繰り込み群法を用いて数値的解析を行う。電子格子相互作用を大きくしていくと、有効引力によりクーロン相互作用が減少するため、スピン揺らぎは抑制されて電荷揺らぎが増強すると考えられる。ここでは特に直列型二重量子ドットに焦点を当てて、電子間相互作用と電子格子相互作用の競合が、微分コンダクタンスや電荷・スピン状態にどう反映するのかを議論する。
柳林 潤; 仲野 友英; 蓮尾 昌裕*; 岩前 敦; 久保 博孝; 伊丹 潔
no journal, ,
タングステンは、プラズマスパッタリングによる損耗や水素の吸蔵が少ないために、ITERのダイバータ材料の候補とされている。しかしタングステンイオンが炉心プラズマに蓄積すると強い放射冷却を起こすことが問題である。蓄積の仕組みを調べる準備として、本研究ではタングステンイオンの真空紫外発光線を同定した。JT-60Uプラズマ(

 6keV)からの真空紫外発光スペクトル(
6keV)からの真空紫外発光スペクトル(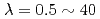 nm)を、平面結像型の斜入射分光器を用いて観測した。その結果、波長3, 5, 6及び13nm付近にピークを持つスペクトルが観測された。Flexible Atomic Codeを用いた理論計算スペクトルとの比較により、3nm付近の発光線は47価以上のイオンの
nm)を、平面結像型の斜入射分光器を用いて観測した。その結果、波長3, 5, 6及び13nm付近にピークを持つスペクトルが観測された。Flexible Atomic Codeを用いた理論計算スペクトルとの比較により、3nm付近の発光線は47価以上のイオンの 準位間の遷移によるもの、また5, 6及び13nm付近の発光線は45価以下のイオンの
準位間の遷移によるもの、また5, 6及び13nm付近の発光線は45価以下のイオンの 準位間の遷移によるものであることがわかった。特に前者は、ITERの高温プラズマ(
準位間の遷移によるものであることがわかった。特に前者は、ITERの高温プラズマ(

 10keV)におけるタングステンイオンの蓄積の診断に有用であると考えられる。
10keV)におけるタングステンイオンの蓄積の診断に有用であると考えられる。
 YCu
YCu O
O の低温構造
の低温構造茂筑 高士*; 畑 慶明*; Tuerxun, W.*; 井川 直樹; 星川 晃範*; 石垣 徹*; 安岡 宏*; 平田 和人*
no journal, ,
FeSr YCu
YCu O
O 系はBa
系はBa YCu
YCu O
O 系超伝導体のCuサイトをFeに置換した磁性超伝導体であり、還元熱処理及びそれに引き続く酸化熱処理によって超伝導と磁性が発現される。高温還元雰囲気で正方晶から斜方晶への相転移が、これら特性の発現のために必要なCuとFeの秩序配列の要因である。本研究では、低温での磁気秩序発現に関する知見を得るために中性子回折実験を行った。その結果、磁性相転移温度以下でも磁気反射は観測されず、この系の磁気秩序は長距離秩序ではないことが明らかになった。格子定数の温度変化は30K付近で極値を持つ傾向がみられ、構造的な変化と磁気秩序の発現が関連している可能性がある。
系超伝導体のCuサイトをFeに置換した磁性超伝導体であり、還元熱処理及びそれに引き続く酸化熱処理によって超伝導と磁性が発現される。高温還元雰囲気で正方晶から斜方晶への相転移が、これら特性の発現のために必要なCuとFeの秩序配列の要因である。本研究では、低温での磁気秩序発現に関する知見を得るために中性子回折実験を行った。その結果、磁性相転移温度以下でも磁気反射は観測されず、この系の磁気秩序は長距離秩序ではないことが明らかになった。格子定数の温度変化は30K付近で極値を持つ傾向がみられ、構造的な変化と磁気秩序の発現が関連している可能性がある。
 Al
Al の上部臨界磁場における1次転移,2
の上部臨界磁場における1次転移,2芳賀 芳範; 本間 佳哉*; 松田 達磨; 立岩 尚之; 青木 大*; 大貫 惇睦
no journal, ,
NpPd Al
Al について極低温磁場中での比熱測定により、上部臨界磁場における電子比熱係数の変化を調べた。極低温を達成するためには
について極低温磁場中での比熱測定により、上部臨界磁場における電子比熱係数の変化を調べた。極低温を達成するためには Npの
Npの 崩壊による発熱が問題となる。これを回避するために、微小試料を用い、熱浴との熱リンクを強くした交流法を用いた。熱浴を0.15Kに保った状態での熱容量の磁場依存性から、電気抵抗で決定した上部臨界磁場Hc2(37kOe)において電子比熱係数の大きな変化が起こっていることがわかる。また、混合状態では比熱の磁場依存性が小さく、CeCoIn
崩壊による発熱が問題となる。これを回避するために、微小試料を用い、熱浴との熱リンクを強くした交流法を用いた。熱浴を0.15Kに保った状態での熱容量の磁場依存性から、電気抵抗で決定した上部臨界磁場Hc2(37kOe)において電子比熱係数の大きな変化が起こっていることがわかる。また、混合状態では比熱の磁場依存性が小さく、CeCoIn あるいは通常の第2種超伝導体と大きく異なる。このことは、上部臨界磁場における1次転移を裏付けるものと考えられる。
あるいは通常の第2種超伝導体と大きく異なる。このことは、上部臨界磁場における1次転移を裏付けるものと考えられる。
 -
- 相互作用の効果
相互作用の効果武藤 巧*; 丸山 敏毅; 巽 敏隆*
no journal, ,
複数個のK中間子が束縛したマルチK中間子原子核(MKN)の構造と性質を相対論的平均場理論に基づく数値計算により、マルチストレンジネスを含むハドロン物質系がいかに形成され、無限系としてのK中間子凝縮といかに関係するかを検討した。特に、非線形 -
- 相互作用の起源と、その斥力効果がMKNの性質にどのような効果をもたらすかを調べた。MKN中でのK中間子1粒子エネルギーと、K中間子有効質量,ベクトル型のK-N相互作用をK中間子数の関数としてプロットすることで、カイラル対称性に特有な非線形
相互作用の起源と、その斥力効果がMKNの性質にどのような効果をもたらすかを調べた。MKN中でのK中間子1粒子エネルギーと、K中間子有効質量,ベクトル型のK-N相互作用をK中間子数の関数としてプロットすることで、カイラル対称性に特有な非線形 場に由来する項からの寄与と、
場に由来する項からの寄与と、 中間子と
中間子と ,
,  ,
,  中間子との結合から生じる寄与があることが示された。
中間子との結合から生じる寄与があることが示された。
五十嵐 誉廣; 中沢 哲也; 都留 智仁; 加治 芳行
no journal, ,
原子炉構造材料であるステンレス鋼の応力腐食割れ(SCC)機構解明のため、鉄を主成分とする合金系のエネルギー安定性解析を行った。ステンレス鋼エネルギー解析の予備検討として、本研究では解析対象の系を鉄クロム合金とし、解析には拡張半経験分子軌道法を用いた。bcc鉄系の原子の一部をクロム原子に置換し構造緩和を行った結果、置換したクロム原子と周囲の鉄原子の原子間距離が大きくなることがわかった。置換したクロム原子周辺の電子状態を詳細に調べたところ各原子の電子数に変化が生じており、これが原子間距離の変化に影響を及ぼしていると考えられる。
 Fe
Fe (C
(C O
O )
) (H
(H O)
O) の中性子散乱
の中性子散乱松田 雅昌; 本多 善太郎*
no journal, ,
Na Fe
Fe (C
(C O
O )
) (H
(H O)
O) (以降SIOと略す)ではFe
(以降SIOと略す)ではFe イオンが2本足スピン梯子鎖を形成している。同様の結晶構造を持つNa
イオンが2本足スピン梯子鎖を形成している。同様の結晶構造を持つNa Co
Co (C
(C O
O )
) (H
(H O)
O) (以降SCOと略す)では、梯子の桟方向の相互作用が支配的で孤立反強磁性ダイマー模型でほぼ説明可能であり、梯子鎖としての性質は見られなかった。一方、磁化測定の結果からSIOでは梯子の足方向の相互作用も有限であることが報告されている。われわれは、中性子散乱実験でSIO粉末の磁気励起を測定することにより、この物質の桟方向,足方向の相互作用を調べた。実験の結果、
(以降SCOと略す)では、梯子の桟方向の相互作用が支配的で孤立反強磁性ダイマー模型でほぼ説明可能であり、梯子鎖としての性質は見られなかった。一方、磁化測定の結果からSIOでは梯子の足方向の相互作用も有限であることが報告されている。われわれは、中性子散乱実験でSIO粉末の磁気励起を測定することにより、この物質の桟方向,足方向の相互作用を調べた。実験の結果、 3.5meVと
3.5meVと 5.3meVに鋭い2つの磁気励起ピークを観測した。この結果から、観測された磁気励起は反強磁性ダイマーの第1励起状態(triplet)が単イオン異方性により2つに分裂したものに相当すると推測される。また、これらのピークのエネルギー幅は分解能程度に狭いため、孤立系からの磁気励起であると推測される。このようにSIOの磁性はSCO同様に異方的な孤立反強磁性ダイマー模型でほぼ説明可能であることが示唆された。
5.3meVに鋭い2つの磁気励起ピークを観測した。この結果から、観測された磁気励起は反強磁性ダイマーの第1励起状態(triplet)が単イオン異方性により2つに分裂したものに相当すると推測される。また、これらのピークのエネルギー幅は分解能程度に狭いため、孤立系からの磁気励起であると推測される。このようにSIOの磁性はSCO同様に異方的な孤立反強磁性ダイマー模型でほぼ説明可能であることが示唆された。
 O
O の磁気カイラリティの研究
の磁気カイラリティの研究脇本 秀一; 木村 宏之*; 福永 守*; 武田 全康; 加倉井 和久; 野田 幸男*
no journal, ,
マルチフェロイック物質RMn O
O における磁性誘起強誘電性の起源としてS
における磁性誘起強誘電性の起源としてS SによるものとS・Sによるものの2つが提唱されている。一方、R=Tmでは、つい最近、LT-ICM相の低温領域(4K)で電気分極の方向がb軸からa軸に変化する新たな転移が発見された。この分極フロップ転移とスピンカイラリティの関係を調べるため、TmMn
SによるものとS・Sによるものの2つが提唱されている。一方、R=Tmでは、つい最近、LT-ICM相の低温領域(4K)で電気分極の方向がb軸からa軸に変化する新たな転移が発見された。この分極フロップ転移とスピンカイラリティの関係を調べるため、TmMn O
O 単結晶を用いて電場中偏極中性子回折実験を行った。結果、6KではP//bの分極発現に寄与するbc面カイラリティが存在するが、分極フロップしP//aとなった3.8Kではこれが完全に消失することを発見し、LT-ICM相ではS
単結晶を用いて電場中偏極中性子回折実験を行った。結果、6KではP//bの分極発現に寄与するbc面カイラリティが存在するが、分極フロップしP//aとなった3.8Kではこれが完全に消失することを発見し、LT-ICM相ではS Sによる分極がドミナントであることを示す結果を得た。
Sによる分極がドミナントであることを示す結果を得た。
橋本 美絵; 深谷 有喜; 河裾 厚男; 一宮 彪彦
no journal, ,
Ge(111)-

 -Sn表面は、220K以下で3
-Sn表面は、220K以下で3 3構造へ相転移する。この相転移は、2次元系のパイエルス転移として注目されたが、その後Sn原子が熱的に揺らいだモデルが報告され、現在も解明が行われている。また最近、30K以下で再び
3構造へ相転移する。この相転移は、2次元系のパイエルス転移として注目されたが、その後Sn原子が熱的に揺らいだモデルが報告され、現在も解明が行われている。また最近、30K以下で再び

 構造へモット転移することが報告された。しかしながら、この走査トンネル顕微鏡像はチップの影響を受けたものであり、
構造へモット転移することが報告された。しかしながら、この走査トンネル顕微鏡像はチップの影響を受けたものであり、

 構造への相転移は起こらないとする論文が発表された。このように研究が盛んに行われているが、相転移のメカニズムやSn原子の変位に関しては、まだ明らかになっていない。そこで本研究では、最表面に敏感な反射高速陽電子回折を用いて、Sn/Ge(111)表面からのロッキング曲線を測定し、動力学的回折理論に基づく強度計算との比較から、それぞれの相転移前後における原子変位について報告する。293Kと110Kからのロッキング曲線の測定を行った結果、ほとんど変化が見られなかった。よって220Kで起こる相転移は、秩序-無秩序相転移であると考えられる。一方、110Kと29Kのロッキング曲線を比較すると、わずかな変化が見られ、極低温でSn原子が変位していることがわかった。
構造への相転移は起こらないとする論文が発表された。このように研究が盛んに行われているが、相転移のメカニズムやSn原子の変位に関しては、まだ明らかになっていない。そこで本研究では、最表面に敏感な反射高速陽電子回折を用いて、Sn/Ge(111)表面からのロッキング曲線を測定し、動力学的回折理論に基づく強度計算との比較から、それぞれの相転移前後における原子変位について報告する。293Kと110Kからのロッキング曲線の測定を行った結果、ほとんど変化が見られなかった。よって220Kで起こる相転移は、秩序-無秩序相転移であると考えられる。一方、110Kと29Kのロッキング曲線を比較すると、わずかな変化が見られ、極低温でSn原子が変位していることがわかった。