Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
 -ray elastic scattering
-ray elastic scatteringOmer, M.; 静間 俊行*; 小泉 光生; 羽島 良一*; 橋本 智*; 宮本 修治*
LASTI Annual Report, 24, p.20 - 22, 2023/12
Nondestructive elemental analysis is highly valued in many fields such as archeology, paleontology, space sciences, nuclear security, and nuclear nonproliferation. These fields usually impose estimating the elemental composition of bulk, large, and inhomogeneous samples nondestructively. Common elemental analysis techniques such as X-ray fluorescence (XRF) may fail in such situations due to self-absorption of low energy X-rays within thin layers of the sample. In the present study, we propose a novel nondestructive method that may be useful in distinguishing the elemental composition of a given sample based on the elastic scattering of linearly polarized and high-energy  -rays. Linear polarization of
-rays. Linear polarization of  -rays causes asymmetry of the elastic scattering cross sections with respect to the polarization plane of the incident
-rays causes asymmetry of the elastic scattering cross sections with respect to the polarization plane of the incident  -rays. At specific
-rays. At specific  -ray energies and scattering angles, the asymmetry ratio, R, of the cross sections in two orthogonal planes is characteristic of each element. The measurement of asymmetry ratio of 1.62 MeV linearly polarized
-ray energies and scattering angles, the asymmetry ratio, R, of the cross sections in two orthogonal planes is characteristic of each element. The measurement of asymmetry ratio of 1.62 MeV linearly polarized  -rays at NewSUBARU facility is presented. This work is a contribution of the JAEA to the International Atomic Energy Agency (IAEA) under the agreement of the coordinated research program (CRP), J02015 (Facilitation of Safe and Secure Trade Using Nuclear Detection Technology - Detection of RN and Other Contraband).
-rays at NewSUBARU facility is presented. This work is a contribution of the JAEA to the International Atomic Energy Agency (IAEA) under the agreement of the coordinated research program (CRP), J02015 (Facilitation of Safe and Secure Trade Using Nuclear Detection Technology - Detection of RN and Other Contraband).
桐原 陽一; 中島 宏; 佐波 俊哉*; 波戸 芳仁*; 糸賀 俊朗*; 宮本 修治*; 武元 亮頼*; 山口 将志*; 浅野 芳裕*
Journal of Nuclear Science and Technology, 57(4), p.444 - 456, 2020/04
被引用回数:10 パーセンタイル:62.77(Nuclear Science & Technology)兵庫県立大学ニュースバル放射光施設ビームラインBL01において、 MeVの単色直線偏光光子ビームを
MeVの単色直線偏光光子ビームを Auへ照射したときの中性子放出スペクトルを、飛行時間法により測定した。これより光核反応によって生成される2成分の中性子スペクトルを測定した。このうちの1つ成分(A)は、4MeVまでのエネルギーであり蒸発に類似したスペクトル形状を示した。もう一方の成分(B)は、4MeV以上のエネルギーでありバンプに類似したスペクトル形状を示した。中性子の放出強度において、成分(A)は角度依存は見られなかったが、成分(B)は偏光と検出器方向を成す角度
Auへ照射したときの中性子放出スペクトルを、飛行時間法により測定した。これより光核反応によって生成される2成分の中性子スペクトルを測定した。このうちの1つ成分(A)は、4MeVまでのエネルギーであり蒸発に類似したスペクトル形状を示した。もう一方の成分(B)は、4MeV以上のエネルギーでありバンプに類似したスペクトル形状を示した。中性子の放出強度において、成分(A)は角度依存は見られなかったが、成分(B)は偏光と検出器方向を成す角度 の関数として、
の関数として、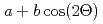 の関係を示すことがわかった。
の関係を示すことがわかった。
 -ray beams
-ray beams早川 岳人; 宮本 修治*; 羽島 良一; 静間 俊行; 天野 壮*; 橋本 智*; 三澤 毅*
Journal of Nuclear Science and Technology, 53(12), p.2064 - 2071, 2016/12
被引用回数:9 パーセンタイル:59.71(Nuclear Science & Technology)準単色の 線による光核反応を用いた選択的な同位体変換法を提案する。この手法は、
線による光核反応を用いた選択的な同位体変換法を提案する。この手法は、 Zr,
Zr,  Pd、ないし
Pd、ないし Seのような長寿命核分裂生成物(LLFP)の粒子閾値が、同じ元素の他の安定同位体の粒子閾値より低いという事実に基づく。そのため、この手法では、ターゲット物質がLLFP以外に安定同位体を含んでいたとしても、新しくLLFPが生成されないという傑出した特徴を有する。レーザーコンプトン散乱
Seのような長寿命核分裂生成物(LLFP)の粒子閾値が、同じ元素の他の安定同位体の粒子閾値より低いという事実に基づく。そのため、この手法では、ターゲット物質がLLFP以外に安定同位体を含んでいたとしても、新しくLLFPが生成されないという傑出した特徴を有する。レーザーコンプトン散乱 線と原子炉の中性子捕獲反応
線と原子炉の中性子捕獲反応 線がこの手法に適した
線がこの手法に適した 線源である。
線源である。
出口 朗*; 梅木 博之*; 植田 浩義*; 宮本 陽一; 柴田 雅博; 内藤 守正; 田中 俊彦*
LBNL-1006984 (Internet), p.12_1 - 12_22, 2016/12
我が国における高レベル放射性廃棄物の地層処分については、1999年に「第2次取りまとめ」として技術的信頼性が取りまとめられたが、その後10年以上が経過するとともに、東北地方太平洋沖地震などの自然事象が発生していることから、政府は、地層処分の技術的信頼性について、改めて最新の科学的知見を反映した再評価を行った。この再評価結果を受け、政府は、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」を変更し、国が「科学的有望地」を提示するとともに、国が調査への協力を自治体に申し入れることを定めた。原子力発電環境整備機構(NUMO)および関係研究開発組織(原子力機構および原子力環境整備センター)は、地層処分の技術的信頼性の向上のため研究開発を進めている。また、NUMOは、一般的なセーフティケースの構築を進めている。
小出 馨; 大澤 英昭; 伊藤 洋昭; 棚井 憲治; 仙波 毅; 内藤 守正; 杉原 弘造; 宮本 陽一
Annual Waste Management Symposium (WM 2015), Vol.5, p.3631 - 3645, 2015/00
原子力機構は高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する研究開発を進めており、その一環として日本の多種多様な地質環境に対応するため、深地層の研究施設計画として超深地層研究所計画(瑞浪)と幌延深地層研究計画を立ち上げた。瑞浪では結晶質岩を対象に深地層の科学的研究を実施している。一方、幌延では堆積岩を対象に深地層の科学的研究と地層処分研究開発を実施している。両プロジェクトとも、計画を「地上からの調査研究段階(第1段階)」「坑道堀削時の調査研究段階(第2段階)」「地下施設での調査研究段階(第3段階)」の3つの段階に分けて進めている。現在、研究坑道の堀削工事は、瑞浪では深度500mまで、また、幌延では深度350mまで終了している。今後、両プロジェクトでは、地質環境の長期変遷に関する研究を含む第3段階の研究を進めるとともに、深地層の研究施設を地層処分分野の研究者・技術者の育成、国民との相互理解促進、国際協力の場として活用していく。
宮本 陽一
デコミッショニング技報, (47), p.10 - 28, 2013/03
我が国においては、原子力発電所以外にもさまざまな原子力施設や放射性同位元素使用施設等があり、これらの施設から低レベル放射性廃棄物(研究施設等廃棄物)が発生している。このような研究施設等廃棄物は、現在に至るまで処分されることなく各機関等に累積保管されており、原子力の研究開発等の実施に支障をきたす懸念が高まっている。そこで、研究施設等廃棄物の処分を早急かつ確実に実施するため、2008年(平成20年)に日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)が法的に実施主体として位置づけられた。これを受けて、原子力機構では、国が定めた埋設処分業務の実施に関する基本方針に即して、埋設処分業務の実施に関する計画を策定し、国の認可を受け、処分事業への取り組みを開始した。現在までに、この実施計画に従い、埋設事業の実施に際して必要な埋設施設の概念設計及び立地選定のための基準・手順の検討等を進めてきている。本報告では、これらの概要について紹介する。
杉原 真司*; 田中 将裕*; 玉利 俊哉*; 嶋田 純*; 高橋 知之*; 百島 則幸*; 福谷 哲*; 安藤 麻里子; 佐久間 洋一*; 横山 須美*; et al.
Fusion Science and Technology, 60(4), p.1300 - 1303, 2011/11
被引用回数:2 パーセンタイル:17.52(Nuclear Science & Technology)原子力施設に起因する環境中トリチウムの挙動を評価する技術の開発を目的として、核融合科学研究所周辺の河川,降水及び地下水中トリチウム濃度の変動を測定した。近年の環境中トリチウム濃度は核実験前のレベルまで低下しているため、固体高分子電解質を用いた電気分解で試料中トリチウムを濃縮し、低バックグラウンド液体シンチレーション測定を行った。降水中のトリチウム濃度は0.09 0.78Bq/Lであり、夏と秋に低く冬と春に高い季節変動を示した。河川水と地下水はほぼ一定の値を示し、それぞれ0.34と0.24Bq/Lであった。トリチウム濃度と同時に河川水の電気伝導度と流量、水素及び酸素同位体比の測定を行った。これらのデータをもとにダイナミックモデルを開発し、トリチウムの挙動を解析した。
0.78Bq/Lであり、夏と秋に低く冬と春に高い季節変動を示した。河川水と地下水はほぼ一定の値を示し、それぞれ0.34と0.24Bq/Lであった。トリチウム濃度と同時に河川水の電気伝導度と流量、水素及び酸素同位体比の測定を行った。これらのデータをもとにダイナミックモデルを開発し、トリチウムの挙動を解析した。
伊東 秀明; 前田 茂貴; 内藤 裕之; 秋山 陽一; 宮本 一幸; 芦田 貴志; 野口 好一; 伊藤 主税; 青山 卓史
JAEA-Technology 2010-049, 129 Pages, 2011/03
「常陽」では、計測線付実験装置の試料部が変形して原子炉容器内の炉内燃料貯蔵ラックから突き出て炉心上部の機器等と干渉しており、「常陽」を再起動するためには、炉心上部機構(UCS)を交換することが不可欠である。そのためには、30余年の使用期間中に放射化し、線量率が数百Gy/hに達するUCSを炉容器内から取り出すための大型キャスクの製作が必要である。炉心から約1.5m上方のUCSの中性子照射量の計算精度を考慮して約1桁の設計裕度を見込むと、キャスクの総重量が取扱いクレーンの最大荷重100トンを超過する約160トンとなり、設備改造や復旧経費の増加が予想された。このため、海外でも実施例の少ない炉容器内の 線量率を実測して計算誤差にかかわる設計余裕を低減することによりキャスク遮へい厚さを削減することとした。実機で想定される広域の線量率をカバーし、約200
線量率を実測して計算誤差にかかわる設計余裕を低減することによりキャスク遮へい厚さを削減することとした。実機で想定される広域の線量率をカバーし、約200 Cの高温環境に耐える
Cの高温環境に耐える 線量率測定装置を製作し、
線量率測定装置を製作し、 Co校正照射施設で
Co校正照射施設で 線検出器の校正曲線及び温度特性を確認した。炉容器内の他の構造物や集合体の放射線の混成場を考慮して評価するため、UCSと検出器の相対位置やナトリウムの液位を変えた条件で詳細な線量率分布を測定し、解析値で内挿することによりC/E:1.1
線検出器の校正曲線及び温度特性を確認した。炉容器内の他の構造物や集合体の放射線の混成場を考慮して評価するため、UCSと検出器の相対位置やナトリウムの液位を変えた条件で詳細な線量率分布を測定し、解析値で内挿することによりC/E:1.1 2.4に評価精度を高めた。上記の結果を反映することによりUCS交換キャスクの遮へい厚さを削減でき、総重量を100トン未満とできる見通しが得られたことから、設備改造を要することなくUCS交換が可能となった。
2.4に評価精度を高めた。上記の結果を反映することによりUCS交換キャスクの遮へい厚さを削減でき、総重量を100トン未満とできる見通しが得られたことから、設備改造を要することなくUCS交換が可能となった。
油井 三和; 石川 博久; 渡邊 厚夫*; 吉野 恭司*; 梅木 博之; 日置 一雅; 内藤 守正; 瀬尾 俊弘; 牧野 仁史; 小田 治恵; et al.
JAEA-Research 2010-015, 106 Pages, 2010/05
本報告書は日米原子力エネルギー共同行動計画廃棄物管理ワーキンググループのフェーズIの活動をまとめたものである。このワーキンググループでは、日米両国間の既存の技術基盤を集約するとともに、今後の協力内容を共同で策定することに主眼を置いている。第一に、両国における核燃料サイクルに関する政策的及び規制の枠組みを概観するとともに、さまざまな先進燃料サイクルシナリオの調査を行い、これらを取りまとめた。第二に、廃棄物管理及び処分システムの最適化について議論を行った。さまざまな区分の廃棄物を対象とした処分システム概念のレビューを行うとともに、最適化において検討すべき要因について議論を行った。これらの作業を通じ、最適化に関する潜在的な協力可能分野と活動の抽出を行った。
臼田 重和; 篠原 伸夫; 桜井 聡; 間柄 正明; 宮本 ユタカ; 江坂 文孝; 安田 健一郎; 國分 陽子; 平山 文夫; Lee, C. G.; et al.
KEK Proceedings 2007-16, p.13 - 22, 2008/02
日本原子力研究開発機構(原子力機構: 2005年発足)では、その前身である日本原子力研究所及び核燃料サイクル開発機構の時代から、おもに原子力施設から環境に漏れる放射線や放射性物質を管理・監視,その影響を評価する目的で、環境放射能にかかわる幅広い研究開発が行われてきた。ここでは、核兵器を廃絶し、原子力の平和利用を推進するため、1990年代の半ばから計画された保障措置にかかわる極微量環境試料分析と包括的核実験禁止条約(CTBT)にかかわる超高感度放射性核種監視に焦点を絞り、核不拡散を目的とした環境放射能に関連する原子力機構の研究開発を紹介する。さらに、開発した技術の応用と今後の展望についても触れる。
 century
century梅木 博之; 内藤 守正; 牧野 仁史; 大澤 英昭; 中野 勝志; 宮本 陽一; McKinley, I. G.*
Proceedings of 15th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE-15) (CD-ROM), 8 Pages, 2007/04
事業段階へ移行した21世紀に入ってから、日本の地層処分計画を取り巻く状況は急速に変化し、とりわけパブリックアクセプタンスへの関心が高まり、また原子力ルネサンスとも関連して処分技術に求められる要件への柔軟性を確保することの必要性が大きくなっている。このため、そのような複雑なプロジェクトを支援するための研究開発を進めるうえで、要件や成果の品質,知識ベースなどを体系的に管理することが極めて重要となってきている。本稿では、現行の4万本のガラス固化体を処分する処分場概念を出発点に、廃棄物の多様化,次世代の処分場概念とその構築に必要な設計/安全評価のツールとデータベース,意思決定の支援に必要な管理ツールなど、幾つかの重要な課題について包括的に論じる。
宮本 陽一; 梅木 博之; 大澤 英昭; 内藤 守正; 中野 勝志; 牧野 仁史; 清水 和彦; 瀬尾 俊弘
Nuclear Engineering and Technology, 38(6), p.505 - 534, 2006/08
クリーンで経済的で社会が受容できるエネルギーの十分な供給を確立することは、21世紀において重要で世界的なチャレンジである。原子力の役割をさらに拡大することが選択の一つと思われるが、このオプションの実施は、すべての放射性廃棄物を安全に処分することにかかっている。安全な処分は専門家の間ではその基本的な実現可能性についてコンセンサスは得られているが、特に主要なステークホルダーにより受け入れられるよう、その概念をもっと実際的なものとしなければならない。ここでは、世界的なトレンドを考慮し、また日本の例を引き合いにして、将来の研究開発の鍵となる分野を明らかにし、有益と思われる国際協力のシナジー効果が生まれる可能性のある分野に焦点を当てていくこととする。
 平成17年度,高レベル放射性廃棄物
平成17年度,高レベル放射性廃棄物梅木 博之; 大澤 英昭; 園部 一志; 宮本 陽一
第5回安全研究成果報告会講演録集; 放射性廃棄物の地層処分について, p.5 - 29, 2006/03
サイクル機構(現、日本原子力研究開発機構)は、国の方針に基づいて高レベル放射性廃棄物地層処分研究の全体計画を作成している。その中で、全体計画にしたがって進める研究開発の成果は、事業の推進,安全規制の策定に資する共通の技術的基盤となることを目指している。特に安全規制の策定に資するという観点からは、上述した安全研究年次計画に応えるものでなければならない。このことを念頭に、年次計画に対応して安全研究計画を作成し、全体計画に沿って進められる研究開発の成果を安全研究という視点で捉えることが可能となるようにした。本稿では、サイクル機構が進めた高レベル放射性廃棄物の地層処分の研究開発について、安全研究としてどのように体系づけられているかを説明したうえで、設定された各個別課題の内容,成果の概要を示す。
広田 直樹*; 伯耆田 貴憲; 井上 洋司; 熊田 政弘; 黒沢 義昭; 宮本 ユタカ; 中原 嘉則; 小田 哲三; 篠原 伸夫; 打越 貴子*; et al.
JAERI-Review 2003-021, 68 Pages, 2003/08
本報告書は、包括的核実験禁止条約(CTBT)検証制度に関連する放射性核種データ解析研究グループの研究活動について述べたものである。本報告書の主題は、(1) CTBT検証制度の概要,(2) 放射性核種データの為の国内データセンターの準備,(3) 日本における高崎と沖縄の放射性核種監視観測所及び東海の公認実験施設の建設・運用である。また当グループは既に公認実験施設のための国際比較試験への参加を果たしており、本報告書にはその試験結果を示す。さらにCTBT関連技術の環境研究への科学的応用についても言及している。
半澤 有希子; 間柄 正明; 渡部 和男; 江坂 文孝; 宮本 ユタカ; 安田 健一郎; 郡司 勝文*; 山本 洋一; 高橋 司; 桜井 聡; et al.
JAERI-Tech 2002-103, 141 Pages, 2003/02
原研で整備した、クリーンルームを有する実験施設である高度環境分析研究棟(CLEAR)について、設計,施工及び2001年6月の運用開始段階における性能評価までを概観する。本施設は、保障措置環境試料分析,包括的核実験禁止条約(CTBT)遵守検証及び環境科学にかかわる研究を目的として、環境試料中の極微量核物質等の分析を行うための施設である。本施設では、クリーンルームの要件と核燃料物質使用施設の要件とを両立した点及び、多量の腐食性の酸を使用した金属元素の微量分析に対応してクリーンルームの使用材料に多大な注意を払った点に大きな特徴がある。そのほか、空調及び空気清浄化の設備,クリーンフード等の実験用設備,分析施設としての利便性及び安全設備についてもその独自性を紹介し、さらに完成したクリーンルームについて、分析操作に対するバックグラウンド評価の結果を示した。本施設の整備により、環境試料中の極微量核物質等の信頼性のある分析を行うための条件が整った。
大湖 岳雄; 宮本 陽一; 川越 浩
サイクル機構技報, (20), p.23 - 30, 2003/00
RI・研究所等廃棄物の余裕深度処分場の場所を特定しない一般的な条件における、概念設計を実施しその結果を取りまとめた。
熊田 政弘; 小田 哲三; 宮本 ユタカ; 打越 貴子*; 中原 嘉則; 山本 洋一; 伯耆田 貴憲; 広田 直樹*; 井上 洋司; 篠原 伸夫
第23回核物質管理学会日本支部年次大会論文集, p.39 - 44, 2002/12
CTBT検証体制では、大気中,水中、及び地中における核爆発の有無を監視するため、世界中に321カ所の観測所を設け、国際監視網を構築することとしている。監視網では、地震,微気圧変動,水中音響及び放射性核種の4つの監視技術が用いられる。このうち、放射性核種監視観測所は世界中に80カ所設けられ、大気粒子をフィルター上に捕集して試料の 線計測を行う。観測所は、一定の技術基準を満たすことによりCTBT機関により認証を受けた後、機関との契約に基づいて、観測網の一部を担うことになっている。また、80カ所の観測所のうち、半数の40カ所には大気放射性希ガス自動計測装置が設置される。原研では、日本に設置される2つの放射性核種監視観測所(群馬県高崎市,沖縄県国頭郡)の設置を進めており、本発表では、観測所設置の現状、及び放射性核種監視観測所の性能等について報告する。
線計測を行う。観測所は、一定の技術基準を満たすことによりCTBT機関により認証を受けた後、機関との契約に基づいて、観測網の一部を担うことになっている。また、80カ所の観測所のうち、半数の40カ所には大気放射性希ガス自動計測装置が設置される。原研では、日本に設置される2つの放射性核種監視観測所(群馬県高崎市,沖縄県国頭郡)の設置を進めており、本発表では、観測所設置の現状、及び放射性核種監視観測所の性能等について報告する。
河村 和廣; 宮本 陽一; 大内 仁
Glass Technology, 39(4), p.142 - 148, 2002/00
動燃が開発した高レベル放射性廃棄物固化処理用のガラスフリット(動燃ガラスコード名:PF798)を用いて、Fe3+/Fe2+比から酸化還元状態を調べ、このガラスの酸化還元平衡が次式で表され、Fe2++(1/4)O2+(3/2)O2-=FeO2- 測定結果を次のようにまとめることができることを明らかにした。log(Fe3+)/(Fe2+)Po2^1/4=-(1.90 0.30)+(4500
0.30)+(4500 430)/(T/K)
430)/(T/K)
河村 和廣; 宮本 陽一
High Temperature Materials and Processes, 16(3), p.169 - 172, 2002/00
動燃が開発した高レベル放射性廃棄物固化処理用のガラスフリット(動燃ガラスコード名:PF798)中のLi2Oに置き換えてMgO、BaOを添加した場合の酸化還元状態の変化を明らかにするため、Fe3+/Fe2+比を測定した。MgOの増加(Li2Oの現象)により、酸素活量が減少し、Fe3+/Fe2+比が減少した。またBaOとLi2Oはほぼ等価の役割を果たし、Fe3+/Fe2+の変化はほとんど無かった。
伯耆田 貴憲; 小田 哲三; 山本 洋一; 宮本 ユタカ; 安達 武雄
第21回核物質管理学会(INMM)日本支部年次大会論文集, p.17 - 24, 2000/00
日本原子力研究所では、国からの要請に基づき、包括的核実験禁止条約(CTBT)にかかわる国際検証制度の一環として、放射性核種に関する国内データセンター(NDC)の整備を行っている。NDCでは、全世界の放射性核種データをもとに条約検証のための解析を行うとともに、国際監視システム(IMS)の制御やネットワークの評価などを行う。この論文では、原研NDCにおける設計仕様、役割及び放射性核種データの解析の流れについて述べる。