Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
沖田 将一朗; 水田 直紀; 高松 邦吉; 後藤 実; 吉田 克己*; 西村 洋亮*; 岡本 孝司*
Proceedings of 30th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE30) (Internet), 10 Pages, 2023/05
Adoption of SiC-matrix fuel elements in future pin-in-block type HTGR designs will enhance oxidation resistance of the fuel element in the event of the air ingress accident, one of the most worrisome accidents in HTGRs. This would eliminate the need for the graphite sleeves used in the current pin-in-block type HTGR designs and enable high power density core designs with sleeveless and direct coolable fuel structure. Such a concept itself has been suggested by Japan Atomic Energy Agency (JAEA) in the past. However, JAEA has not yet demonstrated the feasibility for a core design with the SiC-matrix fuel elements. The present work is intended to demonstrate the feasibility for a new core design upgraded from an existing conceptual core design, called HTR50S, with 50 MW thermal power and reactor outlet temperature of 750 C. The new core design uses SiC-matrix fuel elements and increases the reactor power density to 1.2 times higher than the original HTR50S design. The feasibility is determined by whether the core satisfies the target values in nuclear and thermal-hydraulic designs by performing burn-up calculation with the whole core model and fuel temperature calculations. The calculation results showed that the new core design satisfied these target values on the reactor shutdown margin, the temperature coefficient of reactivity, and the maximum fuel temperature during normal operation.
C. The new core design uses SiC-matrix fuel elements and increases the reactor power density to 1.2 times higher than the original HTR50S design. The feasibility is determined by whether the core satisfies the target values in nuclear and thermal-hydraulic designs by performing burn-up calculation with the whole core model and fuel temperature calculations. The calculation results showed that the new core design satisfied these target values on the reactor shutdown margin, the temperature coefficient of reactivity, and the maximum fuel temperature during normal operation.
森下 日出喜*; 吉田 稔*; 西村 昭彦; 松平 昌之*; 平山 義治*; 菅野 裕一*
保全学, 20(1), p.101 - 108, 2021/04
福島第一原子力発電所の廃止措置においては、遠隔計測技術とロボット技術の融合が不可欠である。損傷を受けた原子炉建屋の健全性を評価するために、現場にロボットにより地震計を設置する模擬試験を実施した。試験には、原子力機構の楢葉遠隔技術開発センターのロボット試験水槽を、原子炉格納容器に見立てて実施した。遠隔計測技術として、白山工業開発の光パルス干渉方式地震計を使用した。ロボット試験水槽の水位を5mから順次下げることで、振動特性の変化を記録した。試験では、偶然に起こった震度1の微小地震を計測することができた。水槽は微小振動の増幅体として振舞うことが判明した。水槽の揺れを表す物理モデルを考察することで、将来の廃止措置の現場適用の問題点を抽出した。
園田 哲*; 片山 一郎*; 和田 道治*; 飯村 秀紀; Sonnenschein, V.*; 飯村 俊*; 高峰 愛子*; Rosenbusch, M.*; 小島 隆夫*; Ahn, D. S.*; et al.
Progress of Theoretical and Experimental Physics (Internet), 2019(11), p.113D02_1 - 113D02_12, 2019/11
被引用回数:1 パーセンタイル:9.82(Physics, Multidisciplinary)理化学研究所の不安定核ビーム施設(RIBF)では、入射核破砕反応や核分裂で生成される多くの核種からインフライト分離装置(BigRIPS)を用いて実験対象の核種を分離している。しかるに、分離された残りの核反応生成物の中にも核構造から興味深い多くの不安定核が含まれている。これらをBigRIPSから取り出して研究することができれば、RIBFの有効利用につながる。そこで、BigRIPS内に設置したガスセル中で核反応生成物を停止させてレーザーでイオン化して引き出す装置(PALIS)を開発中である。開発の一環として、RIBFの Krビームの破砕反応により生成する
Krビームの破砕反応により生成する Se近傍の不安定核をガスセル中で停止させる実験を行なった。実験結果は破砕反応の模型計算の予測とよく一致し、ガスセル中での停止効率は約30%と評価された。この結果を基に、次のステップとして、停止した核反応生成物をガスセルから引き出すことを行う。
Se近傍の不安定核をガスセル中で停止させる実験を行なった。実験結果は破砕反応の模型計算の予測とよく一致し、ガスセル中での停止効率は約30%と評価された。この結果を基に、次のステップとして、停止した核反応生成物をガスセルから引き出すことを行う。
西村 昭彦; 吉田 稔*; 山田 知典; 荒川 了紀
Proceedings of International Topical Workshop on Fukushima Decommissioning Research (FDR 2019) (Internet), 3 Pages, 2019/05
原子力機構は楢葉遠隔技術研究開発センターにおいて、遠隔センシングロボット技術の開発を支援している。センターに設置されている水槽を模擬的な原子炉格納容器に見立てた。光ファイバ干渉方式の小型の地震振動計が使用された。特別設計されたロボットシステムが地震計ユニットの設置のために試験された。本試験では地面の振動を利用して、水槽の振動応答関数を明らかにする準備を行った。
渡辺 均; 中野 政尚; 藤田 博喜; 竹安 正則; 水谷 朋子; 磯崎 徳重; 森澤 正人; 永岡 美佳; 外間 智規; 横山 裕也; et al.
JAEA-Review 2014-042, 175 Pages, 2015/01
核燃料サイクル工学研究所では、「日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所再処理施設保安規定、第IV編 環境監視」に基づき、再処理施設周辺の環境放射線モニタリングを実施している。本報告書は、2013年4月から2014年3月までの間に実施した環境モニタリングの結果、及び大気、海洋への放射性物質の放出に起因する周辺公衆の線量算出結果について、取りまとめたものであり、2011年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故(以下、東電福島第一原発事故)の影響が多くの項目でみられた。なお、環境監視計画の概要、測定方法の概要、測定結果及びその経時変化、気象統計結果、放射性廃棄物の放出状況、東電福島第一原発事故の影響による平常の変動幅を外れた値の評価について付録として収録した。
住谷 秀一; 渡辺 均; 宮河 直人; 中野 政尚; 中田 陽; 藤田 博喜; 竹安 正則; 磯崎 徳重; 森澤 正人; 水谷 朋子; et al.
JAEA-Review 2013-056, 181 Pages, 2014/03
核燃料サイクル工学研究所では、「日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所再処理施設保安規定、第IV編 環境監視」に基づき、再処理施設周辺の環境放射線モニタリングを実施している。本報告書は、2012年4月から2013年3月までの間に実施した環境モニタリングの結果、及び大気、海洋への放射性物質の放出に起因する周辺公衆の線量算出結果について、取りまとめたものであり、2011年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故(以下、東電福島第一原発事故)の影響が多くの項目でみられた。なお、環境監視計画の概要、測定方法の概要、測定結果及びその経時変化、気象統計結果、放射性廃棄物の放出状況、東電福島第一原発事故の影響による平常の変動幅を外れた値の評価について付録として収録した。
河内 哲哉; 長谷川 登; 錦野 将元; 石野 雅彦; 今園 孝志; 大場 俊幸; 海堀 岳史; 岸本 牧; 越智 義浩; 田中 桃子; et al.
X-Ray Lasers 2010; Springer Proceedings in Physics, Vol.136, p.15 - 24, 2011/12
本講演では、原子力機構におけるレーザー駆動X線レーザーの光源開発及び利用研究に関する最新の成果を報告する。利用研究の対象は物質科学,レーザー加工,X線イメージング,生体細胞の放射線損傷等と多岐に渡っている。物質科学への応用に関しては、強誘電体の相転移直上での格子揺らぎの時間相関を初めて観測した。レーザー加工に関しては、短パルスレーザー照射時の試料表面電子融解現象をX線レーザー干渉計で観察した。軟X線回折イメージングに関しては、静止したサンプルの微細構造の観察結果とともに、将来的なポンププローブ観察への計画を紹介する。また、X線レーザーの集光性能を利用した細胞損傷効果の基礎実験では、DNAの2本鎖切断の観察結果とKeV領域のインコヒーレントX線照射の場合との比較を議論する。
柳衛 宏宣*; 熊田 博明*; 中村 剛実; 東 秀史*; 生嶋 一朗*; 森下 保幸*; 篠原 厚子*; 藤原 光輝*; 鈴木 実*; 櫻井 良憲*; et al.
Proceedings of 14th International Congress on Neutron Capture Therapy (ICNCT-14) (CD-ROM), p.157 - 160, 2010/10
In the treatment of hepatocellular carcinoma (HCC), only 30 % patients can be operated due to complication of liver cirrhosis or multiple intrahepatic tumours. Tumour cell destruction in BNCT is necessary to accumulate a sufficient quantity of  B atoms in tumour cells. In this study, we prepared BSH entrapped WOW emulsion by double emulsifying technique using iodized poppy-seed oil (IPSO), BSH and surfactant, for selective intra-arterial infusion to HCC, and performed the neutron dosimetry using CT scan imaging of HCC patient. The
B atoms in tumour cells. In this study, we prepared BSH entrapped WOW emulsion by double emulsifying technique using iodized poppy-seed oil (IPSO), BSH and surfactant, for selective intra-arterial infusion to HCC, and performed the neutron dosimetry using CT scan imaging of HCC patient. The  B concentrations in VX-2 tumour obtained by delivery with WOW emulsion was superior to those by conventional IPSO mix emulsion. In case of HCC, we performed the feasibility estimation of 3D construction of tumor according to the CT imaging of a patient with epithermal neutron mode at JRR-4. Normal liver biologically weighted dose is restricted to 4.9 Gy-Eq; the max., min. and mean tumour weighted dose are 43.1, 7.3, and 21.8 Gy-Eq, respectively, in 40 minutes irradiation. In this study, we show that
B concentrations in VX-2 tumour obtained by delivery with WOW emulsion was superior to those by conventional IPSO mix emulsion. In case of HCC, we performed the feasibility estimation of 3D construction of tumor according to the CT imaging of a patient with epithermal neutron mode at JRR-4. Normal liver biologically weighted dose is restricted to 4.9 Gy-Eq; the max., min. and mean tumour weighted dose are 43.1, 7.3, and 21.8 Gy-Eq, respectively, in 40 minutes irradiation. In this study, we show that  B entrapped WOW emulsion could be applied to novel intra-arterial boron delivery carrier for BNCT.
B entrapped WOW emulsion could be applied to novel intra-arterial boron delivery carrier for BNCT.
 -rays; Guineagrass and sorghum
-rays; Guineagrass and sorghum中川 仁*; 稲福 正史*; 草場 信*; 山口 博康*; 森下 敏和*; 森田 竜平*; 西村 実*; Hoeman, S.*; 横田 裕一郎; 長谷 純宏; et al.
JAEA-Review 2007-060, JAEA Takasaki Annual Report 2006, P. 72, 2008/03
アポミクシス四倍体ギニアグラス(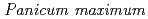 Jacq.)と二倍体有性ソルガム(
Jacq.)と二倍体有性ソルガム( (L.) Moench.)野種子に
(L.) Moench.)野種子に 線及び炭素イオンビームを照射し、突然変異体取得のための最適線量を決定するために、照射当代の発芽率,生存率並びに稔性を調べた。ギニアグラス(品種名ナツユタカ)の
線及び炭素イオンビームを照射し、突然変異体取得のための最適線量を決定するために、照射当代の発芽率,生存率並びに稔性を調べた。ギニアグラス(品種名ナツユタカ)の 線での50%致死線量は600から800Gy、炭素イオンビームでの50%致死線量は40から50Gyであると見積もられた。また、炭素イオンビームでの50%不稔線量は50から60Gyであった。ソルガム(品種名Zhengzu及びDurra)の
線での50%致死線量は600から800Gy、炭素イオンビームでの50%致死線量は40から50Gyであると見積もられた。また、炭素イオンビームでの50%不稔線量は50から60Gyであった。ソルガム(品種名Zhengzu及びDurra)の 線での50%致死線量は350から500Gy、炭素イオンビームでの50%致死線量は30から60Gyであると見積もられた。これらのデータは、アポミクシス遺伝子の影響解析のためのギニアグラス変異体作出及びバイオ燃料生産のためのソルガム変異体の作出に有用な知見を提供する。
線での50%致死線量は350から500Gy、炭素イオンビームでの50%致死線量は30から60Gyであると見積もられた。これらのデータは、アポミクシス遺伝子の影響解析のためのギニアグラス変異体作出及びバイオ燃料生産のためのソルガム変異体の作出に有用な知見を提供する。
 ray
ray森田 竜平*; 森下 敏和*; 中川 仁*; 西村 実*; 山口 博康*; 横田 裕一郎; 長谷 純宏; 田中 淳
JAEA-Review 2006-042, JAEA Takasaki Annual Report 2005, P. 78, 2007/02
イオンビームは新しい変異原としてさまざまな植物で利用されている。しかし、イオンビームで誘発される変異については、シロイヌナズナ以外の植物では情報が乏しい。本研究では、イネでイオンビーム照射により誘発される突然変異を明らかにし、 線と比較する目的で、イネのwaxy突然変異体をスクリーニングし、突然変異の解析を行った。炭素イオンビームと
線と比較する目的で、イネのwaxy突然変異体をスクリーニングし、突然変異の解析を行った。炭素イオンビームと 線を照射したイネ品種「日本晴」と「ひとめぼれ」について、玄米の外観とヨウ化カリウム染色を指標にして、waxy突然変異体を取得した。取得した突然変異体の変異の種類について、DNA配列解読とPCR増幅法で解析した結果、シロイヌナズナで報告されているような、炭素イオンビーム照射による点様突然変異とrearrangementがイネでも生じていることが明らかになった。
線を照射したイネ品種「日本晴」と「ひとめぼれ」について、玄米の外観とヨウ化カリウム染色を指標にして、waxy突然変異体を取得した。取得した突然変異体の変異の種類について、DNA配列解読とPCR増幅法で解析した結果、シロイヌナズナで報告されているような、炭素イオンビーム照射による点様突然変異とrearrangementがイネでも生じていることが明らかになった。
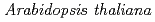 pollen with
pollen with  -rays and carbon ions
-rays and carbon ions内藤 健*; 草場 信*; 鹿園 直哉; 高野 敏弥*; 田中 淳; 谷坂 隆俊*; 西村 実*
Genetics, 169(2), p.881 - 889, 2005/02
被引用回数:116 パーセンタイル:88.65(Genetics & Heredity)放射線による突然変異の分子メカニズムを明らかにするため、シロイヌナズナの花粉に 線とイオンビームを照射し、それを交配することで後代における変異を追跡した。本実験系は、片親の花粉に照射することで、通常では致死になるような染色体異常も検出できる。分子マーカーを用いた欠失サイズの推定の結果、
線とイオンビームを照射し、それを交配することで後代における変異を追跡した。本実験系は、片親の花粉に照射することで、通常では致死になるような染色体異常も検出できる。分子マーカーを用いた欠失サイズの推定の結果、 線照射によるDNA変異の多くは2Mbにも及ぶ巨大な欠失であり、点様の突然変異は1割以下でしかなかった。このことは、
線照射によるDNA変異の多くは2Mbにも及ぶ巨大な欠失であり、点様の突然変異は1割以下でしかなかった。このことは、 線は点様変異誘発が多いという従来の考え方とは異なる結果である。LETが大きい炭素イオンビームにおいても2Mb以上の巨大な欠失が多く観察されたが、そのうち幾つかは致死にならない染色体異常が観察され、
線は点様変異誘発が多いという従来の考え方とは異なる結果である。LETが大きい炭素イオンビームにおいても2Mb以上の巨大な欠失が多く観察されたが、そのうち幾つかは致死にならない染色体異常が観察され、 線とイオンビームの差異を示唆するものかも知れず、今後のさらなる検討が待たれる。
線とイオンビームの差異を示唆するものかも知れず、今後のさらなる検討が待たれる。
上出 英樹; 林 謙二; 軍司 稔; 林田 均; 西村 元彦; 飯塚 透; 木村 暢之; 田中 正暁; 仲井 悟; 望月 弘保; et al.
PNC TN9410 96-279, 51 Pages, 1996/08
動力炉・核燃料開発事業団では「原子炉冷却系総合試験」として,高速炉の実用化を目指し,実証炉段階で採用される原子炉冷却系に係る新概念技術の確立を目的とし,原子炉容器から蒸気発生器までの1次,2次冷却系,水蒸気系,崩壊熱除去系を総合的に模擬した大型ナトリウム試験を計画している。実証炉の特徴であるトップエントリー配管システム,炉内冷却器を用い自然循環を積極的に活用した崩壊熱除去系,低温流体循環方式の炉容器壁保護系,一体貫流型蒸気発生器,再循環系を用いた崩壊熱除去運転などを含め配管短縮化,機器のコンパクト化,高信頼性崩壊熱除去システムなどについて熱流動上の課題,構造上の課題を設定し,それらを解決できる試験装置として特に原子炉容器ならびに1次冷却系の試験モデルの検討を行った。特に(1)実証炉の熱流動と構造上の課題に対する解決方策としての充足,(2)熱流動上の課題と構造上の課題のバランス,(3)総合試験として系統全体での複合現象,構成機器間の熱流動的および構造的相互作用の模擬を重視して,試験モデル候補概念の創出,予測解析を含む定量的な比較評価,モデルの選定を行った。さらに,選定モデル候補概念を元に,「原子炉冷却系総合試験」全体の試験装置概念を構築した。
 線の変異誘発効果の比較
線の変異誘発効果の比較森田 竜平*; 森下 敏和*; 中川 仁*; 西村 実*; 山口 博康*; 横田 裕一郎; 長谷 純宏; 田中 淳
no journal, ,
イオンビームは新しい変異原としてさまざまな植物で利用されている。しかし、イオンビームで誘発される変異については、シロイヌナズナ以外の植物では情報が乏しい。本研究では、イネでイオンビーム照射により誘発される突然変異を明らかにし、 線と比較する目的で、イネのwaxy突然変異体をスクリーニングし、突然変異の解析を行った。炭素イオンビームと
線と比較する目的で、イネのwaxy突然変異体をスクリーニングし、突然変異の解析を行った。炭素イオンビームと 線を照射したイネ品種「日本晴」と「ひとめぼれ」について、玄米の外観とヨウ化カリウム染色により、waxy突然変異体を得た。その結果、シロイヌナズナでは、炭素イオンビーム照射により点様突然変異とRearrangementの両方が生じることが報告されているが、イネでも同様の突然変異が生じることが明らかになった。
線を照射したイネ品種「日本晴」と「ひとめぼれ」について、玄米の外観とヨウ化カリウム染色により、waxy突然変異体を得た。その結果、シロイヌナズナでは、炭素イオンビーム照射により点様突然変異とRearrangementの両方が生じることが報告されているが、イネでも同様の突然変異が生じることが明らかになった。
西村 昭彦; 井出 次男*; 石原 信之*; 伊藤 稔*; 浦田 健勇*
no journal, ,
ピコ秒パルスレーザー精密加工により作製したFBGセンサーの産業展開として新たな共同研究の開始について報告する。原子力機構がFBGセンサー作製技術を移転したdeltafiber.jp社において、耐放射線性FBGセンサーを作製した。このセンサーは、原子燃料再処理工場の人材育成を手掛ける株式会社ジェイテックが所有する研修施設の水撃効果実証およびマニピュレーター用J-CUPIDに設置された。
 線によるイネ胚乳突然変異の誘発
線によるイネ胚乳突然変異の誘発西村 実*; 森田 竜平*; 山口 博康*; 長谷 純宏
no journal, ,
イオンビームが新しい突然変異原として期待されているが、イネ等の主要作物において実用的な形質に関する突然変異率について、 線のような従来からの突然変異原との比較を大規模に実施した報告は未だにない。今回、イネを材料にして、イオンビームと
線のような従来からの突然変異原との比較を大規模に実施した報告は未だにない。今回、イネを材料にして、イオンビームと 線の突然変異系統M2世代において胚乳突然変異率を調査した結果とともにイオンビーム照射で得られた胚乳蛋白質組成変異体について報告する。イオンビーム及び
線の突然変異系統M2世代において胚乳突然変異率を調査した結果とともにイオンビーム照射で得られた胚乳蛋白質組成変異体について報告する。イオンビーム及び 線の総線量の違いによる胚乳の突然変異率に大きな差が認められないことから、各変異原の総線量をこみにして評価した。突然変異率に関して品種間差は明瞭ではないと考えられた。変異原別の突然変異率は、He100
線の総線量の違いによる胚乳の突然変異率に大きな差が認められないことから、各変異原の総線量をこみにして評価した。突然変異率に関して品種間差は明瞭ではないと考えられた。変異原別の突然変異率は、He100
 線
線 C220
C220 C320の順番となった。ひとめぼれのイオンビーム照射突然変異系統から26kDaグロブリンと16kDaプロラミンが減少するタイプと、グルテリン,26kDaグロブリン,16及び13kDaプロラミンが減少し、57kDaグルテリン前駆体がやや増加するタイプの2系統の変異体を見いだしたが、これらはいずれもすでに報告されているものであった。以上のように、イオンビーム照射により誘発される胚乳突然変異体はその出現率やスペクトラムにおいて
C320の順番となった。ひとめぼれのイオンビーム照射突然変異系統から26kDaグロブリンと16kDaプロラミンが減少するタイプと、グルテリン,26kDaグロブリン,16及び13kDaプロラミンが減少し、57kDaグルテリン前駆体がやや増加するタイプの2系統の変異体を見いだしたが、これらはいずれもすでに報告されているものであった。以上のように、イオンビーム照射により誘発される胚乳突然変異体はその出現率やスペクトラムにおいて 線に比べてあまり差がないことが明らかになった。
線に比べてあまり差がないことが明らかになった。
西村 昭彦; 金井 昭夫*; 吉田 稔*
no journal, ,
令和3年度以降、福島第一原子力発電所の2号機格納容器内より、核燃料デブリの取り出しが計画されている。この作業の進展が見通せるまで、1号機と3号機は現状のままで長期安定化措置を施す必要がある。令和元年から令和2年12月末にかけて、英知事業国際協力型廃炉研究プログラムが実施され、炉内に流入する地下水由来の微生物を特定する日露共同研究が開始された。さらに東京大学による連携重点研究として、異なる分野の専門家が知恵を出し合い、長期化する廃止措置の潜在的リスク要因を低下できる具体的な手法を提案する。連携重点研究開始の令和2年度は、8つの研究テーマの内、検討開始となった2テーマについて進捗を報告する。なお、炉内を模擬する自然環境として、閉山となったウラン鉱山を用いる。
西村 昭彦; 金井 昭夫*; 吉田 稔*
no journal, ,
福島第一原子力発電所の廃止措置に関して、文部科学省より英知事業の推進が進められている。原子力機構の福島研究開発部門廃炉環境国際共同研究センターは本事業の取りまとめと連携協力を行っている。2019年に国際協力の推進として日露共研分野において、研究テーマ「微生物生態系による原子炉内物体の腐食・変質に関する評価研究」が採択され、2020年12月末まで実施される。ここでは、炉内に流入する地下水に含まれる微生物が、原子炉構造体の劣化・腐食の促進の一因となる可能性の有無を明らかとする。この研究テーマの発展として、連携重点研究として令和2年度より3年間、研究テーマ「廃止措置のリスク要因低下手法に関する研究」が採択された。ここでも、日露の国際協力の推進の一助を実施する。発表では、連携重点研究として実施する小テーマ8課題を紹介する。併せて、微生物腐食の抑制方法についての提案を行う。
 線における変異誘発効果の比較; ギニアグラスとソルガム
線における変異誘発効果の比較; ギニアグラスとソルガム中川 仁*; 稲福 正史*; 草場 信*; 山口 博康*; 森下 敏和*; 森田 竜平*; 西村 実*; Hoeman, S.*; 横田 裕一郎; 長谷 純宏; et al.
no journal, ,
熱帯イネ科作物・牧草類の生殖様式は多様であり、これらが複雑に関係した多くの種が存在する。このため、特に栄養繁殖やアポミクシス種に関しては突然変異育種が試みられた。ギニアグラスはアポミクシス熱帯牧草種であり、二倍体系統を染色体倍加した四倍体有性生殖中間母本「熱研1号(農1号)」が育成され、四倍体アポミクシス系統との交配技術が確立された。交配によるアポミクシスの連鎖解析が行われたが、その領域はクラスター状でかなり大きいことが示唆され、放射線照射による関連遺伝子領域の破壊による解析が期待されている。一方、ソルガムは熱帯アフリカで栽培化され、アフリカ全域,インド,中国や日本に広がった、稲,麦,トウモロコシ,大麦に次ぐ五大穀物の一つである。我が国ではおもに南九州において飼料用として広く栽培されており、現在、バイオマス作物として新たな育種が期待されている。ここでは、この両種を用いて行った 線照射と炭素イオンビーム照射による生存率等の照射当代に現れた差について報告する。
線照射と炭素イオンビーム照射による生存率等の照射当代に現れた差について報告する。
錦野 将元; 越智 義浩; 長谷川 登; 河内 哲哉; 石野 雅彦; 今園 孝志; 田中 桃子; 佐藤 克俊; 山本 稔; 大場 俊幸; et al.
no journal, ,
レーザープラズマX線レーザーとその応用研究に関して講演を行う。X線レーザー開発においては、出力10J 0.1Hz繰り返しのガラスレーザーを用いて、波長13.9nmの空間フルコヒーレント軟X線レーザーの開発を行った。この高輝度,空間コヒーレント・ピコ秒パルス幅を持つX線レーザーを用いることにより、X線スペックル計測,X線干渉計測,X線回折イメージング,ナノサイズ構造の生成等のさまざまな応用研究を展開している。現在、これらの応用研究のために新しいX線レーザーの応用研究用ビームラインの開発を行っている。X線レーザーによる固体表面のアブレーション研究やチタン酸バリウムの表面のX線スペックル計測、ロイズミラーを用いたX線レーザー干渉計の開発等の応用研究結果について述べる。
0.1Hz繰り返しのガラスレーザーを用いて、波長13.9nmの空間フルコヒーレント軟X線レーザーの開発を行った。この高輝度,空間コヒーレント・ピコ秒パルス幅を持つX線レーザーを用いることにより、X線スペックル計測,X線干渉計測,X線回折イメージング,ナノサイズ構造の生成等のさまざまな応用研究を展開している。現在、これらの応用研究のために新しいX線レーザーの応用研究用ビームラインの開発を行っている。X線レーザーによる固体表面のアブレーション研究やチタン酸バリウムの表面のX線スペックル計測、ロイズミラーを用いたX線レーザー干渉計の開発等の応用研究結果について述べる。
西村 昭彦; 森下 日出喜*; 山田 知典; 吉田 稔*; 田川 明広
no journal, ,
福島第一原子力発電所の廃止措置のため、光ファイバ方式の地震計を特殊設計のロボットを使用して設置を行うデモンストレーションを実施した。使用した水タンクは4.5メートル直径で5メートル水深があり、これをタンク型臨界試験装置に見立てた。実験中に起こった微小地震を光ファイバ地震計が捉えた。また、水タンクの観測窓の振動特性をレーザードップラー干渉計で捉えることにも成功した。