Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
田村 由起子*; 荒川 勝利*; 竹中 幹人*; 中西 洋平*; 藤波 想*; 柴田 基樹*; 山本 勝宏*; 宮田 登*; 山田 雅子*; 瀬戸 秀紀*; et al.
Polymer, 333, p.128662_1 - 128662_8, 2025/08
To investigate the relationship between the mechanical properties of silica-filled styrene-butadiene rubber (SBR) and the amount of bound rubber at the filler/rubber interface, the polymer matrix was extracted from silica-filled SBR using toluene at room temperature. In this study, this extraction process was reproduced by leaching a thermally annealed SBR layer deposited on a Si substrate in toluene at room temperature, where the adsorption layer of the SBR was grown at the interface with the substrate by thermal annealing. The SBR adsorption layer on the Si substrate has two-layer structures consisting of an inner and outer adsorption layers, which correspond to the tightly and loosely bound rubbers on the filler surface of the silica-filled SBR, respectively. For the sample annealed for less than 6 h, the outer adsorption layer, loosely bound to the substrate, was easily leached in toluene for 5 min, leaving only the inner adsorption layer on the substrate. For the samples annealed for more than 24 h, a large portion of the outer adsorption layer remained on top of the inner adsorption layer as a terrace structure. However, even for the sample annealed for 24 h, treating with toluene for 24 h completely leached the outer adsorption layer from the inner adsorption layer, although the inner adsorption layer remained on the substrate. It was found that the loosely bound rubber in the silica-filled SBR could be easily extracted from the filler surface, along with the free polymer chains in the polymer matrix during extraction with toluene at room temperature. In contrast, the tightly bound rubber was not leached by toluene at room temperature. This may be because the interfacial polymer chains within approximately 1 nm of the substrate surface were strongly constrained to the substrate, and even toluene molecules were excluded.

山内 宏樹; 目時 直人; 綿貫 竜太*; Hong, T.*; Fernandez-Baca, J. A.*; 萩原 雅人; 益田 隆嗣*; 吉沢 英樹*; 伊藤 晋一*
Journal of the Physical Society of Japan, 94(5), p.054705_1 - 054705_8, 2025/04
The  -electron states of NdB
-electron states of NdB were determined by observing crystalline electric field (CEF) excitations with inelastic neutron scattering experiments. Our analysis yields CEF excitation energies of 2.8, 12.4, 17.2, and 25.4 meV. The
were determined by observing crystalline electric field (CEF) excitations with inelastic neutron scattering experiments. Our analysis yields CEF excitation energies of 2.8, 12.4, 17.2, and 25.4 meV. The  -electron states are simply described by one of
-electron states are simply described by one of  -multiplets
-multiplets  with negligibly small mixing. The ground state is the pseudo-quartet consist of the ground doublet dominated by
with negligibly small mixing. The ground state is the pseudo-quartet consist of the ground doublet dominated by  and the first excited doublet dominated by
and the first excited doublet dominated by  at 2.8 meV, which is consistent with magnetic specific heat and entropy reported in earlier study. The simple
at 2.8 meV, which is consistent with magnetic specific heat and entropy reported in earlier study. The simple  -electron states in NdB
-electron states in NdB are the consequence of the strong uniaxial and in-plane isotropic CEF potential due to the local structure of Nd
are the consequence of the strong uniaxial and in-plane isotropic CEF potential due to the local structure of Nd ions with point symmetry
ions with point symmetry  .
.
谷口 拓海; 松本 早織; 平木 義久; 佐藤 淳也; 藤田 英樹*; 金田 由久*; 黒木 亮一郎; 大杉 武史
JAEA-Review 2024-059, 20 Pages, 2025/03
廃棄物のセメント固化で求められる基本的な性能である硬化前の流動性および硬化後の強度特性は、廃棄物に含まれる物質や成分などの化学的作用の影響を受けることが予想される。硬化前の流動性および硬化後の強度特性はセメントの硬化速度に大きく影響されることから、セメントの硬化速度に影響を与える化学物質を対象に着目して既往の知見を調査し、取りまとめを行った。本報告書ではセメントの流動性に影響を及ぼす化学物質を大きく分類し、無機物質として(1)陰イオン種、(2)重金属等金属元素、(3)セメント混和剤として用いられる無機物質および(4)セメント混和剤として用いられる有機物質の4つに整理した。調査の結果、化学物質によって硬化を促進する効果と遅延する効果に大きく分類されることが分かったが、一部の化学物質ではその添加量によって硬化に与える影響が逆転するものも見られたことから、実際に化学物質を添加し、凝結時間測定を実施した。その結果、硬化促進に寄与するメカニズムが複数あることが分かった。セメントの硬化反応を阻害する化学物質を調査し、セメント固化における混入禁忌成分を検討するための情報を整理することができた。
國分 祐司; 細見 健二; 瀬谷 夏美; 永岡 美佳; 井上 和美; 小池 優子; 長谷川 涼; 久保田 智大; 平尾 萌; 飯澤 将伍; et al.
JAEA-Review 2024-053, 116 Pages, 2025/03
本報告書は、原子力規制関係法令を受けた「再処理施設保安規定」、「核燃料物質使用施設保安規定」、「放射線障害予防規程」、「放射線保安規則」及び茨城県等との「原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書」、「水質汚濁防止法」並びに「茨城県条例」に基づき、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所から環境へ放出した放射性排水の放出管理結果を取りまとめたものである。再処理施設、プルトニウム燃料開発施設をはじめとする各施設からの放射性液体廃棄物は、濃度及び放出量ともに保安規定及び協定書等に定められた基準値を十分に下回った。
川崎 卓郎; 福田 竜生; 山中 暁*; 村山 一郎*; 加藤 孝典*; 馬場 将亮*; 橋本 英樹*; Harjo, S.; 相澤 一也; 田中 裕久*; et al.
Journal of Applied Physics, 137(9), p.094101_1 - 094101_7, 2025/03
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Physics, Applied)Energy harvesting from waste heat can improve energy efficiency in society. This research investigated the structural behaviors of lead zirconate titanate-based ferroelectric ceramics using operando neutron diffraction measurements under the conditions of two energy-harvesting cycles that involve consideration of the temperature changes of automobile exhaust gas for achieving good harvesting efficiencies. Input and output electrical energies and neutron diffraction data were simultaneously collected. The obtained time-resolved neutron-diffraction intensity data indicate that the applied electric fields and temperature changes induced 90 domain rotation and lattice strain. These structural changes and their variations depending on cycle conditions, such as temperature changes, applied electric fields, and circuit switching, provide insight into the origins of the differences in the behaviors of electrical input/output energies in the cycles.
domain rotation and lattice strain. These structural changes and their variations depending on cycle conditions, such as temperature changes, applied electric fields, and circuit switching, provide insight into the origins of the differences in the behaviors of electrical input/output energies in the cycles.
勅使河原 誠; Lee, Y.*; 達本 衡輝*; Hartl, M.*; 麻生 智一; Iverson, E. B.*; 有吉 玄; 池田 裕二郎*; 長谷川 巧*
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 557, p.165534_1 - 165534_10, 2024/12
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Instruments & Instrumentation)J-PARCの核破砕中性子源において、水酸化第二鉄触媒の機能性を評価するため、1MW運転時の積算ビーム出力9.4MW hの条件で、ラマン分光法を用いてパラ水素割合をその場測定した。その結果、1MW運転におけて触媒が十分に機能していることが分かった。また、触媒を通さないバイパスラインを用いて、中性子照射によるパラからオルソ水素への逆変換率を調べることを試みた。測定されたオルソ水素割合の増加は、500kW運転で積算ビーム出力2.4MW
hの条件で、ラマン分光法を用いてパラ水素割合をその場測定した。その結果、1MW運転におけて触媒が十分に機能していることが分かった。また、触媒を通さないバイパスラインを用いて、中性子照射によるパラからオルソ水素への逆変換率を調べることを試みた。測定されたオルソ水素割合の増加は、500kW運転で積算ビーム出力2.4MW hの場合に0.44%であった。しかしながら、この結果は、冷中性子モデレータ内で引き起こされた逆変換と、バイパスされた触媒容器中の温度上昇によって発生した準静的オルソ水素のメインループへの受動的滲出との合算であることが示された。
hの場合に0.44%であった。しかしながら、この結果は、冷中性子モデレータ内で引き起こされた逆変換と、バイパスされた触媒容器中の温度上昇によって発生した準静的オルソ水素のメインループへの受動的滲出との合算であることが示された。
小手川 恒*; 中村 彰良*; Huyen, V. T. N.*; 新井 祐樹*; 藤 秀樹*; 菅原 仁*; 林 純一*; 武田 圭生*; 田端 千紘; 金子 耕士; et al.
Physical Review B, 110(21), p.214417_1 - 214417_8, 2024/12
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Materials Science, Multidisciplinary)In this study, we show that the orthorhombic system TaMnP exhibits a large anomalous Hall conductivity (AHC) in spite of the small net magnetization. Neutron scattering experiment and the observation of the AH effect comprehensively suggest a dominant AF structure in TaMnP is represented by  . The AHC is one of the largest among those observed in AF materials at zero fields. First-principles calculations suggest that the spin-orbit interaction originating in nonmagnetic Ta-5
. The AHC is one of the largest among those observed in AF materials at zero fields. First-principles calculations suggest that the spin-orbit interaction originating in nonmagnetic Ta-5 electrons significantly contributes to the enhancement of Berry curvatures in the momentum space. We found that the AF domain switching is triggered by the magnetic fields along all the crystal axes. This indicates that the AF domain determining the sign of the Hall response can be controlled even through the small net magnetization symmetrically different.
electrons significantly contributes to the enhancement of Berry curvatures in the momentum space. We found that the AF domain switching is triggered by the magnetic fields along all the crystal axes. This indicates that the AF domain determining the sign of the Hall response can be controlled even through the small net magnetization symmetrically different.
山本 勝宏*; 今井 達也*; 河合 純希*; 伊藤 恵利*; 宮崎 司*; 宮田 登*; 山田 悟史*; 瀬戸 秀紀*; 青木 裕之
ACS Applied Materials & Interfaces, 16(48), p.66782 - 66791, 2024/11
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Nanoscience & Nanotechnology)In this study, a silicon-based copolymer, poly(tris(trimethylsiloxy)-3-methacryloxypropylsilane)-co-poly(N,N-dimethyl acrylamide), thin film was subjected to plasma surface treatment to make its surface hydrophilic (biocompatible). Neutron reflectivity (NR) measurement of the plasma-treated thin film showed a decrease in the film thickness (etching width: similar to 20 nm) and an increase in the scattering length density (SLD) near the surface (similar to 15 nm). The region with a considerably high SLD adsorbed water (D O) from its saturated vapor, indicating its superior surface hydrophilicity. Nevertheless of the hydrophilicity, the swelling of the thin film was suppressed. Hard X-ray photoelectron spectroscopy (HAXPES) performed at various takeoff angles revealed that the thin-film surface (similar to 20 nm depth) underwent extensive oxidation. NR and HAXPES analysis quantitatively yielded the depth profiling of elemental compositions in a few tens of nm scale. Si oxidation and hydrogen elimination (probably CH
O) from its saturated vapor, indicating its superior surface hydrophilicity. Nevertheless of the hydrophilicity, the swelling of the thin film was suppressed. Hard X-ray photoelectron spectroscopy (HAXPES) performed at various takeoff angles revealed that the thin-film surface (similar to 20 nm depth) underwent extensive oxidation. NR and HAXPES analysis quantitatively yielded the depth profiling of elemental compositions in a few tens of nm scale. Si oxidation and hydrogen elimination (probably CH groups) in the vicinity of the surface region increased the SLD and decreased the hydrophobicity. A combination of Soft X-ray photoelectron spectroscopy and NR measurements revealed the surface chemical composition and mass density. It was considered that the surface near the film was chemically composed close to SiO
groups) in the vicinity of the surface region increased the SLD and decreased the hydrophobicity. A combination of Soft X-ray photoelectron spectroscopy and NR measurements revealed the surface chemical composition and mass density. It was considered that the surface near the film was chemically composed close to SiO , forming a gel-like (three-dimensional network) structure that is hydrophilic and suppresses swelling due to moisture, indicating it can be expected to maintain stable hydrophilicity on the film surface.
, forming a gel-like (three-dimensional network) structure that is hydrophilic and suppresses swelling due to moisture, indicating it can be expected to maintain stable hydrophilicity on the film surface.
宮崎 司*; 宮田 登*; 有馬 寛*; 下北 啓輔*; 山本 勝宏*; 竹中 幹人*; 中西 洋平*; 柴田 基樹*; 青木 裕之; 山田 悟史*; et al.
Colloids and Surfaces A; Physicochemical and Engineering Aspects, 701, p.134928_1 - 134928_8, 2024/11
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Chemistry, Physical)Isotactic polypropylene (PP) thin films deposited on Si substrates were subjected to neutron reflectivity (NR) measurements under various humidity conditions to evaluate the isothermal adsorption of water accumulated between the PP layer and Si substrate, with focus on the temperature-dependence of the adsorption isotherm. The adsorption of accumulated water followed a single type II isotherm according to the Brunauer-Emmett-Teller (BET) classification, regardless of temperature. This can be attributed to the weak interactions between the PP layer and Si substrate, and between the PP layer and water molecules. Hydrophobic PP does not significantly interact with water molecules and the hydrophilic Si surface. Therefore, the interfacial water molecules are simply adsorbed on the native oxide layer on Si via simple interaction between the water molecules and the silicon oxide surface without being affected by the PP layer. Consequently, the adsorption isotherm of the accumulated water follows the single type II adsorption isotherm regardless of temperature, similar to the adsorption isotherm of water simply adsorbed on exposed silica surfaces. These weak interactions of the PP layer with the Si surface and water molecules also lead to fast diffusion kinetics for the accumulated water along the interface.
 -ray fields
-ray fields冠城 雅晃; 鎌田 圭*; 石井 隼也*; 松本 哲郎*; 真鍋 征也*; 増田 明彦*; 原野 英樹*; 加藤 昌弘*; 島添 健次*
Journal of Instrumentation (Internet), 19(11), p.P11019_1 - P11019_16, 2024/11
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Instruments & Instrumentation)A new LiCAF:Ce detector with an ultra-thick (99  m) crystal and optimized readout was developed. The LiCAF:Ce and KG2 detectors were used to detect a sealed Cf-252 neutron source (neutron emission rate of ~
m) crystal and optimized readout was developed. The LiCAF:Ce and KG2 detectors were used to detect a sealed Cf-252 neutron source (neutron emission rate of ~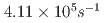 ) using a 5 cm thick high-density polyethylene (HDPE) block located at the front of the detector. At the air kerma rates at the front surface of the HDPE block (
) using a 5 cm thick high-density polyethylene (HDPE) block located at the front of the detector. At the air kerma rates at the front surface of the HDPE block ( ) of up to 1.07 Gy/h, the effective neutron count rate (
) of up to 1.07 Gy/h, the effective neutron count rate ( ) for the LiCAF:Ce detector was the same within margins of errors, but it decreased by 5.7
) for the LiCAF:Ce detector was the same within margins of errors, but it decreased by 5.7  0.8% at 2.97 Gy/h. In contrast, for the KG2 detector, with
0.8% at 2.97 Gy/h. In contrast, for the KG2 detector, with  increased up to 1.07 Gy/h,
increased up to 1.07 Gy/h,  for KG2 increased up to 20
for KG2 increased up to 20  1.0 % at 1.07 Gy/h. Then,
1.0 % at 1.07 Gy/h. Then,  decreased by 20
decreased by 20  1.0% at 2.97 Gy/h. Therefore, the LiCAF:Ce detector exhibited a smaller influence on neutron count rates by
1.0% at 2.97 Gy/h. Therefore, the LiCAF:Ce detector exhibited a smaller influence on neutron count rates by  -rays compared to the KG2 detector because of the faster decay time and optimization of digital pulse processing.
-rays compared to the KG2 detector because of the faster decay time and optimization of digital pulse processing.

 絶縁体Sr
絶縁体Sr OsO
OsO のX線磁気円二色性測定
のX線磁気円二色性測定若林 勇希*; Krockenberger, Y.*; 山神 光平*; 和達 大樹*; 芝田 悟朗; 藤森 淳*; 河村 直己*; 鈴木 基寛*; 谷保 芳孝*; 山本 秀樹*
SPring-8/SACLA利用研究成果集(インターネット), 12(5), p.291 - 293, 2024/10
本研究では、高温強磁性酸化物Sr OsO
OsO の電子状態を明らかにすることを目的として、Os
の電子状態を明らかにすることを目的として、Os  吸収端におけるX線吸収分光(XAS)及びX線磁気円二色性(XMCD)測定を行った。実験結果から、Osの軌道磁気モーメントがスピン磁気モーメントと同程度のオーダーであることが明らかになった。しかし、XMCD総和則による推定では、軌道磁気モーメントはSQUID磁化測定の値よりもかなり小さかった。今後の課題としては、SrやOの吸収端でのXMCD測定による磁気モーメントの観測や、サンプルの経時変化を低減させるための対策が挙げられる。
吸収端におけるX線吸収分光(XAS)及びX線磁気円二色性(XMCD)測定を行った。実験結果から、Osの軌道磁気モーメントがスピン磁気モーメントと同程度のオーダーであることが明らかになった。しかし、XMCD総和則による推定では、軌道磁気モーメントはSQUID磁化測定の値よりもかなり小さかった。今後の課題としては、SrやOの吸収端でのXMCD測定による磁気モーメントの観測や、サンプルの経時変化を低減させるための対策が挙げられる。
下北 啓輔*; 山本 勝宏*; 宮田 登*; 柴田 基樹*; 中西 洋平*; 荒川 勝利*; 竹中 幹人*; 木田 拓充*; 徳満 勝久*; 田中 亮*; et al.
Langmuir, 40(30), p.15758 - 15766, 2024/07
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Chemistry, Multidisciplinary)To investigate the structure of the interface between polyethylene films and substrates, the neutron reflectivity (NR) of deuterated polyethylene (dPE) thin films deposited on Si substrates was measured, demonstrating water accumulation at the interface, even under ambient conditions. After leaching the thermally annealed dPE films in hot p-xylene, NR measurements were conducted on the layers remaining on the substrate, clearly revealing that the adsorption layer of dPE grew during annealing and consisted of two layers, an inner adsorption layer and an outer adsorption layer, as previously proposed for amorphous polymers. The inner adsorption layer was approximately 3.7 nm thick with a density comparable to that of the bulk. The outer adsorption layer was several nanometers thick and appeared to grow insufficiently on top of the inner adsorption layer under the annealing conditions examined in this study. This study clarifying the growth of the adsorption layer of polyethylene at the interface with an inorganic substrate is useful for improving the performance of polymer/inorganic filler nanocomposites due to the wide utility of crystalline polyolefins as polymer matrix materials in nanocomposites.
國分 祐司; 中田 陽; 瀬谷 夏美; 永岡 美佳; 小池 優子; 久保田 智大; 平尾 萌; 吉井 秀樹*; 大谷 和義*; 檜山 佳典*; et al.
JAEA-Review 2023-052, 118 Pages, 2024/03
本報告書は、原子力規制関係法令を受けた「再処理施設保安規定」、「核燃料物質使用施設保安規定」、「放射線障害予防規程」、「放射線保安規則」及び茨城県等との「原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書」、「水質汚濁防止法」並びに「茨城県条例」に基づき、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所から環境へ放出した放射性排水の放出管理結果をとりまとめたものである。再処理施設、プルトニウム燃料開発施設をはじめとする各施設からの放射性液体廃棄物は、濃度及び放出量ともに保安規定及び協定書等に定められた基準値を十分に下回った。
辻 勇人*; 中畑 雅樹*; 菱田 真史*; 瀬戸 秀紀*; 元川 竜平; 井上 大傑*; 江川 泰暢*
Journal of Physical Chemistry Letters (Internet), 14(49), p.11235 - 11241, 2023/12
被引用回数:6 パーセンタイル:63.96(Chemistry, Physical)This work investigates the water-fraction dependence of the aggregation behavior of hydrophobic solutes in water-tetrahydrofuran (THF) and the elucidation of the role of THF using fluorescence microscopy, dynamic light scattering, neutron and X-ray scattering, as well as photoluminescence measurements. Based on the obtained results, the following model is proposed: hydrophobic molecules are molecularly dispersed in the low-water-content region (10-20 vol %), while they form mesoscopic particles upon increasing the water fraction to  30 vol percent. This abrupt change is due to the composition fluctuation of the water-THF binary system to form hydrophobic areas in THF, followed by THF-rich droplets where hydrophobic solutes are incorporated and form loose aggregates. Further increasing the water content prompts the desolvation of THF, which decreases the particle size and generates tight aggregates of solute molecules. This model is consistent with the luminescence behavior of the solutes and will be helpful to control the aggregation state of hydrophobic solutes in various applications.
30 vol percent. This abrupt change is due to the composition fluctuation of the water-THF binary system to form hydrophobic areas in THF, followed by THF-rich droplets where hydrophobic solutes are incorporated and form loose aggregates. Further increasing the water content prompts the desolvation of THF, which decreases the particle size and generates tight aggregates of solute molecules. This model is consistent with the luminescence behavior of the solutes and will be helpful to control the aggregation state of hydrophobic solutes in various applications.
 Ti
Ti O
O single crystals
single crystals高濱 隆成*; 有薗 実駿*; 犬童 代梧*; 吉永 汰正*; 寺倉 千恵子*; 竹下 直*; 白崎 巧*; 野田 正亮*; 桑原 英樹*; 梶本 亮一; et al.
JPS Conference Proceedings (Internet), 38, p.011114_1 - 011114_6, 2023/05
We investigated the transport and magnetic properties of single crystals of the pseudobrookite Al Ti
Ti O
O for
for  grown using a floating zone. We found a correlation of spin-singlet Ti
grown using a floating zone. We found a correlation of spin-singlet Ti -Ti
-Ti dimers even in the conductive
dimers even in the conductive  and
and  phases which develops with increasing
phases which develops with increasing  . The development of the dimer correlation suppresses the magnetic susceptibility at the low temperature and enhances the electric conductivity perhaps due to the suppression of the magnetic scattering at the isolated Ti
. The development of the dimer correlation suppresses the magnetic susceptibility at the low temperature and enhances the electric conductivity perhaps due to the suppression of the magnetic scattering at the isolated Ti ions. The compound shows the best conductivity in the
ions. The compound shows the best conductivity in the  phase near the phase boundary between the
phase near the phase boundary between the  and
and  phases where the dimer correlation is much developed. Some exotic conductive state may be realized under the background of fluctuation of the spin-singlet dimer in the
phases where the dimer correlation is much developed. Some exotic conductive state may be realized under the background of fluctuation of the spin-singlet dimer in the  phase near the phase boudary.
phase near the phase boudary.
神谷 潤一郎; 仁井 啓介*; 株本 裕史; 近藤 恭弘; 田村 潤; 原田 寛之; 松井 泰; 松田 誠; 守屋 克洋; 井田 義明*; et al.
e-Journal of Surface Science and Nanotechnology (Internet), 21(4), p.344 - 349, 2023/05
原子力機構東海タンデム加速器には、40台の超伝導Quarter Wave Resonator(QWR)によって重イオンを10MeV/uまで加速するブースターリニアックがあるが、2011年の震災以降、運転を停止している。近年ウラン等のより重い核種を加速するため、タンデム加速器のアップグレードが精力的に検討され、QWR再稼働の必要性が高まっている。現在、運転時に必要な加速電圧とQ値を得るため、QWR内面荒さを低減するための電解研磨条件を検証している。一方で電解研磨はNb中水素を増加させ、水素病と呼ばれるQ値の減少を引き起こす可能性がある。真空中高温焼鈍で水素を放出させることで水素病を抑えることができるが、QWRのクラッド材を構成するNbとCuの熱膨張差による空洞破損の危険性がある。そのため表面粗さの低減とNbバルク中の水素の増加を最小限に抑えるため、研磨条件を最適化する必要がある。我々はこれまで水素吸蔵量および脱離機構を昇温脱離分析(TDS)により検証できることに着目し、研究を行ってきた。発表では異なる条件で研磨したNb材料のTDS結果、表面観察結果、表面粗さの相関について得られた成果を発表する。
横山 須美*; 浜田 信之*; 辻村 憲雄; 欅田 尚樹*; 西田 一隆*; 江崎 巌*; 加藤 昌弘*; 大久保 秀輝*
International Journal of Radiation Biology, 99(4), p.604 - 619, 2023/04
被引用回数:3 パーセンタイル:27.44(Biology)2011年4月、国際放射線防護委員会は、水晶体の職業被ばく限度の引き下げを勧告した。この新しい水晶体線量限度は、これまで多くの国で取り入れられており、また他の国でも規制実施に向けた議論が盛んに行われている。日本では、2013年4月に日本保健物理学会(JHPS)、2017年7月に放射線審議会で議論が開始され、2021年4月に新しい水晶体線量限度が規制実施されることになった。その経験を共有するために、日本での状況をまとめた論文を、2017年初頭までに入手可能な情報に基づく第1論文、2019年初頭までに第2論文と、順次発表してきた。本稿(シリーズ3回目)では、新たな水晶体線量限度の規制実施、審議会の意見を踏まえた関係省庁の最近の議論、安全衛生管理体制の構築過程、水晶体線量モニタリングと放射線安全に関するJHPSガイドライン、認可事業者の自主対策、水晶体線量校正方法の開発、原子力作業者の水晶体被ばくと水晶体への生物影響に関する最近の研究など、2022年半ばまでに入手できる最新の情報に関して検討することを目的とするものである。
下北 啓輔*; 山本 勝宏*; 宮田 登*; 中西 洋平*; 柴田 基樹*; 竹中 幹人*; 山田 悟史*; 瀬戸 秀紀*; 青木 裕之; 宮崎 司*
Soft Matter, 19(11), p.2082 - 2089, 2023/03
被引用回数:3 パーセンタイル:52.54(Chemistry, Physical)In the case of poly(methyl methacrylate) (PMMA) thin films on a Si substrate, thermal annealing induces the formation of a layer of PMMA chains tightly adsorbed near the substrate interface, and the strongly adsorbed PMMA remains on the substrate, even after washing with toluene (hereinafter called adsorbed sample). Neutron reflectometry revealed that the concerned structure consists of three layers: an inner layer (tightly bound on the substrate), a middle layer (bulk-like), and an outer layer (surface) in the adsorbed sample. When an adsorbed sample was exposed to toluene vapor, it became clear that, between the solid adsorption layer (which does not swell) and bulk-like swollen layer, there was a "buffer layer" that could sorb more toluene molecules than the bulk-like layer. This buffer layer was found not only in the adsorbed sample but also in the standard spin-cast PMMA thin films on the substrate. When the polymer chains were firmly adsorbed and immobilized on the Si substrate, the freedom of the possible structure right next to the tightly bound layer was reduced, which restricted the relaxation of the conformation of the polymer chain strongly. The "buffer layer" was manifested by the sorption of toluene with different scattering length density contrasts.
仁井 啓介*; 井田 義明*; 上田 英貴*; 山口 隆宣*; 株本 裕史; 神谷 潤一郎; 近藤 恭弘; 田村 潤; 原田 寛之; 松井 泰; et al.
Proceedings of 19th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan (インターネット), p.601 - 604, 2023/01
マルイ鍍金工業では、日本原子力研究開発機構(JAEA)と共同で東海タンデム加速器後段の超伝導ブースター用1/4波長型超伝導空洞(QWR)について再表面処理の検討を行っている。この空洞はニオブ-銅のクラッド板で製作されており、底部に大きな開口があるため、再度の電解研磨処理等が可能な構造になっている。再表面処理では、内面ニオブに電解研磨(EP)を施工して表面粗さを小さくし、高い加速電界(5MV/m以上)を発生できるようにすることを目標としている。2020年度には、マルイ鍍金工業がニオブ9セル空洞EPの経験で得た各種パラメータとJAEA所有の電極、治具等を組み合わせて、予備の空洞に対してEPを施工した。しかし、EP後のニオブ表面は光沢が増すものの表面粗さが良好な状態とはならず、加速電界もEP前よりは改善したが、目標値には達していなかった。2021年度には空洞のニオブ表面粗さと加速電界の改善を目指して、EPのパラメータ(電極面積,電圧,流量と揺動)を変えての実験を行い、設備,条件,表面粗さ等の評価を行った。また、今回はこれまでに観察してこなかった中心導体のドリフトチューブ部内面などについても広く観察を行ったので、そちらの結果も併せて報告する。
 data
data嵯峨 涼*; 松谷 悠佑; 佐藤 光*; 長谷川 和輝*; 小原 秀樹*; 駒井 史雄*; 吉野 浩教*; 青木 昌彦*; 細川 洋一郎*
Radiotherapy and Oncology, p.109444_1 - 109444_9, 2023/00
被引用回数:3 パーセンタイル:53.08(Oncology)非小細胞肺癌を治療する際、一度に大線量を照射する定位放射線療法が使用される。この治療計画と治療効果の関係は、一般的に線量と細胞死の関係を予測する数理モデルにより評価される。そのモデルパラメーターの数値は生物実験により決定できるが、臨床では治療成果の経験に基づき決定されるため、実験研究と臨床研究ではパラメータ決定の手法と数値に違いがある。以上の背景から、細胞実験で測定される細胞死と臨床の治療効果を結びつける橋渡し研究を進めた。ここでは、その相違の要因として考えられる癌幹細胞に着目し、細胞死と臨床成果を同時に予測可能な数理モデル(integrated microdosimetric-kinetic (IMK) model)を開発し、弘前大学病院における非小細胞肺癌の定位放射線療後の臨床治験に対して遡及的評価を行った。その結果、癌幹細胞を考慮したIMKモデルを用いることで、広範囲の線量域(0-15Gy)に対する細胞死と様々な治療計画(一回線量6-10Gy)に対する治療成果を同時に再現することに成功した。開発した数理モデルにより、癌幹細胞が臨床の治療効果に与える影響の正確な理解、これに基づく治療効果の予測技術の高精度化が期待できる。