Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
上松 敬; 荒川 和夫; 居城 悟*
JAERI-Review 99-025, TIARA Annual Report 1998, p.257 - 258, 1999/10
原研サイクロトロンの制御用計算機及びマンマシンインターフェース機器は、10年以上稼動してきたが、メンテナンスができなくなってきたことと、新イオン源の増設にともなう容量不足の理由により、更新を行った。計算機は、DEC社製ミニコンピュータをWindows NTのパソコンに置き換えた。
浅野 雅春; 前川 康成; 吉田 勝
JAERI-Review 99-025, TIARA Annual Report 1998, p.87 - 88, 1999/10
イオン穿孔膜自身の物質分離機能を評価することを目的として、種々の分子量をもつPEGを用い、その透過性に及ぼすイオン穿孔膜の種類及び共重合膜の組成比の影響について検討した。CR-39膜(38 m)、CR-39/A-ProOMe共重合膜(38
m)、CR-39/A-ProOMe共重合膜(38 m)は3%IPPを重合開始剤として、70
m)は3%IPPを重合開始剤として、70 、24時間の条件によってキャスト重合によって得た。重イオン照射は450MeVのエネルギーをもつ
、24時間の条件によってキャスト重合によって得た。重イオン照射は450MeVのエネルギーをもつ Xeイオンを10
Xeイオンを10 ions/cm
ions/cm のフルエンスで照射することによって行った。化学エッチング処理は60
のフルエンスで照射することによって行った。化学エッチング処理は60 の6N NaOH水溶液を用いて任意の時間処理することによって行った。イオン穿孔膜にCR-39膜、PET膜、CR-39/A-ProOMe(50/50)共重合膜を用いた時の40
の6N NaOH水溶液を用いて任意の時間処理することによって行った。イオン穿孔膜にCR-39膜、PET膜、CR-39/A-ProOMe(50/50)共重合膜を用いた時の40 での種々の分子量をもつPEGの透過は分子量が70,000から300までは分子量の増加とともに緩やかに上昇し、106で急激に増加した。この傾向は3つの膜に共通して観察されたが、PEGの透過量はCR-39/A-ProOMe(50/50)共重合膜、CR-39膜、PET膜の順に高くなった。この透過量の違いの原因として、膜の親水性、あるいは官能基(CR-39:-CH2OH,PET:-COOH,CR-39/A-ProOMe:-CH2OH,-COOH,-ProOMe)などが考えられる。次に、イオン穿孔膜にCR-39/A-ProOMe共重合膜を用いた時の40
での種々の分子量をもつPEGの透過は分子量が70,000から300までは分子量の増加とともに緩やかに上昇し、106で急激に増加した。この傾向は3つの膜に共通して観察されたが、PEGの透過量はCR-39/A-ProOMe(50/50)共重合膜、CR-39膜、PET膜の順に高くなった。この透過量の違いの原因として、膜の親水性、あるいは官能基(CR-39:-CH2OH,PET:-COOH,CR-39/A-ProOMe:-CH2OH,-COOH,-ProOMe)などが考えられる。次に、イオン穿孔膜にCR-39/A-ProOMe共重合膜を用いた時の40 でのPEGの透過に及ぼす組成比の影響について検討したところ、PEGの透過が共重合膜の組成に強く影響を受け、20%のA-ProOMe組成を含む共重合膜で最大になることがわかった。
でのPEGの透過に及ぼす組成比の影響について検討したところ、PEGの透過が共重合膜の組成に強く影響を受け、20%のA-ProOMe組成を含む共重合膜で最大になることがわかった。
鳴海 一雅; 山本 春也; 楢本 洋
JAERI-Review 99-025, TIARA Annual Report 1998, p.155 - 157, 1999/10
化学的に不活性なサファイア中に酸化バナジウム相を生成することを目的として、サファイアに酸素とバナジウムを注入し、熱処理の際の基板及び注入元素の挙動をラザフォード後方散乱法(RBS)で観察した。還元雰囲気中での800 -1000
-1000 の焼鈍に対してはバナジウムの量がほとんど変化しないのに対し、空気中に焼鈍した試料は800
の焼鈍に対してはバナジウムの量がほとんど変化しないのに対し、空気中に焼鈍した試料は800 以上の温度でバナジウムの量が減少した。これに伴い、RBSにおけるチャネリング条件とランダム条件の収量の比が大きく減少した。これらの結果より、焼鈍雰囲気(酸素の有無)によってサファイア中でのバナジウムの挙動の違い、すなわち生成する酸化バナジウム相が異なることを明らかにした。
以上の温度でバナジウムの量が減少した。これに伴い、RBSにおけるチャネリング条件とランダム条件の収量の比が大きく減少した。これらの結果より、焼鈍雰囲気(酸素の有無)によってサファイア中でのバナジウムの挙動の違い、すなわち生成する酸化バナジウム相が異なることを明らかにした。
川面 澄*; 竹島 直樹*; 寺澤 昇久*; 青木 康; 山本 春也; 梨山 勇; 鳴海 一雅; 楢本 洋
JAERI-Review 99-025, TIARA Annual Report 1998, p.188 - 190, 1999/10
MeV/uの軽イオン及び重イオンをNi, NiO, Cu, CuOに照射して、放出されるLX線の微細構造を調べ、内殻電子の励起過程及び外殻電子の内殻空孔への脱励起過程に対する化学結合効果の影響を調べた。得られたLX線スペクトルはイオン種によって異なり、重イオンの多重電離による衛星線及び超衛星線によるスペクトルの変化が観測された。また、L , L
, L X線スペクトルは明らかに標的に依存する違いが見いだされた。これは、最外殻の3d電子が遷移に関与するために大きな化学結合結果が現れる結果だと考えられる。
X線スペクトルは明らかに標的に依存する違いが見いだされた。これは、最外殻の3d電子が遷移に関与するために大きな化学結合結果が現れる結果だと考えられる。
高広 克巳*; 永田 晋二*; 山本 春也; 山口 貞衛*; 楢本 洋
JAERI-Review 99-025, TIARA Annual Report 1998, p.143 - 145, 1999/10
Ag及びClイオンをSiO と
と -Al
-Al O
O に室温で注入して、その存在状態を、RBS、X線回折、光吸収で調べた研究であり、以下の結論を得た。(1)室温注入でも、AgとClは固相反応して、AgClの超微粒子を形成した。(2)Clは、AgClの形成に関係するだけでなく、Ag自身の析出過程にも影響する。
に室温で注入して、その存在状態を、RBS、X線回折、光吸収で調べた研究であり、以下の結論を得た。(1)室温注入でも、AgとClは固相反応して、AgClの超微粒子を形成した。(2)Clは、AgClの形成に関係するだけでなく、Ag自身の析出過程にも影響する。
川面 澄*; 竹島 直樹*; 寺澤 昇久*; 青木 康*; 山本 春也; 梨山 勇; 鳴海 一雅; 楢本 洋
JAERI-Review 99-025, TIARA Annual Report 1998, p.188 - 190, 1999/10
MeV領域の H
H ,
,  He
He ,
,  C
C イオンをCu, CuO, Ni, NiOに入射して、内殻多重電離過程で誘起されるX線スペクトルの精密測定を行い以下の結論を得た。(1)Cu原子からのLX線の測定では、たとえばターゲットがCuとCuOとの場合に、L
イオンをCu, CuO, Ni, NiOに入射して、内殻多重電離過程で誘起されるX線スペクトルの精密測定を行い以下の結論を得た。(1)Cu原子からのLX線の測定では、たとえばターゲットがCuとCuOとの場合に、L 線, L
線, L 線のエネルギー領域で顕著な違いが見られた(2.5MeV
線のエネルギー領域で顕著な違いが見られた(2.5MeV  He
He 入射の場合)が、定量的評価が必要。(2)入射イオンの原子番号が増すと、エネルギー/核子をそろえた場合でも、特性X線のほかにいわゆる衛星線の発生によりスペクトルが複雑化する。そこで多重電離過程を利用した化学シフトの研究では、ターゲットとの組合せを考慮した入射イオンの選択が重要になる。
入射の場合)が、定量的評価が必要。(2)入射イオンの原子番号が増すと、エネルギー/核子をそろえた場合でも、特性X線のほかにいわゆる衛星線の発生によりスペクトルが複雑化する。そこで多重電離過程を利用した化学シフトの研究では、ターゲットとの組合せを考慮した入射イオンの選択が重要になる。
工藤 博*; 中村 直樹*; 山本 春也; 鳴海 一雅; 楢本 洋
JAERI-Review 99-025, TIARA Annual Report 1998, p.185 - 187, 1999/10
チャンネル条件下で、準表面層で生成する2次電子の収量と2次電子の回折効果を確認するため、Si単結晶表面に非晶質層を形成した後、 100keV/uのHe
100keV/uのHe イオンを入射して、2次電子スペクトル(0.2
イオンを入射して、2次電子スペクトル(0.2 1.0keV)を調べた。その結果、以下の結論を得た。(1)2次電子の回折効果は、この実験の誤差範囲内では明確には現れないので、イオン入射時の結晶学的情報を直接的に反映した表面解析が可能である。(2)2次電子の発生、表面への反跳過程の実験結果は、計算結果とよく対応する。したがって、イオン誘起2次電子分光法は、高感度な表面解析法と有用になる。特にオージェ電子分光と組合せることにより、重元素マトリックス上の軽元素の結晶学的解析が可能になり、ほかに類を見ない貴重な手法となろう。
1.0keV)を調べた。その結果、以下の結論を得た。(1)2次電子の回折効果は、この実験の誤差範囲内では明確には現れないので、イオン入射時の結晶学的情報を直接的に反映した表面解析が可能である。(2)2次電子の発生、表面への反跳過程の実験結果は、計算結果とよく対応する。したがって、イオン誘起2次電子分光法は、高感度な表面解析法と有用になる。特にオージェ電子分光と組合せることにより、重元素マトリックス上の軽元素の結晶学的解析が可能になり、ほかに類を見ない貴重な手法となろう。
荒川 和夫; 中村 義輝; 横田 渉; 福田 光宏; 奈良 孝幸; 上松 敬; 奥村 進; 石堀 郁夫; 田村 宏行
JAERI-Review 99-025, TIARA Annual Report 1998, p.254 - 256, 1999/10
原研サイクロトロンは、1992年に本格的なビームを提供して以来、23,200時間を運転した。昨年度は、3,216時間運転し、28種類のイオンを実験に提供した。また、サイクロトロンの経年劣化対策としてローカルパネルのスイッチ4,000個の交換、RF共振器冷却配管の更新及び既設ECRイオン源のクライストロン電源を更新した。また、高度化対策として制御系計算機を更新し、機能の向上を図った。カクテルビーム加速技術の開発では、M/Q=4シリーズの異種イオン混入防止のためのガス導入系の改造とイオン分離技術を開発した結果について述べた。また、新たにM/Q=2のフルストリップイオンのカクテルビーム加速試験結果について示した。
阿部 健*; 斎藤 究*; 藤 健太郎; 小嶋 拓治; 酒井 卓郎
JAERI-Review 99-025, TIARA Annual Report 1998, p.103 - 105, 1999/10
イメージングプレート(IP, 組成BaFBr:Eu )を用いてサイクロトロンから得られるイオンビームの線種、エネルギー弁別測定技術を開発するため、輝尽発光のLET特性の機構に関する研究を行った。この結果、IPの励起スペクトル応答における線種・エネルギー依存性が、入射イオンの蛍光体層への侵入深さによるものだけでなく、特に重イオンでは入射イオンのLET効果にもよることが、スペクトル成分の分離解析によりわかった。また、このLET効果は、IP中のBr及びFのF
)を用いてサイクロトロンから得られるイオンビームの線種、エネルギー弁別測定技術を開発するため、輝尽発光のLET特性の機構に関する研究を行った。この結果、IPの励起スペクトル応答における線種・エネルギー依存性が、入射イオンの蛍光体層への侵入深さによるものだけでなく、特に重イオンでは入射イオンのLET効果にもよることが、スペクトル成分の分離解析によりわかった。また、このLET効果は、IP中のBr及びFのF センターのレベルに相当するスペクトルに現れていることが明らかになった。さらに、1kGy以上の線量域における輝尽発光量の低下は、基材のポリエチレンテレフタレートの劣化でなく、輝尽発光体の損傷によることがわかった。これらにより、IP応答のLET特性及びその機構をほぼ明らかにした。
センターのレベルに相当するスペクトルに現れていることが明らかになった。さらに、1kGy以上の線量域における輝尽発光量の低下は、基材のポリエチレンテレフタレートの劣化でなく、輝尽発光体の損傷によることがわかった。これらにより、IP応答のLET特性及びその機構をほぼ明らかにした。
小嶋 拓治; 須永 博美; 瀧澤 春喜; 橘 宏行
JAERI-Review 99-025, TIARA Annual Report 1998, p.100 - 102, 1999/10
3 45MeV/amuのイオンビームのフルエンス測定について、これまでに総電荷量5nc/cm
45MeV/amuのイオンビームのフルエンス測定について、これまでに総電荷量5nc/cm 以上では
以上では 2%の高い精度が得られている。これに基づき、ファラデーカップのサプレッション電圧の最適化や非照射時の暗電流評価を行い、これ以下の電流域についても
2%の高い精度が得られている。これに基づき、ファラデーカップのサプレッション電圧の最適化や非照射時の暗電流評価を行い、これ以下の電流域についても 2%以内の精度が得られることを明らかにした。また、4種のフィルム線量計のLET特性を低LET放射線の場合に規格化して整理することにより、低LET放射線で得られる校正曲線への補正係数を
2%以内の精度が得られることを明らかにした。また、4種のフィルム線量計のLET特性を低LET放射線の場合に規格化して整理することにより、低LET放射線で得られる校正曲線への補正係数を 4%以内で与えた。これにより、これまで着色量等の分布でしかなかった情報を線量分布として表すことが可能となった。このため、積層フィルム中の深度線量分布測定などの応用を進めている。
4%以内で与えた。これにより、これまで着色量等の分布でしかなかった情報を線量分布として表すことが可能となった。このため、積層フィルム中の深度線量分布測定などの応用を進めている。
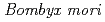 ; Morphological changes of the nuclei and cells after spot irradiation
; Morphological changes of the nuclei and cells after spot irradiation木口 憲爾*; 島 拓郎*; 金城 雄*; Tu, Z. L.*; 山崎 修平*; 小林 泰彦; 田口 光正; 渡辺 宏
JAERI-Review 99-025, TIARA Annual Report 1998, p.53 - 55, 1999/10
日本原子力研究所高崎研究所の細胞局部照射装置を用いてさまざまな生物の受精卵や胚子を重イオンで局部照射することによって、発生過程の解析が可能である。カイコは、その遺伝学的バックボーンや形態的・生理的な特徴から、この実験目的には理想的な材料の一つである。そこで、重イオン局部照射がカイコの初期発生過程に及ぼす影響を調べるために、受精直後の卵及び細胞性胞胚期卵に炭素イオンを局部照射し、照射された分裂核及び細胞の形態変化を観察したところ、照射を受けた分裂核は、その後分裂できずに肥大化し、その多くは正常に移動を続けて周辺細胞質に到達するが、一部は脱落して周囲の正常核と置換する場合があることがわかった。また受精直後卵を局部照射した場合は、発生した胚子には照射による影響が見られなかったのに対し、細胞性胞胚期卵への局部照射では、照射部位に対応した形態異常が胚子に誘導された。
小林 泰彦; 田口 光正; 渡辺 宏; 山本 和生
JAERI-Review 99-025, TIARA Annual Report 1998, p.50 - 52, 1999/10
動物培養細胞へのシングルイオン照射を行うには、大気中に取り出したイオンが標的となる細胞と培養液及びその容器、さらに飛跡検出用CR-39フィルムを貫通した後、イオンの入射個別を計数するプラスチック・シンチレーターまで届くだけの飛程を有していることが必要である。そのため、高崎研究所のサイクロトロンで得られる高エネルギー重イオンをコリメート系を通して大気中に取り出し、顕微鏡観察下の生物試料に照射することができる細胞局部照射装置を製作した。本装置の照準・観察系顕微鏡の対物レンズの位置にプラスチック・シンチレータを取り付けたフォトマルを取り付け、照射試料を貫通したイオンに由来する信号を検出することによって照射されたイオン個数を計測し、ビームシャッターを駆動して照射を終了するシステムを構築した。試料の位置でのイオンの飛跡のバラツキを厚さ10 mのCR-39フィルムを用いて調べたところ、約
mのCR-39フィルムを用いて調べたところ、約 10
10 mの範囲に集中して照射されていることがわかった。
mの範囲に集中して照射されていることがわかった。
土谷 邦彦; 河村 弘; 三輪 幸夫; 浜田 省三
JAERI-Review 99-025, TIARA Annual Report 1998, p.111 - 113, 1999/10
核融合炉(ITER)用ブランケット冷却枝管においては、中性子照射されたものと中性子照射されていないものを溶接することが必要となる。したがって、補修・交換を考えた場合、溶接継手の機械的性質に対するHe生成量依存性、すなわち、溶接補修・交換を行ううえで許容されるHe生成量のしきい値を明らかにすることが重要になる。このための第1段階として、本研究では、サイクロトロンを利用してステンレス鋼(SUS316LN-IG: ITER用構造材の候補材)にHeを最大で20appmまで比較的均一に注入した後、TIG溶接を行い、溶接継手の組織観察を行った。この結果、約20appmまでヘリウムを注入したステンレス鋼の溶接が可能である見通しを得た。
 La isotopes
La isotopes山本 洋*; 柴田 理尋*; 河出 清*; 小島 康明*; 長 明彦; 渡辺 智; 小泉 光生; 関根 俊明
JAERI-Review 99-025, TIARA Annual Report 1998, p.208 - 210, 1999/10
TIARA-ISOLで分離した Laの
Laの 壊変に伴う
壊変に伴う 線最大エネルギーを高純度ゲルマニウム検出器によって測定し、
線最大エネルギーを高純度ゲルマニウム検出器によって測定し、 Laについて初めて実験値を得た。各種の質量公式のうち、橘らによる質量公式が今回の実験値をよく再現しているが、一般に質量公式はこれらの同位元素に関して原子質量を小さく評価している。二中性子分離エネルギーの系統性から、質量数128近傍でLa同位体の核構造が変化していることが示唆された。
Laについて初めて実験値を得た。各種の質量公式のうち、橘らによる質量公式が今回の実験値をよく再現しているが、一般に質量公式はこれらの同位元素に関して原子質量を小さく評価している。二中性子分離エネルギーの系統性から、質量数128近傍でLa同位体の核構造が変化していることが示唆された。
大坪 隆*; 大矢 進*; 後藤 淳*; 出淵 善智*; 武藤 豪*; 長 明彦; 小泉 光生; 関根 俊明
JAERI-Review 99-025, TIARA Annual Report 1998, p.206 - 207, 1999/10
偏極した不安定核はそれ自身の電磁気モーメントの決定のみならず、物質中の不純物効果の研究等に有用である。本研究では、微小角度で入射した不安定核のイオンが表面との相互作用により偏極させ、核磁気共鳴法により偏極度を求める方法を試みている。TIARAオンライン同位体分離器で Ar+Mo反応で生成する
Ar+Mo反応で生成する Cs(半減期31秒)の偏極をこれまで行ってきたが、より大きな偏極度を得るべく今回は
Cs(半減期31秒)の偏極をこれまで行ってきたが、より大きな偏極度を得るべく今回は C+
C+ C反応で生成する
C反応で生成する Na(22秒)について試みた。得られた偏極度は(0.32
Na(22秒)について試みた。得られた偏極度は(0.32 0.23)%に止まり、
0.23)%に止まり、 Csの偏極度(0.23
Csの偏極度(0.23 0.13)%より大きな値は得られなかった。原因は検討中である。
0.13)%より大きな値は得られなかった。原因は検討中である。
 ssbauer isomer shifts of
ssbauer isomer shifts of  Cs-impurity atoms implanted into metallic matrices
Cs-impurity atoms implanted into metallic matrices村松 久和*; 吉川 広輔*; 石井 寛子*; 田中 栄司*; 三浦 太一*; 渡辺 智; 小泉 光生; 長 明彦; 関根 俊明
JAERI-Review 99-025, TIARA Annual Report 1998, p.211 - 213, 1999/10
金属中にイオン注入された Xeは
Xeは Csに
Csに 崩壊し、
崩壊し、 Csはメスバウア核種であってメスバウアスペクトルに
Csはメスバウア核種であってメスバウアスペクトルに Csが置かれた状態を反映するアイソマーシフトが観測される。われわれはアイソマーシフトの大きさとホスト金属の物理的・化学的性質との関係を明らかにするために各種金属に
Csが置かれた状態を反映するアイソマーシフトが観測される。われわれはアイソマーシフトの大きさとホスト金属の物理的・化学的性質との関係を明らかにするために各種金属に Xeをイオン注入、液体ヘリウム温度でメスバウアスペクトルを測定した。これまでにわれわれが得たAl,V,Cr,Co,Ni,Cu,Mo,Rh,W及びTi,Zn,Ta,Re,Irに関する文献値から、ホスト金属の体積弾性率との相関と同時に、最外殻電子数との相関が示唆された。
Xeをイオン注入、液体ヘリウム温度でメスバウアスペクトルを測定した。これまでにわれわれが得たAl,V,Cr,Co,Ni,Cu,Mo,Rh,W及びTi,Zn,Ta,Re,Irに関する文献値から、ホスト金属の体積弾性率との相関と同時に、最外殻電子数との相関が示唆された。
川合 真紀; 小林 泰彦; 大野 豊; 渡辺 宏; 内宮 博文
JAERI-Review 99-025, TIARA Annual Report 1998, P. 56, 1999/10
細胞が自ら死ぬ能力(プログラム細胞死)は多細胞生物が有する基本的な生命活動の一つである。中でもアポトーシスと称される細胞死現象は、近年、特に注目され盛んに研究が行われている。放射線によって引き起こされるDNAの損傷に対して、細胞は自己修復機構を活性化させるが、修復不可能な傷に対しては自殺機構を起動する。これらは厳密に制御されたシグナル伝達系を介しており、障害による受動的な死とは区別される。植物においてもプログラムされた細胞死は形態形成等に重要な役割を担っているが、詳細は知られていない。今回、われわれはイオンビームを植物細胞に照射することによって、動物のアポトーシスと類似の形態的変化を伴う細胞死が誘引されることを見いだした。人為的に細胞死を誘発するシステムを確立することによって、植物のアポトーシスの機構解明への大きな足がかりになると考えられる。
長 明彦; 小泉 光生; 関根 俊明; 桂川 秀嗣*; Jin, W.*; 涌井 崇志*
JAERI-Review 99-025, TIARA Annual Report 1998, p.203 - 205, 1999/10
TIARA-ISOLでは中性子欠損側の希土類元素不安定核の 壊変研究を行ってきた。近年、核物性研究のプローブとしての不安定核ビームが必要となってきた。表面電離型イオン源を用いたNa不安定核の生成分離とレーザーイオン源開発の現状について報告する。
壊変研究を行ってきた。近年、核物性研究のプローブとしての不安定核ビームが必要となってきた。表面電離型イオン源を用いたNa不安定核の生成分離とレーザーイオン源開発の現状について報告する。
楢本 洋; 山本 春也; 鳴海 一雅
JAERI-Review 99-025, TIARA Annual Report 1998, p.191 - 192, 1999/10
互いに固溶しない物質系は、結晶成長・組織化制御による新しい機能性を付与する観点からも、興味ある対象である。本研究では、イオン注入法により非固溶物質系(過飽和)を作成するとともに、MeVイオンを用いて結晶析出過程を解析して、以下の結論を得た。(1)過飽和な系が、結晶か非結晶かにより、その後の析出過程に大きく影響する。(2)Nb/Cu等の金属系では、低温でも、イオン照射下での欠陥輸送の助けにより、例えばCu原子はNb表面に拡散して、整合形析出物を形成する。(3)Ir中の炭素原子の存在状態は、水素原子の存在によって影響され、高温(数百 )では、Ir中に保持できない。
)では、Ir中に保持できない。
森田 健治*; 石川 大*; 柚原 淳司*; 中村 大輔*; 曽田 一雄*; 山本 春也; 鳴海 一雅; 楢本 洋; 斉藤 和雄*
JAERI-Review 99-025, TIARA Annual Report 1998, p.179 - 181, 1999/10
イオン注入と化学エッチングにより作成したSi(111)自己支持薄膜に、Au及びAgを1原子層程度蒸着後、6MeV  Liイオン等を入射させ、透過チャネリング解析を行った。その結果、以下の結論を得た。(1)Au原子は、Si(111)原子列から0.83
Liイオン等を入射させ、透過チャネリング解析を行った。その結果、以下の結論を得た。(1)Au原子は、Si(111)原子列から0.83 離れた位置にあり、Si(111)-2
離れた位置にあり、Si(111)-2
 2
2 (Au, Ag)構造をとっている可能性が高い。(2)Ag原子については、2つの可能性がある。1つはチャネリング軸の中心であり、もう一方は軸からずれた成分である。しかしその割合等は、本実験だけでは決定できない。
(Au, Ag)構造をとっている可能性が高い。(2)Ag原子については、2つの可能性がある。1つはチャネリング軸の中心であり、もう一方は軸からずれた成分である。しかしその割合等は、本実験だけでは決定できない。