Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
出井 俊太郎; 柴田 真仁*; 根岸 久美*; 杉浦 佑樹; 天野 由記; Bateman, K.*; Wilson, J.*; 横山 立憲; 鏡味 沙耶; 武田 匡樹; et al.
Results in Earth Sciences (Internet), 3, p.100097_1 - 100097_16, 2025/12
高レベル放射性廃棄物の地層処分において、セメントと泥岩の相互作用による化学的擾乱領域が形成され、岩盤中の核種移行特性に影響を及ぼす可能性がある。本研究では、11年前に幌延深地層研究センターの140m調査坑道に施工されたセメント(普通ポルトランドセメント(OPC)および低アルカリ性セメント(LAC))と泥岩の界面における変質状態について調査した。複数の分析手法を組み合わせることで、セメントの溶解、方解石やC-(A-)S-H相などの二次鉱物の析出、モンモリロナイトの陽イオン交換、泥岩の空隙率の低下など、セメントと岩石の界面における主要な反応が特定された。また、空隙率の低下による拡散の低下や、変質した泥岩中の二次鉱物への取り込みによる収着の促進など、セメントと泥岩の相互作用が放射性核種の移行に及ぼす影響についても明らかになった。
バックエンド技術部
JAEA-Review 2025-006, 126 Pages, 2025/07
本報告書は、日本原子力研究開発機構原子力科学研究部門原子力科学研究所バックエンド技術部における2023年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の活動をまとめたものであり、所掌する施設の運転・管理、放射性廃棄物の処理・管理、施設の廃止措置に関する業務、これらに関連する技術開発及び研究成果の概要を取りまとめた。2023年度の放射性廃棄物の処理実績は、可燃性固体廃棄物が約156m 、不燃性固体廃棄物が約84m
、不燃性固体廃棄物が約84m 、液体廃棄物が約295m
、液体廃棄物が約295m (希釈処理約173m
(希釈処理約173m を含む)であった。新たな保管体の発生数は、200Lドラム缶換算837本であった。公益社団法人日本アイソトープ協会への保管体の返還作業及び保管廃棄していた廃棄物の減容処理を行うことにより、保管体数の削減に取り組んだ結果、最終的に2023年度末の累積保管体数は2022年度から4,261本減の118,664本となった。保管廃棄施設・Lの保管体健全性確認作業は、本格運用を継続して実施した。また、放射性廃棄物処理場が新規制基準に適合していることの確認を受けるため、設計及び工事方法の認可申請を原子力規制庁に対し、順次、実施した。廃止措置に関しては、再処理特別研究棟において、機器の撤去等を実施した。バックエンドに関連する研究・技術開発においては、廃棄物放射能評価法の構築に向けて、採取した廃棄物試料の放射能分析を実施した。また福島第一原子力発電所事故に伴い発生した除去土壌の埋立処分に関する実証事業について、埋立完了後のモニタリングを継続した。
を含む)であった。新たな保管体の発生数は、200Lドラム缶換算837本であった。公益社団法人日本アイソトープ協会への保管体の返還作業及び保管廃棄していた廃棄物の減容処理を行うことにより、保管体数の削減に取り組んだ結果、最終的に2023年度末の累積保管体数は2022年度から4,261本減の118,664本となった。保管廃棄施設・Lの保管体健全性確認作業は、本格運用を継続して実施した。また、放射性廃棄物処理場が新規制基準に適合していることの確認を受けるため、設計及び工事方法の認可申請を原子力規制庁に対し、順次、実施した。廃止措置に関しては、再処理特別研究棟において、機器の撤去等を実施した。バックエンドに関連する研究・技術開発においては、廃棄物放射能評価法の構築に向けて、採取した廃棄物試料の放射能分析を実施した。また福島第一原子力発電所事故に伴い発生した除去土壌の埋立処分に関する実証事業について、埋立完了後のモニタリングを継続した。
青野 竜士; 後藤 勝則*; 木名瀬 暁理; 佐藤 義行; 原賀 智子; 伊勢田 浩克
JAEA-Data/Code 2025-006, 24 Pages, 2025/07
日本原子力研究開発機構の研究施設等から発生する放射性廃棄物は、放射能レベルに応じて将来的にトレンチとピットに分けて浅地中処分される予定であり、埋設処分を開始するまでに、廃棄体の放射能濃度を評価する方法を構築する必要がある。そこで、原子力科学研究所バックエンド技術部では、研究施設等廃棄物に対する放射能濃度評価方法の検討に資するため、保管廃棄施設・Lに保管されている圧縮体より分析試料を採取し、放射化学分析を実施した。本報告書は、令和2年度に取得した12核種( H、
H、 C、
C、 Co、
Co、 Sr、
Sr、 Nb、
Nb、 Cs、
Cs、 Eu、
Eu、 Eu、
Eu、 Pu、
Pu、 Pu、
Pu、 Pu、
Pu、 Am)の放射能濃度データについて整理し、放射能濃度評価方法の検討のための基礎資料としてまとめたものである。
Am)の放射能濃度データについて整理し、放射能濃度評価方法の検討のための基礎資料としてまとめたものである。
望月 陽人; 松井 裕哉; 中山 雅; 坂本 亮*; 柴田 真仁*; 本島 貴之*; 城 まゆみ*
Case Studies in Construction Materials, 22, p.e04648_1 - e04648_20, 2025/07
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Construction & Building Technology)放射性廃棄物の地層処分で使用される低アルカリ性セメントは、長期にわたる処分場の操業期間中に大気中の二酸化炭素による炭酸化や地下水との接触によってその特性が変化する可能性がある。本研究では、フライアッシュとシリカヒュームを混合した低アルカリ性セメント(HFSC)を用いた吹付けコンクリートの化学的特性、微細構造ならびに輸送特性に対して大気中での炭酸化および地下水との接触が与える影響を、幌延の地下研究施設において16年間にわたり調査した。HFSC吹付けコンクリートの炭酸化領域と溶出領域のいずれにおいても、直径約300nm未満の細孔の毛細管空隙率が増加し、全空隙率は非変質領域よりも高くなった。これらの空隙構造の変化は、ケイ酸カルシウム水和物(C-S-H)の脱灰とエトリンガイトの分解に関連していると考えられる。このような変化は、OPC吹付けコンクリートの変質領域では軽微であったことから、本研究の調査条件下において、HFSC吹付けコンクリートは炭酸化や地下水溶出に対する抵抗性が相対的に低いことが示された。しかしながら、HFSCの透水係数は、地層処分に用いられる低pHセメントに求められる機能要件を満たす程度に低かった。
村上 昌史; 吉田 幸彦; 南郷 脩史*; 久保田 省吾*; 黒澤 卓也*; 佐々木 紀樹
Journal of Nuclear Science and Technology, 62(7), p.650 - 661, 2025/07
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Nuclear Science & Technology)Nondestructive methods were investigated to effectively discriminate disposal-restricted materials, including aluminum, batteries, combustibles, lead, and mercury, inside waste containers without opening them. An industrial computed tomography (CT) system with maximum X-ray energy of 9 MeV was used to visualize inside 27-cm diameter pails and 59-cm diameter drums filled with typical waste materials such as combustibles, glass, concrete, and metals. The CT images with 0.5 mm spacing were acquired, and three-dimensional (3D) models were constructed. A good linear relationship was observed between the gray values in the obtained CT images and the densities of materials. Combustibles, lead, and mercury were extracted via simple segmentation based on their apparent densities. 3D feature-based discriminations were further applied to batteries and certain aluminum objects based on their structural characteristics. Almost all batteries contained in the drums were successfully discriminated regardless of deformation, except for a few cases under extreme conditions. Aluminum was extracted along with glass and concrete; however, pipes with distinctive shapes could be identified in a relatively selective manner. The discrimination methods developed in this study will be effective in revealing the contents of waste containers, particularly for harmful materials that need to be separated for proper disposal.
杉田 裕; 大野 宏和; Beese, S.*; Pan, P.*; Kim, M.*; Lee, C.*; Jove-Colon, C.*; Lopez, C. M.*; Liang, S.-Y.*
Geomechanics for Energy and the Environment, 42, p.100668_1 - 100668_21, 2025/06
被引用回数:1 パーセンタイル:0.00(Energy & Fuels)国際共同プロジェクトDECOVALEX-2023は、数値解析を使用してベントナイト系人工バリアの熱-水-応力(または熱-水)相互作用を研究するためのタスクDとして、幌延人工バリア性能確認試験を対象とした。このタスクは、モデル化のために、1つの実物大の原位置試験と、補完的な4つの室内試験が選択された。幌延人工バリア性能確認試験は、人工的な地下水注入と組み合わせた温度制御非等温の試験であり、加熱フェーズと冷却フェーズで構成されている。6つの研究チームが、さまざまなコンピューターコード、定式化、構成法則を使用して、熱-水-応力または熱-水(研究チームのアプローチによって異なる)数値解析を実行した。
Birkholzer, J. T.*; Graupner, B. J.*; Harrington, J.*; Jayne, R.*; Kolditz, O.*; Kuhlman, K. L.*; LaForce, T.*; Leone, R. C.*; Mariner, P. E.*; McDermott, C.*; et al.
Geomechanics for Energy and the Environment, 42, p.100685_1 - 100685_17, 2025/06
被引用回数:0The DECOVALEX initiative is an international research collaboration (www.decovalex.org), initiated in 1992, for advancing the understanding and modeling of coupled thermo-hydro-mechanical-chemical (THMC) processes in geological systems. DECOVALEX stands for "DEvelopment of COupled Models and VALidation against EXperiments". DECOVALEX emphasizes joint analysis and comparative modeling of the complex perturbations and coupled processes in geologic repositories and how these impact long-term performance predictions. More than fifty research teams associated with 17 international DECOVALEX partner organizations participated in the comparative evaluation of eight modeling tasks covering a wide range of spatial and temporal scales, geological formations, and coupled processes. This Virtual Special Issue on DECOVALEX-2023 provides an in-depth overview of these collaborative research efforts and how these have advanced the state-of-the-art of understanding and modeling coupled THMC processes. While primarily focused on radioactive waste, much of the work included here has wider application to many geoengineering topics.
 sp. nov., a novel hydrogen-producing bacterium isolated from a deep diatomaceous shale formation
sp. nov., a novel hydrogen-producing bacterium isolated from a deep diatomaceous shale formation上野 晃生*; 佐藤 聖*; 玉村 修司*; 村上 拓馬*; 猪股 英紀*; 玉澤 聡*; 天野 由記; 宮川 和也; 長沼 毅*; 五十嵐 敏文*
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 75(6), p.006802_1 - 006802_11, 2025/06
幌延深地層研究センターの地下施設内に掘削されたボーリング孔を用い、深度350mの新第三紀堆積層中の地下水から、グラム陰性、非運動性、桿菌株の偏性嫌気性細菌を単離した。これをZ1-71 株と呼ぶ。細胞は長さ2.7-4.8
株と呼ぶ。細胞は長さ2.7-4.8 m、幅0.4
m、幅0.4 mであり、温度10-42
mであり、温度10-42 C、pH 6.0-9.0及びNaCl濃度0-3.0%(w/v)で生育が認められた。Z1-71
C、pH 6.0-9.0及びNaCl濃度0-3.0%(w/v)で生育が認められた。Z1-71 株は、D-グルコースを基質として生育した場合、水素の生成が認められた。16S rRNA遺伝子配列の系統解析により、Z1-71
株は、D-グルコースを基質として生育した場合、水素の生成が認められた。16S rRNA遺伝子配列の系統解析により、Z1-71 株は
株は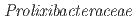 科の
科の 属に分類されることが示された。系統学的および表現型の特徴に基づき、Z1-71
属に分類されることが示された。系統学的および表現型の特徴に基づき、Z1-71 株は
株は 属の新種細菌であると考えられ、
属の新種細菌であると考えられ、 sp. nov.と命名する。Z1-71
sp. nov.と命名する。Z1-71 株を水素資化性メタン生成菌(
株を水素資化性メタン生成菌( T10
T10 株)とグルコースを基質として30
株)とグルコースを基質として30 Cの嫌気環境下で4週間共培養した結果、各単離株のみでの培養では見られなかったメタンの生成が認められた。このことは、Z1-71
Cの嫌気環境下で4週間共培養した結果、各単離株のみでの培養では見られなかったメタンの生成が認められた。このことは、Z1-71 株より生成したギ酸塩と水素がメタン生成菌により利用されることでメタンが生成したことを示していると考えられた。
株より生成したギ酸塩と水素がメタン生成菌により利用されることでメタンが生成したことを示していると考えられた。
武井 早憲
Journal of Nuclear Science and Technology, 45 Pages, 2025/06
日本原子力研究開発機構では、マイナーアクチニドを効率的に核変換する加速器駆動核変換システム(ADS)の研究開発を行っている。このシステムは、未臨界炉と大強度超伝導陽子線形加速器(ADS用陽子加速器)の組み合わせである。ADS用陽子加速器の開発を困難にしている要因の一つは、熱サイクル疲労を誘因するビームトリップ事象であり、この事象によって未臨界炉の機器が損傷するからである。ADS用陽子加速器は大強度陽子加速器の一つであるJ-PARCリニアックと比べて電流比で32倍の差がある。従って、開発段階に応じてADS用陽子加速器のビームトリップ頻度と許容ビームトリップ頻度を比較することが必要になる。今回、J-PARCリニアックの運転データに基づく信頼度関数を使ったモンテカルロ法のプログラムを作成し、ADS用陽子加速器のビームトリップ頻度を推測した。モンテカルロ法のプログラムにより、従来の解析手法では得られなかったビームトリップ事象の時間分布が得られた。その結果、許容ビームトリップ頻度を満足するには、ビームトリップ時間が5分以上のビームトリップ頻度を現状の27%に低減しなければならないことがわかった。
青柳 和平; 尾崎 裕介; 早野 明; 大野 宏和; 舘 幸男
日本原子力学会誌ATOMO , 67(6), p.354 - 358, 2025/06
, 67(6), p.354 - 358, 2025/06
日本原子力研究開発機構は、幌延深地層研究センターの地下施設を活用した"幌延国際共同プロジェクト(Horonobe International Project: HIP)"を開始した。本プロジェクトの主要な目的は、地層処分のための先進的な安全評価技術や工学技術に関わる研究開発の成果の最大化や、次世代の研究者や技術者の育成と知識の継承である。本解説では、日本原子力学会2024年秋の大会におけるバックエンド部会の企画セッション"幌延国際共同プロジェクトの現状と今後の展開"の流れに沿って、本プロジェクトの概要を紹介する。
木下 淳一; 坂本 裕; 鈴木 一朗; 中嶋 瞭太; 森田 祐介; 入江 博文
JAEA-Technology 2024-027, 55 Pages, 2025/05
第2廃棄物処理棟は、原子力科学研究所内で発生する比較的放射能レベルの高い放射性廃棄物を処理することを目的として建設された施設であり、旧建築基準法に基づき設計、建設されたものである。平成25年12月に施行された「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則」の要求事項に従い、現行の建築基準法に基づき耐震評価した結果、耐震強度が不足していることが判明したことから、耐震強度を向上させるための耐震補強工事を平成30年11月から令和2年2月にかけて行った。本稿は、第2廃棄物処理棟の耐震補強工事の設計、工事及び試験検査について取りまとめたものである。
Wilson, J.*; 笹本 広; 舘 幸男; 川間 大介*
Applied Clay Science, 275, p.107862_1 - 107862_15, 2025/05
被引用回数:0高レベル放射性廃棄物の処分場では、鉄または鋼製ベースの容器/オーバーパック及びベントナイト緩衝材が用いられる。25年以上にわたり、鉄とベントナイトの相互作用に関わる研究が行われ、その中では、特に膨潤性粘土(スメクタイト)の鉄に富んだ層状珪酸塩(膨潤能が欠落する鉱物も存在)への変質可能性について検討がなされた。このような変質が生じると、人工バリア材の一つである緩衝材に期待されている膨潤性の欠落或いは低下を引き起こし、せん断応力に対するオーバーパックの保護性、水や溶質の移行抑制にも影響を与える。鉄とベントナイトの相互作用に関わるデータの多くは、実験及び地球化学モデリングによるものであり、ナチュラルアナログによるデータには乏しい。これらの既往データによれば、スメクタイト(アルミ質のモンモリロナイト)が鉄に富んだ固相(層状珪酸塩を含む)に変質したものや、グリーンラスト又は磁鉄鉱のような腐食生成物を伴う鉄に富んだ変質ゾーンが生成される可能性が示唆される。一方、このような変質ゾーンについての実態は複雑であり、現状での理解は不十分な部分もある。25年以上にもわたり研究が行われているにもかかわらず不確実な部分も多いが、今回のレビューにより、鉄とベントナイトの相互作用に伴い生じる尤もらしいシナリオが認識され、考えられ得る緩衝材特性への影響についても提示された。
 in downwind East Asia
in downwind East Asia土屋 望*; 池盛 文数*; 川崎 一雄*; 山田 怜奈*; 畑 光彦*; 古内 正美*; 岩本 洋子*; 兼保 直樹*; 定永 靖宗*; 渡邊 隆広; et al.
Environmental Science & Technology, 59(21), p.10400 - 10410, 2025/05
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Engineering, Environmental)本研究では、能登地方で採取したPM2.5の磁気、安定炭素同位体比、放射性炭素、バイオマスバーニングの有機マーカー等を調査した。特に、磁気と炭素性物質の情報をもとにPM2.5発生源に関する新たな環境指標を提唱した。
荒井 陽一; 渡部 創; 中原 将海; 船越 智雅; 星野 貴紀; 高畠 容子; 坂本 淳志; 粟飯原 はるか; 長谷川 健太; 吉田 稔生; et al.
Progress in Nuclear Science and Technology (Internet), 7, p.168 - 174, 2025/05
STRADプロジェクトの進捗に係る報告として、CPFホットセルの処理状況とともに、新たなターゲットに係る研究計画と最新のトピックスについて報告する。
長田 翔平*; 市田 雄行*; 藤枝 大吾; 青柳 和平
Tunnelling into a Sustainable Future; Methods and Technologies; Proceedings of the ITA-AITES World Tunnel Congress 2025 (WTC 2025), p.3517 - 3524, 2025/05
幌延深地層研究センターの深度500mまでの立坑掘削に先立ち、支保パターン選定のために、覆工コンクリートの強度や厚さ、打設長をさまざまに設定した三次元逐次掘削解析を行い、コンクリートに作用する応力状態を評価した。この結果に基づき、支保パターンを選定し、立坑の掘削を開始した。掘削中のコンクリートに作用する応力の実際の計測結果も参照しながら、東立坑の深度500mまでの掘削を完了させることができた。また、事前の解析や実際のコンクリートに作用する応力の計測結果を踏まえて、適切な支保パターンを選定できることを実証できた。この成果は、立坑掘削を対象とした情報化施工手法の信頼性向上に資するものとなる。
Niu, X.*; Elakneswaran, Y.*; Li, A.*; Seralathan, S.*; 菊池 亮佑*; 平木 義久; 佐藤 淳也; 大杉 武史; Walkley, B.*
Cement and Concrete Research, 190, p.107814_1 - 107814_17, 2025/04
被引用回数:0 パーセンタイル:0.00(Construction & Building Technology)Metakaolin-based geopolymers have attracted significant interest in decontaminating radioactive debris from the Fukushima nuclear accident. This study explored the incorporation of boron (B) into geopolymers using boric acid as the source, with the goal of developing B-enriched geopolymers for enhanced radionuclide immobilisation and neutron capture potential.
明午 伸一郎; 岩元 大樹; 杉原 健太*; 平野 幸則*; 堤 和昌*; 斎藤 滋; 前川 藤夫
JAEA-Technology 2024-026, 123 Pages, 2025/03
J-PARC核変換実験施設ADSターゲット試験施設(TEF-T)の設計をベースとし、J-PARC陽子ビーム照射施設の概念検討を行った。これは、文部科学省の分離変換技術評価タスクフォースの提言「ADSの工学的課題解決に加え、多様なニーズへの対応の可能性を含め、既存のJ-PARCの陽子加速器を利用可能な利点を最大限活用する施設仕様を検討することが望ましい。」を受けたものである。TEF-T設計で不要となった設備を削減する一方、多様なニーズに対応可能な設備の具体化を行った。多様なニーズとして、諸外国の大強度加速器施設の利用法の調査を行った。その結果、1)材料照射試験、2)核破砕中性子を用いた半導体機器のソフトエラー試験、3)医療用RI製造および4)陽子ビーム利用を主な利用目的と特定し、これらの利用に必要な施設の検討を行った。施設概念の検討にあたっては、2022年に施設のユーザーコミュニティを立ち上げ、ユーザーの意見を広く取り入れて施設設計に反映した。本報告書は、陽子ビーム照射施設の概念検討結果、多様なニーズとその対応、施設建設に向けたロードマップおよび今後の課題についてまとめたものである。
江森 達也; 北辻 章浩; 伴 康俊
JAEA-Technology 2024-025, 20 Pages, 2025/03
太陽光発電が期待できない木星以遠の深宇宙探査機用の電源として主にPu-238の崩壊熱を利用した放射性同位体熱電気転換器(RTG: Radioisotope Thermoelectric Generator)が使用されている。しかし、日本国内ではPu-238を生産するための設備が無い上、宇宙利用を目的とした核燃料物質の使用は法規制上の観点から困難である。そこでPu-238の代替として適当な半減期を持つAm-241(半減期: 432年)に注目し、研究目的で貯蔵されている高経年Pu試料中からのAm-241の分離及び精製法について検討を行い、分離回収試験を実施した。分離の方法については固液分離のみと液液分離と固液分離を組み合わせた2パターンの検討を行い、試験を実施した。液液分離と固液分離を組み合わせた場合では、固液分離のみと比べてカラムの本数を1/5以下に抑えられ、試験に要した時間も半分以下に短縮できた。また、得られた試験結果を用いて計6回のPuとAmの分離試験を実施し、約0.43gのAmをシュウ酸塩として分離回収した。
朝日 良光; 福田 茂樹; 白水 大貴; 宮田 晃志; 刀根 雅也; 勝岡 菜々子; 前田 裕太; 青山 雄亮; 新妻 孝一; 小林 秀和; et al.
JAEA-Technology 2024-024, 271 Pages, 2025/03
東海再処理施設で発生した高レベル放射性廃液のガラス固化に用いるTVF3号溶融炉(以下、3号炉)を製作し、この溶融炉でガラス固化体18本分のガラスを溶融・流下するコールド運転を行った。ガラス原料には、ホット運転で処理するものと同等の廃液成分を非放射性元素で置き換えた模擬廃液とガラスファイバーカートリッジを使うことで、溶融ガラス液面に仮焼層を形成させた。TVF2号溶融炉(以下、2号炉)と3号炉の構造の違いに起因する溶融炉固有の温度特性を考慮し、運転操作に用いるパラメータには、2号炉で使ってきたものを修正して適用した。本試験の結果、溶融炉各部の温度推移を確認しながら適切に運転できるパラメータ値を見出すことができ、2号炉のコールド運転に比べ、溶融ガラス温度は高く、二つある主電極の冷却は片側あたり約1kW小さいとき、安定的に運転できることが分かった。主電極間のジュール加熱電力を39kW、主電極冷却空気流量を26Nm /hで運転し炉底加熱方法を改良することで、流下前の炉底加熱時間をこれまでより2時間短い約5時間で完了できる見通しを得た。運転期間中は、炉内のガラス温度分布やケーシング表面の温度推移を計測し、今後のシミュレーションモデル開発に有効なデータが得られた。炉内の溶融ガラスの白金族元素濃度が飽和した後に、原料供給と流下を2日間停止する保持運転を行い、炉底部への白金族元素の沈降を遅らせる一定の効果があることを確認した。保持運転中に仮焼層の溶融過程を観察し、薄膜状の流動しない層が確認されたことから、流動計算で液面にNo-slip境界条件を設定する根拠を得た。流下ガラスの成分を分析して白金族元素の流下特性を調査した結果、運転中に溶融炉に蓄積する白金族元素の量は2号炉と比較して少なかった。溶融ガラスを全量流下した後の炉内には、残留ガラスやレンガ片などの異物は確認されなかった。白金族元素の蓄積による運転停止を判断する基準は、流下終了から炉底ガラス温度850
/hで運転し炉底加熱方法を改良することで、流下前の炉底加熱時間をこれまでより2時間短い約5時間で完了できる見通しを得た。運転期間中は、炉内のガラス温度分布やケーシング表面の温度推移を計測し、今後のシミュレーションモデル開発に有効なデータが得られた。炉内の溶融ガラスの白金族元素濃度が飽和した後に、原料供給と流下を2日間停止する保持運転を行い、炉底部への白金族元素の沈降を遅らせる一定の効果があることを確認した。保持運転中に仮焼層の溶融過程を観察し、薄膜状の流動しない層が確認されたことから、流動計算で液面にNo-slip境界条件を設定する根拠を得た。流下ガラスの成分を分析して白金族元素の流下特性を調査した結果、運転中に溶融炉に蓄積する白金族元素の量は2号炉と比較して少なかった。溶融ガラスを全量流下した後の炉内には、残留ガラスやレンガ片などの異物は確認されなかった。白金族元素の蓄積による運転停止を判断する基準は、流下終了から炉底ガラス温度850 Cへ低下するまでの時間を10.3h以上、主電極間補正抵抗値を0.12
Cへ低下するまでの時間を10.3h以上、主電極間補正抵抗値を0.12 以下と試算したが、今後のホット運転の結果に応じ再検討が必要である。
以下と試算したが、今後のホット運転の結果に応じ再検討が必要である。
富岡 大; 河内山 真美; 小曽根 健嗣; 仲田 久和; 坂井 章浩
JAEA-Technology 2024-023, 38 Pages, 2025/03
日本原子力研究開発機構は、我が国の研究施設等から発生する低レベル放射性廃棄物の浅地中埋設事業の実施主体である。これらの放射性廃棄物の放射能濃度に関する情報は、埋設事業の許可申請及びその適合性審査に向けた廃棄物埋設施設の設計や安全評価に不可欠である。このため、埋設事業センターでは、埋設対象廃棄物のうち試験研究用原子炉から発生する解体廃棄物について、放射化計算に基づく解体廃棄物の放射能評価手順の改良を進めている。今回、多群中性子スペクトルを用いてより精度の高い放射化計算が可能なORIGENコード(SCALE6.2.4に付属)の適用性を検討するため、これまで使用実績が多いORIGEN-Sコード(SCALE6.0に付属)との比較検証を行った。この検証では、炉心周辺の原子炉構造材の放射能分析データを取りまとめている立教大学研究炉の解体廃棄物を対象として両コードにより放射化計算を行った。その結果、ORIGENコードとORIGEN-Sコードの計算時間の差異はほとんどないこと、放射能濃度の評価値として前者は後者の0.8 1.0倍の範囲となり、放射化学分析による放射能濃度と概ね0.5
1.0倍の範囲となり、放射化学分析による放射能濃度と概ね0.5 3.0倍の範囲でよく一致した結果から、ORIGENコードの適用性を確認した。さらに、原子炉構造材に含まれる微量元素の放射化を想定してORIGENコード及びORIGEN-Sコードによる放射化計算を行い、比較を行った。また、浅地中処分における被ばく線量評価上重要な170核種のうち大きな差が見られたものに対してその原因を核種毎に調べた。
3.0倍の範囲でよく一致した結果から、ORIGENコードの適用性を確認した。さらに、原子炉構造材に含まれる微量元素の放射化を想定してORIGENコード及びORIGEN-Sコードによる放射化計算を行い、比較を行った。また、浅地中処分における被ばく線量評価上重要な170核種のうち大きな差が見られたものに対してその原因を核種毎に調べた。