Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
渡部 雅; 横山 佳祐; 今井 良行; 植田 祥平; Yan, X.
Ceramics International, 48(6), p.8706 - 8708, 2022/03
被引用回数:10 パーセンタイル:61.41(Materials Science, Ceramics)SiC, C及びSiC/C傾斜機能材料の焼結は様々な手法が研究されている。しかしながら、放電プラズマ焼結(SPS)法を用いたSiC/黒鉛傾斜機能材料の製造に関する実験的な研究は報告されていない。本研究ではSiC/黒鉛傾斜機能材料をSPS法を用いて作製した。焼結試料の各層の界面にはギャップや層間剥離のような欠陥は見られなかった。また、SiC及び黒鉛はSPS前後で大きな変化を示さなかった。
武田 哲明*; 稲垣 嘉之; 相原 純; 青木 健; 藤原 佑輔; 深谷 裕司; 後藤 実; Ho, H. Q.; 飯垣 和彦; 今井 良行; et al.
High Temperature Gas-Cooled Reactors; JSME Series in Thermal and Nuclear Power Generation, Vol.5, 464 Pages, 2021/02
本書は、原子力機構における今までの高温ガス炉の研究開発の総括として、HTTRの設計、燃料、炉内構造物や中間熱交換器などの要素技術の開発、出力上昇試験、950 Cの高温運転、安全性実証試験などの運転経験及び成果についてまとめたものである。また、HTTRでの知見をもとに、商用炉の設計、高性能燃料、ヘリウムガスタービン、ISプロセスによる水素製造などの要素技術開発の現状について記述しており、今後の高温ガス炉の開発に非常に有用である。本書は、日本機械学会の動力エネルギーシステム部門による化石燃料及び原子力によるエネルギーシステムの技術書のシリーズの一冊として刊行されるものである。
Cの高温運転、安全性実証試験などの運転経験及び成果についてまとめたものである。また、HTTRでの知見をもとに、商用炉の設計、高性能燃料、ヘリウムガスタービン、ISプロセスによる水素製造などの要素技術開発の現状について記述しており、今後の高温ガス炉の開発に非常に有用である。本書は、日本機械学会の動力エネルギーシステム部門による化石燃料及び原子力によるエネルギーシステムの技術書のシリーズの一冊として刊行されるものである。
新里 忠史; 今井 久*; 前川 恵輔; 安江 健一; 操上 広志; 塩崎 功*; 山下 亮*
Proceedings of 19th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE-19) (CD-ROM), 10 Pages, 2011/10
地層処分システムの長期的な安全性にかかわる信頼性を向上させるためには、地質環境の有する安全機能が長期にわたり維持されることを示すための調査・解析手法や事例・論拠の整備が不可欠である。このためには、対象とする地質環境特性の過去から現在に至る変遷の評価が重要である。特に日本列島の沿岸域における地質環境の長期変遷については地層処分の観点からの研究例が少なく、長期的な海水準変動の影響や塩水と淡水の混在など複数の事象を考慮する必要がある。本研究では、北海道北部の幌延地域を事例として地下水流動特性の長期変遷に関する概念モデルを構築し、それに基づく浸透流及び移流分散解析を実施した。その結果、海水準や海岸線位置の変動等の境界条件の変化に対して、全水頭やダルシー流速等の地下水流動特性は応答性が高いものの、地下水中の物質移動を間接的に示す塩分濃度は応答性が低く、これらの応答性は地層・岩盤の透水性に依存することが明らかとなった。また、沿岸域における地下水流動特性と地下水の地球化学特性は、沿岸域の平野部と丘陵部とで異なる変遷を経る可能性を示すことができた。
玉田 太郎; 木下 誉富*; 栗原 和男; 安達 基泰; 大原 高志; 今井 啓祐*; 黒木 良太; 多田 俊治*
Journal of the American Chemical Society, 131(31), p.11033 - 11040, 2009/07
被引用回数:61 パーセンタイル:79.67(Chemistry, Multidisciplinary)セリンプロテアーゼの触媒機構を理解することを目的として、ブタ膵臓エラスターゼの高分解能中性子及びX線構造解析を正四面体型中間体を模倣する阻害剤と複合体の状態で実施した。同一の大型単結晶を用いた室温における測定の結果、1.65 分解能の中性子回折データ及び1.2
分解能の中性子回折データ及び1.2 分解能のX線回折データを取得した。また、別の結晶を用いて100K下で0.94
分解能のX線回折データを取得した。また、別の結晶を用いて100K下で0.94 分解能のX線回折データも併せて取得した。今回の解析は、セリンプロテアーゼとしてはこれまでで最も高分解能で実施された中性子構造解析例である。中性子とX線の両解析結果から、His57とAsp102の間に形成された水素結合は結合距離が2.60
分解能のX線回折データも併せて取得した。今回の解析は、セリンプロテアーゼとしてはこれまでで最も高分解能で実施された中性子構造解析例である。中性子とX線の両解析結果から、His57とAsp102の間に形成された水素結合は結合距離が2.60 と短く、強い水素結合であると判明したものの、水素原子はHis57に結合していた。この結果は、一説として唱えられている低障壁水素結合の特徴(水素原子がドナーとアクセプターの中間付近に存在する)は満たすものではなく、低障壁水素結合仮説を否定するものであった。また、中性子解析結果から、いわゆるオキシアニオンホールの形成とオキシアニオンホール中に阻害剤由来の酸素原子が酸素陰イオンの状態で存在していることが明瞭に示された。これより、セリンプロテアーゼの触媒機構において正四面体型中間体構造の安定化に対するオキシアニオンホールの役割が明らかになった。
と短く、強い水素結合であると判明したものの、水素原子はHis57に結合していた。この結果は、一説として唱えられている低障壁水素結合の特徴(水素原子がドナーとアクセプターの中間付近に存在する)は満たすものではなく、低障壁水素結合仮説を否定するものであった。また、中性子解析結果から、いわゆるオキシアニオンホールの形成とオキシアニオンホール中に阻害剤由来の酸素原子が酸素陰イオンの状態で存在していることが明瞭に示された。これより、セリンプロテアーゼの触媒機構において正四面体型中間体構造の安定化に対するオキシアニオンホールの役割が明らかになった。
今井 久*; 山下 亮*; 塩崎 功*; 浦野 和彦*; 笠 博義*; 丸山 能生*; 新里 忠史; 前川 恵輔
JAEA-Research 2009-001, 116 Pages, 2009/03
地層処分システムの長期挙動予測の信頼性を向上させるためには、隆起・侵食や気候・海水準変動等の天然現象の影響を考慮した地下水流動のモデル化が重要である。このため、(1)天然現象の影響を組み入れた地下水流動解析手法の高度化,(2)現実的な地質構造や涵養量などを反映した地下水流動解析に基づき、(3)地下水流動に影響を及ぼす天然現象の感度解析を行った。(1)地下水流動への地質環境の長期変遷の影響を連続的にモデル化するシステムを考案した結果、課題であったモデル形状が変化する際の解の不連続性を低減できることを確認した。(2)地層の応力状態の変化による過剰間隙水圧の発生には間隙率や有効応力に対応した透水係数の設定が重要であること、氷期の涵養量の影響は丘陵部や沿岸域で見られること、塩分の密度差の影響は沿岸域で見られ、地下深部への淡水の侵入を抑制することが判明した。(3)断層の2種類の形状について透水係数に関する感度解析を実施したが、設定した条件では深度約500mまでの影響は顕著でないことを示した。
木下 誉富*; 玉田 太郎; 今井 啓介*; 栗原 和男; 大原 高志; 黒木 良太
Acta Crystallographica Section F, 63(4), p.315 - 317, 2007/04
被引用回数:8 パーセンタイル:65.83(Biochemical Research Methods)ブタ膵臓エラスターゼは、炎症性疾患の原因となる好中球エラスターゼによく似た特徴を有することから、代表的な創薬標的タンパク質の一つである。エラスターゼに共有結合した阻害剤の水素原子を含む構造的な特徴を調べるために、蒸気拡散法により0.2M硫酸ナトリウムを含む重水緩衝液(pD=5.0)中で1.6mm の大きさの単結晶を作製した。この結晶を用いることにより原子力機構のJRR-3に設置されたBIX3中性子回折計で測定を行った結果、空間群P212121,格子長a=51.2
の大きさの単結晶を作製した。この結晶を用いることにより原子力機構のJRR-3に設置されたBIX3中性子回折計で測定を行った結果、空間群P212121,格子長a=51.2 , b=57.8
, b=57.8 , c=75.6
, c=75.6 , 2.3
, 2.3 分解能の中性子回折データの取得に成功した。
分解能の中性子回折データの取得に成功した。
山本 巧; 牛草 健吉; 坂本 慶司; 今井 剛; 宮 直之; 栗田 源一; 永島 圭介; 北井 達也*; 森 活春*; 菊池 満; et al.
JAERI-Research 97-006, 77 Pages, 1997/02
ECRF加熱装置には、初期プラズマ電流立ち上げ補助及び高磁場中第一壁洗浄用プラズマ生成機能を有するECR予備電離/放電洗浄装置とプラズマ加熱及び電流駆動を効果的に行い、高性能な炉心プラズマを定常的に安定に維持する機能を有する電子サイクロトロン加熱(ECH)装置がある。これらの2つのタイプのECRF加熱装置について、定常炉心試験装置におけるトリチウム取扱の安全性また放射線遮蔽と深く関係するアンテナシステム及び主要コンポーネント(ジャイロトロン)の製作を重点的に設計検討を行った。その結果、これらのECRF加熱装置はいずれも技術的に成立することが可能であることが明らかとなった。本報告書では、これらの概念検討結果を示すものである。
池田 佳隆; 内藤 磨; 牛草 健吉; 佐藤 正泰; 近藤 貴; 井手 俊介; 関 正美; 永島 圭介; S.W.Wolfe*; 朝倉 伸幸; et al.
Nuclear Fusion, 34(6), p.871 - 880, 1994/00
被引用回数:15 パーセンタイル:49.91(Physics, Fluids & Plasmas)JT-60において低域混成波電流駆動(LHCD)におけるLH波の近接条件の影響を調べ、以下の結果を得た。1)硬H,X線の最大検出エネルギーは、近接条件で制限される波の位相速度と対応している。2)電流駆動効率、電流分布制御性は、近接条件の劣化に伴い悪化する。3)近接しない波(非近接波)を入射すると、不純物、リサイクルを増加させ、MARFEを引き起こす場合もある。4)ダイバータ部の静電プローブを利用した周辺部の波の強度は、非近接の割合に比例して増加する。5)非近接波は、波の軌跡解析から周辺部に局在する。これらのことから、LHCDにおいて近接条件の重要性が実験的に明らかとなった。
今井 剛; 牛草 健吉; 池田 佳隆; 内藤 磨; 吉田 英俊; 関 正美; 伊丹 潔; 永島 圭介; 上原 和也; 永島 孝
核融合研究, 65(SPECIAL ISSUE), p.99 - 118, 1991/03
低域混成波帯(LHRF)の電流駆動実験を行い、2MA、3秒の非誘導電流駆動、最大電流駆動積(ne・R ・I
・I )~12.5
)~12.5 10
10 m
m MAを実現した。ダイバータ配位が、ホットスポットを抑制するのに有効である。電流駆動効率を改善するには、高Te、低有効電荷数が良いことがわかるとともに、マルチジャンクション型の結合系を用いることにより、磁場方向の屈折率(N
MAを実現した。ダイバータ配位が、ホットスポットを抑制するのに有効である。電流駆動効率を改善するには、高Te、低有効電荷数が良いことがわかるとともに、マルチジャンクション型の結合系を用いることにより、磁場方向の屈折率(N )のスペクトルを最適化することが有効であることを実験的に示し、通常の電流駆動用結合系に比し、30~40%の改善を達成するとともに、最大3.4
)のスペクトルを最適化することが有効であることを実験的に示し、通常の電流駆動用結合系に比し、30~40%の改善を達成するとともに、最大3.4 10
10 m
m A/Wの電流駆動効率を実現した。低域混成波電流駆動により電流分布制御、及び、鋸歯状振動の抑制が可能であること、また、電流立上げ時の磁束節約が可能であることを、明らかにした。
A/Wの電流駆動効率を実現した。低域混成波電流駆動により電流分布制御、及び、鋸歯状振動の抑制が可能であること、また、電流立上げ時の磁束節約が可能であることを、明らかにした。
辻 俊二; 牛草 健吉; 池田 佳隆; 今井 剛; 伊丹 潔; 根本 正博; 永島 圭介; 小出 芳彦; 河野 康則; 福田 武司; et al.
Physical Review Letters, 64(9), p.1023 - 1026, 1990/02
被引用回数:56 パーセンタイル:88.32(Physics, Multidisciplinary)トカマクのリミタ放電において、低域混成波電流駆動によるHモードが世界で初めて実現された。1.74+2.23GHzや1.74+2.0GHzのように、2つの異なる周波数で高周波パワーを加えるのが、Hモード達成に効果的である。水素プラズマにおいて高周波パワーのしきい値は1.2MWであり、ジュール加熱パワーと同等であるくらい低い。プラズマ表面に局在化した不安定性をともなわない準定常状態が、顕著な不純物の蓄積を起こすことなく最大3.3秒間持続した。エネルギー閉じ込め時間の改善は最大30%であるが、それは粒子閉じ込め改善による電子密度上昇で大部分嫁いでいる。高周波パワーがビームイオンに吸収されるとHモードからLモードに遷移することから、低域混成波によって発生する高速電子がHモード実現に有利に働いている可能性がある。
牛草 健吉; 今井 剛; 池田 佳隆; 坂本 慶司; F.X.Soeldner*; 高瀬 雄一*; 辻 俊二; 清水 勝宏; 内藤 磨; 上原 和也; et al.
Nuclear Fusion, 29(2), p.265 - 276, 1989/02
被引用回数:17 パーセンタイル:58.16(Physics, Fluids & Plasmas)線平均電子密度 3.5
3.5 10
10 m
m で20HWのNB加熱プラズマに、6MWまでのLHWを加えた結果、NB加熱時と同じ加熱効率でプラズマ蓄積エネルギーの上昇が見られた。この時、電子、イオン温度の上昇に加え、NBの入射エネルギー以上の高速イオンが生成されている。同じ密度領域のLH単独加熱では著しく高速電子が発生するのに対し、複合加熱時には高速電子の発生が抑制されている。
で20HWのNB加熱プラズマに、6MWまでのLHWを加えた結果、NB加熱時と同じ加熱効率でプラズマ蓄積エネルギーの上昇が見られた。この時、電子、イオン温度の上昇に加え、NBの入射エネルギー以上の高速イオンが生成されている。同じ密度領域のLH単独加熱では著しく高速電子が発生するのに対し、複合加熱時には高速電子の発生が抑制されている。
牛草 健吉; 今井 剛; 池田 佳隆; 坂本 慶司; F.X.Soldner*; 高瀬 雄一*; 辻 俊二; 清水 勝宏; 内藤 磨; 上原 和也; et al.
JAERI-M 88-115, 28 Pages, 1988/06
20MWの中性粒子ビーム(NB)で加熱された、線平均電子密度 3.5
3.5 10
10 m
m のプラズマに6MWまでの低域混成波を入射した結果、NB単独時と同じインクリメンタルエネルギー閉じ込め時間でプラズマの蓄積エネルギーが増大した。この時、電子温度、イオン温度の上昇とともに低域混成波が入射されたビームイオンを加速するのが観測された。同じ密度領域での低域混成波単独加熱時には、著しい高速電子の発生があるのに対し、複合加熱時には高速電子の発生が抑制される。複合加熱時の低域混成波の加熱高率は電子密度の上昇とともに減少するが、Ray軌跡解析の結果、この依存性は近接条件によるものと推定される。ビームイオンの寄与を考慮した波の減衰の評価の結果、複合加熱時には波が電子に吸収される前にビームイオンに吸収されることが示された。
のプラズマに6MWまでの低域混成波を入射した結果、NB単独時と同じインクリメンタルエネルギー閉じ込め時間でプラズマの蓄積エネルギーが増大した。この時、電子温度、イオン温度の上昇とともに低域混成波が入射されたビームイオンを加速するのが観測された。同じ密度領域での低域混成波単独加熱時には、著しい高速電子の発生があるのに対し、複合加熱時には高速電子の発生が抑制される。複合加熱時の低域混成波の加熱高率は電子密度の上昇とともに減少するが、Ray軌跡解析の結果、この依存性は近接条件によるものと推定される。ビームイオンの寄与を考慮した波の減衰の評価の結果、複合加熱時には波が電子に吸収される前にビームイオンに吸収されることが示された。
横堀 伸一*; 河口 優子*; Yang, Y.*; 川尻 成俊*; 白石 啓祐*; 清水 康之*; 高橋 勇太*; 杉野 朋弘*; 鳴海 一成; 佐藤 勝也; et al.
no journal, ,
熱圏を周回するInternational Space Station (ISS)を利用し、極限環境における微生物存在の検証実験を行うことを計画している。超低密度エアロゲルを長期間曝露し、惑星間塵や宇宙デブリを含む微粒子を捕集する。捕集された微粒子とそれが形成する衝突痕に対して、微生物又は微生物関連生体高分子の検出を試み、ISS軌道での地球由来微生物の存在密度の上限を推定する。また、微生物を宇宙曝露することにより、微生物の宇宙環境での生存可能性と生存に影響を与える環境因子について推定を行う。宇宙曝露実験に用いる微生物として、現在、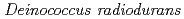 (R1株とDNA修復系変異株),
(R1株とDNA修復系変異株),  TR0125,
TR0125,  ST0316,
ST0316,  sp. HK-01,
sp. HK-01,  JY3を検討している。実際の運用では、同装置は汎用曝露装置に固定され、きぼう与圧部エアロックからロボットアームによって同曝露部に設置され、一定時間曝露された後に再度同ルートで回収、有人帰還船に搭載して地球に帰還する予定である。
JY3を検討している。実際の運用では、同装置は汎用曝露装置に固定され、きぼう与圧部エアロックからロボットアームによって同曝露部に設置され、一定時間曝露された後に再度同ルートで回収、有人帰還船に搭載して地球に帰還する予定である。
玉田 太郎; 木下 誉富*; 大原 高志; 栗原 和男; 今井 啓介*; 黒木 良太; 多田 俊治*
no journal, ,
エラスターゼは、立体構造情報を基盤とした創薬手法(Structure-Based Drug Design: SBDD)研究の代表的な題材として用いられてきたセリンプロテアーゼである。しかしながら、X線結晶構造に基づいた多くのSBDD研究の実施にもかかわらず、特異性の高い阻害剤の作製が困難であるのが現状である。よって、エラスターゼの全原子構造情報の取得を目指して、エラスターゼとその阻害剤(FR130180)の中性子結晶構造解析を実施した。試料にはブタ膵臓由来のエラスターゼ(Porcine Pancreatic Elastase: PPE)を用い、FR130180との複合体結晶を作製した。取得した結晶はマクロシーディング法を繰り返すことにより3mm 程度まで成長させた後、JRR3に設置した生体高分子用中性子回折計BIX3で回折実験を行い、1.65
程度まで成長させた後、JRR3に設置した生体高分子用中性子回折計BIX3で回折実験を行い、1.65 分解能の回折データを収集した。中性子とX線回折データを組合せた精密化により、約2000個の水素及び重水素原子を含むPPEとFR130180の複合体構造を決定した。今回用いた阻害剤FR130180は、エラスターゼの基質を模倣したペプチド様の構造を持っており、PPEとFR130180複合体はセリンプロテアーゼの反応中間体状態を示していると考えられ、セリンプロテアーゼの触媒機構の理解を深めることができた。また、阻害剤とPPE間に、興味深い相互作用の形成も確認され、特異性の高い阻害剤設計に有用な構造情報を取得することができた。
分解能の回折データを収集した。中性子とX線回折データを組合せた精密化により、約2000個の水素及び重水素原子を含むPPEとFR130180の複合体構造を決定した。今回用いた阻害剤FR130180は、エラスターゼの基質を模倣したペプチド様の構造を持っており、PPEとFR130180複合体はセリンプロテアーゼの反応中間体状態を示していると考えられ、セリンプロテアーゼの触媒機構の理解を深めることができた。また、阻害剤とPPE間に、興味深い相互作用の形成も確認され、特異性の高い阻害剤設計に有用な構造情報を取得することができた。
前川 恵輔; 新里 忠史; 今井 久*; 塩崎 功*; 山下 亮*
no journal, ,
高レベル放射性廃棄物処分の安全性を評価するうえで、地質環境の長期変遷に伴う地下水流動への影響を把握することが重要である。著者らは、地質環境の長期変遷を考慮した地下水流動解析手法の開発として、地下水流動に対する影響が大きいと考えられる鉛直方向の地形・地質構造の変化(変形)とともに、海水準やかん養量の変動などの地下水流動への影響を評価するための解析手法を開発してきた。しかし、実際の地形・地質構造の変化は水平方向にも変化することから、そうした変化を考慮可能な解析手法の開発が課題であった。今回、これまでの手法を改良し、鉛直及び水平方向の地形・地質構造の変化を考慮した仮想的なモデルへの適用性を確認したので報告する。
横堀 伸一*; 河口 優子*; Yang, Y.*; 川尻 成俊*; 白石 啓祐*; 清水 康之*; 高橋 勇太*; 杉野 朋弘*; 鳴海 一成; 佐藤 勝也; et al.
no journal, ,
地地球以外の天体に生命(又はその痕跡)を探そうとする研究、探査が盛んに行われるようになってくるとともに、「パンスペルミア仮説」が再考されている。そのようなパンスペルミアがそもそも可能であるかを検討するため、微生物の宇宙空間曝露実験による生命の宇宙空間での長期間生存可能性の検証が行われてきた。われわれは、ISS-JEM(国際宇宙ステーション・日本実験棟)曝露部上での微生物と生命材料となり得る有機化合物の天体間の移動の可能性の検討と微小隕石の検出及び解析実験を提案し[たんぽぽ:有機物・微生物の宇宙曝露と宇宙塵・微生物の捕集]、2013年度に実験開始を実現するため、準備を進めている。超低密度エアロゲルを長期間(1年以上)曝露し、惑星間塵や宇宙デブリを含む微粒子を捕集するとともに、新規に開発したエアロゲルの利用可能性を検証する。捕集された微粒子とそれが形成する衝突痕(トラック)に対して、微生物又は微生物関連生体高分子(DNA等)の検出を試み、ISS軌道(高度約400km)での地球由来微生物の存在密度の上限を推定する。また、微生物を宇宙曝露することにより、微生物の宇宙環境での生存可能性と生存に影響を与える環境因子について推定を行う。
前川 恵輔; 新里 忠史; 今井 久*; 塩崎 功*; 山下 亮*
no journal, ,
高レベル放射性廃棄物等の地層処分における数万年を超える長期の安全性を評価するうえで必要な、地形や地質構造,気候や海水準変動などの地質環境の長期的な変遷を考慮した地下水流動を把握するための手法の信頼性の向上を目的として、解析における時間ステップ間の解析値の不連続性を緩和するための解析手法の改良を行った。また、断層の形状等の解析結果への影響についての検討を、幌延深地層研究計画で取得した情報等に基づいて行った。その結果、解析手法の改良の効果を確認するとともに、時間間隔の細分化による影響等を踏まえた適切な時間間隔の設定の重要性が明らかとなった。また、断層が地表付近まで達している場合では地下深部の全水頭が相対的に低い傾向を示すなどの影響を確認した。今後、現地調査結果に基づいて解析手法の妥当性を確認し、解析手法の最適化を図る。
新里 忠史; 前川 恵輔; 安江 健一; 浅森 浩一; 操上 広志; 今井 久*; 塩崎 功*
no journal, ,
地層処分にとって重要な地質環境の特性やプロセスの時間変化について、調査・解析・評価を体系的に進めるための手法の整備を目的として、北海道北部の幌延地域を事例にgeosynthesis methodologyを適用し、得られた知見や問題点を整理した。その結果、データフローダイアグラムを用いることにより、調査・解析・評価にいたる具体的なデータの流れを示すことができるとともに、必要な情報を漏れなく網羅的に取得しつつ調査研究を進めることが可能であるとの見通しを得た。また、相互作用マトリクスを用いることにより、地層処分にとって重要な地質環境の特性やプロセス、及びそれらに変化をもたらすことが想定される天然現象の発生様式や傾向について、それらの相互作用を網羅的に記述し整理することができた。
前川 恵輔; 新里 忠史; 操上 広志; 浅森 浩一; 今井 久*; 塩崎 功*
no journal, ,
地層処分における安全評価は万年オーダーの長期に渡る期間を対象としている。こうした長期間で影響が顕在化する隆起・侵食や気候・海水準変動などの天然現象は、安全評価において重要となる地下深部の地下水流動や水質分布などに影響を与えることが考えられる。そのため、安全評価手法の信頼性を向上する観点においては、天然現象の長期的な変動が地質環境に与える影響を検討することが重要となっている。そこで、天然現象が地質環境に与える影響を理解するための一環として、気候・海水準変動が地下水流動に与える影響を、北海道幌延地域を事例として解析的に検討した。解析の結果、海水準変動に伴う陸部の地下水位や塩分濃度の空間分布の変化などが推定された。
今井 久*; 塩崎 功*; 山下 亮*; 操上 広志; 新里 忠史; 前川 恵輔; 安江 健一
no journal, ,
地下深部の地下水流動場は地形や地質,気候の変化など自然現象の長期的変遷の影響を受けており、現在の流動場を理解し、将来の流動場を予測するには、これらの影響を考慮する必要がある。特に、高レベル放射性廃棄物の地層処分における安全評価では、数10万年以上の期間を対象にすることから、自然現象の影響を考慮した地下水流動場の評価が必要となる。そこで、この安全評価に必要な地下水流動場を評価する手法の開発の一環として、堆積時から現在までの自然現象の変遷が調査されている北海道幌延地域について、地形・地質構造の変化を考慮した地下水流動解析を試みた。