Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
森田 健司; 森本 誠; 久田 雅樹; 福井 康太
JAEA-Technology 2015-037, 28 Pages, 2016/01
重水臨界実験装置(DCA)は昭和44年に初臨界を迎えて以来、数多くの炉物理データの取得により、新型転換炉原型炉「ふげん」及び同実証炉の研究開発に大きく寄与した後、平成13年9月を以てすべての運転を停止した。その後、解体届を平成14年1月(廃止措置計画の認可は平成18年10月)に提出し、廃止措置に移行した。DCAの廃止措置工程は4段階に分類され、施設の本格解体を行う第3段階「原子炉本体等の解体撤去」は、平成20年度に開始し、現在、平成34年度の完了を目指して工事を継続中である。本報では平成25年度に実施した解体実績及び解体に係る各種データ等についての評価取りまとめ結果を報告するものである。
 O
O -SiO
-SiO including CrPO
including CrPO , Out-of-pile tests
, Out-of-pile testsKulsartov, T. V.*; 林 君夫; 中道 勝*; Afanasyev, S. E.*; Shestakov, V. P.*; Chikhray, Y. V.*; Kenzhin, E. A.*; Kolbaenkov, A. N.*
Fusion Engineering and Design, 81(1-7), p.701 - 705, 2006/02
被引用回数:46 パーセンタイル:92.99(Nuclear Science & Technology)核融合炉構造材料へのセラミック被覆は、トリチウム透過防止膜として使用されることが考えられている。本研究では、リン酸クロム(CrPO )を含む酸化クロム-二酸化ケイ素のセラミック皮膜がある場合とない場合におけるF82H鋼について、水素及び重水素透過実験を行った。まず第1段階として、300
)を含む酸化クロム-二酸化ケイ素のセラミック皮膜がある場合とない場合におけるF82H鋼について、水素及び重水素透過実験を行った。まず第1段階として、300 600
600 Cの100
Cの100 1000Paの水素及び重水素雰囲気において、皮膜のないF82H鋼中の透過実験を行った。得られた拡散係数,透過定数及び溶解度は、以前に公刊されている値と良い一致を示した。第2段階としては、皮膜を施したF82H鋼中について、400
1000Paの水素及び重水素雰囲気において、皮膜のないF82H鋼中の透過実験を行った。得られた拡散係数,透過定数及び溶解度は、以前に公刊されている値と良い一致を示した。第2段階としては、皮膜を施したF82H鋼中について、400 600
600 C, 1000
C, 1000 1500Paの重水素雰囲気において、上と同様な透過実験を行い、皮膜の透過低減係数(PRF)を算出した。600
1500Paの重水素雰囲気において、上と同様な透過実験を行い、皮膜の透過低減係数(PRF)を算出した。600 Cにおける透過低減係数は約400であった。この値は、同じ皮膜を316ステンレス鋼に施した場合の透過低減係数(約1000)に匹敵する値である。本発表は、国際科学技術センター(ISTC)によるパートナープロジェクト(K-1047p)として実施した研究の成果の一部を発表するものである。
Cにおける透過低減係数は約400であった。この値は、同じ皮膜を316ステンレス鋼に施した場合の透過低減係数(約1000)に匹敵する値である。本発表は、国際科学技術センター(ISTC)によるパートナープロジェクト(K-1047p)として実施した研究の成果の一部を発表するものである。
林 孝夫; 落合 謙太郎; 正木 圭; 後藤 純孝*; 沓掛 忠三; 新井 貴; 西谷 健夫; 宮 直之
Journal of Nuclear Materials, 349(1-2), p.6 - 16, 2006/02
被引用回数:10 パーセンタイル:55.89(Materials Science, Multidisciplinary)核反応分析法(NRA)を用いてJT-60Uダイバータ部のプラズマ対向壁に用いられている炭素タイル中の重水素保持量深さ分布を測定した。最も重水素濃度が高かったのは外側ドームウィングタイルでD/ Cの値は0.053であり、その重水素蓄積過程は炭素-重水素の共堆積によるものと推定された。また外側及び内側のダイバータターゲットタイルにおいてはD/
Cの値は0.053であり、その重水素蓄積過程は炭素-重水素の共堆積によるものと推定された。また外側及び内側のダイバータターゲットタイルにおいてはD/ Cは0.006以下であった。軽水素を含めた水素同位体の濃度については、NRA及びSIMS分析結果からドーム頂部タイルの(H+D)/
Cは0.006以下であった。軽水素を含めた水素同位体の濃度については、NRA及びSIMS分析結果からドーム頂部タイルの(H+D)/ Cを0.023と推定した。一方OFMC計算を用いてNBIで入射した高エネルギー重水素がドーム領域に打ち込まれることを示した。また重水素の打ち込みや炭素との共堆積などによる重水素蓄積は、タイルの表面温度や損耗・堆積などの表面状態の影響を受けることを示した。重水素保持量深さ分布,SEM分析及びOFMC計算により、重水素分布はおもに重水素-炭素の共堆積,重水素イオンの打ち込み及びバルクへの拡散の複合したプロセスにより決まることを明らかにした。
Cを0.023と推定した。一方OFMC計算を用いてNBIで入射した高エネルギー重水素がドーム領域に打ち込まれることを示した。また重水素の打ち込みや炭素との共堆積などによる重水素蓄積は、タイルの表面温度や損耗・堆積などの表面状態の影響を受けることを示した。重水素保持量深さ分布,SEM分析及びOFMC計算により、重水素分布はおもに重水素-炭素の共堆積,重水素イオンの打ち込み及びバルクへの拡散の複合したプロセスにより決まることを明らかにした。
Luo, G.; 洲 亘; 西 正孝
Journal of Nuclear Materials, 347(1-2), p.111 - 117, 2005/12
被引用回数:90 パーセンタイル:98.10(Materials Science, Multidisciplinary)鏡面仕上げした焼結材タングステン試料片にITERダイバータ周辺プラズマを模擬する重水素プラズマを照射し、そのブリスタリング挙動を調べた。今回行った照射の条件は、フラックス:1 10
10 D/m
D/m /s,エネルギー:7
/s,エネルギー:7 98eV/D,フルエンス:3
98eV/D,フルエンス:3 10
10
 6
6 10
10 D/m
D/m ,照射温度:室温であるが、いずれのエネルギーの照射においても、ブリスタリングの発生がSEM観察により確認された。また、ブリスタリング発生のフルエンス閾値が入射エネルギーの減少とともに増加すること、特に20eV/D以下の入射エネルギーの場合には、この閾値の増加が著しいことを見いだした。本現象は、試料表面に酸化皮膜が存在し、重水素の外部への再放出と内部への侵入に影響を及ぼしていると考えることによって説明できる。さらに、ブリスタの寸法と数はフルエンスの増加とともに初期にはいずれも増加するが、直径が2
,照射温度:室温であるが、いずれのエネルギーの照射においても、ブリスタリングの発生がSEM観察により確認された。また、ブリスタリング発生のフルエンス閾値が入射エネルギーの減少とともに増加すること、特に20eV/D以下の入射エネルギーの場合には、この閾値の増加が著しいことを見いだした。本現象は、試料表面に酸化皮膜が存在し、重水素の外部への再放出と内部への侵入に影響を及ぼしていると考えることによって説明できる。さらに、ブリスタの寸法と数はフルエンスの増加とともに初期にはいずれも増加するが、直径が2 m程度に逹すると成長が止まり、数のみが増加していく結果を得た。本結果は、ブリスタが2
m程度に逹すると成長が止まり、数のみが増加していく結果を得た。本結果は、ブリスタが2 m程度に成長すると亀裂が発生して内部のガスが放出されるため、と考えられる。
m程度に成長すると亀裂が発生して内部のガスが放出されるため、と考えられる。
安藤 麻里子; 熊倉 康治*; 天野 光; 福井 正美*
Fusion Science and Technology, 48(1), p.771 - 774, 2005/07
被引用回数:3 パーセンタイル:23.49(Nuclear Science & Technology)イネによるトリチウムの取り込み量は、成長段階のどの時期にトリチウムに曝露されたかにより大きく異なることが報告されている。本研究では、可食部への移行量が増える出穂から収穫までの期間をさらに細分化し、各段階におけるトリチウム取り込み量と収穫時までの残留の違いを明らかにすることを目的とした。実験ではトリチウムの代わりに安定同位体である重水を使用し、光量及び温湿度を制御した室内チェンバー内で鉢植えの稲に対し重水水蒸気を4時間曝露した。曝露後、稲を直ちに屋外に移して、定期的に試料を採取しながら収穫時まで栽培し、穂,葉,茎中の重水濃度を測定した。穂中有機態重水素(OBD)の生成量は穂の成長量の大きい出穂後初期の段階で最も高かった。出穂後26日以降に曝露した場合には、葉から穂へのOBDの移行がみられず、穂のOBD上昇はごくわずかにとどまった。
上田 良夫*; 井上 多加志; 栗原 研一
日本原子力学会誌, 46(12), p.845 - 852, 2004/12
核融合開発の現状と今後の展望を、核融合分野外の日本原子力学会会員に理解してもらうことを目的とした、原子力学会核融合工学部会企画の連載講座の第1回である。最も実現に近い核融合炉として、DT反応を用いたトカマク型炉を取り上げ、エネルギー発生に必要な炉心プラズマ条件を概説する。また安全性,廃棄物,トリチウム,環境負荷,必要資源,建設コストの観点から核融合炉の特徴と課題を議論するとともに、トカマク型核融合炉の構成機器を紹介する。
Gordon, E. B.*; 熊田 高之; 石黒 正純; 荒殿 保幸
Journal of Experimental and Theoretical Physics, 99(4), p.776 - 783, 2004/10
固体ヘリウム中への重水素分子のドープ法の開発と、1.3K, 3Mpaの固体ヘリウム中にドープされた重水素クラスターのCARS(Coherent anti-Stokes Raman spectroscopy)法による分光研究を行った。ドープされた重水素のオルト,パラ体の含有量,クラスターサイズを関数としてスペクトルの、強度,線幅,シフト等を検討し、オルト,パラ体のラマン散乱断面積の比が、気相とは10000倍異なることなどを明らかにした。
 resolution
resolution茶竹 俊行*; 栗原 和男; 田中 伊知朗*; Tsyba, I.*; Bau, R.*; Jenney, F. E. Jr.*; Adams, M. W. W.*; 新村 信雄
Acta Crystallographica Section D, 60(8), p.1364 - 1373, 2004/08
被引用回数:34 パーセンタイル:88.49(Biochemical Research Methods)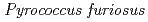 由来ルブレドキシンの高い熱安定性の起源を明らかにするため、その変異型に対する1.6
由来ルブレドキシンの高い熱安定性の起源を明らかにするため、その変異型に対する1.6 分解能中性子結晶構造解析(重水中で結晶育成)を生体高分子用中性子回折装置BIX-3(原研原子炉JRR-3内設置)を用いて行った。
分解能中性子結晶構造解析(重水中で結晶育成)を生体高分子用中性子回折装置BIX-3(原研原子炉JRR-3内設置)を用いて行った。 由来ルブレドキシンは、通常の熱安定性を持つ常温菌由来のルブレドキシンと異なるアミノ酸残基部分を持つ。そこで、その中で重要と考えられる3つの残基を常温菌のものに変えた変異型を発現させ、その水素結合パターンを変異の無い野生型と比較した。その結果、変異を行った残基の一つで水素結合パターンの違いが明らかになった。これをもとに熱安定性の議論を行った。一方で、このタンパク質の水素/重水素置換率の詳細も調べた。その結果、ルブレドキシンの鉄-硫黄中心(酸化還元機能を司る)にかかわる4つのシステイン残基周辺は、最も水素/重水素置換が進んでいないということがわかった。これはこの周囲の構造が安定であることを示唆している。加えて、この高分解能な中性子構造解析により、水和水の秩序性も含めた詳細な水和構造が明らかになった。
由来ルブレドキシンは、通常の熱安定性を持つ常温菌由来のルブレドキシンと異なるアミノ酸残基部分を持つ。そこで、その中で重要と考えられる3つの残基を常温菌のものに変えた変異型を発現させ、その水素結合パターンを変異の無い野生型と比較した。その結果、変異を行った残基の一つで水素結合パターンの違いが明らかになった。これをもとに熱安定性の議論を行った。一方で、このタンパク質の水素/重水素置換率の詳細も調べた。その結果、ルブレドキシンの鉄-硫黄中心(酸化還元機能を司る)にかかわる4つのシステイン残基周辺は、最も水素/重水素置換が進んでいないということがわかった。これはこの周囲の構造が安定であることを示唆している。加えて、この高分解能な中性子構造解析により、水和水の秩序性も含めた詳細な水和構造が明らかになった。
落合 謙太郎; 林 孝夫; 沓掛 忠三; 後藤 純孝*; 正木 圭; 新井 貴; 宮 直之; 西谷 健夫
Journal of Nuclear Materials, 329-333(Part1), p.836 - 839, 2004/08
被引用回数:4 パーセンタイル:28.64(Materials Science, Multidisciplinary)FNSでは重陽子加速器ビームによる核反応分析法を用いて、黒鉛実機ダイバータ表面のDとTの保持量及び深さ分布について測定を行った。測定対象である黒鉛ダイバータは2つである。利用核反応と検出荷電粒子はD分布測定の場合、D(d,p)T核反応によるプロトン粒子を、T分布測定の場合はT(d, )n核反応による
)n核反応による 粒子である。D(d,p)T核反応によるプロトンとトリトン及び
粒子である。D(d,p)T核反応によるプロトンとトリトン及び C(d,p)
C(d,p) Cのプロトンのスペクトルピークが得られており、その検出エネルギーは計算で求まる試料表面からの放出エネルギーとよく一致していることから、重水素が試料表面から
Cのプロトンのスペクトルピークが得られており、その検出エネルギーは計算で求まる試料表面からの放出エネルギーとよく一致していることから、重水素が試料表面から mオーダーで深く堆積していることが明らかとなった。これらの収量から重水素の平均保持量は内側ダイバータで約1
mオーダーで深く堆積していることが明らかとなった。これらの収量から重水素の平均保持量は内側ダイバータで約1 10
10 cm
cm であり、トリチウムベータ線の放射能は18kBq/cm
であり、トリチウムベータ線の放射能は18kBq/cm に相当するという結果を得た。また350keV入射のみアルファスペクトルを得ている結果から、トリチウムの深さ分布については母材2
に相当するという結果を得た。また350keV入射のみアルファスペクトルを得ている結果から、トリチウムの深さ分布については母材2 mより深い位置にあると考えられる。
mより深い位置にあると考えられる。
杉江 達夫; 河西 敏; 谷口 正樹; 永津 雅章*; 西谷 健夫
Journal of Nuclear Materials, 329-333(2), p.1481 - 1485, 2004/08
被引用回数:30 パーセンタイル:85.09(Materials Science, Multidisciplinary)ITERのダイバータ領域に生成されるプラズマの温度は数十eV程度であり比較的温度が低い。そのダイバータに近接して、計測用ミラーが設置される。低エネルギー粒子の衝突により、反射率などの性能がどの程度劣化するか調べる必要がある。ここでは、SLEIS(Super Low Energy Ion Source with High Ion Flux)装置を使いモリブデンとタングステンミラーに対してエネルギー67eVから80eVの重水素イオンで照射し、反射率等の変化を調べた。焼結法で生成した場合に生じる表面の小さな穴を電子ビームで表面を溶融することにより消滅させたミラーは、照射前はその反射率は焼結のみで生成したものよりも高かったが、照射量に対して反射率が急速に低下した。ブリスタリングによるものと考えられる。それに対して、焼結のみで作ったモリブデン及びタングステンミラーは照射量に対する反射率の低下は少なく、照射量が1.3 10
10 m
m のところで10%程度の低下であった。講演では、これらのミラーのITERへの適用の可能性について述べる。また、ダイバータ板等のエロージョンの結果生ずる粒子がミラーへ付着する問題と、その防止対策についても議論する。
のところで10%程度の低下であった。講演では、これらのミラーのITERへの適用の可能性について述べる。また、ダイバータ板等のエロージョンの結果生ずる粒子がミラーへ付着する問題と、その防止対策についても議論する。
佐々木 政義*; 森本 泰臣*; 木村 宏美*; 高橋 幸司; 坂本 慶司; 今井 剛; 奥野 健二*
Journal of Nuclear Materials, 329-333(Part1), p.899 - 903, 2004/08
核融合炉用ミリ波帯高周波加熱システムのトーラス窓(高周波窓)の窓材として、CVDダイアモンドは標準となっている。トーラス窓は、トリチウム障壁としての役割も担うことから、トリチウムやヘリウム,放射性ダスト環境下にあり、したがって、ダイアモンドの化学構造に対する水素同位体等の影響を解明することは重要である。本研究では、窓と同一グレードのCVDダイアモンド試料( =10.0mm, t=0.21mm)を、アルゴンイオンビームスパッタリング(E
=10.0mm, t=0.21mm)を、アルゴンイオンビームスパッタリング(E =1keV)による酸素等の不純物除去の後に、重水素及びヘリウムイオンを照射した。照射エネルギーはそれぞれ0.25keV, 0.45keVである。照射サンプルをX線光電子分光(XPS)測定によって調べたところ、C1ピークが低エネルギー側にシフトしていることが観測された。この結果は、ダイアモンドがC-D結合によりアモルファス化したことを示唆している。
=1keV)による酸素等の不純物除去の後に、重水素及びヘリウムイオンを照射した。照射エネルギーはそれぞれ0.25keV, 0.45keVである。照射サンプルをX線光電子分光(XPS)測定によって調べたところ、C1ピークが低エネルギー側にシフトしていることが観測された。この結果は、ダイアモンドがC-D結合によりアモルファス化したことを示唆している。
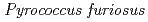 by BIX-3, a single-crystal diffractometer for biomacromolecules
by BIX-3, a single-crystal diffractometer for biomacromolecules栗原 和男; 田中 伊知朗*; 茶竹 俊行*; Adams, M. W. W.*; Jenney, F. E. Jr.*; Moiseeva, N.*; Bau, R.*; 新村 信雄
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(31), p.11215 - 11220, 2004/08
被引用回数:48 パーセンタイル:60.08(Multidisciplinary Sciences)原研原子炉JRR-3設置の生体高分子用中性子回折装置BIX-3を用いて、高い熱安定性を持つ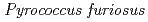 由来ルブレドキシンの中性子結晶構造解析を行った。結晶化はH原子からのバックグラウンドを抑えるため重水中で行った。回折実験は常温で行い、1.5
由来ルブレドキシンの中性子結晶構造解析を行った。結晶化はH原子からのバックグラウンドを抑えるため重水中で行った。回折実験は常温で行い、1.5 分解能でデータ収率81.9%を得た。立体構造モデルの精密化では、306個のH原子と50個のD原子及び37個の水和水を同定した。その結果、モデルの信頼性を示す
分解能でデータ収率81.9%を得た。立体構造モデルの精密化では、306個のH原子と50個のD原子及び37個の水和水を同定した。その結果、モデルの信頼性を示す 因子及び
因子及び
 因子は最終的に各々18.6%, 21.7%となった。この中性子解析により、X線解析では明確でなかったアミノ酸側鎖のO-D結合の方位を明らかにできた。また、主鎖のN-H結合のH原子は多くがD原子に置換されている一方で、その中で5つのH原子は置換されずに保たれていることがわかった。これはその周囲の高い構造安定性を示す。さらに中性子散乱密度図では、このタンパク質の高い熱安定性に寄与していると考えられているND
因子は最終的に各々18.6%, 21.7%となった。この中性子解析により、X線解析では明確でなかったアミノ酸側鎖のO-D結合の方位を明らかにできた。また、主鎖のN-H結合のH原子は多くがD原子に置換されている一方で、その中で5つのH原子は置換されずに保たれていることがわかった。これはその周囲の高い構造安定性を示す。さらに中性子散乱密度図では、このタンパク質の高い熱安定性に寄与していると考えられているND
 末端のその周囲に広がる水素結合ネットワークを詳細に明らかにすることができた。
末端のその周囲に広がる水素結合ネットワークを詳細に明らかにすることができた。
武田 哲明; 岩月 仁*
Nuclear Technology, 146(1), p.83 - 95, 2004/04
被引用回数:14 パーセンタイル:64.92(Nuclear Science & Technology)高温工学試験研究炉(HTTR)に接続する水素製造システムにおいては、中間熱交換器や水蒸気改質器に使用されている高温耐熱材料中の水素同位体透過は重要な問題である。本研究では管の外側に存在する水素が重水素の透過量に及ぼす影響を調べることが目的である。管内の重水素の分圧が100Paより低く、外側の水素分圧が10kPaより高いとき、管外の水素分圧が増大すると重水素の透過量が減少した。対向透過における重水素透過量は、金属表面での水素,重水素,HD分子の平衡状態を考慮し、重水素拡散係数に対する効果係数を用いた解析により定量的に予測することができた。これより、HTTRの1次系から水素製造システムへ移行するトリチウム量は、改質器反応管内の高分圧水素の存在により、少なくすることができると予想できる。
武田 哲明; 岩月 仁*; 稲垣 嘉之
Journal of Nuclear Materials, 326(1), p.47 - 58, 2004/03
被引用回数:22 パーセンタイル:78.27(Materials Science, Multidisciplinary)高温工学試験研究炉(HTTR)に接続する水素製造システムでは中間熱交換器の伝熱管や水蒸気改質器の反応管に使用される高温耐熱合金の水素同位体透過が重要な問題となる。そこで、中間熱交換器の伝熱管に使用されているハステロイXRの水素,重水素透過係数を取得するため水素同位体透過実験を実施した。本論文ではハステロイXRの水素及び重水素透過係数の活性化エネルギーと前指数部の係数を求めた。
中村 博文; 東島 智; 磯部 兼嗣; 神永 敦嗣; 堀川 豊彦*; 久保 博孝; 宮 直之; 西 正孝; 小西 哲之*; 田辺 哲朗*
Fusion Engineering and Design, 70(2), p.163 - 173, 2004/02
被引用回数:19 パーセンタイル:74.35(Nuclear Science & Technology)核融合炉における有効で簡便なトリチウム除去方法を確立するために、壁調整用放電洗浄法の1つであるグロー放電洗浄(GDC)のJT-60U真空容器からのトリチウム除去への適用を目的として、ヘリウムと水素を用いたGDCによるJT-60Uプラズマ対向面からの水素同位体放出挙動を調べた。その結果、水素同位体の放出挙動は、3種類の時間に対する単純指数減少関数の組合せで表せることを見いだした。解析の結果、水素GDCがヘリウムGDCよりも水素同位体除去に優れていることが判明し、これは、水素の放電に起因する化学スパッタと放電水素とタイル表面水素同位体との同位体交換反応の相乗効果等の化学的な反応によるものと推測される。本結果で得られた放出特性に基づけば、573Kにおける連続的な水素GDCによりJT-60Uの表面水素同位体濃度を1/2に低減させるのに数日程度を要することが示唆された。
中村 博文; 西 正孝; 杉崎 昌和*
JAERI-Research 2003-018, 32 Pages, 2003/09
核融合炉の安全評価上必要な材料中のトリチウム輸送挙動の評価は、トリチウム輸送物性値、もしくは、軽水素,重水素輸送特性の同位体効果理論によるトリチウムへの外挿値により評価される。しかしながら、トリチウム輸送物性値の測定例は稀少であり、また、同位体効果理論の外挿性についてもトリチウムデータの稀少さゆえに完全に確証されておらず、材料中トリチウム挙動予測に不確実性が存在する。そこで本研究では、この材料中におけるトリチウムの輸送特性を評価するために、イオン駆動透過法を用いて、水素透過挙動がよく知られたニッケルに対するトリチウムの拡散係数及び表面再結合係数を測定し、全く同じ条件で実施した重水素の結果との比較により拡散と表面再結合のトリチウム-重水素間の同位体効果を評価した。その結果、拡散係数の同位体間効果に関しては、古典拡散理論から予測される同位体効果を示さず、トリチウムが重水素よりも大きな拡散係数を持つこと及び拡散の活性化エネルギーがトリチウムの方が小さいという傾向を得た。これらの結果は、振動温度を従来報告値より若干高く仮定することにより、既存の修正拡散モデルで説明可能であることを明らかにした。さらに、表面再結合に関する同位体効果に関しても、修正溶解モデルにより同様に説明可能なことを示した。
奥野 浩; 秋山 秀夫*; 望月 弘樹*
Journal of Nuclear Science and Technology, 40(1), p.57 - 60, 2003/01
被引用回数:1 パーセンタイル:10.57(Nuclear Science & Technology)国際原子力機関(IAEA)の現行の放射性物質安全輸送規則を厳密に適用すると、低レベル廃棄物(LLW)ドラムが核分裂性物質として輸送することが要求される。この問題は、LLWドラム中のコンクリートの水分が重水素(D)を含み、その量が核分裂性物質質量の0.1%を超え、従ってLLW運搬物が核分裂性物質を含む輸送物に関する除外規定要求を満たさないことの帰結である。軽水素( H)とDの中性子吸収断面積の相違に関する検討から、水素減速体系において天然水中のDの存在による中性子増倍率の相対的な増加が0.015%以下であることを示す。
H)とDの中性子吸収断面積の相違に関する検討から、水素減速体系において天然水中のDの存在による中性子増倍率の相対的な増加が0.015%以下であることを示す。 U/H質量比5%の
U/H質量比5%の U金属と水の混合物において、無限中性子増倍率がD/H原子個数比に比例して増加し、D/H原子個数比0.015%に対して無限中性子増倍率の相対的な増加割合が0.03%未満であることを数値計算により確認する。除外規定にある核分裂性核種と水素の制限質量比5%が、天然水にDを含む水素減速体系にも適用可能であることを結論付ける。
U金属と水の混合物において、無限中性子増倍率がD/H原子個数比に比例して増加し、D/H原子個数比0.015%に対して無限中性子増倍率の相対的な増加割合が0.03%未満であることを数値計算により確認する。除外規定にある核分裂性核種と水素の制限質量比5%が、天然水にDを含む水素減速体系にも適用可能であることを結論付ける。
武田 哲明; 岩月 仁*; 西原 哲夫
JAERI-Tech 2002-090, 30 Pages, 2002/11
高温工学試験研究炉(HTTR)に接続する水素製造システムでは、中間熱交換器の伝熱管や水蒸気改質器の触媒管に使用される高温耐熱合金中の水素同位体透過が重要な問題となる。そこで、安全審査や数値解析コードの開発に必要なデータを取得するため、機器要素試験の一つとして水素透過試験を実施した。本研究の目的は、ハステロイXRや他の高温耐熱合金に対する水素同位体透過係数を取得するとともに、酸化膜が水素同位体透過量の低減効果に及ぼす影響を定量的に評価することである。試験の結果から、原子炉運転初期に伝熱管表面に形成される酸化膜により、HTTR1次系から熱利用系に透過するトリチウム透過量は低減されると予想される。本報告書は、伝熱管表面に酸化膜が形成された場合のハステロイXRに対する水素と重水素透過量の低減効果と酸化膜の形成状態についてまとめたものである。
五十嵐 慎一; 武藤 俊介*; 田辺 哲朗*; 相原 純; 北條 喜一
Surface & Coatings Technology, 158-159, p.421 - 425, 2002/09
低角度入射電子顕微鏡法を用いて、シリコンブリスタリングのその場観察を行った。重水素照射により形成されるブリスターの大きさ,密度は、電子線照射領域内では領域外より明らかに小さいことがわかった。これは高エネルギー電子線による電子励起により、シリコン不飽和結合の重水素による終端化が抑制されたためである。また、フラックスが高いと、ブリスターが形成されるより前に、フレーキングが起きることも明らかにした。さらに、重水素照射では、注入重水素の最大飛程よりさらに浅いところで、重水素終端された欠陥が形成され、そこで劈開が起こり、ブリスターとなることを明らかにした。
安藤 麻里子; 天野 光; 柿内 秀樹; 一政 満子*; 一政 祐輔*
Health Physics, 82(6), p.863 - 868, 2002/06
被引用回数:7 パーセンタイル:43.36(Environmental Sciences)トリチウムの環境中での挙動を調べるため、安定同位体である重水を使用して放出実験を行い、稲による重水の取り込みと有機結合型重水素(OBD)の生成及び生成したOBDの収穫までの残留について調べた。結果として、昼のOBD生成が夜間の2-3倍であること、昼の実験で生成されたOBDの方が夜間に生成されたOBDに比較して収穫時まで残留する割合が高いことなどが示された。また、昼夜の差について、生成過程が光合成によるかそのほかの反応によるかによる違いを考慮したモデルを用いて解析を行い、実験値と一致する結果が得られることを確認した。