Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
酒瀬川 英雄; 野村 光生; 澤山 兼吾; 中山 卓也; 矢板 由美*; 米川 仁*; 小林 登*; 有馬 立身*; 檜山 敏明*; 村田 栄一*
Progress in Nuclear Energy, 153, p.104396_1 - 104396_9, 2022/11
被引用回数:1 パーセンタイル:0.00(Nuclear Science & Technology)ウラン濃縮施設の使用済み遠心分離機を解体する際、解体部品のウラン汚染面のみを選択的に除去できる除染技術を開発することは重要である。これは適切な除染を通じて、解体部品を非放射性廃棄物として処分、もしくは、再利用するためである。これまでの研究により、ウラン汚染面を除去できる酸性電解水を利用した湿式除染技術を開発した。ただし、実用化のためにはさらなる技術の最適化は必要である。解体部品は、様々な運転履歴、七フッ化ヨウ素ガスを使用した不均一な系統除染の状況、そして、解体後の長期保管条件の変化により、ウラン汚染状態が異なるためである。本研究は遠心分離機の低炭素鋼製ケーシングからウラン汚染状態の異なる試料を採取して酸性電解水を利用した湿式除染を実施した。その結果、ウラン汚染面のみを効果的に除去することができ、最大20分間で放射能の目標値を下回った。実際の除染時間は解体部品の大きさや形状にも依存することになるが、この方法が遠心分離機のウラン汚染部品に対する除染技術として利用できることを明らかとした。
山根 いくみ; 高橋 信雄; 澤山 兼吾; 西脇 大貴; 松本 孝志; 小川 潤平; 野村 光生; 有馬 立身*
JAEA-Technology 2021-038, 18 Pages, 2022/02
人形峠環境技術センターの設備解体撤去による解体物の発生予想量は全体で約13万トンである。そのうち放射性廃棄物でない廃棄物(以下NR: Nonradioactive wasteという)となる非放射性廃棄物は約80%である。しかしながら、このNR対象となる鋼材の一部には汚染された可能性を否定できないものがあり、これらについては汚染が疑われる部分の表面塗装膜を分離・除去させた後、搬出のためのサーベイを実施してからNRとしている。現在の分離・除去方法ではグラインダー等の回転研磨工具による手作業を採用しているが、この方法は粉塵の飛散と吸入防止のためのグリーンハウスの設置や作業員のタイベックスーツと全面マスクの着用を必要とする。このため、分離・除去方法のさらなる改良による作業の短時間化(低コスト化)、作業員への負荷低減、そして、過剰な研磨による二次廃棄物発生の抑制が望まれている。そこで本研究では、工事現場等で塗装膜分離・除去に使用されるレーザークリーニング技術に着目した。NR対象物の塗装膜分離・除去技術の向上を目的とし、レーザークリーニング装置を用いたNR鋼材表面塗装膜の分離・除去性能評価、高速度カメラによる塗装膜飛散挙動の観測と塗装膜回収方法の検討、鋼材表面の粉体に対するレーザー分離・除去性能評価、鋼材表面上のウラン化合物の熱力学的評価を行った。またこれらに基づいて、今後のレーザークリーニング技術の導入による実作業への適合性についても検討して今後の展開について整理した。
中山 卓也; 野村 光生; 美田 豊; 米川 仁*; 分枝 美沙子*; 矢板 由美*; 村田 栄一*; 保坂 克美*; 杉杖 典岳
Proceedings of 2019 International Congress on Advances in Nuclear Power Plants (ICAPP 2019) (Internet), 8 Pages, 2019/05
金属廃棄物は、放射性廃棄物量最小化の観点から、クリアランスして資源化することが重要である。適用可能な除染技術の中で、金属廃棄物のように、形状・材質が多様であるものに対しては、湿式除染が有効な手法と考えられる。一方、一般的には、湿式除染は、廃液処理から生ずる二次廃棄物量が多くなる傾向がある。本件では、六フッ化ウランで汚染した鋼材をクリアランスするための目標レベル(0.04Bq/cm )以下まで除染し、かつ二次廃棄物発生量を最小化することを目標とする。本試験では、除染液の液性に着目し、酸性電解水,塩酸,硫酸,オゾン水を試験した。その結果、酸性電解水は六フッ化ウランで汚染した鋼材の除染液として有効であることがわかった。
)以下まで除染し、かつ二次廃棄物発生量を最小化することを目標とする。本試験では、除染液の液性に着目し、酸性電解水,塩酸,硫酸,オゾン水を試験した。その結果、酸性電解水は六フッ化ウランで汚染した鋼材の除染液として有効であることがわかった。
大橋 裕介; 野村 光生; 綱嶋 康倫; 安藤 詞音; 杉杖 典岳; 池田 泰久*; 田中 祥雄
Journal of Nuclear Science and Technology, 51(2), p.251 - 265, 2014/02
被引用回数:10 パーセンタイル:57.48(Nuclear Science & Technology)人形峠環境技術センターにおけるウランの転換技術開発によって、ウランを含んだスラッジ状廃棄物が発生している。これらのうち、珪藻土及びCaF 中和沈澱物からウランを回収するプロセスとして、塩酸を用いた湿式プロセスを提案した。中和沈澱物を溶解した塩酸溶液中の異なるpH領域における溶存種の存在比を化学平衡計算によって検討し、回収したウラン中のフッ素量について実験値と比較した。回収したウランへのフッ素の混入量は溶液中のアルミニウム濃度の増加によって減少することを確認した。珪藻土については、ウランが選択的に回収可能であることがわかった。回収したウランは、pHの増加とともに粒径が小さくなり、ウラン回収後の廃液から発生する中和沈澱物のウラン濃度は1Bq/gを下回った。
中和沈澱物からウランを回収するプロセスとして、塩酸を用いた湿式プロセスを提案した。中和沈澱物を溶解した塩酸溶液中の異なるpH領域における溶存種の存在比を化学平衡計算によって検討し、回収したウラン中のフッ素量について実験値と比較した。回収したウランへのフッ素の混入量は溶液中のアルミニウム濃度の増加によって減少することを確認した。珪藻土については、ウランが選択的に回収可能であることがわかった。回収したウランは、pHの増加とともに粒径が小さくなり、ウラン回収後の廃液から発生する中和沈澱物のウラン濃度は1Bq/gを下回った。
岡本 芳浩; 中田 正美; 赤堀 光雄; 駒嶺 哲*; 福井 寿樹*; 越智 英治*; 仁谷 浩明*; 野村 昌治*
電気化学および工業物理化学, 81(7), p.543 - 546, 2013/07
被引用回数:8 パーセンタイル:19.07(Electrochemistry)高温溶融状態の高レベル模擬ガラス中のルテニウム元素の挙動と化学状態を、放射光X線イメージング技術を使用して分析した。溶融から気泡発生、ルテニウムの凝集と沈殿までを、12ビットCCDカメラで動的に観察した。X線強度は、画像の濃淡を数値化することによって得た。また、ルテニウムの存在は、そのK吸収端直後のエネルギーにおいては、図中にて黒く強調されて観測される。位置分解能を備えたイメージングXAFS分析技術を駆使して、溶融状態のルテニウムの化学状態についても調べた。
岡本 芳浩; 中田 正美; 赤堀 光雄; 駒嶺 哲*; 福井 寿樹*; 越智 英治*; 仁谷 浩明*; 野村 昌治*
Proceedings of 4th Asian Conference on Molten Salt Chemistry and Technology & 44th Symposium on Molten Salt Chemistry, Japan, p.47 - 52, 2012/09
模擬ガラスの溶融状態と融体中のルテニウムの挙動を、放射光イメージング分析によって調べた。溶融,気泡の発生と成長、ルテニウムの凝集と沈降を、高感度CCDカメラの12ビットグレースケール連続画像として動的に観察した。ルテニウムの存在は、画像中に黒色で強調される。また、透過X線強度は、画像のグレースケールを数値化することによって得た。さらに、位置分解能を備えたイメージングXAFS測定を行い、高温融体中のルテニウムの化学状態を明らかにする試みを実施した。
岡本 芳浩; 中田 正美; 赤堀 光雄; 塩飽 秀啓; 駒嶺 哲*; 福井 寿樹*; 越智 英治*; 仁谷 浩明*; 野村 昌治*
日本原子力学会和文論文誌, 11(2), p.127 - 132, 2012/06
模擬ガラス中のルテニウム元素の分布とその化学状態を、放射光イメージング測定技術を使い分析した。この方法では、ダイレクトX線CCDカメラを、イオンチェンバーの代わりに使用している。X線CCDカメラによる画像の濃淡を数値化解析することにより、位置分解能を備えたX線吸収スペクトルが取得可能である。本研究では最初に、ルテニウム金属と酸化物が混在したテスト試料の測定を実施した。その結果、ルテニウム元素の分布情報を取得できたうえに、さらにルテニウムリッチの微小領域における化学状態、すなわちそれが金属か酸化物かの評価が可能であることを示すことができた。この手法を模擬ガラス試料へ適用し、ガラス中のルテニウム元素が酸化物の状態でいることを明らかにした。
 Li(d,t)
Li(d,t) Li reaction
Li reaction橋本 尚志; 石山 博恒*; 渡辺 裕*; 平山 賀一*; 今井 伸明*; 宮武 宇也; Jeong, S.-C.*; 田中 雅彦*; 吉川 宣治*; 野村 亨*; et al.
Physics Letters B, 674(4-5), p.276 - 280, 2009/04
被引用回数:7 パーセンタイル:46.18(Astronomy & Astrophysics) Li(d,t)
Li(d,t) Li反応の反応断面積を重心系で1.2から0.3MeVのエネルギーで7点直接測定した。これらのエネルギーは1
Li反応の反応断面積を重心系で1.2から0.3MeVのエネルギーで7点直接測定した。これらのエネルギーは1 3
3 10
10 Kのガモフピーク領域をカバーする。重心系で0.8MeVのエネルギーで断面積の増大が観測され、これは複合核である
Kのガモフピーク領域をカバーする。重心系で0.8MeVのエネルギーで断面積の増大が観測され、これは複合核である Beの22.4MeVの励起状態の寄与によると考えられる。また、この寄与によって天体核反応率は1
Beの22.4MeVの励起状態の寄与によると考えられる。また、この寄与によって天体核反応率は1 10
10 Kで従来用いられていた値よりも1桁大きいことが明らかとなった。
Kで従来用いられていた値よりも1桁大きいことが明らかとなった。
 Li(
Li( , n)
, n) B reaction
B reaction石山 博恒*; 橋本 尚志; 石川 智子*; 渡辺 裕*; Das, S. K.*; 宮武 宇也; 溝井 浩*; 福田 共和*; 田中 雅彦*; 渕 好秀*; et al.
Physics Letters B, 640(3), p.82 - 85, 2006/09
被引用回数:33 パーセンタイル:84.17(Astronomy & Astrophysics)終状態を抑えながら、 Li(
Li( ,n)
,n) B反応の励起関数をE
B反応の励起関数をE =0.7-2.6MeVの領域で測定した。従来よりも高統計で得られた結果は、E
=0.7-2.6MeVの領域で測定した。従来よりも高統計で得られた結果は、E 1.5MeVで、以前の測定データと二倍以上小さな断面積を示した。E
1.5MeVで、以前の測定データと二倍以上小さな断面積を示した。E =0.85MeV近傍に共鳴ピークを観測した。
=0.85MeV近傍に共鳴ピークを観測した。
 Li(
Li( ,n)
,n) B reaction for astrophysical interest
B reaction for astrophysical interestDas, S. K.*; 福田 共和*; 溝井 浩*; 石山 博恒*; 宮武 宇也*; 渡辺 裕*; 平山 賀一*; 田中 雅彦*; 吉川 宣治*; Jeong, S.-C.*; et al.
AIP Conference Proceedings 847, p.374 - 376, 2006/07
軽い中性子過剰核を含む( ,n)反応は速い中性子捕獲過程やビッグバン元素合成中で重要な役割を担う。特に
,n)反応は速い中性子捕獲過程やビッグバン元素合成中で重要な役割を担う。特に Li(
Li( ,n)
,n) B反応は安定核の存在しない質量数8のギャップを越えて重い元素を生成する反応の一つとして注目を集めている。今回、
B反応は安定核の存在しない質量数8のギャップを越えて重い元素を生成する反応の一つとして注目を集めている。今回、 Li(
Li( ,n)
,n) B 反応の重心系で0.45-1.75MeVのエネルギー領域での直接測定を行った。このエネルギー領域は1
B 反応の重心系で0.45-1.75MeVのエネルギー領域での直接測定を行った。このエネルギー領域は1 10
10 Kでのガモフピークに相当する。
Kでのガモフピークに相当する。 Liビームは
Liビームは Be(
Be( Li,
Li, Li)反応を用いて生成し、反跳核質量分析器(RMS)を用いて一次ビームや同時に生成される核種とわけた。検出器系はビーム飛行時間測定装置,Multiple-Sampling and Tracking Proportional Chamber(MSTPC)と中性子検出器からなる。ビームの飛行時間で
Li)反応を用いて生成し、反跳核質量分析器(RMS)を用いて一次ビームや同時に生成される核種とわけた。検出器系はビーム飛行時間測定装置,Multiple-Sampling and Tracking Proportional Chamber(MSTPC)と中性子検出器からなる。ビームの飛行時間で Liビームのエネルギーをイベントごとに決定した後、MSTPCに直接打ち込む。MSTPC内にはHe+CO
Liビームのエネルギーをイベントごとに決定した後、MSTPCに直接打ち込む。MSTPC内にはHe+CO (10
(10 )の混合ガスが140torrの圧力で封入されており、このガスは検出器ガスとターゲットの両方の役割を果たす。反応で放出された中性子はMSTPCの周りを取り囲んだ中性子検出器で検出される。MSTPC内で反応が起こった場合、エネルギー損失シグナルの急激な変化が測定され、反応位置とエネルギーを決定できる。中性子検出器からの情報を加えて、反応の運動学的条件を満たすものを本物のイベントとした。本実験の結果はわれわれのグループが過去に測定した結果とエネルギーの重なる範囲で一致した。本講演では得られた実験結果について報告する。
)の混合ガスが140torrの圧力で封入されており、このガスは検出器ガスとターゲットの両方の役割を果たす。反応で放出された中性子はMSTPCの周りを取り囲んだ中性子検出器で検出される。MSTPC内で反応が起こった場合、エネルギー損失シグナルの急激な変化が測定され、反応位置とエネルギーを決定できる。中性子検出器からの情報を加えて、反応の運動学的条件を満たすものを本物のイベントとした。本実験の結果はわれわれのグループが過去に測定した結果とエネルギーの重なる範囲で一致した。本講演では得られた実験結果について報告する。
石山 博恒*; 石川 智子*; 橋本 尚志; 渡辺 裕*; 平山 賀一*; 今井 伸明*; 宮武 宇也; 田中 雅彦*; 渕 好秀*; 吉川 宣治*; et al.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 560(2), p.366 - 372, 2006/05
被引用回数:7 パーセンタイル:46.85(Instruments & Instrumentation)核子移行逆反応の特性を利用して軽い中性子過剰核領域における低エネルギー短寿命核ビームを生成した。原研反跳核分析器が持つ質量分離,速度分離は、ビームの高純度化に役に立った。これまでに、 Li,
Li,  Bと
Bと N-RNBsを生成し実験に用いている。それぞれのビーム強度,純度は1.4
N-RNBsを生成し実験に用いている。それぞれのビーム強度,純度は1.4 10
10 ppsで99
ppsで99 、7.8
、7.8 10
10 ppsで98
ppsで98 、そして4.7
、そして4.7 10
10 ppsで98.5
ppsで98.5 である。
である。
橋本 尚志; 石山 博恒*; 石川 智子*; 川村 隆史*; 中井 浩二*; 渡辺 裕*; 宮武 宇也; 田中 雅彦*; 渕 好秀*; 吉川 宣治*; et al.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 556(1), p.339 - 349, 2006/01
被引用回数:33 パーセンタイル:88.21(Instruments & Instrumentation)三次元の飛跡検出型の比例ガス検出器を開発した。ゲーティンググリッドの採用により、4 10
10 個/秒の荷電粒子入射に対しても安定な性能を持続できる。ほぼ100
個/秒の荷電粒子入射に対しても安定な性能を持続できる。ほぼ100 の検出効率を持つので、ビーム強度の弱い短寿命核ビームによる天体核反応率の測定実験に最適な検出器である。
の検出効率を持つので、ビーム強度の弱い短寿命核ビームによる天体核反応率の測定実験に最適な検出器である。
 Cs(
Cs(
 = 1.63 m) by ABMR
= 1.63 m) by ABMRPinard, J.*; Duong, H. T.*; Marescaux, D.*; Stroke, H. H.*; Redi, O.*; Gustafsson, M.*; Nilsson, T.*; Matsuki, S.*; 岸本 泰明*; Kominato, K.*; et al.
Nuclear Physics A, 753(1-2), p.3 - 12, 2005/05
被引用回数:4 パーセンタイル:35.32(Physics, Nuclear)磁場が原子核内で有限な分布を持つと超微細構造異常(ボーア ワイスコップ効果)が生じる。この効果を系統的に調べるためには、超微細構造定数と核磁気モーメントを系統的に高い精度で求める必要がある。本研究では、不安定核の超微細構造定数の精密測定のために、オンライン-レーザー光ポンピング原子線磁気共鳴装置を開発し、 Cs(
Cs(
 m)の基底状態6s
m)の基底状態6s S
S の超微細分岐
の超微細分岐 を求めた。その結果、
を求めた。その結果、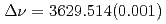 MHzを得た。
MHzを得た。
冨安 博*; 野村 光生; 山崎 斉; 林原 健一
JNC TY6400 2004-004, 18 Pages, 2004/07
本研究は、ウランを含むNaFおよびCaF2廃棄物(以後NaFおおびCaF2廃棄物と呼ぶ)から二次廃棄物を作ることなくウランを回収する技術を開発することを目的として始められた。ウランの回収は完全で、最終的に回収したNaFおよびCaF2を再利用するものとする。この目的を達成するため、先ず、超臨界CO2を用いる方法を試みた。抽出剤としては、TBPが一般的であるが、二次廃棄物を作らないことの前提があるため、TBPに代わる抽出剤の使用を検討した。TBPには必ずりん廃棄物の問題が生じるからである。様々な抽出剤の中でも、超臨界CO2への溶解度、ウランに対する選択性等を考慮してアセチルアセトンを使用することにした。実験の結果、アセチルアセトンがTBPよりも強い配位能力を有することが分かった。超臨界二酸化炭素とアセチルアセトンによる混合流体を用い、硝酸ウラニル中からウランの回収が可能であることを確認した。実際に、アセチルアセトンを含む超臨界CO2を用い、NaF廃棄物からウランを回収する実験を試みた。その結果、ウランの一部は溶媒中に回収されたが、大部分は廃棄物中に留まった。これは、ウランがフッ化物と強く結合し、しかもNaFの内部に侵透しているため、表面の洗浄では完全なウラン回収は不可能であることを意味する。そこで、ウランを完全に回収することを目指し、以下に示す新たな実験を試みた。最初に、廃棄物を熱湯水に溶解する。この水溶液にNaOHを加え、ウランを加水分解種の沈殿として分離した。この操作によりウランを99.9%以上回収することができる。ウラン分離後、溶液に少量のエタノールを加える。この操作によりNaFを粉末として回収した。結論として、NaFおよびCaF2廃棄物では、ウランはフッ化物と強力に結合しているため、超臨界二酸化炭素を用いた乾式回収は極めて困難である。しかし、廃棄物を一旦熱湯に溶解する湿式処理により、ウランをほぼ完全に回収し、NaFも純粋な粉末として高収率で回収することができた。この際、回収したウランは加水分解種として水分を含んでいるが、これを水あるいはエタノールに分散させ、溶液を超臨界状態にすると、ウランは、それぞれ、U3O8あるいはUO2として安定化させることができる。
相原 雅彦*; 楊井 慎二郎*; 嶋崎 洋平*; 野村 光生; 山崎 斉; 林原 健一
JNC TY6400 2004-003, 93 Pages, 2004/07
核燃料サイクルを安全に運転していくためには放射性廃棄物のあたらしい処理法や廃棄法が開発されなければならない。超臨界二酸化炭素抽出法は低レベル固体放射性廃棄物中のウラン回収技術として注目されている。本報告書では、超臨界プロセスから排出される高圧の二酸化炭素の回収と再利用するシステムにおいて、酸化カルシウムの炭酸化反応と炭酸カルシウムの脱炭酸化反応の利用を提案する。酸化カルシウム吸収剤による高圧二酸化炭素の繰り返し反応実験を行い、反応速度解析、反応固体の固体分析、反応の数値解析、回収.再利用プロセスの評価がなされた。炭酸化反応は約2MPaで最も速く、5回の繰り返し反応に関しても0.4程度で安定していた。 酸化カルシウム吸収剤は1.10 m程度の粒子から構成され、さらにそれらの粒子はサブミクロンオーダーの微粒子の集合体となっていることがわかった。その集合体の空隙は炭酸化反応で閉塞が起こり、反応性に影響を及ぼしていることがわかった。 反応解析データより本回収.再利用システムの二酸化炭素回収熱原単位を試算した。
m程度の粒子から構成され、さらにそれらの粒子はサブミクロンオーダーの微粒子の集合体となっていることがわかった。その集合体の空隙は炭酸化反応で閉塞が起こり、反応性に影響を及ぼしていることがわかった。 反応解析データより本回収.再利用システムの二酸化炭素回収熱原単位を試算した。
中山 卓也; 杉杖 典岳; 美田 豊; 野村 光生
矢板 由美*; 村田 栄一*
【課題】金属母材溶解量を抑制しつつ効率的に除染できる汚染金属の除染方法を提供する。 【解決手段】汚染金属の除染方法は、表面が汚染された金属を、次亜塩素酸を含む酸性電解水で除染することを特徴とする。
綱嶋 康倫; 島崎 雅夫; 大橋 裕介; 田中 祥雄; 野村 光生
no journal, ,
ウラン製錬転換プラントやウラン濃縮プラントの操業廃棄物である澱物類については、有害物であるフッ素を多く含むため、セメント固化して廃棄体とする場合、フッ素の溶出が課題となっている。また澱物類は、硫酸カルシウムも多く含んでいるため、エトリンガイドの過剰生成による廃棄体の膨張も懸念されている。本件では、フッ素を多く含む澱物類をセメント固化した場合の固化・溶出特性を確認するとともに、フッ素の溶出や膨張を抑制する方法として酸化マグネシウム系固化材を用いた澱物類の固化・溶出試験結果を報告する。
中山 卓也; 野村 光生; 美田 豊; 杉杖 典岳; 米川 仁*; 分枝 美沙子*; 矢板 由美*; 村田 栄一*; 保坂 克美*
no journal, ,
六フッ化ウラン(UF  )に曝露された金属を対象として、大気開放後に生成する腐食層や母材に付着した放射性物質を、合理的に除染する方法の研究として、腐食層を模擬した試料を使って、水, 希釈酸, 酸性機能水(電解生成水)による除染特性を評価した。その結果、酸性機能水の特徴である高い酸化還元電位が除染性能に影響することが分かった。
)に曝露された金属を対象として、大気開放後に生成する腐食層や母材に付着した放射性物質を、合理的に除染する方法の研究として、腐食層を模擬した試料を使って、水, 希釈酸, 酸性機能水(電解生成水)による除染特性を評価した。その結果、酸性機能水の特徴である高い酸化還元電位が除染性能に影響することが分かった。
中山 卓也; 野村 光生; 美田 豊; 杉杖 典岳; 米川 仁*; 分枝 美沙子*; 矢板 由美*; 村田 栄一*; 保坂 克美*
no journal, ,
六フッ化ウラン(UF )に曝露された金属を対象として、大気開放後に生成する腐食層や母材に付着した放射性物質を、合理的に除染する方法の研究として、模擬試料および実試料を使った除染試験結果から、除染効率, 二次廃棄物発生量等の評価を実施した。その結果、酸性機能水除染は他の希釈除染と比較して総合的に優れていることを確認した。
)に曝露された金属を対象として、大気開放後に生成する腐食層や母材に付着した放射性物質を、合理的に除染する方法の研究として、模擬試料および実試料を使った除染試験結果から、除染効率, 二次廃棄物発生量等の評価を実施した。その結果、酸性機能水除染は他の希釈除染と比較して総合的に優れていることを確認した。
 Li(d,t)(d,p)(d,
Li(d,t)(d,p)(d, )反応の直接測定
)反応の直接測定橋本 尚志; 石山 博恒*; 平山 賀一*; 渡辺 裕*; 今井 伸明*; 宮武 宇也; Jeong, S.-C.*; 吉川 宣治*; 田中 雅彦*; 野村 亨*; et al.
no journal, ,
宇宙初期での非一様ビッグバン模型や超新星爆発中の元素合成過程においては中性子過剰な環境が作られるため、原子核反応の経路は安定線よりややずれて中性子過剰核を経由して進むと予想される。この過程において Liは安定核の存在しない質量数8を越える鍵となる元素として注目されている。われわれのグループでは
Liは安定核の存在しない質量数8を越える鍵となる元素として注目されている。われわれのグループでは Liの関与する反応の断面積を測定することで反応経路を明らかにすることを目的として実験を行っている。本講演ではTRIACで行われた
Liの関与する反応の断面積を測定することで反応経路を明らかにすることを目的として実験を行っている。本講演ではTRIACで行われた Li(d,t),
Li(d,t),  Li(d,p),
Li(d,p),  Li(d,
Li(d, )反応断面積の測定について報告する。
)反応断面積の測定について報告する。