Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
Initialising ...
 -lactamaseのCs
-lactamaseのCs 選択性結合部位の発見
選択性結合部位の発見新井 栄揮; 柴崎 千枝; 清水 瑠美; 安達 基泰; 玉田 太郎; 徳永 廣子*; 石橋 松二郎*; 徳永 正雄*; 黒木 良太
九州シンクロトロン光研究センター年報,2014, p.17 - 19, 2016/03
タンパク質は生物の生命活動のために、金属イオンの電荷数の違いやイオン半径のわずかな違いを識別して結合するなど、緻密な原子・分子認識機構を有する。多くのタンパク質が必須元素の金属を結合することは広く知られている。しかし、タンパク質が必須元素ではないセシウム(Cs)を選択して結合しうるのか、また、その結合部位はどのような構造をしているのか等は明らかにされていなかった。特に、東京電力福島第一原子力発電所事故によって放出された放射性Csの生物への影響を知るためや、タンパク質を利用したCs吸着剤を開発するためには、タンパク質におけるCs の結合のしやすさや結合部位の構造を解明することが重要と考えられた。そこで我々は、好塩性タンパク質とCs
の結合のしやすさや結合部位の構造を解明することが重要と考えられた。そこで我々は、好塩性タンパク質とCs の相互作用の研究に着手した。好塩性タンパク質は、塩湖・岩塩・塩蔵食品・発酵食品などの高塩濃度環境に生息する好塩性細菌が作るタンパク質である。好塩性タンパク質は、高塩濃度環境に適応するために多く酸性アミノ酸を含有し、多くの負電荷を有することから、Cs
の相互作用の研究に着手した。好塩性タンパク質は、塩湖・岩塩・塩蔵食品・発酵食品などの高塩濃度環境に生息する好塩性細菌が作るタンパク質である。好塩性タンパク質は、高塩濃度環境に適応するために多く酸性アミノ酸を含有し、多くの負電荷を有することから、Cs を含む様々な金属イオンを結合する可能性があると我々は考えた。本研究では、好塩性タンパク質の中でも比較的高い酸性アミノ酸含量を有し[(Asp + Glu) / (Arg + Lys) = 2.11]、かつ、大腸菌への遺伝子組換えによって大量調製が可能な好塩菌
を含む様々な金属イオンを結合する可能性があると我々は考えた。本研究では、好塩性タンパク質の中でも比較的高い酸性アミノ酸含量を有し[(Asp + Glu) / (Arg + Lys) = 2.11]、かつ、大腸菌への遺伝子組換えによって大量調製が可能な好塩菌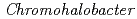 sp. 560由来
sp. 560由来 -lactamase (以下、HaBLA)について、立体構造の解明とCs
-lactamase (以下、HaBLA)について、立体構造の解明とCs 結合部位の検出を試みた。
結合部位の検出を試みた。
廣本 武史; 安達 基泰; 柴崎 千枝; Schrader, T. E.*; Ostermann, A.*; 黒木 良太
JPS Conference Proceedings (Internet), 8, p.033003_1 - 033003_6, 2015/09
T4ファージリゾチーム(T4L)は、大腸菌の細胞壁を構成するムラミルペプチドを加水分解し、溶菌を引き起こす酵素である。野生型T4Lは、加水分解後の生成物のアノマー構造を逆転する酵素であるが、26番目のThr残基を部位特異的にHis残基に置換したT26H変異型T4Lは、加水分解生成物のアノマー構造を保持する酵素に変換されるのみならず、高い糖転移活性を獲得する。そこで、変異型酵素に導入したHis残基の糖転移反応における役割と隣接する酸性残基(Asp20)との関係を中性子構造解析によって明らかにするため、T26H変異型T4Lの完全重水素化とその大型結晶作製を試みた。完全重水素化タンパク質(d-T26H)は、一般的な大腸菌発現ベクターを用い、完全重水素化培地で組換え大腸菌を培養後、過剰発現させることによって調製した。精製試料を用いて、タンパク質濃度と沈殿剤濃度を変化させたスクリーニングを実施し、約0.12mm の結晶を取得した。本結晶をミュンヘン工科大学の研究用原子炉(FRM II)において極低温下(100K)での予備的中性子回折実験を実施した結果、2.8
の結晶を取得した。本結晶をミュンヘン工科大学の研究用原子炉(FRM II)において極低温下(100K)での予備的中性子回折実験を実施した結果、2.8 分解能を超える回折点の観測に成功した。
分解能を超える回折点の観測に成功した。
 -lactamase from the moderate halophile
-lactamase from the moderate halophile 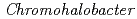 sp.560 and the discovery of a Cs
sp.560 and the discovery of a Cs -selective binding site
-selective binding site新井 栄揮; 米澤 悌*; 岡崎 伸生*; 松本 富美子*; 柴崎 千枝; 清水 瑠美; 山田 貢*; 安達 基泰; 玉田 太郎; 河本 正秀*; et al.
Acta Crystallographica Section D, 71(3), p.541 - 554, 2015/03
被引用回数:8 パーセンタイル:52.61(Biochemical Research Methods)蛋白質を利用した希少・有害金属捕集材料の研究開発の一環として、中度好塩菌Chromohalobacter sp.560由来・高酸性 -Lactamase(HaBLA)のX線結晶構造を解明するとともに、X線異常分散測定により、HaBLA分子上のCs
-Lactamase(HaBLA)のX線結晶構造を解明するとともに、X線異常分散測定により、HaBLA分子上のCs , Sr
, Sr 結合部位の抽出を試みた。PFのNW3AにてHaBLAのX線結晶構造を解明した後、Cs吸収端(
結合部位の抽出を試みた。PFのNW3AにてHaBLAのX線結晶構造を解明した後、Cs吸収端( =2.175
=2.175 )近傍のX線を利用できるSAGA-LSのBL7やPFのBL17A、及び、Sr吸収端(
)近傍のX線を利用できるSAGA-LSのBL7やPFのBL17A、及び、Sr吸収端( =0.770
=0.770 )近傍のX線を利用できるSPring-8のBL38B1やPFのBL5Aなどを使用して、HaBLA分子に結合したCs
)近傍のX線を利用できるSPring-8のBL38B1やPFのBL5Aなどを使用して、HaBLA分子に結合したCs 及びSr
及びSr を同定した。その結果、HaBLA分子上に少なくとも1ヶ所のCs
を同定した。その結果、HaBLA分子上に少なくとも1ヶ所のCs 結合部位、3ヶ所のSr
結合部位、3ヶ所のSr 結合部位を発見した。特に、今回発見したCs
結合部位を発見した。特に、今回発見したCs 結合部位は、Na
結合部位は、Na がCs
がCs の9倍量存在する条件下(Na
の9倍量存在する条件下(Na /Cs
/Cs = 90mM/10mM)でもCs
= 90mM/10mM)でもCs を選択的に結合できることが明らかになった。このCs
を選択的に結合できることが明らかになった。このCs 選択的結合部位は、Trp側鎖のベンゼン環によるカチオン-
選択的結合部位は、Trp側鎖のベンゼン環によるカチオン- 相互作用、および、主鎖の2つの酸素原子によってCs
相互作用、および、主鎖の2つの酸素原子によってCs を結合していた。本研究で得たCs
を結合していた。本研究で得たCs 結合部位の立体構造情報は、原発事故によって放出された放射性Cs
結合部位の立体構造情報は、原発事故によって放出された放射性Cs を捕集する蛋白質材料の設計(人工的Cs
を捕集する蛋白質材料の設計(人工的Cs 結合部位の設計)の土台として利用できる。
結合部位の設計)の土台として利用できる。
柴崎 千枝; 安達 基泰; 清水 瑠美; 黒木 良太
no journal, ,
カゼインキナーゼは、細胞に広く存在するセリン/スレオニンキナーゼであり、その一つであるカゼインキナーゼII(CK2)は、細胞周期の進行や細胞の生存・増殖に関与することが知られている。またCK2の過剰な発現は、発癌や癌転移との関係が指摘されている。CK2の阻害剤開発において有効な立体構造的知見を得るため、我々はCK2のキナーゼ触媒サブユニット(CK2 )の中性子構造解析を目指している。大腸菌にて過剰発現させたCK2
)の中性子構造解析を目指している。大腸菌にて過剰発現させたCK2 をカラムクロマトグラフィーによって精製し、大型結晶の作製を試みた。大型結晶の作製にはマクロシーディング法を用い、約40mg/mLに濃縮したタンパク質試料に種結晶を加えることによって実施した。その結果、最終的に約2mm
をカラムクロマトグラフィーによって精製し、大型結晶の作製を試みた。大型結晶の作製にはマクロシーディング法を用い、約40mg/mLに濃縮したタンパク質試料に種結晶を加えることによって実施した。その結果、最終的に約2mm の大型結晶を得ることができた。取得した結晶を、重水および重水素化試薬を用いて作製した結晶保存溶液で透析し、ミュンヘン工科大学の研究用原子炉(FRM-II)中性子ビームライン(BioDIFF)において、予備的中性子回折実験を実施した。結晶を100Kに冷却し、約30分間の照射を行うことによって、1.9
の大型結晶を得ることができた。取得した結晶を、重水および重水素化試薬を用いて作製した結晶保存溶液で透析し、ミュンヘン工科大学の研究用原子炉(FRM-II)中性子ビームライン(BioDIFF)において、予備的中性子回折実験を実施した。結晶を100Kに冷却し、約30分間の照射を行うことによって、1.9 分解能を超える回折点の観測に成功した。今後、取得した結晶を用いた中性子回折実験を実施し、CK2の詳細な構造解析を実施する予定である。
分解能を超える回折点の観測に成功した。今後、取得した結晶を用いた中性子回折実験を実施し、CK2の詳細な構造解析を実施する予定である。
廣本 武史; 安達 基泰; 柴崎 千枝; 黒木 良太
no journal, ,
T4ファージリゾチーム(T4L)は、大腸菌の細胞壁を構成するムラミルペプチドを加水分解し、溶菌を引き起こす酵素である。野生型T4Lは、加水分解後の生成物のアノマー構造を逆転する酵素であるが、26番目のThr残基を部位特異的にHis残基に置換したT26H変異型酵素は、加水分解生成物のアノマー構造を保持する酵素に変換されるのみならず、高い糖転移活性を獲得する。一般に糖加水分解酵素では、酸性残基の2つのカルボン酸がそれぞれ酸および塩基触媒として関与するが、T26H変異型酵素ではカルボン酸の代わりにヒスチジン側鎖が反応に関与する。そこで、変異型酵素に導入したHis残基の糖転移反応における役割と隣接する酸性残基(Asp20)との関係を中性子構造解析によって明らかにするため、野生型およびT26H変異型T4Lの完全重水素化とその大型結晶作製を試みたので報告する。それぞれの完全重水素化タンパク質は、一般的な大腸菌発現ベクター(pET-24a)を用い、完全重水素化培地で組換え大腸菌を培養後、過剰発現させることによって調製した。取得した試料を用いて、タンパク質濃度と沈殿剤濃度を変化させたスクリーニングを実施し、約0.1mm の結晶を取得した。本結晶をミュンヘン工科大学(FRM-II)において極低温下(100K)での予備的中性子回折実験を実施した結果、小型の結晶ではあるが2.5
の結晶を取得した。本結晶をミュンヘン工科大学(FRM-II)において極低温下(100K)での予備的中性子回折実験を実施した結果、小型の結晶ではあるが2.5 分解能を超える回折点の観測に成功した。
分解能を超える回折点の観測に成功した。
柴崎 千枝; 上田 実咲*; 高田 慎一; 安達 基泰*; 阿久津 和宏*
no journal, ,
The amino acids are the main components of proteins, and they are deeply involved in physiological functions such as metabolism and immunity. For example, oligo peptides consisting of 8 to 50 amino acid residues are being rapidly expanded in their use as fibers, films, and pharmaceuticals. Deuterated amino acids, where some hydrogen atoms (H) are replaced with deuterium (D), are applied in the elucidation of enzyme reaction mechanisms and protein structure analysis. Additionally, leveraging the fact that the C-D bond in deuterated compounds is stronger compared to the C-H bond, the deuteration is accelerating improvement of chemical stability. On the other hand, most amino acids in proteins have enantiomers (L-form and D-form). Natural amino acids are almost exclusively L-form, whereas it is known that some organisms utilize D-form amino acids. Contribution of the D-form should be less degradation compared to the L-form amino acids as a reason. Therefore, studying the properties of each deuterated enantiomer, which have not been thoroughly examined, will result in the development of new materials. We have considered that developing selective deuteration techniques for the alpha-position and side chains of amino acids using Pt/C and Pd/C catalyst at 100-200 degree and synthesizing polypeptides including deuterated amino acids can lead to the creation of novel functional molecules. Here, we found that a selective and efficient chemical synthesis method for deuterated amino acids (L-alanine), although the resulting deuterated compounds formed racemic mixtures (mixtures of L-form and D-form). Our next issue is separation the enantiomers of deuterated amino acids. Further, we have plans to synthesize and analyze the properties of deuterated peptides forward application to new functional materials.
柴崎 千枝; 阿久津 和宏*; 上田 実咲*; 高田 慎一; 安達 基泰*
no journal, ,
Amino acids play a crucial role in physiological functions such as metabolism and immunity. Deuterated amino acids, in which some hydrogen atoms (H) are replaced with deuterium (D), are used to elucidate enzyme reaction mechanisms and analyze protein structures. Additionally, because the C-D bond in deuterated compounds is stronger than the C-H bond, deuteration enhances chemical stability. Investigating the properties of deuterated polymers, which have not been thoroughly studied, could lead to the development of new materials. We believe that developing deuteration techniques for amino acids and oligopeptides using metal catalysts at high temperatures can result in the creation of novel functional molecules.
柴崎 千枝; 安達 基泰*
no journal, ,
The green fluorescent protein derived from the jellyfish Aequorea victoria is well-known as a fluorescent protein. A red fluorescent protein absorbs orange light and emits red fluorescence. mRuby derived from the sea anemone Entacmaea quadricolor exhibits strong red emission, significant Stokes shift, short maturation time from chromophore precursor to fluorophore, and high stability as a monomer. Its excellent pH stability and photostability also make it a valuable protein for cellular imaging and for visualizing molecular interactions through FRET. Our aim is to investigate the ionization and protonation states of the dissociable groups of the chromophore and surrounding amino acid residues, and the orientation of water molecules using neutron diffraction experiments. Here, mRuby protein was expressed in E. coli cultured in heavy water in addition to light water. We conducted X-ray diffraction experiments after crystallization, obtaining diffraction data at 0.93A (pH 8.0) and 1.09A (pH 3.7) for hydrated protein, and diffraction data at 1.04A (pH 8.0) for deuterated protein. In this poster, we will report the differences in stability between hydrated and deuterated mRuby, as well as the results of the structural analysis.
柴崎 千枝; 鈴木 陽茉梨*; 池上 貴久*; 吉田 将喜*; 奥 隆之; 安達 基泰*; 阿久津 和宏*
no journal, ,
日本国内における重水の価格は、過去10年間で数倍に急騰しており、各種実験で使用済みとなったD O溶液を高濃度の純粋なD
O溶液を高濃度の純粋なD Oへと低コストで再生する新たな方法の開発が重要となっている。本研究では、重水で微生物を培養する過程で発生した廃棄D
Oへと低コストで再生する新たな方法の開発が重要となっている。本研究では、重水で微生物を培養する過程で発生した廃棄D O溶液を対象に、蒸留および活性炭処理で不純物を除去した後、電気分解によって重水素濃度を高めることで、純粋なD
O溶液を対象に、蒸留および活性炭処理で不純物を除去した後、電気分解によって重水素濃度を高めることで、純粋なD O(再生D
O(再生D O)を生成する手法を開発した。その結果、不純物を多く含む重水濃度96.6%の廃棄D
O)を生成する手法を開発した。その結果、不純物を多く含む重水濃度96.6%の廃棄D O溶液(3L)を、重水濃度98.8%の再生(1L)に精製することに成功した。更に、この再生D
O溶液(3L)を、重水濃度98.8%の再生(1L)に精製することに成功した。更に、この再生D Oをアミノ酸の一種であるグリシンの重水素化実験に用いたところ、反応の阻害は認められず、収率95.5%、重水素化率90.6%の重水素化グリシンをgスケールで合成できることが確認できた。重水素化グリシンの作成コストは、そのほとんどが重水の値段となっている。よって、今回の廃重水から純粋な重水(再生D
Oをアミノ酸の一種であるグリシンの重水素化実験に用いたところ、反応の阻害は認められず、収率95.5%、重水素化率90.6%の重水素化グリシンをgスケールで合成できることが確認できた。重水素化グリシンの作成コストは、そのほとんどが重水の値段となっている。よって、今回の廃重水から純粋な重水(再生D O)を作製する手法は、D
O)を作製する手法は、D Oのコスト削減を実現し、持続可能な資源としての再利用を促進する。今後は、再生D
Oのコスト削減を実現し、持続可能な資源としての再利用を促進する。今後は、再生D Oの更なる活用を目指し、アラニンやヒスチジンなど側鎖を持つアミノ酸の完全重水素化方法の開発や、重水素化ペプチドの機能特性を探究する。
Oの更なる活用を目指し、アラニンやヒスチジンなど側鎖を持つアミノ酸の完全重水素化方法の開発や、重水素化ペプチドの機能特性を探究する。
柴崎 千枝; 安達 基泰; 黒木 良太
no journal, ,
生体分子の分子認識機構・反応触媒機構の解明のためには、X線と中性子線を併用した結晶構造解析が正確な水素原子の位置や触媒活性部位の水和構造を知るために必要となる。本研究では、中性子解析に必要な良質で大型の結晶を、効果的に作製する技術を確立するとともに、結晶化条件の知識データベースの構築を目指した。まず、結晶核生成を制御する添加剤に着目した新しいスクリーニングシステムを考案した。今回の発表では、新しいスクリーニングシステムを4種類のタンパク質に適用し、そのシステムの有効性を検討した。その結果、どの試料においてもスクリーニング条件内に結晶化ドロップに1 2個だけ結晶が析出する条件を見いだすことができた。今後は、今回スクリーニングを行ったタンパク質について大型結晶作製を進めるとともに、本スクリーニング系をできるだけ多くのタンパク質に適用することによって、結晶大型化のための知識データベースの構築を目指す。また、J-PARC/MLFに建設計画中の新装置(生体高分子専用高分解能中性子回折計)を効果的に利用することにより、医薬品開発やバイオエネルギー開発にも繋がると考えられる。
2個だけ結晶が析出する条件を見いだすことができた。今後は、今回スクリーニングを行ったタンパク質について大型結晶作製を進めるとともに、本スクリーニング系をできるだけ多くのタンパク質に適用することによって、結晶大型化のための知識データベースの構築を目指す。また、J-PARC/MLFに建設計画中の新装置(生体高分子専用高分解能中性子回折計)を効果的に利用することにより、医薬品開発やバイオエネルギー開発にも繋がると考えられる。
安達 基泰; 柴崎 千枝; 新井 栄揮; 清水 瑠美; 黒木 良太
no journal, ,
HIV-1プロテアーゼ(HIV-PR)は、エイズ治療のための創薬標的タンパク質である。本研究では、2量体HIV-1プロテアーゼにおける各サブユニットを区別して、構造・機能的解析を行い、量子ビームの応用によって阻害剤結合機構を詳細に明らかにすることを目的とする。今回、プロトマー間でN及びC末端が隣接することに着目し、タンデムに結合した遺伝子間に2アミノ酸残基分のリンカー配列を挿入することで、一本鎖化HIV-PRの作製を試みた。一本鎖化HIV-PRは、野生型と同様に大腸菌内に封入体として発現した。リフォールディングした一本鎖化HIV-PRを精製し、KNI-272との複合体を結晶化した。得られた結晶を用いて、放射光施設(SPring-8)にて1.3 分解能の回折データを収集し、R値19%まで構造を精密化した。一本鎖化HIV-PRの立体構造は、野生型とほとんど同じ(RMSD[Calpha]=0.17
分解能の回折データを収集し、R値19%まで構造を精密化した。一本鎖化HIV-PRの立体構造は、野生型とほとんど同じ(RMSD[Calpha]=0.17 )であった。この結果は、導入したリンカーが、HIV-PRの全体構造に影響を与えていないことを示しており、一本鎖化が成功したことを示す。
)であった。この結果は、導入したリンカーが、HIV-PRの全体構造に影響を与えていないことを示しており、一本鎖化が成功したことを示す。
柴崎 千枝; 安達 基泰; 廣本 武史; 清水 瑠美; 黒木 良太
no journal, ,
カゼインキナーゼ(CK2)は、その過剰な発現と、発癌や癌転移との関係が指摘されていることから、創薬標的タンパク質の一つとなっている。我々は、CK2の中性子結晶構造解析によって、阻害剤開発に有効な水素・水和構造に関する立体構造的知見を得ることを目的として、大型結晶作製と予備的中性子回折実験を実施した。大腸菌にて過剰発現させたCK2a(触媒サブユニットのみ)をカラムクロマトグラフィーによって精製し、大型結晶の作製を試みた。CK2の阻害剤であるEmodinとCX-4945との複合体試料について、約40mg/mLに濃縮したタンパク質試料に種結晶を加えることによって、約2mm の大型結晶を得ることができた。取得した結晶を、重水および重水素化試薬を用いて作製した溶液に対して透析処理した後、ミュンヘン工科大学の研究用原子炉(FRM-II)に設置の中性子回折計(BioDIFF)を用いて、予備的中性子回折実験を実施した。結晶を100Kに冷却し、約30分間照射した結果、阻害剤非結合型、Emodin複合体、CX-4945複合体についてそれぞれ、1.9, 2.0, 1.8
の大型結晶を得ることができた。取得した結晶を、重水および重水素化試薬を用いて作製した溶液に対して透析処理した後、ミュンヘン工科大学の研究用原子炉(FRM-II)に設置の中性子回折計(BioDIFF)を用いて、予備的中性子回折実験を実施した。結晶を100Kに冷却し、約30分間照射した結果、阻害剤非結合型、Emodin複合体、CX-4945複合体についてそれぞれ、1.9, 2.0, 1.8 の分解能を示す回折点の観測に成功した。
の分解能を示す回折点の観測に成功した。
柴崎 千枝; 篭谷 勇児*; 安達 基泰*
no journal, ,
Green fluorescent protein (GFP)はオワンクラゲ(Aequorea Victoria)から単離された蛍光タンパク質であり、青色の光を吸収して緑色の蛍光を発する。蛍光強度や波長特性、発色団形成速度などが異なる様々なGFPが変異体として作製されており、例えば、折りたたみ効率と蛍光輝度を増加させたEGFP (Enhanced GFP)や、青色の蛍光を発するBFP (blue fluorescent protein)がある。このような変異体は、細胞生物学および生化学研究において、特定のタンパク質の局在の可視化や発現レポーターとして広く使用されている。今回は、BFPの中性子結晶解析を中心に報告する。試料の準備としては、結晶化条件等を最適化することにより、X線回折実験で1Aを超える高分解能を確認した。中性子回折実験用に、1mm 以上の体積を目標に大型結晶を作製し、得られた結晶を用いて回折実験(X線: BL5A@KEK-PF、中性子: BIODIFF@FRM II)を実施した。現在、構造の精密化の最終段階にある。蛍光タンパク質の発色団のヒドロキシル基の電離状態、発色団に隣接したアミノ酸残基の解離状態、および重要な水分子の配向に係る知見は、タンパク質内の特殊な環境の理解と高度な分子設計へ貢献する。
以上の体積を目標に大型結晶を作製し、得られた結晶を用いて回折実験(X線: BL5A@KEK-PF、中性子: BIODIFF@FRM II)を実施した。現在、構造の精密化の最終段階にある。蛍光タンパク質の発色団のヒドロキシル基の電離状態、発色団に隣接したアミノ酸残基の解離状態、および重要な水分子の配向に係る知見は、タンパク質内の特殊な環境の理解と高度な分子設計へ貢献する。
柴崎 千枝; 安達 基泰; 廣本 武史; 清水 瑠美; 黒木 良太
no journal, ,
細胞に広く存在するセリン/スレオニンキナーゼであるカゼインキナーゼII(CK2)は、2つの サブユニットと2つの
サブユニットと2つの サブユニットからなる4量体構造を有しており、細胞周期の進行や細胞の生存・増殖に関与することが知られている。CK2
サブユニットからなる4量体構造を有しており、細胞周期の進行や細胞の生存・増殖に関与することが知られている。CK2 の生物学的機能を理解するために、我々は、中性子結晶構造解析を用いて、CK2
の生物学的機能を理解するために、我々は、中性子結晶構造解析を用いて、CK2 の水素原子や水和水の情報を含む蛋白質構造を明らかにすることを目指している。大腸菌にて過剰発現させたCK2
の水素原子や水和水の情報を含む蛋白質構造を明らかにすることを目指している。大腸菌にて過剰発現させたCK2 をカラムクロマトグラフィーによって精製し、得た蛋白質を用いて大型結晶の作製を試みた。大型結晶の作製にはマクロシーディング法を用い、40mg/mLの蛋白質溶液と同量の沈殿剤溶液(25mM Tris-HCl(pH8.5)、0.85M硫酸アンモニウム、1mM DTTおよび5%アセトニトリル)を混ぜた後、種結晶を添加した。その後、リザーバー溶液の硫酸アンモニウムの濃度を数日間かけて1.2Mまで上昇させた。その結果、子結晶の形成が抑えられ、最終的に約2mm
をカラムクロマトグラフィーによって精製し、得た蛋白質を用いて大型結晶の作製を試みた。大型結晶の作製にはマクロシーディング法を用い、40mg/mLの蛋白質溶液と同量の沈殿剤溶液(25mM Tris-HCl(pH8.5)、0.85M硫酸アンモニウム、1mM DTTおよび5%アセトニトリル)を混ぜた後、種結晶を添加した。その後、リザーバー溶液の硫酸アンモニウムの濃度を数日間かけて1.2Mまで上昇させた。その結果、子結晶の形成が抑えられ、最終的に約2mm の大型単結晶を得ることができた。取得した結晶を中性子実験と同一の条件(重水および重水素化試薬を用いて作製した結晶保存溶液)で透析し、X線回折実験を行った。その結果、100Kで1.1
の大型単結晶を得ることができた。取得した結晶を中性子実験と同一の条件(重水および重水素化試薬を用いて作製した結晶保存溶液)で透析し、X線回折実験を行った。その結果、100Kで1.1 の分解能の回折像を得ることができた。今後、作製した大型結晶を用いて中性子回折実験を実施し、CK2の詳細な構造解析を実施する予定である。
の分解能の回折像を得ることができた。今後、作製した大型結晶を用いて中性子回折実験を実施し、CK2の詳細な構造解析を実施する予定である。
小田 隆; 井上 倫太郎*; 柴崎 千枝; 青木 裕之; 奥 隆之; 杉山 正明*
no journal, ,
中性子を用いた生体高分子の構造・ダイナミクス解析において、試料の重水素化は非常に重要である。中性子結晶構造解析では非常に大型の結晶を必要とし、その作製に多くの時間と労力を費やす。重水素化タンパク質を用いると、軽水素体タンパク質と比較して、より小型の結晶で解析が可能となる。さらに、軽水素体タンパク質よりも、水素原子や水素イオンの密度をより明確に同定できると期待される。中性子小角散乱(SANS)や中性子準弾性散乱(QENS)では、マルチドメインタンパク質の特定のドメインや、タンパク質複合体の特定のサブユニットを重水素化した試料を用いることで、残りの軽水素体のドメインやサブユニットの構造やダイナミクス情報を、選択的に取得することが可能である。マルチドメインタンパク質の特定のドメインのみを重水素化した試料(区分重水素化試料)等の試料調製、試料評価を例に、J-PARC MLF重水素化ラボにおけるタンパク質重水素化の取り組みについて報告する。
清水 瑠美; 廣本 武史; 安達 基泰; 柴崎 千枝; 黒木 良太
no journal, ,
T4ファージリゾチーム(T4L)は、大腸菌の細胞壁を構成するムラミルペプチドを加水分解し、溶菌を引き起こす酵素である。野生型T4Lは、加水分解後の生成物のアノマー構造を逆転する酵素であるが、26番目のThr残基を部位特異的にHis残基に置換したT26H変異型酵素は、加水分解生成物のアノマー構造を保持する酵素に変換されるのみならず、高い糖転移活性を獲得する。一般に糖加水分解酵素では、酸性残基の2つのカルボン酸がそれぞれ酸塩基触媒として機能するが、T26H変異型酵素ではカルボン酸の代わりにヒスチジン側鎖が反応に関与する。そこで、変異型酵素に導入したHis残基の糖転移反応における役割と隣接する酸性残基(Asp20)との関係を中性子構造解析により明らかにするため、T26H変異型T4Lの完全重水素化とその大型結晶作製を試みた。タンパク質試料は、一般的な大腸菌発現ベクター(pET-24a)を用い、完全重水素化培地で組換え大腸菌を培養後、過剰発現させることによって調製した。取得した試料を用いて、タンパク質濃度と沈殿剤濃度を変化させたスクリーニングを実施し、約0.9mm の結晶を取得した。米国オークリッジ国立研究所の研究用原子炉(HFIR)に設置されたイメージングプレート単結晶回折計(IMAGINE)を用いた室温での中性子回折実験の結果、2.1
の結晶を取得した。米国オークリッジ国立研究所の研究用原子炉(HFIR)に設置されたイメージングプレート単結晶回折計(IMAGINE)を用いた室温での中性子回折実験の結果、2.1 分解能の回折強度データを完全性79.8%で収集することに成功した。
分解能の回折強度データを完全性79.8%で収集することに成功した。
廣本 武史; 清水 瑠美; 安達 基泰; 柴崎 千枝; 黒木 良太
no journal, ,
T4ファージリゾチーム(T4L)は、大腸菌の細胞壁を構成するムラミルペプチドを加水分解し、溶菌を引き起こす酵素である。26番目のThr残基をHis残基に置換したT26H変異型酵素は、加水分解生成物のアノマー構造を保持する酵素に変換されるのみならず、高い糖転移活性を獲得する。一般に糖加水分解酵素では、酸性残基の2つのカルボン酸がそれぞれ酸塩基触媒として機能するが、T26H変異型酵素ではカルボン酸の代わりに同じ位置を占めるヒスチジン側鎖が反応に関与すると考えられている。そこで変異型酵素に導入したHis残基の糖転移反応における役割と隣接する酸性残基(Asp20)との関係を中性子構造解析により明らかにするため、T26H変異型T4Lの完全重水素化とその大型結晶作製を試みた。タンパク質試料は、一般的な大腸菌発現ベクター(pET-24a)を用い、完全重水素化培地で組換え大腸菌を培養後、過剰発現させることによって調製した。精製試料を用い、約0.9mm の結晶を作製した。米国オークリッジ国立研究所の研究用原子炉(HFIR)に設置されたイメージングプレート単結晶回折計(IMAGINE)を用い、室温での中性子回折実験を実施した結果、2.1
の結晶を作製した。米国オークリッジ国立研究所の研究用原子炉(HFIR)に設置されたイメージングプレート単結晶回折計(IMAGINE)を用い、室温での中性子回折実験を実施した結果、2.1 分解能の回折強度データを完全性79.8%で収集することに成功した。現在、同一結晶より収集した1.7
分解能の回折強度データを完全性79.8%で収集することに成功した。現在、同一結晶より収集した1.7 分解能のX線データを併用し、分子モデルの同時精密化を進めている。
分解能のX線データを併用し、分子モデルの同時精密化を進めている。